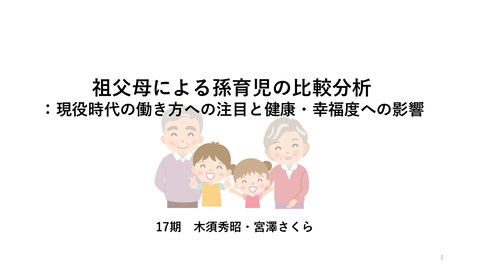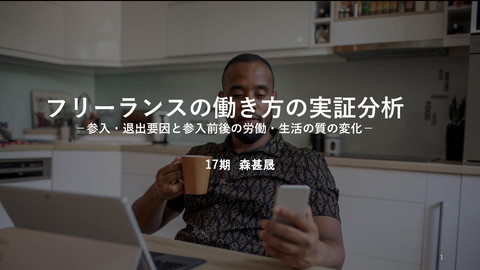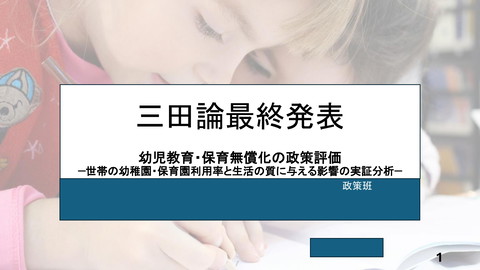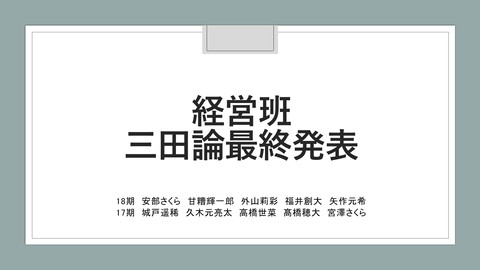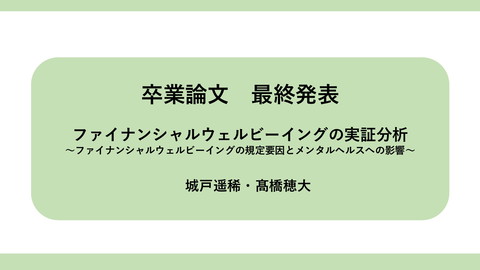2024卒業論文_髙橋世菜・吉崎遼希
1.4K Views
February 19, 25
スライド概要
この発表では、若年期(20~30代)の就業女性に焦点を当て、彼女たちの保健行動の規定要因とその後のキャリアや健康に与える影響について実証的に分析します。女性の就業率が上昇する中、特に女性が抱える健康課題や時間的制約により適切な保健行動が実施されていない現状を問題視し、その結果がキャリア形成や健康にどのように結びついているのかを明らかにします。最終的には、働きながら健康を維持できる社会の実現に向けた提言を行います。
慶應義塾大学商学部商学科山本勲研究会 ホームページ: https://www.yamazemi.info Instagram: https://www.instagram.com/yamazemi2024
関連スライド
各ページのテキスト
卒論最終発表 山本勲研究会17期 髙橋世菜&吉崎遼希
テーマ概要 若年期就業女性の保健行動の規定要因とその後の キャリア・健康に与える影響に関する実証分析 ・若年期(20~30代)の就業女性の保健行動の規定要因、その後のキャリアに与える 長期的な影響を定量的に分析する。 ・より適切な保健行動を促すことで、女性が継続して健康に働ける社会を目指す。 2
アウトライン 1.背景・問題意識 2.先行研究 3.分析アプローチ 4.分析結果 5. 質疑応答 3
1.背景・問題意識
1. 背景・問題意識 女性の就業率の推移 図1:女性就業率の推移 少子高齢化が進む現在の日本において、 女性の就業率は、 15~64歳:72.4% 25~44歳:79.8% 近年、上昇傾向が見られる 出典:令和5年度男女共同参画白書(男女共同参画局) 5
1. 背景・問題意識 女性の健康課題による問題 図2:女性特有の健康課題による社会全体の経済損失(試算結果) 〈女性特有の健康課題に伴う労働損失等の経済損失〉 ・欠勤 ・パフォーマンス低下 ・離職 ・休職 ・追加採用活動にかかる費用 社会全体で 年間 約3.4兆円 出典:女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について (経済産業省 ヘルスケア産業課) 6
1. 背景・問題意識 女性の健康課題の現状① 図3:女性特有・男性特有の病気の総患者数 出典:令和6年度経済白書概要版 図4:最も気になる症状への対処法 ・女性特有の健康課題は20〜50代と幅広く、男性と比較し働く世代に多いことがわかっている。 ・最も気になる症状に対して「特になにもしていない」と答えた女性就業者は3割以上。 7
1. 背景・問題意識 女性の健康課題の現状① 図3:女性特有・男性特有の病気の総患者数 出典:令和6年度経済白書概要版 図4:最も気になる症状への対処法 女性の方が健康課題を抱えたまま、働いている可能性 女性の健康と労働を両立させることが重要! ・女性特有の健康課題は20〜50代と幅広く、男性と比較し働く世代に多いことがわかっている。 ・最も気になる症状に対して「特になにもしていない」と答えた女性就業者は3割以上。 8
1. 背景・問題意識 女性の健康課題の現状② 図5:最も気になる症状に十分対処できていない理由 図6:男女別に見た生活時間(週平均) 出典:令和6年版男女共同参画白書概要版(男女共同参画局) 出典:令和2年度男女共同参画白書(男女共同参画局) ・対処できない理由として、仕事と家事育児などで忙しいという時間的余裕のなさが挙げられる。 ・OECD(経済協力開発機構)が2020年にまとめたデータによるOECDのデータによると、 日本人女性は無償労働に対して男性の5.5倍費やしている。 9
1. 背景・問題意識 女性就業者の働き方と健康 図7:働く上での健康課題や困りごとに対する改善策 出典:令和5年度男女の健康意識に関する調査(内閣府委託調査) 図8:健康や休暇に関する制度などの使用意向と使用経験 ・働く上での健康課題に対する改善策として、「仕事の量・仕事時間の改善」が上位として挙げられてる。 ・健康や休暇に関する制度に関しては、全項目が女性のほうが使用意向が高い。 10
1. 背景・問題意識 女性就業者の働き方と健康 図7:働く上での健康課題や困りごとに対する改善策 出典:令和5年度男女の健康意識に関する調査(内閣府委託調査) 図8:健康や休暇に関する制度などの使用意向と使用経験 女性就業者は症状を自覚しているものの 時間的な制約が主な理由として、 適切な保健行動ができていないまま労働をしており、 働き方が女性の健康を改善するために関連している可能性がある。 ・働く上での健康課題に対する改善策として、「仕事の量・仕事時間の改善」が上位として挙げられてる。 ・健康や休暇に関する制度に関しては、全項目が女性のほうが使用意向が高い。 11
1. 背景・問題意識 女性就業者の健康が与える影響 図9:最も気になる症状への対処状況と昇進意欲 気になる症状に対処できている人ほど 昇進意欲が高い傾向にあることが 明らかになっている。 適切な保健行動を取れている 健康状態が良い その後のキャリアに正の影響を与える という可能性が考えられる。 出典:令和6年版男女共同参画白書概要版(男女共同参画局) 12
1. 背景・問題意識 保健行動の定義 図10:保健行動の分類 宗像(1991)は、 健康状態への主観的・客観的気づきの観点から、 ①健康増進行動 ②予防的保健行動 ③病気回避行動 ④病気対処行動 ⑤ターミナル対処行動 の5つに保健行動を分類している。 出典:大学生の病気対処行動とソーシャルサポートの関連(飯塚ら, 2005) 本論文では、自覚がありながらも適切な行動を取らないことを問題視しているため、 病気対処行動を保健行動と定義する。 13
1. 背景・問題意識 問題意識まとめ 1 女性の就業率が上昇しているとともに、女性特有の健康課題も問題視されている。 2 女性の方が健康課題を抱えたまま就業している可能性があるため、 女性の労働と健康の両立が重要である。 3 時間的制約が理由となり適切な保健行動ができていない可能性があるため、 働き方が女性の健康に影響を与えている可能性がある。 4 適切な保健行動がその後のキャリアや健康に正の影響を与えている可能性がある。 14
1. 背景・問題意識 本論文の目的 女性就業者が健康課題を自覚しながらも働いている現状を問題視し、 それを防ぐための保健行動(病気対処行動)に着目する。 ・保健行動(病気対処行動)の一つである病院受診は若年期(20~30代)で 控える傾向にあることがわかっている。(中川ら, 2022) ・キャリア形成の重要な時期であると考えられる。 ・女性特有の健康課題は、男性と比べて、若年期から存在する。 上記の理由により、若年期の女性就業者に焦点を当てて分析を行うとともに、 そのような保健行動の規定要因と その後のキャリア・健康に及ぼす影響について分析を行う。 15
2. 先行研究・独自性 本論文で明らかにすること 1 若年期就業女性の働き方による保健行動の違い 働き方がメンタルヘルスや健康に与える影響はわかっているが、 健康への対処(保健行動)が働き方の違いにより どう変化するかはわかっていない。 2 若年期女性就業者の保健行動が、 その後のキャリアや賃金、健康に与える影響 不調な就業者が対処せずに出勤することで健康が悪化するなどの 因果関係はわかっているが、そういった不調に対処するという保健行動が 長期的なキャリアや就業の継続、健康などに与える影響はわかっていない。 16
2. 先行研究・独自性 各分析の独自性① 若年期女性就業者の保健行動の規定要因 独自性 分析意義 ・保健行動の指標として、受診行動 だけでなく、薬購入行動も含めた順 序変数を用いること。 ・若年期の保健行動が低い傾向にあること ・女性の健康課題が労働生損失に大きな影響を与え ていること ・女性が時間的制約を理由に男性より気になる症状 に対処できていないこと ・若年期女性の保健行動と働き方の 関係に着目している点。 以上の現状により、短時間勤務や時間短縮などと いった働き方が若年期の女性の保健行動にどう 影響を与えているかを明らかにし、今後の日本 企業での健康と労働の両立を可能にする制度作 りの一助とする。 17
2. 先行研究・独自性 各分析の独自性② 若年期の保健行動がその後のキャリア・賃金、健康に与える影響 独自性 ・パネルデータを用いることで、 保健行動がその後の賃金やキャリア、 健康に与える長期的な影響を分析する 点。 分析意義 気になる症状に対処せず出勤を続けた不調就業者は その後、健康悪化・失業などを起こすことが 先行研究で明らかになっている よって、若年期に保健行動をしているか否かが、 その後のキャリアや賃金、健康に影響を与えて いることを明らかにし、若年期女性就業者が継 続的に働いていくために政府や企業が保健行動 を促すエビデンスとし、労働力確保の一助とす る。 18
2.先行研究
2. 先行研究 先行研究の分類 1 女性特有の健康課題に関する研究 2 保健行動に関する研究 3 働き方が健康に与える影響 4 就業者の不調が与える影響 20
2. 先行研究 ①女性特有の健康課題に関する研究 西岡ほか(2024) 甲斐村ほか(2023) 【概要】 ・女性特有の症状とその対処およびがん検診受験状況について、正規雇用と 非正規雇用での比較 2018年時点の働く女性2000名のweb調査 【結果】 ・月経痛・月経前の症状を有する女性は約8割(77.6%)だが、産婦人科を 受診する人は19.0% ・月経の特有症状について非正規の方が症状を自覚してから受診するまで時 間がかかる。 【概要】 ・看護師の月経随伴症状が労働生産性およびQOLに及ぼす影響について、あ る市の6つの医療機関看護師に対し郵送調査 【結果】 ・月経症状による欠勤者は2.3%であったが、月経周辺期に労働パフォーマ ンスおよびQOLが低下する人はそれぞれ90.2%、94.8%であり、症状が重 症になる程低下する傾向。 甲斐村ほか(2014) 【概要】 ・若年女性における月経随伴症状と関連要因がQOLへ及ぼす影響について、 看護系の大学在学女子学生対象に無記名式自記式質問紙調査 【結果】 ・月経随伴症状を軽減させる要因は肯定的月経観と健康的生活習慣である、 増強させる要因は効果的ではない症状対処行動。 ・月経随伴症状はQOLを低下させる要因。 21
2. 先行研究 ①女性特有の健康課題に関する研究 渡部真澄(2019) 佐々木ほか(2021) 【概要】 ・女性疾病・疾病罹患者のプレゼンティズムとその要因分析 【結果】 ・職業的・個人的要因によって適切な時期に適切な治療を受けられていない ことが女性疾病・疾患がプレゼンティズム(生産性低下)を引き起こしてい る。 ・不調を抱えたまま出勤したものの生産性の低下が起きたことにより、結果 として体調を優先して離職した、解雇を言い渡された。 【概要】 ・日本人女性労働者の就労上課題となる生物心理社会的な要因、制度利用状 況についてのインターネット調査 【結果】 ・就労上課題となる生物心理社会的な要因として、心身症状(8.9%)、月 経に関する悩み(65%)、精神症状(49%)、ワークライフバランス (39%)、妊娠出産に伴うキャリアの悩み(38%)の順で多かった。 ・制度利用の状況としてはフレックスタイムやテレワークに関しては1~3%、 短時間勤務制度は8%、生理休暇4%に留まっている。 22
2. 先行研究・独自性 ①女性特有の健康課題に関する研究 ・症状に対して受診という病気対処行動をとっている女 性は少ない 渡部真澄(2019) 佐々木ら(2021) ・適切ではない保健行動は症状を悪化させる 【概要】 【概要】 ・女性疾病・疾病罹患者のプレゼンティズムとその要因分析 【結果】 ・職業的・個人的要因によって適切な時期に適切な治療を受けられていない ことが女性疾病・疾患がプレゼンティズム(生産性低下)を引き起こしてい る。 ・不調を抱えたまま出勤したものの生産性の低下が起きたことにより、結果 として体調を優先して離職した、解雇を言い渡された。 ・日本人女性労働者の就労上課題となる生物心理社会的な要因、制度利用状 況についてのインターネット調査 【結果】 ・就労上課題となる生物心理社会的な要因として、心身症状(8.9%)、月 経に関する悩み(65%)、精神症状(49%)、ワークライフバランス (39%)、妊娠出産に伴うキャリアの悩み(38%)の順で多かった。 ・制度利用の状況としてはフレックスタイムやテレワークに関しては1~3%、 短時間勤務制度は8%、生理休暇4%に留まっている。 ・女性特有の健康課題は短期的なQOLや生産性を低下 させる。 23
2. 先行研究 ②保健行動に関する研究 中川・樋口(2022) 阿部(2013) 【概要】 ・女性就労者を対象として、どのような労働要因・社会経済的要因が受診抑 制と関連しているかをロジスティック分析で検証。 【結果】 ・若年層(20〜30)のほうが受診を控える傾向。 ・正規雇用者に限定すると、受診抑制に影響を当てる要因は就労年数であり、 逆V字型で、中堅レベル(2年~5年)が一番受診抑制の傾向がある。 ・非正規雇用者に限定すると、若年層ほど受診を控える傾向。若年層はライ フイベントが多く、時間に余裕がないことが関連している可能性。 【概要】 ・受診抑制の理由別の発生状況、受診を抑制する人々の属性を「まちと家族 の健康調査」を利用して明らかにする。 【結果】 ・時間的制約による受診行動に要因となっているのは、就業形態よりも子供 の有無であった。 ・経済的制約による受診行動の要因となっているのは、世帯所得や、所得の 低い非正規、失業中、無職の男性であった。 田村ほか(2023) 飯塚ほか(2005) 【概要】 ・看護師を対象にアンケート調査を行い、職場のソーシャルキャピタルと予 防的保健行動と病気対処行動に及ぼす影響をロジスティック回帰分析を用い て分析。 【結果】 ・看護師の職場のソーシャル・キャピタルは,ヘ ルスリテラシーを備えた人 的環境が相談や受診等の病気対処行動に影響を与える可能性がある。 ・職場の排他的職場風土は,未受診の傾向がみられ,健康維持を妨げる可能 性がある 【概要】 ・大学生を対象にアンケート調査を行い、ソーシャルサポート(家族や先生 友人からの)と病気対処行動(積極的対処・回避的対処・サポート希求)の 関連を分析。 【結果】 ・ソーシャルサポートと積極的対処行動、サポート希求行動には正の相関が ある。 ・ソーシャルサポートと回避的対処行動に負の相関があるという仮説は立証 されなかった。 24
2. 先行研究 ②保健行動に関する研究 山崎ほか(1993) Sato et al.(2011) 【概要】 ・大学生のライフスタイルを構成する生活行動を因子分析的手法により分類 し、いくつかに分類されたそれぞれの保健行動が、心身の健康状態、自己管 理度、健康に対する淫的資源、行動特性、その他の健康に関する意識などの 中のどの要因によって強く影響を受けているかを検討 【結果】 ・医療機関の受診有無が保健行動を起こす要因である ・男女で保健行動に差が見られる。 ・病気罹患の有無は保健行動に影響を及ぼさない。 【概要】 ・日本人男性フルタイム労働者の労働時間、経験した症状、および医療資源 の利用状況との関係を調査 【結果】 ・労働時間が短い就労者ほど、医師の診療を受ける頻度が高かった。 ・月に250時間以上働く参加者は、補完代替医療(CAM)提供者への訪問頻 度が低く、症状に対してサプリメントを使用する傾向が見られた。 中添ほか(2000) 松本ほか(2010) 【概要】 予防的保健行動に着目し、保健行動を促進する目的で行われるM町の健康チェックデータに、 自主的に参加した住民の年齢の違いによる健康意識と生活習慣の特徴を明らかにする。 【結果】 ・45歳未満よりも65歳以上の人が、健康意識が高く、予防的保健行動をとる傾向であった。 ・45歳未満の人は、健康には関心を持っているが、予防的保健行動には繋がりにくい。なぜ なら、健康が日常生活上の最優先課題ではないからである。 ・生活習慣病の予防には、45歳未満の人が、自らの健康をコントロールし、改善できるよう な支援をすることが重要である。 【概要】 ・労働者の保健行動と喫煙状況、特にTDS(ニコチン依存評価)によるニコ チン依存度との関連性を調査 【結果】 ・保健行動への取り組み状況は、喫煙者は非喫煙者及び過去喫煙者に比べ有 意に低かった。 ・ニコチン依存度は、男女により差があり、女性の方が高い。 25
2. 先行研究・独自性 ②保健行動に関する研究 ・職場環境(周りの行動)が受診率に影響を与えている 松本ら(2010) ・若年層(20~30代)の方が保健行動をとる確率が低い 中添ら(2000) ・正規雇用、非正規雇用といった雇用形態が受診率の違い 【概要】 ・労働者の保健行動と喫煙状況、特にTDS(ニコチン依存評価)によるニコ に影響を与えている チン依存度との関連性を調査 【結果】 ・保健行動への取り組み状況は、喫煙者は非喫煙者及び過去喫煙者に比べ有 ・子供の有無が、時間的余裕を低減させ、受診行動の低下 意に低かった、 ・ニコチン依存度は、男女により差があり、女性の方が高い。 に繋がっている ・低所得者、非正規雇用、失業といった経済的余裕のなさ が受診行動の低下に繋がっている 森谷(2005) 松嵜(2001) ・男女や年齢差が、保健行動の差(度合い)に影響を与え 【 【概要】 る。 ・大学生が保健行動のどの段階にいるのか、各段階にどのような要因が影響 【概要】 予防的保健行動に着目し、保健行動を促進する目的で行われるM町の健康チェックデータに、 自主的に参加した住民の年齢の違いによる健康意識と生活習慣の特徴を明らかにする。 【結果】 ・45歳未満よりも65歳以上の人が、健康意識が高く、予防的保健行動をとる傾向であった。 ・45歳未満の人は、健康には関心を持っているが、予防的保健行動には繋がりにくい。なぜ なら、健康が日常生活上の最優先課題ではないからである。 ・生活習慣病の予防には、45歳未満の人が、自らの健康をコントロールし、改善できるよう な支援をすることが重要である。 しているかについて分析 【結果】 ・男女により、保健行動段階の進展に影響する要因の効果に違いがある 概要】 ・ Health Locus of Control(以下HLC)とは、行動を予測する上での一種の人格変数であ り、健康を自分の行為によるものと認知する内的統制傾向と健康を自分以外の重要他者や運 などによるものと外的統制傾向で ・HLCと企業労働者の保健行動の関連について分析 【結果】 ・管理職は、他の職種よりも内的統制傾向が強かった ・労働者において、内的統制傾向が強いものが、外的統制傾向が強いものより多くの保健行 動を実施した。 ・労働者において、HLCが他の要因より保健行動の実施に最も関連性があった。 26
2. 先行研究 ③働き方が健康に与える影響 高橋(2022) 高橋(2023) 【概要】 ・5か年分(2014~2018)のJHPSを用いて労働者の心身症状指標がそのような要 因で決まるのか実証分析 ・働き方や労働時間、詳細な業種職種の違い、経済状況、その他の属性がどのよう な影響を与えているのか検証 【結果】 ・女性において労働時間とフレックスタイム制で働いていることが心身の健康を悪 化させている。業種別にも違いが見られる。 →女性労働者の健康には、働き方や業種によって違いがあり、格差の存在が伺える。 【概要】 ・パネルデータを用いて、労働者の心身の不調がどのような要因で決まるのか、実証分析を 行う。 ・労働者の雇用形態や雇用の安定性、働き方や労働時間、職場環境などがどのような影響を 与えているかについて着目する。 【結果】 ・労働時間の長さは、男性の心理的不調に影響を与えており、不本意型の非正規雇用につい ては、男性において身体的不調が小さくなっている。 ・女性では、フレックスタイム制で働いている場合、 心身共に不調がみられる ・女性では、配偶者がいる場合、生活、仕事満足度が高くなっており、同居人数が多い場合、 生活満足度が低くなっている。女性の生活満足度を除けば、年収の多さは、生活、仕事満足 度を高めている。 山岡(2015) 【概要】 ・労働者の「心の病」が急激にすすむIT化や産業構造の変化、新しい経済環 境・労働環境により増えている。そこで、労働者のメンタルヘルス悪化の要 因について、職場環境がどのように関わっているかについて明らかにする。 【結果】 ・労働時間や通勤時間の長さが労働者のメンタルヘルスの悪化の要因となっ ている。 27
2. 先行研究・独自性 ③働き方が健康に与える影響 高橋(2023) 高橋(2022) 【概要】 ・パネルデータを用いて、労働者の心身の不調がどのような要因で決まるのか、実証分析を 行う。 ・労働者の雇用形態や雇用の安定性、働き方や労働時間、職場環境などがどのような影響を 与えているかについて着目する。 【結果】 ・労働時間の長さは、男性の心理的不調に影響を与えており、不本意型の非正規雇用につい ては、男性において身体的不調が小さくなっている。 ・女性では、フレックスタイム制で働いている場合、 心身共に不調がみられる ・女性では、配偶者がいる場合、生活、仕事満足度が高くなっており、同居人数が多い場合、 生活満足度が低くなっている。女性の生活満足度を除けば、年収の多さは、生活、仕事満足 度を高めている。 ・働き方や業種などの違いが、女性の健康格差を生んでい る。 【概要】 ・5か年分(2014~2018)のJHPSを用いて労働者の心身症状指標がそのような要 因で決まるのか実証分析 ・働き方や労働時間、詳細な業種職種の違い、経済状況、その他の属性がどのよう な影響を与えているのか検証 【結果】 ・女性において労働時間とフレックスタイム制で働いていることが心身の健康を悪 化させている。業種別にも違いが見られる。 →女性労働者の健康には、働き方や業種によって違いがあり、格差の存在が伺える。 ・勤務時間や通勤時間といった働き方が、仕事満足度低下 やメンタルヘルス悪化の要因となっている。 山岡(2015) 【概要】 ・労働者の「心の病」が急激にすすむIT化や産業構造の変化、新しい経済環 境・労働環境により増えている。そこで、労働者のメンタルヘルス悪化の要 因について、職場環境がどのように関わっているかについて明らかにする。 【結果】 ・労働時間や通勤時間の長さが労働者のメンタルヘルスの悪化の要因となっ ている。 28
2. 先行研究 ④就業者の不調が与える影響 Fujino et al. (2024) Suzuki et al.(2015) 【概要】 プレゼンティイズムとして作業機能障害尺度を使用し、コロナ禍の日本人労 働者におけるプレゼンティイズムと退職および失業のリスクとの関連性を調 査。 【概要】 日本人労働者を対象に二年間のパネル調査を用いてプレゼンティイズムとう つ病の関連を分析。 【結果】 労働機能障害のある労働者は、1年後の退職または失業のリスクが高くなる。 岡庭, 2017 【概要】 ・平成19年度「国民基礎調査」を用いてメンタルヘルス不全の影響として, 実際に得た所得が健康な人と比較してどの程度低くなっているのか分析 【結果】 ・メンタルヘルス状態が悪いが受診せずに就業している人が多い。 ・推計の結果、メンタル不全や精神疾患は所得に対して負の影響を及ぼして いる。 【結果】プレゼンティイズムが高い(三分位)労働者のその後のメンタルヘ ルスの悪化が見られ、うつ病による欠勤率が高まる可能性が示された。 Tsuchiya(2012) 【概要】 ・世界メンタルヘルス調査のうち日本人データを使用して、一般的な精神疾 患が病欠と職場での仕事のパフォーマンスに与える影響について分析した。 【結果】 ・大うつ病性障害とアルコール乱用/依存症が職場のパフォーマンスの低下 (プレゼンティズム)と正の相関関係にあることが示されているが、精神疾 患は欠勤日数(アブセンティズム)と関連していなかった。 29
2. 先行研究 ④就業者の不調が与える影響 Taloyan et al.(2012) Conway et al.(2014) 【概要】 ・スウェーデンの労働者を対象に不調をもちながら働く場合と、 休む場合のその後の影響を分析。 【結果】 ・7日以上の不調を抱えながら働いた人は、その後の主観的健康 感が低下するリスクが高かった。 【概要】 ・デンマークの労働者を対象にプレゼンティイズムと将来的なう つ病の発生率の関連性を分析 【結果】 ・8日以上の不調を抱えながら働いた人は、2年後のうつ病のリス クが高まる。 Kivimaki et al.(2005) Hansen et al.(2009) 【概要】イギリス男性公務員のプレゼンティイズムと重篤な冠動脈の発生率 との関連性 【結果】病気でも出勤している人で欠勤しなかった人は欠勤したことのある 人に比べ3年後の重篤な冠動脈の発生率が約2倍高まっていた。 【概要】デンマークの労働者を対象に、プレゼンティイズムと将来の病気に よる長期欠勤の関連を分析。 【結果】 ・1年間に6回以上病気で出勤した参加者は、ベースラインの健康状態や過去 の長期病気欠勤だけでなく、さまざまな潜在的交絡因子をコントロールした 後でも、2か月以上病気リストに載るリスクが74%高かった 30
2. 先行研究 ④就業者の不調が与える影響 Fujino et al, 2024 Suzuki et al, 2015 ・就業者が不調を抱えている場合、退職や失業といった 【概要】プレゼンティイズムとして作業機能障害尺度を使用し、コロナ禍の 就業継続へ短期的に負の影響を及ぼす。 【概要】 日本人労働者を対象に二年間のパネル調査を用いてプレゼンティ 日本人労働者におけるプレゼンティイズムと退職および失業のリスクとの関 イズムとうつ病の関連を分析。 連性を調査。 【結果】プレゼンティイズムが高い(三分位)労働者のその後のメンタルヘ ルスの悪化が見られ、うつ病による欠勤率が高まる可能性が示された。 ・病気がわかっても欠勤しない(気になる症状に対処しな い)人は、欠勤する(対処する)人と比較し、 その後の健康に短期的に負の影響を及ぼす 【結果】労働機能障害のある労働者は、1年後の退職または失業のリスクが 高くなる。 Kivimaki et al, 2005 【概要】イギリス男性公務員のプレゼンティイズムと重篤な冠動脈の発生率 との関連性 【結果】病気でも出勤している人で欠勤しなかった人は欠勤したことのある 人に比べ3年後の重篤な冠動脈の発生率が約2倍高まっていた。 Hansen et al, 2009 【概要】デンマークの労働者を対象に、プレゼンティイズムと将来の病気に よる長期欠勤の関連を分析。 【結果】 ・1年間に6回以上病気で出勤した参加者は、ベースラインの健康状態や過去 の長期病気欠勤だけでなく、さまざまな潜在的交絡因子をコントロールした 後でも、2か月以上病気リストに載るリスクが74%高かった 31
2. 先行研究 先行研究まとめ 〈明らかになっていること〉 〇 女性特有の健康課題と保健行動の関係 〇 雇用形態による保健行動(受診行動)の規定要 因の違い 〈明らかになっていないこと〉 〇若年期就労女性の保健行動に着目した定量的な 分析 〇受診行動以外の保健行動を含めた分析 〇 保健行動の規定要因 労働要因:職場環境、就労年数 社会経済的要因:所得、年齢、子供の有無 〇 保健行動の規定要因として就業者の働き方に焦 点をあてた分析 〇 健康に影響を与える働き方の雇用形態間、男女 間による違い 〇 女性就業者の保健行動が、長期的にその後の就 業や昇進といったキャリアに与える影響 〇 就業者の不調がその後の就業継続・主観的健康 に与える短期的な負の影響 〇 女性就業者の保健行動が、長期的にその後の健 康(主観的健康度)に与える影響 32
3.分析アプローチ
3. 分析アプローチ 分析の流れ 1 若年期女性就業者の保健行動の規定要因 2 若年期における保健行動がその後に与える影響 2-1 キャリアに与える影響 2-2 賃金に与える影響 2-3 健康に与える影響 34
3. 分析アプローチ 推計1 若年期女性就業者の保健行動の規定要因 順序ロジットモデル 被説明変数 保健行動スコア ⇒若年期(20〜30代)の就業者に限定して分析を行い、 男女と女性内での雇用形態で比較する。 説明変数 勤務時間制度 ・フレックスタイムダミー ・短時間勤務制度ダミー ・在宅勤務制度ダミー ・半日・時間単位の休暇制度ダミー ・通常勤務時間制度ダミー ・変形労働時間制交代制ダミー ・裁量労働みなし労働制ダミー 週労働時間 週労働時間の二乗 コントロール変数 収入、管理職ダミー、勤 続年数、婚姻ダミー、子 供ありダミー、未就学児 ダミー、学歴、年ダミー、 年齢ダミー、職種ダミー、 産業ダミー、企業規模ダ ミー 35
3. 【仮説】 分析アプローチ 推計① 企業制度を利用していて、柔軟な働き方をしている人の方が、 若年期女性就業者の保健行動の規定要因 1 保健行動を起こしやすい。 Ex)時間的余裕から、健康状態が悪化した時に病院に行きやすい 順序ロジットモデル ⇒若年期(20〜30代)の就業者に限定して分析を行う。 2 労働時間が短い人の方が、保健行動を起こしやすい。 Ex)時間的余裕から、健康状態が悪化した時に病院に行きやすい 説明変数 被説明変数 コントロール変数 勤務時間制度 ・フレックスタイムダミー ・短時間勤務制度ダミー ・在宅勤務制度ダミー ・半日・時間単位の休暇制度ダミー ・通常勤務時間制度ダミー ・変形労働時間制交代制ダミー ・裁量労働みなし労働制ダミー 正 保健行動スコア 週労働時間 週労働時間の二乗 負 収入、管理職ダミー、 勤続年数、婚姻ダ ミー子供ありダミー 未就学児ダミー学歴 年ダミー年齢ダミー、 職種ダミー、産業ダ ミー、企業規模ダ ミー 36
3. 分析アプローチ 推計2-1 若年期における保健行動がその後のキャリアに与える影響 変量効果プロビットモデル 被説明変数 ⇒全体、男女で比較する。 説明変数 若年期保健行動スコアの平均値 40代以降の管理職ダミー 若年期保健行動ダミーの平均値 ・売薬を購入したダミー ・病院や診療所に通院したダミー ・保健行動非実施ダミー コントロール変数 勤続年数、勤続年数の 二乗、週労働時間、週 残業時間、年齢、年齢 の二乗、婚姻ダミー、 子供ありダミー、未就 学児ダミー、学歴、収 入 37
3. 分析アプローチ 推計2-2 若年期における保健行動がその後の賃金に与える影響 ⇒全体、男女、女性間の雇用形態で比較する 変量効果モデル 被説明変数 説明変数 若年期保健行動スコアの平均値 40歳以降の収入 若年期保健行動ダミーの平均値 ・売薬を購入したダミー ・病院や診療所に通院したダミー ・保健行動非実施ダミー コントロール変数 勤続年数、勤続年数の二乗、 週労働時間、週残業時間、年 齢、年齢の二乗、婚姻ダミー、 子供ありダミー、未就学児ダ ミー、学歴、年ダミー 35歳時点の収入 38
3. 分析アプローチ 推計2-3 若年期における保健行動がその後の健康に与える影響 順序ロジットモデル 被説明変数 40代以降の主観的健康指標 (値が高いほど、健康状態が良 いことを示す) ⇒全体、男女、女性間の雇用形態で比較する。 説明変数 若年期保健行動スコアの平均値 若年期保健行動ダミーの平均値 ・売薬を購入したダミー ・病院や診療所に通院したダミー ・保健行動非実施ダミー コントロール変数 勤続年数、勤続年数の二乗、 年齢、年齢の二乗、婚姻ダ ミー、子供ありダミー、未就 学児ダミー、学歴、職種ダ ミー、産業ダミー、企業規模 ダミー、年ダミー 39
3. 分析アプローチ 推計2 仮説 2-1 2-2 若年期の保健行動スコアが高い人ほど、管理職率は向上する 。 Ex)健康状態が良くなるため、労働生産性が上がる。 若年期の保健行動スコアが高い人ほど、昇進確率が上がるた め、収入も上がる。 Ex)健康状態が良くなるため、労働生産性が上がる。 2-3 若年期の保健行動スコアが高い人ほど、その後の健康状態が良 くなる Ex)若い時に適切に病気に対処している人ほど、その後の健康も良い 40
3. 分析アプローチ 推計② 仮説 2-1 若年期の保健行動スコアが高い人ほど、管理職率は向上する 。 被説明変数 説明変数 コントロール変数 Ex)健康状態が良くなるため、労働生産性が上がる。 勤続年数、勤続年数の二 若年期保健行動スコアの平均値 乗、年齢、年齢の二乗、 ・40代以降の管理職ダミー 若年期保健行動スコアの平均値 正 若年期保健行動ダミーの平均値 婚姻ダミー、子供ありダ 若年期の保健行動スコアが高い人ほど、昇進確率が上がるた ・売薬を購入したダミー ミー、未就学児ダミー、 ・40代以降の収入 2-2 め、収入も上がる。 ・病院や診療所に通院したダミー 学歴、職種ダミー、産業 Ex)健康状態が良くなるため、労働生産性が上がる。 ・保健行動非実施ダミー ダミー、企業規模ダミー、 ・40代以降の主観的健康指標 負 年ダミー 35歳時点の収入 2-3 若年期の保健行動スコアが高い人ほど、その後の健康状態が良 くなる Ex)若い時に適切に病気に対処している人ほど、その後の健康も良い 41
3. 分析アプローチ 使用データ 日本家計パネル調査(JHPS/KHPS) 〈調査対象〉 KHPS:20歳~69歳の男女 JHPS:20歳以上の男女 〈対象時期〉 KHPS:2004年~2022年 JHPS:2009年~2022年 調査対象者とその配偶者のデータを使用し かつ就業者に標本を限定している。 42
3. 分析アプローチ 変数説明(保健行動スコア) 保健行動スコア 保健行動 2 3「病院や診療所に通院した」 1 5「売薬を購入した」 0 2「症状があったがなにもしていない」 上記のように点数化した保健行動スコアの年度ごとの合計値を その年の保健行動指標と定義し、値が大きい方が保健行動をとっていることを示す 順序変数として扱う。 43 推計2においては、若年期の合計スコアを回答年度で割った平均を用いる。
3. 分析アプローチ 変数説明(保健行動ダミー) 同様の質問項目において、2, 3, 5のいずれかを回答した就業者を対象に それぞれの保健行動を選択していれば1、していなければ0をとるダミー変数を作成。 推計2においては、若年期の保健行動ダミー合計スコアを回答年度で割って算出した平均値を用いる。 回答番号 変数名 2 保健行動非実施ダミー 3 病院や診療所に通院したダミー 5 売薬を購入したダミー 44
3. 分析アプローチ 変数説明(保健行動指標) 対象者の健康状態を等しくするという観点から 「1 健康体でとくになにもしていない」「4 入院した」を回答した標本は 除外している。 45
3. 分析アプローチ 変数説明(勤務時間制度ダミー) それぞれの項目を選択していれば1、 それ以外を0とする ダミー変数を作成 「3 利用経験あり」を選択している 場合を1、それ以外を0とするダミー 変数を作成 46
3. 分析アプローチ 変数説明(管理職ダミー・主観的健康) 管理職ダミー 2 常勤の職員・従業員(正規社員)ー役職あり 3 常勤の職員・従業員(正規社員)ー経営者 を回答していれば1、 それ以外を0とするダミー変数 主観的健康指標 反転させ、値が大きいほど健康状態が良いことを示す5段階の指標 47
3. 分析アプローチ 基本統計量(被説明変数・説明変数) 若年期保健行動スコアに関して 平均値が男性より女性が高く、特に女性の正 規雇用で高いため、若年期になんらかの症状 があった場合、 正規雇用者を中心に女性の方が保健行動を起 こしやすいと考えられる。 令和5年度内閣府委託調査における 女性の方が保健行動を起こしやすいという結果と整合的 時間的制約の大きい正規雇用者のほうが病院に行く時間 がないという結果とは異なる傾向 48
3. 分析アプローチ 基本統計量(コントロール変数) 49
4. 分析結果
4.分析結果 分析の流れ 1 若年期女性就業者の保健行動の規定要因 2 若年期における保健行動がその後に与える影響 2-1 キャリアに与える影響 2-2 賃金に与える影響 2-3 健康に与える影響 51
4.分析結果 推計1 予備的分析 女性において、一定時間を超えると、 若年期の保健行動スコアが 低下する傾向が見られる。 全体において、短時間勤務、半日・時間単位 の休暇制度を取り入れている方が、若年期の 保健行動スコア平均値は高まる。 52
4.分析結果 推計1 予備的分析 男性において、短時間勤務、在宅勤務、半 日・時間単位の休暇を取り入れている方が、 若年期の保健行動スコア平均値が高まる。 女性全体において、短時間勤務、半日・時間 単位の休暇制度を取り入れている方が、若年 期の保健行動スコア平均値が高まる。 53
4.分析結果 推計1 予備的分析 女性正規雇用者において、フレックスタイ ム、短時間勤務を取り入れている方が、若 年期の保健行動スコア平均値が高まる。 女性非正規雇用者において、特に短時間勤務、 半日・時間単位の休暇制度を取り入れている方 が、若年期の保健行動スコア平均値が高まる。 54
4.分析結果 推計1 結果(全体) 55
4.分析結果 推計1 結果(抜粋) 女性全体 短時間勤務制度ダミーと半日・時間 単位の休暇制度ダミーで正に有意で ある。また、週労働時間は有意では ないが係数は負の値である。 女性正規 勤務時間制度で有意は出なかった。 週労働時間は負に有意である。 女性非正規 全サンプル 在宅勤務制度を除いた全ての勤務 時間制度が正に有意である。週労 働時間は有意ではないが、係数は 負の値である。 男性 半日・時間単位の休暇制度ダミーが 正に有意である。週労働時間は有意 ではないが係数は負の値である。 短時間勤務ダミー、半日・時間単位 の休暇制度ダミー、裁量労働・みな し労働制ダミーが正に有意である。 56
4.分析結果 推計1 暫定結果(抜粋) 女性非正規雇用者について、勤務時間制度ダミーから 短時間勤務制度や半日・時間単位の休暇制度ダミーといった柔軟な働き方が 女性全体 短時間勤務制度ダミーと半日・時間 保健行動に正の影響を与えていると考えられる。 単位の休暇制度ダミーで正に有意で ある。また、週労働時間は負の傾向 また、女性正規雇用者について、週労働時間が負に有意であることから、長 がある。 時間労働は、保健行動を阻害する要因となっている可能性がある。 女性正規 週労働時間の二乗については女性就業者で正に有意であることから、労働時 間が短いと保健行動を取り、増加すると保健行動を取らなくなる傾向がある 勤務時間制度で有意は出なかった。 が、一定時間を超えて増加すると、心身への負荷がかかり、症状が悪化する 週労働時間は負に有意である。 ため保健行動をとるという解釈ができる。 女性非正規 全サンプル 短時間勤務ダミー、半日・時間単位 就業者にとって、柔軟な勤務時間制度や時間的余裕が、 の休暇制度ダミー、裁量労働・みな 男性 保健行動を促す要因となる可能性が高い。 し労働制ダミーが正に有意である。 在宅勤務制度を除いたすべての勤務時間 制度が正に有意である。また、週労働時 間は有意ではないが、係数は負の値であ る。 半日・時間単位の休暇制度ダミーが正に有 意である。また、週労働時間は有意ではな いが、係数は負の値である。 57
4.分析結果 分析の流れ 1 若年期女性就業者の保健行動の規定要因 2 若年期における保健行動がその後に与える影響 2-1 キャリアに与える影響 2-2 賃金に与える影響 2-3 健康に与える影響 58
4.分析結果 推計2-1 予備的分析 全体を通して、若年期の保健行動スコアが高いほど 管理職になる割合が高い。 女性が平均値未満との差が一番大きい。 わずかに薬購入した人の方が、管理職割合が高い。 59
4.分析結果 推計2-1 予備的分析 男性を中心に通院した人の方が管理職割合が高い。 女性を中心に保健行動を行っていなかった人の方が 管理職である割合が低く、男性ではわずかに逆の傾 向が見られた。 60
4.分析結果 推計2-1 結果(全体) 61
4.分析結果 推計2-1 結果(抜粋) 全体 男性 女性 + + 正に有意 正に有意 正に有意 + 病院や診療所に通院したダミー + - + 若年期保健行動非実施ダミー - + − 若年期保健行動スコア平均値 売薬を購入したダミー 62
4.分析結果 推計2-1 結果(抜粋) 女性就業者について、若年期保健行動スコア平均値の係数が 有意になっていることから 若年期に保健行動を行なっていると、 40代以降に管理職になる確率が高まることが考えられる。 若年期保健行動実施ダミーからは、有意ではないものの係数が正の値であ り、保健行動は40代以降の管理職のなりやすさに正の影響を与えると言え る。 全体 男性 女性 若年期保健行動スコア平均値 + + 正に有意 売薬を購入したダミー - + - 病院や診療所に通院したダミー - - - 適切な保健行動は、将来のキャリアに正の影響を与える可能性が高い 通院+薬購入ダミー + 正に有意 + 若年期保健行動非実施ダミー - + - 63
4.分析結果 分析の流れ 1 若年期女性就業者の保健行動の規定要因 2 若年期における保健行動がその後に与える影響 2-1 キャリアに与える影響 2-2 賃金に与える影響 2-3 健康に与える影響 64
4.分析結果 推計2-2 予備的分析 全サンプルと女性においては、 若年期の保健行動スコアが高い人ほど、 その後の収入変化率が高いことがわかる。 一方で男性サンプルにおいては女性と逆の傾向が見られた。 若年期に売薬を購入している人ほど 女性正規雇用者を中心に、 その後の収入変化率は高まる。 65
4.分析結果 推計2-2 予備的分析 女性を中心に、通院した人の方がその後の収入変化率が 高い。 女性非正規就業者が特に、保健行動を取っていない人 の方が収入が低下する傾向が見られる。 66
4.分析結果 推計2-2 結果(全体) 67
4.分析結果 推計2-2 結果(抜粋) 全体 男性 女性 女性正規 女性非正規 若年期保健行動スコア 平均値 + - + − 正に有意 売薬を購入したダミー − − − + - 病院や診療所に通院し たダミー + − 正に有意 負に有意 正に有意 保健行動非実施ダミー + + - + 負に有意 68
4.分析結果 推計2-2 結果(抜粋) 女性非正規雇用者では、若年期保健行動スコア平均値の係数から 若年期に保健行動を行なっていると、40代以降の収入変化率が高いことがわかる。 特に症状があった際に、病院や診療所に通院していると その後の収入変化率を高めていると考えられる。 また、症状があったがなにもしていない就業者は 、他の保健行動を行っている就業者に比べて、収入変化率が低下している。 さらに、全体として売薬を購入することは収入変化率に負の影響を与えていることから 、薬を購入することは長期的にはキャリアに何らかの障壁をもたらし、 全体 賃金が低下している可能性を指摘できる 男性 女性 女性正規 女性非正規 若年期保健行動スコア 平均値 + - + − 正に有意 売薬を購入したダミー − − − + - 病院や診療所に通院し たダミー + − 正に有意 正に有意 負に有意 雇用形態や保健行動の形態によって異なるが、女性非正規雇用者に着目すると、 保健行動非実施ダミー 適切な保健行動が将来の賃金変化率に正の影響を与えている可能性が高い。 + + - + 負に有意 69
4.分析結果 分析の流れ 1 若年期女性就業者の保健行動の規定要因 2 若年期における保健行動がその後に与える影響 2-1 キャリアに与える影響 2-2 賃金に与える影響 2-3 健康に与える影響 70
4.分析結果 推計2-3 予備的分析 全サンプルと男性において、 若年期の保健行動スコアが平均値以上のほうが その後の主観的健康指標の平均値が高いことがわか る。女性非正規雇用者では逆の傾向が見られた。 女性雇用形態別に見ると、 非正規雇用者において、わずかに若年期に売薬を購入した ダミー平均値が高い人ほど、主観的健康指標が低下する傾 向が見られた。 71
4.分析結果 推計2-3 予備的分析 女性を中心に、若年期に病院や診療所に通院したダ ミー平均値が高い人ほど、主観的健康指標が低下し ている。 女性を中心に、若年期保健行動非実施ダミー平均値が高い 人ほど、主観的健康指標が低い傾向にある。 72
4.分析結果 推計2-3 結果(全体) 73
4.分析結果 推計2-3 結果(抜粋) 全体 男性 女性 女性正規 女性非正規 若年期保健行動スコア 平均値 正に有意 正に有意 + 正に有意 - 売薬を購入したダミー 正に有意 + 正に有意 正に有意 正に有意 病院や診療所に通院し たダミー 正に有意 正に有意 − + 負に有意 保健行動非実施ダミー 負に有意 負に有意 負に有意 負に有意 負に有意 74
4.分析結果 推計2-3 結果(抜粋) 全体として、若年期保健行動スコア平均値や 保健行動実施ダミー平均値の係数が、正に有意となっている割合が高く、 反対に症状があったが何もしていない就業者は他の保健行動を行なってい る就業者に比べて、その後の主観的健康度が低下している。 しかし、女性非正規雇用者に着目すると、通院することがその後の主観的 健康を低下させる傾向が見られた。 全体 男性 女性 女性正規 女性非正規 若年期保健行動スコア 平均値 正に有意 正に有意 + 正に有意 - 売薬を購入したダミー 正に有意 + 正に有意 正に有意 正に有意 雇用形態や保健行動形態により若干の違いは見られるが、全体を通し、 正に有意 正に有意 − + 負に有意 若年期の保健行動はその後の主観的健康に正の影響を与える可能性が 保健行動非実施ダミー 負に有意 負に有意 負に有意 負に有意 負に有意 高い。 病院や診療所に通院し たダミー 75
5. おわりに
5. おわりに まとめ①(若年期保健行動の規定要因) 週労働時間 少 時間的余裕 保健行動を起こ しやすくなる 柔軟な働き方 女性正規雇用者では、週労働時間が少ないほど、また女性非正規雇用者では、短時間勤務制度、 半日・時間単位の休暇制度などの柔軟な働き方が、若年期の保健行動を起こしやすくしていると 考えられる 77
5. おわりに まとめ②(若年期保健行動がその後に与える影響) キャリア 女性において全体的に若年期の保健行動をしている就業者ほど、 40代以降の管理職割合が高く、 適切な保健行動がその後のキャリアに正の影響を与えていることが分かった。 男性においては、若年期に薬を購入して症状に対処していることが40代以降の管理職割合を高めていた。 収入 健康 女性非正規雇用者において、若年期に保健行動をしている人ほど、 その後の収入が高まっていた。また、収入に与える影響は雇用形態や保健行動の 種類により異なっており、具体的には女性正規雇用者では病院や診療所への通院 がその後の収入を高めるが、女性非正規雇用者では逆の傾向が見られた。 健康に与える影響も雇用形態や保健行動の種類により違いが見られ、 女性正規雇用者では保健行動全般がその後の主観的健康指標を向上させるこ とが示されたが、女性非正規雇用者では、通院することがその後の主観的健 康を低下させる傾向が見られた。 78
5. おわりに まとめ③ 女性就業者において、柔軟な働き方とそれらを選択できる企業制度が 若年期における適切な保健行動を促している。 また、若年期に症状があった場合、適切な保健行動をとっている就業者ほど その後のキャリア・収入・健康が高まっている。 政府や企業は若年層に向けて保健行動を取ることの重要性を訴えることに加え、 保健行動を促す支援実施などを積極的に行い、 若年層の健康サポートを強化していく必要性があると言える。 79
5. おわりに 懸念点 女性の標本数が、男性と比較して少ない点 サンプルの健康状態を等しくするという観点から除外している サンプルがあるため、サンプルセレクションバイアスが生じて いる可能性がある点 80
参考文献 ・Taloyan et al.(2012) “Sickness Presenteeism Predicts Suboptimal Self-Rated Health and Sickness Absence: A Nationally Representative Study of the Swedish Working Population”. pp1-8 ・Tsuchiya et al. (2012)”Impact of mental disorders on work performance in a community sample of workers in Japan: The World Mental Health Japan Survey 2002–2005”,Psychiatry Res, 198(1), pp140-145 ・Kivimaki et al. (2005) “Working while ill as a risk factor for serious coronary events: the Whitehall II study”. 95(1) pp 98-102 ・Conway et al. (2014) “Is Sickness Presenteeism a Risk Factor for Depression? A Danish 2-Year Follow-Up Study”. 56(6) pp 595603 ・Hansen et al.(2009) “Sick at Work — A Risk Factor for Long-Term Sickness Absence at Later Date”. 63(5) pp 397-402 ・Fujino et al, (2024) “A prospective cohort study 1 of presenteeism and increased risk of unemployment among Japanese workers during COVID-19 pandemic”, Journal of Occupational Health, 66(1), ・Suzuki et al., (2015) “Relationship between sickness presenteeism (WHO–HPQ) with depression and sickness absence due to mental disease in a cohort of Japanese workers”,Journal of Affective Disorders, 180(15), pp14-20. ・中添和代・斉藤静代・松村千鶴・森口靖子(2000)「予防的保健行動をとる人の健康意識と生活習慣」香川県立医療短期大学紀要, pp123-128 ・松本泉美・富永紀子・遠藤將光・東山明子・王宝禮(2010)「職域における喫煙者のニコチン依存と保健行動」喫煙科学, pp1-41 81
参考文献 ・阿部彩(2013)「誰が受診を控えているのか:J-SHINEを使った初期的分析」CIS Discussion Paper Series No.603 ・飯塚暁子・箕口 雅博・兒玉 憲一(2005)「大学生の病気対処行動とソーシャルサポートの関連」広島大学大学院心理臨床教育センター紀要, 4, pp90-99 ・岡庭英重(2017)「メンタルヘルス不全が所得に及ぼす影響に関する実証分析」厚生の指標, 64(5), pp14-21 ・田村香奈・宮崎有紀子(2023)「職場のソーシャル・キャピタルが看護職の予防的保健行動と 病気対処行動に及ぼす影響」日本健康学会誌, 89(1), pp4-14 ・髙橋勇介(2022)「パネルデータによる労働者の心身の健康についての実証分析ー労働経済学の観点からみた労働者のストレス反応の問題」 経済政策ジャーナル, 19(2), pp1-16 ・髙橋勇介(2023)「労働者の健康問題と生活と仕事の満足度についての考察 -労働市場政策との関係から-」社会関係研究, 2(4), pp41-53 ・中川栄利子・樋口倫代(2022)「就労女性における就労形態別の労働要因および社会経済的要因と受診抑制の関連」日本公衛誌, 69(6), pp447-458 ・山岡順太郎・小林美樹(2015)「労働者のメンタルヘルスと職場環境に関する実証分析」Discussion Paper No.1505. February 2015, 神 戸大学大学院経済学研究科 82
参考文献 ・西岡笑子・ 飯島佐知子・三上由美子・横山和仁(2024)「働く女性の健康に関するweb調査ー女性特有症状とその対処およびがん検診受験状 況正規雇用と非正規雇用の比較ー」順天堂保健看護研究, 第12巻, pp12-23 ・甲斐村美智子・上田公代(2014)「若年女性における月経随伴症状と関連要因がQOLへ及ぼす影響」女性心身医学, 18(3), pp412-421 ・甲斐村美智子・羽田野花美・末永芳子(2023)「看護師の月経随伴症状が労働生産性および QOL に及ぼす影響」女性心身医学, 27(3), pp305-312 ・佐々⽊那津・津野香奈美・日高結⾐・安藤絵美子・浅井裕美・櫻⾕あすか ・日野 亜弥子・井上嶺子・今村幸太郎・渡辺和広・堤明純・川上 憲人(2021)「 日本人女性労働者の就労上課題となる生物心理社会的な要因、制度利用状況、期待する職場での研究テーマのニーズ:患者・ 市民参画(PPI:Patient and Public Involvement)を用いたインターネット調査による横断研究」産業衛生学雑誌 ・渡部真澄(2019)「女性疾病・疾患罹患者の プレゼンティズムとその要因 」社会デザイン学会学芸誌, pp98-108 ・ Sato et al., (2011)”Associations between Hours Worked, Symptoms and Health Resource Utilization among Full time Male Japanese”, Journal of Occupational Health, 53(3), pp197-204. ・山崎久美子・森田眞子・大芦治(1993)「大学生の心身の保健行動とその影響要因」心身医, pp502-507 83
参考文献 ・男女共同参画局(2022)『令和5年度男女共同参画白書』 https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r05/zentai/pdfban.html ・厚生労働省(2023)『令和6年度経済白書』 https://www5.cao.go.jp /keizai3/whitepaper.html ・経済産業省 ヘルスケア産業課(2024)『女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について』 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles /jyosei_keizaisonshitsu.pdf ・男女共同参画局(2021) 『令和4年度男女共同参画白書』 https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/html/honpen/b1_s02_01.html ・内閣府委託調査(2024) 『男女の健康意識に関する調査』 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/kenkou_r05s/00.pdf ・男女共同参画局(2020)『コラム1 生活時間の国際比較』 https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/html/column/clm_01.html 84
- https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r05/zentai/pdfban.html
- https://www5.cao.go.jp/keizai3/whitepaper.html
- https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/jyosei_keizaisonshitsu.pdf
- https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/html/honpen/b1_s02_01.html
- https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/kenkou_r05s/00.pdf
- https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/html/column/clm_01.html
ご清聴ありがとうございました
6. 質疑応答