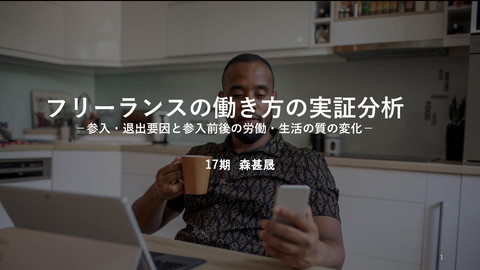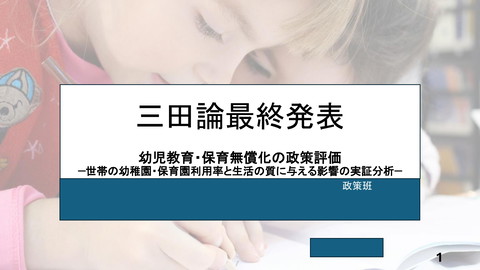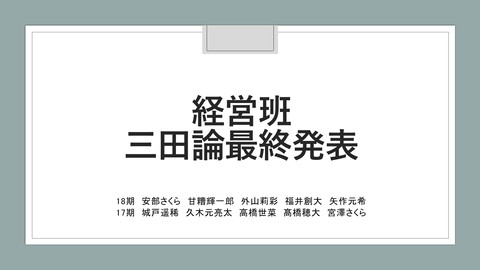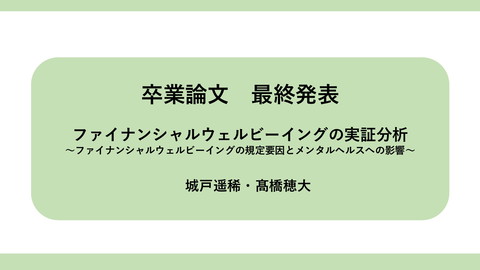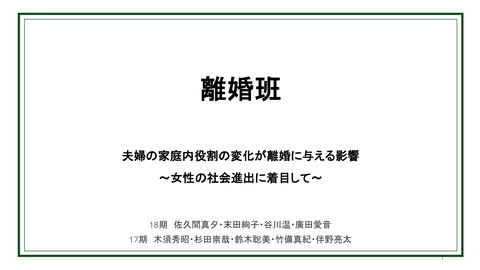2024卒業論文_木須秀昭・宮澤さくら
4K Views
February 19, 25
スライド概要
このスライドでは、祖父母による孫育児の現状とその背景について考察しています。特に、男性の働き方が育児参加にどのような影響を与えるかに注目しています。また、祖父母が孫育児に参加することが、親の育児負担軽減や母親の健康・幸福度に与える影響についても触れています。さらに、父方と母方の祖父母の育児参加の違い、及び育児参加が祖父母自身の幸福度に与える影響も分析しています。最後に、育児参加を支援するための制度的な取り組みについても言及しています。
慶應義塾大学商学部商学科山本勲研究会 ホームページ: https://www.yamazemi.info Instagram: https://www.instagram.com/yamazemi2024
関連スライド
各ページのテキスト
祖父母による孫育児の比較分析 :現役時代の働き方への注目と健康・幸福度への影響 17期 木須秀昭・宮澤さくら 1
アウトライン 背景・問題意識 先行研究 分析アプローチ 考察・課題点 質疑応答 4
アウトライン 背景・問題意識 先行研究 分析アプローチ 考察・課題点 質疑応答 5
背景・問題意識 性別役割分業意識の薄まり かつて日本には「男性は仕事、女性は家庭」という性別役割分業意識があったが、 女性の社会進出や、政府・社会による男性の育休取得促進に伴い、徐々に薄まりつつある 【生産年齢人口における女性の就業率の推移】 1986年 53.1% 増加 2016年 66.0% (男女雇用機会均等法施行) 第1節 働く女性の活躍の現状と課題 | 内閣府男女共同参画局 (gender.go.jp)) 6
背景・問題意識 家庭内における性別役割分業意識 松田(2000) 家庭内における分業はいまだ強固に維持されている。 6歳未満の子供の育児時間 父:1時間6分 < 母:3時間37分 2016年と比較して男性の育児時間の増加は 女性と比べて顕著に小さい。 育児負担の割合は女性に大きく偏っており、 男性は女性と比べて育児に参加していないこと がわかる。 総務省統計局結果の概要 (stat.go.jp) https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2019/201912/201912_04.html 7
背景・問題意識 男性による育児参加の現状 男性・正社員が利用した育児休業制度 の利用状況および利用希望 育児休業制度の利用を希望していたものの 利用しなかった割合➤37.5% 厚生労働省雇用環境・均等局 職業生活両立課000851662.pdf (mhlw.go.jp) https://www5.cao.go.jp/keizai2/wellbeing/covid/pdf/result3_covid.pdf 1カ月以上の育児休暇を取得しない理由 4割以上の男性➤「職場に迷惑をかけたくない」 3割近くの男性➤「会社や上司、職場の育児休業 制度取得への理解がない」 8
背景・問題意識 男性による育児参加の現状 【男性・正社員が利用した育児休業制度 の利用状況および利用希望】 【1カ月以上の育児休暇を取得しない理由】 多賀(2005)が解釈しているように、男性は育児に参加したいと 思っても、仕事を理由に育児参加できていない現状がある。 育児休業制度の利用を希望していたものの 利用しなかった割合➤37.5% 厚生労働省雇用環境・均等局 職業生活両立課000851662.pdf (mhlw.go.jp) https://www5.cao.go.jp/keizai2/wellbeing/covid/pdf/result3_covid.pdf 4割以上の男性➤「職場に迷惑をかけたくない」 3割近くの男性➤「会社や上司、職場の育児休業 制度取得への理解がない」 9
背景・問題意識 男性による育児参加と仕事の関係性 男性による現役時代の働き方が子への育児参加に与える影響を分析した研究が多く存在する Nishioka(1998) 労働時間が長いと育児参加率が低 下することを示した 多喜代ほか(2019) 週労働時間が増加すると育児参加率 が低下する 【日本労働組合総連合会の調査】 週労働時間が長い父親ほど、週平 均育児時間は短くなることが示さ れている https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20191008.pdf 10
背景・問題意識 祖父母による育児参加の重要性 育児負担の大きい子育て世代をサポートする仕組み 保育所や育児サロンといった公的な支援とともに、祖父母からの支援もまた大事な 育児支援資源であると、小松ほか(2010)で述べられている Asai et.al.(2015) 祖父母が孫育児に参加すること で、妻の労働力率が高くなる Morita et.al.(2021) 祖父母による孫の育児支援があると、 母親の子への虐待リスクが低下する 11
背景・問題意識 祖父母による育児参加の重要性 育児負担の大きい子育て世代をサポートする仕組み 保育所や育児サロンといった公的な支援とともに、祖父母からの支援もまた大事な 祖父母による育児参加は、親の育児負担を軽減させる。 育児支援資源であると、小松ほか(2010)で述べられている 近年では、政府や自治体、民間企業の間で、祖父母が孫の育児のために 仕事を休むことができる「孫休暇」という制度の導入が進んでいる。る。 Asai et.al.(2015) 祖父母が孫育児に参加すること で、妻の労働力率が高くなる Morita et.al.(2021) 祖父母による孫の育児支援があると、 母親の子への虐待リスクが低下する 12
背景・問題意識 祖父母による育児参加の現状 八重(2003) 孫への子育て参加の頻度は、①母方祖母、②父方祖母、③母方祖父、④父方祖父の順に高い。 平井(2021) 3世代同居家族における祖父母の家事・育児時間は、祖父で34.55分であるのに対して、 祖母で230.15分となっており、育児・家事負担が祖母に大きく偏っている 13 https://www.nstac.go.jp/sys/files/static/services/pdf/211118_6.pdf
背景・問題意識 祖父母による育児参加の現状 八重(2003) 孫への子育て参加の頻度は、①母方祖母、②父方祖母、③母方祖父、④父方祖父の順に高い。 平井(2021) 現役世代の男性は仕事を理由に育児参加できておらず、 3世代同居家族における祖父母の家事・育児時間は、祖父で34.55分であるのに対して、 そのような状況は祖父となり仕事を退職した後も変わっていない。 祖母で230.15分となっており、育児・家事負担が祖母に大きく偏っている 14
背景・問題意識 孫への育児参加が与える影響 孫への育児参加は、祖父母に様々な影響を与えることが分かっている Dunifon et.al.(2020) 孫と同居しながら育児を 行っている祖父母は、単 独世帯や孫と同居してい ない高齢者と比べて幸福 度が高くなる Wang et.al.(2019) 孫の育児をした場合、うつ病の割合が 2.9%下がることや健康状態が良好な人 の割合が増加し、また生活満足度につ いて非常に満足している人が2.7%増え るという結果が得られた 小松ほか(2010) 文献的考察では、孫への 育児参加が祖父母に悪影 響を与える可能性を示唆 海外の研究では、孫育児をすることは祖父母に対して身体的・精神的に良い影響を与えると まとめる研究が多いものの、日本の祖父母を対象にした文献的考察では、悪影響を示している 17
背景・問題意識 現役時代の働き方に注目 多くの先行研究では、現役時代と退職後のそれぞれの時点において、男性の育児参加の 規定要因について分析し、働き方や年齢などの個人属性が影響を与えることが指摘されてきた 男性の現役時代の働き方が、退職後の祖父に よる孫の育児参加に影響を与えるかについて は分析されていない 日本の祖父母に着目し、孫の育児参加が彼らの健 康・幸福度に与える影響について実証分析した研 究は存在しない 18
背景・問題意識 本研究で明らかにすること 本分析 孫育児に影響を与える働き方について、現役時代という過去に注目して分析する。 かつて労働時間が長く正規雇用かつ自営業・自由業等ではない祖父ほど、孫への育児参 加が減少するかを明らかにする。 ◼ 仕事を理由に育児参加していなかった男性は、退職し祖父となっても孫の育児を せず、負担は祖母に偏っているため ◼ 海外の先行研究から、日本の祖父母においても孫育児は彼らの健康・幸福度を高 める影響があると考える 19
背景・問題意識 独自性 ①男性に注目して、現役時代の働き方が孫の育児参加に与える影響と祖父母の健康・ 幸福度に長期的に与える影響を分析する点 • 現役時代の働き方に着目し、過去の就業形態が祖父となった後の孫への育児参加に与える影響について分 析した研究は存在しない • 現役時代の働き方が健康・幸福度に与える影響を分析した研究は日本では存在しない ②パネルデータを用いて同一個人を長期的(現役時代~現在)に分析する点 • 先行研究では、男性による育児参加の規定要因について、ある一時点におけるデータを使用した研究が多 く、数年にわたって長期的な個人の変化を分析した実証分析は存在しない • パネルデータを用いて、パネルデータを用いることで、観測不能な個々人の特性をコントロールした上で、 同一主体における変化を的確に示す 21
アウトライン 背景・問題意識 先行研究 分析アプローチ 考察・課題点 質疑応答 22
先行研究 先行研究の分類 祖父母による育児参加が親に与える影響 男性による育児参加の規定要因 孫への育児参加が祖父母の健康・幸福度に与える影響 23
先行研究 祖父母による育児参加が親に与える影響 八重樫ら(2003) Asai et.al.(2015) Morita et.al.(2021) • 祖父母が孫育児に参加することで、母親の労働力 • 祖父母による孫育児に対する支援があると、母親 率が高くなる。 の子への虐待リスクが低下する。 八重樫ら(2003) 余田ら(2018) • 孫をお風呂に入れてあげたり、一緒に遊んだり、 • 専業主婦に比べて働いている母親の方が祖父母か 子育て相談をしてくれるような祖父母を持ってい らより多くの育児サポートを受けていることや、 る母親ほど、子育てへの不安は低減することを明 母親の正規雇用転換などの就業状況の変化が祖父 らかにした。 母からの育児支援の変化と連動していることを示 した。 24
先行研究 祖父母による育児参加が親に与える影響 八重樫ら(2003) Asai et.al.(2015) Morita et.al.(2021) • 祖父母が孫育児に参加することで、妻の労働力率 • 祖父母による孫育児に対する支援があると、母親 が高くなる。 の子への虐待リスクが低下する。 祖父母による育児参加は、現役世代の育児負担を減ら すことに大きく貢献している 八重樫ら(2003) 余田ら(2018) • 孫をお風呂に入れてあげたり、一緒に遊んだり、 • 専業主婦に比べて働いている母親の方が祖父母か 子育て相談をしてくれるような祖父母を持ってい らより多くの育児サポートを受けていることや、 る母親ほど、子育ての不安は低減することを明ら 母親の正規雇用転換などの就業状況の変化が祖父 かにした。 母からの育児支援の変化と連動していることを示 した。 25
先行研究 男性による育児参加の規定要因 水落(2006) 平井(2001) • 労働時間に加えて、通勤時間などの時間外労働時間を含めた父親の 仕事による拘束時間を同時に推定し、父の子への育児参加に与える 影響について分析した。また、共働き世帯か否かに分け、かつ母親 の就業状態をコントロールして分析した結果、父親の労働時間が長 いほど育児時間は減少し、共働き世帯では、労働時間よりも通勤時 間のほうが育児参加により大きな影響を与えることを明らかにした • 3世代同居世帯の祖父母に対象を絞って、家事・育児時間の算出や その規定要因についての分析を行った。祖父はほとんど家事や育児 をしないことが分かった。また、学歴が高く同居する父の家事・育 児時間が長いほど、祖父による家事・育児時間も増えることが分 かった。祖母においては学歴による効果は見られず、妻方同居の場 合や両親が共働きであるほど長くなることが分かった。祖父母それ ぞれの家事・育児の規定要因は本人の年齢、学歴、父母の就業状況、 孫の年齢や数、同居形態によって決定付けられる。 多喜代ほか(2019) 西岡(1998) 松田(2000) • 園児の父親を対象に、育児の参加時 間や意欲、育児を行う上での周囲の 環境に関するアンケート調査行った 結果、週労働時間が長くなるほど、 平日の育児時間が減少することが分 かった。 • 育児に参加する父親を対象にして、 育児を5類型(遊び、入浴、寝かし つけ、食事、おむつ交換)に分けて 分析した。では、、子供の年齢が低 く正規雇用長時間労働になると育児 参加が減りの妻を持つ場合に育児参 加が増えることが分かった。 • 夫の家事・育児参加の要因分析では、 年収や学歴が高く、妻が正規雇用の 場合、また末子年齢が12歳以下の 場合に育児参加が増加する。祖母や 13歳以上の子が同居していた場合、 育児参加が減ることが分かった。 26
先行研究 男性による育児参加の規定要因 青木ほか(2004) Gasser(2017) • 都内の保育園に通う子を持つ父母163人を対象にし • フレックスタイム制度の利用状況や職場での職位が たアンケート調査では、性別役割分業意識が強い父 親ほど育児参加しないことが分かった。 子の育児時間にどのような影響を与えるかを分析し、 管理職に就いていない父親は平日に約93.2分育児に 携わる一方で、管理職に就いている父親は平日に約 85.3分育児に携わることから、職位が高いほど育児 に参加しないことがわかった。 Brayfield(1995) Craig(2011) • 母親との勤務時間帯が異なる場合に子育てにより • 母親が職に就いている人ほど父親は育児により積 積極的に参加することを明らかにしている。 極的に参加することや、オーストラリアやデン マークの家庭では、高学歴の父親ほど育児に参加 することが示唆されている 27
先行研究 男性による育児参加の規定要因 青木ほか(2004) Gasser(2017) • 都内の保育園に通う子を持つ父母163人を対象にし たアンケート調査では、性別役割分担の意識が強い 父親ほど育児参加しないことが分かった。 • フレックスタイム制度の利用状況や職場での職位が 子の育児時間にどのような影響を与えるかを分析し、 管理職に就いていない父親は平日に約93.2分育児に 携わる一方で、管理職に就いている父親は平日に約 男性による育児参加の規定要因には、本人の就業状況、親の共 85.3分育児に携わることを示した 働き状況、子や孫の年齢や数、年収や学歴などが挙げられる。 Brayfield(1995) Craig(2011) • 母親との勤務時間帯が異なる場合に子育てにより • 母親が職に就いている人ほど父親は育児により積 積極的に参加することを明らかにしている。 極的に参加することや、オーストラリアやデン マークの家庭では、高学歴の父親ほど育児に参加 することが示唆されている 28
先行研究 孫への育児参加が祖父母の健康・幸福度に与える影響 Wang et.al.(2019) Powdthavee(2011) 小松ほか(2010) • 生活満足度については孫の世話をして • イギリスに住む祖父母を対象に行った • 孫の育児に参加する祖父母の精神的健 いる人はそうでない人と比べて2.7%高 実証分析では、孫がいることと人生の 康に関する文献的考察では、精神的健 まることや、孫育児をすることでうつ 満足度において正の相関関係があるこ 康に影響を与える要因が複数あること 病を訴える人の割合が2.9%低くなるこ とが分かった。 や、精神的影響については良い面と悪 とが分かった。 い面のそれぞれで影響を与えることが 分かった。 • また、孫の数が1人増えると健康であ る確率は1.3%高まることが分かった。 Jendrek(1993) Bonita and Barbara(1999) Dunifon et.al.(2019) • アメリカオハイオ州に住む114人お祖 父母を対象として、精神的・身体的な 影響についてアンケート調査した研究 では、祖父母は孫と同居していた場合 に、そうでない場合と比べて大きく影 響を受けることが分かった。 • 100人の祖母を対象にした分析では、 正規雇用で育児をする祖母ほど非正規 雇用で育児する祖母よりも育児負担が 大きく、満足度が低いということが分 かった。 • アメリカで孫と同居する3世帯である 祖父母868人を対象に分析を行った結 果、孫と同居する祖父母はそうでない 場合と比べて、孫と一緒に活動するこ とでより高い幸福感を得ることが分 かった。 29
先行研究 孫への育児参加が祖父母の健康・幸福度に与える影響 Wang et.al.(2019) Powdthavee(2011) 小松ほか(2010) • 生活満足度については孫の世話をして • イギリスに住む祖父母を対象に行った • 孫の育児に参加する祖父母の精神的健 いる人はそうでない人と比べて2.7%高 実証分析では、孫がいることと人生の 康に関する文献的考察では、精神的健 まることや、孫育児をすることでうつ 満足度において正の相関関係があるこ 康に影響を与える要因が複数あること 病を訴える人の割合が2.9%低くなるこ とが分かった。 や、精神的影響については良い面と悪 とが分かった。 い面のそれぞれで影響を与えることが 分かった。 海外の研究では、祖父母は孫への育児参加を行うと高い幸福感を る確率は1.3%高まることが分かった。 得ることができ、生活満足度が向上するとまとめる研究が多い • また、孫の数が1人増えると健康であ Jendrek(1993) Bonita and Barbara(1999) Dunifon et.al.(2019) • アメリカオハイオ州に住む114人お祖 父母を対象として、精神的・身体的な 影響についてアンケート調査した研究 では、祖父母は孫と同居していた場合 に、そうでない場合と比べて大きく影 響を受けることが分かった。 • 100人の祖母を対象にした分析では、 正規雇用で育児をする祖母ほど非正規 雇用で育児する祖母よりも育児負担が 大きく、満足度が低いということが分 かった。 • アメリカで孫と同居する3世帯である 祖父母868人を対象に分析を行った結 果、孫と同居する祖父母はそうでない 場合と比べて、孫と一緒に活動するこ とでより高い幸福感を得ることが分 かった。 30
先行研究 先行研究 まとめ 明らかになっていること 明らかになっていること ・祖父母による育児参加は、現役世代の育児負担を軽減させる。 ・男性(現役世代の父親、退職後の祖父)による育児参加の規定要因には、本人の就 業状況、配偶者の雇用形態、子や孫の年齢、年収や学歴などが挙げられる。 ・海外の研究では祖父母は孫育児を行うと高い幸福感を得ることができ、生活満足 度が向上するとまとめる研究が多い。 明らかになっていないこと ・祖父となった後の育児参加の規定要因について、現役時代の働き方に注目した定量的な 分析。 ・日本の祖父母を対象にして、祖父母による孫育児が彼らの健康状態・幸福度に与える影 響。 31
アウトライン 背景・問題意識 先行研究 分析アプローチ 考察・課題点 質疑応答 33
分析アプローチ 推計の流れ 現役時代の働き方が祖父による孫への育児参加に与える影響に関する分析 • 推計1-1)現役時代の働き方と現在の育児への参加意欲の関係性を明らかにする • 推計1-2)育児時間の代替変数として家事時間を用いて、労働と育児の関係性を明らかにする 現役時代・現在の育児・家事参加が現在の健康・幸福度に与える影響に関する分析 • 推計2)育児がもたらす影響を明らかにし、育児の担い手としての高齢者について考える 34
分析アプローチ 推計1 仮説 仮説 現役時代に長時間労働、自営業・自由業等ではない、また正規雇用で働くなどの労働時間 をマネジメントしにくい職に就いていた祖父ほど、またかつて育児参加に消極的だった祖 父ほど、孫の育児時間や育児頻度は少ない 仮説の根拠① 子の育児時間の減少 • 水落(2006)より実証 ジェンダーバイアス • • 「男性は仕事、女性は家庭」 退職後もこの意識は持続する 可能性が高い 長時間労働 子の育児に時間が取れなかっ たため育児のノウハウがなく、 また孫育児の参加意欲が上が らず育児に消極的 仮説の根拠② 仮説の根拠② 育児から得られるやりがいや喜びについて十分に知らない 育児の参加意欲が低いため、 育児に消極的 35
分析アプローチ 推計2 仮説 仮説 積極的な孫への育児参加は健康状態を良くし、幸福度を高めるが、育児時間がある一定以 上を超えると、身体的・精神的疲労が原因で健康状態や幸福度は低下する 積極的な育児により、身体的活動量が増える ため、健康の維持や改善に寄与する 孫や家族との繋がりが深まり幸福度が高まる 育児に費やす時間が過剰に多いと、 身体的な疲労やストレスが増加し、 健康状態が悪化したり幸福度が低下 する可能性があるため 36
分析アプローチ 推計1 推計方法 変量効果モデル・変量効果順序ロジットモデル 𝒀𝒊𝒕 𝒑 𝒑 = 𝜶 + 𝜷𝟏 𝑯𝒊 + 𝜷𝟐 𝑯𝒊 × 𝑫𝒊 + 𝜷𝟑 𝑯𝒊𝒕 + 𝜷𝟒 𝑯𝒊𝒕 × 𝑫𝒊 + 𝜸𝑿𝒊𝒕 + 𝑭𝒊 + 𝒖𝒊𝒕 定数項 被説明変数 男性ダミー 説明変数(現役) 説明変数(現役) 男性ダミー 固有効果 誤差項 コントロール変数 推計1-1 週平均育児時間 週の育児頻度 労働時間・育児時間 およびその男性ダミー との交差項 推計1-2 労働時間・家事時間 およびその男性ダミー との交差項 正規雇用ダミー 就業形態ダミー 従業員規模ダミー およびその男性ダミー との交差項 年齢、大卒ダミー、世帯収入、 子の共働きダミー、男性ダミー、 業種、職種、年ダミー 37
分析アプローチ 推計1 推計方法 変量効果モデル・変量効果順序ロジットモデル 【現役時代の定義】 推計1-1(育児時間)… 祖父母の子の末子年齢が15歳未満である時期 𝒑 𝒑 𝒀𝒊𝒕 =推計1-2(家事時間)… 𝜶 + 𝜷𝟏 𝑯 𝒊 + 𝜷𝟐 𝑯𝒊 × 𝑫 祖父母の年齢が55歳以下 𝒊 + 𝜷𝟑 𝑯𝒊𝒕 + 𝜷𝟒 𝑯𝒊𝒕 × 𝑫𝒊 + 𝜸𝑿𝒊𝒕 + 𝑭𝒊 + 𝒖𝒊𝒕 定数項 被説明変数 男性ダミー 説明変数(現役) 説明変数(現役) 男性ダミー 固有効果 誤差項 コントロール変数 推計1-1 週平均育児時間 標本数の不足 週の育児頻度 を補うために 育児時間の代 替変数として 家事時間を用 いる 労働時間・育児時間 およびその男性ダミー との交差項 推計1-2 労働時間・家事時間 およびその男性ダミー との交差項 正規雇用ダミー 就業形態ダミー 従業員規模ダミー およびその男性ダミー との交差項 年齢、大卒ダミー、世帯収入、 子の共働きダミー、男性ダミー、 業種、職種、年ダミー 38
分析アプローチ 推計2 推計方法 変量効果順序ロジットモデル・2段階最小二乗法 変量効果順序ロジットモデル 𝒑 𝒀𝒊𝒕 = 𝜶 + 𝜷𝑯𝒊 + 𝜸𝑿𝒊𝒕 + 𝑭𝒊 + 𝒖𝒊𝒕 𝒀𝒊𝒕 = 𝒂 + 𝜷𝑯𝒊𝒕 + 𝜸𝑿𝒊𝒕 + 𝑭𝒊𝒕 + 𝒖𝒊𝒕 定数項 被説明変数 説明変数(現役・現在) 健康状態 幸福度 現役・現在 育児時間・育児頻度 家事時間・家事頻度 固有効果 誤差項 コントロール変数 孫の数、孫と同居ダミー、喫煙 ダミー、飲酒ダミー、通院無し ダミー、年齢、年齢の二乗、世 帯収入、年ダミー 祖父母それぞれでサンプルを分けて推計を回し、性別による影響の違いを確認する 39
分析アプローチ 推計2 推計方法 操作変数 逆の因果性 健康・幸福度 育児・家事 操作変数の条件 ①説明変数に影響を与える(祖父母の育児・家事に影響を与える) ②被説明変数との直接的な相関がない(祖父母の健康・幸福度には影響なし) 逆の因果性に対処するために、それぞれの説明変数に対 して下記の操作変数を用いて対処する。 【説明変数】 現在の育児時間 現在の育児頻度 現在の家事時間 現在の家事頻度 --------- 【操作変数】 配偶者の現在の育児時間 配偶者の現在の育児時間 配偶者の現在の家事時間 配偶者の現在の家事頻度 全ての操作変数において F値は十分に10を超えたため、 弱操作変数ではない ➤2段階最小二乗法を適用する 40
分析アプローチ 使用データ 日本家計パネル調査(JHPS/KHPS) 調査元:慶應義塾大学パネルデータ設計・解析センター 対象時期 調査対象 推計1 推計2 2018年~2022年 2018年~2022年 現役時代(子が15歳未満/55歳以下)のデータ が得られる、15歳未満の孫を持つ60歳以上の男 女(=祖父母) 15歳未満の孫を持つ 60歳以上の男女(=祖父母) 41
分析アプローチ 使用データ 日本家計パネル調査(JHPS/KHPS) 調査元:慶應義塾大学パネルデータ設計・解析センター 対象時期 2018年~2022年 調査対象 現役時代(子が15歳未満/55歳以下)のデータ が得られる、15歳未満の孫を持つ60歳以上の男 女(=祖父母) 42
分析アプローチ 変数説明 現役時代のデータ抽出方法 現役時代 祖父母 説明変数 被説明変数 推計1-1:子どもの末子年齢が0∼15歳未満の時期 推計1-2:年齢が55歳以下の時期 60歳以上かつ 孫の末子年齢が0∼15歳未満 現役時代全ての年の値の和 = ÷ 現役時代の年数 現役時代1年あたりの平均値 43
分析アプローチ 利用データ・変数 正規雇用ダミー 自営業・自由業ダミー 1,2,3であれば1 それ以外であれば0 を取るダミー変数 1,2,3,6であれば1 それ以外であれば0 を取るダミー変数 子の共働きダミー 子どもと子どもの配偶者 の就業形態が共に 4,5であれば1 それ以外であれば 0を取るダミー変数 労働時間に対する柔軟性が低く、 時間的制約の大きい就業形態 ➤育児や家事に費やせる時間の 確保に一定の困難が伴う 44
分析アプローチ 基本統計量(推計1) わかること • 現役時代の育児時間が平均0.718時間に比べて、 退職後の現在の育児時間は平均1.018時間で、増 加傾向にあるが大差はない • 家事時間は現役時代と現在で変化は小さい 45
分析アプローチ 基本統計量(推計2) わかること • 現在の育児時間は平均0.622時間に対して現役時代は3.982時間 • 退職後に孫の育児に参加したときの時間が大幅に減少することを 示す 46
分析アプローチ 推計1-1 予備的分析 2 2 1.8 1.8 1.6 1.6 1.4 1.4 1.2 1.2 育児頻度 育児時間 現役時代:祖父の子の末子年齢が15歳未満である時期 1 0.8 1 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0 0 祖父 祖母 祖母と比べて祖父の孫の育児時間は短い 従業員規模が1∼99人の企業にかつて勤めてい た祖父、および労働時間がかつて短かった祖父 ほど孫の育児時間は長い 祖父 祖母 祖母と比べて祖父の孫の育児頻度は少ない 従業員規模が1∼99人の企業にかつて勤めてい た祖父、および労働時間がかつて短かった祖父 ほど孫の育児頻度は多い 47
分析アプローチ 推計1-2 予備的分析 現役時代:祖父母の年齢が55歳以下である時期 1.5 1.2 1.45 1.4 0.8 育児頻度 育児時間 1 0.6 0.4 1.35 1.3 1.25 1.2 0.2 1.15 0 1.1 祖父 祖母 祖父 祖父母とも家事時間がかつて短かった人ほど、 孫の育児時間は長い 祖母 家事時間がかつて短かった人ほど、 孫の育児頻度は多い 48
分析アプローチ 推計1 推計結果(全体) 49
分析アプローチ 推計1 推計結果(被説明変数:育児時間) 【労働時間】 (1)列 労働時間単体の係数:正に有意 男性ダミーとの交差項の係数:負に有意 男性の現役時代の労働時間の係数=0.003(=0.0667-0.0637) ※有意水準1%未満で正に有意になりゼロと異なった (3)列 労働時間単体の係数:正に有意 男性ダミーとの交差項の係数:負に有意 男性の現役時代の労働時間の係数= 0.0025(=0.0675-0.0650) ※有意水準1%未満で正に有意になりゼロと異なった 現役時代の労働時間が長い人ほど孫の育児時間は→ 女性 (1)列では0.0667時間、 (3)列では0.0675時間長くなる 男性 (1)列では0.003時間、 (3)列では0.0025時間長くなる ➤男性は女性と比べてその増え方は小さい 50
分析アプローチ 推計1 推計結果(被説明変数:育児時間) 他の説明変数はいずれも、統計的に有意ではない 育児時間に直接的な影響を与えているとは言えない 51
分析アプローチ 推計1 推計結果(被説明変数:育児頻度) 【労働時間】 (6)列 労働時間単体の係数:正に有意 男性ダミーとの交差項の係数:負に有意 男性の現役時代の労働時間の係数=-0.0253(=0.0777-0.103) ※有意水準1%未満で正に有意になりゼロと異なった (8)列 労働時間単体の係数:正に有意 男性ダミーとの交差項の係数:負に有意 男性の現役時代の労働時間の係数= -0.0303(=0.0717-0.102) ※有意水準1%未満で正に有意になりゼロと異なった 現役時代の労働時間が長い人ほど孫の育児頻度は→ 女性 (6)列では0.0777だけ、 (8)列では0.0717だけ増える 男性 (6)列では0.0253、 (8)列では0.0303だけ減る ➤女性では増えるが、男性では減る 52
分析アプローチ 推計1 推計結果(被説明変数:育児頻度) 【育児時間】 (7)列 育児時間単体の係数:正に有意 男性ダミーとの交差項の係数:負に有意 男性の現役時代の育児時間の係数=0.104(=0.365-0.261) ※有意水準1%未満で正に有意になりゼロと異なった (8)列 育児時間単体の係数:正に有意で係数は0.318 労働時間と一緒に説明変数を入れた場合は、性別による違いは見られなかった 現役時代の育児時間が長い人ほど孫の育児頻度は→ 女性 (7)列では0.365だけ (8)列では0.318だけ増える 男性 (7)列では0.104だけ増える ➤男性は女性と比べてその増え方が小さい 53
分析アプローチ 推計1 推計結果(被説明変数:育児頻度) 【家事時間】 (10)列 家事時間単体の係数:正に有意で0.0521 現役時代に家事時間が長かった人ほど、退職後にも家事に参加する頻度は 0.0521増えるが、性別による違いはない 【従業員規模】 (7)列、(9)列 従業員100∼499人単体の係数:有意でない 男性ダミーとの交差項の係数:負に有意 男性で現役時代に中規模企業であった人の係数=-2.505 <(7)列>、=-2.605 <(9)列> 男性は、かつて中規模企業に勤めていた人ほど、育児を行う頻度は減る 54
分析アプローチ 推計1 推計結果まとめ 労働時間や育児・家事時間がかつて長かった人ほど、 孫ができた際には積極的に育児や家事に参加する傾向にあるものの、 男性においては労働時間が長かった人ほど、そして中規模の企業に勤 めていた人ほど、孫の育児にあまり参加しない 55
分析アプローチ 推計2 予備的分析(育児・家事時間と健康) 3.24 3.22 3.2 健康 3.18 3.16 3.14 3.12 3.1 3.08 3.06 祖父 祖母 祖父は祖母と比べて現役時代の育児時間が増 えると健康状態は良い 現在は、孫の育児時間が短い祖父母の方が健 康状態は良くなる 現在・現役ともに、家事時間が少ない祖父母ほ ど健康状態は良い 56
分析アプローチ 予備的分析(育児・家事頻度と健康) 3.25 3.2 健康 推計2 3.15 3.1 3.05 3 2.95 祖父 現在の孫の育児頻度が少ない祖父母の方が健 康状態は良くなる 祖母 現在・現役ともに、家事頻度が少ない祖父母ほ ど健康状態は良い 祖母においては、現役時代に家事をよりしてい た人ほど、わずかに健康状態は良くなる 57
分析アプローチ 推計2 予備的分析(育児・家事時間と幸福度) 6.8 6.7 6.6 幸福度 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6 5.9 5.8 祖父 現在・現役ともに、祖父は育児時間が短い人ほど 幸福度が高い。現在の方が現役よりも幸福度の差 が顕著である 祖母は、育児時間が短い人ほど幸福度が低い 祖母 現在・現役ともに、祖父は家事時間が短い人ほど 幸福度が高い。現在の方が現役よりも幸福度の差 が顕著である 祖母は、家事時間が短い人ほど幸福度が低い 58
分析アプローチ 推計2 予備的分析(育児・家事頻度と幸福度) 現在・現役ともに、祖父は育児時間が短い 人ほど幸福度が低い 現在に関してはその差が顕著である 現在・現役ともに、祖父は家事時間が短 い人ほど幸福度が低い 現在に関してはその差が顕著である 59
分析アプローチ 推計2 祖父 推計結果(健康状態全体) 祖母 60
分析アプローチ 推計2 推計結果(健康状態) 祖父 現役時代の家事頻度の係数は0.443で正に有意 現役時代により多く家事をしていた男性ほど、祖父に なった際の健康状態が高くなる 祖母 現在の家事時間の係数は0.00847、 現在の家事頻度の係数は0.0604で正に有意 現在家事に積極的に参加するほど健康状態が 高くなる 61
分析アプローチ 推計2 祖父 推計結果(幸福度全体) 祖母 62
分析アプローチ 推計2 推計結果(幸福度) 祖父 現役時代の家事頻度の係数は0.261で正に有意 現役時代により家事を行っていた人ほど、祖父に なった際の幸福度は高まる 祖母 現役時代と現在ともに育児参加と家事時間は 有意でないため、幸福度に影響を与えない 現在の家事頻度の係数は-0.169で負に有意 現在の家事頻度が多くなると、より大きなストレス がかかり幸福度が低下する 63
分析アプローチ 推計2 推計結果(孫の数と幸福度) 祖父 祖母 孫の数が増えると、祖父は幸福度が低下する一方で、祖母は幸福度が上昇する 性別役割分業意識が存在する場合の祖父母の心理的状況の違いを反映している可能性 祖父 祖母 現役時代に仕事中心の生活を送る傾向が強かったため、育児などに慣 れておらず接し方がわからない状況に陥り、心理的負担も感じた結果、 幸福度が低下 これまでの経験から育児を積極的に担ってきた為、 孫が増える事により家族との繋がりや自身の役割の充実感を得ることで、 幸福度が向上 64
分析アプローチ 推計2 祖父 推計結果まとめ 祖母 【祖父】 現役時代により家事をしていた男性ほど、退職後の健康状態や幸福度に良い影響を もたらす 子や孫への育児参加は祖父の健康や幸福度に影響を与えず、育児参加にやりがいを 見出せていないことが示唆される 【祖母】 現役時代の育児・家事参加が健康や幸福度に影響を与えないが、現在の家事参加は 健康や幸福度に異なる影響をもたらす ➤身体的に活発な生活を促進する一方で、精神的ストレスを増大させている可能性 65
アウトライン 背景・問題意識 先行研究 分析アプローチ 考察・課題点 質疑応答 66
考察・課題点 考察(推計1) 推計1 現役時代の働き方が、祖父による孫への育児・家事参加に与える影響 祖父 • 女性ほど顕著ではないものの現役時代の育児時間と孫の育児頻度には正の相関が見られ、労 働条件や企業規模の影響も受けやすい • かつて労働時間が長かった人の育児頻度は減るが育児時間は伸びる結果について、本来育児 参加の意欲はあったが仕事を理由にできていなかった男性が、退職後には孫育児の頻度は増 えなくても1日あたりに育児に費やす時間は伸ばしていると推察できる 祖母 • 現役時代の子の育児時間と孫の育児参加に正の相関 育児時間や労働環境の違いが男女間で異なる影響を与える理由 ジェンダーに基づく役割分担が世代を超えて継承されていることを示唆しており、 今後の家庭内での在り方や育児・家事への参加に関してさらなる分析が求められる 68
考察・課題点 考察(推計2) 推計2 育児・家事の参加が健康や幸福度に与える影響 祖父 • 健康や幸福度の向上には、現役時代の家事参加の蓄積が退職後の生活の質に持続的な影響を与える可能性 がある • ただし、現在の育児や家事の参加度合いの説明変数では有意ではなかったため、祖父の健康状態や幸福度 は、育児や家事の参加ではなく、他の余暇時間から影響を受けている可能性があると推察する 祖母 • 現在の家事負担が身体的な活動を促進して健康状態を良くするが、負担を感じることで幸福度は低下する 育児と家事で異なる理由の考察 • 育児:子どもが一定の年齢に達するまでの比較的短期間に集中して行われるため、現役時代を通じて一貫し て蓄積される経験とは言い難い ➤限定的かつ短期的な影響 • 家事:日常生活で必要不可欠で、継続的かつ一貫した労力を伴う活動 ➤長期的な影響 70
考察・課題点 課題点 • 現役時代の働き方で、業種や職種による違いを明らかにできず、コントロール変数 で処理した • 中規模企業に勤めていた男性の育児頻度が減る理由として、育児支援制度が整って いるか否かで企業をより細かく分析できておらず、また業種や職種の違いも考慮で きていないため、明確な考察ができていない • 企業規模別に注目した場合、従業員100∼499人の中規模企業の男性においてのみ被 説明変数が育児頻度で有意であったが、中規模企業故の柔軟な働き方や、業種・職 種を交差項に入れるなどして、明確な理由を明らかにできていない点 71
参考文献 【論文】 Asai Yukiko, Ryo Kambayashi and Shintaro Yamaguchi (2015) “ Childcare availability, household structure, and maternal employment” Journal of the Japanese and International Economies Volume 38 pp.172-192 Bonita F, Bowers and Myers Barbara J.(1999)”Grandmothers Providing Care for Grandchildren: Consequences of Various Levels of Caregiving,” Family Relations, Vol. 48, No. 3, 48, pp.303-311 Brayfield, April (1995) “Juggling Jobs and Kids: The Impact of Employment Schedules on Fathers' Caring for Children” Journal of Marriage and Family Vol. 57, No. 2 pp. 321- 332 Bygren, Magnus and Ann-Zofie Duvander (2006) “Parents’ Workplace Situation and Fathers ’ParentalLeave Use,” Journal of Marriage and Family 68 (May 2006): pp.363-372 Craiga, Lyn and Killian Mullan (2011) “How Mothers and Fathers Share Childcare: A CrossNational Time-Use Comparison” American Sociological Review 76(6) pp.834–861 Dunifon, Rachel E., Kelly A. Musick, and Christopher E. Near (2019) “Time with Grandchildren: Subjective Well-Being Among Grandparents Living with Their Grandchildren,” Social Indicators Research, 148, pp.681–702. Gasser, Martin(2017)“Time Spent on Child Care by Fathers in Leadership Positions: The Role of Work Hours and Flextime”Journal of Family Issues 2017, Vol. 38(8) pp.1066 –1088 Hachiro Nishioka(1998)「『第一回全国家庭動向調査』データ利用による実証的研究 Men's Domestic Role and the Gender System: Determinants of Husband's Household Labor in Japan」、『人口問題研究』54(3):56-71頁 Hughes, Mary Elizabeth, Linda J. Waite, Tracey A. LaPierre and Ye Luo (2007) “All in the Family: The Impact of Caring for Grandchildren on Grandparents' Health,” The Journals of Gerontology: Series B, Volume 62, Issue 2, pp. S108–S119 Jendrek, Margaret Platt(1993)”Grandparents Who Parent Their Grandchildren: Effects on Lifestyle,” Journal of Marriage and Family , Aug., 1993, Vol. 55, No. 3 (Aug 1993), pp. 609-621 Morita Masahito, Atsuko Saito, Mari Nozaki and Yasuo Ihara (2021) “Childcare support and child social development in Japan: investigating the mediating role of parental psychological condition and parenting style” Powdthavee, Nattavudh (2011) “Life Satisfaction and Grandparenthood: Evidence from a Nationwide Survey,” Discussion Paper No. 5869 Wang, Hao, Jan Fidrmuc, and Qi Luo (2019) “A happy way to grow old? Grandparent caregiving, quality of life satisfaction,” CESifo 72 Working Paper, No. 7670, Category 3: Social Protection
参考文献 青木聡子・岩立京子(2004)「幼児を持つ父親の育児参加を促す要因:父母比較による検討」『東京学芸大学リポジトリ』 北村安樹子(2015)「祖父母による孫育て支援の実態と意識 ― 祖父母にとっての孫育ての意味 ―」 小松紗代子・斎藤民・甲斐一郎(2010)「孫の育児に参加する祖父母の精神的健康に関する文献的考察」 水落正明(2006)「父親の育児参加と家計の時間配分」『季刊家計経済研究 2006 SUMMER』 No.71 多喜代健吾・北宮千秋(2019)「父親の育児参加への育児参加要因およびソーシャルサポートの影響」『日本看護研究学会雑 誌』Vol.42 No.4 平井太規(2021)「祖父母による家事・育児動向の基礎的分析ー3世代世帯家族を対象にー」『2021(令和3)年度研究集会 「官民オープンデータ利活用の動向及び人材育成の取組」』 松田茂樹(2000)「夫の家事・育児参加の規定要因」 宮中文子(2001)「中高年女性(祖母)の子育て参加と心理的健康との関連についてー心の健康にプラスとなる孫との関わり 方一」『日本女性心身医学会雑誌 Journal of JSPOG』 Vol.6,No.2,pp.173−180 本保恭子・八重樫牧子(2003)「母親の子育て不安と父親の家事・子育て参加との関連性に関する研究」『川崎医療福祉学会』 八重樫牧子・江草安彦・李永喜・小河孝則・渡邊貴子(2003)「祖父母の子育て参加が母親の子育てに与える影響」『川崎医 療福祉学会誌』 Vol.13 No.2 pp.233-245 余田翔平・新谷由里子(2018)「母親の就業と祖父母からの育児支援 ―「固体内の変動」と個体間の差異」の検討―」『人口 問題研究(J. of Population Problems)』 74−1 pp.61-73 脇坂明(2008)「育児休業は本人にとって能力開発の妨げになるか」『学習院大学 経済論集』第44巻 第4号 73
参考文献 <ウェブサイト> 総務省統計局、「我が国における家事関連時間の男女の差~生活時間からみたジェンダーギャップ~」、総称統計巨億統計調査部労 働力人口統計室長 奥野重徳 結果の概要、(最終閲覧日 2024年12月27日) https://www.stat.go.jp/info/today/pdf/190.pdf 総務省統計局、「令和3年社会生活基本調査 詳細行動分類による生活時間に関する結果」、(最終閲覧日 2024年7月2日) https://www.stat.go.jp/data/shakai/2021/pdf/gaiyoub.pdf 内閣府男女共同参画局、「第1節働く女性の活躍の現状と課題」、(最終閲覧日2024年7月2日) https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h29/zentai/html/honpen/b1_s00_01.html 内閣府男女共同参画局、「共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移(妻が64歳以下の世帯)」、(最終閲覧日 2024年6月7日) https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r05/zentai/html/zuhyo/zuhyo00-op02.html 厚生労働省、「育児・介護休業法の改正について~男性の育児休業取得促進等~」、(最終閲覧日 2024年12月28日) https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/content/contents/001071728.pdf 日本労働組合総連合会、「男性の家事・育児参加に関する実態調査2019」、(最終閲覧日 2025年1月13日) https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20191008.pdf 74
ご清聴ありがとうございました 色々教えてくださった方々、山本先生、 ありがとうございました 76