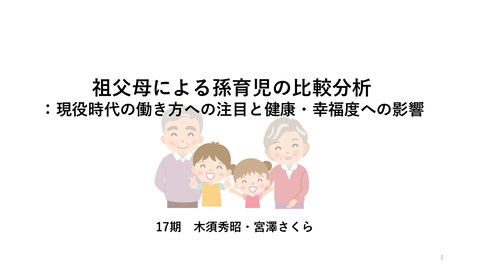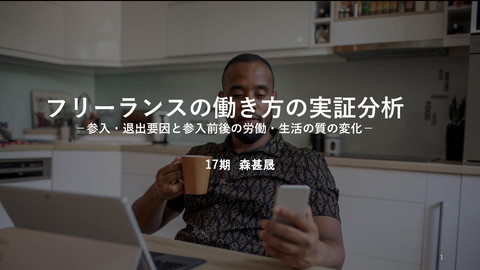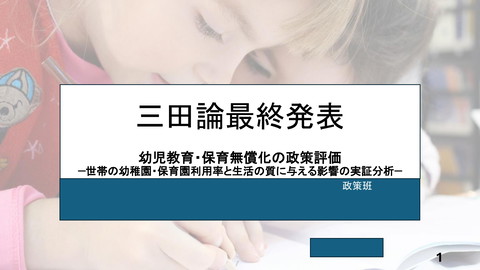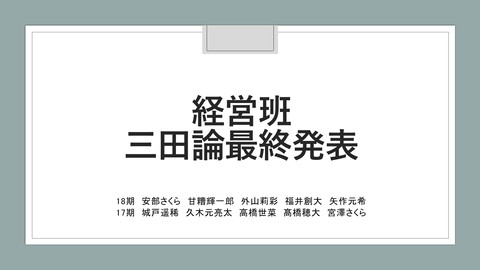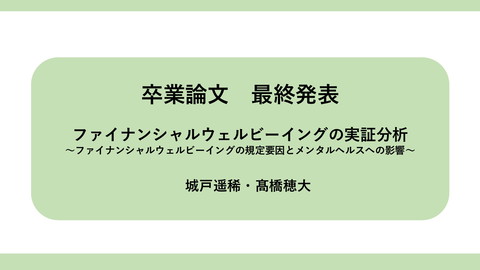2024卒業論文_久木元亮太・松永直之
1K Views
February 19, 25
スライド概要
サプリメント摂取の規定要因や市場拡大要因、さらにウェルビーイングに与える影響についての実証分析を行います。近年市場拡大が続くサプリメントについて、パネルデータを用いて分析を行い、健康志向の高まりによる市場の変化を考察します。また、がん治療や妊娠機能改善などの事例を挙げつつ、サプリメントの利用実態を探り、プラシーボ効果やピア効果を仮説として検討します。成果としては、サプリメントとの関わり方や市場拡大の一助となる知見を提供します。
慶應義塾大学商学部商学科山本勲研究会 ホームページ: https://www.yamazemi.info Instagram: https://www.instagram.com/yamazemi2024
関連スライド
各ページのテキスト
卒業論文最終発表 山本勲研究会17期 久木元亮太・松永直之 1/15(水) 1
アウトライン 1 研究概要 4 分析アプローチ 2 はじめに 5 推計 3 先行研究 6 まとめ 4 1 5 6 2 2 3
アウトライン 1 研究概要 4 分析アプローチ 2 はじめに 5 推計 3 先行研究 6 まとめ 4 1 5 6 3 2 3
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ サプリメント摂取の規定要因・市場拡大要因と ウェルビーイングに与える影響に関する実証分析 近年市場拡大を続けているサプリメントであるが、これまで単年のアン ケート調査が多いことを踏まえ、パネルデータを用いてサプリメント摂取 の規定要因や市場拡大要因、ウェルビーイングに与える影響に ついて明らかにする。その上で、サプリメントとの関わり方や市場拡大の 一助とすることを目的とする。 4
アウトライン 1 研究概要 4 分析アプローチ 2 はじめに 5 推計 3 先行研究 6 まとめ 4 1 5 6 5 2 3
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 6,まとめ 5、推計 サプリメント市場の現状 現状 健康志向の高まりを背景に、特定の成分を濃縮した健康商品の市場が拡大しつつある。 その中でもサプリメント市場が拡大を続けている。 9000億円を 市場規模が 達成する見込み 出典:株式会社矢野経済研究所(2024) 6
2、はじめに 1、研究概要 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ サプリメント市場の現状 ーがん治療ー 1 〇大浜(2010) 【概要】 がん患者の44.6%がなんらかの補完代替医療を利用しており、 そのうちの96.2%が健康食品・サプリメントを使用しているこ とが分かった。さらに、使用目的もがん進行抑制や治療が多く、 症状緩和や通常医療を補完するといった役割を期待しての利用 は少なかった。 ー妊娠機能の改善ー 2 〇山口ほか(2022) 【概要】 これまでの基礎研究より、加齢に伴い卵巣機能が低下する過程 で活性酵素による酸化ストレスが蓄積し、卵子の質が低下する 可能性が示唆された。そのため高齢不妊に対する不妊治療では、 卵子の質の改善を期待して、抗酸化剤やホルモンを中心とした サプリメントの服用が期待されている。 利用用途は、医療から日常的な健康維持まで多岐に渡る。 7
はじめに 研究概要 先行研究 分析アプローチ 推計 まとめ サプリメント市場の現状 ーがん治療ー 1 ー妊娠機能の改善ー 〇大浜(2010) 2 〇山口ら(2022) 多様な利用実態から、サプリメントの分析は、 現代社会の健康志向を理解するうえで重要な意義を持つ。 【概要】 がん患者の44.6%がなんらかの補完代替医療を利用しており、 そのうちの96.2%が健康食品・サプリメントを使用しているこ とが分かった。さらに、使用目的もがん進行抑制や治療が多く、 症状緩和や通常医療を補完するといった役割を期待しての利用 は少なかった。 【概要】 これまでの基礎研究より、加齢に伴い卵巣機能が低下する過程 で活性酵素による酸化ストレスが蓄積し、卵子の質が低下する 可能性が示唆された。そのため高齢不妊に対する不妊治療では、 卵子の質の改善を期待して、抗酸化剤やホルモンを中心とした サプリメントの服用が期待されている。 利用用途は、医療から日常的な健康維持まで多岐に渡る。 8
2、はじめに 1、研究概要 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ サプリメントの研究について 研究 サプリメント摂取に関する研究は、少ないが行われてきている。マイボイスコム株式会社(2020) 26.5 サプリメント使用の効果を実感している人 7.6% ある程度実感している人 38.5% どちらともいえない 約45% 34.5% 以前は利用していたが、現在は利用していない と回答した人 26.5% あまり・実感していない 19.4% 過半数が効果を実感することができていない。 9
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ サプリメントの研究について サプリメントに不満を持っている人の理由 =期待したほどの効果がなかったと答えた人 (複数回答可) 80% 内閣府『消費者の「健康食品」の利用に関する実態調査』(2012) 10
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 紅麹の事件について 2024年7月28日時点で紅麹関連含む死者数 300人 多くの国民が関心を寄せる機会となった 厚生労働省 健康被害情報(2024) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/ shokuhin/daietto/index.html 11
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、予備的分析 5、推計 6,懸念点 紅麹の事件について 2024年7月28日時点で紅麹関連含む死者数 サプリメント摂取の調査などによると、正の効果だけではなく、 300人 負の効果も生じる可能性があることがわかる。 多くの国民が関心を寄せる機会となった 厚生労働省 健康被害情報(2024) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/ shokuhin/daietto/index.html 12
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 5、推計 4、分析アプローチ 6,まとめ サプリとウェルビーイグの関係ついて 研究 1 ウェルビーイングといった心的要因との関係性を示したものはほどんどない。 〇藤本(2001) 【概要】 プラシーボ効果とは、効果の示した薬を服用す ることにより本来は症状の改善がみられないはず だが、病状が回復するような効果のことを指す。 本稿の仮説 プラシーボ効果により、サプリメントを摂取すると いう行為そのものが心的要因に影響を与えているの ではないか? 「サプリメントを摂取している」という感覚(思い込み)が、 ウェルビーイングに影響を与えているのではないか。 ウェルビーイングに与える影響については分析の余地がある。 13
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 規定要因と時間割引率について 研究 規定要因に関する考え方として、行動経済学特性や性格特性がある。 ー行動経済学特性ー ー性格特性ー 1 2 〇山本ら(2022) 【概要】 時間割引率とは経済学の中で扱われる性格指標の一つであり、 「待つことをどれだけ嫌がるか」という人間の性質に着目した 指標とされている。サプリメント摂取の効果は即効性があるも のではないため、時間割引率が低い人が摂取に意欲的であると 考えられる。 〇佐藤ら(2018) 【概要】 女子大学生を対象に属性やサプリメントの利用状況、主要 5因子性格検査(big five)によるパーソナリティ特性を質 問項目として調査した結果、サプリメント利用者は非利用 者よりも外向性得点が高かった。 規定要因については行動経済学特性や性格特性が関係しているが、実証的に 分析したものはない。 14
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 市場拡大要因について 仮説 健康意識の高まりや健康寿命延命のほかに、ピア効果の影響がある 一般的に、周りの人々の行動を参考にして 自身の行動を決定する傾向のことを指す。 本稿の仮説 1 自身の周りの人がサプリメント摂取をしていると、自身の摂取に影響を与える という関連性が想定される。 〇杉山ほか(2007) 2 〇Bruce(2011) 【概要】 【概要】 スポーツサプリメントは友人やコーチの勧めで、 一般サプリメントは家族の勧めで利用される ケースが多いことを示した。 学業成績において、人種や能力レベルといった 身近な属性からのピア効果が顕著であることを 示唆している。 本稿では、特に配偶者の行動に着目する。 15
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 本研究で行うこと 『日本家計パネル調査(JHPS/KHPS)』を用いて、規定要因と二つの仮説について検証を行う。 1 2 3 時間割引率や性格特性を考慮したうえで、サプリメント摂取の規定要因について分析する。 配偶者のサプリメント摂取行動はピア効果を通じて自身の摂取行動に影響を与えるというピア効果仮説を検証。 サプリメント摂取はプラシーボ効果を通じてウェルビーイングに影響を与えるという仮説を検証。 16
2、はじめに 1、研究概要 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 独自性 1 2 3 パネルデータを用いることで、時間の変化に伴う効果を分析する点。 時間割引率・性格特性とサプリメント摂取との関係性について分析する点。 サプリメント摂取の頻度を考慮した分析を行なう点。 17
アウトライン 1 研究概要 4 分析アプローチ 2 はじめに 5 推計 3 先行研究 6 まとめ 4 1 5 6 18 2 3
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 先行研究の分類 1 2 3 サプリメント摂取の規定要因 サプリメント摂取のピア効果検証 サプリメント摂取とウェルビーイングとの関係性について 19
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 1、規定要因に関する先行研究 1 〇BENDER(1992) 2 〇櫻井・海野(2023) 【概要】 異なる二つの調査結果について分析し、サプリメントの 使用は、1つ以上の健康問題を抱えている人、および自 身の健康状態を非常に良い、あるいは優れいていると認 識している人ほど、より多く、より強く見られることを 明らかにした。 【概要】 サプリメント利用者は常に効果を実感しているわけで はないが、摂取を止めるタイミングが分からず、その ため多くの種類の薬を長期間服用することになった。 その結果、副作用や精神的依存の傾向が見られるよう になった。 3 1 4 ○吉田ほか(2018) 【概要】 がん患者におけるサプリメント摂取状況について 調査した結果、再発がん患者ほど健康食品やサプ リメントの利用頻度が高く、手術を受けるがん患 者ほど利用頻度が低いことが分かった。 〇佐藤ほか(2018) 【概要】 女子大学生を対象に属性やサプリメントの利用状 況、主要5因子性格検査(big five)によるパーソ ナリティ特性を質問項目として調査した結果、サ プリメント利用者は非利用者よりも外向性得点が 高かった。 20
1、研究概要 3、先行研究 2、はじめに 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 1、規定要因に関する先行研究 5 6 〇嘉山ら(2006) 【概要】 男子アスリートと男子学生では、サプリメン トの使用と食行動・意識との間に異なる関係 があることが示唆された。 7 1 ○佐藤ほか(2016) 【概要】 成人16,275人を対象に調査を行なった結果、カ ルシウムサプリメント使用者は身体活動的で非喫 煙者である傾向が強いこと、鉄サプリメント使用 者は非喫煙者である傾向が強いことを示した。 〇壬生ほか(2012) 【概要】 全体をサプリメント使用群と非使用群に分け、女 性、40歳以上、BMIが高いか低い、血圧・空腹 時血糖値・LDL-Cのすべてが正常値である者に おいてサプリメント使用率が高いことを示した。 21
1、研究概要 3、先行研究 2、はじめに 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 2、ピア効果に関する先行研究 1 2 〇嘉山ら(2006) 【概要】 非体育会系学部に在籍する男子大学生を対象と して調査した結果、スポーツサプリメントは友 人やコーチの勧めで、一般サプリメントは家族 の勧めで利用されていることを示した。 3 ○田内ほか(2003) 【概要】 健診受診者を対象に問診票による調査を行なった 結果、サプリメント摂取の動機は「疲労回復」や 「人に勧められて」の順に高かったことを明らか にした。 〇佐藤ほか(2016) 【概要】 子どもに焦点を当てて分析を行ない、サプリメン トを使用している子どもは使用していない子ども と比較して、母親がサプリメントを使用する傾向 にあることを明らかにした。 22
1、研究概要 3、先行研究 2、はじめに 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 3、ウェルビーイングに与える影響に関する先行研究 1 2 〇両角・井伊(2003) 【概要】 栄養摂取活動と主観的健康観の関係に着目しBivariate Probit Modelを用いて推計を行った結果、健康的な食 事習慣と主観的健康観の間には正の相関があり、サプ リメント・ドリンク剤需要と主観的健康観の間には負 の相関があることがわかった。 3 〇小池ら(2013) 【概要】 57,000件以上の医薬品副作用症例報告が登録されてい るCARPISデータベースから健康食品・サプリメント関 連の副作用症例を抽出し、単変量ロジスティック回帰分 析を行った結果、女性は対象者の66%を占め、サプリ メントとの関連は有意であった。 湯田(2010) 【概要】 2000-2006年のJGSSの個票データを用いて推定し た結果、男性においては健康状態の悪化に伴って賃 金率が有意に減少することが確認された。一方で、 女性においては健康状態と賃金率の間に有意な関係 性は見られなかった。 23
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 明らかになっていること 1 サプリメント・ドリンク剤と主観的健康観には負の関係性が見られる 2 食生活、睡眠時間、運動習慣など様々な生活習慣と健康状態との関係性が あることが示されている。 3 4 良い生活習慣は、主観的幸福感などウェルビーイングにも影響を与えている。 性格特性に関しては、外向性の関連性が強い。 24
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 明らかになっていないこと 1 2 3 4 食生活の中でもサプリメントに焦点を当てたものは少ない。 ウェルビーイングとサプリメントに関して研究は進んでいない。 パネルデータを用いてサプリメントの 規定要因に関して研究したものはない。 サプリメント摂取について行動経済学特性や性格特性を分析をしたものはない。 25
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 独自性(再掲) 1 2 3 パネルデータを用いることで、時間の変化に伴う効果を分析する点。 時間割引率・性格特性とサプリメント摂取との関係性について分析する点。 サプリメント摂取の頻度を考慮した分析を行なう点。 26
アウトライン 1 研究概要 4 分析アプローチ 2 はじめに 5 推計 3 先行研究 6 まとめ 4 1 5 6 27 2 3
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 推計案 1 2 3 サプリメント摂取の規定要因 サプリメント摂取のピア効果検証 サプリメント摂取とウェルビーイングとの関係性について 28
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 5、推計 4、分析アプローチ 6,まとめ 推計案 1 サプリメント摂取の規定要因について 使用モデル;変量効果順序ロジットモデル 𝑺𝒊𝒕 = 𝜶 + 𝜷𝟏 𝑴𝒊 + 𝜷𝟐 𝑵𝒊 + 𝜷𝟑 𝑲𝒊𝒕 + 𝜷𝟒 𝑿𝒊𝒕 + 𝑭𝒊 + 𝜺𝒊𝒕 分類 変数 被説明変数 サプリ摂取頻度 説明変数 時間割引率 性格特性 食事・生活習慣変数 コントロール変数 個人属性 収入 29
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 推計案 2 サプリメント摂取拡大とピア効果の関係 使用モデル;固定効果操作変数法 𝒀𝒊𝒕 = 𝜶 + 𝛄𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝑿𝒊𝒕 + 𝑭𝒊 + 𝜺𝒊𝒕 分類 変数 被説明変数 個人iのサプリ摂取頻度 説明変数 配偶者のサプリ摂取頻度 個人属性(年齢、婚姻、性別) 操作変数;配偶者の外食頻度 配偶者のサプリメント摂取とは相 関する一方で、本人のサプリメン ト摂取には影響を与えないため。 コントロール 変数 仕事形態(勤務時間、雇用形態) 収入 30 c
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 6,まとめ 5、推計 操作変数の必要性 今回の推計では被説明変数に、個人iのサプリメント摂取頻度を置き、説明変数に配偶者のサプリメント摂 取頻度を置くことで、サプリメント摂取のピア効果検証を行う。 一致性の問題 「本人がサプリメント摂取をしていると配偶者も摂取する傾向にある」 逆の因果性 〇この場合、説明変数と誤差項に相関が生じてしまい、一致性を欠く恐れがある。 この問題に対処するために、本稿では操作変数を用いる。 31
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 操作変数の妥当性 ① 適切な操作変数の条件 操作変数が説明変数に影響を与える。 F検定によりF値が10を超える必要がある。 ② 適切な操作変数の条件 被説明変数の影響を直接受けない。 1 過剰識別検定で、相関がないか確認する 32
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,懸念点 操作変数の妥当性 ① 適切な操作変数の条件 配偶者の外食頻度を操作変数として採択する 操作変数が説明変数に影響を与える。 F値が10を超える 弱操作変数ではないので、影響を与えている。 F値② が10 を超え、過剰識別検定でも相関がないことが示されたので、推計に使用する。 適切な操作変数の条件 被説明変数の影響を直接受けない。 1 過剰識別検定 33
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 6,まとめ 5、推計 推計案 2 サプリメント摂取拡大とピア効果の関係 使用モデル;変量効果モデル・固定効果モデル 𝒀𝒊𝒕 = 𝜶 + 𝛄𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝑿𝒊𝒕 + 𝑭𝒊 + 𝜺𝒊𝒕 分類 変数 被説明変数 個人iのサプリ摂取頻度 説明変数 配偶者のサプリ摂取頻度 (二年前) 個人属性(年齢、婚姻、性別) コントロール 変数 説明変数 同様に逆の因果性に考慮するために、 当年の配偶者の摂取頻度ではなく、二 年前の摂取頻度をもちいる。 仕事形態(勤務時間、雇用形態) 収入 34 c
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 6,まとめ 5、推計 推計案 3 サプリメント摂取がウェルビーイングに与える影響について 使用モデル;固定効果操作変数法・変量効果モデル・固定効果モデル 𝑾𝒊𝒕 = 𝜶 + 𝜹𝑺𝒊𝒕 + 𝜷𝑿𝒊 + 𝑭𝒊 + 𝜺𝒊𝒕 分類 変数 被説明変数 ウェルビーイング (主観的生産性・ワークエンゲージメント) 説明変数 個人属性(年齢、婚姻、性別) 操作変数;配偶者のサプリメント摂取頻度 本人のサプリ摂取頻度と相関し、 ウェルビーイングに直接影響を与えないため サプリメント摂取頻度 コントロール 変数 仕事形態(勤務時間、雇用形態) 収入 35 c
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 操作変数の必要性 今回の推計では被説明変数に、ウェルビーイングを置き、説明変数にサプリメント摂取変数を置くことで、 サプリメント摂取が健康状態やウェルビーイングが変化するのかに着目する。 一致性の問題 「ウェルビーイングが満たさせている人ほどサプリメントを摂取する」 逆の因果性 〇この場合、説明変数と誤差項に相関が生じてしまい、一致性を欠く恐れがある。 この問題に対処するために、本稿では操作変数を用いる。 36
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 操作変数の妥当性 ① 適切な操作変数の条件 操作変数が説明変数に影響を与える。 F検定によりF値が10を超える必要がある。 ② 適切な操作変数の条件 被説明変数の影響を直接受けない。 1 過剰識別検定で、相関がないか確認する 37
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,懸念点 操作変数の妥当性 ① 適切な操作変数の条件 配偶者のサプリメント摂取頻度を操作変数として採択する 操作変数が説明変数に影響を与える。 F値が10を超える 弱操作変数ではないので、影響を与えている。 F値② が10 を超え、過剰識別検定でも相関がないことが示されたので、推計に使用する。 適切な操作変数の条件 被説明変数の影響を直接受けない。 1 過剰識別検定 38
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 利用データ 慶應義塾大学パネルデータ設計・解析センター提供のミクロパネルデータ 日本家計パネル調査(JHPS/KHPS) 期間; 2018-2022 年 (サプリメント 摂取に関する質問がこの期 間<2018、2020、2022>にしか実 施されていなか ったため) 対象者;20歳以上の男女 39
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 使用変数 サプリメント摂取について 上記の質問項目を使用し作成 サプリメント摂取カテゴリー変数 質問項目の番号を反転させた変数を作成(7ー質問項目番号) EX)まったく摂取しない=0 毎日2回以上=6 40
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 主観的生産性 今回はWHOが定義した「WHO-HPQ」を使用する。これはプレゼンティーズムを 測る指標として企業が健康経営銘柄を取得するための項目としても使用されるもの。 体調不良やメンタルヘルス不調などが原因で従業員のパフォーマンスが低下している状態 JHPSでの下記の質問項目を用いて算出する。 相対的生産性 =問2÷問1 絶対的生産性 =問2×10 41
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ ワークエンゲージメント JHPSでの下記の質問項目を用いて算出する。 「仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる。」 のような9つの質問に対して、月にどの程度感じるかを 7段階に表したものの合計の平均値を算出したものを使 用する。 42
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 性格 bigfive 小塩ほか(2012)によって作成された日本語版Ten Item Personality Inventory(TIPI-J) に基づく10個の質問項目から算出しており、5つの性格因子(外向性、協調性、勤勉性、 神経症傾向、開放性)を各2項目で測定している。 性格bigfiveは、データの性質上2019年単年しかとられていないが、 時間不変の要因と捉え、同一主体の他年度に拡張を行っている。
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 食習慣・生活習慣変数について 朝食頻度 朝食頻度に関して4段階で回答したものの値を反転させたものを使用する。 外食頻度 外食頻度に関して7段階で回答したものの値を反転させたものを使用する。 惣菜購入頻度・自炊頻度 惣菜購入・自炊頻度に関して7段階で回答したものの値を反転させたものを使用する。
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 食習慣・生活習慣変数について 運動習慣ダミー 定期的に運動していると答えた場合1,定期的な運動はしていないと回答した場合0 喫煙ダミー 毎日吸う・時々吸うと回答した場合1,今は吸わない・以前から吸わないと回答した場合0 飲酒頻度 飲酒頻度に関して5段階で回答したものの値を反転させたものを使用する。
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 基本統計量 46
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 基本統計量 サプリメント摂取頻度の平均値が1.88となっていることから、 およそ一週間に1回摂取していることがわかる 外食頻度の平均値は1.93 惣菜購入頻度は2.61 置き換えると、週に一度程度であることがわかる 自炊頻度の平均値は4.68 置き換えると、週に4~6度程度であることがわかる 朝食頻度の平均値は6.56 置き換えると、ほとんど毎日摂取していることがわかる 47
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 基本統計量 飲酒頻度の平均値は3.56 運動習慣ダミーは0.46 喫煙ダミーは0.17 喫煙ダミーに関しては、『令和5年国民健康・栄養調査』(厚生 労働省)によると、全体の15.7%であり、本稿の17%と乖離 が少ないことから、サンプルに偏りがないことがわかる。 年齢の平均値が56.39と年齢層が少し高いサンプルに なっている。 男性ダミーが0.48であり、男女に偏りがないことがわかる 婚姻ダミーも平均値が0.71であり、推計2・3でも十分に サンプルが確保できる 48
アウトライン 1 研究概要 4 分析アプローチ 2 はじめに 5 推計 3 先行研究 6 まとめ 4 1 5 6 49 2 3
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 5、推計 4、分析アプローチ 6,まとめ 推計案(再掲) 1 サプリメント摂取の規定要因について 使用モデル;変量効果順序ロジットモデル 𝑺𝒊𝒕 = 𝜶 + 𝜷𝟏 𝑴𝒊 + 𝜷𝟐 𝑵𝒊 + 𝜷𝟑 𝑲𝒊𝒕 + 𝜷𝟒 𝑿𝒊𝒕 + 𝑭𝒊 + 𝜺𝒊𝒕 分類 変数 被説明変数 サプリ摂取頻度 説明変数 時間割引率 性格特性 食事・生活習慣変数 コントロール変数 個人属性 収入 50
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 仮説 1 時間割引率が低い人ほど、サプリメント摂取に意欲的である。 1 佐藤(2018)より、外向性が高い人ほど、サプリメント摂取に意欲的である。 2 2 51
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 予備的分析 1 時間割引率 2 性格特性 摂取頻度上位と下位で時間割引率はあまり変わらない。 外向性、勤勉性、開放性の値が高い人、協調性の値が低い人はサプリメントを摂取しやすい。 52
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 予備的分析 3 食事習慣 4 生活習慣 食事習慣については、全ての変数で上位のほうがサプリメント摂取頻度が多い。 運動習慣のある人、喫煙頻度の少ない人ほどサプリメントを摂取頻度が多い。 53
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 推計結果 54
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 推計結果 全サンプルでは、係数が有意に推計されなかったが、男性サンプルでは、係数が負に有意に 推計された。 全サンプルでは、外向性を除いたすべての性格特性の係数が正に有意 男性サンプルでは、開放性の係数が正に有意 女性サンプルでは、協調性の係数が負に有意 55
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 推計結果 男性の場合、時間割引率が低い人ほど、サプリメント摂取する傾向があることが示された。 係数の値に着目すると、協調性や開放性が高い人のほうが摂取しやすい傾向がある。 サンプルごとに有意な係数が異なるため、性別ごとに摂取要因が異なることが示された。 56
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 推計結果 朝食頻度を除いたほとんどの係数が正に有意に推計されている。 女性サンプルの自炊頻度のみ、係数が有意になっていない。 運動習慣ダミーの係数が正に有意に推計されている。 喫煙頻度の係数が、負に推計されている。 57
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 推計結果 女性のほうが自炊が身近にあり、 健康意識と結びつきづらいと考えられる。 外食頻度やバランスのいい食事がとれない人は、サプリメントを代替的に摂取する傾向がある 惣菜購入や自炊頻度が高い人ような健康意識の高い人は、補完的に摂取する傾向がある。 運動習慣がある人は栄養に対する意識が高く、サプリメントを補完的に摂取する傾向がある。 喫煙をする人は、健康意識が低いことが背景にあり、サプリメントを摂取しない傾向にある。 58
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 推計結果 男性ダミーの係数が負に推計されていることから、男性のほうが女性より サプリメントを摂取しない傾向にある。 年齢ダミーの係数は、全ての列で正に有意に推計されていることから、年齢を重ねるごとに摂 取する傾向があることがわかる。 59
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 推計1まとめ 1 男性の場合、時間割引率が低い人のほうがサプリメント摂取に意欲である。 1 健康意識が高い人は補完的に、低い人は代替的に摂取する傾向がある。 3 3 性格特性においては、性別ごとに摂取要因が異なる。 2 2 60
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 推計案(再掲) 2 サプリメント摂取拡大とピア効果の関係 使用モデル;固定効果操作変数法・変量効果モデル・固定効果モデル 𝒀𝒊𝒕 = 𝜶 + 𝛄𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝑿𝒊𝒕 + 𝑭𝒊 + 𝜺𝒊𝒕 分類 変数 被説明変数 個人iのサプリ摂取頻度 説明変数 配偶者のサプリ摂取頻度 個人属性(年齢、婚姻、性別) 操作変数;配偶者の外食頻度 配偶者のサプリメント摂取と は相関する一方で、本人のサ プリメント摂取には影響を与 えないため。 コントロール 変数 仕事形態(勤務時間、雇用形態) 収入 61 c
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 予備的分析 1 配偶者のサプリ摂取 2 2年前の配偶者のサプリ摂取 すべての分類で、配偶者の摂取頻度が多いほうが本人の摂取頻度も多くなる。 ピア効果が存在すると想定される。 62
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 推計結果 63
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 推計結果 操作変数「配偶者の外食頻度」が弱操作変数でないか検証 したところ、F値は(1)列で15.68であった。 配偶者の外食頻度は弱操作変数になっていないと言える。 64
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 推計結果 配偶者のサプリメント摂取頻度の係数に着目すると、正に 有意に推計されいている。 二年ラグを考慮した配偶者のサプリメント摂取頻度の係数は、変量 効果モデルを用いた場合、正に有意に推計されている。 配偶者のような身近な人がサプリメント摂取を行っていると、その 本人もサプリメント摂取を促される可能性が高いことが示された。 サプリメント摂取行動にピア効果が存在している 65
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 推計案(再掲) 3 サプリメント摂取がウェルビーイングに与える影響について 使用モデル;固定効果操作変数法・変量効果モデル・固定効果モデル 𝑾𝒊𝒕 = 𝜶 + 𝜹𝑺𝒊𝒕 + 𝜷𝑿𝒊 + 𝑭𝒊 + 𝜺𝒊𝒕 分類 変数 被説明変数 ウェルビーイング (主観的生産性・ワークエンゲージメント) 説明変数 個人属性(年齢、婚姻、性別) 操作変数;配偶者のサプリメント摂取頻度 本人のサプリ摂取頻度と相関し、 ウェルビーイングに直接影響を与えないため サプリメント摂取頻度 コントロール 変数 仕事形態(勤務時間、雇用形態) 収入 66
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 予備的分析 1 主観的生産性(相対的指標) 2 主観的生産性(絶対的指標) 67
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 予備的分析 3 ワーク・エンゲイジメント 全ての指標・分類において、サプリメント摂取頻度 上位と下位で大きな差は見られない。 サプリメント摂取頻度の多寡はウェルビーイング に影響を与えないと考えられる。 68
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 推計結果 固定効果操作変数法 操作変数「配偶者のサプリ摂取頻度」が弱 操作変数でないか検証したところ、F値は (1)列で64.56、(2)列で26.95、(3)列で 28.81、(4)列で27.64、(5)列で26.73、 (6)列で23.74であった。 いずれもF値が10を上回っているため、弱操 作変数にはなっていないといえる。 69
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 推計結果 固定効果操作変数法 被説明変数がワークエンゲージメントを置 いた時のみ、サプリメント摂取頻度の係数 が正に推計された。 コントロール変数を含めた(6)列では、有 意な係数ではないので、サプリメント摂取が ワークエンゲージメントに明確な影響を 与えているとは裏図けられない。 70
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 推計結果 変量効果モデル いずれの場合もサプリメント摂取頻度の係数が 有意に推計されなかった。 71
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 推計結果 固定効果モデル 被説明変数が相対的生産性を置いた時のみ、 サプリメント摂取頻度の係数が正に推計された。 その他の被説明変数を置いた場合、サプリメント 摂取頻度の係数は有意に推計されなかった。 72
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 推計3まとめ 1 固定効果操作変数法を用いた際に、サプリメント摂取が ワークエンゲージメントに正の影響与えている。 1 2 2 固定効果モデルを用いた際には、サプリメント摂取が主観的生産性に正の影響を与えている。 73
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 推計3まとめ 1 固定効果モデルを用いた際には、サプリメント摂取が主観的生産性に正の影響を与えている。 1 いずれもほかの推計方法では有意な結果を得れていないため、本研究では、 サプリメント摂取とウェルビーイングに与える明確な影響を定量的に 図ることはできなかった。 2 2 固定効果操作変数法を用いた際に、サプリメント摂取が ワークエンゲージメントに正の影響与えている。 74
アウトライン 1 研究概要 4 分析アプローチ 2 はじめに 5 推計 3 先行研究 6 まとめ 4 1 5 6 75 2 3
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ まとめ 1 2 3 男性サンプルのみ時間割引率が低い人ほどサプリメント摂取に意欲的である。 1 代替的に摂取する人と、補完的に摂取する人がいることが示された。 2 4 3 4 配偶者の摂取行動が本人の摂取行動に影響を与えるピア効果が示された。 サプリメント摂取とウェルビーイングの関係性については、定量的に示せなかった。 76
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 考察 サプリメントの役割 時間がなくバランスの良い商事が取れない人にとっての代替的な手段としての役割 運動習慣のあるような健康意識の高い人にとっての補完的な役割 ピア効果検証 サプリメント摂取するきっかけとして 、身近な人の摂取が重要な要因であることを示唆 サプリメント市場拡大を目指すうえでは、上記の属性を持つ人に対してターゲティング を行い、紹介キャンペーンや販売活動を展開することが効果的であると考えられる。 77
1、研究概要 2、はじめに 3、先行研究 4、分析アプローチ 5、推計 6,まとめ 懸念点 1 データのサンプル数と期間に制約があった。 1 使用したデータが実質的に3年分であったことが、ピア効果やウェルビーイングを検証する際に特に制約となった。 2年のラグ期間を設けたが、期間が長すぎた可能性がある。 2 ウェルビーイング指標の妥当性 2 主観的生産性とワーク・エンゲイジメントが適切か、他に妥当な指標がなかったか 78
参考文献 【論文】 ・Bender, Mary M. (1992) “Trends in prevalence and magnitude of vitamin and mineral supplement usage and correlation with health status’’.Journal of the American Dietetic Association, 92 (9), 1096-1101. ・Bruce, Sacerdote (2011) “Peer effects in education: How might they work, how big are they and how much do we know thus far?’’. Handbook of the Economics of Education, Vol. 3, 249-277. ・Lyle, Barbara J., Mares-Perlman Julie A., Klein Barbara E., Klein Ronald, and Greger Janet L. (1998) ‘‘Supplement users differ from nonusers in demographic, lifestyle, dietary and health characteristics’’. The Journal of nutrition, 128(12), 2355-2362. ・Sato, Yoko, Sachina Suzuki, Tsuyoshi Chiba, and Keizo Umegaki. (2016) “Factors associated with dietary supplement use among preschool children: Results from a nationwide survey in Japan’’. Journal of Nutritional Science and Vitaminology , 62(1), 47-53. ・Sato, Yoko, Megumi Tsubota-Utsugi, Tsuyoshi Chiba, Nobuyo Tsuboyama-Kasaoka, Hidemi Takimoto, Nobuo Nishi, and Keizo Umegaki. (2016) “Personal behaviors including food consumption and mineral supplement use among Japanese adults: a secondary analysis from the National Health and Nutrition Survey, 2003-2010’’. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 25(2), 385-392. ・Tauchi, Kazutami, Sigeko Matuura, Yuji Satoh, Takayuki Tanizaki, and Yumiko KODAMA. (2003) “Present State and Problem of a Supplement Intake of Medical Examinee’’. Health Evaluation and Promotion , 30(3), 334-338. ・大浜修(2010)「サプリメントと治療の関係」『がん看護』15(7), 704-707. ・嘉山有太・稲田早苗・村木悦子・江端みどり・角田伸代・加園恵三(2006)「大学生におけ るサプリメントの利用と食行動・食態度との関連―運 動部学生と薬学部学生との 比較―」『栄養学雑誌』64(3), 173-183. ・小池麻由・大津史子・榊原仁作・後藤伸之(2013)「健康食品・サプリメントによる健康被 害の現状と患者背景の特徴」『医薬品情報学』14(4), 134-143. ・小塩真司・阿部晋吾(2012)「日本語版 Ten Item Personality Inventory (TIPI-J) 作成の 試み」『パーソナリティ研究』21(1), 40-52. ・櫻井浩子・海野碧希(2023)「サプリメントの利用状況と精神依存傾向に関する調査」 『Oyo Yakuri (Pharmacometrics)(0300-8533)』,104. ・佐藤陽子・千葉剛・梅垣敬三(2018)「女子大学生におけるパーソナリティ特性とサプリメ ント利用行動」『日本公衆衛生雑誌』65(6), 300307. 79
参考文献 【論文】 ・杉山寿美・岡松久美・廣田彩(2007)「非体育学部系男子大学生のサプリメントの利用実態 と食に関する保健行動」『県立広島大学人間文化学部 紀要』2, 83-93. ・藤本理平(2001)「情報のプラシーボ効果」『情報管理』44(1), 63-63. ・壬生茉莉衣・久保田優・辻林明子・東山幸恵・永井亜矢子・坂井三里・坂下清一(2012) 「臨床検査値と主観的健康把握から見た検診受診者にお けるサプリメント使用実 態」『日本補完代替医療学会誌』 9(2), 115-120. ・両角良子・井伊雅子(2003)「生活習慣と主観的健康観についての実証分析 健康的な食事習 慣とサプリメント・ドリンク剤需要に着目して」『医 療と社会』13(3), 3_45- 3_72. ・山口祐之・佐藤可野・河村和弘(2022)「高齢不妊女性に対するサプリメントの有用性」 『Journal of mammalian ova research』39(1), 2734. ・山下未来・荒木田美香子(2006)「Presenteeismの概念分析及び本邦における活用可能性」 『産業衛生学雑誌』48(6), 201-213. ・山本修平・冨永登夢・倉島健・戸田浩之・西岡秀一(2022)「日々の行動データを用いた時 間割引率の推定」『マルチメディア, 分散, 協調とモバ イルシンポジウム2022論 文集』2022, 17-27. ・湯田道生(2010)「健康状態と労働生産性」『日本労働研究雑誌』601, 25-36. ・吉田阿希・舘知也・兼松勇汰・杉田郁人・野口義紘・大澤友裕・寺町ひとみ(2018)「がん 患者における健康食品およびサプリメントの使用に影 響を及ぼす要因の解明」 『医療薬学』44(1), 49-53. 80
参考文献 【ウェブサイト】(最終閲覧日:2024年12月16日) ・厚生労働省「健康食品の安全性と有効性について」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-S yokuhinanzenbu/0000152250.pdf ・厚生労働省「健康被害情報」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html ・厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査」 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001338334.pdf ・厚生労働省『ワーク・エンゲイジメントに着目した「働きがい」をめぐる現状について』 https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/19/dl/19-1-2-3_01.pdf ・マイボイスコム株式会社 『【サプリメントの利用】に関するアンケート調査(第9回)』 https://myvoice.co.jp/biz/surveys/26909/index.html ・内閣府『消費者の「健康食品」の利用に関する実態調査』 088_120518_shiryou1-2.pdf (cao.go.jp) ・矢野経済研究所『2024年番版 健康食品の市場実態と展望 ~市場調査編~』 https://www.yano.co.jp/press-release/shou/press-id/3467 81
- https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500- Shokuhinanzenbu/0000152250.pdf
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html
- https://www.mhlw.go.jp/stf/saisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/syokuhin/daie tto/index.html
- https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/19/dl/19-1-2-3_01.pdf
- https://myvoice.co.jp/biz/surveys/26909/index.html
- https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2012/088/doc/088_120518_shiryou1-2.pdf
- https://www.yano.co.jp/press-release/shou/press-id/3467
ご清聴ありがとうござい ました! 82