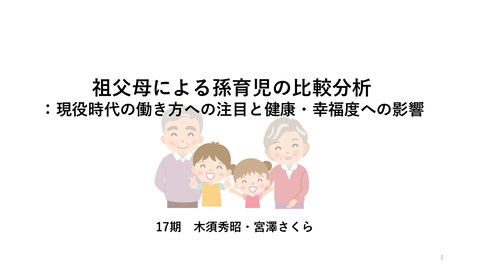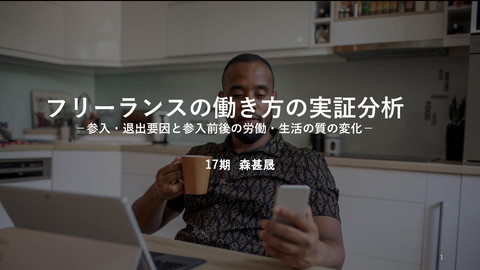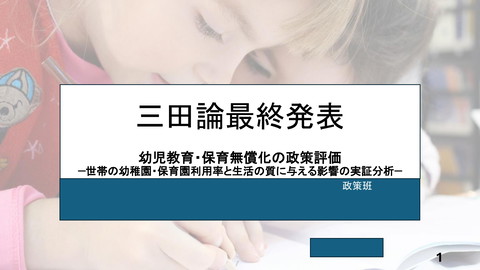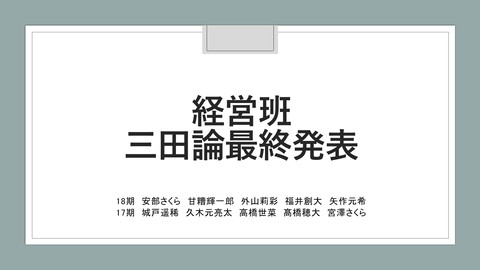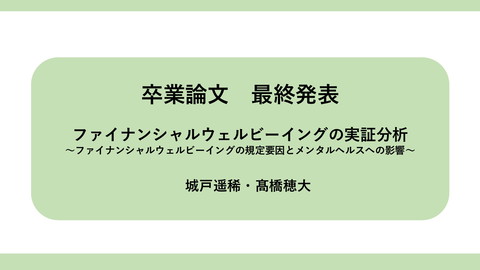2024卒業論文_清原麻央・竹備真紀
1.1K Views
February 19, 25
スライド概要
三世代生活の属性分析と親世代への影響について実証的に分析しています。居住形態や居住スタイルの要因を考察し、三世代で生活することで親世代の生活面や仕事への影響を調査しています。この発表では、背景や問題意識、先行研究、分析アプローチ、予備的分析を踏まえ、三世代での暮らしがもたらす効果について考察します。
慶應義塾大学商学部商学科山本勲研究会 ホームページ: https://www.yamazemi.info Instagram: https://www.instagram.com/yamazemi2024
関連スライド
各ページのテキスト
卒論最終発表 居住形態の属性分析と 三世代生活が親世代に 与える影響の実証分析 17期 清原 竹備
テーマ 居住形態の属性分析と 三世代生活が親世代に与える影響の実証分析 世帯構成や居住スタイル の属性・要因分析 三世代で生活することによ る、親世代の生活面(生活 満足度や健康意識など)へ の効果に関する分析 三世代で生活することによ る、親世代の仕事面(ワー クエンゲージメント・仕事 満足度)への効果に関する 分析 1
アジェンダ 1 背景・問題意識 2 先行研究 3 分析アプローチ 4 予備的分析・推計 5 おわりに 2
アジェンダ 1 背景・問題意識 2 先行研究 3 分析アプローチ 4 予備的分析・推計 5 おわりに 3
1.背景・問題意識 世帯構造の推移 厚生労働省「国民生活基礎調査」(2022)より作成 内閣府 令和3年版高齢社会白書 核家族が増える一方で三世代世帯は減ってきている 4
1.背景・問題意識 女性の就業の推移① ・女性の産後の就業 継続率は約7割 ・出産を理由に退職 する人も3割と一 定数存在する 厚生労働省『令和3年版 労働経済白書』 ・共働き夫婦は年々増加 厚生労働省『今後の仕事と育児・介護の 両立支援に関する研究会(第1回)』 5
1.背景・問題意識 女性の就業の推移② 厚生労働省 『今後の仕事と育児・介護の 両立支援に関する研究会(第1回)』 6
1.背景・問題意識 女性の就業の推移② ・就業率は高いが、正規雇用比率は25~29歳をピークに減少 ・女性の平均出産年齢は30.9歳 →ライフイベント(出産・育児)が原因で正規雇用として働き続けることが 難しい ・共働き世代が増えているが、増加しているのはパートタイム労働者 厚生労働省 『今後の仕事と育児・介護の 両立支援に関する研究会(第1回)』 7
1.背景・問題意識 女性の就業の推移③ 妊娠・出産を機に退職した理由 仕事と育児の両立は依然として困難 厚生労働省『今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会(第1回)』((2023) 8
1.背景・問題意識 女性の正規雇用継続のために ①職場環境の改善 ②公的支援の向上 ③三世代での暮らし 9
1.背景・問題意識 ①職場環境の改善 育児休業取得率の推移 『育児・介護休業法の改正について』厚生労働省 雇用環境・均等局 職業生活両立課 女性の育児休業率は8割以上だが、男性は2割未満 10
1.背景・問題意識 ①職場環境の改善 【再掲(◯ページ)】 妊娠・出産を機に退職した理由 職場環境が原因で退職している人もいる。 厚生労働省『今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会(第1回)』((2023) 11
1.背景・問題意識 ②公的支援の向上 保育所等数は増加している 三世代世帯から核家族への移行 =インフォーマルケアから フォーマルケアへの クラウディングアウト 認可保育所の利用しやすさ向上 母親の就業率が増加 西立野、四方(2017) こども家庭庁『保育所等関連状況取りまとめ(令和5年4月1日)』 12
1.背景・問題意識 ②公的支援の向上 ・保育待機児童は解消されたが、 学童待機児童は増加している ・隠れ待機児童は依然として高止まり 【隠れ待機児童】 自宅近くなど特定の保育 所を希望するといった理 由で保育所に入所できな い場合 待機児童数に含まれない 日本経済新聞(2024年9月22日) 日本経済新聞(2024年8月31日) 13
1.背景・問題意識 ②公的支援の向上 幼児教育・保育の無償化が 令和元年10月からスタート 【対象】 ◯幼稚園、保育所、認定こど も園等を利用する3~5歳のす べてのこどもの利用料 ◯住民税非課税世帯の0~2歳 のこども しかし、 延長保育や土曜保育の利用料は 無償化対象外 〈土曜保育〉 週によって開園状況が異なり、利 用希望日の数日前や1週間前まで に申請が必要な場合が多い。 また、毎月◯日までに申請用紙を 提出するというルールがある保育 園も多い。 急遽仕事が入ってしまった場合に 預けられないということが起こりうる。 14
1.背景・問題意識 ②公的支援の向上 幼児教育・保育の無償化が 令和元年10月からスタート 〈土曜保育〉 保育所等の数が増加し、保育待機児童の問題が解消されたことに加え、 週によって開園状況が異なり、利 【対象】 幼児教育・保育の無償化によって、 用希望日の数日前や1週間前まで 母親は就業を継続しやすい環境になっている ◯幼稚園、保育所、認定こど に申請が必要な場合が多い。 も園等を利用する3~5歳のす しかし、 また、毎月◯日までに申請用紙を べてのこどもの利用料学童待機児童や隠れ待機児童の存在や 提出するというルールがある保育 ◯住民税非課税世帯の0~2歳 無償化対象外の保育サービス、土曜保育の柔軟性の低さに課題がある。 園も多い。 のこども しかし、 延長保育や土曜保育の利用料は 無償化対象外 急遽仕事が入ってしまった場合に 預けられないということが起こりうる。 15
1.背景・問題意識 女性の正規雇用継続のために 近年、職場環境が改善されたり、 公的支援が向上したことによって、 女性は正規雇用を継続しやすくなっている。 しかし、依然として、 職場環境の差や公的支援の限定性により、 カバーできていないところもある。 三世代での暮らしが、 それらをカバーできるのではないか。 16
1.背景・問題意識 ③三世代での暮らし 〇西本ら(2004) 母親との同居は、その母親が就業しているかどうかに関わらず 妻のフルタイム・パートタイム就業を促進させる。 〇福田ら(2012) 夫方の母親は妻の非正規就業率の確立を高める一方、 妻方の親は特に子どもの年齢が低い場合に正規就業の確率を高める。 〇佐々木(2022) 効果は小さいながらも三世代同居が妻の雇用を促進する効果が認められた。 17
1.背景・問題意識 三世代で暮らすことのメリット 孫世代 〇兪崢(2015) ・三世代世帯の子どもの方が認知能力も非認知能力も高い傾向にある。 特に非認知能力に関して、 祖父母には親からは与えられない効果がある。 ・時間、財ともに教育投資が高い。 ※認知能力…理解・判断・論理などの知的能力 非認知能力…知能以外の特性・選好 18
1.背景・問題意識 三世代で暮らすことのメリット 【フレイル】 加齢により心身が老い衰えた状態 健康な状態と要介護状態の中間の段階 祖父母世代 1.老化予防 要支援以上の要介護認定になりやすい高齢者の特徴 ・4年前にメンタルヘルスの悪い人 ・低所得で経済的に不安定である人 ・10年前に運動習慣のない人 ... ・鬱状態などの心身の健康 ・歩行時間30分未満 ・外出頻度が少ない ・友人と会う頻度が月1回未満 ・地域の会への参加がない ・家事をしていない フレイルになりやすい高齢者の特徴 ... 平井ほか(2009) また、10年前の食事習慣が良好で あるほど、フレイルになりにくい 髙﨑(2023) オーラルフレイル=口の機能が健常な状態と口の機能低下との間にある状態 高齢期に生じる複数の課題(話す頻度の減少や柔らかいものを食べることなど)が重複して生じる口の衰え オーラルフレイルであると、将来のフレイル、要介護認定、死亡のリスクが高い。 日本老年歯科医学会(2024) 19
1.背景・問題意識 三世代で暮らすことのメリット 祖父母世代 1.老化予防 要支援以上の要介護認定になりやすい高齢者の特徴 【フレイル】 加齢により心身が老い衰えた状態 健康な状態と要介護状態の中間の段階 フレイルになりやすい高齢者の特徴 ... ・鬱状態などの心身の健康 三世代で生活することで、 ・4年前にメンタルヘルスの悪い人 ・歩行時間30分未満 ・低所得で経済的に不安定である人 人との交流や家事、運動、外出、所得などといった面で、 ・外出頻度が少ない ・10年前に運動習慣のない人 ・友人と会う頻度が月1回未満 老化の予防につながると考えられる。 ・地域の会への参加がない また、10年前の食事習慣が良好で ・家事をしていない あるほど、フレイルになりにくい 平井ほか(2009) ... 髙﨑(2009) オーラルフレイル=口の機能が健常な状態と口の機能低下との間にある状態 高齢期に生じる複数の課題(話す頻度の減少や柔らかいものを食べることなど)が重複して生じる口の衰え オーラルフレイルであると、将来のフレイル、要介護認定、死亡のリスクが高い。 日本老年歯科医学会(2024) 20
1.背景・問題意識 三世代で暮らすことのメリット 祖父母世代 2.主観的幸福度の向上 〇中村ら(2007) ・孫に対する情緒的な感情が高齢者の主観的幸福度を高める ・孫のいる高齢者の方が孫のいない高齢者に比べて健康度自己評価(主観的健康観)が高い 〇宮田ら(2013) ・孫の存在がもたらす生きがいのある充実した生活の質の向上が、精神的な満足感を高め、 ポジティブな感性を育む 〇内田ら(2015) ・『自分の余生を振り返させる度合』『孫とのふれあいの度合』 『日常の中でも相互の関心度合』が祖父母の精神的健康度に良い影響をもたらす 21
1.背景・問題意識 三世代で暮らすことのメリット 祖父母世代 主観的幸福度の向上 〇中村ら(2007) ・孫に対する情緒的な感情が高齢者の主観的幸福度を高める ・孫のいる高齢者の方が孫のいない高齢者に比べて健康度自己評価(主観的健康観)が高い 多くの祖父母にとって、孫は生きがいの1つとなっており、 孫の存在は祖父母の主観的幸福度や健康度を高める。 〇宮田ら(2013) ・孫の存在がもたらす生きがいのある充実した生活の質の向上が、精神的な満足感を高め、 ポジティブな感性を育む 〇内田ら(2015) ・『自分の余生を振り返させる度合』『孫とのふれあいの度合』 『日常の中でも相互の関心度合』が祖父母の精神的健康度に良い影響をもたらす 22
1.背景・問題意識 三世代で暮らすことのメリット・デメリット 親世代 就業 〇西本ら(2004) 同居している祖父母世代に家事や育児を代替してもらえることから 妻の就業を促進する効果 祖父母世代の介護や看護が妻の負担となり、妻の就業を抑制する効果 23
1.背景・問題意識 三世代で暮らすことのメリット・デメリット 親世代 就業 〇福田ら(2012) 妻の母親が近くに住んでいると、妻の正規雇用が促進される 夫の母親の同居・近居は同様の効果を与えない 24
1.背景・問題意識 三世代で暮らすことのメリット・デメリット 親世代 出典:不破(2014) 世帯構造や妻の就業形態に関わらず、妻が最も多く家事を負担している 25
1.背景・問題意識 研究内容 <問題意識> ・三世代での暮らしがどのような目的で選択されているのか(介護が目的か否かなど)を考慮 した研究が非常に少ない。 →研究① ・三世代世帯による親世代のメリットについての研究は、就業状況が中心であり、 他の効果についての研究が非常に少ない。 (就業面においても、祖父母が父方か母方か、同居か近居かで効果が異なる) ・三世代世帯においても、妻に家事の負担が偏っている。 →研究②・研究③ 先行研究で明らかになっていない、親世代へのメリットを明らかにすることで、 三世代生活を推進する意義を強める一助としたい。 26
1.背景・問題意識 研究内容 研究① 世帯構成や居住スタイルの属性・要因分析 研究② 三世代で生活することによる、親世代の生活面(生活満足度 や健康意識など)への効果に関する分析 研究③ 三世代で生活することによる、親世代の仕事面(仕事の パフォーマンス・スキル向上)への効果に関する分析 27
1.背景・問題意識 独自性 ①JHPSのデータを利用することによって、以下の項目について細分化できる点 ■同居する祖父母が父方か母方か ■同居・準同居・近居を区別 ■介護が必要な家庭か否か ■親の職種や働き方 ■親の家事・育児を含む生活時間 ■祖父母からの経済的援助の金額 〈研究の意義〉 ・先行研究では十分に考慮されていない詳細な家庭環境に着目することでより精密な分析を行う。 ・介護が必要な場合とそうでない場合での生活の差を明らかにすることができる。 その結果から三世代世帯に対する介護支援制度の強化の必要性を考えたい。 ・働き方の変化が三世代での生活にもたらす効果ついて明らかにすることができる。 ・同居よりも近居の方が女性の就労率を上げるという先行研究、完結出生児数を上げるというデータが あるが、他にも近居のメリットを挙げることで、同居に加えて近居の支援や政策にも強化すべきだと 言える。 28
1.背景・問題意識 独自性 ②パネルデータを使用することで世帯構造の変化による効果に 着目することができる点 〈研究の意義〉 パネルデータによって同一世帯を追跡調査することが可能であり、 アウトカムの変化の要因を明らかにすることができる。 ③親世代の生活面・仕事面における変化に着目する点 〈研究の意義〉 先行研究では祖父母世代や孫世代のメリット、母親の就業に関する研究が多かったた め、親世代へのその他のメリットについての研究を重ねることで、三世代生活推進の 一助となると考える。 29
アジェンダ 1 背景・問題意識 2 先行研究 3 分析アプローチ 4 予備的分析・推計 5 おわりに 30
2.先行研究 先行研究 三世代同居の動機やメリット 居住距離(同居と近居) 祖父母の家事育児参加の属性・要因、メリット 31
2.先行研究 三世代同居の動機やメリット 西本ら(2004) 兪崢(2015) 【概要】 親との同居や介護が妻の就業選択にどのような影響を及ぼす かについての分析 【結果】 ・母親との同居が妻の就業を促す。 ・非就業及び短時間労働の父親との同居が妻のフルタイム就 業を促す。 (同居による家事や育児の援助が受けられる状況) ・介護は妻の就業を抑制 【概要】 祖父母の有無と子どもの教育の関係について、世帯構成が子どもの 認知・非認知能力と教育投資に与える影響を検証 【結果】 ・三世代世帯の子どもの方が認知能力も非認知能力も高い。 ・子どもの勉強の面倒をみる意味では、祖父母の存在は親と同様の 効果を持ち、非認知能力を育む意味では、祖父母には親が与えられ ない効果がある。 ・時間と財ともに教育投資が多い。 安藤(2017) 大西ら(1997) 【概要】 初孫の母親のフルタイム就業と祖父母の親役割代替経験の認識 とその関連性についての研究 【結果】 ・同居もしくは近居であると、遠居よりも祖父母による子育て のサポートを受けやすい。 ・三世代同居は妻の就業継続、育児不安解消などにも一定程度 寄与する。 【概要】 家族形態が高齢者の主観的幸福感に与えている影響についての研究 【結果】 GDS(鬱度)が低くLSIK(生活満足度)が高かった三世代世帯の 高齢者の場合は、 子どもや孫と一緒に生活できることの幸せや、 病気や介護に対する不安があったとしても、老親 の扶養に対する 子どもへの期待度が高いことが、主観的幸福感として現れていると 考えられる。 32
2.先行研究 三世代同居の動機やメリット 西本ら(2004) 【概要】 親との同居や介護が妻の就業選択にどのような影響を及ぼす かについての分析 【結果】 ・母親との同居が妻の就業を促す。 ・非就業及び短時間労働の父親との同居が妻のフルタイム就 業を促す。 (同居による家事や育児の援助が受けられる状況) ・介護は妻の就業を抑制 兪崢(2015) 【概要】 祖父母の有無と子どもの教育の関係について、世帯構成が子どもの 認知・非認知能力と教育投資に与える影響を検証 【結果】 ・三世代世帯の子どもの方が認知能力も非認知能力も高い。 ・子どもの勉強の面倒をみる意味では、祖父母の存在は親と同様の 効果を持ち、非認知能力を育む意味では、祖父母には親が与えられ ない効果がある。 ・時間と財ともに教育投資が多い。 三世代で同居することによって、 祖父母から家事・育児のサポートが受けられ、 妻の就業促進につながる。 また、子どもの能力や教育投資にも好影響をもたらす。 安藤(2017) 介護は妻の就業を抑制する。大西ら(1997) 【概要】 初孫の母親のフルタイム就業と祖父母の親役割代替経験の認識 とその関連性についての研究 【結果】 ・同居もしくは近居であると、遠居よりも祖父母による子育て のサポートを受けやすい。 ・三世代同居は妻の就業継続、育児不安解消などにも一定程度 寄与する。 【概要】 家族形態が高齢者の主観的幸福感に与えている影響についての研究 【結果】 GDS(鬱度)が低くLSIK(生活満足度)が高かった三世代世帯の 高齢者の場合は、 子どもや孫と一緒に生活できることの幸せや、 病気や介護に対する不安があったとしても、老親 の扶養に対する 子どもへの期待度が高いことが、主観的幸福感として現れていると 考えられる。 33
2.先行研究 居住距離(同居と近居) 新田ら(2016) 【概要】 親子の同居や近居の住み方が比較的多いとされる中部・北陸地 方において、高齢者の親世帯と子世帯の住み方に着目し、親子 の居住形態の規定要因及び親子間の居住距離と子世帯の生活安 心感・居住満足度等の関係について研究 【結果】 ・親との居住距離が「近居」から「中距離近居」の層で住み方 に対する満足度が高い。 ・同居の利点は何かあったときの安心感があること、親の世話 がしやすいこと、家計上助かることが多いこと。 福田ら(2012) 【概要】 子育て世代の男女それぞれの母親の効果を同居と近居に分けて分析 【結果】 ・6歳未満の子どもの存在は女性の就労を抑制するが、女性の親が 近く(徒歩15分以内)に住んでいる場合は子どもがいないときと ほぼ同程度にまで回復する。 ・女性の母親の同居には同様の効果がなく、女性の就労に当たって は同居よりも近居の方が重要と考えられる(→共働き夫婦は親世代 と同居する経済的なインセンティブに乏しいことを反映していると 考えられる。) 千年(2016) 齋藤ら(2017) 【概要】 3~5歳児を持つ親の育児におけるソーシャルサポー ト を就業形態別に 様々な角度から研究 【結果】 ・母方祖母が、最も頻繁に子どもと会い、最も様々な種類の関わりをし ており、かつ最も頼れる相手であると母親が認識してい ることがわかっ た。 ・居住地の距離は祖父母の種類により有意な違いはなかった。 ・パートタイムの母親ほど祖父母から様々な面でサポート受ける傾向が ある(パートタイムの母親は、公的な支援(保育所や病児保育等)を受 けるのがフルタイムの母親に比べ困難であるため) 【概要】 妻・夫それぞれの母親との居住距離と女性の就業について,近 居が及ぼす影響、また親との近居が有配偶女性の就業にどのよ うな影響を及ぼすのかについて研究 【結果】 ・近居は女性の正規就業を促進する効果があるが、同居にはみ られなかった。 (同居は育児と母の見守りのダブルケアが必要) ・同居は必ずしも祖父母による子育て支援を意味しない。 34
2.先行研究 居住距離(同居と近居) 新田ら(2016) 【概要】 親子の同居や近居の住み方が比較的多いとされる中部・北陸地 方において、高齢者の親世帯と子世帯の住み方に着目し、親子 の居住形態の規定要因及び親子間の居住距離と子世帯の生活安 心感・居住満足度等の関係について研究 【結果】 ・親との居住距離が「近居」から「中距離近居」の層で住み方 に対する満足度が高い。 ・同居の利点は何かあったときの安心感があること、親の世話 がしやすいこと、家計上助かることが多いこと。 福田ら(2012) 【概要】 子育て世代の男女それぞれの母親の効果を同居と近居に分けて分析 【結果】 ・6歳未満の子どもの存在は女性の就労を抑制するが、女性の親が 近く(徒歩15分以内)に住んでいる場合は子どもがいないときと ほぼ同程度にまで回復する。 ・女性の母親の同居には同様の効果がなく、女性の就労に当たって は同居よりも近居の方が重要と考えられる(→共働き夫婦は親世代 と同居する経済的なインセンティブに乏しいことを反映していると 考えられる。) 千年(2016) 【概要】 3~5歳児を持つ親の育児におけるソーシャルサポー ト を就業形態別に 様々な角度から研究 【結果】 ・母方祖母が、最も頻繁に子ど もと会い、最も様々な種類の関わりをし ており、かつ最も頼れる相手であると母親が認識してい ることがわかっ た。 ・居住地の距離は祖父母の種類により有意な違いはなかった。 ・パートタイムの母親ほど祖父母から様々な面でサポート受ける傾向が ある(パートタイムの母親は、公的な支援(保育所や病児保育等)を受 けるのがフルタイムの母親に比べ困難であるため) 「近居」は住み方に対する満足度が高い。 「近居」は女性の正規就業を促進する効果がある。 (同居は育児と介護のダブルケアの状況が生まれるため) 齋藤ら(2017) 【概要】 妻・夫それぞれの母親との居住距離と女性の就業について,近 居が及ぼす影響、また親との近居が有配偶女性の就業にどのよ うな影響を及ぼすのかについて研究 【結果】 ・近居は女性の正規就業を促進する効果があるが、同居にはみ られなかった。 (同居は育児と母の見守りのダブルケアが必要) ・同居は必ずしも祖父母による子育て支援を意味しない。 35
2.先行研究 祖父母の家事育児参加の属性・要因、メリット 平井(2022) 【概要】 三世代同居家族における、祖父母の家事・育児時間算出、祖父母 の家事・育児時間の規定要因分析、祖父母の家事・育児時が妻の 負担軽減に寄与するかについての研究 【結果】 ・祖父の家事・育児時間は、祖父の年齢や学歴が高いほど長くな る。 ・祖母は母方同居であるほど、平日であるほど、父母が共働きで あるど、末子が0歳のときほど、孫の数が多いほど、長くなる。 ・祖母の家事・育児参加は母の家事・育児時間を短くする。 Jan et al.(2023) 【概要】 アメリカコミュニティ調査における三世代家族に関する情報を 使用し、三世代世帯における祖父母の孫に対する責任の認識に 関連する要因を分析。 【結果】 ・三世代世帯において、祖父母が孫に対する責任があると報告 する可能性と経済的な資源が関連していた。 ・就学前の孫がいる場合、孫に対する責任を自認する可能性が 低くなった。 八重樫ら(2003) 【概要】 乳幼児を持つ母親を対象に、祖父母の子育て参加の実態を明らかにし、 祖父母の子育て参加と母親の子育て不安との関連性について研究 【結果】 ・孫の近くに住んでいる祖父母は、孫とよく交流(訪問・電話)して いた。 ・母方祖母、父方祖母、母方祖父、父方祖父の順で、祖父母の子育て 参加や孫との関係が多かった。 ・祖父母の子育て支参加や孫との関わり方が適度であると、母親の子 育て負担が低かった。 平河(2018) 【概要】 保育所や祖父母による保育の利用可能性が母親の就業に与える 影響を実証分析 【結果】 ・全国の保育所定員数に対する各市区町村の保育所定員数の比 率は、母親の就業確率を有意に上昇させる。 ・祖父母との近居は母親の就業確率を有意に上昇させる。同居 は正の効果があるものの、有意ではない。=同居と遠方に居住 する場合で効果は変わらない。 36
2.先行研究 祖父母の家事育児参加の属性・要因、メリット 平井(2022) 【概要】 三世代同居家族における、祖父母の家事・育児時間算出、祖父母 の家事・育児時間の規定要因分析、祖父母の家事・育児時が妻の 負担軽減に寄与するかについての研究 【結果】 ・祖父の家事・育児時間は、祖父の年齢や学歴が高いほど長くな る。 ・祖母は母方同居であるほど、平日であるほど、父母が共働きで あるど、末子が0歳のときほど、孫の数が多いほど、長くなる。 ・祖母の家事・育児参加は母の家事・育児時間を短くする。 八重樫ら(2003) 【概要】 乳幼児を持つ母親を対象に、祖父母の子育て参加の実態を明らかにし、 祖父母の子育て参加と母親の子育て不安との関連性について研究 【結果】 ・孫の近くに住んでいる祖父母は、孫とよく交流(訪問・電話)して いた。 ・母方祖母、父方祖母、母方祖父、父方祖父の順で、祖父母の子育て 参加や孫との関係が多かった。 ・祖父母の子育て支参加や孫との関わり方が適度であると、母親の子 育て負担が低かった。 祖父母の育児参加は、母親の家事・育児時間を 短縮させ、子育て不安を軽減させる。 Jan et al.(2023) 【概要】 アメリカコミュニティ調査における三世代家族に関する情報を 使用し、三世代世帯における祖父母の孫に対する責任の認識に 関連する要因を分析。 【結果】 ・三世代世帯において、祖父母が孫に対する責任があると報告 する可能性と経済的な資源が関連していた。 ・就学前の孫がいる場合、孫に対する責任を自認する可能性が 低くなった。 平河(2018) 【概要】 保育所や祖父母による保育の利用可能性が母親の就業に与える 影響を実証分析 【結果】 ・全国の保育所定員数に対する各市区町村の保育所定員数の比 率は、母親の就業確率を有意に上昇させる。 ・祖父母との近居は母親の就業確率を有意に上昇させる。同居 は正の効果があるものの、有意ではない。=同居と遠方に居住 する場合で効果は変わらない。 37
2.先行研究 明らかになっていること 祖母との同居が母親の就業状況や 出生数、家事・育児時間に与える影響 親との居住距離が近いことが現在の 住み方に対する満足度に与える影響 三世代同居が子どもの認知能力や 非認知能力に与える影響 近居/同居が女性の就労に与える影響 三世代同居が時間と財の教育投資に 与える影響 祖父母の家事/育児参加の属性 38
2.先行研究 明らかになっていないこと どのような人が三世代暮らしを選ぶのか 三世代同居や近居による親世代の生活満足度や 心身の健康に与える影響 (育児と介護を区別) 三世代同居や近居による 親世代の仕事面への効果 同居する祖父母が父方か母方による違い 39
明らかにしたいこと 世帯構成や居住スタイルの属性・要因分析 三世代で生活することで、親世代の生活面(生活満足度や健康意識)に どのような影響があるのか 三世代で生活することが、親世代の仕事面(仕事のパフォーマンス・ スキル向上)にどのような影響があるのか 40
アジェンダ 1 背景・問題意識 2 先行研究 3 分析アプローチ 4 予備的分析・推計 5 おわりに 42
3.分析アプローチ 推計1 分析アプローチ 世帯構成や居住スタイルの属性・要因分析 【使用モデル】多項ロジットモデル 𝑓𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑔𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑀𝑖𝑡 , 𝑀𝑖𝑡 【被説明変数】 居住距離(カテゴリー変数) 0:遠距離ダミー(ベース) 1:三世代同居ダミー 2:三世代準同居ダミー 3:近居ダミー , 𝑀𝑖𝑡𝑠𝑒𝑚𝑖 , 𝑀𝑖𝑡𝑛𝑒𝑎𝑟 = 𝑎0 + 𝑎1𝑃1 + 𝑎2 𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 【説明変数】 要介護ダミー、末子年齢、子どもの 数、大卒ダミー(夫・妻)、正規雇 用ダミー(夫・妻)、夫婦正規雇用 ダミー、大企業ダミー(夫・妻) 【コントロール変数】 年ダミー、年齢ダミー、業種ダミー 43
3.分析アプローチ 推計1 仮説 世帯構成や居住スタイルの属性・要因分析 祖父母のサポートを受けられる、三世代同居、準同居、近居の家庭の方が、 祖父母のサポートを受けられない遠居の家庭よりも、 ・祖父母が要介護の傾向が高い ・末子年齢が低い ・夫と妻の共働きの傾向が高い 44
3.分析アプローチ 推計2 分析アプローチ 三世代生活の親世代の健康・生活満足度などへの影響分析 【使用モデル】固定効果モデル(ハウスマン検定の結果) 【被説明変数】 ・主観的健康状態 ・健康問題なしダミー ・メンタルヘルス指標 ・生活満足度 ・幸福度 要介護ダミー 【説明変数】 ・同居ダミー ・準同居ダミー ・近居ダミー ・夫方同居ダミー ・妻方同居ダミー ・夫方準同居ダミー ・妻方準同居ダミー ・夫方近居ダミー ・妻方近居ダミー 【コントロール変数】 年齢、勤続年数、給与、 週労働平均時間、週労働 残業時間、週平均家事時 間、週平均育児時間、喫 煙頻度、飲酒頻度、運動 習慣ダミー、平均睡眠時 間、朝食毎日ダミー、通 勤徒歩時間孫の数、孫の 末子年齢、職種ダミー、 職位ダミー 時間効果 ・年ダミー 45
3.分析アプローチ 推計2 仮説 三世代生活の親世代の健康・生活満足度などへの影響分析 祖父母のサポートを受けられる、三世代同居、準同居、近居の夫婦の方が、 祖父母のサポートを受けられない遠居の夫婦よりも、 ・主観的健康状態が良い。 ・健康問題がない。 ・メンタルヘルスが良い。 ・生活満足度が高い。 ・幸福度が高い。 46
3.分析アプローチ 推計3 分析アプローチ 三世代生活の親世代の仕事への影響分析 【使用モデル】固定効果モデル(ハウスマン検定の結果) 【被説明変数】 ・相対的プレゼンティーズム ・絶対的プレゼンティーズム ・ワークエンゲージメント ・仕事満足度 要介護ダミー 【説明変数】 ・同居ダミー ・準同居ダミー ・近居ダミー ・夫方同居ダミー ・妻方同居ダミー ・夫方準同居ダミー ・妻方準同居ダミー ・夫方近居ダミー ・妻方近居ダミー 【コントロール変数】 年齢、勤続年数、給与、 週労働平均時間、週労働 残業時間、週平均家事時 間、週平均育児時間、孫 の数、孫の末子年齢、職 種ダミー、職位ダミー 時間効果 ・年ダミー 47
3.分析アプローチ 推計3 仮説 三世代生活の親世代の仕事への影響分析 祖父母のサポートを受けられる、三世代同居、準同居、近居の夫婦の方が、 祖父母のサポートを受けられない遠居の夫婦よりも、 ・主観的生産性(相対評価) ・主観的生産性(絶対評価) ・ワークエンゲージメント ・仕事満足度 が高い。 48
3.分析アプローチ 使用データ 日本家計パネル調査(JHPS/KHPS) →就業、所得、教育、健康・医療などについて1年ごとに追跡調査したもの 日本家計パネル調査(JHPS) 対象年:2009年~2022年 対象者:20歳以上の男女 慶應義塾家計パネル調査(KHPS) 対象年:2004年~2022年 対象者:20歳~69歳の男女 日本家計パネル調査(JHPS/KHPS) 本稿では、2004年~2022年のデータを高校生以下の子どもがいる親世代に サンプルを絞って分析を行う 49
3.分析アプローチ 変数説明① すべて、夫と妻で区別している 変数名 変数説明 回答者年齢 同居人数 三世代暮らしダミー 次頁参照 居住スタイル① 次頁参照 三世代同居ダミー 次頁参照 三世代準同居ダミー 次頁参照 近居ダミー 次頁参照 居住スタイル② 父方同居ダミー 三世代で同居している人のうち、夫の両親と生活している場合に1を取るダミー変数 母方同居ダミー 三世代で同居している人のうち、妻の両親と生活している場合に1を取るダミー変数 父方準同居ダミー 三世代が同一の建物で別生計、あるいは同一敷地内で生活している人のうち、夫の両親と生活している場合に1を取るダミー変数 母方準同居ダミー 三世代が同一の建物で別生計、あるいは同一敷地内で生活している人のうち、妻の両親と生活している場合に1を取るダミー変数 父方近居ダミー 三世代で近くに住んでいる人のうち、夫の両親と生活している場合に1を取るダミー変数 母方近居ダミー 三世代で近くに住んでいる人のうち、妻の両親と生活している場合に1を取るダミー変数 主観的健康状態 次頁参照 生活満足度(生活全般) 次頁参照 幸福感(最近1週間) 次頁参照 メンタルヘルス指標(K6) 気分や不安障害を示す尺度で、合計が高いほどメンタルヘルスが良い 相対的プレゼンティーズム WHO-HPQの質問における指標で、【問2】÷【問1】 絶対的プレゼンティーズム WHO-HPQの質問における指標で、【問2】×10 ワークエンゲージメント 次頁参照 健康問題なしダミー 検診の結果、何も問題を指摘されなかった人を1とするダミー変数 健康状態 健康状態についての1~5の回答を反転させたもの 要介護ダミー 次頁参照 末子年齢 その世帯の最も若い年齢 孫の数 就業ダミー 就業している場合に1を取るダミー変数 大卒ダミー 大学を卒業している場合に1を取るダミー変数 50
3.分析アプローチ 変数説明② 変数名 変数説明 大卒ダミー 大学を卒業している場合に1を取るダミー変数 飲酒頻度 飲酒頻度についての1~6の回答を反転させたもの 喫煙頻度 喫煙襟度についての1~4の回答を反転させたもの 運動習慣ダミー 定期的な運動をしている場合に1を取るダミー変数 生活時間 次頁参照 家事時間 次頁参照 育児時間 次頁参照 介護・看護・介助 次頁参照 家事 家事の頻度が「週に1回」以上と回答した人の週の平均時間 育児 育児の頻度が「週に1回」以上と回答した人の週の平均時間 スキル取得ダミー 該当年に自分の意志で仕事にかかわる技術や能力の向上のための取り組み(学校に通う、講座を受講する、自分で勉強する、など) をした場合に1を取るダミー変数 就業 職種ダミー 農林漁業 農林漁業の場合に1を取るダミー変数 販売 販売業の場合に1を取るダミー変数 サービス サービス業の場合に1を取るダミー変数 管理 管理の場合に1を取るダミー変数 事務 事務の場合に1を取るダミー変数 運輸 運輸の場合に1を取るダミー変数 製造 製造業の場合に1を取るダミー変数 雇用形態ダミー 役職無し 役職無しの場合に1を取るダミー変数 役職有り 役職がある場合に1を取るダミー変数 経営者 経営者である場合に1を取るダミー変数 契約社員 契約社員である場合に1を取るダミー変数 パートタイム パートタイムである場合に1を取るダミー変数 正規雇用ダミー 正規雇用である場合に1を取るダミー変数 大企業ダミー 大企業に勤めている場合に1を取るダミー変数 週平均勤務時間 週平均残業時間 月平均労働日数 51
3.分析アプローチ 変数説明 *三世代暮らしダミー 三世代同居ダミー 三世代準同居ダミー 近居ダミー ↓ 夫方祖父母 ↓ 妻方祖父母 52
3.分析アプローチ 変数説明 *要介護ダミー 問1で1~3「いる」 かつ 問2で3「あなたの父母」 または4「配偶者の父母」 と回答した場合に 1をとるダミー変数 53
3.分析アプローチ 変数説明 推計2 *メンタルヘルス指標 調査期間:2019~2022 本研究では6項目を平均し、 1~5点の範囲で高いほど メンタルヘルスが良いとする。 「K6」:Kesslerらが開発した6項目からなる 尺度で、うつ病・不安障害などの精神疾患を スクリーニングすることを目的とするもの。 54
3.分析アプローチ 変数説明 推計2 *生活満足度 *幸福感 55
3.分析アプローチ 変数説明 推計2 *主観的健康状態 高いほど健康状態が良く なるように回答を反転 *健康問題なしダミー 付問1において、 12「何も問題は指摘されな かった」と回答した場合に 1をとるダミー変数 56
3.分析アプローチ 変数説明 推計3 *主観的生産性(仕事のパフォーマンス) 調査期間:2019~2022 相対的プレゼンティーズム→ 【問2】÷【問1】 ※0.25>を0.25に、2.0<を2.0にする。 数値が大きいほど通常の自分のパフォーマンス に近いことを示す。 WHO-HPQの質問で、 労働者の健康状態と職業パフォーマンス(仕事の 生産性や欠勤など)を評価するためのもの。 絶対的プレゼンティーズム→ 【問2】× 10 数値が大きいほど個人の労働パフォーマンスが 高いことを示す。 ※「プレゼンティーズム」 体調不良やメンタルヘルス不調などが原因で 従業員のパフォーマンスが低下している状態 57
3.分析アプローチ 変数説明 推計3 *ワークエンゲージメント 調査期間:2019~2022 ①~⑨を平均し、数値が大きいほ どワークエンゲージメントが高い 58
3.分析アプローチ 変数説明 推計2 *仕事満足度 59
3.分析アプローチ 変数説明 コントロール変数 *生活時間 それぞれの項目で「週に1回」 以上の場合の、週の平均時間 「ほとんど毎日」の」場合、 1日の平均時間×7で算出 60
3.分析アプローチ 基本統計量 61
3.分析アプローチ 基本統計量 ・三世代同居は約16%、準同居は約4%、近居は約30%、 遠距離は約48% ・同居と準同居→夫方祖父母 近居→妻方祖父母 のパターンの家庭が多い ・祖父母が要介護の家庭は全体の5% 62
3.分析アプローチ 基本統計量 ・生活面→夫に比べ妻の平均値の方が高い ・仕事面→ワークエンゲージメントのみ妻の方が高く、 プレゼンティーズム、仕事満足度は夫の方が高い 63
アジェンダ 1 背景・問題意識 2 先行研究 3 分析アプローチ 4 予備的分析・推計 5 おわりに 64
4.推計 推計1 予備的分析 世帯構成や居住スタイルの属性・要因分析 居住状況の推移 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 同居 準同居 近居 それ以外 三世代で同居する家庭が減少傾向にある。= 政府統計との乖離は見られない 近居が上昇傾向にある。 66
4.推計 推計1 予備的分析 世帯構成や居住スタイルの属性・要因分析 要介護ダミー 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 同居(4,390) 準同居(1,069) 近居(8,894) それ以外(8,153) 要介護ダミー 同居、準同居、近居、それ以外の順で介護が必要な家庭の割合が高くなっている → 介護を考慮するべき 67
4.推計 推計1 予備的分析 世帯構成や居住スタイルの属性・要因分析 平均末子年齢 孫の数の平均 11 2.2 2.18 2.16 2.14 2.12 2.1 2.08 2.06 2.04 2.02 2 1.98 10.5 10 9.5 9 8.5 8 同居 準同居 平均末子年齢 近居 それ以外 同居 準同居 近居 それ以外 孫の数の平均 同居や準同居の家庭の末子年齢の平均が高い →同居を選択した世代の年齢が高く、末子年齢も高くなっている可能性 同居、準同居、近居、それ以外の順で孫の数の平均が大きい。 68
4.推計 推計1 予備的分析 世帯構成や居住スタイルの属性・要因分析 就業ダミー 夫婦の就業状況 100.0% 80.0% 80.0% 70.0% 60.0% 60.0% 40.0% 50.0% 20.0% 40.0% 0.0% 30.0% 同居 準同居 夫 近居 それ以外 20.0% 10.0% 妻 0.0% 同居 週労働時間 準同居 共働き 50 40 30 20 10 0 近居 それ以外 両方正規 ・同居、準同居では共働きが多い ・同居、準同居、近居の順にどちらとも正規雇用の割合が高い 同居 準同居 近居 週労働時間 夫 週労働時間 妻 それ以外 69
4.推計 推計1推計結果 ある年を境に、同居・準同居・近居に変化した人の変化前の属性・要因分析 世帯構成や居住スタイルの属性・要因分析 被説明変数=居住距離(遠距離〈ベース〉、同居、準同居、近居) 同居 準同居 近居 要介護ダミー 0.712*** 0.0684 0.0922 (3.24) (0.20) (0.53) 末子年齢 0.00666 -0.0128 -0.0200** 孫の数 (0.39) (-0.64) (-2.29) 0.134 0.0539 -0.0694 (1.48) (0.42) (-0.96) 0.0303 大卒ダミー 夫 妻 -0.120 -0.00854 (-0.47) (-0.02) (0.15) -0.121 0.599 -0.274 (-0.32) (1.10) (-1.02) -0.0633 0.888* 0.297 (-0.18) (1.86) (1.25) 正規雇用ダミー 夫 妻 共働き正規ダミー -0.395 0.490 0.291 (-0.70) (0.61) (0.62) 1.120** -0.247 -0.135 (1.96) (-0.29) (-0.28) -0.456*** -0.505* -0.271** (-3.10) (-1.95) (-2.57) -0.136 -0.269 -0.144 (-0.92) (-1.08) (-1.35) -1.556** -3.975*** 0.316 (-2.15) (-3.24) (0.72) 大企業ダミー 夫 妻 定数項 年ダミー yes 年齢ダミー yes 業種ダミー yes 標本数 9,021 ID数 2,062 (注1)括弧内はクラスタ標準誤差を表す。 (注2) ***,**,*はそれぞれ1%,5%,10%水準で統計的に有意であることを示す。 72
4.推計 末子年齢 推計1推計結果 孫の数 0.00666 -0.0128 -0.0200** (0.39) (-0.64) (-2.29) 0.134 0.0539 -0.0694 -0.120 -0.00854 0.0303 (-0.47) (-0.02) (0.15) ある年を境に、同居・準同居・近居に変化した人の変化前の属性・要因分析 (1.48) (0.42) (-0.96) 大卒ダミー 夫 世帯構成や居住スタイルの属性・要因分析 被説明変数=居住距離(遠距離〈ベース〉、同居、準同居、近居) 要介護ダミー 末子年齢 孫の数 同居 準同居 近居 0.712*** 0.0684 0.0922 (3.24) (0.20) (0.53) 0.00666 -0.0128 -0.0200** (0.39) (-0.64) (-2.29) 0.134 0.0539 -0.0694 (1.48) (0.42) (-0.96) 妻 正規雇用ダミー 夫 妻 共働き正規ダミー 夫 妻 妻 共働き正規ダミー 0.297 (-0.70) (0.61) (0.62) 1.120** -0.247 -0.135 (1.96) (-0.29) (-0.28) -0.456*** -0.505* -0.271** (-3.10) (-1.95) (-2.57) -0.136 -0.269 -0.144 (-0.92) (-1.08) (-1.35) -1.556** -3.975*** 0.316 (-2.15) (-3.24) (0.72) -0.00854 0.0303 (-0.47) (-0.02) (0.15) -0.121 0.599 -0.274 (-0.32) (1.10) (-1.02) 年ダミー yes -0.0633 0.888* 0.297 年齢ダミー yes (-0.18) (1.86) (1.25) 業種ダミー yes -0.395 0.490 0.291 標本数 9,021 (-0.70) (0.61) (0.62) ID数 2,062 1.120** -0.247 -0.135 (注1)括弧内はクラスタ標準誤差を表す。 介護を必要としている祖父母がいる家庭ほど、 (1.96) (-0.29) (-0.28) 同居する傾向 大企業ダミー 夫 0.888* (-0.18)大企業に行く人は、大学進学時や就職時に上京 (1.86) (1.25) -0.395してこの3つのパターンに該当しにくい可能性 0.490 0.291 -0.120 正規雇用ダミー 夫 -0.0633 大企業ダミー 大卒ダミー 夫 -0.121 0.599 -0.274 夫婦どちらも正規雇用として働いている家庭 (-0.32) (1.10) (-1.02) ほど祖父母と同居する傾向 -0.456*** -0.505* -0.271** (-3.10) (-1.95) (-2.57) 妻 定数項 (注2) ***,**,*はそれぞれ1%,5%,10%水準で統計的に有意であることを示す。 73
4.推計 推計1 まとめ 世帯構成や居住スタイルの属性・要因分析 ・介護を必要とする祖父母がいる家庭ほど同居を選択する ・夫婦共に正規雇用として働いている家庭ほど同居を選択する ・夫が大企業に勤めている家庭ほど同居、準同居、近居を選択しにくい →大学進学時や就職時に地元を離れ、核家族化しやすい可能性 ・ 74
4.推計 推計2 予備的分析 三世代生活の親世代の健康・生活満足度などへの影響分析 主観的健康状態 健康問題なしダミー 3.7 0.4 0.35 3.65 0.3 0.25 3.6 0.2 3.55 0.15 0.1 3.5 0.05 3.45 0 同居 準同居 近居 夫 遠居 妻 ・妻は同居の場合に健康状態が良い傾向にある。 ・同居、準同居の場合に夫婦差が大きい。 ・全体的に妻の方が良い傾向 同居 準同居 近居 夫 遠居 妻 ・夫の方が健康に問題がない傾向 ・近居、遠居の場合に夫婦差が大きい 76
4.推計 推計2 予備的分析 三世代生活の親世代の健康・生活満足度などへの影響分析 メンタルヘルス指標 生活満足度 4.35 6.6 4.3 6.4 4.25 6.2 4.2 6 4.15 5.8 4.1 5.6 同居 準同居 メンタルヘルス 夫 近居 遠居 メンタルヘルス 妻 ・準同居の場合に夫のメンタルヘルスが最も低く、 妻のメンタルヘルスが最も高い傾向にあり、 夫婦差が小さい。 ・遠居の場合に夫のメンタルヘルスが最も高く、 妻のメンタルヘルスが最も低い傾向にあり、 夫婦差が大きい。 5.4 同居 準同居 近居 夫 遠居 妻 ・同居の場合に生活満足度が非常に低い傾向に ある。 ・遠居の場合に生活満足度の夫婦差が小さく、 夫婦ともに高い傾向にある。 77
4.推計 推計2 予備的分析 三世代生活の親世代の健康・生活満足度などへの影響分析 生活満足度 幸福感 6.5 6.7 6.6 6 6.5 6.4 6.3 5.5 6.2 ≒ 6.1 6 5.9 同居 準同居 近居 夫 遠居 妻 ・同居の場合に生活満足度が非常に低い傾向にある。 5.8 同居 準同居 近居 夫 妻 遠居 ・遠居の場合に生活満足度の夫婦差が小さく、 夫婦ともに高い傾向にある。 ・遠居の場合に幸福度が高く、 同居の場合に低い傾向にある。 78
4.推計 推計2 推計結果(夫) 三世代生活の親世代の健康・生活満足度などへの影響分析 79
4.推計 推計2 推計結果(夫) 三世代生活の親世代の健康・生活満足度などへの影響分析 <主観的健康状態> 正に有意:同居ダミー×要介護ダミー 妻方同居ダミー×要介護ダミー <健康問題なしダミー> 負に有意:準同居ダミー×要介護ダミー 夫方準同居ダミー×要介護ダミー 祖父母が要介護状態である場合には、 同居、特に配偶者の親との同居によって 主観的健康状態が良くなりやすく、 準同居、特に自分の親との準同居によって 健康問題がある確率が高くなりやすい。 主観的健康状態の解釈 同居している祖父母の介護によって 生活が規則正しくなることが関係している。 80
4.推計 推計2 推計結果(夫) 三世代生活の親世代の健康・生活満足度などへの影響分析 <メンタルヘルス> 負に有意:準同居ダミー <生活満足度> 正に有意:夫方準同居ダミー 負に有意:近居ダミー、妻方近居ダミー 準同居は遠居よりもメンタルヘルスが 悪くなりやすい。 自分の親との準同居は遠居よりも 生活満足度が高くなりやすく、 近居、特に配偶者の親との近居は 遠居よりも低くなりやすい。 ( 新田ら(2016)の住み方に対する満足度の結果) 81
4.推計 推計2 推計結果(夫) 三世代生活の親世代の健康・生活満足度などへの影響分析 <メンタルヘルス> 負に有意:準同居ダミー、 準同居ダミー×要介護ダミー 夫方準同居ダミー×要介護ダミー 準同居は遠居よりもメンタルヘルスが悪くなりやすく、 祖父母が要介護の場合、さらに悪くなりやすい。 祖父母が要介護の場合には、自分の親との準同居によって メンタルヘルスが悪くなりやすい。 82
4.推計 推計2 推計結果(妻) 三世代生活の親世代の健康・生活満足度などへの影響分析 83
4.推計 推計2 推計結果(妻) 三世代生活の親世代の健康・生活満足度などへの影響分析 <主観的健康状態> 正に有意:近居ダミー、妻方近居ダミー <メンタルヘルス> 正に有意:夫方近居ダミー×要介護ダミー ・近居、特に自分の親と近居の場合、主観的健康状態が 良くなりやすい。 ・祖父母が要介護状態の場合には、配偶者の親との 近居によってメンタルヘルスが良くなりやすい。 84
4.推計 推計2 推計結果(妻) 三世代生活の親世代の健康・生活満足度などへの影響分析 <生活満足度> 負に有意:近居ダミー、 妻方準同居ダミー 夫方準同居ダミー×要介護ダミー 近居、自分の親との準同居の場合、 生活満足度が低くなりやすい。 祖父母が要介護の場合には、 配偶者の親との準同居によって、 生活満足度が低くなりやすい。 85
4.推計 推計2 まとめ 三世代生活の親世代の健康・生活満足度などへの影響分析 ・自分の親との準同居の場合に生活満足度が高くなりやすい。 ・近居、特に配偶者の親との近居の場合には生活満足度が低くなりやすい。 ・準同居の場合にメンタルヘルスが悪くなりやすい。 ・祖父母が要介護状態であることはマイナスの影響を与えることが多い。 しかし、主観的健康状態については、要介護である場合、同居、特に配偶者の親との同居 がプラスの影響を与えている。(←介護による規則正しい生活の影響?) ・近居の場合、主観的健康状態は良くなりやすいが、生活満足度は低くなりやすい。 ・近居の中でも特に自分の親との近居の場合に主観的健康状態が良くなりやすい。 ・祖父母が要介護である場合には、 配偶者の親との準同居によって、生活満足度が低くなりやすく、 配偶者の親との近居によってメンタルヘルスが良くなりやすい。 86
4.推計 推計3 予備的分析 三世代生活の親世代の仕事への影響分析 相対的プレゼンティーズム 1.15 ワークエンゲージメント 1.1 3.15 1.05 1 3.1 0.95 3.05 同居 準同居 近居 夫 遠居 妻 3 2.95 絶対的プレゼンティーズム 2.9 66 2.85 64 2.8 62 同居 60 準同居 近居 夫 58 同居 準同居 近居 夫 遠居 妻 遠居 妻 大差はないが、三世代同居の妻がどちらも低い傾向 ・妻のワークエンゲージメントが高い傾向 ・準同居の夫婦が最も高く、夫婦差も小さい傾向 87
4.推計 推計3 予備的分析 三世代生活の親世代の仕事への影響分析 仕事満足度 5.7 5.6 5.5 ・ワークエンゲージメント以外の指標で、 妻よりも夫の方が高い傾向にある。 5.4 5.3 5.2 ・どの指標も同居が低い傾向 5.1 5 4.9 同居 準同居 近居 夫 遠居 妻 ・同居の夫婦が低く、遠居の夫婦が高い傾向 ・同居の妻が夫よりも高い傾向 88
4.推計 推計3 推計結果 夫 三世代生活の親世代の仕事への影響分析 89
4.推計 推計3 推計結果 夫 三世代生活の親世代の仕事への影響分析 <絶対的プレゼンティーズム> 負に有意:同居ダミー、準同居ダミー 夫方同居ダミー、 夫方準同居ダミー、 妻方準同居ダミー、 妻方近居ダミー×要介護ダミー ・同居、特に自分の親との同居の場合と、 準同居の場合、どちらの親との準同居に おいても遠居の場合に比べて、 労働パフォーマンスが低くなりやすい。 ・祖父母が要介護状態には、 配偶者の親との近居によって、 労働パフォーマンスが低くなりやすい。 90
4.推計 推計3 推計結果 夫 三世代生活の親世代の仕事への影響分析 <ワークエンゲージメント> 正に有意:要介護ダミー 負に有意:同居ダミー、夫方近居ダミー、 夫方準同居ダミー×要介護ダミー、 妻方近居ダミー×要介護ダミー <仕事満足度> 負に有意:近居ダミー、妻方近居ダミー 交差項と要介護ダミーの係数の合計が0 であるという帰無仮説についてt検定を 行なった結果、 →夫方準同居では、p値が0.6872とな り、 帰無仮説は棄却されず、 妻方近居では、p値が0.0911となり、 帰無仮説が棄却された。 91
4.推計 推計3 推計結果 夫 三世代生活の親世代の仕事への影響分析 <ワークエンゲージメント> 正に有意:要介護ダミー 負に有意:同居ダミー、夫方近居ダミー、 夫方準同居ダミー×要介護ダミー、 妻方近居ダミー×要介護ダミー <仕事満足度> 負に有意:近居ダミー、妻方近居ダミー ワークエンゲージメントは同居、 自分の親との近居の場合、低くなりやすい。 祖父母が要介護状態の場合には、そうでない 場合より高くなりやすいが、 配偶者の親との近居によって低くなりやすい。 仕事満足度は近居、特に配偶者の親との近居 によって低くなりやすい。 92
4.推計 推計3 推計結果 妻 三世代生活の親世代の仕事への影響分析 93
4.推計 推計3 推計結果 妻 三世代生活の親世代の仕事への影響分析 <相対的プレゼンティーズム> 正に有意:準同居ダミー、 夫方準同居ダミー、 夫方近居ダミー 準同居、特に配偶者の親との 準同居の場合と、 配偶者の親との近居の場合に、 通常の自分と近いパフォーマンスを 出しやすいといえる。 94
4.推計 推計3 推計結果 妻 三世代生活の親世代の仕事への影響分析 <ワークエンゲージメント> 負に有意:準同居ダミー、近居ダミー、 夫方近居ダミー、 妻方近居ダミー、 妻方近居ダミー×要介護ダミー <仕事満足度> 負に有意:妻方近居ダミー×要介護ダミー ワークエンゲージメントは準同居の場合と、 近居の場合、どちらの親との近居において も、低くなりやすい。 自分の親と近居の場合、祖父母が要介護 であると、さらに低くなりやすい。 仕事満足度は、祖父母が要介護状態の場合 には、自分の親との近居によって低くなり やすい。 95
4.推計 推計3 まとめ 三世代生活の親世代の仕事への影響分析 ・同居や準同居によって労働パフォーマンスが低下しやすい。 ・同居や自分の親との近居によってワークエンゲージメントが低下しやすい。 ・近居によって仕事満足度が低下しやすい。 ・祖父母が要介護状態である場合には、配偶者の親との近居によって、 労働パフォーマンスもワークエンゲージメントも低くなりやすい。 ・祖父母が要介護状態である場合に、三世代同居をしていることは親の仕事の ウェルビーイングに悪影響を与えていない。 ・準同居や近居の場合に本来の自分と近いパフォーマンスを出しやすいものの、 ワークエンゲージメントは低下しやすく、 要介護状態の祖父母がいる場合、 自分の親との近居によってその影響が強まり、仕事満足度も低くなりやすい。 96
アジェンダ 1 背景・問題意識 2 先行研究 3 分析アプローチ 4 予備的分析・推計 5 おわりに 97
5.おわりに 本研究の概要 問題意識 ・三世代での暮らしがどのような目的で選択されているのか(介護が目的か否かなど)を 考慮した研究が非常に少ない。 ・三世代世帯による親世代のメリットについての研究は、就業状況が中心であり、 他の効果についての研究が非常に少ない。 (就業面においても、祖父母が父方か母方か、同居か近居かで効果が異なる) ・三世代世帯においても、妻に家事の負担が偏っている。 「日本家計パネル調査(JHPS/KHPS)」を用いて実証分析 【推計1】居住形態の属性分析(多項ロジットモデル) 【推計2】三世代生活の親世代の健康・生活満足度などへの影響分析(固定効果モデル) 【推計3】三世代生活の親世代の仕事への影響分析(固定効果モデル) 98
5.おわりに 推計結果概要【再掲】 【推計1】世帯構成や居住スタイルの属性・要因分析 ・介護を必要とする祖父母がいる家庭ほど同居を選択する ・夫婦共に正規雇用として働いている家庭ほど同居を選択する ・夫が大企業に勤めている家庭ほど同居、準同居、近居を選択しにくい →大学進学時や就職時に地元を離れ、核家族化しやすい可能性 ・ 99
5.おわりに 推計結果概要【再掲】 【推計2】三世代生活の親世代の健康・生活満足度などへの影響分析 ・自分の親との準同居の場合に生活満足度が高くなりやすい。 ・近居、特に配偶者の親との近居の場合には生活満足度が低くなりやすい。 ・準同居の場合にメンタルヘルスが悪くなりやすい。 ・祖父母が要介護状態であることはマイナスの影響を与えることが多い。 しかし、主観的健康状態については、要介護である場合、同居、特に配偶者の親との同居 がプラスの影響を与えている。(←介護による規則正しい生活の影響?) ・近居の場合、主観的健康状態は良くなりやすいが、生活満足度は低くなりやすい。 ・近居の中でも特に自分の親との近居の場合に主観的健康状態が良くなりやすい。 妻 ・祖父母が要介護である場合には、 配偶者の親との準同居によって、生活満足度が低くなりやすく、 配偶者の親との近居によってメンタルヘルスが良くなりやすい。 100
5.おわりに 推計結果概要【再掲】 【推計3】三世代生活の親世代の仕事への影響分析 ・同居や準同居によって労働パフォーマンスが低下しやすい。 ・同居や自分の親との近居によってワークエンゲージメントが低下しやすい。 ・近居によって仕事満足度が低下しやすい。 ・祖父母が要介護状態である場合には、配偶者の親との近居によって、 労働パフォーマンスもワークエンゲージメントも低くなりやすい。 ・祖父母が要介護状態である場合に、三世代同居をしていることは親の仕事の ウェルビーイングに悪影響を与えていない。 ・準同居や近居の場合に本来の自分と近いパフォーマンスを出しやすいものの、 ワークエンゲージメントは低下しやすく、 要介護状態の祖父母がいる場合、 自分の親との近居によってその影響が強まり、仕事満足度も低くなりやすい。 101
5.おわりに まとめ 介護や育児のために三世代生活を選択しているが、 親世代におけるウェルビーイングにはデメリットが大きい。 準同居や近居の場合に介護が悪影響になりやすい。 ・三世代での生活を支援する政策や、 より柔軟な働き方、そのような状況がキャリアアップなどに不利にならないような制度や環境 ・準同居や近居の家庭への介護支援 102
5.おわりに 本研究の課題 ◯居住形態が健康・生活満足度、仕事に与える影響の分析(推計2、3)で、 以下の内生性が生じる可能性を考慮した操作変数法を使用できなかった。 ・親の健康状態が良好だから三世代生活ができる ・親の仕事が順調だから三世代生活ができる ◯ウェルビーイング指標の調査期間が3年間と短いため、サンプルサイズが小さくなっている。 ◯3年間の間で居住形態を変更する家庭は非常に少なく、 同一世帯の居住形態変更に伴うウェルビーイング指標の変化について十分に分析できていない。 ◯地方では家族従業者が多いことなどから三世代で生活する家庭が多いと考えられるが、 住んでいる地域による違いを考慮できていない。 103
参考文献 <論文、書籍> ・Kessler, Ronald C, Ames Minnie, Hymel Pamela. A, Loeppke Ronald, McKenas David. K, Richling, Dennis. E, Stang Paul E, and Ustun T. Bedirhan (2004). “Using the World Health Organization Health and Work Performance Questionnaire (HPQ) to evaluate the indirect workplace costs of illness”. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 46(6), S23-37 ・Mutchler, J.E. (2023). “Economic Resources Shaping Grandparent Responsibility Within Three-Generation Households”. Journal of Family and Economic Issues 2023, 44, pp.461-472 . Schaufeli, and Arnold Bakker (2004). “Utrecht Work Engagement Scale”. Preliminary Manual, 1(1), pp.1-60 ・安藤究(2017)「祖父母の親役割代替経験の認識と家族変動」『名古屋市立大学大学院人間文化研究科人間文化研究』15、 17-39頁 ・大西美智恵・小野ツルコ・田中昭子(1997)「家族形態と高齢者の主観的幸福感との関係」『日本看護科学会誌』17(3) 、 76-77頁 ・齋藤慈子・野嵜茉莉(2017)「3~5歳児を持つ親の育児におけるソーシャルサポート:母親の視点から」『武蔵野教育學 論集』(1) 、11-19頁 ・千年よしみ(2016)「女性の就業と母親との近居―第2回・第5回全国家庭動向調査を用いた分析―」『人口問題研究 (J. of Population Problems)』、72(2) 、120-139頁 ・西本真弓・七條 弘(2004)「親と西の同居と介護が既婚女性の就業に及ぼす影響」 『季刊家計経済研究』61、62-72頁 ・新田米子・志水暎子・小川裕子・神川康子(2016)「親子の居住距離が生活安心感・移住満足度に及ぼす影響―中部・北 陸地方における親子の居住形態の動向(その1)―」 『岐阜聖徳学園大学短期大学部紀要』48、59-72頁 104
参考文献 ・平井太規(2022)「祖父母による家事・育児動向の基礎的分析―3世代世帯家族を対象に―」『立教大学コミュニティ福祉 研究所紀要』10、115-127頁 ・平河茉璃絵(2018)「祖父母による保育の利用可能性と保育所による保育の利用可能性が母親の就業に与える影響」『年金 研究』10、53-67頁 ・福田順・久本憲夫(2012)「女性の就労に与える母親の近居・同居の影響」『社会政策』 4(1) 、 111-122頁 ・不破麻紀子(2014)「世帯に見る家事分担」『社会科学研究』65(1) 、51-70頁 ・八重樫牧子・江草安彦・李永喜・小河孝則・渡邊子(2003)「祖父母の子育て参加が母親の子育てに与える影響」『川崎医 療福祉学会誌』13(2)、233-245頁 ・兪崢(2015)「世帯構成が子どもの認知・非認知能力と教育投資に与える影響」『卒業論文集』 <ウェブサイト> ・厚生労働省子ども家庭局保育「保険を取り巻く状況について」(最終閲覧日2024年12月14日) https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000784219.pdf ・こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ(令和5年4月1日)及び『新子育て安心プラン』集計結果」(最終閲覧日2024 年12月14日)https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/torimatome/r5 ・こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化制度でよくあるご質問はこちら(1)」(最終閲覧日2024年12月14日) https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/about/faq1 105
参考文献 ・株式会社 日本能率協会総合研究所 「厚生労働省委託事業令和4年度仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査 研究事業」(最終閲覧日2024年12月14日)https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001085269.pdf ・厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課「仕事と育児・介護の両立に係る現状及び課題」(最終閲覧日2024年12月 14日)https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001045156.pdf ・国立社会保障・人口問題研究所 「第16回出生動向基本調査(夫婦調査)」(最終閲覧日2024年12月14日) https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001101627.pdf ・厚生労働省「国民生活基礎調査」(最終閲覧日2024年12月14日https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/ktyosa22/dl/14.pdf ・内閣府「令和3年版高齢社会白書」 (最終閲覧日2024年12月14日) https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w2021/zenbun/pdf/1s1s_03.pdf ・厚生労働省「今後の仕事と育児・介護の 両立支援に関する研究会(第1回)」(最終閲覧日2024年12月14日) https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001101627.pdf ・厚生労働省 雇用環境・均等局 職業生活両立課 「育児・介護休業法の改正について」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf ・日本経済新聞(2023年11月13日)「共働き、保育・民間学童費に備え『隠れ待機』負担重く[会員限定記事]」(最終閲 覧日2024年12月14日)https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB0108B0R01C23A1000000/ ・日本経済新聞(2024年9月22日)「見えぬ『待機学童』、実態は1.7倍 基準変更で潜在化[会員限定記事]」(最終閲覧 日2024年12月14日)https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE168WG0W4A810C2000000/?type=my#cAAUAgAAMA 106
- https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001085269.pdf
- https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001045156.pdf
- https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001101627.pdf
- https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/dl/14.pdf
- https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2021/zenbun/pdf/1s1s_03.pdf
- https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf
- https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB0108B0R01C23A1000000/
- https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE168WG0W4A810C2000000/?type=my
ご清聴ありがとうございました! 107