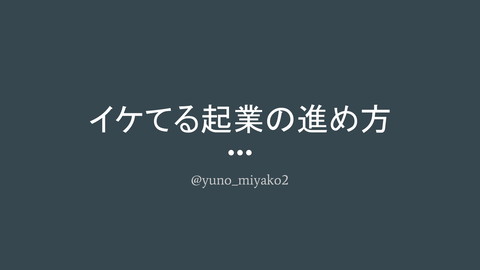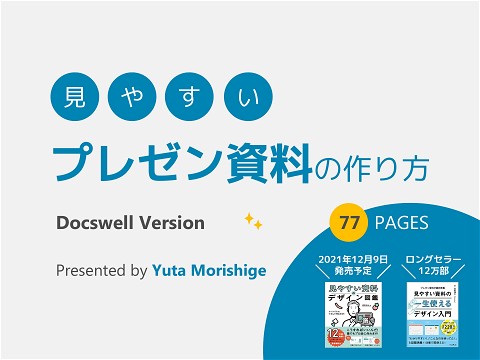関連スライド
各ページのテキスト
Agile Japan 2025 - Reboot Japan - Day 2 2025-11-14 変われない組織で、変わり続けることを選んだ SI企業で続けてきた現場と管理職の7年間 小さな実践が組織を動かし始めた
Bronze Sponsor NHK朝ドラ効果で 観光客が急増して いるにゃ! 島根県松江市 てぷにゃん (企業キャラクター) Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 2
Mission 技術の先に、 より良い生き方を創造する テクノプロジェクトは、 技術を通じて人々に安心と喜びをもたらし、 誰もが笑顔で過ごせる社会を創造します。 私たちは、関わる全ての人々と、 共に成長し、支え合う企業であり続けます。 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 3
まつもと すぐる 松本 俊 株式会社テクノプロジェクト 2010年にアジャイル開発と出会い、以来、受託開発 の現場を中心にアジャイルプラクティスやスクラムを 実践してきた。ここ数年は社内のチームを支援し、組 織全体へアジャイルの考え方を広げる活動にも注力。 2025年度からはプロダクトと組織の両軸で価値を 探索する部署に所属し、実践を重ねながらその両軸 の成長を目指している。 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 4
―― 試してきた、受託の中での挑戦 約7年間、受託側の中でできることを試してきた。 けれど、発注側と同じリズムで変化していく関係には、 なかなかたどり着けなかった。 ―― チームの中で感じたもどかしさと光 受託側の仲間とは、良い関係をつくれていた。 7年前のモヤモヤ ―― 2018年 でも、プロジェクトが終わるたびに、 学びや信頼が積み重ならない構造にもどかしさを感じていた。 物理のツールを使っていたので、 周囲からもチームの動きを見ることができた。 迷いながら進む毎日だったが、 「あのチームは楽しそうだね」と言われるくらい、 チームはいきいきしていた。 しかし、その空気が組織全体に広がることはなかった。 ―― 外の世界と、自分たちの輪郭 社外では、アジャイルが語られる場や成功事例が増えていった。 けれど自分は、目の前の現場に入り込むことで精一杯だった。 気づけば、自分たちにできることの“輪郭”が見えてきた。 それは、納得でもあり、悔しさでもあった。 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 5
じゅやま ゆうき 壽山 雄己 株式会社テクノプロジェクト バリューディスカバリー部 部長 入社以降、20年以上ヘルスケア分野で 大規模受託開発を経験。 2018年にアジャイル開発に出会って以降は 受託でも積極的にアジャイルを提案してきた。 趣味 : さかな釣り(船の上から) Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 6
7年前のモヤモヤ 従来型の受託開発への違和感 「なぜ作るのか」から切り離された開発 「プロジェクトを終わらせる」ミッション エンジニアとしても管理者としても感じていた痛み 「やりがい(エンゲージメント)」の喪失 「チームが成長する機会」の欠如 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 7
2018年に2人は同じプロジェクトでアジャイル開発を実践 そこから7年間、管理者、現場の立場でアジャイルを推進 本日はそのうち2つのプロジェクトのエピソードとともに、 管理者(ジュヤマ)、現場(マツモト)のそれぞれの視点で、 工夫した点や気づきをお伝えします Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 8
プロジェクトA Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 9
プロジェクトAの概要 新規/更新 新規 開発内容 業務アプリケーション開発 人数 9~10人 期間 10カ月 契約 準委任 アジャイル 開発の目的 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. ・競合製品の動向にあわせて優先度を調整をしたい ・ユーザー稼働日にあわせてスコープを調整をしたい 10
受託側 発注側 ステークホルダー ステークホルダー 管理サイド プロジェクト プロジェクト 管理責任者 管理責任者 カウンターパート 現場サイド 開発者 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. スクラムマスター 兼プロダクトオーナー プロジェクトリーダー (SM/PO) スクラムチーム 開発者 11
Episode プロジェクトA 現場 サイド Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 12
制約の中で、アジャイルをはじめる 顧客組織はウォーターフォール前提の制度と承認プロセスを持ち、 成果物や工程完了承認など、形式がすべて定められていた。 リリース日はすでに決まっており、 限られた期間で価値を届ける必要があった。 チームの多くはスクラム未経験。 経験者だった松本は、チームの中で自然とSMの役割を担っていた。 理想のスクラムを理解していても、 ガイド通りには始められない現実があった。 SMはチームの状況を見ながら、 いまの制約の中で実践できる方法を選び取っていった。 それが、この挑戦の最初の一歩だった。 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 13
理想ではなく、「できること」から 専任のPOはいない。 SMは、発注側と対話を重ねながら、 チームで少しずつバックログを整えていった。 スプリントは2週間。 チームが無理なく続けられるリズムを優先した。 デイリースクラム、タスクボード、ユーザーストーリー、ふりかえり。 それぞれの目的を伝えながら、試し、学びながら進めた。 印象的だったのは、ふりかえり。 「続けたいこと」「困ったこと」「次に試したいこと」を話し合い、 チームの中に、自分たちの言葉が少しずつ増えていった。 完璧ではなくても、実践を通して形にしていく。 それが、このチームの「できること」だった。 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 14
自分たちらしさを形にしていった スプリントを重ねるうちに、 動くものが少しずつ形になっていった。 プロダクトもチームも、共に成長していくのを感じていた。 日々の開発の中では、 つくりやふるまいについての会話が自然に始まり、 その場で意見を出し合いながら進める場面が増えていった。 チームは、そのときの状況に合わせてプラクティスを調整し、 例えば、タスクボードからカンバンへと進化させながら、 少しずつ“自分たちらしい進め方”を形にしていった。 制度は変わらない。 けれど、チームの中には “自分たちで変えられることがある”という実感が生まれていた。 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 15
変わる勇気は、制度の中でも育つ 制度や契約の枠を、 すぐに変えることはできなかった。 けれど、その中で工夫し、学び、少しずつ形を変えていくことはできた。 スクラムの考え方を手がかりに、 できることを探しながら、少しずつ試していった。 理想を掲げながらも、 そのとおりには進めない日もあった。 それでも、立ち止まらずに考え続けた。 その積み重ねが、 “制度の中でも変われる”という確信につながった。 変化を恐れず、共に学び、共に進む。 それが、私たちがこのプロジェクトで見つけた“勇気”だった。 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 16
当たり前を続けることの難しさ 対話やふりかえり、学びの積み重ね。 どれも、アジャイルでは“当たり前に見える”こと。 けれど、制度や契約のもとでそれを続けるのは、 簡単なことではなかった。 その“当たり前に見える実践”を続けた時間が、 現場を少しずつ変えていった。 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 17
Episode プロジェクトA 管理 サイド Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 18
コンテキスト(顧客) ・部門初となるアジャイルでの製品開発 ・管理責任者はアジャイルの理念や導入目的を理解し、協力的姿勢 ・(当時の)ソフトウェア開発ルールはウォーターフォール前提のもの ・スクラム導入を決めたが、制度上避けられない手続きが多く存在 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 19
工夫したこと ~重厚過ぎるプロジェクト計画 ・商談フェーズにて計画書の作成からがっつり支援 ・後にチームで作るインセプションデッキの参考にできることを意識 ・スクラムの実態に合わせて定義した内容 分類 方針 成果物 つくらないものを削除(必要性を精査した上で) コミュニケーション 不要な会議体を削除(スクラムイベントに寄せる) 変更管理 バックログリファインメントの運用方針を定義 品質管理 「リードタイム閾値」「カバレッジ目標値」「手戻り率」 「統計指標目標値(/ポイント数)」を用いて評価 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 20
工夫したこと ~避けられなかった設計工程 ・別動隊による先行設計(モックアップ、外部設計) ・設計工程以降でも変更を前提として進めることで合意 要件 定義 要件 定義 設計 フィード バック 評価 設計成果物 テスト 受入 設計 評価 設計成果物 sprint1 計画 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 製造 設計 設計工程 完了まで テスト 受入 sprint2 計画 製造 設計 21
プロジェクトA 結果 初期ユーザー稼働に間に合い、無事製品をリリース 多くのエンドユーザーから高い製品評価をいただいた その後のエンハンスや保守開発も受注し、現在も継続中 顧客部門内でアジャイル開発を採用するケースが増えた メンバーの多くが一番楽しかったプロジェクトと評価 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 22
プロジェクトA まとめ スクラムの価値を最大化するため、顧客と共に 現場サイド 制度の中でも「できること」の積み重ねが変化を生む 管理サイド どうやったら制度を活かせるかを考え続ける 制度への従属よりも、共に変わる勇気を Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 23
プロジェクトB Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 24
プロジェクトBの概要 新規/更新 新規 開発内容 Webアプリケーション開発 人数 9~13人 期間 6カ月 契約 準委任 アジャイル 開発の目的 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. ・大まかな機能イメージはあるが、細かい要件は 開発を進めながら決めたい ・必達のリリース日にあわせてスコープを調整したい 25
受託側 発注側 ステークホルダー ステークホルダー 管理サイド プロジェクト プロジェクト 管理責任者 管理責任者 カウンターパート 現場サイド 開発者 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. スクラムマスター プロダクトオーナー (SM) (PO) スクラムチーム 26
Episode プロジェクトB 現場 サイド Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 27
オンラインの距離と、機能起点の会話 • 顧客(発注側)は東京/自社(受託側)は島根のオンライン中心 • ステークホルダーが多く、報告文化の強い環境 • 参照資料や説明は“機能”を単位に語られており、体験や価値の意図が 伝わりにくかった • POはアジャイル経験者。SMはPOを孤立させない仕組みづくりに着手 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 28
SMが設計した「共に考えるための時間」 • SMは、POが孤立しないようにチーム全体で 「共に考える時間」をスプリント内に設計した • 開発者もプロダクトを一緒に考えられるよう、 対話のリズムと仕組みを整えた • リファインメントを定常化し、PO・SM・開発者 が価値を共有する時間を持ち続けた • POは“決める人”ではなく、“共に考える人” であり続ける関係を育てた Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 29
対面でのユーザーストーリーマッピングで 生まれた信頼の空気 • SMは、顧客作成資料をもとにユーザーストーリーマッピングのたたき台を 準備した • 模造紙に付箋を貼り出し、発注先の会議室でPOと並んでワークを実施 • 同じ壁を見ながら、同じ付箋を指差し、手を動かして考える • 画面越しでは生まれなかった信頼の空気が流れた • 「共に描いている」実感が、POとSMの間に芽生えた 信頼は、言葉を交わすだけでなく、 同じ壁を見ながら描くことから始まった Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 30
オンラインに戻っても続いた自然な対話 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 31
オンラインに戻っても続いた自然な対話 • 対面での共同作業を経て、オンラインでも自然な会話が生まれるように なった • チーム内では、雑談や相談がしやすい空気が広がった • POから「一緒に考える仲間ができた」という言葉が出た • POが上位層(顧客側管理層)に報告する際も、一度もチームを悪く言 わなかった • チーム全員が「信頼されている」と実感できた瞬間だった 一度つながった信頼は、距離を越えて対話の中に生き続けた Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 32
発注と受託、その線を越えて同じ目的へ • スプリントレビューには、発注側・受託側の多くのメンバーが参加した • それでも、レビューの時間は立場を越えて同じ目的を語る場になっていた • POは、ステークホルダーの期待とチームの現実をつなげる役割を果たした • POは、成果を求める立場から、価値を共に磨く仲間へと変わっていった • 同じ目的を見つめる関係が、チームの中に生まれた 信頼は、立場を越えて “目的”を共に見つめるところから育つ Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 33
信頼は、誠実な時間の積み重ねから生まれる ――共に描いた時間が、信頼という文化を育てた • 信頼は、契約ではなく、誠実な時間の積み重ねから生まれる • 共創とは、立場を超えて「見えない答えを一緒に探すこと」から 始まる • 受託の現場では、与えられた枠を問い直し、同じ目的を見つめ 直すことが第一歩になる Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 34
プロジェクトB まとめ(現場サイド) 現場サイド 立場を越えて、共に描く。その時間が、信頼を育てる。 役割の境界よりも、信頼による共創を Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 35
Episode プロジェクトB 管理 サイド Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 36
コンテキスト(プロジェクト) マネジメント 基盤開発 (WF) アプリ開発 (スクラム) 連携システム開発 (WF) ・基盤、連携システム開発が同時進行 ・アプリは双方と密な連携が必須 ・マネジメントレイヤーでは計画駆動を前提とした管理 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 37
進捗状況はなるべく定量値で報告 MMF(Minimum Marketable Feature)状況 現在スプリント状況 ・想定ベロシティでの理想線と実績線 (理想線は見通しとして提示済み) ・チーム活動で作成、運用中のもの 課題状況 ・プロジェクト全体に影響する課題を吸い上げたもの テストカバレッジ ・単体テスト(自動)のC0カバレッジ Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 38
起きたこと 優先PBIが想定より多く発生 ↓当初見込んでいたPBIをスコープアウト ↓最終的な機能数が当初見込みより減った 結果的に期待値の乖離が発生 初期からベロシティが想定値を下回る ↓想定値が守るべき目標値にすり替わる ↓時間外対応で維持するも疲弊 ↓増員するも短期的な改善には至らず やりきったが現場の疲弊に繋がった Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 39
プロジェクトB 結果 予定通りにサービスローンチできた メンバーは疲弊し、チームの健全性が損なわれた チームの生産性に疑義が発生し、説明を求められた 次期バージョンアップ開発は従来型に戻った 楽しかった、と評価したメンバーは・・・ Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 40
プロジェクトB まとめ(管理サイド) 管理サイド 「どれだけつくったか(アウトプット)」ではなく、 「どんな価値を生んだか(アウトカム)」を伝える 工夫と努力をすべき 形式的な報告よりも、誠実な透明性を 管理サイド 継続的な価値創出を続けるために、ベロシティは チームの健全性を測る1つの指標に過ぎないことを 管理サイドの共通理解とすべき 完了の約束よりも、価値を育てる協働を Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 41
私たちは、受託開発という制約のある現場で、アジャイルの考え方をどう生か せるかを模索してきた。その歩みの中で、次の価値の大切さを実感した。 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 42
役割の境界よりも、信頼による共創を 発注側と受託側という線を越え、同じ目的を見つめ、同じ成果を喜び合う。信頼は、契約を越えて価値 をつなぐ最初の力である。 形式的な報告よりも、誠実な透明性を 成果を飾る報告ではなく、現実をそのままに共有し、課題を共に見つめる。透明性は、信頼を育てるた めの最も人間的な技術である。 完了の約束よりも、価値を育てる協働を 一度きりの納品で終えるのではなく、リリースと学びを重ねながら、価値を磨き続ける。納品は終わりで はなく、対話の続きである。 制度への従属よりも、共に変わる勇気を 制度や計画の枠に縛られることを恐れず、共に学び、変化を価値に変える。変化は、信頼を試すもので はなく、信頼を深める機会である。 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 43
7年間の経験から、いま言えること 受託開発という現場で、アジャイルの考え方をどう活かすか その問いと向き合い続ける中で、現場と管理者がこれからも大切にしたい6つの姿勢 顧客と共に早期に学び、価値を育てる 動く成果と学びで計画を磨く 短期間で最小限の機能を持つMVPを動かし、顧客が早 期に検証・学びを得られる環境を整えます。 そこから得た学びを生かし、価値ある成果を継続的に届 けます。 計画はあくまで見通しであり、顧客と共に価値を探るため の仮説です。 動く成果と学びを通して、その仮説を確かめ続けます。 越境しながら、同じ方向を見つめる 品質を、価値を育てる習慣として捉える ビジネス側と開発者が臆することなく越境し、常に同じ方 向を見つめながら協力しあいます。 品質は評価基準ではなく、価値を育てるための習慣です。 顧客と共に品質をつくり込み、変化の中でその意味を磨 き続けます。 チームが力を発揮できる環境をつくる 人を埋めるより、価値を流す プロジェクトのために集まったメンバー一人ひとりが、高い エンゲージメントを持てるよう、チームとして環境を整えま す。 人の稼働率ではなく、価値が届くまでの時間を重んじます。 その流れの中でこそ、学びと信頼が育ちます。 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 44
おわりに 今年度、私たちは「バリューディスカバリー部」という新しい 部署を立ち上げました。プロダクトと組織の両軸で価値を探し、 育てていくための場所です。 これからも現場での学びを、組織の変化につなげていく。 その挑戦を通して、もっと多くの仲間と価値を見つけていきたい と思っています。 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 45
変わることをあきらめずに試し続けてきた 私たちの小さな実践が 誰かの「やってみよう」の一歩につながればうれしいです Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 46
もう一度、ここから。 一緒に変化を楽しめる現場をつくっていきましょう Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 47