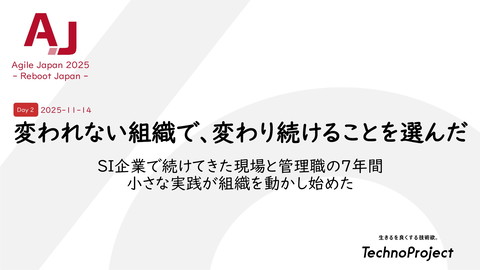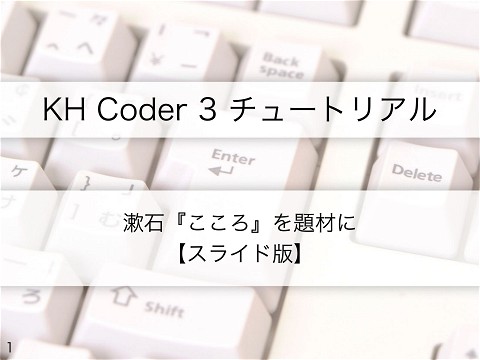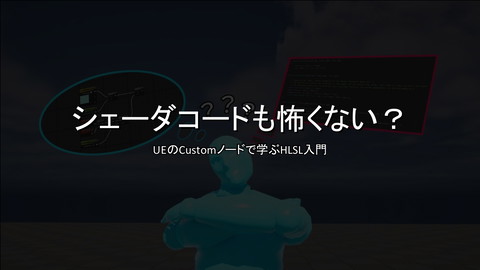型が広がったその先で、問いが聞こえなくなった
746 Views
October 04, 25
スライド概要
関連スライド
各ページのテキスト
スクラム祭り 2025 島根トラック 2025年10月4日 型が広がったその先で、問いが聞こえなくなった 松本 俊
まつもと すぐる 松本 俊 本社:島根県松江市 設立:1984年3月1日 https://www.tpj.co.jp/ 株式会社テクノプロジェクト 2010年にアジャイル開発と出会い、以来、受託開発の 現場を中心にアジャイルプラクティスやスクラムを実 践してきた。ここ数年は社内のチームを支援し、組織 全体へアジャイルの考え方を広げる活動にも注力。 2025年度からはプロダクトと組織の両軸で価値を探索 する部署に所属し、実践を重ねながらその両軸の成長 を目指している。 スクラム祭り 2025 島根トラックオーナー。 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 事業内容 • システムインテグレーション事業 • 特定業種ソリューション開発 • クラウドサービス提供 • ICTに関するコンサルティング、計画および実行支援 • デジタル人材育成 型が広がったその先で、問いが聞こえなくなった てぷにゃん (企業キャラクター) 2
やり方を真似るだけでは、意味は育たない ——問いがあるから実践になる Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 型が広がったその先で、問いが聞こえなくなった 3
2010年にアジャイルと出会う 島根県内で「Ruby × Agile」を推し進めるための事業 ——島根県の「Rubyビジネスモデル研究実証事業」に参画 出典:杉原健司『アジャイル開発との出会いで始まった地方の変化、そして未来 〜島根編〜』 https://2020.agilejapan.jp/pdf/DAY1_CH2_1330.pdf Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 型が広がったその先で、問いが聞こえなくなった 4
非日常の日常があった アジャイルコーチに「アジャイル開発」をゼロから学び、体験する • よりよいものを一緒に考える仕掛け • よりよいものを一緒につくろうとする姿勢 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 型が広がったその先で、問いが聞こえなくなった 5
非日常が終わり、 受託開発や SIer という環境、限られた裁量の日常 スクラムとは程遠い現実 ロールに頼らず、 自分がいるチームの中ではじめる Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 型が広がったその先で、問いが聞こえなくなった 6
自分にできることを重ねてきた 当時は模造紙やプラスチック段ボール(プラダン)に付箋を貼る“アナログ”な やり方を含めて、さまざまな小さな実践を試していた。 その中の一部を挙げると—— • タスクボード:タスクを付箋で可視化。Done に移す瞬間を チームで共有し、自然な声かけが生まれた。 • ふりかえり(KPT):スプリントごとに付箋で実施。自分た ちで決めたことを次に試し、「変えていいんだ」という感 覚が芽生えた。 • ユーザーストーリーマッピング:付箋で全体像と進捗を可 視化。「済」の付箋が増える達成感を共有し、機能だけで はなく“ユーザー”を語れるようになった。 どの実践も理想や本来の形からは外れていた 与えられた環境でできることには限りがあった それでも小さく始め、問い続けることで、 仲間と変化を感じながら、一歩ずつ進んでいけた Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 型が広がったその先で、問いが聞こえなくなった 7
影響が少しずつ広がり 周囲にアジャイル開発のプロジェクトが増えていく 2020年から 他チームのチーム改善やアジャイル開発の支援に関わる Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 型が広がったその先で、問いが聞こえなくなった 8
はじめは“やること”が先行する それは自然なこと 新しいチームが誕生し、 既存チームのやり方を真似ることからはじまった Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 型が広がったその先で、問いが聞こえなくなった 9
“問いの空白” 「なぜやるのか?」が 語られないまま継続 「やることをやっている」 という安心感と満足感 問いや学びが 失われていく危うさ Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 型が広がったその先で、問いが聞こえなくなった 10
ただの感覚ではなく、チームのセルフチェックの結果に表れていた チームのセルフチェック 吉羽龍太郎(@ryuzee)さんが作った「スクラムチーム用セルフチェック リスト」を参考に、チーム内で対話するために活用している。 スクラムに関する10の観点があり、それぞれに10の質問がある。 (合計100問のセルフチェックリスト) 私たちの集計方法 チームメンバー全員が各質問に Yes/No で回答し、Yes の割合をチームの値 としている。 例:5人中4人が Yes → 80% スプリントごとにセルフチェックし、チームの結果を可視化している。 ちなみに、 スクラムチームのセルフチェックも最初に取り組んだチームから広がった 一例である。 吉羽龍太郎(@ryuzee)『スクラムチーム用セルフチェックリスト』 https://www.ryuzee.com/contents/blog/14561 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 型が広がったその先で、問いが聞こえなくなった 11
セルフチェックの結果でチーム間を比較して優劣をつけてはならない。 チームの特徴を知った上で結果からわかることがある。 3チーム(チームA, B, C)を対象に1スプリントの結果を選定し、考察する。 なお、各チームは他のスプリントの結果でも同様の傾向があることを確認済み。 特徴 セルフ チェック 回答数 セルフチェック 結果の傾向と考察 チームA Sprint#153 メンバーの入れ替わりはあるが、6年以上スクラム を実践しているチーム。 5 凹凸がある。 成熟して自己評価が厳しい。 チームB Sprint#13 1年未満のチームであり、スクラム初心者のメン バーがチームAの取り組みを真似て活動している。 5 Yes割合が高い。 型を真似てYesが多い。 チームC Sprint#8 立ち上げて約半年が経過したチーム。 チームの規模が大きく、チームの3分の1はスクラム 経験者(チームAを離任したメンバー)。 12 Yes割合は中間。 意図を理解しつつ実施。 チーム 選定スプリント* * 3チームとも1スプリントを2週間としている 数値は高ければよいというものではない。型や真似でYesが増えることもあり、そのとき問いが見え なくなる危うさがある。 セルフチェックの10の観点のうち、特に「プロダクトオーナー」「デイリースクラム」「スクラム マスター」の3つに注目して見ていく。 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 型が広がったその先で、問いが聞こえなくなった 12
プロダクトオーナー 5-1 プロダクトオーナーが明示的に1人いる 5-2 プロダクトオーナーの意思決定はステークホルダーから十分尊重されてい る 5-3 プロダクトゴールやプロダクトビジョンを明確にしている 5-4 プロダクトゴールやプロダクトビジョンを繰り返しスクラムチームに説明 している 5-5 プロダクトゴールやプロダクトビジョンを繰り返しステークホルダーに説 明している 5-6 プロダクトバックログの管理を行っている 5-7 プロダクトバックログアイテムの並び順の最終判断をしている 5-8 開発したものが完成しているかどうかを判断している 5-9 プロダクトに関する情報をステークホルダーやスクラムチームに公開して いる 5-10 WHATとWHYに注力し、HOWは開発者を信頼して任せている 出典:吉羽龍太郎(@ryuzee)『スクラムチーム用セルフチェックリスト』 https://www.ryuzee.com/contents/blog/14561 チームAとチームCはYes割合に凸凹がある。一方 で、チームBは満点。 型や真似でYesが積み上がると、意図や価値への問いが薄れ、実態以上に“できてい る”かのような安心感を生み、対話が深まらない危うさを含んでいるように見える。 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 型が広がったその先で、問いが聞こえなくなった 13
デイリースクラム 2-1 デイリースクラムを毎日実施している 2-2 15分のタイムボックスを守っている 2-3 開発者が中心となって自律的に運営している 2-4 必要に応じて参加者は最新の状況を話せるように準備している 2-5 スプリントゴール達成の可能性を検査している 2-6 次の1日分の計画を最新化している 2-7 デイリースクラム以外でも必要に応じて頻繁に話し合っている 2-8 スクラムマスターや特定の誰かに向けて報告していない 2-9 再計画や詳細な調整が必要な場合、速やかに別の会議等を用意している 2-10 進め方を適宜改善している 出典:吉羽龍太郎(@ryuzee)『スクラムチーム用セルフチェックリスト』 https://www.ryuzee.com/contents/blog/14561 チームAとチームBはいずれも高得点。ただし、 チームBの得点の高さが「問いや学びの深さ」を 示すとは限らない。また、チームCはYes割合に ばらつきがある。 Yesが多くても、ゴール検査や改善の問いが置き去りになり、『やっているから大 丈夫』という満足にとどまり、学びが止まる危うさが潜んでいる可能性がある。 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 型が広がったその先で、問いが聞こえなくなった 14
スクラムマスター 7-1 スクラムマスターとしてふるまう人が1人いる 7-2 スクラムチームがタイムボックスを守れるようにしている 7-3 スクラムチームやステークホルダーにスクラムの教育を行っている 7-4 必要に応じてイベントのファシリテーションを行っている 7-5 スクラムチームが権限を持てるよう組織への働きかけを行っている 7-6 プロダクトオーナーを支援している 7-7 開発者を支援している 7-8 スクラムチームの進捗を妨げる障害物を排除するように働きかける 7-9 タスクをアサインしたり進ちょくを管理したりしていない 7-10 スクラムチームを観察し、意図的に何もしない 出典:吉羽龍太郎(@ryuzee)『スクラムチーム用セルフチェックリスト』 https://www.ryuzee.com/contents/blog/14561 チームAとチームCは、スクラムマスターと他の 観点(例:「プロダクトオーナー」や「デイ リースクラム」)の結果の傾向がそろっている。 一方で、チームBはスクラムマスターの結果が目 立って低いのに、他の観点では高得点。 スクラムマスターが低い一方で他の観点が高いという結果は、『やっているから Yes』と形式的に答えている可能性を示している。問いが生まれていないまま型や 真似に従い、やり方の形だけが残る危うさが表れているように見える。 Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 型が広がったその先で、問いが聞こえなくなった 15
Yesの数では測れないこと • Yes割合が高いこと自体は悪いことではない • しかし、型に従い真似るだけでもYes割合は高くなる • 問いがなければ、その結果に疑問を持てず、安心や満足に とどまり、改善の機会を見失う危うさにもなる 問いが実践を育てる • 大切なのは、Yes割合の結果をどう受け止めるか • 「なぜやるのか?」「どうすれば良くなるのか?」という 問いを持つことで、チームの考え方が変わり、それが日々 の行動や活動の変化につながり、さらにセルフチェックリ ストの答え方やチームのあり方にまで影響していく • 複数のチームの数値を比較して優劣をつけてはならない 3チームの比較は、その無意味さと危うさを物語っている Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 型が広がったその先で、問いが聞こえなくなった 16
日常の外で問いに出会う 外の実践や学びに触れることで視野が広がる 自分の現場に違和感を覚え、問いに気づくきっかけになる 外に触れ、広がりを得て、自分の現場を見直す Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 型が広がったその先で、問いが聞こえなくなった 17
問いを手放さず、歩み続ける 問いを問いとして生かすには 現場に根ざした実践を続けることが必要 日々の実践に宿る情熱や想いがあるとき、問いは生き続ける それらを失えば、やること自体が目的となってしまう 日常を離れることで、視野が広がり、新しい気づきに出会えることもある Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 型が広がったその先で、問いが聞こえなくなった 18
やり方を真似るだけでは、意味は育たない 型が広がったその先で、問いが聞こえなくなった ——問いがあるから実践になる Copyright 2025 Techno Project Japan Co. 型が広がったその先で、問いが聞こえなくなった 19