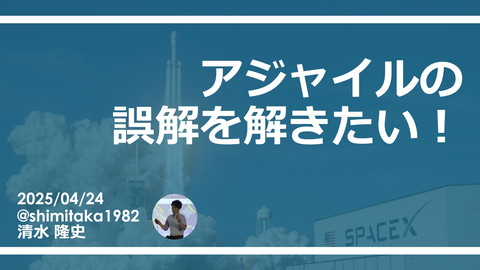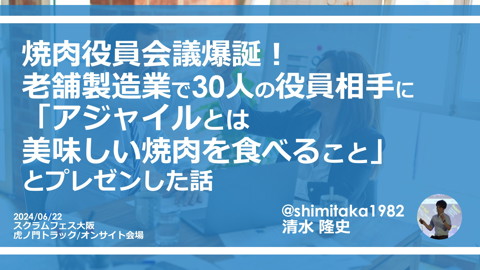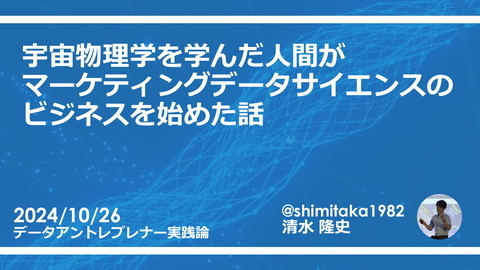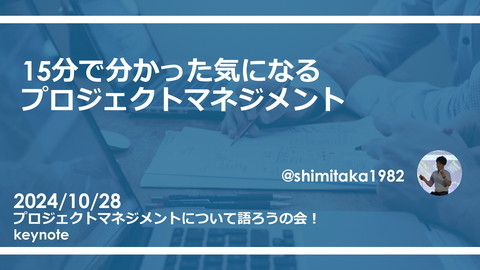「学習する組織」を読み解くー自らの経験と考察も添えてー
0.9K Views
October 13, 25
スライド概要
(AIによる要約)
この資料は、ピーター・センゲらによる「学習する組織」の概念を、自身の経験と照らし合わせながら読み解いた内容です。学習する組織とは、目的達成に向けて集団の意識と能力を継続的に高める組織であり、個人の成長と組織の価値創出を目指します。変化への抵抗や情報の欠落・劣化・タイムラグといった課題を乗り越えるために、システム思考や5つのディシプリン(自己マスタリー、メンタル・モデル、共有ビジョン、チーム学習、システム思考)が重要とされます。「ビールゲーム」などの体験を通じて、全体視点の必要性や内省の重要性を実感し、今後は認知行動療法やU理論も学びたいと締めくくっています。
アジャイル/スクラム/データサイエンス/プロダクトマネジメント/プロジェクトマネジメント/組織論など、日々の学びをスライドにします。
関連スライド
各ページのテキスト
「学習する組織」 を読み解く ー自らの経験と考察も添えてー 2025/10/13 清水 隆史 @shimitaka
はじめに
参考にした書籍 『学習する組織』の原典、入門書、マンガの3点を 参考にしています 原典 学習する組織――システム思考で未来を創造する https://amzn.asia/d/3wfN52w 入門 「学習する組織」入門――自分・チーム・会社が 変わる 持続的成長の技術と実践 https://amzn.asia/d/7EUmkE5 マンガ マンガでやさしくわかる学習する組織 https://amzn.asia/d/i4fdgj7
今回の経緯と動機 直接的なきっかけはKindleの199円フェアで『学習する 組織』のマンガ版を購入したこと(笑)それ以前から入 門書を読んではいたが、読んだだけになっていた 企業で活動をしていて我々は学習する組織になれている のか?という漠然とした課題感があった 改めて学習する組織とは何か、自分に何が 出来るのかを、自分自身の経験や試行錯誤に 照らし合わせながら思考してみることにした 私の経験と考察
学習する組織 とは
学習する組織とは 入門 学習する組織(ラーニング・オーガニゼーション)は、 MIT(マサチューセッツ工科大学)のピーター・センゲ や行動科学の大家クリス・アージリス(ハーバード大) らが生み出し普及させた概念であり、理論・手法体系 ナイキ、ユニリーバ、インテル、VISA、世界銀行、日産、 リクルート、JICA(国際協力機構)など多くの企業・組 織に取り入れられてきた ※以降、書籍を表現する場合は『』で表記
学習する組織とは 目的に向けて効果的に行動するために集団としての意識 と能力を継続的に高め、伸ばし続ける組織 入門 組織と個人が目的を効果的に達成するための集団として の意識と能力を高め続けることによって、 ✓社員一人ひとりのやる気と潜在的な力を引き出し、成長を促す ✓職場をより働きやすく生産的な場にする ✓会社が社内外の人たちにとって高い価値を創り出し、必要とされ続ける ことを目指す マンガ
この定義に照らし合わせて、 あなたのいる組織 (職場、チーム、部署、会社など)は 学習する組織と いえるでしょうか? 入門
さらに問い あなたの組織は、 ✓目的の達成に向けて前進しているでしょうか? ✓目的に至るための個々の目標はクリアできているでしょうか? ✓自分や組織の能力と意識が目的達成のために十分なものであるかを 振り替えっていますか? ✓能力や意識を高める努力をしていますか? ✓現実に組織メンバーや組織の能力と意識は 高まっているでしょうか? 入門
私の場合 私の経験と考察 (例)宇宙開発系システム開発プロジェクトの プロジェクトマネージャの時 ✓仕様に応じていかに効率的にシステムを開発するかをずっと考えていた ✓そのためにメンバー(外注含む)にどう仕事を割り振れば効率的に仕事 が進むかをずっと考えていた(パズルゲームのような感じ) ✓プロジェクトチームでよく勉強会をやっていた (デザインパターンとか) ✓実際にメンバーのやる気と潜在的な力を引き出して成長を促せていたか というと、正直よく分からない ✓よりよい業務プロセスを提案すると関連部門や関連会社に抵抗された (当時はまだ若かったので「それが日本という国か」と諦めた)
なぜ人は 変化に 抵抗するのか
人は変化に抵抗する マンガ 慣れ親しんだ自分たちの行動パターンを変えることは 心理的にも負担が大きい 変化した状態について、どのようなメリットが生じるの かが分からないことも多い 変わることのメリットよりもデメリットの実感が大きく、 不安や恐れが変化への抵抗につながる 人は変えられることに抵抗する傾向が強くある
(参考)プロスペクト理論 私が思い出した こと 損失回避性:人は利益を得る喜びよりも損する苦痛を より強く感じるという行動経済学の考え方 価値+ 5万円を貰ったときの嬉しさ:+100 2.25倍 損失 利得 5万円を失ったときの嬉しさ:-225 価値- 現状維持バイアスにも繋がる 損したく ない!
組織の成功循環サイクル 関係性の質 視野が狭まる ② 結果の質 マンガ ①業績の不調など結果がよくないとき、 しばしば関係性の質の悪化を招く ① ④ Bad サイクル涙 思考の質 自分はやるべきことをやっている。 問題が起こっているのは 他の誰か(部署・会社)の責任だ! ②ひどいときには互いに話し合うのがムダ にしか思えない状況になる。そして他者の 視点が入らず、自分の見えている範囲だけ で考え思考の質が悪化する ③そうした思考から生じる行動の質は低く、 ムダや混乱を引き起こす ③ 行動の質 ④そうした行動からはよい結果の質は望めない ①’そして関係性の質がさらに悪化して・・・ 『学習する組織』著者のピーター・センゲと成功循環サイクルを示したダニエル・キムは MIT時代の同僚で、数多くの組織で組織開発のファシリテーションを行っていたそう
組織の成功循環サイクル 関係性の質 視野が広がる ② 結果の質 マンガ ①チームの関係性を強化できれば、質の 高いコミュニケーションが可能になり、 視野が広がる ① ④ Good サイクル嬉 思考の質 こういう課題があるんですね! 教えていただき ありがとうございます! ②より視野の広い、さまざまな可能性に開かれ た思考が生まれる ③効果的な行動を積み重ねる ④結果の質が高まる ③ 行動の質 ①’さらに関係性の質が高まる好循環へ!
ビールゲームと システム思考
ビールゲームとは MITで開発されたビジネスゲーム ビール工場のサプライチェーンを疑似的に体験する 各工程(工場、一次卸、二次卸、小売店)の役割を 分担してプレイする 参加者は在庫・欠品コストの最適化を目指す 体験を通じてプレイヤーの内側にある 思考の質や行動の質についての気付きを誘発し、 能力を強化する マンガ
ビールゲームとは 製造工場 卸売 小売店 消費者 大量の注文を受け さらなる増産 需要増を見込み さらに多く発注 欠品を恐れ 少し多めに発注 ビールの需要が 少しだけ増える 供給:大 タイムラグがある 過剰在庫が発生 需要:小
ビールゲームとは 製造工場 卸売 小売店 消費者 なんや事情は 大量の注文を受け 知らんけど さらなる増産 なんや事情は 需要増を見込み 知らんけど さらに多く発注 なんや事情は 欠品を恐れ 知らんけど 少し多めに発注 なんや事情は ビールの需要が 知らんけど 少しだけ増える 供給:大 タイムラグがある 過剰在庫が発生 需要:小
ここまで来るのは だいぶ時間が経ってから (数年とか) 私の場合 (例)人材不足 情報の欠落 情報の劣化 が起こっていた タイムラグ 研修企画担当 研修企画 しよう! 問題が抽象化されすぎ 自分に返ってくることも 育成委員会 作るか 人材教育が 必要だ! 私の経験と考察 人材不足は 深刻だなぁ 採用は今 厳しくて… 人が足りない らしい システムアーキテクトを 考えられる人がいない!
私の場合 ここまで来るのは だいぶ時間が経ってから (数年とか) (例)人材不足 みんな他の組織・人の 情報の欠落 都合はあまり考えられて 情報の劣化 いなかったかも? が起こっていた 私の経験と考察 人材不足は 深刻だなぁ なんや事情は 知らんけど 採用は今 タイムラグ 厳しくて… なんや事情は なんや事情は 知らんけど 人が足りない 知らんけど なんや事情は 育成委員会 らしい 研修企画 なんや事情は 作るか 知らんけど なんや事情は 研修企画担当 しよう! 知らんけど 知らんけど 人材教育が システムアーキテクトを 問題が抽象化されすぎ 自分に返ってくることも 必要だ! 考えられる人がいない! なんや事情は なんや事情は
ビールゲームの教訓 自分の思考と行動が他者に影響を与える それがやがて巡り巡って自分に戻ってくる このように互いに影響を与え合う集合体がシステム システムの中で生じたトラブルを打破するためには 全体を見ることが大切 マンガ これが システム思考
システム思考とは 学習する組織の5つのディシプリンのうちの1つ 構造がパターンに影響を与える 個々の行動の背景にある、問題となっている現象を起 こりやすくしている構造に目を向ける必要がある 入門 組織内の多くの人たちが効果的な学習ができていない とき、学習を阻害するパターンは組織の構造によって もたらされる マンガ
論理的思考とシステム思考 マンガ では論理的思考とシステム思考を対比して紹介 論理的思考 ※どちらか一方が正しいというわけでは なく、状況や課題に応じて使い分ける システム思考 原因 短期的かつ効率的に 問題解決を図ろうとする (西洋医学的な対処) 長期的に病気にならない 状態を生み出そうとする (東洋医学的な対処) 問題 問題にははっきりした原因がひとつあって、 それを突き詰めて解消すれば解決する、という考え方 問題がシンプルなら論理的思考の方が適している 色々な要素をはらんだ範囲の広い複雑な問題や 答えがひとつではなく適応を必要とする場合は システム思考の方が適している
5つの ディシプリン
5つのディシプリン 『学習する組織』の英題はThe Fifth Discipline : The Art & Practice of The Learning Organization 3本脚の椅子がメタファー チームの中核的な (どれが欠けてもダメ) 学習能力 システム思考だけで 複雑性の理解 志の育成 ⚫ システム思考 原典 第Ⅱ部まるまる ⚫⚫ 自己マスタリー 共有ビジョン (他の4つは第Ⅲ部に マンガ 共創的な対話 まとめられている) 入門 ⚫ メンタル・モデル ⚫ チーム学習
(参考)『学習する組織』目次 複雑性の理解 志の育成 「学習する組織――システム思考で未来を創造する:英治出版」より抜粋 https://eijipress.co.jp/products/2101 共創的な対話
(参考)デミング博士との関係 原典 冒頭の「改訂版によせて」でデミング博士との逸話が 書かれている(センゲが旧版の推薦文を依頼) 当時デミング博士は「総合的品質管理(TQM)」とい う用語をほとんど使わなくなっており、短期的な業績 改善を求める経営者を批判し「深遠なる知識」の必要 性を説いていた その「深遠なる知識」の要素が 5つのディシプリンに繋がった
(参考)デミング博士との関係 原典 デミング博士はマネジメントと教育の一般的体系は同 様と考えのちにセンゲが以下の8つに要素化 ✓評価によるマネジメント(「大事なことのうち測ることができるのは たった3%である」-デミング博士) ✓追従を基盤にした文化(恐怖によるマネジメント) ✓結果の管理(経営陣が目標を設定し社員はその達成責任を負う) ✓「正しい答え」対「誤った答え」(意見の分かれる問題は軽視) ✓画一性(対立は表面的な調和の為に抑制される) ✓予測とコントロールが可能であること ✓過剰な競争と不信(「私たちは競争によって裏切られてきた」 -同) ✓全体性の喪失(断片化)
共創的な対話 2つのディシプリン マンガ メンタル・モデル ✓個人レベル ✓内省を通じて学習を阻害するメンタルモデルへの気づきを促す ✓「保留する」という技術により探究と行動の質を高め、的確な選択を 意識的に行えるようにする チーム学習 ✓組織レベル ✓グループで探究、考察、内省を行う ✓自分たちの意識と能力を共同で高めるプロセスの実践に取り組む
志の育成 2つのディシプリン マンガ 自己マスタリー ✓個人レベル ✓継続的に個人のビジョンを明確にし、それを深めることであり、エネ ルギーを集中させること、忍耐力を身に付けること、そして、現実を 客観的に見ること 共有ビジョン ✓組織レベル ✓私たちが創り出そうとする未来の共通像であり、組織全体で深く共有 されるようになる目標、価値観、使命
学習する組織に なるためには?
組織はなぜ学習しないのか? アリー・デ・グース*の研究によれば経営者やマネ ジャーは多くの場合自分の理解している範囲で合理的 な推論を行っている どんなに合理的に考えたとしても、そもそも視野が狭 かったり、思考のパターンにバイアスがかかっていた りすると、一見合理的な意思決定が戦略上の失敗を生 み出す 入門 限定合理性 *ピーター・センゲと共に組織学習協会を立ち上げた ハーバート・サイモン (1978年・ノーベル経済学賞)
限定合理性とメンタル・モデル 私たちの認知はごく限られ ている 経験によって培われた認知 や行動の前提は、検証される ことが少ない(自分自身の無 知を認める恐怖から) メンタル・モデル:頭の中 にある現実を模したモデルで あり思考や行動の前提となる 入門 認知の範囲 メンタル・ モデル この中でだけ合理的 ≒限定合理性
ここまで来るのは だいぶ時間が経ってから (数年とか) 私の場合 (例)人材不足 みんな認知できる限られた 情報の欠落 範囲の中では合理的に思考 し行動していたのかも? 情報の劣化 が起こっていた タイムラグ 研修企画担当 研修企画 しよう! 問題が抽象化されすぎ 自分に返ってくることも 育成委員会 作るか 人材教育が 必要だ! 私の経験と考察 人材不足は 深刻だなぁ 採用は今 厳しくて… 人が足りない らしい システムアーキテクトを 考えられる人がいない!
所詮、手際良く解ける入試問題という箱庭の中 でしか生きていけない解答に過ぎないんだ… 【ガチ】数学ヤクザによる接点t 荻野先生 / プレスル先生 https://youtu.be/3rQcY_L4YqA?si=2PjhepuoChfSBR4a
メンタル・モデルの功罪 マンガ 無意識のうちに結論を下すことは、過去の学習の成果 でもあり、効率的に行動できるという側面もある だが、その代償として人や状況に対して勝手に解釈し、 決めつけ、ステレオタイプに従って行動する、という ことも起こりうる さらに、自分の見方を他人へ「分からせよう」とする 危険性もある 新しい学習を阻む
メンタル・モデルの上手な対処 内省の習慣とスキルを身に付ける ✓自分の内側について省みる ✓自身の体験や行動と関連する思考、感情を じっくりと見つめる 「推論のはしご」をゆっくりと登る ✓行動、発言、判断が飛躍していないかを省みる マンガ 行動する 結論を出す 仮説を立てる データの 意味付け 相手も観察可能 なデータ
私の場合 人それぞれに 「認知」がある 私の経験と考察 認知 会議の録画を見返した 私自身のクセに気付いた 認知 認知 事実 ✓たまに論理飛躍がある (おそらく自分の頭の中では論理が繋がって いるが、表出化された言葉だけをみると論理飛躍がある) ✓たまに事実と認知を混ぜて語っている 1つだけ 自分が喋っている会議の録画を見直すのは気恥ずかし いが敢えてやってみると新しい発見があった
学習する組織への道 原典 本書にある他責思考や縦割り意識、当事者意識の欠如な どのさまざまな学習障害は、程度の違いこそあれほとん どの組織に見受けられる。 簡単な課題ではなく、一朝一夕には解決しない。 「学習する組織」を構築できる特効薬などありはしない 「学習する組織」づくりは長い年月に及ぶ実践の積み重 ねが必要であり、しばしば職業人生をかける
とはいえ、戦略はある 原典 学習と仕事を一体化させる ✓しばしば、学習は学習、仕事は仕事と分けて考えられるが、仕事の中に 学習する時間(振り返り)を敢えて取る そこにいる人たちとともに、自分のいる場所から始める ✓“いちいち経営陣が後押ししてくれるのをただぼんやりと待っていたら、 長い間待つことになるでしょう” 二つの文化を併せもつ ✓学習志向の世界と、より伝統的な世界、それぞれの基本原則を尊重する 練習の場を創る
ということで、 「学習する組織」になるための 直接的な答えは書いていない まずは自分の出来るところから 始めてみよう!
学習する組織になるために 私が意識してみたいこと システム全体のことを 考える ビジョンを明確にする 内省や対話を大切にし 先入観(クセ)を 自覚する 相互に学び合う場を つくる 私の経験と考察
まとめ
まとめ 『学習する組織』の原典・入門書・マンガの3冊を起 点に自分の経験も含めて思考を深めた 組織では情報の欠落・劣化・タイムラグが起こる システム思考が大事 5つのディシプリン:システム思考、メンタル・モデ ル、チーム学習、自己マスタリー、共有ビジョン) 内省や対話を大切にし、相互に学び合う場をつくろう
今後に向けて 今回まとめられたのは『学習する組織』のエッセンス の一部であり全体のほんのわずか 読み応えのある本なので(原典は600ページ近い!) じっくりと読んでもう少し自身の経験との整合をとっ て今後の取り組みを考えていきたい 認知行動療法やU理論についても関連しそうなので、 併せて学習を進めていきたい(これもKindle199円セー ルで知った笑)。人と組織の力学にも興味が湧いた。
興味を持って今読んでる本 マンガでやさしくわかる認知行動療法 https://amzn.asia/d/30O3855 マンガでやさしくわかるU理論 https://amzn.asia/d/2M16f2a だけどチームがワークしない ――“集団心理”か ら読み解く 残念な職場から一流のチームまで https://amzn.asia/d/6wsJ5xe
興味を持って今読んでる本 チームレジリエンス 困難と不確実性に強いチー ムのつくり方 https://amzn.asia/d/h9cGI9R なぜ人と組織は変われないのか ― ハーバード流 自己変革の理論と実践 https://amzn.asia/d/6qsnr9N 企業変革のジレンマ 「構造的無能化」はなぜ起 きるのか (日本経済新聞出版) https://amzn.asia/d/33X6V4L
Thank you for your attention !!