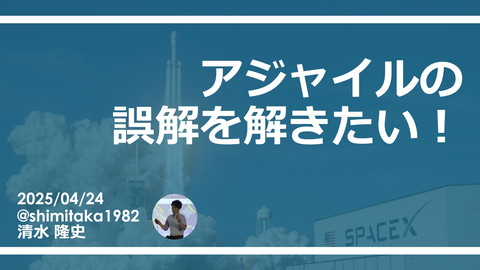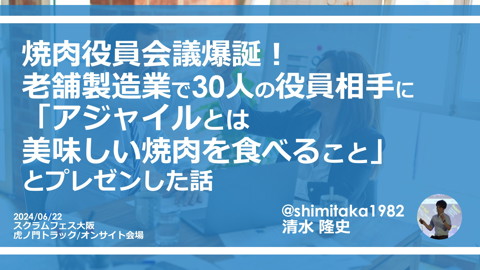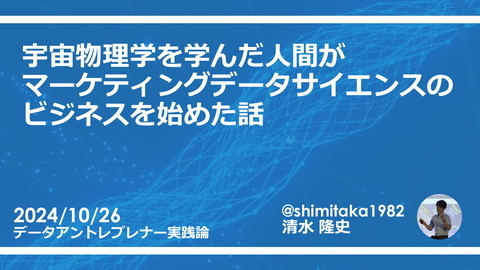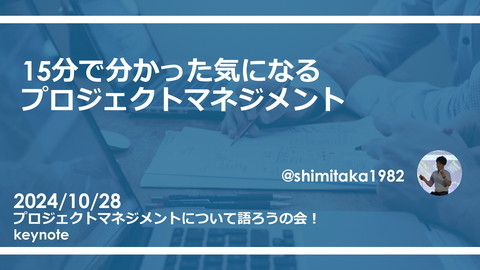自己組織化とはなにかを科学的に捉えて自ら動き出すチームの条件を3つ考えてみた
2.2K Views
July 07, 25
スライド概要
(生成AIによる要約)
本資料は、自己組織化の科学的背景とビジネスへの応用を解説し、自律的に動くチームを実現するための3条件(①開放系、②非平衡状態、③ポジティブ・フィードバック)を提示しています。VUCA時代における階層型組織の限界を踏まえ、変化に強いチームづくりのヒントを提供します。
アジャイル/スクラム/データサイエンス/プロダクトマネジメント/プロジェクトマネジメント/組織論など、日々の学びをスライドにします。
関連スライド
各ページのテキスト
自己組織化とはなにかを科学的に 捉えて自ら動き出すチーム の条件を3つ考えてみた 2025/07/07 @shimitaka1982 清水 隆史
本スライドを見ていただきたい方 自己組織化という言葉をたまに聞くが どういうことかいまいちよく分かっていない方 そもそも自己組織化とは何なのか? なぜその考え方が必要なのか? どのように身に付けていけばよいのか? 仕事にどのように生かしていけばよいのか?
本スライドのアウトカム * 自己組織化とは何なのか(What)を理解できます なぜ(Why)自己組織化が大事なのかを理解できます どのように(How)自己組織化していけばよいのかが イメージできます 日々の仕事をよくするために今日から始められることを お持ち帰りいただけます *アウトカム(outcome):このスライドを読むことによってみなさんが得られるもののこと
自己紹介 清水隆史(shimitaka) 専攻は宇宙物理学 専門はプロジェクトマネジメント 【資格】情報処理技術者試験プロジェクトマネージャ、 PMP®、CSP-SM、A-CSPO等 オンライン学習プラットフォーム「Udemy」講師 ✓【2025年最新版】PMP®はじめの一歩!国際的なプロジェクトマネジメン ト資格の学習項目や具体例を講義形式で徹底解説!
What 自己組織化とは なにか?
自己組織化とは? 生成AIに 聞いてみました! 自己組織化とは、外部からの指示や制御がなくても、 システムを構成する要素同士の相互作用によって、 秩序や構造が自律的に形成される現象です。 生物、化学、物理、社会など、様々な分野で見られます。 例 ✓生物:雪の結晶、細胞のネットワーク、ウイルスの殻など ✓化学:液晶、分子集合体、金属錯体など ✓社会:金融市場、交通渋滞、群衆行動など
なるほど よく分からん
自己組織化とは? もう少し よく読んでみよう! 自己組織化とは、外部からの指示や制御がなくても、 システムを構成する要素同士の相互作用によって、 秩序や構造が自律的に形成される現象です。 生物、化学、物理、社会など、様々な分野で見られます。 例 秩序が自律的に形成される、 というところがポイント ✓生物:雪の結晶、細胞のネットワーク、ウイルスの殻など のようだ ✓化学:液晶、分子集合体、金属錯体など ✓社会:金融市場、交通渋滞、群衆行動など
イメージ 要素 キャーキャー! ワーワー! ピシッ! ・・・ ワーワー! キャーキャー! ・・・ いわゆるランダムな状態 なんか知らんけど 要素同士で 相互作用が起こる なんか知らんけど 秩序化・構造化される
科学界でも出てくる 化学・生物学でよく出てくる ちなみに私の専攻である宇宙物 理学でも宇宙にある銀河はいわ ゆる”自己組織化”によって形成 される、という考え方があるら しい [出典]自己重力多体系での非線形現象と自己組織化 https://www.jstage.jst.go.jp/article/japannctam/61/0/61_0_44/_pdf
ソフトウェア開発界でも出てくる 「アジャイル宣言の背後にある原則」には 「自己組織的なチーム」という用語が出てくる [出典]アジャイル宣言の背後にある原則 https://agilemanifesto.org/iso/ja/principles.html
(参考)エントロピーとの関係 熱力学第二法則(エントロピー*増大の法則) ✓孤立系のエントロピー*は増大する(より無秩序な)方向へと向かう ✓(例)放っておくと部屋の温度は一定になる 系は自然とどんどん揺らぎがない状態 (柔軟性や変化能力がない状態)へと向かう。 これを平衡状態(熱的死)という。 一見すると自己組織化と矛盾しているように見えるが、 熱力学第二法則の枠組みの中で局所的に秩序化を実現し ているのが自己組織化だともいえる *エントロピー:乱れている状態やカオス度を表す熱力学の概念
ここまでのまとめ 「自己組織化」はもともとは科学用語 転じて、社会やビジネス(ソフトウェア開発界など) においても用いられるようになった 秩序や構造が自律的に形成される現象 自然界は放っておくとエントロピー増大の法則に則り 柔軟性や変化能力を失い平衡状態(熱的死)に向かう 自己組織化はある意味それに抗う現象
Why なぜ自己組織化が 重要なのか?
環境の変化 VUCAの時代 変化が激しく、不確実で、複雑 性が高く、曖昧な世の中 仕事においても情報量が加速度 的に増大している このような状態では今までのよ うな仕事のやり方・考え方では うまくいかない V 変動性 U 不確実性 C 複雑性 A 曖昧性
階層型組織の限界 従来の階層型組織(ヒエラルキー)では、 トップの人間が情報を集約し、 経営 戦略を構築し、現場に展開してきた (その方が効率的だったから) だが現代は、情報が極めて増大・ 多様化し、戦略の構築と組織の 統制が極めて困難になった 管理職 一般職
ここで出てくるのが 自己組織化
自己組織型組織を目指すようになってきた 情報を組織全体で共有 現場が権限を持つ 情報・権限を 与える 自律的に動く 変化に素早く対応する これってつまり 自己組織化だよね 制御・指示が 無くても動ける
素朴な疑問 自己組織化出来たら嬉しいのは分かったけど、 どうすれば自己組織化できるの?? そこが 知りたいのよ
ここまでのまとめ VUCAの時代、階層型組織は限界を迎えつつある 情報を共有し現場が権限を持ち自律的に動くことで、 変化に素早く対応できる組織が出来る 世界をそれは自己組織化と呼ぶんだぜ
How どうしたら 自己組織化 できるのか?
散逸構造論から読み解いてみる 自然界(科学の世界)を考えてみよう イリヤ・プリゴジン氏の散逸構造論が参考になりそう (1977年にノーベル化学賞を受賞) 散逸構造 ✓エネルギーが散逸する過程で、自己組織化によって形成される定常的 な構造(例:雲や台風の発生) 散逸構造(≒自己組織化)が生じる3つの条件 ✓1.開放系であること ✓2.非平衡状態であること ✓3.ポジティブ・フィードバックが存在すること
1.開放系であること 外部からエネルギーや物質の出入りがある状態 閉じられた系では、エントロピーが増大し、秩序が 失われるため、自己組織化は起こりにくい ビジネスシーンで 解釈すると 系 ✓オープンマインド ✓多様な人・チームと交流しよう ✓情報や人が入ってきやすい環境を整えよう
(参考)知識創造理論 野中郁次郎先生の「知識創造理論」 でも、知識が生まれる「場」の条件 として 「場」の境界は開閉自在でつねに 動いていること が挙げられている [出典]知識創造企業(新装版) https://amzn.asia/d/goB45YG
2.非平衡状態であること 外部からのエネルギーや物質の流入により、 系が平衡状態から離れている状態を指す 平衡状態では、熱力学的な安定性が高いため、自己組 織化は起こりにくい ビジネスシーンで 解釈すると ✓混乱や対立や変化を恐れないようにしよう ✓悪い意味で安定していないか?自問自答しよう ✓問いかけや対話により”ゆらぎ”を与えよう 系
3.ポジティブ・フィードバック ある状態が変化する際に、その変化をさらに促進する 方向に働くフィードバックが存在すること これにより特定のパターンが形成されやすくなる ビジネスシーンで 解釈すると ✓他者からのフィードバックを大切にしよう ✓ふりかえりや内省をしよう ✓人・チーム・組織の変化を賞賛しよう 系
自己組織化のジレンマ 冒頭のスライドを思い出してみる 「自己組織化をしよう!」と 外部からの指示や制御をすることは 自己組織化の考え方に反する つまり、誰から言われるわけでもなく、自己組織的に 自己組織化しなければならない これを自己組織化のジレンマと名付けたい(命名:私)
そこで提案 自己組織化を 考えるな 感じろ
自己組織化を体験してみる 自己組織化をやろうとしない 頭で考えすぎるより実際に体験するといい 自己組織化の現場に行ってみよう! ✓アジャイルなイベント・チーム ✓アーティストのライブイベント ✓コミケなどの同人誌即売会 ✓スポーツチームの応援席 自分なりの自己組織化の形を 模索してみよう!
つまり Don’t just Do 自己組織化 Be 自己組織化 オマージュだよ
まとめ 自己組織化とは秩序や構造が自律的に形成される現象 VUCAの時代は階層型組織から自己組織型組織への 転換が求められる 自ら動き出すチーム(自己組織化チーム)の秘訣は、 開放系・非平衡状態・ポジティブフィードバックの3つ。 オープンマインドで変化を恐れず賞賛しよう 身近なところから自己組織化を体験して日々の仕事に 活かしていこう
最後に簡単な問い あなたのチームでは情報や権限は与えられていますか? あなたのチームでは人や情報の流動性はありますか? あなたのチームでは他者からのフィードバックを大切に できていますか? あなたのチームは平衡状態(熱的死・悪い意味での安定) に陥っていませんか? あなたのチームは自己組織化できていますか? *「チーム」を「会社」「組織」「グループ」「プロジェクト」などと置き替えても良い
(参考)ケオディックパス ケオディックパス(Chaordic Path) ✓カオス(混沌)とオーダー(秩序)の間にある(chaos + order) ✓これからの組織はカオスとオーダーの間を行き来するケイオードな組織 でなければならない、という考え方 ✓予測不能な状況や変化に対応するための概念 カオス ケオディックパス Chaordic Path オーダー
Thank You !!