未来の医工学を考える③
320 Views
February 24, 25
スライド概要
九州大学1年生約50人を1クラスとして開講している「課題協学科目」にフューチャー・デザインを導入した授業のスライド資料。③では2コマ全体で提言書の作成(第4週に実施する発表会で各班が用いるスライド資料)を実施しました。
脳の研究と教育をしています。『焚き火の脳科学』の著者。大学の必修科目の設計や全学教育マネジメント、合理的配慮申請システムの設計・開発にも携わっています。さらに「フューチャー・デザイン」を教育、人材育成、組織運営に導入する活動にも力を入れています。
関連スライド
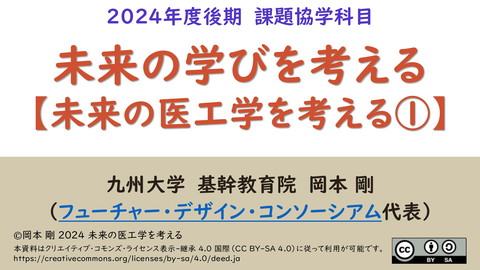
未来の医工学を考える①
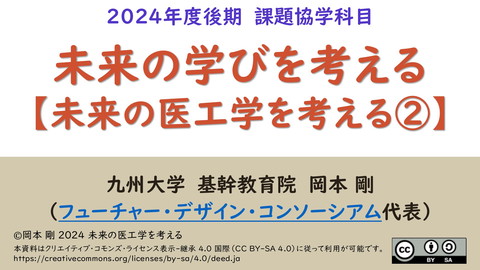
未来の医工学を考える②
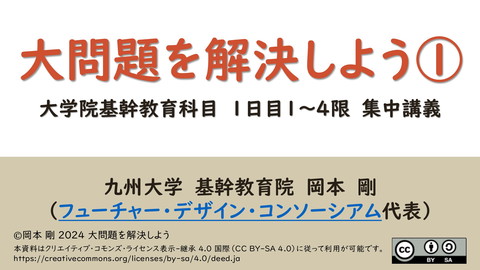
大問題を解決しよう①
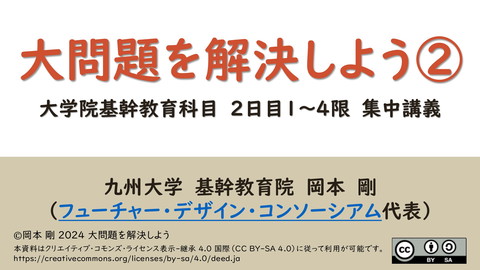
大問題を解決しよう②
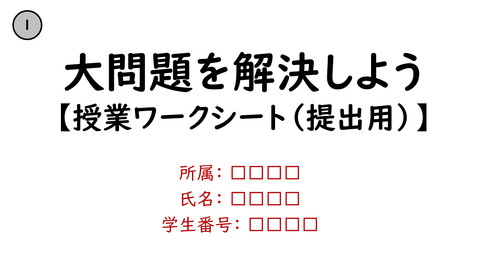
大問題を解決しようワークシート
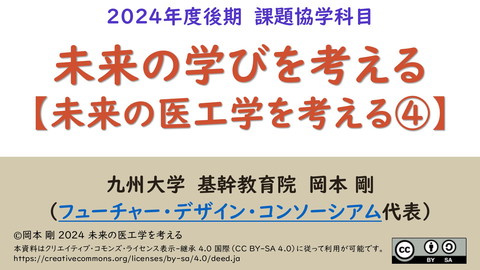
未来の医工学を考える④
各ページのテキスト
2024年度後期 課題協学科目 未来の学びを考える 【未来の医工学を考える③】 九州大学 基幹教育院 岡本 剛 (フューチャー・デザイン・コンソーシアム代表) ©岡本 剛 2024 未来の医工学を考える 本資料はクリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示-継承 4.0 国際(CC BY-SA 4.0)に従って利用が可能です。 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja
連絡事項 授業資料はMoodleからも閲覧できます 13:00~13:10
提出物 ◍ 毎週(第1~3週)出すもの ⚫ 活動報告【全員】→Moodleの課題「活動報告」 ⚫ 宿題【全員】→Moodleのフォーラム「班活動の記録と宿題」 ⚫ ホワイトボードシートの写真【記録係・第3週はなし】 →Moodleのフォーラム「班活動の記録と宿題」 ◍ 最終週(第4週)に出すもの ⚫ スコアシート(活動報告を含む)【全員】 ⚫ 発表資料【班の代表】・・・未提出だと班員全員に悪影響 ✓ グループワークは重要ですが、班の成果物やスコアシートの 評価がそのまま個人の成績になるわけではありません。 ✓ 成績には、授業態度、個人の提出物、班の提出物が反映されます。
授業の進め方 第1週(プレゼント・デザインとパスト・デザイン) ① 現在の医工学の実態を調べ共有しよう(医工学の実態調査) ② 現在世代としてこれからの医工学を考えよう (プレゼント・デザイン) ③ 過去を振り返ろう(パスト・デザインの準備) ④ 過去世代へのアクション(パスト・デザインの実施) 宿題:フューチャー・デザインのための「想像の練習」 第2週(フューチャー・デザイン) ⑤ 仮想的にタイムスリップして、50年後の「未来人」になりきる(フ ューチャー・デザイン1) ⑥ 未来人として、「未来の医工学」の理想的な姿を想像する(フュ ーチャー・デザイン2) ⑦ 未来人から現在人に対して、「未来の医工学を実現する」または 「未来の医工学を軌道修正する」ために今すべきことを提案する (フューチャー・デザイン3) ⑧ 提案の効果予想と現実的な評価をし、必要に応じて提案内容を 修正する(フューチャー・デザイン4) 未来の医工学のために「提言書」を作る! 第3週(提言書の作成) ⑨ 「未来の医工学を実現する」または「未来の医工学を軌道修正 する」ために今すべきこと、予想される効果と懸念点をスライドに まとめる。 第4週(提言書の発表) ⑩ 全ての班が提言書をプレゼンし、スコアシートに記入して学生同 士で評価する。 ⑪ プレゼント・デザインとフューチャー・デザインで思考がどのよう に変わったかをふりかえり、フューチャー・デザイン思考の効果に ついて検討する。
次回の発表スケジュール ◍ 13:00-13:10 諸連絡 ◍ 13:10-13:30 最終打合せ・リハーサル ◍ 13:30-14:30 発表(1~5班)と審査 ◍ 14:50-15:50 発表(6~10班)と審査 ◍ 15:50-16:20 資料提出・活動報告
審査について 審査のポイント(以下の項目についてそれぞれ0~5点で採点) ⚫ 説得力:メッセージが具体的で、未来からの視点として納得感がどの程度あるか。 ⚫ 独創性:解決策や視点がどれだけ新しいか。未来人としてどれだけユニークな視点か。 ⚫ 共感性:メッセージを送られた「現在人」として、どれだけ共感でき、受け入れられるか。 ⚫ プレゼン:資料の質、準備、わかりやすさ、質疑応答の的確さ ◍ 審査のやり方(発表班以外の学生全員) ⚫ スコアシートに採点・メモをして発表後に提出 ◍ 発表後の審査コメントと質問 ⚫ 審査担当班の担当者のみがコメントと質問をする ⚫ 岡本とTAがすべての発表の最後に全体にコメントをする
質疑応答で困ったときの常套句 ◍ 「いい質問ですね~!」 ⚫ 質問者を褒めて、答えを考える時間を稼ぐ。 ⚫ 学会等でこれを発する時は、大抵発表者が冷や汗をかいている。 ◍ 「素晴らしいご指摘ありがとうございます。 ぜひ前向きに検討させていただきます。」 ⚫ 良い提案をもらったときは、素直に取り入れる意思を伝える。 ⚫ ただ、全部取り入れてしまうと、自分たちの不十分さを露呈することになる。 ◍ 「正確な数字を覚えて(調べて)いないので・・・」 「担当者と確認して後で回答させていただきます」 ⚫ 苦し紛れな返答ですが、何も言えないよりはマシ。
班活動 (分担決めと資料作成) 13:10~16:05
今日やること 1. 今日の役割分担の決定 2. 来週の発表の役割分担の決定 3. 発表資料作成(発表7分+質疑応答3分) ⚫ Office365を使うとパワーポイントの共同編集が可能(九大の場合) ⚫ 他のツールを使っても可 4. 完成したらリハーサル(収録しても可) 5. 想定質問を考え、質疑応答を乗り切ろう
今日の役割分担の決定 ◍ 話し合う場面では、ファシリ(加点対象)が進行 ⚫ リーダー以外の班員の意見もしっかり拾ってください。時間管理をしっかり!! ◍ 作業する場面では、リーダー(加点対象)が指示・決断 ⚫ フォーラムに自班のトピックを作成し、今日と来週の役割分担を書こう ⚫ リーダーシップは重要ですが、一方的になりすぎないようみんなの意見を聞きながら 進めましょう ◍ 発表資料は、発表資料責任者(加点対象)が責任をもって完成さ せ、Moodleフォーラムに提出 ◍ その他の人は作業を頑張る係として貢献しましょう ◍ 全体発表はありません
来週の発表の役割分担の決定 ◍ 発表(全員でも可) ◍ 発表補助(何名でも可) ◍ 感想を言ってから質問する人(1~2名) ⚫ スコアシートは全員がつけますが、「感想を言ってから質問する人」には班を代表して 発表後に感想(審査コメント)を言ってから質問をしてもらいます。 ⚫ 1~5班が発表 → 班番号+5の班の担当者が、発表後に感想と質問 ⚫ 6~10班が発表 → 班番号-5の班の担当者が、発表後に感想と質問
共同編集のツール ◍ Office 365でPowerPointが共同編集できます ⚫ 授業時には共同編集のマニュアル参照先を記載しています ⚫ 「プレゼン 共同作業」で検索 ◍ Google スライド ◍ その他ツール
資料作成について注意すべき点 ◍ まずはキャッチーかつ内容を的確に表現するタイトルを考えよう ◍ 考えているより大きめのフォントを使い、長い文章は入れない ◍ 話す内容のメモは、「ノート」の部分に書いておこう (スマホにセリフをメモしておいて、当日見ながら話してもOK) ◍ イラストや図などを多用すると見やすい(出典明記) ◍ 生成AIにイラストを描かせても良いが、文章を書かせるのは禁止!! ◍ 余裕があれば、「付録」の資料を作っておくと良い ◍ 迷ったときはリーダーに相談!!リーダーが決断!! ◍ 発表資料責任者は責任をもって完成させMoodleに提出!!
発表資料作成(発表7分+質疑応答3分) 「未来人を経験した自分たちからの提言書」をスライド10枚程度(以下1.~6.を含めること)にまとめる (動画にして当日動画を再生しても良いが、質問には直接答えること) 1. 表紙: 内容を的確に表すキャッチーなタイトル/班の番号/メンバー氏名(全不参加の人は除く) 2. テーマ説明: 医工学に関して注目したトピックは何か 3. 未来人になって見てきた世界: 2074年の人々の暮らしと上記トピックの未来実態 4. 提言: 「未来人を経験した自分たち」から「未来人を経験していない現在の人々」へ伝えたいこと • 2074年の何を実現したいのか or 2074年の何をなかったことにしたいのか • そのために、2024年の誰(個人、病院、研究機関、自治体、厚生労働省、政府・・・)に何をリクエスト(継続 or 廃止 or 新設)するのか • ここでは理想的な提言を考えよう 5. 自己評価: 現在の人々の視点から提言を評価 • (A) そのまま受け入れ可能 or (B) 修正すれば受け入れ可能 or (C) 現実的には受け入れ不可 6. (B)や(C)の場合、提言を修正して現実的な着地点を探ろう 16:10までに完成! 事例や根拠資料は説得力を上げる。他人の著作物等は必ず出典を明記すること。
完成したら想定質問を考え、リハーサルをしよう ◍ 想定質問を考えておくことはとても重要 ◍ 本番と同じように7分計って発表練習 ⚫ 練習の量は如実に発表に出ます ⚫ ±30秒を目指そう ◍ 質疑応答の練習もしておこう
休憩は上限20分で適宜取ってください 休憩を取る人は教室の外に出てください 以下は減点対象です。 ⚫ 教室の中で遊んでいる ⚫ 教室の中で寝ている ⚫ 20分を過ぎて帰ってこない
発表資料作成(発表7分+質疑応答3分) 「未来人を経験した自分たちからの提言書」をスライド10枚程度(以下1.~6.を含めること)にまとめる (動画にして当日動画を再生しても良いが、質問には直接答えること) 1. 表紙: 内容を的確に表すキャッチーなタイトル/班の番号/メンバー氏名(全不参加の人は除く) 2. テーマ説明: 医工学に関して注目したトピックは何か 3. 未来人になって見てきた世界: 2074年の人々の暮らしと上記トピックの未来実態 4. 提言: 「未来人を経験した自分たち」から「未来人を経験していない現在の人々」へ伝えたいこと • 2074年の何を実現したいのか or 2074年の何をなかったことにしたいのか • そのために、2024年の誰(個人、病院、研究機関、自治体、厚生労働省、政府・・・)に何をリクエスト(継続 or 廃止 or 新設)するのか • ここでは理想的な提言を考えよう 5. 自己評価: 現在の人々の視点から提言を評価 • (A) そのまま受け入れ可能 or (B) 修正すれば受け入れ可能 or (C) 現実的には受け入れ不可 6. (B)や(C)の場合、提言を修正して現実的な着地点を探ろう 16:10までに完成! 事例や根拠資料は説得力を上げる。他人の著作物等は必ず出典を明記すること。
次回の予告と宿題 活動報告、後片付け 16:10~16:20
来週の予告と宿題の内容 ◍ 13:00-13:10 諸連絡 ◍ 13:10-13:30 最終打合せ・リハーサル ◍ 13:30-14:30 発表(1~5班)と審査 ◍ 14:50-15:50 発表(6~10班)と審査 ◍ 15:50-16:20 資料提出・活動報告 宿題1(フォーラム提出): 想定質問を考えて、資料を集めたり、回答例を作ったりする 宿題2: 資料が完成していない場合は協力して完成させる
活動報告 1. 班の番号と自分が担当した役割(例:3班 作業を頑張る係) 2. 来週の自分の役割(例:発表) 3. 資料作成で自分が一番頑張った点 4. 進捗状況(資料は何割程度作れたか) 5. 共同作業をしてうまく行ったことと、うまく行かなかったこと 締め切り:次の授業の開始まで (締め切りは延長しません)
やるべきことが終わったら 後片付けをして帰りましょう 良いお年を...