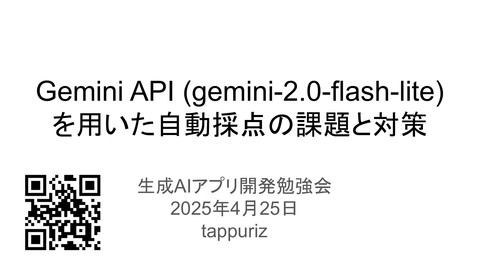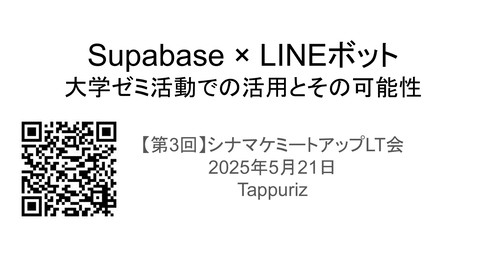生成AIとLINEミニアプリで挑む大学院ゼミ運営
1.6K Views
September 15, 25
スライド概要
関連スライド
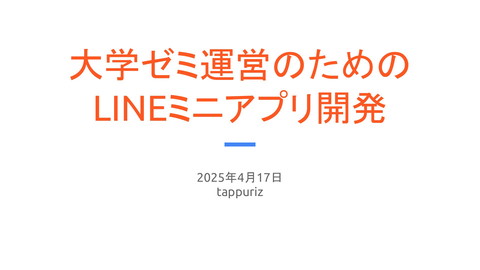
ゼミ運営のための LINEミニアプリ開発
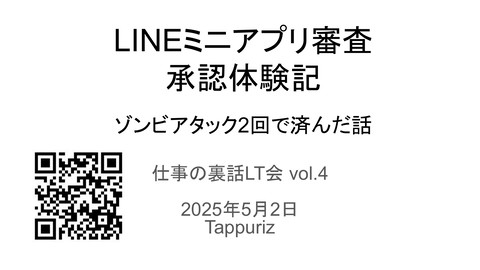
LINEミニアプリ審査承認体験記
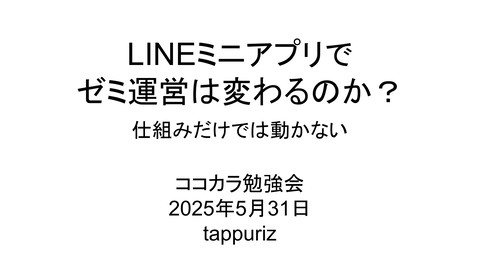
LINEミニアプリでゼミ運営は変わるのか
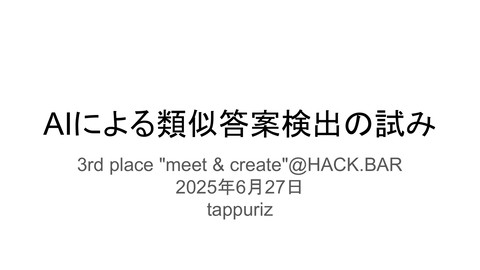
AIによる類似答案検出の試み
各ページのテキスト
生成AIとLINEミニアプリで挑む 大学院ゼミ運営 Developers Summit 2025 KANSAI【前夜祭】 2025年9月16日 本間利通(大阪経済大学)
自己紹介 本間利通 生年:1977年 大阪経済大学経営学部 教授 担当科目:経営組織論 株式会社團コミュニケーションズ 顧問 大学院ゼミ 春入学 修士1年(2名)+ 修士2年(3名) 秋入学 修士1年(2名)+ 修士2年(1名) 教育の最前線に立つフルスタック大学教員ソルジャー →人類禁止領域でリミックス
生成AIとLINEミニアプリ 生成AIが教育を解体し始めている。 これを5分で語れと????? (テーマを決めたのは私です) LINEミニアプリ ツールとして依然として優秀 アプリは動くんだけど、学生が動かない!(泣) LINEミニアプリで、すでに解体された教育を支えたかったんだが。
LINEミニアプリ 2025年3月 LINEミニアプリ開発開始:作った 2025年4月 LINEミニアプリ認証取得:認証取った 2025年4月 connpassアカウント取得:勉強会へ 2025年7月 バックエンドをGASからsupabaseに変更:データベースを意識 2025年9月 大学院生向けコンテンツ拡充計画
大学院ゼミ 運営方針 1.研究っぽいことをする 修士論文執筆(4万字)を2年で完成させる データ取得にもコミットする 2.ゼミっぽいことをする ゼミ合宿を手配して思い出作りを支援 研究会に参加する
学部ゼミ 課題山積 教員の巻き込む力に欠ける でも、このままいくいしかない 今後:AIが生成したものにどう対峙するのか :学部セミはAIと葛藤する場所になる AI利用 Gemini APIによる自動採点・添削 → 継続使用 OpenAI API + LINEボット → 現在のところ使い所なし
希望 大学院生は呼べばイベントに参加してくれる 修士論文を書くことに強くコミットしている これに関連する活動ならば容易に巻き込める AIとの戦い:この文章の作者は誰になるの? GitHub Education加入
AI活用の前にやるべきこと 学生がコミットやプルリクという単語を聞いても怖くない状態にすること GitHub Education活用 現状:修士論文の先行研究はGoogle Documentsでボワボワと毎週加筆 書くこと自体が大変なのに、追加の学習が発生ってどうなの? でも精緻なバージョン管理は学生との共著論文や学会発表に直結する。 可能性がすごい!となって教員だけが興奮している。
まとめ(まとめる気がない) 大学・大学院教育 生成AI出現以降の教育とは? よくわからないけど、生成AIにこのまま何から 何までやってもらう 教育DXの真実 システムは完成する。 ただし、教員も含めてユーザーは未熟なまま。