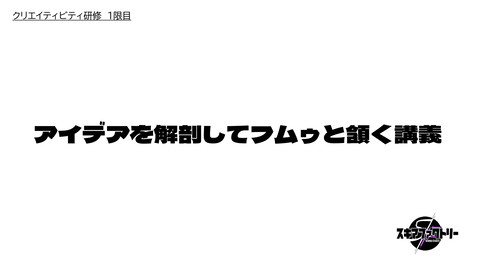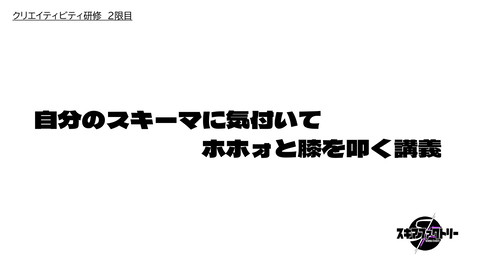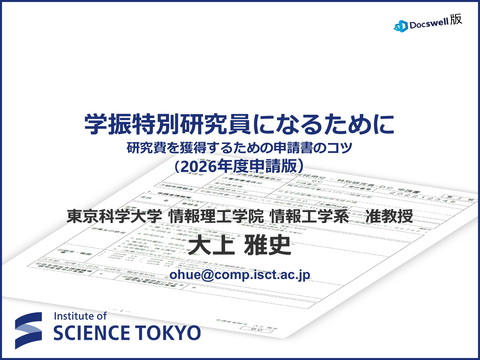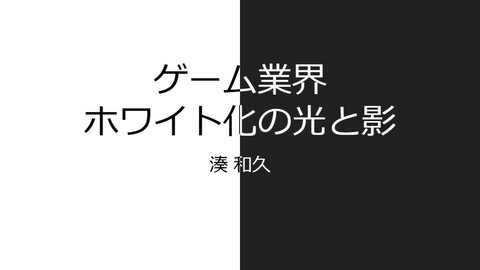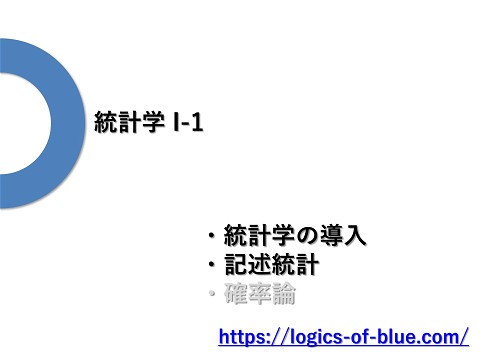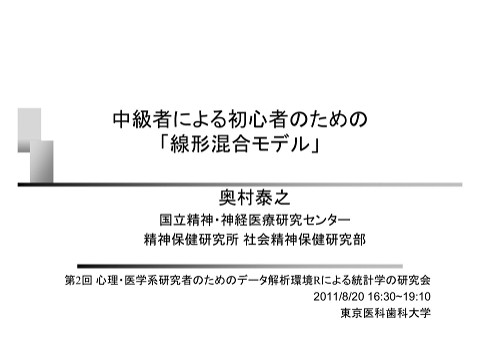グループでアイデアを出してウムと首肯する講義
103 Views
September 13, 25
スライド概要
クリエイティビティ研修で使った資料。せっかくなので放流。
全3回構成の3回目です。
ここまでの内容を結集してグループワークでアイデアを話し合ってみよう、という内容です。
いわゆる「クリエイティビティ研修」で良くある手順にやっと辿り着きます。
ただし、単なるアイデア出しではなく、制約事項を一つ設定しています。
主に組み込み界隈でシステム開発に携わりながら生活している個人事業主。
関連スライド
各ページのテキスト
クリエイティビティ研修 3限目 グループでアイデアを出して ウムと首肯する講義
ざっくり概要 ここまでの学びをグループワークで実践します。
おさらい 事例から逆算して、創造的思考の仕組みに触れました そもそも考えるとはどういうことか? を考えました スキーマというものの存在に目を向け、これが思考を 阻害する可能性について論じました
1限目のおさらい (1) 「課題」や「疑問」や「制約」があっての「創造的思考」 課題や制約の無いところに創造性は持ち込めない まずは解決力 新奇性は二の次 課題を発見する段階から創造的思考が始まっている
1限目のおさらい (2) 「世の中に無い」は、「単にそこに登場していない」も含む 「他分野の解決策」をそこに連れてくることも立派な創造的思考 「世の中に無い」は、たまたまそういう「課題」だった、というだけ いかなる課題でもベストアンサーが必ず新奇性を備えるとは限らない
1限目のおさらい (3) 創造的思考は論理の外側にあるという誤解 普通に、指折り順番に筋道を立てた考えから生まれる 「自由な逸脱」を伴うかどうかがカギ 論理的な枠組みを維持したまま、意図的なズレを加える 守破離の教えそのものだったりする
2限目のおさらい (1) スキーマ =暗黙のルールや思い込み プラスに働くと… マイナスに働くと… ・柔軟な発想 ・固定観念 ・既存の枠に囚われないアイデア ・過去の経験に縛られる ・新しい視点を受け入れる ・失敗を恐れる ・物怖じせず提案できる 創造的思考
2限目のおさらい (2) 知識の量 「発想の引き出し」の数や種類 固定観念のキャンセル 「引き出しのジャンル」を決め付けない 無意識の阻害要因への気付き 「発想のブレーキ」が働いていないかどうかを察知する
2限目のおさらい (3) 柔軟な発想への阻害要因 自由な考えに対する制限
2限目のおさらい (4) OKエリアに入っているかどうかを 平面上に投影しているだけ OKエリア OKエリアに入っていなかったとしても、 軌道修正する道は無数にある
理論のアップデート 作用点に着目する 必ずしも、解決策そのものが創造的であるとは限らない 仮に解決策そのものは既存であったとしても、 解決策のヒントの求め方やジャンル選び 解決策を導入するためのルート そこに至るまでや、実現までの道のりに創造的思考が働けばOKと考える
理論のアップデート 何らかの状況や情報に対して、無意識に働くスキーマ 「評価する側」に立った時も、当然スキーマが働いている 「機能不全状態に気付けるかどうか」 「アイデアやその種を拾えるかどうか」 「すごいアイデア」が提示されたとして、誰でも等しく認識できるだろうか? = 生成AIの運用限界問題
グループワークの流れ 1 解決したい機能不全を特定する 事前に各自で考えてきたものを持ち寄って、グループテーマを決める 2 発表 3 機能不全に対する解決方法を考える 機能不全の抽象化 機能不全と異なる領域にヒントを求める 説得力ある説明に繋げる 4 発表 グループ間でどこが創造的であったかを品評 5 振り返りと発表
機能不全を読み取るために 抽象化 → 単に「抽象的表現」にすることではない 具体の世界 起点 終点 整理されていない “具体” 抽象の世界 抽象的表現 整理された 解決可能性の高まった “具体” 一旦「抽象」に変換することで、他の分野と繋げやすくなる
グループワーク ステップ1 事前に各自で考えてきたものを持ち寄って、 グループテーマを決める
グループワーク ステップ2 他グループのテーマを聞いた時、 脊髄反射的に考えたことをメモしておく
グループワーク ステップ3 異なる領域(ジャンルや分野)を必ず関連させる →機能不全を抽象化して、問題の領域を特定 風景変化を意識して、説得力ある説明に繋げる
グループワーク ステップ4 グループ間でどこが創造的であったかを品評 機能不全を聞いた時のスキーマとも比べてみる
グループワーク ステップ5 振り返り 自分にどんなスキーマが働いていたかにも着目
グループワーク ステップ6 振り返りの発表
クリエイティビティ再考 ・論理的思考からの派生であり、 ・機能不全に気付いて、 ・他分野から説得力ある解答を導く 論理的思考をベースに、 批判的思考を働かせて、 創造的思考で解を導く 構造的思考で仕組みを捉える 「〇〇的思考」を連動させないといけない 個別訓練と一連の動きは別物 = 思考系研修が抱える機能不全ポイント
最後に 本研修自体が、本研修の講義内容に基づいた作例です 「クリエイティビティ」と題していますが、突き詰めると 「問いを立てる力」であり、これが創造性のスタート地点です あらゆる場面で発揮できる力なので、小さなことから大きなこと まで、創造的にクリアしていきましょう!
研修は以上! お疲れ様でした!