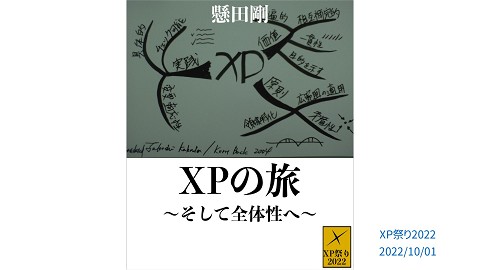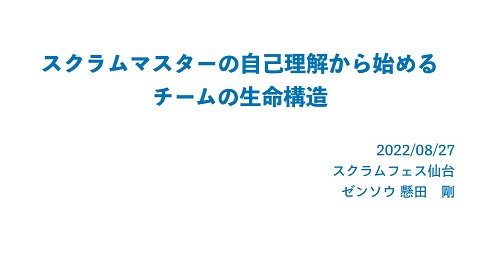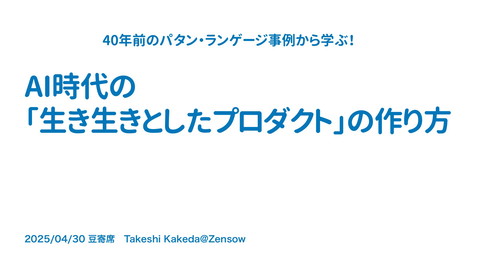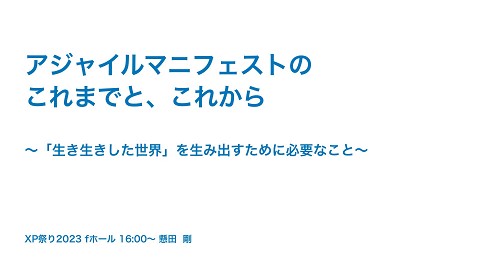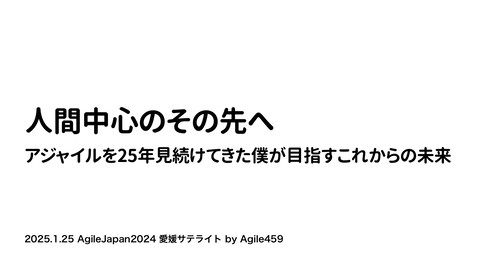『小さな美しい村』の紹介(Agile Tour Yokohama 2025)
312 Views
November 07, 25
スライド概要
Agile Tour Yokohama 2025で話した、パタン・ランゲージの最大事例の回想録である『小さな美しい村』の紹介をPO・PdM向けにしました。
全体性探究家、忘れられたXPer、アジャイル実践者、 『「アジャイル式」健康カイゼンガイド』著者 https://amzn.to/3zNK4cJ
関連スライド
各ページのテキスト
Agile Tour Yokohama 2025 『小さな美しい村』の紹介 2025/11/01 Takeshi Kakeda@Zensow
自己紹介 懸田 剛(Kakeda Takeshi) • 愛媛県松山市在住 • 「生き生き」した組織やプロダクトを作る お手伝い • 「人間を知り、人間を活かす」 • 「全体性」を展開(Unfolding)するプ ロセス • 最近お仕事募集中w https://note.com/kkd [email protected]
2025/10/29 あいテレビ Nスタえひめ https://www.youtube.com/watch?v=-h6bk2KUlyI
グラスハート大ハマリ中
ここ数年は本を作っている事が多い 2022年 2024年 2025年4月14日
https://amzn.asia/d/5lIc5YY
今日の概要 • 『小さな美しい村』の紹介 • 40年前のパタン・ランゲージの事例「盈進プロジェクト」の概要 • 建設プロセスのポイント • 細井さんのここがすごい
『小さな美しい村』とは
『小さな美しい村』 クリストファー・アレグザンダーと夢見た 理想の学び舎建設記 • 1985年4月に開校した 「埼玉県入間市 東野高校」の建設回想録 • パタン・ランゲージの世界最大規模の事例 • 作者は学園側責任者であった「細井久栄」氏 • Web公開の原稿を、Amazon KDPにて書籍発売 • 事実調査に基づく修正・注釈追加を行う • 娘:編集、孫:写真撮影、の親子三代の仕事の結晶
盈進プロジェクトの概要
盈進プロジェクトの発端 • 手狭になった校舎の建て替えのプロジェクト • 国内外の学校・建築物を数十カ所、見学 • 100冊以上の建築家の書籍を乱読 • 当初はRC造高層校舎をイメージしていた
RC造の高層校舎から、木造低層校舎へ • イギリスのパブリック・スクールを見学 • 旧領主の館を利用した学校で、広大な敷地に森や川がある • “敷地は広ければ広いほど良い。自然が残されていればさらに良い。” • 愛媛県八幡浜市の日土(ひづち)小学校 • “木という素材が与えてくれるくつろぎと落ち着き” • 「低層木造にしよう」と決めた
“どこか覚えのある懐かしい空間”
「盈進プロジェクト」開始 • 高層RC校舎から、低層木造校舎の構想に転換。 • 1981年12月の理事会 • 承認を得て「盈進プロジェクト」がスタート • 新たに新キャンパス建設の責任者へ • 「東野高校」という名前が決まる
伝統的な手法で作りたい、建築家探しが難航 • 伝統的な手法は「大工が施主と話ながら建築を進める」やり方 • ことごとく建築家に断られる • 国内の建築家は「近代建築家」ばかりだった • 大工の棟梁も探したが見つからなかった
プロジェクトを阻むいくつもの困難(今回は割愛) • 用地探しと開発認可 • どうやって農業振興地域の開発認可を取得する? • 建築確認 • どうやって45日間で、28の建築の基本設計図の確認申請を取得する? • 学校設立認可 • 2回の私学審議会で妨害活動により設立認可を留保、最後のチャンスでどう認可を取得する? • 直営方式 • ゼネコンを介さない建設は、途中で頓挫。請負でゼネコンの力を借りる。なんとか直営的にできないか?
1985年4月に開校 • ゼネコンの力を借りつつ直営方式を模索 • あまりにも短い工期(施工:9ヶ月)、なんと か開校 • 開校後、多数のメディアに注目 • 「個性伸長」「木に交わりて学ぶ」 • 戦後最大の木造建築物(当時) • 残バックログは、開校後に対応し完了
本の構成(本編)
第一部:概論 • 手狭になった校舎の建て替えが発端 • 大幅に変更「木造低層の広大なキャンパス」 • 建築家探しの末にアレグザンダーに依頼 • 立て続けに現れる困難をどう乗り越えるかか? • 1985年4月の開校を迎える
第二部:各論 • (1) キャンパスに求めていたもの、考えていたこと • 思想的な側面、なぜ学校に「日常性」や「調和」を求めるのか • (2) キャンパスツアー • 各建物の設計意図、問題のエピソードが面白い • (3) 二人の職人 • 大工の住吉氏、左官の石黒氏の比類なき匠の話
付録 • パタン・ランゲージ一覧 • キャンパス周辺の土地変遷(航空写真)、年表 • 妻明子さん、中埜博さんの寄稿文 • 監修者の推しポイント
建設プロセスのポイント
盈進プロジェクトの特徴的なポイント • 利用者参加型による設計 • パタン・ランゲージの使い方 • 徹底した現場主義 • (1)土地の声を聞く • (2)原寸設計 • (3) 現地現物による実験
利用者参加型設計
全員とのインタビューし、本音を聞く • 設計スタッフが、教職員(84名)+学生=100名以上と話を聞く • 一人ひとりに、目をつむって理想のキャンパスのイメージを想像することが求められ た。「イメージの源泉となるものの発見と教諭の本当の考えや希望の発見」 • 「好き放題言って」いい、「本音」であればいい。 • いくら「聞いて」も出てこない場合もあった
「聞いてもでてこない」ものもある 柔道場は、「体育館」なのか「武道場」なのか? • アレグザンダーは、武道の「精神性」を尊重 • 体育教官の話は、単なる「体育館」にしかならない • 石段、高窓、両開き戸、高天井で「静けさと緊張感」 ©松田真生 ©松田真生
最大公約数でなく、「個人のアイデア」を拾い上げる 建築家が馬鹿にした塀 • まったく個人的なアイデアも採用される • 「個性伸長」の教育理念の実現にふさわしけれ ば取り上げる • “教職員の思いで学校を表現している 『詩』ではないか。” • 見学にきた建築家が批判した塀 • 教員のデザインをアレグザンダーが採用した ©松田真生
利用者の関与の度合い パタン・ランゲージの 作成 4ヶ月 教職員への インタビュー 配置計画 基本設計 実施設計 3ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 教員も一緒に現地で 建物の配置を設計 建物ごとに 教員グループを作り 担当した 施工・設計監理 完成まで アレグザンダーと協議し ながら、空間デザイン、細 建設工事委員会への参 部検討、素材選択で積極 加や意思表明 的に関わる 最初から、最後まで、濃淡ありながらも、関わり続ける
パタン・ランゲージ
東野高校における「パタン・ランゲージ」 • 「パタンリスト」から選んだものではなく、利用者のニーズから作られた • 問題の解決というより、利用者の「理想のキャンパス像」 • 「〜する」というよりも、「〜ようになっている」という、「理想の状態」 • 関係者の間で共有された設計の指針となるもの • 異なるスケール(大・中・小)における理想の状態 • 「利用者」の視点で作られている
パタンの例(全体) • 1. 石の土台塀、木の柱、白い壁、2、3箇所特別なところに朱色の漆材、深々とひさしをのばす 屋根、濃い地味な屋根の色、地面の石や草が建物や敷地を特徴づけている。 • 2. まず敷地を囲む外塀がある。 • 3. 外塀の内側に、全敷地の約5分の1にあたる小さな面積を囲む内塀がある。 • 4. 内塀の内側の領域を「内境内」と呼ぶ。ここは、学校の主要な建物が建つ密度の高い領域 である。 • 5. 内塀と外塀の間は「外境内」であり、庭園や運動場、そして種々の独立して建つ外建築が ある。
パタンの例(内境内) • 1. 内境内への入り口は、外境界で始まる。外境界の重要なポイントに正門がある。 • 2. この第一の門、は建築物である。 • 3. 第一の門より内境内に向けて玄関道がある。玄関道の両側に壁か樹木が並び、非常に静 かである。 • 4. 玄関道路が内境内と出会うところに第二のより大きな門がある。これが、メイン・ゲート「正 門」である。 • 5. 正門の内側には中央広場がある。この広場は大講堂とともに構成され、その講堂の正面 は庭に向かっている。
パタンの例(建物の内装の特徴) • 1. 内装の調子は暖かく控えめである。木の柱、床、壁が各所に有り、白障子白天井の 横には、淡い黄色の紙や絹の布に似た淡黄色の壁がある。 • 2. 建物の床は、通常のものより少し高く持ち上げられている。 • 3. 教室の床の多くは木で、靴は教室でぬぐ。 • 4. 教室の多くは、一方に縁側が有り、そこから入ってくる光は、格子窓を通して差し込 んでくる。
目を瞑ってイメージして その中を歩けるか?
徹底した現地・現物主義
「土地の声を聞く」 丘陵地の茶畑、湿地をどうするか? • 敷地内の起伏や高低差どうする? • どう解決する? • どう活かす? 地理院地図より、1978-1983
「なるべくして生まれた池」
原寸設計 現場で決める、絶えざる修正 『Eishin Higashino 1985 』より https:// www.youtube.com/watch?v=m11ov0cwMrY
現物で実験 色見本では決めない、試し塗りで決める ©松田真生
細井さんという人
細井さんのここがすごい • ブレない自分軸、行動力 • 権限移譲、合意形成力 • 困難に立ち向かう勇気・楽観性・戦略 • 自我を越える(間違っていたら謝る、土下座できる) • 「責任」と「理想の実現」の狭間でバランス • 「論理と感性」の両輪
“Hosoi is a brave man. Even today, he insists that he did not give in to threats or violence. Because of his courage, we did manage to build the campus in the way both he and I, and Hajo, felt that it must be built.” (細井は勇敢な人物です。今日に至るまで、彼は脅迫や暴力に屈しなかっ たと主張しています。彼の勇気があったからこそ、私とハイヨ、そして 細井自身が「こうでなければならない」と感じていた方法で、私たちは キャンパスを築き上げることができたのです。) 『The Battle』Chapter 14 より
「細井さんなら、どうするだろう?」
40年前の日本で 近代合理性の真っ只中で 全体性を信じた物語
では読書会メンバーに お渡しします!!