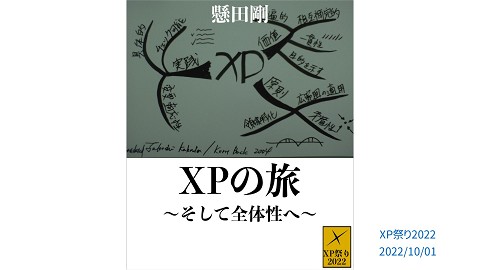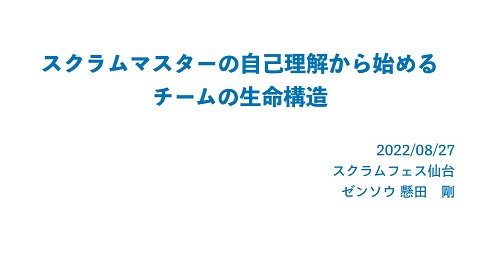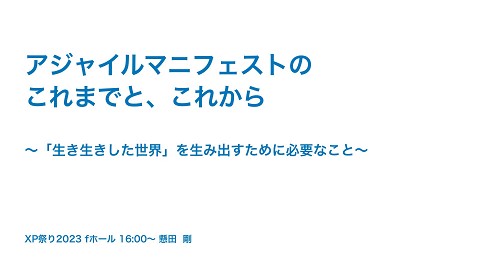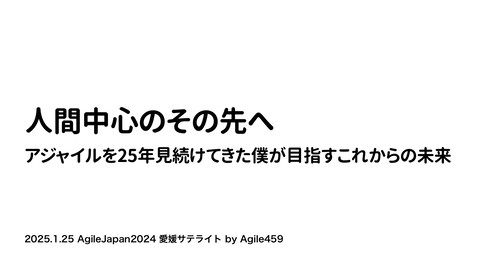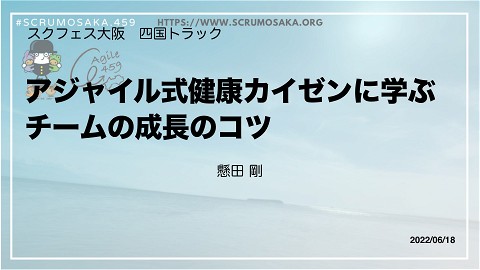40年前のパタン・ランゲージ事例から学ぶ!AI時代の「生き生きとしたプロダクト」の作り方
8.2K Views
May 07, 25
スライド概要
20250430 豆寄席 にて『小さな美しい村』をテーマにした講演資料です。
https://mamezou.connpass.com/event/351892/
全体性探究家、忘れられたXPer、アジャイル実践者、 『「アジャイル式」健康カイゼンガイド』著者 https://amzn.to/3zNK4cJ
関連スライド
各ページのテキスト
40年前のパタン・ランゲージ事例から学ぶ! AI時代の 「生き生きとしたプロダクト」の作り方 2025/04/30 豆寄席 Takeshi Kakeda@Zensow
自己紹介 懸田 剛(Kakeda Takeshi) • 愛媛県松山市在住 • 「生き生き」した組織やプロダクトを作る お手伝い • 「人間を知り、人間を活かす」 • 「全体性」を展開(Unfolding)するプ ロセス • https://note.com/kkd [email protected]
里山のビオトープ管理保全、様々な「生命」を増やす 生命を育み、そこで人も生き生きする https://note.com/kkd/m/md63c79037754
2025年4月14日 2022年 2024年
今日の概要 • 『小さな美しい村』の紹介 • 40年前のパタン・ランゲージの事例「盈進プロジェクト」の概要 • 建設プロセスのポイント • AI時代に必要なこと何か?
『小さな美しい村』とは
『小さな美しい村』 クリストファー・アレグザンダーと夢見た 理想の学び舎建設記 • 1985年4月に開校した 「埼玉県入間市 東野高校」の建設回想録 • パタン・ランゲージの世界最大規模の事例 • 作者は学園側責任者であった「細井久栄」氏 • Web公開の原稿を、Amazon KDPにて書籍発売 • 事実調査に基づく修正・注釈追加を行う • 娘:編集、孫:写真撮影、の親子三代の仕事の結晶
『Battle』と『小さな美しい村』の関係 A面 B面 専門家視点 発注者・施主視点
盈進プロジェクトの概要
盈進プロジェクトの発端 • 手狭になった校舎の建て替えの責任者として細井さんが任命 • 国内外の学校・建築物を数十カ所、見学して回った • 100冊以上の建築家の書籍を読み漁った • 当初はRC造高層校舎をイメージしていたが、ある学校に出会い構想が変化した
RC造の高層校舎から、木造低層校舎へ • イギリスのパブリック・スクールを見学 • 旧領主の館を利用した学校で、広大な敷地に森や川がある • “敷地は広ければ広いほど良い。自然が残されていればさらに良い。” • 愛媛県八幡浜市の日土(ひづち)小学校 • “木という素材が与えてくれるくつろぎと落ち着き” • 「低層木造にしよう」と決めた
日土小学校 • 1956-58年に落成 • 設計者は松山市の松村正恒氏 • 木造モダニズム建築の稀有な建築物 • 2012年、戦後木造建築として初の国の 指定重要文化財に指定
優しさ・調和
“よくほかの学校で研修会があって参加するのですが、 どこへ行ってもコンクリートの校舎で心身ともに疲れるのです。 終わってここへ戻ってくると、心からホッとします。 やはり木の良さなのでしょうね。” 日土小学校、教頭先生の言葉
“どこか覚えのある懐かしい空間”
「盈進プロジェクト」開始 • 高層RC校舎から、低層木造校舎の構想に転換した。 • 1981年12月の理事会 • 承認を得て「盈進プロジェクト」がスタート • 新たに新キャンパス建設の責任者へ • 「東野高校」という名前が決まる
伝統的な手法で作りたい、建築家探しが難航 • 伝統的な手法は「大工が施主と話ながら建築を進める」やり方 • ことごとく建築家に断られる • 国内の建築家は「近代建築家」ばかりだった • 大工の棟梁も探したが見つからなかった
建築家が建築の前の「学校についての話し合い」を拒否 細 「学校とは何か」についての認識を教職員との話し合いで確かめ、建築家と教員で共 有してもらいたいのです。建築についてプロのイメージで誘導してほしくありません。 手前どもは建築設計が仕事で、スタッフもそのために働いています。建 築以外の話で社員を学校に行かせることはできません。 細 ただで来てくれと言っているのではなく、費用はちゃんと十分にお支払い します。 お断りします。設計の仕事に対してお支払いをいただくので、その仕事なし でいただくわけにはいきません。前例もないし、理由のわからない要望には 対応いたしかねます。 建 建
『オレゴン大学の実験』そして、アレグザンダーへ • 「近代建築の失敗」と 「オレゴン大学の実験」に出会う • 利用者参加型設計で「これだ!」 • 中埜さん経由でバークレーへ • アレグザンダーと意気投合し快諾 • 契約は1982年5月 • 教職員全員に2冊を配布(200冊)
プロジェクトを阻むいくつもの困難(今回は割愛) • 用地探しと開発認可 • どうやって農業振興地域の開発認可を取得する? • 建築確認 • どうやって45日間で、28の建築の基本設計図の確認申請を取得する? • 学校設立認可 • 2回の私学審議会で妨害活動により設立認可を留保、最後のチャンスでどう認可を取得する? • 直営方式 • ゼネコンを介さない建設は、途中で頓挫。請負でゼネコンの力を借りる。なんとか直営的にできないか?
パタン・ランゲージを使って1985年4月に開校 • ゼネコンの力を借りるが、その中でも直営方式に近いやり方を模索 • あまりにも短い工期(施工:9ヶ月)だったが、なんとか開校にこぎつける • 開校後、多数のメディアに注目される • 「個性伸長」の校風、「木に交わりて学ぶ」木造校舎との相乗効果 • 残バックログは、開校後に対応し完了
建設プロセスのポイント
盈進プロジェクトの特徴的なポイント • 利用者参加型による設計 • パタン・ランゲージの使い方 • アーキテクト・ビルダーという職能 • 徹底した現場主義 • (1)土地の声を聞く • (2)原寸設計 • (3) 現地現物による実験
利用者参加型設計
どのように行われたのか? • 1. 全教員と個別のインタビュー • 2. 無意識に隠されている「本音」を探る • 3. 教員は、それぞれの考え、希望を率直に述べる。最大公約数を求めたりはしない。 • 4. 誰にも共有されない個人的なアイデア、要望であっても、キャンパスにふさわしい 場合には、積極的に取り上げる。 • 5. 教育理念を具体化することを念頭において、「住まい」の創造という目標に照らして 意見、要望を述べていく。
全員とのインタビューし、本音を聞く • 設計スタッフが、教職員(84名)+学生=100名以上 と話を聞く • 一人ひとりに、目をつむって理想のキャンパスのイメー ジを想像することが求められた。「イメージの源泉とな るものの発見と教諭の本当の考えや希望の発見」 • 「好き放題言って」いい、「本音」であればいい。 • いくら「聞いて」も出てこない場合もあった
「聞いてもでてこない」ものもある 柔道場は、「体育館」なのか「武道場」なのか? • アレグザンダーは、武道の「精神性」を尊重 • 体育教官の話は、単なる「体育館」にしかならない • 石段、高窓、両開き戸、高天井で「静けさと緊張感」 Photo : 松田真生
最大公約数でなく、「個人のアイデア」を拾い上げる 建築家が馬鹿にした塀 • まったく個人的なアイデアも採用される • 「個性伸長」の教育理念の実現にふさわしけれ ば取り上げる • “教職員の思いで学校を表現している 『詩』ではないか。” • 見学にきた建築家が批判した塀 • 教員のデザインをアレグザンダーが採用した Photo : 松田真生
“彼らの共通の手法であるが、建築家の施主へのプレゼンテーシ ョンとして、設計作業に入る前に完成予想図=パースが提示さ れるのが普通である。これで、施主側のイメージは設計者の主 観に基づくイメージに拘束されてしまう。「使用者参加の原理」 は、決定的な制約を受け、働く余地がなくなるのだ。”
設計・施工プロセスへの関与の度合い パタン・ランゲージの 作成 4ヶ月 教職員への インタビュー 配置計画 基本設計 実施設計 3ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 教員も一緒に現地で 建物の配置を設計 建物ごとに 教員グループを作り 担当した 施工・設計監理 完成まで アレグザンダーと協議し ながら、空間デザイン、細 建設工事委員会への参 部検討、素材選択で積極 加や意思表明 的に関わる
パタン・ランゲージ
「パタン・ランゲージ」のイメージは? • 過去の「成功体験」から「パターン」を抽出して書く • 現状にあうパターンをカタログから選んで適用する • パタンで問題を解決する
東野高校における「パタン・ランゲージ」 • 「パタンリスト」から選んだものではなく、利用者の要望から作られた • 問題の解決というより、利用者の「理想のキャンパス像」 • 「〜する」というよりも、「〜ようになっている」という、「理想の状態」 • 設計の指針となるもの • 異なるスケール(大・中・小)における理想の状態 • 「利用者」の視点で作られている
パタンの例(全体) • 1. 石の土台塀、木の柱、白い壁、2、3箇所特別なところに朱色の漆材、深々とひさしをのばす屋根、 濃い地味な屋根の色、地面の石や草が建物や敷地を特徴づけている。 • 2. まず敷地を囲む外塀がある。 • 3. 外塀の内側に、全敷地の約5分の1にあたる小さな面積を囲む内塀がある。 • 4. 内塀の内側の領域を「内境内」と呼ぶ。ここは、学校の主要な建物が建つ密度の高い領域であ る。 • 5. 内塀と外塀の間は「外境内」であり、庭園や運動場、そして種々の独立して建つ外建築がある。 •
パタンの例(内境内) • 1. 内境内への入り口は、外境界で始まる。外境界の重要なポイントに正門がある。 • 2. この第一の門、は建築物である。 • 3. 第一の門より内境内に向けて玄関道がある。玄関道の両側に壁か樹木が並び、非常に静かである。 • 4. 玄関道路が内境内と出会うところに第二のより大きな門がある。これが、メイン・ゲート「正門」である。 • 5. 正門の内側には中央広場がある。この広場は大講堂とともに構成され、その講堂の正面は庭に向かっている。 • 6. 中央広場の先、そして第三の門を通り抜けると、ホーム・ルーム通りがある。ホーム・ルーム通りは幅広く、活気のある、陽のあたる通り、個々 のホーム・ルーム教室建物群によって構成される。 • 7. ホーム・ルーム通りの先に、第四の門を通り抜けると、学校の最も大切な中心がある。この大切な中心は、前にも述べてきたように幾重もの 層を通り抜けて到達できる場所である。そしてそれ自体にも更に重なり合いがあり、それ以上の静けさがそこにある。 • 8. この最も大切な中心は、かなり大きくて、それ自体1つの世界を形勢している。内境内の内部にあって、小道や門で区切られ、この中心は学 校の大部分を構成している。
パタンの例(建物の内装の特徴) • 1. 内装の調子は暖かく控えめである。木の柱、床、壁が各所に有り、白障子白天井の横には、淡い黄色の 紙や絹の布に似た淡黄色の壁がある。 • 2. 建物の床は、通常のものより少し高く持ち上げられている。 • 3. 教室の床の多くは木で、靴は教室でぬぐ。 • 4. 教室の多くは、一方に縁側が有り、そこから入ってくる光は、格子窓を通して差し込んでくる。 • 5. 各所の壁や表面は自然のままで、加工されていない木でできている。 • 6. 大きい建物には、学生が自分達を見ることができる鏡が置かれている。 • 7. 建物の外には、花壇がいたるところにある。
東野高校のパタン・ランゲージとの比較 東野高校のパタン・ランゲージ ソフトウェア業界のパターン・ランゲージ 目的 利用者視点で 感性を反映したニーズを満たす 設計指針を作る ある状況における設計上の 問題解決を行う 使う人 利用者(当事者)と専門家 当事者(主に専門家) 作り方 利用者が作成プロセスに深く関与し「本 音」や「望む」姿を言語化する 専門家の過去の知見から抽出する 表現する内容 人間の内面、感性、文化に根ざした 質の表現 技術的、機能的、合理的な 問題解決策
「パタン・ランゲージの源流」の目的 • パタン・ランゲージは「当事者が自ら設計できるための言語」として生まれた • 「専門家のための、専門家による、専門家が使うパタン」になってしまった • 「利用者をエンパワーする」のが本来のパタン・ランゲージであった • ソフトウェアパターンを経由して、その目的は一度失われた。 • 「知恵の共有ツール」としてとりあげられたのは時代の必然であった • 今だからこそ、その本来の目的を思い出してほしい
徹底した現地・現物主義
「土地の声を聞く」 丘陵地の茶畑、湿地をどうするか? • 敷地内の起伏や高低差をどうする? • 近代建築家は「起伏を3つのレベルに均して造 成」と考えた • 無意識に行ってしまう造成計画 • アレグザンダーは「起伏をどう活かすか」と考えた • 20センチ単位の測量図を作成して既存の起伏 を理解しようとした 地理院地図より、1978-1983
構造保存変容 • 現況の構造を捉え、構造を保存しながら、より全体が生き生きするように変容する • “ポジティブな発展の全体は、一連の構造保存変容のシーケンス(連続性のあるプ ロセス)として実現されます。新しい構造は、既存の全体に基づいており、その全体に 影響を与える変容のシーケンスによって生成されます。結果として得られるシステム は、ほとんどの場合、機能的で効率的で美しいものとなります。”(『パタン・セオリー』) • 自然界のプロセスはすべて「構造保存変容」であり、無駄がなく効率的。 • 人間が行うのは「構造破壊変容」であり、「現況の構造」を無視しがち
「なるべくして生まれた池」 雨が降ると水が貯まる窪地をどうするか? • 元々、雨が降ると湿地になり、野菜も茶 畑にもならないで放置されていた • 水が溜まりやすいなら、池にするのが 自然である。パタン・ランゲージにも 「池」は登場していた • 「なるべくして生まれた池」 Photo : 松田真生
原寸設計 現場で決める、絶えざる修正 • 配置計画は「すべて現場で決めた」 • 通常は基本設計→配置計画、 東野高校は配置計画→基本設計 • 環境を無視して図面や建築家の頭の中 だけで決めることを防ぐ • 現場で「感じた」ことによって決めた 『Eishin Higashino 1985 』より https://www.youtube.com/watch?v=m11ov0cwMrY
現物で実験 色見本では決めない、試し塗りで決める • 壁面の色を「緑色」にする→一悶着 • 「色見本で決めない、試し塗りで決める」 • 小さな切れ端で判断するのは不可能 • 乾燥後の色変化は、実際の塗装でしかわからない • 同じ材質のサンプルではなく、実際の壁面で実験 • 刷毛による手仕事を要請したが、ローラーで妥協 Photo : 松田真生
アーキテクト・ビルダー • 施主との相談を続けながら、建築家が、設計から施工に至る全過程に責任を持つ • 「建築家は設計、大工・施工業者は施工」の職能分離を解決する • それらに加えて、利用者参加を支援するファシリテータ・コーチの役割も持つ • 利用者を設計に参加するプロセス管理 • 利用者が設計に用いるパタン・ランゲージの作成 • アレグザンダーは、教職員が積極的に設計に参加できるように相談にのっていた
アジャイル開発との類似と差異 • アジャイルは、設計者とプログラマーの分離を統合しようと試みた • 後工程から、前工程を統合 • アーキテクトビルダーは、設計者と施工者の分離を統合しようと試みた • 前工程から、後工程を統合 • 共に利用者(当事者)参加を促進させたが、アジャイルはやや弱い(DDDで補完) • 常に職能は分化していくので、分化と共に統合が不可欠
専門家の恫喝と、利用者のエンパワーメント 利用者参加だけでは足りない • 専門家が「こうだ」と言ってしまうと、素人は反論できない • 木の体育館を、ゼネコンが鉄骨に説得しようとしたときの話 • “「日本の建築の実態を知らない外国人の建築家〈アレグザンダー〉を起用し現実を見な いで勝手な夢を描いている夢想家〈私のこと〉の行き方と、長年の実績を持つ大手ゼネコ ンの現実的で安心出来る提案があります。さあ、どちらを取るのですか?答えは明らかで はないですか。」と理事会に迫ったのである。” • 利用者がただ参加するだけでは、素人は自信が持てない。 • 利用者に自信をもたせ、力づける(エンパワーメント)支援が不可欠 Photo : 松田真生
対立をどう乗り越えるか?
『当たり前のやり方』から『Battle』へ • 当初は『Ordinary Way(当たりまえのやり方)』という本のタイトルにする予定 • 蓋を開けてみたら『Battle(闘争)』になってしまった。 • なぜなら、盈進プロジェクトは「対立」の連続だったから • 時代との対立 • ゼネコンとの対立 • 教職員との対立 • アレグザンダーと細井さんの対立
時代との対立 • 木造で学校を作る、大型木造建築を作る、 池を作る、すべて非常識 • 時代の流れと真っ向から対立する 内田 祥哉. 「協会設立10周年 記念講演 伝統的建築から戦後の木造建築の変遷」. PSATS report, 2009年1月.
ゼネコンとの対立 • 「木の思想」感性を大事にする学園・CES、 「効率・合理性」を重視するゼネコン • 対立を厭わない「建設工事委員会」を毎週実施 • CESとゼネコンが互いに、本音をぶつけ合う • 教員は黙ってその場にいる「おしん会議」 • 徐々にゼネコンも受け入れていくようになった https://www2.nhk.or.jp/archives/articles/?id=C0010292
「感性」と「合理性」の対立をどうしたか? 細井さんの戦略 • 同じ土俵で「戦わない」 • “感性を抜きにして、合理の次元で議論をすれば、木に勝ち目がないのは、窓のサッシュの場合と同じ である。” • 相手の立場も理解する • “感性や好みで仕事をしていたのでは、ゼネコンの利益は出てこない。所長の立場は、当然であった。” • ただ、お願いする • “議論はなし、とにかく絶対に木の体育館を建ててくれ、土下座してでも頼むと、床に土下座して頭を 下げた。生涯を通じてただ一度の土下座であった。”
教職員との対立 • 民主的プロセスで決定を積み上げても、覆され、反対される • 「木の窓枠はやめて、アルミにするべき」 • 根本的な「思想の共有」ができていなかった • 「地域の自然と風土を尊重」 「木造低層を主体とする木を主にしたキャンパス」 • 他教職員は、プレッシャーで揺らいでしまう • 「時代の常識」に抵抗できる強い人は少ない Photo : 松田真生
思想共有、ソース移転は現代にも通じる課題 • 早期からの関係者間の思想共有・共通理解の徹底 • 「なぜ作るか」の更に前提にある「思想・哲学」的な部分の共有 • プロダクトの「いのち」をどう継承するか? • 『ソース原理』がそのヒントになる • 「人の弱さ」を受け入れる • 誰もが「自分の意志や信念を貫ける」わけではないことを理解する
AI時代に必要なことは何か?
AIにおんぶにだっこでOSSのライブラリを作って公開した 「効率的」と引き換えに「失った」こと • 3時間でアイデアをOSSでライブラリで公開 • すべてChatGPTにお任せ • テスト、ドキュメント、パッケージングも行った • 作ったものに「自信が持てない」ことを体験 https://note.com/kkd/n/n902cf2dcc865
「合理性・効率性」が技術によって実現された先は? • AIが「より簡単」「より効率」を駆動する • ゼネコンが当時「鉄骨なら簡単にできますよ」と言ったように • 教員たちが「アルミサッシなら補助金でますよ」と言ったように • 「楽に、快適に」を追求した先にあるものは何か? • 「人間の心の底からの喜びやニーズ」ってなんだろう?に向き合わざるを得ない
当時、東野高校は非常識だった、今は? • 大型木造建築物→1980年代後半から大型木造建築は増え続けている • 役に立たない池→ビオトープ、生物多様性、気温緩和効果に役立つ • 直営方式→選択肢として選択可能になってきた • パタン・ランゲージ→さまざまな分野で応用されている。 • 利用者参加型設計→アジャイル開発、デザイン思考、ドメイン駆動設計などで広が っている
時代のターニングポイント “木造学校の可能性を最初に示す役割を果たしたのが, 昭和 60 年完成の私立盈進学園東野高等学校です。 理事者が「機能的,合理的だけでなく, 精神性を持った学校らしい学校」を作りたいと考え, 辿り着いたのが木造でした(図 1-9)。” 「木の学校づくりーその構想からメンテナンスまでー(改訂版)」. 文部科学省, 2019年3月. https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11373293/www.mext.go.jp/a̲menu/shisetu/ mokuzou/1414326.htm.
アルミサッシの高シェアは日本だけ • 先進国ではマイナー • 安く、耐候性は高いが、 • 断熱性が低く、結露しやすい • 木は調湿、デザイン、断熱性に優れる https://www.satohome.net/column/sash/
東野高校は 当時の非常識、今の常識を現実化した 「未来の現実化」
時を超えた質を生み出すのは「感性・感情」ではないか? • 「感性」で捉えたものは、「論理」では説明できない • 今はそうでも、未来では違うかもしれない。しかし「木の合理性」は今は説明できる • 説明できなくても「感じた」ものは「ある」 • 「感じた」ものを無視するのは「なかったことにしている」こと • 自分の「感性」を信じて貫く • そうすることで「時を超えた質(=生命の質)」が生み出されるのではないか?
自分の「感性・感情」を信じることができるか? 「感性を開く」ことがこれからの時代に不可欠
「感性」と「合理性」の対立から、統合へ 『Battle』のアレグザンダーの未発表原稿より • 「Large-scale building production: uni cation of the human system and the physical system(大規模建築 生産:人間システムと物理システムの統合)」 • システムA(感性・生命)と、システムB(合理性・効率)が対 立するのでなく協力する • “この問題について真剣に議論を始めるためには、まず現在 fi の建築業界が、世界規模でシステムAを排除し、システムB を支える役割を果たしてきたという事実を認識しなければ ならない。これは、現代における否定的な現実である。”
職人の喜び、生きがい 大工の住吉棟梁、左官の石黒氏 • 住吉氏は「大工の腕」をふるうことはなかった • “自分の仕事はない” • “仕事をしていることだけが、職人には最高の幸せなん ですよ。” • 石黒氏は1年間泊まり込みで大講堂の黒漆喰を仕上げた • “この仕事が終わったら、もう、いつ死んでもえーよ。” Photo : 松田真生
最初に自分が「生き生き」することが 生き生きとしたプロダクトの実現に 繋がるのでは?
皆さんへの、問いかけ • 「40年前の事例」から何が学べますか? • 「パタン・ランゲージの源流」に興味がもてましたか? • あなたは「自分の感性・感情」を信頼できていますか? • 「苦難があっても成し遂げたい」ことはなんですか? • 「AIに任せたくないもの」はなんですか? • 「あなたの喜び」は何ですか?
5/31 にイベントやります! https://forms.gle/LEeBjSbdoX7u5z8z5