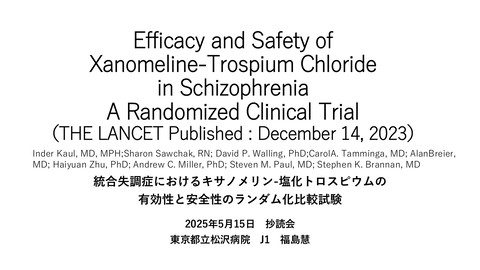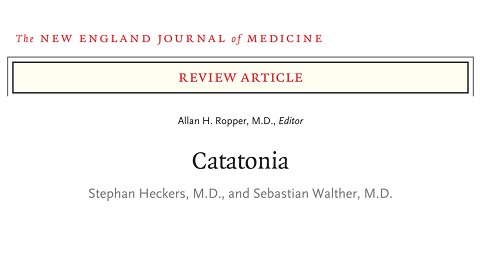スマートフォンを用いた心理療法が乳がん生存者の再発への恐怖を軽減する:完全分散型ランダム化比較臨床試験
411 Views
August 11, 25
スライド概要
某病院精神科後期研修医が運営するアカウントです。日々の勉強会の内容など情報発信をしていきますので、 よろしくお願い申し上げます。
関連スライド
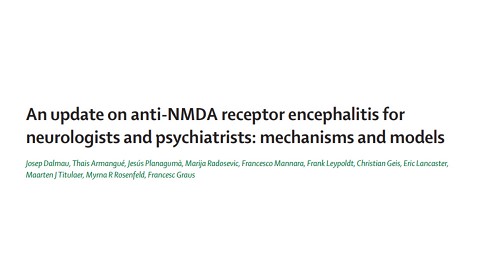
抗NMDA受容体脳炎uptodate
 レジデント
1.7K
レジデント
1.7K

リフィーディング症候群
 レジデント
1.4K
レジデント
1.4K
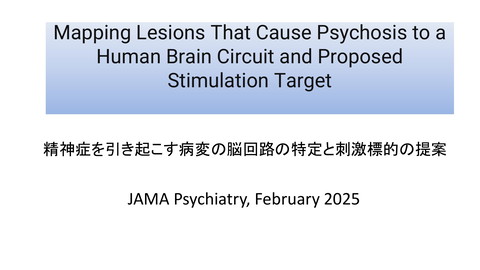
JAMA Psy 精神症脳回路
 レジデント
1.1K
レジデント
1.1K
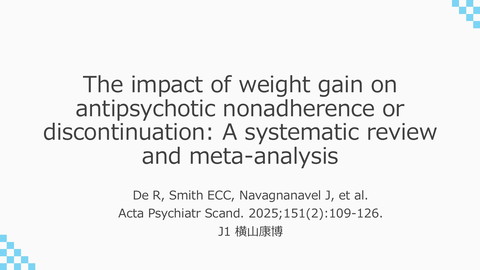
0717抄読会_横山康博
 レジデント
444
レジデント
444
各ページのテキスト
Smartphone Psychotherapy Reduces Fear of Cancer Recurrence Among Breast Cancer Survivors: A Fully Decentralized Randomized Controlled Clinical Trial (J-SUPPORT 1703 Study) Tatsuo Akechi et al. J Clin Oncol. 2023 Feb 10;41():1069-1078. 5
目的 ・早期発見と個別化医療の進歩により、乳がん患者の生存率は向 上している(10年生存率90%) ・多くの乳がん生存者は、再発に対する不安や恐怖に苦しんでい る傾向にある ・J-SUPPORTにおける前回の研究では、外来乳がん患者が経験 する最も一般的なアンメットニーズは心理的なもの、特にがん再 発の恐怖(FCR; Fear of cancer recurrence)であり、参加患者 の半数以上がそのような問題を訴えていた ・乳がん患者の間では、FCRは非常に多く見られ 、生活の質の 低下とも関連している
目的 ・これまでの研究では、マインドフルネス、認知行動療法 (CBT)、新しい理論に基づいた心理介入(Conquer Fear)な どが乳がん生存者の FCR を改善したことが実証されている ・近年のメタ分析では、FCR に対する心理学的介入は小さいな がらも有意な効果があった ・課題として、時間および距離の問題による参加率の低さが懸念 されている(参加資格がある可能性のある参加者の60%以上が参 加を辞退する)。また、専門的なケアを提供できる治療者はきわ めて少ない
目的 ・先行研究では、問題解決療法(PST; Problem-Solving therapy)や行動活性化療法(BA; Behavioral Activation)を含 むCBTが、FCRの低減に有効と示されている ・PSTとBAは、看護師などでも実施できる簡単な介入だが、こ れらは8~12回の対面セッションで構成されるため、PSTまたは BAを受ける意思のある患者が実際に治療を受けることは難しい ・乳がんと診断される女性の数が毎年増加していることを考える と、新たな治療法の開発が望まれる
目的 ・最近の研究では、コンピューター化されたCBT (iCBT) がうつ 病治療に有効であることが実証されており、同様の長さの対面式 CBTと同等の効果が得られる可能性があるとされている ・スマートフォンを活用したCBT は、アクセスしやすさや携帯 性の観点から、よりFCRに適した治療オプションであるといえる ・今回のランダム化研究の目的は、スマートフォンを使った PSTとBA介入が乳がん生存者の FCR を低下させる有効性を調査 することである
方法-参加者 ①乳がんの診断を受けていること ②20~49歳であること(乳がんリスクの高さおよびスマート フォンの所有率の高さを鑑み年齢層を設定した) ③乳房手術から1年が経過していること ④現在乳がんに罹患していないこと ⑤iPhoneまたはiPadを用いて患者報告アウトカム評価(EPO) を電子的に完了できること
方法-参加者 除外基準: (1)重篤な身体疾患あるいは乳がん以外のがんの病歴がある (2)日本語を理解できない (3) 現在、精神科医またはその他のメンタルヘルス専門家による フォローアップと治療を受けている (4) 過去に構造化されたPST、BA療法、またはCBTを受けたこと がある (5) 研究者により不適切と判断された(例:個人情報の盗難、重 複エントリー)
方法-介入 ・スマートフォンベースのPST(Kaiketsuアプリ)とBA(Genki アプリ)を用いて介入 ・完全に分散化された個別ランダム化、並行群間多施設共同試験 では、参加者は対面での接触なしに登録された ・参加者は、スマートフォンを用いた介入および通常の治療を受 ける群と、通常の治療を受ける待機リスト対照群に無作為に割り 付けられた
方法-介入 ・iPhone および iPad用のKaiketsuアプリ(スマートフォンベー スの PSTプログラム)は、9つのセッションで構成され、各セッ ションの完了には10分を要した ・GenkiアプリはスマートフォンベースのBAプログラム(患者が 楽しい行動や有意義な行動を増やすことを奨励するプログラム) であり、6つのセッションで構成され、各セッションの完了には 10分を要した ・8週間のプログラム期間中、参加者は週に1回電子メールでリ マインドを受けた。いずれのアプリも一般使用を目的として開発 されたものであった
方法-手順 ・研究情報は、SNS、がん拠点病院に掲示されるポスター、リー フレットを通じて配布された。研究ウェブサイトでも本研究に関 する情報が提供された ・0週目に電子インフォームドコンセントを提供し、ベースライ ン調査を完了した後、参加者は、電子データ収集ウェブプログラ ムを使用して、スマートフォンベースのPSTおよびBAグループ または待機リスト対象群にランダムに割り当てられた ・アウトカム測定値の提供に応じて最大5,000円の報酬が提供さ れた。研究期間は2018年4月2日から2020年7月13日まで、追跡 調査は2021年1月15日に完了した
方法-評価尺度 ・参加者は研究期間中(0~8週目)2週間ごとに評価され、24週 目にスマートフォン経由で追跡評価が実施された ・主要評価項目は、再発に対する不安尺度(CARS-J)の日本語 版による総合的恐怖スコアで評価したFCRであった。総合的恐怖 のスコアの範囲は4~24であり、スコアが高いほど再発に対する 恐怖が大きいことを示す ・副次的評価項目には、がん再発に対する恐怖評価尺度-短縮版 (FCRI-SF)、病院不安・抑うつ尺度(HADS)、支持療法ニー ズ調査質問票(SCNS-SF34)、日本語版心的外傷後成長評価尺 度(PTGI-J)、介入に対する満足度(0~100点)が含まれた
方法-評価尺度 ・CARS-JおよびHADSは0週、2週、4週、8週、24週目に評価さ れ、FCRI-SF、SCNS-SF34、PTGI-Jは0週、8週、24週目に実施 された ・介入に対する満足度を評価し、8週目に介入の質的評価を実施 した。満足度は介入のあらゆる側面(スマートフォンアプリ、自 動励ましメール)を網羅することを目指し、質的評価では介入の 肯定的側面と否定的側面、そして介入の有害性を考慮した ・介入は複数の複雑な要素で構成されていたため、8週目に30名 の参加者を対象に、介入の有用性、メリット、有害性を評価する ための簡易な構造化電話インタビューを実施した
方法-サンプルサイズの推定 ・前回の第 II 相試験では、CARS-J の平均スコアは介入前(ベー スライン)で12.8、4週目で12.4、8週目であった ・上記を踏まえ、2週目でのCARS-Jの平均スコアは 12.6、全体 的な CARS-J スコアは変化せず、スコアの分散は常に 30、級内 相関は 0.82と仮定。P =0.05(両側)で有意差を検出するために サンプルサイズを推計したところ、444人の参加者を募集する必 要があった ・CARS-J スコアにおける臨床的に重要な最小限の差に関する データがなく、この試験を有効性試験として実施したいと考えた ため、サンプルサイズは以前の研究に基づいて設定した
方法-統計分析 ・主要解析対象集団において無作為に割り付けられた全患者の治 療効果パラメータを、intention-to-treat原則に基づき検討する ため、非構造化共分散と標準誤差を用いた一般化線形モデルを用 いて主要評価項目を解析した ・固定効果は、ベースライン時のCARS-Jスコア、治療割り当て、 時間、および治療と時間の交互作用とした ・主要評価項目は、8週目における2群間のCARS-Jスコアの差と した。効果量(ES)は、Cohenのdに基づいて算出した
結果-参加者の特徴 ・合計447名の患者が無作為に 割り付けられた。223名が介入 群、224名が対照群に割り当て られた ・8週時点の主要評価項目デー タは、無作為に割り付けられた 444名(全447名のうち99.7%) から得られた介入を受けた223 名のうち、213名(95.5%)が 24週目に追跡評価を完了した
結果-参加者の特徴 ・患者は概ねフルタイムまたは パートタイムで就業しており、 既婚であった ・患者の約半数が術後化学療法 を受け、65%は、以前の研究で 推定された高いFCR(CARS-J の一貫性に関する項目の恐怖の スコアが3以上[5段階リッカー ト尺度; 1=心配しない、5=常に 心配する])であった
結果-受けた治療 ・スマートフォンアプリでは、介入群の参加者のほとんどがPST (89.2%)とBA(82.1%)のセッションを少なくとも1回完了し た ・PSTアプリの完了セッションの平均、中央値、範囲はそれぞれ 6.7±3.3、9、0~9で、BAアプリの完了セッションの平均、中央 値、範囲はそれぞれ4.7±1.9、6、0~6だった
結果 ・介入群(n = 223)の参加者 は、対照群と比較して、8週目 にCARS-Jスコアにおいて統計 的に有意な改善を示した (P <.0001) ・介入群は8週目に、FCRI-SF スコア(P <.001)、HADSう つ病スコア(P < .05)、 SCNS-SF34心理領域スコア (P < .05)において統計的に 有意な改善を示した
結果 ・全体的な恐怖スコアのベース ラインからの変化は右図の通り ・介入群と対照群の治療に対す る全体的な満足度はそれぞれ 73.4(標準偏差=17.3)、73.9 (標準偏差=17.7)と評価され、 有意差はなかった(P =.26)
結果-追加解析 ・介入がFCRの高い参加者に対してより効果的であったかどうか を判断するため、参加者をベースラインのFCRスコアによって2 つのグループに層別化した ・両方のグループ(0週目から8週目)で有意な改善が見られた が、FCRの高い参加者の方がFCRの低い参加者と比較してより大 きな改善が見られた
結果-アドヒアランスについて ・アプリ毎に、セッションの80%以上を完了しているか否かを評 価し、参加者を2つのグループに分けた。 Kaiketsuアプリへのア ドヒアランスを8回以上: 高、7回以下: 低、Genkiアプリへのアド ヒアランスを6回以上: 高、5回以下: 低と定義した ・アドヒアランスがアウトカムに及ぼす潜在的な影響を調査する ため、研究アウトカムの変化(0週目から8週目)を分析したが、 アプリへの関与度はアウトカムと有意な関連がなかった (Kaiketsuアプリ: P = .35、Genkiアプリ: P = .54)
結果-質的評価 ・KaiketsuアプリとGenkiアプリの使いやすさについて、それぞ れ参加者の43%と50%が肯定的に回答した ・Kaiketsuアプリの利点として、問題解決への体系的かつ段階的 なアプローチ、後押しされているという感覚などが挙げられた ・Genkiアプリの強みとして、楽しいゲーム機能、小さな活動を 始めるための励ましなどが挙げられた ・アプリが複雑で使いにくいという否定的な体験を報告した参加 者もいた
結果-24週目のフォローアップ ・介入群のアウトカムは、 CARS-J、FCRI-SF、SCNSSF34心理領域スコアにおいて、 8週目と24週目に有意差は認め られなかった ・HADSうつ病スコアは、24週 目において8週目と比較して有 意に減少した(P < .05)
考察 ・本研究は、乳がんサバイバーのFCRに対するスマートフォンを 用いた心理療法の有効性を実証した初めての研究である ・介入群のESを臨床指標として算出し、8週時点での群間ESは 0.32であった。これはスマートフォン介入がFCRの低下に小~中 程度の効果を有することを示唆する ・心理介入のFCRへの効果を調べたメタ分析では、対面式CBTで 同様の効果(g: 0.24-0.42)が示されている
考察 ・介入はFCRの高いサバイバーに対してより効果的であったこと から、現在のESではFCRの高いサバイバーに対する真の介入効 果を過小評価している可能性があることを示唆している ・アプリへの関与度 (遵守) と結果の間に有意な関連性がないこ とについては議論の余地がある(改善したためにアプリをやめた のか、アプリの使用をやめたために改善しなかったのかを判断で きない)
考察 ・Wagner らは3 つの認知行動スキル (リラクゼーション、認知 制限、心配の練習) を含む標的eHealth 介入が、乳がんサバイ バーの中等度から高度のFCRに有効性を示さなかったと報告した ・参加者の年齢や介入の方法など、本研究と先の研究の間にはい くつかの違いがあった。スマートフォンベースのPSTとBAは若 年乳がんサバイバーのFCR低減に十分に寄与した ・多くの乳がんサバイバーは忙しい日常生活と並行して FCR に 対処する必要があり、世界中に多数の患者が存在するため、アク セス性、携帯性、簡潔性、費用対効果などの利点がある心理療法 アプリは、FCR に対する有望な治療介入となる可能性がある
考察 ・うつ病に対する様々な認知行動スキルの有効性を調査したコン ポーネントネットワークメタ分析では、BAが最も効果的であり、 次いで不眠症と問題解決能力に対する行動療法が効果的であるこ とが示された ・FCRに対するCBTに焦点を当てたメタ分析では、認知プロセス に焦点を当てた現代的なアプローチは、認知内容に焦点を当てた 従来のCBTよりも高い有効性を示した ・異なる認知行動スキルは、心理的苦痛に異なる影響を与える可 能性があり、がん患者のFCRを軽減するために最も適切なCBTの 組み合わせを明らかにするには、さらなる研究が必要である
考察 ・本研究では、介入が乳がんサバイバーのうつ病および心理的 ニーズにも潜在的な有効性を持つことが示された ・うつ病と満たされていない心理的ニーズは、がん患者の心理的 苦痛の一般的な原因であるため、スマートフォンを用いた心理療 法が他の種類の苦痛にも有効であるかどうかを調査するには、さ らなる研究が必要と考えられた ・スマートフォン心理療法は拡張性が高く社会実装の可能性も高 く、対象者を遠隔地在住者や対面でのカウンセリングが困難な 人々へと拡大していくことも期待される
考察-分散型臨床試験のメリット ・本研究の主眼点ではないものの、分散型臨床試験は、データ収 集において従来の研究施設や専門の仲介機関への依存度が低いと いう特徴がある ・臨床試験参加時の医師と患者の負担は少なく、登録後の追跡率 も非常に良好であった(主要評価項目の完了率が99%以上)。こ れは、分散型臨床試験が今後の臨床試験においても実行可能な方 法となる可能性を示唆している
考察-研究の限界 ・KaiketsuアプリとGenkiアプリに興味を持ち、利用を希望した 患者全員がスマートフォンを所有していたわけではなかった ・本研究の結果のFCRの高い乳がんサバイバー全員への適用性お よび一般化可能性は低い可能性がある。特に、発展途上国の患者 や情報通信技術リテラシーの低い患者には、本研究の結果は当て はまらない ・しかしながら、手術後1年経過しても再発を強く恐れる可能性 のある患者、および本サービスを必要とすると想定されるサバイ バーを対象とするように適格基準を設定したため、臨床的に重要 な患者群を対象とすることができたと考えている
考察-研究の限界 ・スマートフォンアプリが高齢患者に及ぼす影響、および心理療 法や精神科治療を受けている患者への複合的な影響を明らかにす るには、さらなる研究が必要である ・介入として2種類の心理療法(BAとPST)を用いており、どの 介入がFCRの管理に最も有益であったか判断しかねる ・CARS-Jは全体的な心配に加えて4つの因子で構成されていたが、 CARS-Jの因子構造がオリジナル版と異なるため、これらの因子 は評価しなかった。これは、介入がFCRの特定の領域に及ぼす影 響を判断できないことを意味する
考察-結論 ・本研究は、PSTおよびBAスマートフォンアプリが8週目にFCR を減らす効果があることを実証し、その効果は24週目も維持さ れている ・がん生存者の数が増える一方、適切な心理療法を実施できる治 療者の数が限られていることを考慮すると、新しいスマートフォ ン心理療法はFCRを減らす有望な方法となる可能性がある