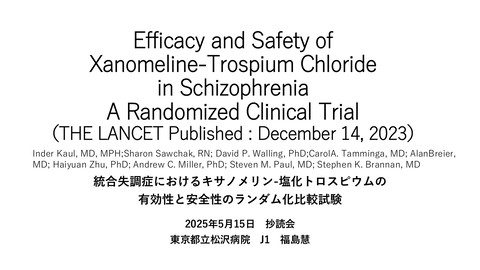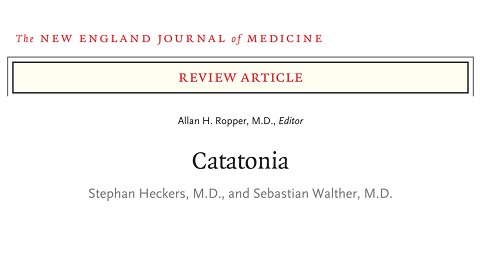精神科救急患者に対する詐病疑いのアンケート調査及び分析
324 Views
July 13, 25
スライド概要
デンマークの精神科救急病棟の医師に対して行われたアンケートを元に、詐病の疑いをかけられやすい精神科疾患や症状について、カイ二乗検定及びフィッシャー検定で分析しています。
某病院精神科後期研修医が運営するアカウントです。日々の勉強会の内容など情報発信をしていきますので、 よろしくお願い申し上げます。
関連スライド
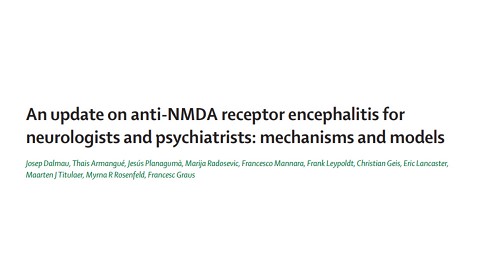
抗NMDA受容体脳炎uptodate
 レジデント
1.7K
レジデント
1.7K

リフィーディング症候群
 レジデント
1.4K
レジデント
1.4K
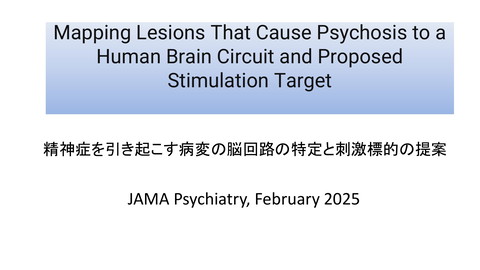
JAMA Psy 精神症脳回路
 レジデント
1.1K
レジデント
1.1K
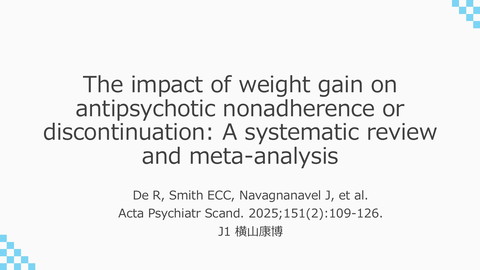
0717抄読会_横山康博
 レジデント
444
レジデント
444
各ページのテキスト
Do we know the mind of others? Suspicion of malingering in emergency psychiatry
はじめに ・「詐病かも?」 ・アメリカの精神科救急部門では、ある病院では20%、別の病 院では42%の患者が詐病の疑いをかけられていた ・ICD-10「詐病は法的および軍事的な状況では比較的一般的だ が、一般市民生活では比較的まれである」 →実際の詐病の発生率よりも、医師が疑う詐病の頻度の方が高 いように見える
背景 ・患者が詐病を認めても、必ずしも真実とは言えない ・逆に症状を隠すことも起こりうる ・詐病の疑いがあっても、正式に記録されることはまれ →精神科における詐病の正確な有病率は不明 同時に、医師の詐病疑いの頻度にも明確な説明がない 本研究ではヨーロッパの精神科救急の現場でも、アメリカ同 様の高頻度(20〜40%)の詐病疑いが見られるかを検証
目的 本研究の目的は、 医師が患者に対してどの程度詐病を疑っているのかを調 査し、詐病が疑われる患者に対してどのような診断名、 症状、そして動機が関連づけられているのかを明らかに することである
方法(参加者、調査場所) 参加者 精神科救急外来に来院した患者を診察した、医学生と医師(初期研修 医から専門医まで)総勢300名 調査場所(Setting) ・デンマークの首都圏に位置する2病院と地方の1病院が対象(精神科 病棟は福祉制度によって全額負担) ・調査期間:2020年8月と11月の各14日間 ・質問票とプロジェクトの情報を記載したポスターは各病棟に掲示され、 勤務中の医師には定期的にリマインダーメッセージを送信 ・質問票1枚記入ごとにチョコレートを提供
方法(詐病の定義) •「模倣」:外的報酬(刑事訴追の回避、違法薬物の取得、 兵役の回避、病休や住居など生活条件の改善)を目的とし た意図的な症状の捏造 •「誇張」:既存症状の程度や深刻さを過剰に描写すること
方法(データ収集) ・担当医(評価者)の経験年数、患者の診断情報を質問票で 取得し、カルテでも確認した ・評価者は、患者について5段階評価スケールで評価を行い、 詐病と疑われた場合は疑われた症状と詐病の動機を記入した。 また、評価者は以下の中から詐病の理由を評価した:「食事 /住居目的」「薬物目的」「注目を集めたい」「孤独感」
方法(データ分析) ・患者はICD-10に基づいて分類された ・詐病の5段階評価は、「なし」「軽度〜中等度」「強度〜確実」と3分類に集 約した ・診断群ごとの詐病の頻度差は、カイ二乗検定を用いて解析した ・診断が2つ記載されていた16名の患者は、ICD-10における階層の高い診断に 基づいて分析された ・また、医師の経験年数と詐病の疑いとの関係をカイ二乗検定で、物質使用障 害およびパーソナリティ障害の患者と他の患者との違いについては二項の フィッシャーの正確検定(両側)を用いた。該当診断群の患者に特定の症状・ 理由がより多く当てはまるかどうかは片側のフィッシャー検定で分析した。
結果(患者情報) 救急受診件数:822件 回収率:44%
結果(評価者情報)
結果(頻度)
結果(頻度) • 全体の25%(90人)の患者が模倣を疑われた。 • 8%(29人)の患者は「強く」または「確実に」模倣してい るとされた。 • 誇張の疑いは22%(89人)、うち6%(22人)が強度〜確実 に誇張しているとされた。
結果(診断と詐病) • 診断ごとに模倣および誇張の疑いの頻度は有意に異 なっていた。 • 物質使用障害とパーソナリティ障害を持つ患者は、他 の診断群に比べて有意に模倣・誇張の疑いをかけられ ていた。 • 性別、年齢、医師の経験年数による有意差は確認され なかった。
結果(症状、動機)
結果(症状) • 詐病と疑われた症状の中で、自殺念慮が最多 • 統合失調症様の精神病症状を模倣しているとされたの は6%(23人)、誇張では4%(15人) • 特に、パーソナリティ障害と診断された患者は、自殺 念慮を詐病していると疑われやすかった(46%が自殺 念慮を模倣しているとされた)
結果4(動機) • 評価者が推察した動機の中で、物質使用障害の患者は 「薬物目的」が有意に多かった。 • パーソナリティ障害の患者は「注目を集めたい」が最多 (50%) • その他の理由→「入院している友人に会いたいから」 「その患者が境界性パーソナリティ障害と診断を受けて いたから」
考察1 • 25%の患者が何らかの模倣を疑われ、そのうち8%は「強 く」または「確実に」模倣しているとされた。 • 重要なのは、今回評価したのはあくまで医師の「疑い」で あり、患者が実際に詐病していたかどうかを示したもので はないという点である。 • 本研究での詐病の疑いの頻度は、アメリカよりもやや低 かった。
考察2 • 自殺念慮を訴える詐病の疑いがある患者は、他の症状より も入院の可能性が高いと考察されている →長年にわたる受診歴を持つ患者は、特定の訴えが入院に 結びつきやすいことを認識している可能性がある • 一方で、詐病の疑いは、医療スタッフの偏見が影響してい る可能性もある →特に境界性パーソナリティ障害の患者に対しては、医療 従事者の否定的な態度が多く報告されている
考察3 • 患者と医師との関係の中で、患者の表現(態度)が変化 することもある →警戒的な医師には「操作的な人物」として映り、共感 的な医師には「打ちひしがれた人物」として映る可能性 • 精神疾患の症状と行動の関係は、必ずしも一致しない →声の性質・話者の特定・明瞭さ・頻度・長さ・内容・ 無視のしやすさなど、どの症状も確実な詐病の判別基準に はならない
考察5 • 病院のベット数不足 →医師が詐病と疑う要因に • 精神病理学に関する教育や、疾患プロトタイプへの理解 の欠如 →医師が独自の「私的プロトタイプ」を持つようになり、 詐病を判断している可能性
結論 • 詐病は従来、極めて稀な状態と考えられてきた →現代の精神科医は、詐病の疑いを持つ場合でも慎重に判断 すべきである • 明確な外的動機を特定するのは困難であり、症状の単純な パターンのみで診断してはならない • 多くの場合、詐病は正式な診断として記録されないが、 一度疑いを持たれた時点で、患者はそれまでとは異なる扱い を受けることがある
限界 • 回答率が44%と低かった →詐病の疑いが強い患者のみが過大に報告される「応 答バイアス」が生じた可能性がある (ただし、米国の同様の研究では本研究よりも高い回 答率であっても、詐病疑いの割合は本研究と同等ある いはそれ以上であった) • 診断記録が存在しない患者が19%(n=69)いた
補足 患者についての5段階評価スケール 1.該当しない 2.軽度に疑われる 3.中等度に疑われる 4.強く疑われる 5.確実とされる →1を「なし」、2.3を「軽度〜中等度」、4.5を「強度〜 確実」と3分類に集約して解析を行った
感想・批判的吟味 • 精神科救急に絞った状況で、患者の平均年齢38は若めかも • 疾患ごとにするとNが少ない、ばらつきがある • 評価者に医学生がいるのはどうなんだ?33%多すぎるでしょ • 専門医が7%しかいない →・アメリカの研究との比較の際に影響しそう。 ・精神科医としての経験が増えると詐病疑いの頻度は上がるの か?下がるのか?これって若手の精神科医の成長に使えそう(歴 戦の医者の臨床経験をスポイトできそう) • 国の情勢とか景気でも詐病の確率と動機は変わるよね