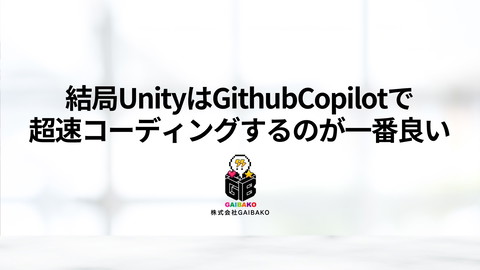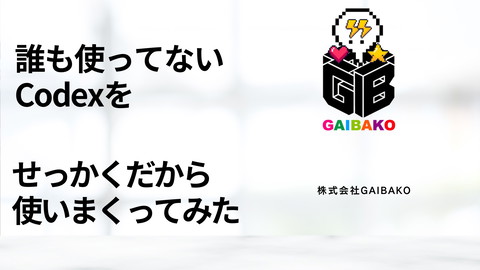アンディウォーホルの生涯
128 Views
October 20, 25
スライド概要
株式会社GAIBAKO代表取締役。 ゲーム制作、AI研究、イラスト。
関連スライド
各ページのテキスト
広告デザイナーとして成功した後 スープ缶を描いて大量生産アートを構築したら を描いて大量生産アートを構築したら テレビ 功 成 大 して調子に乗って工場をつくったりテレビを始めたり に 的 界 を始めたり 世 死をテーマにマリリン・モンローや 電気椅子 をアートにしたが をアートにしたが けど生還し 過激な作家に銃で撃たれたけど生還し 今でも現代アートの巨匠として扱われている 今でも 電気椅子 銃で撃たれた ル ル ホ ホ ー ー ォ ォ ウ ウ ・ ・ ィ ィ デ デ ン ン アア について 話 します。
キャンベルスープ缶 ― 「日常を“美術館に置いた”瞬間」 「ウォーホルは、“アートを消費社会の鏡”に変えた。 アンディ・ウォーホルは、広告の世界からアートの世界に飛び込んだ。 彼が選んだ題材は、毎日飲んでいたキャンベル社のスープ缶。 1962年、その作品を発表した瞬間アートの価値基準がひっくり返った。 それまでの美術は「個性」と「手仕事」を重んじていた。 だがウォーホルは、同じ缶を印刷のように何十枚も並べ、 “人間の痕跡”を消して見せた。 アートを工業製品のように作ったのは、彼が初めてだった。 この作品は単なる缶詰の絵ではない。 それは大量生産と消費社会そのものの象徴だった。 誰もが知る日用品を“作品”に変えたことで、 アートは特別な人のものではなく、 誰もが目にする現実の一部になった。 このとき生まれたのがポップアート、 つまり“大衆文化を美術の文脈で扱う”という考え方だった。 ウォーホルは、現代の広告やSNSにまで続く 「イメージが消費される時代」の始まりを告げたのだ。 キャンベルスープⅠ ビーフ
Factory ― アートを“仕組み”に変えた男 Factory=現代クリエイティブ産業のプロトタイプ キャンベルスープ缶で名を広めたアンディ・ウォーホルは、 次に“アートの作り方”そのものを変えた。 彼が設立した「Factory(工場)」は、ただのアトリエではない。 そこではアシスタントたちがシルクス クリーンを使い、 ウォーホルの作品を大量に印刷していった。ウォーホルはもう筆を取らない。 彼はアーティストではなく、プロデューサーになった。 作品はチームによって生産され、 ウォーホルは サインをするだけで完成とされた。 それは、 芸術を「手作業の神聖な行為」から “システムと しての生産”に置き換えた瞬間だった。 Factoryには、アーティスト、俳優、モデル、 ミュージシャン、 ドラッグとカメラが入り混 じっていた。 その混沌はやがてニューヨークの 文化発信地になり、 アートとファッション、 音楽、広告の境界が溶けていった。今日のクリ エイティブ産業―― たとえばチームで作る広告、 ブランド、映像プロジェクトの形は、 すべて このFactoryの構造から始まった。 ウォーホルは、“アートを作る人”ではなく、 “アートを作る仕組み”を作った人だった。
死と終幕 ― “死”すらも作品にしたアーティスト ウォーホルは、“死をもデータ化した最初の人間” ウォーホルは、生涯を通して「死」を描き続けた。それは悲しみの表現ではなく、メディアが死を“商品”として 扱う時代を見つめるため。彼はニュース写真から交通事故や電気椅子などのイメージを選び、 それらをシルク スクリーンで反復印刷した。 悲劇は繰り返されるうちに感情を失い、 “痛みのない死”として再生産されていく 冷たさを、現代社会の真実として提示した。マリリン・モンローの死をテーマにした作品では、 彼女の笑顔を 何度も複製し、偶像が死を超えて生き続ける仕組みを描いた。 そして1968年、ウォーホル自身が作家ヴァレリー・ソ ラナスに銃撃され、重傷を負う。彼は奇跡的に生還し たが、以後の作品には宗教や死の象徴が増えていっ た。その後、彼に帰せられる有名な言葉がある。 「未来には、誰でも15分間は世界的な有名人になれる だろう」 少なくともウォーホルの時代感覚を的確に言い表して いる。名声も、死も、メディアによって消費される時 代—— 彼はその現実を最も早く、最も美しく可視化し た。1987年、手術中の合併症で亡くなったが、 彼の作 品は今も複製され、世界中のスクリーンに映り続けて いる。 マリリンのディスパッチ