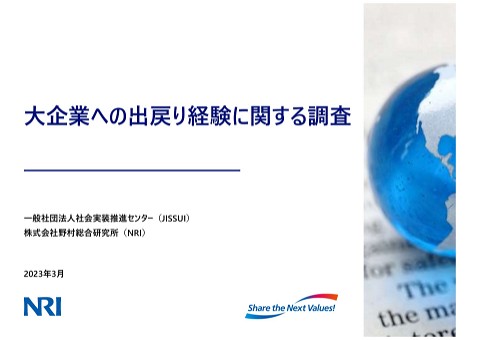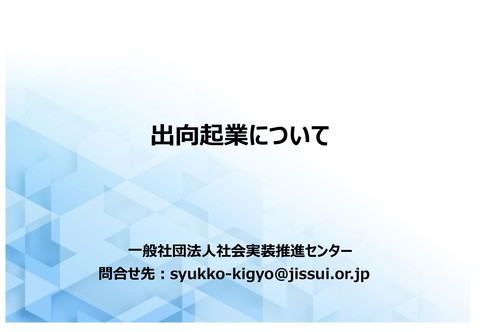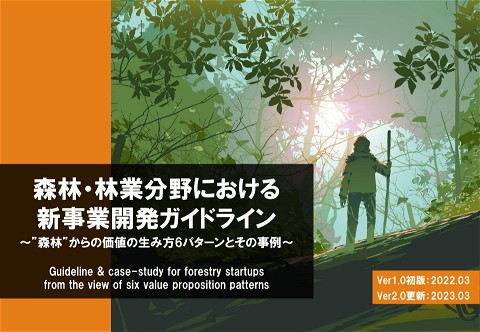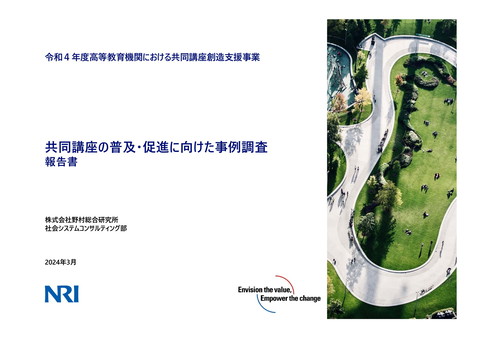共同講座R5補正_調査報告書
3.5K Views
March 31, 25
スライド概要
"旗"を掲げ、挑戦したい人を応援するメディアです。 第一線で挑戦する人のインタビュー・コラム、政策・ビジネスに関するレポート、公募の情報など、「じっくり読みたくなる」情報をお届けしています。note:https://flag.jissui.jp/ | 運営会社JISSUIの情報はこちらから→ https://jissui.or.jp/
関連スライド
各ページのテキスト
令和5年度⾼等教育機関における共同講座創造⽀援事業 共同講座の普及・促進に向けた事例調査 報告書 株式会社野村総合研究所 社会システムコンサルティング部 2024年12月
1 調査の目的・実施内容 2 事例:DOWAホールディングス株式会社×東北大学 3 事例:シナノケンシ株式会社×信州大学 4 事例:岩渕薬品株式会社×千葉大学 5 全体的な示唆 1
1.調査の目的・実施内容|目的 過年度調査の結果を踏まえ、昨年度の共同講座について幅広い視点で成果を捉えつつ、 実際の開設に向けた企業と⾼等教育機関の検討体制・方法についても把握した 調査の目的 背景、問題意識 具体的な検討事項 • 過年度調査で、企業内における受講者以外への波 及効果を把握したが限定的 • 共同講座の関係者は、共同講座を通じてどのような 成果・利点を得られたと考えているか? • また、大学への調査はあまり実施しておらず、特に大 学経営陣や学生、各教員等からの評価は未確認 • 共同講座で得られた成果・利点には、どのような 背景があるのか? 1 幅広い視点で 成果を捉える 2 • 企業と高等教育機関の「接点」の傾向が見えてきた 協働での 検討体制・ 方法を知る • 今後、共同講座の自走化に向け、どう講座を始めれ ばよいかについて、知見を共有することが求められる • 例えば、企業・大学で人材育成のための勉強会等を 始めたところから、講座開設につなげた例もあった。こ のような双方での議論が活発に行われる事例への探 求、深堀が必要 • 共同講座の実施に向けて、企業と⾼等教育機関は 人材育成課題・ニーズをどのような場ですり合わせて いるか? • 検討にあたって、ハードルや工夫の仕方はあるか? 令和5年度に採択・実施された共同講座より、3事例を抽出し、それぞれに幅広い関係者へのインタビュー調査を実施 2
1.調査の目的・実施内容|調査対象の選定 組織内で人材育成に対して多様な意見があることが想定されたり、 企業と⾼等教育機関で密に連携したと想定される講座を対象として抽出した 調査対象事業者を選定する観点 調査の目的(再掲) 調査対象事業者を選定する考え方・狙い 1 幅広い視点で 成果を捉える 2 協働での 検討体制・ 方法を知る これまで、当該テーマ等での人材育成の取組みが日常的でなく、 組織内で多様な意見や葛藤、捉えられ方があると予想される事業者 • 様々な意見を聞くことで、共同講座実施に係る組織内での壁も知れる • 高等教育機関との連携の初期段階で気を付けるべき点・壁等を確認できる ⾼等教育機関と密に連携し、会議等が開催された、あるいは そうしたやり取りを定期的に実施していることが想定される事業者 • どのようにして共同講座の内容を具体化していったか、その協議の進め方を把 握する 3
1.調査の目的・実施内容|調査対象事例の選定 関係各位より許諾いただいた3事例について調査を実施した 調査対象とした事例 DOWAホールディングス株式会社×東北大学 「DOWA×東北大学共創研究所」 シナノケンシ株式会社×信州大学 「デジタル人材育成共同研究講座」 岩渕薬品株式会社×千葉大学 「健康まちづくり共同研究」 4
1.調査の目的・実施内容|調査方法 共同講座の関係者に幅広くインタビューし、成果や検討過程を多面的に検証した インタビューの対象範囲 企業側の体制 共同講座 担当者 • 共同講座の企業側の主担当者 受講者 (社員) ⾼等教育機関側の体制 共同講座 担当者 • 共同講座の高等教育機関側の主担当教 員 • 共同講座を受講した社員 (インタビュー自体は1名程度に実施) 受講者 (学生) • 共同講座を受講した学生 (インタビュー自体は1名程度に実施) 受講者 上司 • 受講者の直接の上司 (インタビュー自体は1名程度に実施) 他の講座 担当教員 • 上記の主担当者とは別に、講座の企画や 授業そのものを担当した教員 (インタビュー自体は1名程度に実施) HR担当 • 人事・総務部門等における人材開発担当 者 産学連携 担当部門 • 産学連携推進部門の教員やコーディネー ター 経営層 • 共同講座を統括する役員 経営層 • 産学連携を担当する理事・副学長や学部 長 連携 5
1.調査の目的・実施内容|調査項目 調査の目的ごとに、“事実確認” “評価” “今後の展望” を確認した 調査項目の全体像 調査の目的(再掲) 1 調査項目の例 事実確認(共同講座との関わり) ✓ 共同講座に参加した・関わったきっかけ ✓ 共同講座との関わり方、立ち位置 幅広い視点で 成果を捉える 共同講座に対する評価 ✓ インタビュー対象者自身の変化(行動変容や参加により受けたメリット、等) ✓ 組織への波及効果 共同講座に係る今後の展望 ✓ 共同講座や産学連携での人材育成に関する今後の取組み・要望 ✓ 共同講座や産学連携での人材育成を進める上での課題 2 事実確認(検討体制・方法) ✓ 企業-大学が人材育成課題について議論する場面・お相手 ✓ 検討の場の位置づけや議論内容 協働での 検討体制・ 方法を知る 会議体等の検討の場に対する評価 ✓ 議論結果が産学連携や人材育成の取組みに与える影響 ✓ 検討の場で工夫している点 会議体等の検討の場に係る今後の展望 ✓ 議論の場に関する今後の開催・参加意向 ✓ 議論内容の活かし方や課題に係るご意見 6
1 調査の目的・実施内容 2 事例:DOWAホールディングス株式会社×東北大学 3 事例:シナノケンシ株式会社×信州大学 4 事例:岩渕薬品株式会社×千葉大学 5 全体的な示唆 7
2.事例:DOWAホールディングス株式会社×東北大学 「DOWA×東北大学共創研究所」 2023年度の共同講座の概要 共同講座の背景と目的 金属加工業界において、自動車や情報機器向けを中心 に、高特性な銅合金の供給を主な事業領域としている。 効率的に新しい価値を創造し、今後も中国メーカーに勝 ち続けるためには、これまでの材料組織制御をベースとした 「職人型素材開発人材」を「DX型素材開発人材」へ育 てていく必要がある。即ち、データ駆動型の素材開発技 術、並びに、データ駆動型開発に供せる正確なデータ取 得技術を有する人材の開発が不可欠である 東北大学大学院工学研究科 DOWAホールディングス株式会社 教授・機構長 (コーディネータ) 特任教授 (運営総括アドバイザー ・取締役) 自社社員 社内の各開発拠点において、DX技術を手の内化し、活 用しながら材料開発分野を牽引する人材が必要である TA (大学院・学部学生) 連携高等教育 機関の学生 自社社員との交流の中で、学生が社会人になったときの 開発スタンスのギャップを緩和させると共に、学生自身の 研究がどのように産業界で貢献するのかといった新しい視 点を取入れてもらうことに期待している 講義や実習を担当する自社社員が学生へ教えることによ るリカレントの場としても考えている 人材育成テーマ・分野を 選んだ背景と狙い 人人 材材 開戦 発略 課・ 題 自社社員 将来的にはDX技術を活用しながら材料開発分野を牽 引する人材となることに期待している。本講座を通じて、 DX技術に興味を持つ社員を増やし、これら技術を取込 むといったモチベーションの向上も期待している 連携高等教育 機関の学生 非鉄業界に興味を持つ学生を増やし、DX技術を有する 学生の採用に繋げたい 共同講座で特に注力す るポイント • 計測技術の確立 • 新銅素材創成に関する共同研究を通した若手人材の 育成 • 工場実証実験を通した、学生への事業化意識の植え 込み 期 待 し て い る 変 化 連携体制 出所)2023年度の事業者への書面調査、提出された実績報告書等より作成 教授 (運営⽀援責任者) :専任教員 学生募集 受講者 特任教授 (運営総括責任者 ・事業開発部長) 連携 DOWAメタルテック 磐田技術センター (銅合金開発拠点) 社員選定 工学部・工学研究科学生 企業社員 申込・受講者数等 属性 申込者数 受講者数 自社社員 26 26 連携高等教育機関の学生 43 43 8
2.事例:DOWAホールディングス株式会社×東北大学 「DOWA×東北大学共創研究所」 ⾼等教育機関との連携の狙い、共同講座の成果 連携の経緯、狙い、課題 連携の経緯 連 携 の 狙 い ・ 利 点 連 課携 題に 等係 る 連携を主導した事業開発部は、自社グループの各部門の研 究開発推進や横串活動を支援する組織で、産学連携も主 要業務の一つである。従来より東北大学大学院環境科学 研究科に寄附講座を設置、運営しており、かつ大学本部とも 包括連携協定の締結を行い、交流を行っていた。将来を見 据えた研究を行う研究組織・社内の研究員の専門性を上げ、 研究者のモチベーションを向上させる場の必要性を感じていた ところ、大学より全部局との共創が可能である共創研究所の 紹介を受け、目指したい方向が一致していることを確認し、 2021年11月に大学の産学連携担当理事より技術・事業開 発管掌取締役に説明があり、設置に向けて一気に加速、 2022年4月に共同講座を設置した 企業側 東北大学は材料、特に金属材料に関して優れた研究開発 実績を持っており、さらには近年DXおよびGXに関する開発に も力を入れており、特に自社内では技術を有していないMIを 活用した材料開発について知見を保有していた。東北大学と 連携することでこれら最先端技術の獲得を期待した 高等 教育 機関側 • 産学連携による人材育成の実現 • 企業等と連携体制の強化、繋がりの獲得 • 学生の、企業等における実践的な学びの受講 企画時 対経営層:特になし 対現場:現場ニーズに合致する講座内容にする必要があった 対⾼等教育機関:企業側、高等教育機関側の構成メン バーが共に多忙であり、企画等の打合せを開催するのに苦労 した 運営時 対経営層:特になし 対現場:講座内容の自社ニーズと高等教育機関側が望ん でいる内容のすり合わせ 対⾼等教育機関:同上 出所)2023年度の事業者への書面調査、提出された実績報告書等より作成 効果促進施策、成果、今後の展望 受講者 への フォロー アップ 実施前 事業開発部長が研究所長クラスへ昨年の共同研究の実績 を対面で事前説明し、受講への理解促進と受講者への動 機づけを依頼した 共同講座と一部連動する社会人博士号取得支援制度につ いて社員全員がアクセスできる社内サイトに概要を掲載し、受 講への動機づけを図った 実施中 ー 実施後 来年度の受講者の拡大のため、講義終了後、社内ポータル サイトや社内報にも共同講座の内容等について広報した 人材育成の達成 状況、評価方法 狙い通りの効果が得られた。受講者へのヒアリングを通じて機 械学習やMIを用いた新規な合金開発への興味が深まってい ることを感じられた。実際に講義受講者(自社社員)は、2023 年度には前年の同講座と比べ約50%増加した 受講者からの フィードバック内容、 観測された 行動変容 自社社員:昨年度講座はMI技術の初歩的な内容が中心 であったが、今年度は自社内で取り扱っている銅合金を軸と した応用編を作成、好評であった。DX技術を利用した材料 開発等のセミナーや勉強会や当グループ内の生産技術部門 が行っている実例紹介等の横串活動への参加率も向上した 連携⾼等教育機関の学生:本講義は、工産学連携・共創 の重要性の理解や将来の職業を考える上で貴重。また、現 場体験型WSは、大学での実験研究との相違や共通性を認 識する絶好の機会となり、学生の材料開発や工学研究モチ ベーションの向上にも有意義なものであった 人材育成効果を 踏まえた処遇・採 用等の検討状況 講座を受講する自社社員との交流や講義、実習の中で業界 に興味を持つ学生を増やすことで、自社内では持ち合わせて いないDX技術を有する学生の採用に繋げたいと考えている 今後の成果の 把握方法、 追跡調査方法 受講者のうち、2022年度は1名が博士後期課程に在学中、 2023年度は1名が東北大学博士後期課程に編入学予定で あり、その後のフォローアップも進めていく計画である 9
2.事例:DOWAホールディングス株式会社×東北大学 「DOWA×東北大学共創研究所」 主な講義の内容 No. 1 日程 2023年10月 実施時間 講義名 概要 1.5時間×8コマ 計12時間 講義:材料科学工学 特 別講義 (2022年度より 継続) ①DOWAの会社紹介と東北大学との取組み ②自動車用銅合金材料および量産技術開発 ③④銅合金の基礎 と 次世代銅合金の開発最前線 ⑤銅合金薄膜の塑性変形挙動 ⑥状態図をベースとした合金開発 ⑦機械学習による合金開発 ⑧データ駆動型の新銅合金開発 • DOWAグループの研究拠点にて、大学と企業側研究者の交流を通じ、学生は工場 でのモノ作りの体感と企業での試験を体験、企業側研究者は講師となることで学生 へ教えることによる学び直しをする機会とする。 実際に条件を振った銅合金サンプル を作製、評価を行い、加工条件の違いによる特性発現のメカニズムを考察 2 2023年11月 7時間×4日間 計28時間 実習:現場体験型ワーク ショップ (2022年度より 継続) 3 2023年5月~ 2024 年2月 自社:135時間 大学:200時間 共同研究:極薄板材の 引張試験時における破断 挙動に関する研究 (2022年度より継続) • 極薄材の引張試験時における変形挙動の解明と機械特性の正確な評価方法の 確立を行い、将来的には評価法のJISや国際規格化を目指す 4 2023年5月~ 2024 年2月 自社:150時間 大学:200時間 共同研究:新規高強度 高導電銅合金 (2023 年度より新規) • 機械学習による新規銅合金の組成を探索し、合金サンプルを製作、評価を実施 • 機械学習に必須となる系統的かつ多量のデータ取得の実現に向け、ハイスループット 実験計測系(硬度および導電性の自動マッピング計測)の構築・検証に取組んだ 出所)2023年度の事業者への書面調査、提出された実績報告書等より作成 10
開設の 準備 2.事例:DOWAホールディングス株式会社×東北大学 「DOWA×東北大学共創研究所」 企業技術者と大学教員のフリーディスカッションを繰り返すことで、 双方の課題感・関心を反映させたプログラムに落とし込むことができた 実施 内容 講座の 成果 講座の土台となったポイント 共同講座の主な成功要因と成果の全体像 開設の準備 実施内容 講座の成果 企業技術者と大学教員によるフリーディス カッションを通じて講座テーマを検討 双方の課題感・関心を 反映させたプログラムを構築 企業の研究レベルが向上し、 大学としても研究活動が活性化 • DOWAの担当者および現場社員から示される課 • 題について、大学からは、講座の実施手法や講 座を担当する教員についての適切な提案がなさ れ、座学やワークショップといった具体的な中身に 落とし込まれていった 大学側の関心や最新の研究成果もプログラムに 企業側 • 専門的な知識を体系的に学べ、企業内の知見 が増えた • まだ答えのない“研究”に共に取組むことで「考え 方・考える力」が企業社員に身についた • 若手社員の知見や、ものづくりにおける実行力・ ディスカッション能力が向上した 双方 • 共創研究所の仕組みをベースに、両者がともに知 恵を絞り、講座テーマを検討した 企業側 • 企業側の講座担当者が開発現場の課題・ニーズ • を広く把握できる立場にいた 大学に対して学びたい方向性(企業では学べな い理論・メカニズム等)を提示し、大学とのフリー ディスカッションをリードした 反映させた 大学側 • 担当教員が改めて学内の研究情報を精査し、 企業への提案の下準備を進めておいた • 企業側とのディスカッションには複数の専門分野 の教員が関わり、議論に広がりをもたらした 大学側 • 共同研究が増え、教員の実績になった • 大学教員にとって、自身の研究が世の中でどのよ うに役に立つかを知ることができた • 一部の大学教員では、通常は一人でやる実験を、 補助員と実施できて時間の節約になった • 学生が企業の研究者の働き方をイメージできるよ うになった 講座の土台となったポイント 共創研究所のスキーム 経営層の理解と後押し 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2022~2024年度に実施した各調査結果より作成 11
2.事例:DOWAホールディングス株式会社×東北大学 「DOWA×東北大学共創研究所」 開設の 準備 実施 内容 講座の 成果 講座の土台となったポイント 講座テーマをあらかじめ設定せずに、様々なステークホルダーを巻き込む形の フリーディスカッションを行ったことで、双方がニーズや関心を伝えやすい状況となった DOWAと東北大学の検討プロセス Step1-1 並 行 し て 実 施 フリーディスカッション 企業 大学 Step1-2 大学シーズ (教員の研究内容) の整理 • 大学の担当者側で、改めて研究科内の教員の専門や研究内容の精査を行った • また、企業担当者が大学に籍を置いていたことで、お互いの事情も把握しやすかった • 共創研究所の枠組みによって、学内の様々な教員へ依頼しやすかった 大学 Step2 企業ニーズ の具体化 企業 • 当初は講座テーマが決まっていなかったが、技術や研究を進展させるためには、深い知見・視 座の獲得が必要だという課題意識があった • 両者がともに知恵を絞り、講座テーマの設定から一緒に考えて何かを成し遂げよう、という雰 囲気で議論が始まった。共創研究所という仕組みには、何をするか自由に考えられるという “余白”があるからこそ、企業が目指す姿に対し、大学としてできることを様々な面で検討する ことが可能になった 大学 • 企業側担当者は事業開発部門の責任者であり、開発現場の課題・ニーズが集まる立場 • DOWAの現場の技術者と東北大学の教員が直接議論をする場が開催され(現地あるい はweb)、複数の専門分野の教員がかかわることで、議論に広がりがもたらされた • とにかく何でも話してみようという雰囲気で行われた(話題は、必ずしもゴールに直結しなく てもよい) Step3 大学シーズ・ニーズ の打ち返し 企業 大学 • 通常の共同研究とは異なり、自由に設計できる余地がある枠組みだったからこそ、材料自 体はDOWAの関心に応じて設定しつつ、大学側の関心や最新の研究成果をプログラムに反 映させたり、学生の教育という要素を混ぜ込んだりするような議論にまで発展させられた 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2022~2024年度に実施した各調査結果より作成 12
2.事例:DOWAホールディングス株式会社×東北大学 「DOWA×東北大学共創研究所」 現場で実際に抱えている課題を講座内容に反映するとともに、 上層部とも講座の意義を共有した 開設の 準備 実施 内容 講座の 成果 講座の土台となったポイント ◼ 共同講座は、研究活動の推進・強化を図る「共創研究所」の枠組みの中で設置された。 ◼ この枠組みを活用し、現場から上層部まで様々な関係者が企業の課題について検討する場を持った。 DOWAと東北大学が人材育成ニーズ・課題について検討する場 共同講座の企画 (企画・立案時) 参加者 協議内容 や様子 • 企業側経営層・担当者 • 大学側担当者・他教員 ※企業・大学の上層部とも 適宜共有・議論 • 共創研究所の枠組みに基 づき、企業・大学の担当者 の双方が一定の業務量を 割くことを定めた状態でス タート • 企業が提示する大きなテー マをもとに、右記の技術者 とのフリーディスカッションも 踏まえ、大学側の関心も 合わせて内容をすり合わせ DOWAの技術者と 東北大学の教員の フリーディスカッション • 企業側担当者・技術者 • 大学側担当者・他教員 ※企業上層部も適宜参加 • 企画段階から開催し、企 業の技術者が抱えている 課題を探索 • とにかく何でも話してみよう という雰囲気で行われた • 見えてきた課題は共同講 座の内容に反映 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2022~2024年度に実施した各調査結果より作成 運営に係る定期的な会議 • 企業側担当者・経営層 • 大学側担当者・他教員 ※企業・大学の上層部とも 適宜共有・議論 • 共同講座や関連する共同 研究の進捗が主な議題 • 「実は○○も課題である」と いったこぼれ話が出ることも ある DOWA担当者と 東北大学経営層の ディスカッション • 企業側担当者 • 大学側経営層 • 求める人材像や企業から 大学への期待について、自 由な意見交換をする • 企業からは、大学のスタン スとして産業寄りになる必 要はなく、課題の深掘りを 手伝ってほしいと伝えてい る 13
2.事例:DOWAホールディングス株式会社×東北大学 「DOWA×東北大学共創研究所」 共同講座の実施内容の概要 開設の 準備 実施 内容 講座の 成果 講座の土台となったポイント 実施プログラム 実施主体・プログラム 概要 ✓ DOWAグループ研究拠点にて、現場体験型ワークショップを実施 ✓ 企業側研究者が講師となり、学生は工場でのものづくりや試験等を体験した ✓ 機械学習により予測された新銅合金素材の製造・評価を実施してもらうことで、学生に事業化視 点を意識付けた 企業と大学の 共同研究 ✓ 極薄板材の引張試験時における破断挙動に関する研究及び新規高強度高度導電銅合金のサン プル製作、評価を実施した ✓ 企業・大学がそれぞれ、これまで積み重ねてきたデータ・機械学習による予測技術をお互い提供しあ うことで、新素材の提案を目指した DOWA 学生向け 実習 東 北 大 学 企業の社会人・ 学生向け 講義・実習 ✓ 東北大学教員による最新の研究動向や、素材開発技術の特別講義を実施した ✓ DOWAからは、企業スケールでの研究開発事例や将来に向けた課題について講義を実施した。 講義内で企業紹介も開催し、わかりやすく学生も真剣に聞いていたと好評だった 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2022~2024年度に実施した各調査結果より作成 14
開設の 準備 2.事例:DOWAホールディングス株式会社×東北大学 「DOWA×東北大学共創研究所」 実施 内容 講座の 成果 講座の土台となったポイント 講義から得られる専門知識に加え、 答えのない研究を大学と取組むことで、考えるための基礎体力を身につけることができた 共同講座で得られた成果と将来的な期待(企業側) 企業側 人材育成面 事業運営面 能力の向上と定着 対大学 ものづくりのレベルがあがった 知識の習得 得られた 成果 研究の進め方が身についた 思考力の強化 振り返りによる 定着 将来的な 期待 • 機械学習を活用した材料研究・開発に関する知識を体系的にか つ研究への活用方法を学べ、企業内の知見が増えた • 業務上の課題の背景にあるメカニズムを学ぶことができた • 具体的な解析結果を得ることができた • まだ答えのない“研究”に共に取組むことで「考え方・考える力」が企 業社員に身についた • 実習や大学教員とのディスカッションへの参加で、若手社員の知 見や、ものづくりにおける実行力・ディスカッション能力が向上した 再確認・整理等を通じて知識が定着した • 通常の開発の進め方とは異なり、原理原則に立ち返って条件を設 定するなど、考えを深める良いきっかけになった • 業務として課題に取組むことができたため、学んだ内容をじっくりと 振り返ることができた 企業と大学の関係が深まり、別の共同研究や 人材育成の取組みにつながる可能性がある 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2022~2024年度に実施した各調査結果より作成 受講者の行動変容 学んだスキルを開発や製造 に活用するようになった • 講座で学んだ素材のメカニズ ムを実際の製造工程に活か すことができた • 企業の開発において実験室 レベルでの取組みが増え、開 発がよりはかどるようになった • 受講した若手がより積極的に アイディアを出して研究を進め てくれるようになった 大学との距離が近くなった • 企業側が大学教員へ相談し やすくなった • 複数の分野の教員とのつなが りができた 対学生 企業の認知度が上がった • 説明会に来る学生が増えた • 講座を通じて、自社が求める 人材の育成・発掘ができた 本講座・研究を通じて企業・大学が それぞれアピールできる成果を生みたい 15
2.事例:DOWAホールディングス株式会社×東北大学 「DOWA×東北大学共創研究所」 開設の 準備 実施 内容 講座の 成果 講座の土台となったポイント 企業と関係を深めて社会実装を目指す好事例となった。 今後、共創研究所での取組み活性化など、さらなる共同研究・人材育成が期待される 共同講座で得られた成果と将来的な期待(大学側) 大学側 教員にとって 研究活動の活性化に繋がった • 共同研究が増え、教員の実績になった • 共同講座を通じて得られるフィードバックが刺 激になった 社会のニーズを把握できた 得られた 成果 • 企業との共同研究を通して、産業界での実装 に向けて求められる内容が明確化された • 「必ず社会実装につなげる」という強い意志で 研究に取組む必要がある、という意識が教員 に広まった 大学内での自身の研究アピールを従来以上 に行えるようになった • これまでの共同研究は、企業の研究者と先生 が一対一でやっており、内容を先生同士で知 る機会がなかった一方、今回のような取組み は学内でもアピールしやすかった 将来的な 期待 学生にとって 大学組織にとって 自身の研究が社会でどう生かせるのかを考え る良い機会となった 東北大学における産学連携の良い事例になっ た • 実際に銅合金作成の実験を行うことで、座学 で学んできた内容を実践することができた • 研究と社会の繋がりを実感でき、今後の研究 に対し、より一層身が入るようになった • 企業との連携のTipsを蓄積することができた • 学内においても、今回の取組み事例の存在が 他学科へ広まった • 共同研究の本数が増加する効果が表れた 研究分野以外への学びにも繋がった 共創研究所での取組みに関する今後への示 唆を獲得した • 自身の研究内容とは異なる材料への学びを得 る良い機会となった(例としては、普段は半導 体の研究をしていた学生が、銅の研究に携わっ た) 企業や業界への理解を深められた • 実習を通じて銅業界への関心が高まり、実際に 就職する人も現れた 企業と大学の関係が深まり、別の共同研究や 人材育成の取組みにつながる可能性がある 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2022~2024年度に実施した各調査結果より作成 • 本講座を通じて、共創研究所を一つのシステム として定型化することができた • 一般的な共同研究では個人(教員等)の力 量に左右され、異動により終わってしまうことも 多い。共創研究所の枠組みで組織対組織で 繋がることによって、安定性が増した 企業の若手研究者が大学で学び、学んだ知識を企業に還元する 好循環をさらに活性化していきたい 16
2.事例:DOWAホールディングス株式会社×東北大学 「DOWA×東北大学共創研究所」 共創研究所のスキーム及び経営層の巻き込みを通じて 企業・大学双方が長期的にコミットできる体制が構築できた 開設の 準備 実施 内容 講座の 成果 講座の土台となったポイント 講座の土台となったポイント 1 共創研究所の スキーム 企業・大学の双方が主体的に動ける仕組みの構築 • 共同講座の立ち上げ以前、共創研究所の構想段階で、過去の寄付講座、共同研究講座等の経験を踏 まえ、企業・大学双方が一定程度のエフォートを提供する仕組みが必要と考えた • 共創研究所のスキームの下、一定の人員・予算を投入して本講座を実行することができた • 企業側担当者はクロスアポイントメント制度で大学にも籍を置いている • 大学側の担当者も共創研究所の枠組みで一定時間のコミットが定められている • 企業側担当者が大学内でも活動できたことから、双方の橋渡し役となり、各種調整を実施できた 活動の“余白” • 通常の共同研究と異なり、課題テーマの設定から、企業・大学で自由に考えられる“余白”がある枠組みだっ たからこそ、大学側の関心や最新の研究成果をプログラムに反映させたり、学生の教育という要素を混ぜ込 んだりすることもできた 2 経営層の 理解と後押し 経営層の後押しを得て、長期的な取組みを実現 • 研究開発担当の経営者が講座運営に関与し、その他の経営層にも定期的に報告するなどして、経営層を 積極的に巻き込んだ • 経営からの後押しを受けながら、企業として必要な成果を出せるように、目標に向けて数年単位で動くことが できる状況を構築した 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2022~2024年度に実施した各調査結果より作成 17
2.事例:DOWAホールディングス株式会社×東北大学 「DOWA×東北大学共創研究所」 【参考】 東北大学「共創研究所」制度 開設の 準備 実施 内容 講座の 成果 講座の土台となったポイント ◼ 共同研究や人材育成など、産学共創活動を企画・実施するための連携拠点を、大学内に構築する制度となっている。 ◼ 活動内容は限定せず、幅広い活動を随時企画・遂行できる。また、大学の教員、知見、設備などに柔軟にアクセスできる。 出所)東北大学ウェブサイト 18
1 調査の目的・実施内容 2 事例:DOWAホールディングス株式会社×東北大学 3 事例:シナノケンシ株式会社×信州大学 4 事例:岩渕薬品株式会社×千葉大学 5 全体的な示唆 19
3.事例:シナノケンシ株式会社×信州大学 「デジタル人材育成共同研究講座」 2023年度の共同講座の概要 共同講座の背景と目的 人材育成テーマ・分野を 選んだ背景と狙い 自社の主力事業は厳しい価格競争に晒されており、価 格競争力がある競合他社と性能面での差別化を図りつ つ、業務の効率化を進め、市場での競争力を維持するこ とが求められる。これらを実現する人材として、①付加価 値を高められる分野へ参入するために機械学習等に精 通し高度な設計を行える人材や、②既存市場で競争力 を維持する為に保有する各種データを有効に活用して業 務効率化を進められる人材が必要となる これらの背景から、共同講座を通じて、データサイエンスや AIのスキル、高度な制御設計技術、社内外の人と技術 的な内容について円滑にコミュニケーションを取れるスキル の習得を目指す 自社社員 データサイエンスが使える人材を育成して、業務の効率化 と新しい技術の実装をすることで自社の競争力を向上さ せ、売上や利益の向上に繋げる 連携高等教育 機関の学生 学生に対する自社の知名度を向上させ、デジタル人材活 躍の場があることを周知すること 自社社員 データサイエンスを使って何ができるかを理解し、データサイ エンスを適用して新しい価値の創出ができるようになる 連携高等教育 機関の学生 事例の学習を通じて、将来の技術者としての姿を想像で きるようになる。また、学びへのモチベーションにつなげる 共同講座で特に注力す るポイント 本共同研究講座は2022年に設置したもので、学習した 技術を製品に実装するという成果も出た。一方で、実施 後アンケートでは課題解決型学習で理解を深めたいと言 うフィードバックが多かったため、今年度は実務に関わる課 題解決型学習を増やすことを改善点として注力する 人 材 開戦 発略 課・ 題人 材 期 る 待 変し 化て い 出所)2023年度の事業者への書面調査、提出された実績報告書等より作成 連携体制 信州大学工学部 責任教員 教授 シナノケンシ(株) (ASPINA) 担当教員(特定雇用) 准教授 (専 任教員 ) 担当教員(特任) 特任教授 総務本部 副本部長 総務本部 IT改革推進部 部長 開発技術本部 本部長(企画/統括) 協力教員 教授 教授 教授 准教授 准教授 助教 総務本部 人事課 総務本部 IT改革推進部 DX推進係 (社内企画) 相互教育 受講者 常務 (総責任者) ※2022年度 受講者 からDX推進 専任者 を設置 信州大学工学部学生 シナノケンシ(株)社員 申込・受講者数等 属性 申込者数 受講者数 自社社員 68 68 連携高等教育機関の学生 120 120 20
3.事例:シナノケンシ株式会社×信州大学 「デジタル人材育成共同研究講座」 ⾼等教育機関との連携の狙い、共同講座の成果 連携の経緯、狙い、課題 連携の経緯 連 携 の 狙 い ・ 利 点 2019年に信州大学工学部と包括連携協定を締結し、相互 教育や共同研究に取組んでいたところ、信州大学工学部よ り包括連携協定を発展させて共同講座を設置する提案を受 けた。経営層も最新のデジタル技術を活用して新しい価値を 創出できる人材の育成を行う必要があると考えており、共同 研究と相互教育に加えてデータサイエンスの教育を盛り込む 形で2022年に共同研究講座を設置した 企業側 • 自社に不足している技術を体系的に学ぶことができる • 人材育成のための適切な教材を獲得できる • 学生に対する認知度が向上する 高等 教育 機関側 • 企業等と連携体制の強化、繋がりの獲得 • 学生の、企業等における実践的な学びの受講 企画時 対経営層:短期的には利益を生まない活動である一方で、 一定の出費と別途工数が必要となることに対して理解をして もらうこと 対現場:各部門から受講者を選定してもらい、通常業務を 止めて、教育に参加してもらう時間を確保すること 対⾼等教育機関:参加教員・役割や、企業から派遣する 特任教授の報酬の支払い方法等の調整 連 課携 題に 等係 る 運営時 対経営層:人材の育成はすぐに収益に貢献できないために 経費の負担の根拠や得られる利点を合意してもらうこと 対現場:受講者の選出や教育時間の捻出、日常の業務と 教育時間の調整に協力してもらうこと 対⾼等教育機関:講座内容の調整 出所)2023年度の事業者への書面調査、提出された実績報告書等より作成 効果促進施策、成果、今後の展望 受講者 へのフォ ローアッ プ 実施前 自社社員には、受講前に講座の目的や進め方を事前説明 実施中 自社社員が参加する講座で、受講者以外の社員を専任者 として設置し、講義の前後でフォローの会を実施したり、確認 試験に立ち会ったりした。さらに、一部の講座では、個人毎に 進捗を確認し、学習が進むようフォローした 実施後 理解度や定着度、難易度、その他改善点や講座内容を適 用可能な実務についてアンケートで確認 人材育成の達成 状況、評価方法 受講者からのフィー ドバック内容、 観測された行動変 容 制御講座では、製品の課題について検討し、講座の成果を 今後一部製品のシステムへ実装する予定 DE/DS講座では特にPBLを通して学んだことを実際の業務改 善に活かすよう、社員同士が議論できるようになった オンデマンド型のDE/DS講座で、講座内容や難易度、今後の 活用場面についてアンケートを実施し、受講者が内容に満足 し、難易度も丁度良いことが確認できた。ただし、理系社員 以外では難しいとする様子もあり、今後の課題として検討する 活用場面についても様々な意見があり、これまでとは違った視 点を社員に与えることができ、新たな解決策が考えられている ことがわかった。なお、PBL形式の講座でも、受講者が学んだ ことを実務に活かしていた 人材育成効果を踏 まえた処遇・採用 等の検討状況 学生からの応募数が増えた 自社社員に関しては、手当の追加や昇進等を検討している が、講座への参加だけで判断することは難しい。スキルを活か せる社員を適正に配置して昇給や昇格などに繋げて行きたい 今後の成果の 把握方法、 追跡調査方法 受講者に対し、アンケートやインタビューを実施し、企業担当 者や大学教員で振り返りを行う 21
3.事例:シナノケンシ株式会社×信州大学 「デジタル人材育成共同研究講座」 主な講義の内容 No. 日程 実施時間 講義名 概要 1 2023年4月~7月 12時間 先端産業論 学生に向けての講義で、主に開発設計時の課題の克服事例の紹介と課題克服に活 用した工学的な技術や分析方法の講義 2 2023年5月 ~ 2024年2月 16時間 制御講座(PBL) 社内の課題を持ち寄り、昨年度までに座学やPBLで学んだ知識を使って、適時教員から 助言や指導を受けながら、受講者で解決策を考える課題解決型講座 3 2023年6月 ~ 2024年1月 16時間 DE/DS講座(PBL) 社内でDE(データエンジニアリング)/DS(データサイエンス)の技術と社内保有のデー タで解決できそうな課題を持ち寄り、教員と共にデータの分析やAIの活用方法などを試 しながらこれまでの座学で学んだ知識を定着させるための課題解決型講座 4 2023年12月 ~ 2024年2月 DE講座:30時間 DS講座:25時間 DE/DS講座 (オンデマンド) DEおよびDSの基礎について、信州大学のオンライン学習システムを活用して、自社社員 が業務の隙間時間を活用して学べるようにした講座で、データの取り扱いの基礎から 様々な分析手法とその理論についての学習を実施 出所)2023年度の事業者への書面調査、提出された実績報告書等より作成 22
3.事例:シナノケンシ株式会社×信州大学 「デジタル人材育成共同研究講座」 開設の 準備 実施 内容 講座の 成果 講座の土台となったポイント 経営層の理解を背景に、大学との密な関係性を構築した上で、 PBLによる実践的な学びを進めることで、受講者の行動変容につながる成果を得た 共同講座の主な成功要因と成果の全体像 開設の準備 実施内容 講座の成果 両担当者及び産学連携コーディネーターの 仲介による、良好な関係性の構築 企業ニーズに合わせた 課題解決型学習(PBL)の実施 受講者の挑戦意欲の向上、 大学における産学連携の好事例に 座学や共同研究に加え、企業側のニーズに沿った 企業側 • ○○をやろう、という前向きな意識が醸成された • ○○ができそう、といった仮説の筋が良くなった • 講座を通じて得た知見に基づき新たな技術を試 行し想定どおりの効果を上げるなど、実務への活 用がイメージしやすくなった • 講義を通じて学生のシナノケンシへの関心が高 まった 企業側 • • 大学側の状況・目線に合わせて、企業・大学の 双方にとって実現可能性が高くなるようなニーズを 提示した 大学側の反応に沿って、柔軟に企業側のニーズを 調整した • テーラーメイドのPBLプログラムを大学側が提供した 大学側 • 学内教員のシーズをあらかじめ整理し、適切な教 員を講座に配置するなどして学内調整を円滑に 実施した • 大学側 • 社会人向けに伝わりやすい講義手法を学べた • 教員の研究内容を実務向けに拡張できた • 手に入りづらい実データをもとにデータ分析を行うこ とができた • 学んだ学問の活かされ方を学び、学生のモチベー ションが向上した • 参加学生は研究成果を国内外の学会で発表し、 学会賞も受賞 両者間に産学連携コーディネーターが入り、伝えに くい内容を適宜翻訳・補足し、円滑に進行した 講座の土台となったポイント 経営層の講座に対する理解の深さ、コミットメントの強さ シナノケンシと信州大学による包括連携協定の締結 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2022~2024年度に実施した各調査結果より作成 23
3.事例:シナノケンシ株式会社×信州大学 「デジタル人材育成共同研究講座」 深い相互理解に基づく強固な信頼関係を軸に、 実現可能性の⾼い要望や提案を交わすことができた 開設の 準備 実施 内容 講座の 成果 講座の土台となったポイント シナノケンシと信州大学の検討プロセス 1 Why の整理 経営層の巻き込み 2 企業 大学 What の提示 企業ニーズを伝える 3 企業 How の打ち返し 大学 大学シーズを提示する • 信州大学から、シナノケンシ経営層に対して本講座を実施するそもそもの理由・意義を検討する重要 性を伝えた • 企業側の経営層・担当者間の定期的な打合せにて、経営層の意向や目的感を把握した • 大学と連携することで想定される変化について、小さなものでも余すことなく報告し、経営層の期待を 醸成した • 大学側の時間軸に合わせ、数か月単位で解決したい課題ではなく、数年後をイメージした目的感 (ビジョン)を大学と共有した • オープンイノベーションをすべく、一方的に企業のニーズを提示するのではなく、ともに作り上げていこうとい う姿勢を心掛けた • 企業側の講座担当者が現場の実務も担当していたことから、実業務の課題に対する深い洞察をベー スに、大学側とのコミュニケーションをスムーズに行うことができた • 企業から提示された「数年後にこう在りたい」というゴールに対して、どのように大学としてアプローチすべき か、できるかを検討した • 担当教員のバックグラウンドを鑑み、大学側として受けられるテーマを設定した • 企業・大学間の「緩衝材」として大学の産学連携コーディネーターが入り、企業担当者が提示するニー ズに対する大学側の感触を伝えたり、反対に大学担当者に対して、企業側が受入れやすい伝え方を アドバイスするなど、ステークホルダー間の交通整理を担った 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2022~2024年度に実施した各調査結果より作成 24
3.事例:シナノケンシ株式会社×信州大学 「デジタル人材育成共同研究講座」 様々なステークホルダーを巻き込みつつ、 講義の設計及び運営を円滑に進めた 開設の 準備 実施 内容 講座の 成果 講座の土台となったポイント ◼ 2019年に包括連携協定を締結し、共同研究を実施していたところ、シナノケンシ社内でデジタル人材の必要性に係る課題意識が顕 在化したため、改めて人材育成も推進することとなった。 ◼ 双方の担当者、責任者等に加え、大学側の産学連携コーディネーターが介在することでより円滑なコミュニケーションが促進された。 シナノケンシと信州大学が本講座及び人材育成ニーズ・課題について検討する場 共同講座の企画 (企画・立案時) 参加者 協議内容 や様子 • 企業担当者・HR担当者 • 大学担当者・コーディネー ター ※企業・大学の上層部とも 適宜共有・議論 • 「何をするか」ではなく、「何 を目指したいか」、「どのよう な人材を育てたいか」を大 学と共有する • 企業のWhatに対して、大 学がHowを返す • 大学教員に直接打診する 前に、コーディネーターに話を することで大学の感触を確 かめた 経営層への打ち込み 運営に係る会議 シナノケンシの担当者と 経営層の 定期的な進捗報告 • 企業経営層・担当者 • 大学担当者・他教員 • 企業担当者・HR担当者 • 大学担当者・他教員 • 企業担当者 • 企業経営層 • 経営者層はまた違った観 点でニーズがあるため、ベー スとなる経営層への理解を 早期に醸成する必要があ る • Whyについてきちんと考え る必要がある、と議論した • 共同講座の事務的な内容 が主な議題 • 定期的に共同講座の進捗 報告を行っている 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2022~2024年度に実施した各調査結果より作成 25
開設の 準備 3.事例:シナノケンシ株式会社×信州大学 「デジタル人材育成共同研究講座」 共同講座の実施内容の概要 プログラムの全体像 実施主体・プログラム 学生向け講義 (先端産業論) シ ナ ノ ケ ン シ 企業と大学の 共同研究 信 州 大 学 企業の 社会人向け講義・ PBL 実施 内容 講座の 成果 講座の土台となったポイント DE/DS講座(PBL)の実施内容 概要 ✓ 大学の新たな科目として、企業から学生に 向けた講義を設置 ✓ 開発時の課題の克服事例の紹介等、実 務に沿った内容を多数紹介 ✓ 実務的な課題解決に係る研究を実施 ✓ 社員、教員、学生が参加 ✓ 期間中に、中間報告と最終報告を各4時 間、対面で実施 ✓ 企業内の課題に対して、教員の助言・指 導を受けながら解決策を考える課題解決 型講義を設置 ✓ 基礎的内容を学びたい受講者向けに、隙 間時間を活用することができるようオンデマ ンド講義を提供 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2022~2024年度に実施した各調査結果より作成 時期 学習テーマ 6月 目指す姿と保有データの拾い出し(人事) 7月 目指す姿と保有データの拾い出し(経営企画) 8月 保有データの準備と確認(人事) 9月 保有データの準備と確認(経営企画) 10月 ギャップの把握と打ち手の立案(人事) 11月 ギャップの把握と打ち手の立案(経営企画) 12月 目指す姿実現のストーリー作成(人事) 1月 目指す姿実現のストーリー作成(経営企画) 26
開設の 準備 3.事例:シナノケンシ株式会社×信州大学 「デジタル人材育成共同研究講座」 実施 内容 講座の 成果 講座の土台となったポイント 受講者が講座にて小さな成功体験を重ねることで、 挑戦する意識が⾼まり、社内の課題解決に向けた具体的な行動変容がみられた 企業側 共同講座で得られた成果と将来的な期待(企業側) 意識・風土の変化 人材育成面 事業運営面 対大学 挑戦に対する前向きな意識・雰囲気が醸成された • 「社内のデータを大学の先生と一緒に眺めよう」という敷居の低いステップか らスタートし、小さな成功事例を複数積み重ねることで、「まずはやってみよ う」という意識が芽生えた • 社員のデータエンジニアリングやデータサイエンスへの感度や意欲が向上した • 経営層や上司も講座に参加することで、部下の取組みに対する理解や応 援する機運が高まった WILL やりたい 得られた 成果 スキルが⾼まり、さらに必要なスキルへの見通しも得られてきた • Python活用スキルが高まった • 「○○のような成果を出すためには、○○のような分析が必要。したがって ○○についてスキル習得・学習が必要」というように、ゴールから逆算して考 えることができるようになってきた • 企業側が大学教員へ相談しやすくなった CAN できる MUST やるべき 将来的な 期待 社内の課題を発見できた • 講座を通じて、社内データ連携に向けて取組むべき課題が明らかになった • 今後はデータ分析に際して新たなツール(Python)を使うべきである、と いった、ツールの活用に係る社員の認識が変わった 受講者の行動変容 学んだスキルを現場の課題 解決に活用するようになった • Pythonでプログラムを組み分 析し、課題を特定する受講 者が出てきた ➢ 例えば、品質保証にお いて不良分析を実施す るために本講座で学ん だ統計的手法を活用 することができた • 学びを抽象化して、似たよう な他の事例への適用の議論 が行われるようになった 大学を通じて地域の企業・団体へも知見を共有し、地域全体の底上げを図る ことで、地域でのオープンイノベーションが進展 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2022~2024年度に実施した各調査結果より作成 大学側と目線をあわせ、実現 可能性が⾼い要望を提示し、 巻き込みに成功した • 企業側の目的感を具体化しすぎ ない段階で大学に相談することで、 オープンイノベーションのような形で 大学とともに講座を作り上げること ができた 対学生 企業の認知度が上がった • 説明会に来る学生が増えた 企業側の技術を大学側にもインプットし、 win-winの関係を構築 27
開設の 準備 3.事例:シナノケンシ株式会社×信州大学 「デジタル人材育成共同研究講座」 教員、学生、大学組織全体のそれぞれに成果があった。 今後は、本講座を好事例として様々な横展開につながることが期待される 教え方をアップデートできた 工学に対する価値観が向上した 新たな分野、周辺領域の学び直し につながった 自身の研究・スキル向上に活かされ た • 社会人向け講義を通じて、社会人 向けの効果的な講義手法を身につ けることができた 得られた 成果 • 大学教員はタコつぼ化しやすいが、 本講座を通じて新たな手法を整理・ 検討し、自身のリスキリングにもつな がった • 自身の研究内容を実務向けに拡 張できた 生データを扱うことができた • PBLを通じて、通常は入手しづらい 企業の生データを扱うことができた 将来的な 期待 学生にとって • 大学で学ぶ内容が社会でどのように 活かされているのか、イメージできるよ うになった 講座の 成果 講座の土台となったポイント 共同講座で得られた成果と将来的な期待(高等教育機関側) 教員にとって 実施 内容 大学側 大学組織として 社会的要請に沿った人材育成に貢献できた • DS・AI人材といったデジタル人材の育成に寄与したことは大学と して意義深い 信州大学における産学連携のPRになった • 優れた産学連携の取組み事例として、地域企業に周知された • 共同研究テーマを国内外の多数の 学会で発表し、学会賞を得ることが できた • 企業側の発表を通じてプレゼンテー ション能力が向上し、自信もついた 新たな教育サービスの道筋が見えた 社会との接点ができた • 企業側のニーズを聞き取り、大学側からHowを提案する、とい うサイクルを繰り返し、産業界の最新のニーズを知るとともに、 Howに対するフィードバックも受けることができた • 企業理解が深まった • 学生スタートアップに対して企業側か らアドバイスを受けたケースもあった 本講座を産学連携のグッドプラクティスとして、他企業に横展開することで、 地域人材の底上げと、大型共同研究や知財・特許取得につなげていきたい 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2022~2024年度に実施した各調査結果より作成 • 企業ニーズに寄り添った社会人教育プログラムを構築するための 方法論を獲得することができた • 企業による学生向けの講義を新たに立ち上げることができた 産業界のニーズを把握することができた 産学連携と親和性が⾼い情報分野のみならず、 他分野の教員も巻き込んでいきたい 28
3.事例:シナノケンシ株式会社×信州大学 「デジタル人材育成共同研究講座」 講座の準備・実施が円滑に進み、成果が得られた背景には、 経営層による深い理解や、包括的な連携に係る協定の締結があった 開設の 準備 実施 内容 講座の 成果 講座の土台となったポイント 講座の土台となったポイント 1 経営層の理解の 醸成 2 包括連携協定の 締結 経営層による講座の受講 • 過年度の本講座において、経営層・部門長向けの講座が開講された。同講座で経営層はDXの必要性や 技術に係る内容を学び、現場との共通認識を得るきっかけとなった • 経営層による受講により、本講座の意義の理解が進み、部下の講座受講に対する抵抗感がなくなり、受講 を推奨する雰囲気が醸成された 講座担当者や大学との対話の場の設置 • 経営層は、講座担当者との週1回の打合せを通じて、本講座に係る進捗報告を受けた。さらに、企業と大 学の共同研究の報告の場に同席し、アウトプットや時間軸について大学側とのすり合わせを先導した • これにより、企業の講座担当者は設計や運営にあたって経営層の意向に沿った判断がしやすくなり、大学と しても、経営層目線でのニーズを把握することができた 包括連携協定からの派生による共同講座の設置 • 新しい技術の開発及び相互の人材育成を目的に、2019年に信州大学工学部と包括連携協定を結び、 複数の共同研究を開始した。その後、企業内でデジタル人材の必要性について話が挙がるようになったことを 踏まえ、包括連携協定を基盤として、デジタル人材の育成に取組む検討を開始した 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2022~2024年度に実施した各調査結果より作成 29
3.事例:シナノケンシ株式会社×信州大学 「デジタル人材育成共同研究講座」 【参考】 信州大学工学部とシナノケンシ株式会社との連携に関する協定書 開設の 準備 実施 内容 講座の 成果 講座の土台となったポイント 信州大学工学部とシナノケンシ株式会社との連携に関する協定書(2019年) 信州大学工学部とシナノケンシ株式会社との連携に関する協定書(2022年) 出所)信州大学ウェブサイト 30
1 調査の目的・実施内容 2 事例:DOWAホールディングス株式会社×東北大学 3 事例:シナノケンシ株式会社×信州大学 4 事例:岩渕薬品株式会社×千葉大学 5 全体的な示唆 31
4.事例:岩渕薬品株式会社×千葉大学 「健康まちづくり共同研究」 2023年度の共同講座の概要 共同講座の背景と目的 人材育成テーマ・分野を 選んだ背景と狙い 医薬品卸領域においては、競合の全国大手卸の拡大化 や他業種からの参入など、将来の市場競合激化が課題 となっている。新規事業である「予防」を軸としたまちづくり 推進事業を実現するには、これまで医療用医薬品・周辺 サービス提供の役割を担ってきた人材が、社内での適切 なサービス提供の構築と社外への発信、関連ステークホル ダーとの連携等を担っていく必要がある。そのためには学 術的な知識だけでなく、実際に行われてきた取組みを学 習し、実践的な活動指針となる知識が必要となった 人 材 発戦 略 課・ 題人 材 開 自社社員 新規事業に対する意識の醸造および人材育成を実施し、 自社事業推進に活かす 自社社員以外 の社会人 健康なまちづくりを事業として検討し、社内と協力関係を 築いてもらう 連携高等教育 機関の学生 社会人学生として参加しているため、個人、現在所属す るセクションとの協力関係を築く 期 待 し て い る 変 化 自社社員 新規事業に興味を持ち、研修で学んだ内容を社内に広 める。また、現職においてのステークホルダーが持つ課題の 発見と共有ができるようになる 自社社員以外 の社会人 各企業がもつ強みの活かし方とSIB/PFS* によるマネタイ ズを学習し、自社の健康まちづくり事業に協力してもらう 連携高等教育 機関の学生 現職がもつ強みの活かし方とSIB/PFSによるマネタイズを 学習し、自社の健康まちづくり事業に協力してもらう 共同講座で特に注力す るポイント 連携体制 千葉 大学予 防医学 センター 岩渕 薬品株 式会社 ソーシャルソリューション本部 事業部 教授 本部 長 特任 准教授 部長 特任 助教 特任 助教 ✓ 生徒募集・選定 受講 者 部署 員 四街 道市 ⾼齢 者⽀援 課 ✓ 高齢者の健康づくり研究に 協力要請 部署 員 ✓ 社内公募・選定 千葉 大学生 自社 の従 業員 (推薦) 千葉 薬品、 ハウス食品 など ✓ 高齢者の健康づくり研究にお ける 協業 ✓ 社内公募・選定 自社 以外の社会 人 (グループ会社/取引先等) 申込・受講者数等 属性 申込者数 受講者数 自社社員 11 11 自社社員以外の社会人 14 14 連携高等教育機関の学生 4 4 行政・企業等のステークホルダーの課題を、予防領域の角 度から的確に把握し、自社のサービスと結びつける。全く 新しいサービスを他企業を巻き込み創造できるようになる * SIB:Social Impact Bond(ソーシャルインパクトボンド)、PFS:Pay For Success(成果連動型民間委託契約) 出所)2023年度の事業者への書面調査、提出された実績報告書等より作成 32
4.事例:岩渕薬品株式会社×千葉大学 「健康まちづくり共同研究」 ⾼等教育機関との連携の狙い、共同講座の成果 連携の経緯、狙い、課題 連携の経緯 連 携 の 狙 い ・ 利 点 連 課携 題に 等係 る 2023年4月から千葉大学との共同研究を開始 自社の新規事業に関わる内容であり、スキルや社内での理解 度が足りていない状況だった。そこで、社内教育によるスキル アップと、新規事業の重要性を社内に拡大するため、共同講 座については同年3月頃から具体的な検討を始めた 企業側 高等教育機関と連携することによって、講義の組み立てにつ いてロジカルに設計することができる。実際に、自社・他社を含 め、受講するメンバーが納得感を得られる内容となった 高等 教育 機関側 • 産学連携による人材育成の実現 • 企業等と連携体制の強化、繋がりの獲得 企画時 対経営層:研修対象者の選定 対現場:当事業への参加者の組織上司への合意 対⾼等教育機関:出席者のテスト方法についての合意 運営時 対経営層:自社内参加者の選定 対現場:講義参加時間の確保とモチベーション向上 対⾼等教育機関:打合せの時間と講義の日程調整 出所)2023年度の事業者への書面調査、提出された実績報告書等より作成 効果促進施策、成果、今後の展望 受講者 へのフォ ローアッ プ 実施前 上司と本人にはメールで、本人には追加的に直接趣旨を説 明。プレスリリースなどで共同研究講座を広報。関連企業に も周知し、参加者の増員とモチベーションのアップを図った 実施中 確認テストや意識付けのための講義のリマインドを実施した 実施後 受講者、受講者の同僚、上司へのアンケートを実施。 また、グループワーク時の提案を実行に移すため、関連企業と ミーティングを実施した 人材育成の達成 状況、評価方法 事業についての興味と理解度をアンケートで調査。これまでの 本業ではない事業についての取組みであり、社内への周知が 足らなかった面もあったが、様々な部署からの参加者において、 新規事業に関する知識を学び、また意識付けができていた 受講者からのフィー ドバック内容、 観測された行動変 容 全体としては、健康まちづくりは事業や取組みとして良いこと だと捉えているが、具体的なマネタイズ案を検討していくことが 重要との感想が散見された。また、当該事業についての社内 インフォメーション不足が課題として認識できた 健康まちづくりへの注目度・意識度が高まるなど、行動変容 についても効果が見られた 人材育成効果を踏 まえた処遇・採用 等の検討状況 新規事業の開始時であるため、現状はテストの評点で実施。 今後は、主体的に活動し、他のステークホルダーを巻き込み、 提案にプラスアルファの思考ができる社員を育成し、処遇反映 や新規採用につなげていくことを想定 今後の成果の 把握方法、 追跡調査方法 受講者及び上司・同僚に対してアンケートを実施 33
4.事例:岩渕薬品株式会社×千葉大学 「健康まちづくり共同研究」 主な講義の内容 No. 日程 実施時間 講義名 概要 第1回(シンポジウム) 【1H】①健康まちづくり共同研究講座概要説明 【1H】②SIB/PFS概要説明 第2回 【1H】③ウェルアクティブコミュニティ(WACo)について 1 2023年7月14日 ~11月15日 12コマ 12時間 健康まちづくり研修 第3回 【1H】④社会参加~社会参加しやすい環境について~ 【1H】⑤建造環境と健康行動・健康について 【1H】⑥ICTで目指すウェルビーイング:デジタルウェルビーイングの実現に向けて 第4回 【1H】⑦ヘルスケア分野の動向とPFS/SIB政策について 【1H】⑧まちづくり分野におけるPFS/SIBの活用可能性ついて 【1H】⑨ソーシャルインパクトボンド(SIB)の可能性~社会課題の解決とビジネスの両 立への挑戦~ 第5回 【1H】⑩フィールド自治体の強みと課題 【1H】⑪岩渕薬品が目指すまちづくり 【1H】⑫健康まちづくり推進・モニタリング・評価に必要なロジックモデル構築について: 効果検証に必要な評価デザイン 2 2023年12月13日 3コマ 3時間 健康まちづくり研修 (フィールドワーク) 出所)2023年度の事業者への書面調査、提出された実績報告書等より作成 四街道の課題を解決するまちづくり案 【1H】⑬四街道市の強みと課題のインプット 【1H】⑭強みと課題を加味したアイデア出しと討議 【1H】⑮課題解決法の決定 34
4.事例:岩渕薬品株式会社×千葉大学 「健康まちづくり共同研究」 開設の 準備 実施 内容 講座の 成果 講座の土台となったポイント 経営層が強力にコミットし、構想段階から時間をかけて大学と対話。 事業と密接に関わる講座の開講は、学びだけでなく、事業推進にも直接的に貢献した 共同講座の主な成功要因と成果の全体像 開設の準備 実施内容 講座の成果 産学連携部門が中心となり、企業、研究 室それぞれとの対話を時間をかけて実施 新規事業(健康まちづくり)を対象に、 理論と実践を組み合わせた講座を実施 新規事業への理解と基礎能力を獲得し、 連携先拡大・横展開の足掛かりともなった • 座学では、全体をカバーした教科書等がない領域 • において、体系的に全体像がつかめるような一連 の講義として設計。さらに実際に取組まれている 事例も紹介し、理論と実践の両面の学びを提供 した グループワークでは、岩渕薬品の社員、他の地域 企業側 • 人材育成面について、新規事業への理解浸透と 意識改革が進んだ。さらに、事業推進にあたって 必要な基礎能力を獲得した • 加えて事業推進への直接的なインパクトとして、 地域における各社との連携強化や、講座終了後 のプロジェクト化などにつながった Step1:企業⇔大学 • 企業(経営層)と大学(産学連携部門)が 長期間かけて対話し、目指す方向性や実現した いことの目線合わせを進めた Step2:大学内 • 学内の産学連携部門と、専門知見を有する研 究室のメンバーが対話し、何ができるかを自由に 議論。研究室としてメリットがあり、かつ企業ニー ズにも即した企画提案内容を検討した • 企業の社員、大学院生等による混成チームを組 成。四街道市をフィールドとして、市の実情や課 題に基づき、今後に向けた提案を検討した 岩渕薬品における受講者について、テスト合格者 には報奨金(一時金)を支給した Step3:企業⇔大学 • まずは人材育成が必要との認識で一致し、講座 内容の詳細設計を進めた 大学側 • 担当教員にとっては、関連知見の「教科書的」な 整理・体系化や、「学びながら実装する」ことがで きる場となった • 大学院生にとっては、講座の内容が自身の研究 に良い影響を得られただけでなく、グループワーク 等を通じて実践的な学びを得ることができた • 大学全体として、本共同講座が一つのGood Practiceとなり、他の研究室、企業、自治体等へ の横展開をするための足掛かりとなった 講座の土台となったポイント 経営層の強力なコミット 連携協定等の締結(千葉大学イノベーションパートナー制度への加入、「健康まちづくり共同研究部門」の正式立ち上げ) 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2023~2024年度に実施した各調査結果より作成 35
4.事例:岩渕薬品株式会社×千葉大学 「健康まちづくり共同研究」 開設の 準備 実施 内容 講座の 成果 講座の土台となったポイント 構想・設計段階では、企業のやりたいこと、大学として得られること等を 時間をかけて丁寧に検討。その内容を踏まえ、双方に利のある講座へと具体化していった 岩渕薬品と千葉大学の検討プロセス Step1 企業ニーズ (やりたいこと) の具体化 構 想 ・ 設 計 段 階 企業 大学 • 岩渕薬品が、千葉大学IMOの「イノベーションパートナー制度」の第1号正会員に加入 • 岩渕薬品の経営層と千葉大学IMOで、半年超の期間をかけた対話を通じて、地域 へどのような恩返しができるか、無関心層をどう巻き込めるか等、構想をじっくり検討 • 最終的に、「健康まちづくり」についての共同研究を立ち上げる方針を確認 Step2 大学シーズ (実現可能な提案) の検討 • 千葉大学IMOと近藤研究室にて、まずは自由に「何ができるか」を議論 • 大学のサイエンスとしての立場も重視し、研究室のこれまでの活動やネットワークとのシ ナジーが見込めるか、サイエンスとしての新規発見が見込めるか、等を幅広く確認 • 上記を踏まえつつ、企業ニーズにも合致した提案内容を作成 大学 Step3 共同講座の 内容の設計 実 詳 施 細 準 段 備 階 ・ 講座の詳細や運営 に係る調整・検討 企業 企業 大学 大学 • 共同研究を進めるにあたり、まず人材育成が必要であることを双方で確認 • 共同講座の内容を設計しつつ、経済産業省「高等教育機関における共同講座創造 支援事業」への応募を準備 • 月1回のハイレベル会合(岩渕薬品の経営層や千葉大学の近藤教授が参加)と、 週1回の実務レベル打ち合わせ(それぞれの主担当者、准教授層が参加)を実施 • 特に実務レベルの打ち合わせは頻度高く実施し、またTeams等を通じてリアルタイムで コミュニケーションを取ることで、本取組みへの企業・大学双方の熱量を維持 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2023~2024年度に実施した各調査結果より作成 36
開設の 準備 4.事例:岩渕薬品株式会社×千葉大学 「健康まちづくり共同研究」 経営層が企業のこれからを考えるところから大学がサポート。 講座開始後も経営層含め関係者が集まる場が定期的に設けられた 実施 内容 講座の 成果 講座の土台となったポイント ◼ 千葉大学IMOの「イノベーションパートナー制度」を活用し、両者で企業のやりたいことを模索する場がもたれた。 ◼ 講座開始後からは、経営層や大学コーディネーターも参加して全体の方向性を定期的に確認するとともに、実務レベルではより頻度 高くコミュニケーションを取ることで、関係者が円滑にかつ熱量を維持しながら講座や関連する事業を推進できた。 岩渕薬品と千葉大学が本講座及び人材育成ニーズ・課題について検討する場 イノベーションパートナー制度に 基づく対話 参加者 • 企業経営層・担当者 • 大学コーディネーター・担当者 協議内容 や様子 • 当初は企業経営層・大学コーディネー ターを中心に、半年超の期間をかけて 企業の今後の構想についてじっくり検 討・対話をする機会があった • 最終的に「健康まちづくり」についての 共同研究を立ち上げる方針を確認し、 学内の関係する教員も交えた検討を 通じ、人材育成に取組むこととなった ハイレベル会合 • 企業経営層・担当者 • 大学担当者・他教員・コーディネーター ※事業に関連する自治体担当者も参加 • 講座およびまちづくり推進事業全般の 方向性を決める場として月1回程度 開催 • 事業のフィールドとなる自治体での課 題や対策状況の共有を受けたり、今 後関係者三者で取組みたいこと等に ついて議論したりする(内容は人材 育成に限らない) 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2023~2024年度に実施した各調査結果より作成 実務レベル打ち合わせ • 企業担当者 • 大学担当者・他教員 • 講座の設計・実施にあたり週に1回 程度開催 • 大学側が共同講座に関連するレク チャーを行いつつ、より細かい知識面や 連携先について両者で議論した。講 座実施期間中は企業側から講座内 容へのFBも行った • コミュニケーションツールも併用しながら、 タイムリーに情報・進捗を共有し、認 識の齟齬を防いでいた 37
4.事例:岩渕薬品株式会社×千葉大学 「健康まちづくり共同研究」 開設の 準備 実施 内容 講座の 成果 講座の土台となったポイント 新規事業(健康まちづくり)を対象に、理論・実践、座学・グループワークを 組み合わせた講座を実施。また、他社や大学院生など様々な関係者と協働できる場とした ◼ 新規事業である「健康まちづくり」を対象とした講座とすることで、実際の事業・業務と密接に関わる内容となった。 講座の特徴・工夫 座学 • 全体をカバーした教科書等がない領域において、体系的に全体像がつかめるような一連 の講義として設計 • 実際に取組まれている事例も豊富に紹介し、理論と実践の両面の学びを提供 講座内容の 特徴 グループワーク (フィールドワーク) その他の工夫 • 四街道市をフィールドとして、市の実情や課題を把握し、今後に向けた提案を検討 • 岩渕薬品の社員、他の地域企業の社員、大学院生等による混成チームを組成 • (上記と重複するが)岩渕薬品の社員だけでなく、他の地域企業の社員や千葉大学 院生など、様々な主体が参加する講座として開催 • 講義は千葉大学で実施するなど、「普段と異なる学びの場」を演出 • 岩渕薬品における受講者について、テスト合格者には報奨金(一時金)を⽀給 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2023~2024年度に実施した各調査結果より作成 38
開設の 準備 4.事例:岩渕薬品株式会社×千葉大学 「健康まちづくり共同研究」 新規事業(健康まちづくり)の基礎固めとなる学びを得ただけでなく、 社内外での理解が浸透したことで、事業推進への追い風を得られている 講座の 成果 講座の土台となったポイント 企業側 共同講座で得られた成果と将来的な期待(企業側) 人材育成面 事業運営面 新規事業への理解と、事業にあたって必要な基礎能力を獲得 新規事業への思いが他社にも浸透し、実プロジェクトに発展 意識の 変革 • 「健康まちづくり」という新規事業について、どのようなも のか、何を目指しているかへの理解が社内に浸透した • 「医薬品卸の会社である」との固定観念が外れつつあ り、視野が広がり、新規事業へ取組む意欲が上がった • 他地域における実際の実践事例も学ぶことで「実現で きそう」という手ごたえが広がった • 社外で活躍する人材との交流が新たな刺激となった 他社 への 広がり • 他の地域企業も受講し、 健康まちづくりへの意欲・ 意向が高まるなど“自分事”化され始めたことにより、 新規事業への想いを共有・浸透してきた • 同じような想いを持つ経営層とコミュニケーションを 取ったり、スタートアップと連携したりと、具体的な取 組みを進める段階に移行できた 能力の 向上 • 「健康まちづくり」の理論と実践について、体系的に全 体像がつかめるような講義を受講することで、これから 新規事業を具現化するにあたっての基礎固めができた • 受講後も学ぶ時間が増えるなど、継続的な能力向上 への取組みの足掛かりとなった 実事業 への 展開 • 千葉大学以外の専門家・有識者や専門事業者・ スタートアップなど、社外との新たなネットワークが広 がり、また、これまで関係のあった地域企業とのつな がりが深くなった • 講座終了後も、「健康まちづくり」に向けたプロジェ クトが、社外との連携を通じて進んでいる 得られた 成果 将来的な 期待 実施 内容 「健康まちづくり」に対する 社内外での理解・共感の更なる広がり 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2023~2024年度に実施した各調査結果より作成 共同講座から実際の事業への発展、 事業化の後押し 39
4.事例:岩渕薬品株式会社×千葉大学 「健康まちづくり共同研究」 開設の 準備 実施 内容 講座の 成果 講座の土台となったポイント 関わった教員・学生にとって、実践的に学び、実装できる場となった。 大学全体としても一つのGood Practiceとなり、今後の横展開への足掛かりが得られた 共同講座で得られた成果と将来的な期待(高等教育機関側) 教員にとって 「教科書」的な整理・学び直し 得られた 成果 将来的な 期待 • 決定的な教科書となるものが存在しない 中で、講座を作りながら、必要なことを体 系的に整理できたことが学びになった(そ の領域の教科書を作っていく感覚) 「学びながら実装する」場の実現 • 講座で得られた学びや産学官ネットワー クを活かすことで、社会実装や実際の地 域介入といったプロジェクトに展開させるこ とができた 大学側 大学院生にとって 研究へのポジティブな影響 • フィールドワークを通じて、地域の実情等に ついて具体的なイメージが持て、自身の 地域高齢者研究にも良い影響があった • フィールドワークでは、量的・質的情報をつ なぎ合わせた分析や対策検討ができ、こ の点は研究に役にも立った グループワークからの実践的な学び • 多様な参加者がおり、多様な視点が得 られた • そのような参加者がいるディスカッションを どう進めればよいか、積極的に関われば よいかを学べた 大学組織として Good Practiceの獲得 • 研究費を獲得して共同研究を実施し、 学生や地域の社会人への新たな学びを 提供し、産学官連携による社会実装を 進める、といった一連の先進的な経験や 成果を獲得した • 学内外の更なる協力・連携先を広げるた めの有力なアピール材料となった 新たな共同研究部門の設置 • 実際に、本事例を見た学内の別セクショ ンから反応があり、新たな共同研究が立 ち上がった 今回の共同講座をGood Practiceとして、産学官連携の更なる拡大・横展開へ (学内で関心を寄せる教員・研究室の拡大、学生に提供できる教育内容の広がり、連携先となる企業・自治体の増加、等) 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2023~2024年度に実施した各調査結果より作成 40
4.事例:岩渕薬品株式会社×千葉大学 「健康まちづくり共同研究」 開設の 準備 実施 内容 講座の 成果 講座の土台となったポイント 本講座には経営層が強力にコミットし、方向性のすり合わせ等を主導。 共同研究部門を設置するなど正式に連携したことも、円滑な準備・運営に寄与した 講座の土台となったポイント 1 経営層と大学との豊富な対話の場 • 経営層は、構想段階において千葉大学IMO(産学連携担当部門)との対話を長期間かけて実施。その 後も、月1回のハイレベル会合に出席するなど、目指す方向性や実現したいことのすり合わせを主導した 経営層の 強力なコミット • これにより、企業担当者は設計や運営にあたって経営層の意向に沿った判断がしやすくなり、大学としても、 経営層目線でのニーズを把握することができた 経営層による講座の受講 • 全ての講義に社長・専務が参加するなど、本共同講座へのコミットを明確に示した • 経営層が、本講座での議論や受講者の反応・手ごたえを直接的に把握することができた 2 「イノベーションパートナー制度」の正会員に加入 • 千葉大学IMOの当該制度に加入することで、大学内リソースへのアクセスを容易なものとした • 他に、IMOが提供する伴走支援など、様々なサービスを受け取れるようになった 連携協定等の 締結 • なお、この制度への加入には、千葉大学の客員産学官連携研究推進コーディネーター制度が活用された (当該コーディネーターに委嘱された地域金融機関が、イノベーションパートナー制度を岩渕薬品に紹介した) 「健康まちづくり共同研究部門」の立ち上げ • 上記会員だけでなく、近藤研究室と共同研究部門を正式に設置し、企業・大学の双方に求められるコミット 内容や役割分担を明確にした 出所) 2024年度インタビュー調査、その他の2023~2024年度に実施した各調査結果、企業・大学ウェブサイトより作成 41
4.事例:岩渕薬品株式会社×千葉大学 「健康まちづくり共同研究」 【参考】 千葉大学IMO「イノベーションパートナー制度」 開設の 準備 実施 内容 講座の 成果 講座の土台となったポイント パートナー正会員特典 ①IMO主催イベントへの招待 企業向け・学内向けセミナーやイベントへ招待 ②技術シーズの情報提供 千葉大学の新着特許情報の提供 ③知的財産の事業化⽀援 千葉大学の知財を活用したパートナー企業の事業化に向けて、その事前の仮説検証(PoC) や試 作品製作等、権利活用相談等について担当URAが伴奏支援 ④イノベーション創出コンシェルジュ⽀援 パートナー企業の技術開発の課題について担当URAが、「パートナー企業の技術課題の整理、課題解 決に向けた千葉大学研究シーズの提案、千葉大学との共同研究コーディネートや千葉大学技術の導 入サポート、大型助成事業の獲得支援」を行い、イノベーション創出活動を支援 ⑤イノベーション人材育成サポート IMOが企画する“アントレプレナーシップ”や“知的財産経営”等のセミナーを提供し、パートナー企業のイノ ベーション人材の育成を支援。また、インターンシップを希望している千葉大学大学院生等と、その受 入れに関心のあるパートナー企業とのコーディネートを実施 ⑥年次総会の参加 年1回開催し、パートナー企業同士の交流が可能 出所)千葉大学ウェブサイト ⑦会員名又はロゴの掲載 パートナー企業の名称又はロゴをIMOのHPに掲載 42
1 調査の目的・実施内容 2 事例:DOWAホールディングス株式会社×東北大学 3 事例:シナノケンシ株式会社×信州大学 4 事例:岩渕薬品株式会社×千葉大学 5 全体的な示唆 43
5.全体的な示唆: 共同講座づくりのモデルフロー 44
5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー|全体像 共同講座づくりは、主に4フェーズに分かれる。各フェーズにおいて取るべきアクションを提示する フェーズ1 連携先との コンタクト・ 合意形成 • 企業と高等教育機関が出会い、連携して共同講座を展 開させることに合意するフェーズ (企業・高等教育機関の責任者が共同講座の実施を 内々に合意し、基本協定等を締結するまで) フェーズ2 講座の設計・開発 • 基本協定等に基づき、体制を組成し、共同講座の具体的 な内容や実施方法等を設計・開発するフェーズ (運営開始の直前まで) フェーズ3 講座の実施 • 共同講座を実際に運営するフェーズ フェーズ4 講座のフォローアップ • 共同講座を通じて得られた成果を評価するフェーズ 45
5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー|要点の整理 各フェーズにおいて取るべきアクションの要点は、下記7点に整理される フェーズ1 連携先との コンタクト・ 合意形成 フェーズ2 講座の設計・開発 ⾼等教育機関との既存の接点を活用し(共同研究等)、人材育成課題についても議論する場をセットする 具体的な取組みを進めるにあたっては、企業・⾼等教育機関とで連携協定等を締結し、双方の経営層の下で お互いに一定のエフォートを割けるようにするなど、活動の“後ろ盾”を設ける 企業・⾼等教育機関の双方の経営層や様々なステークホルダーを巻き込み、まずは講座の意義や将来的な ビジョンを、経営課題に紐づけつつ検討する(経営層向けの講座実施や、インパクトマップ作成も有効) 具体的な講座の内容は、実業務に近いテーマについての課題解決学習(PBL)を取入れるなど、研修転移を 意識した検討を進める (研修転移とは、研修で学んだことが、仕事の現場で適用・実践され役立てられ、かつその効果が持続すること) フェーズ3 講座の実施 フェーズ4 講座のフォローアップ 研修転移が起こるかどうかは、講座内容だけでなく職場環境にも左右されるため、講座の実施前・実施中・実 施後の各タイミングにおいて、講座担当者や受講者の上司からのフォローやサポートを積極的に実施する 講座終了から一定期間後のフォローアップ調査や、それらの内容も踏まえつつ講座の意義・成果を社内外に発 信することで、受講者の研修転移や、組織への波及効果を促す 講座運営に関わる担当者を増やし、講座運営チームとして拡大することで、さらに多様な意見を取入れた運営 を目指しつつ、ノウハウ等の継承を図る 出所)2022~2024年度に実施した各調査結果より分析 46
5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー|全体像 フェーズ1:連携先とのコンタクト・合意形成 フェーズ1 連携先との コンタクト・ 合意形成 • 企業と高等教育機関が出会い、連携して共同講座を展 開させることに合意するフェーズ (企業・高等教育機関の責任者が共同講座の実施を 内々に合意し、基本協定等を締結するまで) フェーズ2 講座の設計・開発 • 基本協定等に基づき、体制を組成し、共同講座の具体的 な内容や実施方法等を設計・開発するフェーズ (運営開始の直前まで) フェーズ3 講座の実施 • 共同講座を実際に運営するフェーズ フェーズ4 講座のフォローアップ • 共同講座を通じて得られた成果を評価するフェーズ 47
5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー|連携先とのコンタクト・合意形成 フェーズ1 コンタクト・合意 初期段階では、既存の接点を活用し、人材課題を明示的に議論する場のセットが重要。 具体的な取組みを進める場合、連携協定等を締結し、活動の“後ろ盾”を設けることが有効 共同講座の開設につなげるための初期段階での論点と取るべきアクション 初期段階の論点 接点の模索 (どのように⾼等教育機関との 接点を作るか) 効果的な対話の実施 (⾼等教育機関と、 何をどのように話すか) 継続的な関係構築 (連携が長期的に続くような 仕掛けをどのように仕込むか) 出所)2022~2024年度に実施した各調査結果より分析 取るべきアクション 既存の接点を 活用する • 共同講座の開設につながりやすい接点は、「トップ同士の個人的つながり」や「管理職層 以下での個人的つながり」等、偶発的接点が多い • より再現性の高い接点として、「共同研究からの発展」や「既存のコンソーシアム・協議会 等でのつながり」など、既存の接点を活用したアプローチの有効性も確認されている • 「コールドコール」のようなゼロベースでのアプローチは、時間を要する可能性もあるが、企業 からの気軽な相談を受け入れる枠組みを持つ大学も多い。周囲の高等教育機関におい て、そのような窓口の有無をまず確認し、問い合わせることもできる 人材課題について 話す場を設ける • 既存の共同研究やコンソーシアム等から、共同講座へと発展させた事例では、人材育成 に関するニーズ・課題にフォーカスした意見交換や勉強会を開催していることが多い • このように議題をフォーカスして⾼等教育機関と具体的に協議する場・時間を十分に設け ることが、共同講座への発展に向けた有効な道筋である • その場に人事担当者等のみならず、事業担当者や双方の経営層を巻き込むことで、経 営課題に合致した視座の高い議論を実施することができる 連携協定など、 今後の活動の “後ろ盾”となる 仕掛けを入れる • 講座開始前に包括連携協定等を締結し、企業・⾼等教育機関がお互いに組織的に取 組むことや、お互いに一定のエフォートを割くようコミットしている事例が多い • この締結により、誰がどれくらい活動するのか、企業・高等教育機関でどのように役割分 担をするのか、といったアクションプランを具体化することができる • さらに、双方にとっての広報効果も期待できる ※接点についての詳細は2023年度報告書に記載 48
5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー フェーズ2:講座の設計・開発 フェーズ1 連携先との コンタクト・ 合意形成 • 企業と高等教育機関が出会い、連携して共同講座を展 開させることに合意するフェーズ (企業・高等教育機関の責任者が共同講座の実施を 内々に合意し、基本協定等を締結するまで) フェーズ2 講座の設計・開発 • 基本協定等に基づき、体制を組成し、共同講座の具体的 な内容や実施方法等を設計・開発するフェーズ (運営開始の直前まで) フェーズ3 講座の実施 • 共同講座を実際に運営するフェーズ フェーズ4 講座のフォローアップ • 共同講座を通じて得られた成果を評価するフェーズ 49
5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー|講座の設計・開発 フェーズ2 設計・開発 講座の設計・開発段階においては、まずその意義を経営層を交えて精査し、 その上で企業のニーズと大学のシーズを多面的な視点を交えて調整することが肝要である 講座設計のステップと要点 1 Why の整理 講座の意義の検討 2 企業 大学等 What の提示 企業 企業ニーズの具体化 3 • 引き続き経営層を設計段階に巻込み、組織的な目標と連動した講座を設計することで、 講座開設への納得感が醸成できる • 高等教育機関側も整理の場に同席することで、経営層目線のニーズを把握できる • 数か月単位で解決する課題ではなく、数年後を見据えたビジョンを⾼等教育機関と共有す ることで、連携の意義への認識がより深まり、効果的な内容の設計につながる • 企業における人材課題・ニーズを議論をする際には、企業側の講座担当者のみならず、業務 課題に知見のある現場の実務担当者や、高等教育機関側の周辺領域の担当教員を含め、 様々な関係者を招き、長い時間をかけて、広がりのある議論を実施するとよい • 人材課題・ニーズをあらかじめ限定しすぎずに、自由な設計の余地を持たせて、高等教育機 関側の意向やケイパビリティにも配慮しながら講座を設計し、双方にとってwin-winな状況を 生み出した例もある すり合わせは長い時間 をかけて、密に実施 How の打ち返し 大学シーズ (運用可能な提案)の提示 大学等 出所)2022~2024年度に実施した各調査結果より分析 • 企業から提示されたニーズに対して、どのように高等教育機関として提案すべきかを検討する だけでなく、アカデミアとしての立場も重視し、高等教育機関における既存の研究や各活動・ ネットワークとのシナジーの有無や、成果への期待等も確認するとよい • 大学内部で関連分野の教員の専門や研究内容の精査を実施し、提供できるシーズを整理 することも有効である 50
5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー|講座の設計・開発 フェーズ2 設計・開発 共同講座の意義を検討する段階から、多くのステークホルダーを巻き込みつつ、 経営課題とリンクさせて⾼等教育機関側と議論することが求められる 1 Whyの整理 「共同講座の意義の検討」を進めるための工夫 経営・現場を巻き込み、 社内体制を充実させる 検 討 体 制 ゴ ー ル 設 定 • 経営層の協力を得て、経営方針として示してもらうことで、社内調整をスムーズに進める • 経営層向けプログラムを作成し受講してもらうことも一案(⇒次ページで詳述) • 現場部門を巻き込み、人材育成ニーズを随時把握するとともに、現場との意見調整を任せる ⾼等教育機関との 連携体制を強化する • 定期的な場をセットし、共同講座の内容を具体的に協議する時間を確保する • 講座担当教員だけでなく、授業等を担当する他の教員も参画し、授業内容等を具体的に議論する (授業内容がわかる担当者が参画することで、より効果的、効率的に進められる) 経営課題や、現場課題と 連動させて講座のゴールを 設定する • 現場へのヒアリング・アンケート調査、高等教育機関の担当者・教員を伴った現場視察や現場との意見 交換、模擬講義の実施など、様々な手段を用いて現場の人材課題・ニーズを把握する • インパクトマップ等を用いながら、経営課題や日々の業務と連動させて、講座で学ぶべきことを整理する (⇒次ページ以降で詳述) 出所)2022~2024年度に実施した各調査結果より分析 ※詳細は2023年度報告書に記載 51
5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー|講座の設計・開発 経営層の関与の仕方には様々な形がある。 その中でも、経営層が実際に講座を受講することは効果的なアプローチである 経営層の関与度を高める方策(例) フェーズ2 設計・開発 1 Whyの整理 経営層の関与に係る現場の声 経営層の理解について 各種打合せに 積極的に出席して もらう • 経営層が共同講座の構想段階から関 与することで、設計や運営にあたって経 営層の意向に沿った判断がしやすくな る • 高等教育機関としても、経営層目線 のニーズを把握できる • 経営層の理解が大前提として必要。経営者層はまた違った観点でニーズがあ る。大学・高等教育機関の実務者同士での議論も大事だが、並行して、かな り早期に経営層へ打ち込みすることが重要である 経営層の打合せへの参加について • 役員層に定期的に報告することで、どんどん進めていこう、といった講座への期 待感が高まる 講座を 受講してもらう • 受講することで、学びの意義や、講座 が対象としている人材課題への共通 認識を得やすくなる • 経営層が受講することの社内へのイン パクトは大きく、講座の意義への理解 が進み、受講を推奨する雰囲気が醸 成される • 一般受講者と同じく受講したり、見学 した場合は、受講者の反応・手ごたえ も直接的に把握できる 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2022~2024年度に実施した各調査結果より分析 経営層の受講について • 経営層が講座を受講しているので、講座で扱うテーマの重要性に理解がある 経営層の関与に係る経営層の声 • 共同講座には毎回、自身も一受講者として参加しており、参加メンバーの様 子を見ていた。社員が普段見せないような反応も見ることができた 52
フェーズ2 設計・開発 5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー|講座の設計・開発 経営課題とリンクさせた講座を検討する方法の一つとして、 インパクトマップの作成が有効である 1 Whyの整理 ◼ 人材開発においては、学びを通じて「行動」の変化を促し、その行動変容を通じて「成果」に貢献する必要がある。 ◼ 例えば、インパクトマップ等の枠組みで、講座と成果のつながりを描くことができる。 ⚫ インパクトマップはロバート・ブリンカーホフが提唱するモデルで、人材開発の取組みにおける学習成果が企業の目標に結び付く までの道筋を整理する枠組み。 インパクトマップと人材開発における達成度レベルの関係 レベル2 学習 レベル3 行動 学習成果 重要な 仕事上の 行動 *レベルについては、次々ページ参照 レベル4 成果 結果 出所)中原淳、関根雅泰、島村公俊、林博之 『研修開発入門 研修評価の教科書』(2022年)より作成 部門目標 ※詳細は2023年度報告書に記載 全社目標 53
フェーズ2 設計・開発 5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー|講座の設計・開発 インパクトマップにより、全社目標に紐づく部門目標に向けて、仕事上でどのような 行動をすべきか、そのために何を学習すべきかを、連動させて関係者間で検討する インパクトマップを用いて、関係者と検討すべきこと レベル2 学習 レベル3 行動 学習成果 重要な 仕事上の 行動 1 Whyの整理 *レベルについては、次ページ参照 レベル4 成果 結果 部門目標 全社目標 ⾼等教育機関関係者* 管理職層*・現場社員 経営層 レベル2 学習 ~ レベル4 成果 レベル3 行動 レベル4 成果 • 実際に教える立場として、この講座 でどんな知識・スキルを獲得すること が目的かをすり合わせる • 専門性や中立的な立場を活かし、 業界の人材育成課題をより広い視 野で議論できる可能性がある • 忙しい現場を離れて講座に参加す る意義を感じてもらうために、講座を 通じて業務に良い影響があると納得 してもらう • 主に、日々の業務に関係して、現場 社員の行動がどう変わるかを考える • 講座を実施する意義を感じてもらう ために、企業としての戦略を踏まえた 人材育成ニーズを共有する • 主に、講座を通じてどのような目標を 達成したいか、を考える *教員、等 *受講者の上司、等 出所)中原淳、関根雅泰、島村公俊、林博之 『研修開発入門 研修評価の教科書』(2022年)より作成 ※詳細は2023年度報告書に記載 54
5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー|講座の設計・開発 フェーズ2 設計・開発 【参考】人材開発(共同講座含む)の達成度は、一般的に4レベルに分けられる 1 Whyの整理 ◼ 企業における人材開発の達成度の評価方法として、4レベルに分けて測定する考え方が一般的に用いられる。 ◼ 評価にあたっては、人材開発を通じて達成したい“成果”につながるような行動の変化(=レベル3)が起きているか、に焦点を当てる べきとされる。 ⚫ 最終的には成果(売上や利益、新規事業創出など)を挙げること(=レベル4)が求められるとしても、その要因は様々で、人材開発以外の 影響も考えられる。 カークパトリックの「4レベル評価モデル」 内容 レベル 名称 1 Reaction 反応 学習イベントに対して、受講者がどの程度、 肯定的に反応したか Learning 学習 学習イベントに参加することで、受講者がどの程度、 • 学習していても、学習内容が現場で実践されるとは 目標とされた知識、スキル、態度を獲得したか 限らない Behavior 行動 学習イベント中に学んだことを、受講者がどの程度、 • “行動”を導けたときのみ、 “成果”が生み出される 仕事に戻ったときに活用したか 可能性が生じる Results 成果 学習イベントとその後の定着によって、どの程度の 結果が生み出されたのか 2 3 4 特徴 例)測定方法 例)受講直後に行われる満足度や実用度に関するアンケート • 「感情的反応」(満足度、等)よりも「実用的反応」 (有用度、等)の方が、その後の“学習“や”行動”に 影響を与える 例)研修後半に行われるテストやロールプレイ 例)本人による自己評価、上司や同僚による他者評価 例)生産性の向上、品質の向上 出所)中原淳、関根雅泰、島村公俊、林博之 『研修開発入門 研修評価の教科書』(2022年)より作成 • 企業活動において最終的に期待されるレベル • 測定結果の背景には様々な要因があり、複雑 ※詳細は2023年度報告書に記載 55
フェーズ2 設計・開発 5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー|講座の設計・開発 双方のニーズ・シーズをすり合わせる際には、密な連携を前提としつつ、 実情に合わせて、概ね3パターンのいずれかの手法が選択されている 2 Whatの提示 3 企業ニーズ・高等教育機関シーズのすり合わせ方法の類型 具体的な 進め方 留意点 Howの 打ち返し 「企業主導」型 「中間」型 「⾼等教育機関主導」型 企業が、企業側のニーズを、 ⾼等教育機関側が受けやすい内容に調整 両者間のフリーディスカッション を通じてゼロベースで検討 ⾼等教育機関の産学連携部門等が 中心となり、企業、研究室との対話を 時間をかけて実施 • 企業側が高等教育機関の状況や意向 をあらかじめ把握し、企業・高等教育機 関の双方にとって実現可能性が高いニー ズや課題意識を大学側に提示する • ニーズやシーズに対する適切な期待値を 双方が共有することで、高等教育機関 側の調整負担が軽減されると同時に、 初期段階での信頼関係の構築が促進 される • 企業側に高等教育機関側の状況や意 向に詳しい人材が求められる • 特定のテーマを設定せずに、双方でまず はフリーディスカッションを実施する • この場には、企業側の実務担当者や高 等教育機関側の周辺領域の教員といっ た直接的には共同講座に関与しない者 も招き、多角的な視点で検討する • 企業のニーズに偏ることなく、高等教育 機関側の関心や研究成果も適切に反 映される、バランスの取れた対話の場を 構築することが可能となる • お互いに、共同講座の設計・開発段階 から十分にエフォートを割ける状態である 必要がある 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2022~2024年度に実施した各調査結果より分析 • まず高等教育機関の産学連携部門が、 企業との対話を継続的に主導し、共同 講座で目指す方向性や実現したいこと の目線合せを進める • 企業ニーズが具体化されたのちに、高等 教育機関の産学連携部門と、専門知 見を有する研究室が対話し、企業への 具体的な提案内容を検討する • 高等教育機関側に、企業のニーズを把 握し、それをシーズ提案に具体化できる 人材が求められる 56
フェーズ2 設計・開発 5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー|講座の設計・開発 なお、前述のような「受講者の行動の変化」を起こし、研修転移* を促せるかどうかは、2 Whatの提示 受講者の特徴や研修デザイン(研修の中身)、職場環境によって左右される 3 研修転移* のモデル 研修のインプット 研修のアウトプット 転移の状況 学習と保持 一般化と維持 Howの 打ち返し 受講者の特徴 • 能力 • 性格 • 動機 研修デザイン • 学習原理 • 一連の流れ • 研修内容 職場環境 • 同僚・上司の支援 • 風土 • 使用機会 * 研修転移とは、研修で学んだことが、仕事の現場で一般化され役立てられ、かつその効果が持続すること 一般化:研修で学んだことが現場で適用されること(実践されること) 持続 :現場に適用された効果性が、直ちに失われれるのではなく、持続すること 出所) 中原淳、島村公俊、 鈴木英智佳、関根雅泰 『研修開発入門 研修転移の理論と実践』(2018年)、 Grossman et al. 2011. The transfer of training: what really matters. より作成 ※詳細は2023年度報告書に記載 57
5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー|講座の設計・開発 研修デザインについては、例えば、講座での学習内容を実業務に近づけて 設計することで、「近転移」により研修転移が起きやすくなることが期待される 近転移とは 研修内容と現場状 況の類似性が低い 2 Whatの提示 3 Howの 打ち返し 近転移を促すプログラム例(インタビュー結果より) ◼ 研修で学習した内容と、現場での状況との類似度が高い状況への転移 は「近転移」と呼ばれ、学習内容と異なる状況への転移より、生じやすい とされている ◼ このため、研修転移を高めるためには、学ぶべき内容や状況を学んだことを 適用する場所や状況に近づけて設計することも一案である 研修内容と現場状 況の類似性が⾼い フェーズ2 設計・開発 近転移 遠転移 研修転移が 起きやすい 研修転移が 起きにくい 課題解決学習(PBL)の設計・実施について • 座学で学んだ技術を活用すべく、PBLとして、人事系における人員の最 適配置と、経営管理系における会社の収益予測に関する課題を設定 した • 社内に存在する実データを教員と共に確認し、これらの課題を解決す るために、教員を交えたブレーンストーミングを通じて仮説を構築した。さ らに、教員によるデータ分析のデモンストレーションを通じて、必要となる データの形式や、分析のための前処理、様々な分析手法によって得ら れる知見を実例を通じて学んだ • 受講者は、座学で学んだ専門用語を駆使しながら、他の分析方法を 用いた場合の可能性や、他の課題に対して今回の分析手法が応用で きるかどうかといった議論を、教員が不在でも積極的に行うようになった 出所)中原淳、島村公俊、鈴木英智佳、関根雅泰 『研修開発入門 「研修転移」の理論と実践』(2018年)、 2024年度インタビュー調査結果、その他の2022~2024年度に実施した各調査結果より分析 58
5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー フェーズ3:講座の実施 フェーズ1 連携先との コンタクト・ 合意形成 • 企業と高等教育機関が出会い、連携して共同講座を展 開させることに合意するフェーズ (企業・高等教育機関の責任者が共同講座の実施を 内々に合意し、基本協定等を締結するまで) フェーズ2 講座の設計・開発 • 基本協定等に基づき、体制を組成し、共同講座の具体的 な内容や実施方法等を設計・開発するフェーズ (運営開始の直前まで) フェーズ3 講座の実施 • 共同講座を実際に運営するフェーズ フェーズ4 講座のフォローアップ • 共同講座を通じて得られた成果を評価するフェーズ 59
再掲 5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー|講座の実施 フェーズ3 講座の運営 研修転移* が起こるかどうかは、職場環境によっても左右される 研修転移* のモデル 研修のインプット 研修のアウトプット 転移の状況 学習と保持 一般化と維持 受講者の特徴 • 能力 • 性格 • 動機 研修デザイン • 学習原理 • 一連の流れ • 研修内容 職場環境 • 同僚・上司の支援 • 風土 • 使用機会 * 研修転移とは、研修で学んだことが、仕事の現場で一般化され役立てられ、かつその効果が持続すること 一般化:研修で学んだことが現場で適用されること(実践されること) 持続 :現場に適用された効果性が、直ちに失われれるのではなく、持続すること 出所) 中原淳、島村公俊、 鈴木英智佳、関根雅泰 『研修開発入門 研修転移の理論と実践』(2018年)、 Grossman et al. 2011. The transfer of training: what really matters. より作成 ※詳細は2023年度報告書に記載 60
フェーズ3 5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー|講座の実施 講座の運営 共同講座の効果を⾼めるために、講座実施前・実施中・実施後において、 講座担当者や現場の上司から受講者に各種⽀援を行うことが効果的である 研修転移を促進するために、効果的とされている受講者への支援策(例) 講座担当者による受講者への働きかけ 現場の上司による受講者への働きかけ 実施前 • 事前課題の提供:事前に本講座の内容に関するe-learning を実 施 • 研修の説明責任の通知:研修後に、報告書の作成や上司との面 談など、席名責任の伴う義務を課す • 研修前のミーティング:講座に参加する目的について、受講者と話し 合い、研修内容の活用についての具体的な期待を伝える • 上司/同僚による同様の研修への参加:上司がまず研修を受け、下 の階層が受けていく 実施中 • 研修中のミスに対するポジティブなサポートの提供:ミスから自主 的に学ぶことを推奨する • 受講者グループによる定期的な会合の設定:直面している課題 等について受講者間で共有・議論 • 現場メンバーの協力:講座に集中できるように、現場メンバーと業務 を調整する 実施後 • 受講内容のリマインド:講座で学んだ内容や立てた活動計画をリマ インドする • 研修内容の有用性の確認:アンケート調査等 • 受講者への個別コーチング:講座で立てた行動目標や活動計画を 実行できるよう、受講者に対してフォローアップ • 活用機会の提供:講座で学んだ内容を活かせる機会を作る • 他の受講者と継続的にかかわっていく学習環境の整備:メーリングリ ストやチャットツール等で、講座後の実践事例を報告する場を提供 • 研修後のミーティング:スキル習得度合いや研修内容の活用機会に ついての合意等を確認するミーティングを設ける • 活用機会の提供:講座で学んだ内容を活かせる機会を作る • コーチング・フィードバック:受講者に対するコーチングや、実践度合い についてのフィードバックを行う 出所)中原淳、島村公俊、 鈴木英智佳、関根雅泰 『研修開発入門 研修転移の理論と実践』(2018年)、 Heimbeck et al. 2010. Integrating Errors into the Training Process: The Function of Error Management Instructions and the Role of Goal Orientation.出所)Brinkerhoff et al. 1995. Partnerships for training transfer: Lessons from a corporate study. . Martin et al. 2010. Workplace climate and peer support as determinants of training transfer. 、Baldwin et al. 1991. Organizational training and signals of importance: Linking pretraining perceptions to intentions to transfer. より整理 ※詳細は2023年度報告書に記載 61
フェーズ3 5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー|講座の実施 講座の運営 例えば、職場における上司の態度は、研修転移に大きな影響を与えることが 知られている。より行動変容を促すには、上司による要求的な態度が効果的である 受講者の行動変容を左右する、職場における上司の雰囲気 雰囲気の5段階 特徴 抑止的 Preventing 学んできたことの活用を、上司が禁止している やる気をそぐ Discouraging 「やってはいけない」と直接的にはいわないが、 上司が快く思っていないことは確実に伝えられている 中立的 Neutral 研修を受けてきたという事実を上司が無視している 職務が今までどおりに完了するのであれば、何も言わない 奨励的 Encouraging 学んだ成果を職務に活用することを奨励している 要求的 Requiring 部下が何を学んできたかを上司は把握していて、 それを確実に仕事に転用させたいと思っている 出所)中原淳、関根雅泰、島村公俊、林博之 『研修開発入門 研修評価の教科書』(2022年)より作成 ※詳細は2023年度報告書に記載 より行動変容を促す 62
5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー フェーズ4:講座のフォローアップ フェーズ1 連携先との コンタクト・ 合意形成 • 企業と高等教育機関が出会い、連携して共同講座を展 開させることに合意するフェーズ (企業・高等教育機関の責任者が共同講座の実施を 内々に合意し、基本協定等を締結するまで) フェーズ2 講座の設計・開発 • 基本協定等に基づき、体制を組成し、共同講座の具体的 な内容や実施方法等を設計・開発するフェーズ (運営開始の直前まで) フェーズ3 講座の実施 • 共同講座を実際に運営するフェーズ フェーズ4 講座のフォローアップ • 共同講座を通じて得られた成果を評価するフェーズ 63
5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー|講座のフォローアップ フェーズ4 フォローアップ 講座後には、フォローアップ調査や社内外への成果の発信だけでなく、講座の “運営チーム”を拡大していくことにより、人材育成の好循環を生み出すことが期待できる 共同講座の効果を高めるための、実施後段階での論点と取るべきアクション 実施後段階の論点 研修転移の促進 (どのようにして受講者の 研修転移を促すか) 波及効果の促進 (どのように受講者以外への 波及効果を起こすか) 今後の改善点の抽出 (今後の人材育成に向けた 改善点をどう把握するか) 取るべきアクション 行動変容の有無 の確認(フォロー アップ調査) • 講座終了後に一定期間を置いて、前述のような「研修転移」が起きているかどうか等 を受講者等に確認することで、改善点を見つけるための重要な参考情報が得られる • このような受講者へのフォローアップ調査は、それ自体が講座内容のリマインド機能を 持ち、研修転移を促すと考えられている • 以上の具体的な調査手法として「サクセスケース・メソッド」が挙げられる 講座の意義や 成果の発信 • 受講者が講座から得た知識等を業務に活用することで、周囲の未受講の社員におい ても、スキル向上への意識がポジティブに変化するなど、波及効果が発生する • さらに、講座の意義や受講者の成果を、講座担当者が社内外に積極的に発信する ことで、人材育成の意義を組織に浸透させるという好循環を生み出すことも可能であ る 運営チームの 拡大 • 共同講座の運営に係る高等教育機関との打合せの場に、企業側から多様な人材を 参加させることは、様々な意見を拾い上げ、質を向上させることにつながる • また、このような打合せに参加すること自体が、参加者にとっての学びの場にもなる • このように講座運営に関わる人材を広げていくことは、運営の属人化を防ぐことにもつ ながる 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2022~2024年度に実施した各調査結果より分析 ※「フォローアップ調査」、「講座の意義や成果の発信」についての詳細は2023年度報告書に記載 64
フェーズ4 5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー|講座のフォローアップ フォローアップ 定量・定性データを組み合わせながら受講者の“行動”の変化の有無を測定し、 その内容・背景を深掘りする調査方法として、「サクセスケース・メソッド」が挙げられる フォローアップ 調査 ◼ 少数の成功例からも多くを学べるということを前提に、「成功例」を見つけ出し、深く話を聞くサクセスケース・メソッド(Success Case Method)という調査方法がある。 ◼ 「行動」に注目し、現場の声も交えることで、社内での納得感を得やすいという利点がある。 サクセスケース・メソッドの全体像・調査の方法 • 事前にインパクトマップを設計したうえで研修を実施し、受講者が当初設定した目標に到達しているかを調査する 準備 ・研修実施 実施結果の 調査 取りまとめ・ 発信 1. インパクトマップの作成 研修後の状況を確認 アンケート 2. 3. ① 研修で学んだことを仕事で活用しなかった ② 研修で学んだことを仕事で活用し、良い結果が出た 研修の実施 ③ 研修で学んだことを仕事で活用したが、 まだ結果は出ていない 数か月後の「簡易アンケート」の実施 アンケートの回答に応じて、回答内容・背景を深堀り 4. 5. 成功例・失敗例への 「深掘り」インタビューの実施 物語としての提示 ➢ ➢ ➢ 研修前の受講者の状態 研修中のでき事や研修で得たもの 研修後の受講者の状態 出所)中原淳、関根雅泰、島村公俊、林博之 『研修開発入門 研修評価の教科書』(2022年)より作成 インタビュー 【成功例(回答:②)】 • (研修で学んだことのうち)何を使った? • (それを行ったことで)どんな結果が? • (研修内容を活用する際に)何が手助けに? • (他の受講者や教育スタッフに対して)助言があれば 【失敗例(回答:①)】 • • (研修内容を活用しなかった理由として)何が邪魔した? (他の受講者や教育スタッフに対して)助言があれば ※詳細は2023年度報告書に記載 65
フェーズ4 5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー|講座のフォローアップ フォローアップ 【参考】フォローアップ調査には3つの役割があるとされている フォローアップ 調査 フォローアップ調査の3つの役割(機能) ①形成的評価機能 研修をより良くする そのことによって…… 研修転移の効果が増す ②総括的評価機能 研修効果の見える化 ステークホルダーへの説明、 研修の持続可能性 ③リマインド機能 研修で学んだことのリマインド 出所)中原淳、関根雅泰、島村公俊、林博之 『研修開発入門 研修評価の教科書』(2022年)より作成 研修転移の促進 経 営 ・ 現 場 に イ ン パ ク ト を 与 え る 66
フェーズ4 5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー|講座のフォローアップ フォローアップ 講座の意義や受講者の成果を、講座担当者が社内外に積極的に発信することで、 人材育成の意義を組織に浸透させるという好循環を生み出すことも可能である 成果の発信 共同講座による成果の発信に取組む事例 E社 G社 共同講座が業務から隔離されている ✓ 組織の規模が大きく、講座が「社内の一部の 取組み」と捉えられてしまう ✓ 講座外の方も巻き込まないと、講座が「通常の 業務とは違う世界のもの」と切り取られてしまう 人材育成の意義が見失われている ✓ 受講者の成果が見えないと、非受講者が学ぶ 意義を感じられない ✓ 経営層や管理職層は人材育成の重要性を認 識しつつも、単年度の業績や目の前の業務を 優先してしまう場合がある 取組み・成果 の発信 • 共同講座の発表会等に管理職を招待 • 社内報や社外の媒体で取組みを発信 取組み事例をナレッジ化 • 社内報を通じて、Off-JTの機会があること、講座を 通じてスキルアップや新たな業務での活躍が見込める ことを発信(資格等による成果の見える化も検討) • 人材育成の意義や講座の成果を経営層や管理職層 に説明 組織内への 波及 • 共同講座の様子を実際に見てもらうことで、受講者の 成果を前向きに捉えてもらえる • 発信を通じて講座の存在が組織に浸透する • ナレッジ化により、非受講者も「やる意義がありそう」 「自分もできそう」と講座に関心を持つ • 成果を出す人材が現れていることに影響され、 講座に興味を持つ若手が増えつつある • 経営層を中心に、人材育成への関心が⾼まりつつ ある 当初の 問題意識・ 背景 出所)2023年度事業者インタビューより作成 ※詳細は2023年度報告書に記載 67
フェーズ4 5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー|講座のフォローアップ フォローアップ ⾼等教育機関との“運営チーム”への企業側参加者を拡大、多様化することで、 多様な意見を拾いつつ運営チームとしても学びを深め、また属人化を防ぐことができる 講座運営に関する、企業側の講座担当者等の課題感 講座担当者 の声 • 現状は共同講座の運営で手一杯で、共同講 座を立ち上げ、運営する仕組みの継承が課題 である 考えられる方策(案) 企業側における “講座運営チーム” の拡大、多様化 • 講座の運営に係る高等教育機関との打合せの 場に、若手社員を含む多様な人材を巻き込む • 多様な意見を拾うことで、講座の改善に向けたヒ ントを得ることができる • 参加者は、高等教育機関との協議を通じて教 員等から様々な刺激を得ることができ、それ自体 が学びにつながる • 講座の設計・開発・運営等のノウハウも継承しや すくなる 取組み事例の ナレッジ化 • 共同講座の継続と次回への応用を図るために、 企画書や報告書に加え、写真や動画も含めて 実践状況を詳細に記録することが有効である • 特に、講座の内容や成果だけでなく、設計や実 施にあたってどのような苦労や工夫があったのかも 記録することで、今後の様々な産学連携活動へ の教訓が得られる • 現時点では、講座の運営に関与しているメン バーがごく一部なので、定例ミーティングへの参加 メンバーをもう少し広げていきたい 経営層 の声 • 社員は特に狭い業界の中で長年働いているため、 大学や自治体などの色々な方と話をすることで 非常に勉強になる。これは、スキルというよりは、 より基礎的なモチベーションや考え方が変化する のではと感じる 出所)2024年度インタビュー調査、その他の2022~2024年度に実施した各調査結果より分析 運営チームの 拡大 68
再掲 5.全体的な示唆:共同講座づくりのモデルフロー|要点の整理 【参考】アクションの要点に関連する事例の掲載箇所 アクションの要点 フェーズ1 連携先との コンタクト・ 合意形成 フェーズ2 講座の設計・開発 関連事例の掲載箇所 ⾼等教育機関との既存の接点を活用し(共同研究等)、人材育成課題についても議論する 場をセットする ‘23報告書p.50-56 具体的な取組みを進めるにあたっては、企業・⾼等教育機関とで連携協定等を締結し、双方 の経営層の下でお互いに一定のエフォートを割けるようにするなど、活動の“後ろ盾”を設ける p.17-18, 29-30, 41-42 企業・⾼等教育機関の双方の経営層や様々なステークホルダーを巻き込み、まずは講座の意 義や将来的なビジョンを、経営課題に紐づけつつ検討する(経営層向けの講座実施や、インパ クトマップ作成も有効) p.12-13, 24-25, 36-37、 ‘23報告書p.59-69 具体的な講座の内容は、実業務に近いテーマについての課題解決学習(PBL)を取入れるな ど、研修転移を意識した検討を進める p.14, 26, 38, 58、 ‘23報告書p.59-69, 90, 95, 100, 110, 別紙1 (研修転移とは、研修で学んだことが、仕事の現場で適用・実践され役立てられ、かつその効果が持続すること) フェーズ3 講座の実施 フェーズ4 講座のフォローアップ 研修転移が起こるかどうかは、講座内容だけでなく職場環境にも左右されるため、講座の実施 前・実施中・実施後の各タイミングにおいて、講座担当者や受講者の上司からのフォローやサ ポートを積極的に実施する p.60-62、 ‘23報告書p.71-78, 110 講座終了から一定期間後のフォローアップ調査や、それらの内容も踏まえつつ講座の意義・成 果を社内外に発信することで、受講者の研修転移や、組織への波及効果を促す p.67、 ‘23報告書p.40, 95, 100, 105, 別紙2 講座運営に関わる担当者を増やし、講座運営チームとして拡大することで、さらに多様な意見を 取入れた運営を目指しつつ、ノウハウ等の継承を図る p.68 出所)2022~2024年度に実施した各調査結果より分析 69
5.全体的な示唆: 共同講座の利点と意義の再整理 70
5.全体的な示唆:共同講座の利点と意義の再整理|企業にとってのメリット ⾼等教育機関のケイパビリティは、研究・教育機関としての能力・実績にとどまらず、 学ぶ環境としての特徴にも現れている 高等教育機関のケイパビリティ、人材育成への付加価値 ⾼ 等 教 育 機 関 の 主 要 機 能 に 基 づ く 価 値 一般的な企業の人材育成(民間の研修等)と比較した 優位性 当該テーマにおける高度な専門性、先端性 アカデミック・理論的・体系的な知見 学際的な知見 研究を深めるためのノウハウや方法論、経験 先端的で豊富な研究設備 • 「この大学・研究室でなければ学べない」という圧倒的 な優位性 • 理系だけでなく、人文社会系においても優位性は発 揮される • 体系的なカリキュラムの設計・実施に係る専門 性 • 特に、大掛かりな講座(長期間・長時間)でも 提供できるノウハウ・経験 • 大掛かりかつ体系的なカリキュラムにより、学びがより 身につきやすい • (連携方法にもよるが)専門的な内容を企業側の ニーズ・実情を踏まえながらカリキュラムに落とし込める 人材・ ネットワーク • 様々な碩学とのディスカッションから得られる刺 激、知的興奮 • 学部生・院生からの新鮮な質問・意見 • 多様な研究者・企業・自治体等とのネットワーク • 特に包括的な提携ができた場合、高等教育機関と の人材交流が活発化し、様々な刺激がもたらされる • 様々な企業・自治体等との新たなつながりが増え、よ り大掛かりな産学連携プロジェクト等につながりうる 場 • キャンパスにおける、学びの意欲を向上させる/気 持ちを切り替え学びに集中させるような「学ぶ場、 究める場」としての雰囲気、魅力 研究 能力・実績 教育 能力・実績 多様な 人 と 場 の 魅 力 企業側 の魅力 • • • • • • 連携先として、「中立的である」、「信頼できる」と いう安心感 出所)2022~2024年度に実施した各調査結果より分析 • “学ばない社会人”であっても、学びへのモチベーション を高める仕掛けとなり、自律的な学びを促す • 高等教育機関と連携することにより、共同講座等の 取組みに対する社内外の信頼性が高まる 71
5.全体的な示唆:共同講座の利点と意義の再整理|企業にとってのメリット ⾼等教育機関のケイパビリティが発揮された共同講座を実施することにより、 受講者には3つの変化がもたらされる 高等教育機関のケイパビリティ、人材育成への付加価値(再掲) ⾼ 等 教 育 機 関 の 主 要 機 能 に 基 づ く 価 値 研究 能力・実績 教育 能力・実績 多様な 人 と 場 の 魅 力 人材・ ネットワーク 場 の魅力 • • • • • 当該テーマにおける高度な専門性、先端性 アカデミック・理論的・体系的な知見 学際的な知見 研究を深めるためのノウハウや方法論、経験 先端的で豊富な研究設備 • 体系的なカリキュラムの設計・実施に係る専 門性 • 特に、大掛かりな講座(長期間・長時間) でも提供できるノウハウ・経験 • 様々な碩学とのディスカッションから得られる 刺激、知的興奮 • 学部生・院生からの新鮮な質問・意見 • 多様な研究者・企業・自治体等とのネット ワーク • キャンパスにおける、学びの意欲を向上させる /気持ちを切り替え学びに集中させるような 「学ぶ場、究める場」としての雰囲気、魅力 • 連携先として、「中立的である」、「信頼でき る」という安心感 出所)2022~2024年度に実施した各調査結果より分析 企業側 共同講座の受講者にもたらされる変化 Can • 新しい領域・テーマ等に取組むための知識・スキ ルや思考力を獲得する • 連携先の高等教育機関や、その他の様々なス テークホルダーとのネットワークが強化される Must • 教員から助言を受けつつ、通常の業務や研修と は異なる形でじっくり取組む(一度立ち止まって 考え直す)ことで、事業や業務において解くべき 課題が明確になる Will • 高等教育機関の教員等から学び、コミュニケー ションを取ることで、知的好奇心が刺激される • 新しいことに取組むことや、学び直しそのものへの モチベーションが⾼まる 「できる」ことが 増える 「やるべきこと」 が見える 「やりたい・ やってみよう」 が広がる 72
5.全体的な示唆:共同講座の利点と意義の再整理|企業にとってのメリット 受講者に3つの変化が起きることにより、学んだことを業務で活かすような行動変容、 すなわち「研修転移」が生じる 高等教育機関のケイパビリティ ⾼ 等 教 育 機 関 の 主 要 機 能 に 基 づ く 価 値 受講者に もたらされる変化 研究 能力・実績 Can 「できる」ことが 増える 学んだことが業務で活かされる「研修転移」が起きる 教育 能力・実績 多様な 人 と 場 の 魅 力 企業側 Must 「やるべきこと」 が見える (例) • 学んだことを活かして、実際の製造工程を改善することができた • 社内のデータ連携に係る課題を発見し、講座で得られた知識を使って業 務改善を試みる事例が出てきた • 講座で得られた知識を活かし、さらに講座で繋がった社外とのネットワーク も活かして、新たなプロジェクトが進んでいる Will ※その他の事例や、研修転移を促す各種方策は2023年度報告書に記載 人材・ ネットワーク 場 の魅力 出所)2022~2024年度に実施した各調査結果より分析 「やりたい・ やってみよう」 が広がる 73
5.全体的な示唆:共同講座の利点と意義の再整理|企業にとってのメリット 【参考】 「研修転移」とは 企業側 研修転移とは、 研修で学んだことが、仕事の現場で一般化され役立てられ、 かつその効果が持続すること 一般化:研修で学んだことが現場で適用されること(実践されること) 持続 :現場に適用された効果性が、直ちに失われれるのではなく、持続すること 出所)中原淳、島村公俊、 鈴木英智佳、関根雅泰 『研修開発入門 研修転移の理論と実践』(2018年)、 中原淳、関根雅泰、島村公俊、林博之 『研修開発入門 研修評価の教科書』(2022年)より作成 注)2023年度報告書より転記 74
5.全体的な示唆:共同講座の利点と意義の再整理|企業にとってのメリット 研修転移が発生することにより、事業・経営へのインパクトや、周囲の社員への 波及効果も期待される 高等教育機関のケイパビリティ ⾼ 等 教 育 機 関 の 主 要 機 能 に 基 づ く 価 値 受講者に もたらされる変化 研究 能力・実績 多様な 人 と 場 の 魅 力 「できる」ことが 増える Must 「やるべきこと」 が見える Will の魅力 出所)2022~2024年度に実施した各調査結果より分析 受講者が、 講座で学んだこと を職場で活かす 受講者を中心として、業務改善・変革 が進められることにより、事業や経営へ の具体的なインパクトにつながる 「研修転移」 が起きる 人材・ ネットワーク 場 さらに期待される波及効果 Can 教育 能力・実績 企業側 受講者自身の行動変容や、上記の業 務改善・変革等を通じて、受講しな かった社員にも行動変容が広がるなど、 効果が波及する 「やりたい・ やってみよう」 が広がる 75
5.全体的な示唆:共同講座の利点と意義の再整理|⾼等教育機関にとってのメリット 共同講座の成果は⾼等教育機関側にももたらされている。教員・学生にとっては、 新たな知見や実践的な学びだけでなく、研究そのものへのメリットも生まれている 参画した教員にとっての成果・メリット 自身の学び直し・ リスキリングになる 産業界側の実例・ 課題・ニーズを把握 できる • 社会人向けの効果的な講義方法が身につく • 自身の研究分野の周辺領域に関する知見や 手法を新たに学び直すことができる • 教科書的な知見の整理・体系化ができる • 社会実装につなげるためのニーズを把握できる • 企業の生データ等に触れることができる • 自身の研究に対する産業界からのフィードバッ クが得られる 産学連携の実績が 増える • 学内外にPRできる産学連携の実績となる • 外部資金獲得の実績となる • 「学びながら社会実装する」場が実現できる 更なる研究への 足掛かりを得られる • 以上を通じて、自身の研究を更に進めていくた めの視点やヒント、足掛かりが得られる 出所)2022~2024年度に実施した各調査結果より分析 大学等側 受講した学生にとっての成果・メリット 実践的な学びを 得られる • 高等教育機関で学ぶ内容が企業や社会でど のように活かされているのか、実践的なイメージ が持てるようになる • 企業やその他の多様な参加者から、多様な 視点を得られる 研究・学習に係る 能力やモチベーショ ンを⾼められる • 得られた知見が、自身の研究に直接役に立つ • ディスカッション能力やプレゼンテーション能力が 身につく • 研究内容と社会との繋がりを実感し、研究に 一層身が入るようになる 企業・業界への 理解が深まる • 講座を通じて企業や業界への理解が深まり、 就職活動に活用できる 76
5.全体的な示唆:共同講座の利点と意義の再整理|⾼等教育機関にとってのメリット ⾼等教育機関の組織全体としては、人材育成や社会実装といった本来のミッションを 大学等側 実現するだけでなく、産学連携の拡大に向けた経験値やアピール実績を増やすことができる 高等教育機関の組織全体にとっての成果・メリット 産学連携による 人材育成や、 社会実装を実現する 産業界側の実例・課題・ ニーズを把握できる • 産業界から要請されている人材を育成することができる • 共同研究やその他の関連活動も含めて実施することにより、社会実装に貢献する • これらの社会貢献により、信頼度やブランド力が向上する • 共同講座の準備・実施等の様々な段階において、企業側のニーズ・課題の聞き取りや、実際に 現場を見るといった活動を多数実施することができ、産業界の最新事情や生の声が得られる ※教員個人だけでなく、組織として蓄積することができる 社会人教育に係る Good Practiceを 獲得する • 産学連携による社会人教育についての経験値が得られる • 企業ニーズに寄り添った社会人教育プログラムを構築するための方法論を獲得できる • 組織体組織の産学連携のためのTipsを蓄積できる 産学連携の更なる 拡大や横展開の 足掛かりを得られる • 共同講座の取組み事例をアピールすることにより、産学連携の更なる拡大・横展開が期待できる (学内で関心を寄せる教員・研究室の拡大、学生に提供できる教育内容のバリエーション増加、 連携先となる企業・自治体の増加、等) 出所)2022~2024年度に実施した各調査結果より分析 77
5.全体的な示唆:共同講座の利点と意義の再整理|共同講座が求められる局面 企業は、戦略立案・遂行や経営/事業課題解決のために様々なリソースを活用・獲得 しようとする。その中で、共同講座は能力獲得の一手法として位置づいている 企業側 経営課題/事業課題 を解くために… どのように 必要な能力を 獲得するか? 社内で育成する OJT Off-JT 自己研鑽の⽀援 (通常の)研修 共同講座 社外から獲得する キャリア採用 新たな能力を獲得するための 一つの選択肢 では、どのようなときに 共同講座は有効か? 専門事業者への 外注 出所)2022~2024年度に実施した各調査結果より分析 78
5.全体的な示唆:共同講座の利点と意義の再整理|共同講座が求められる局面 共同講座は、新しくて難しい課題で、内製化が重要であり、人材獲得競争が熾烈な テーマ・領域に取組む際の能力獲得手段として有効である 高等教育機関との共同講座が有効となる局面・条件 新しいこと に挑戦する 難しいこと に挑戦する 内製化 が重要である 熾烈な競争下 にある 企業側 他の能力獲得方法との比較 • その経営/事業課題が、新しいことへの挑戦であり、 社内での経験値やノウハウが少ない • OJTでは、社内にノウハウ等がないため対応しにくい • その経営/事業課題の難易度が高く、対応するための 高度な専門性を身につけるためには長期間を要する • その領域の専門家や、社外の産官学の様々な関係 者と連携しないと、対応を進められない • 自己研鑽や、通常の研修では、高度な専門性に基 づき長期間にわたって学び続けることや、専門家・各 種関係者と繋がることが難しい • 競争優位性を獲得・強化するために、知識・スキル・ ノウハウ等を社内に蓄積することが重要である • そのための教育者による伴走が必要である • 専門事業者への外注では、自社内に知識・スキル・ ノウハウ等が残りにくいか、残ったとしても限定的である • その専門性を有する人材が少なく、熾烈な人材獲得 競争になっている • キャリア採用は重要だが、それだけでは十分な人員数 をまかなえない これらの局面・条件に該当するような経営/事業課題に取組む場合、共同講座を通じた能力獲得が有効 出所)2022~2024年度に実施した各調査結果より分析 79
5.全体的な示唆:共同講座の利点と意義の再整理|共同講座が求められる局面 今年度に調査した3事例では、いずれも、 前述の4つの条件に合致したテーマ・領域を対象として、共同講座を実施していた 企業側 3事例が対象としていたテーマ・領域についての、前述4条件に照らした一致状況 新しいこと に挑戦する 難しいこと に挑戦する 内製化 が重要である 熾烈な競争下 にある DOWAホールディングス シナノケンシ 岩渕薬品 • 材料開発プロセスについて、これまで の経験に頼った“職人型”から“データ 駆動型”へのシフトを目指している • 主力事業は厳しい価格競争に晒され ており、DXを通じた付加価値の向上 や、各種データを活用した業務効率 化が新たに必要となっている • 医薬品・医療機器の卸売事業を長 らく営んできた中で、新たに「健康まち づくり」を新規事業として着手した • 材料開発×DXは、アカデミアにおいて も先端的な研究テーマであり、企業が その技術を単独で獲得することは非 常に難しい • データサイエンス、AIスキル、データを活 用した高度な制御設計技術など、単 なるIT活用よりも数段高いレベルの DXスキルの獲得を目指している • 「健康まちづくり」に関する事例は国 内ではまだ少ない。体系的に学べる 教科書や、まとまった情報もなく、先 端的なテーマである • 材料開発分野は熾烈な国際競争が 続いており、継続的な競争優位性を 獲得するためには、DX技術を“手の 内”化する必要がある • 社内の全体的な底上げと、DXリー ダー人材の抜擢・養成を当面は目指 している • 新規事業として位置づけて将来的な マネタイズを目指しているため、専門 性やノウハウを社内に蓄積する必要が ある • 「材料開発×DX」への専門性を持つ 人材は極めて少ない • DX人材、データサイエンティスト等への 需要は非常に高まっており、キャリア 採用での獲得は容易ではない • 「健康まちづくり」や、そのカギとなる概 念であるPFS/SIBについて詳しい人材 は、ほとんど労働市場に存在しない 出所)2022~2024年度に実施した各調査結果より分析 80