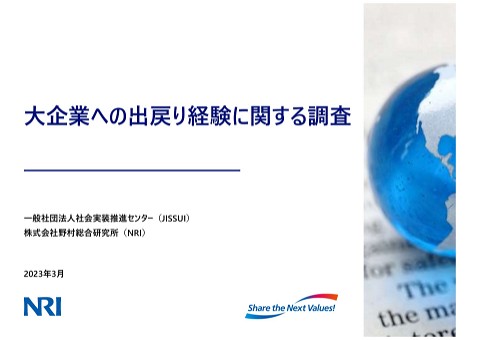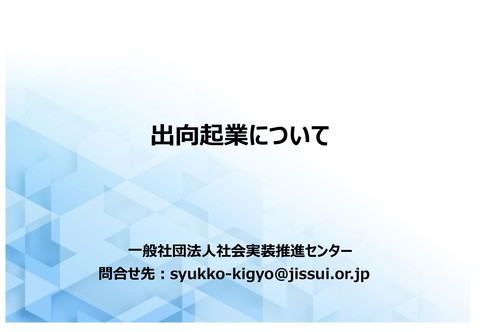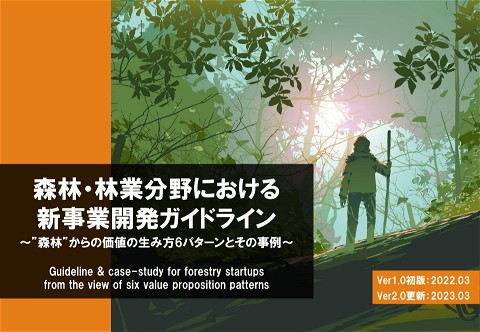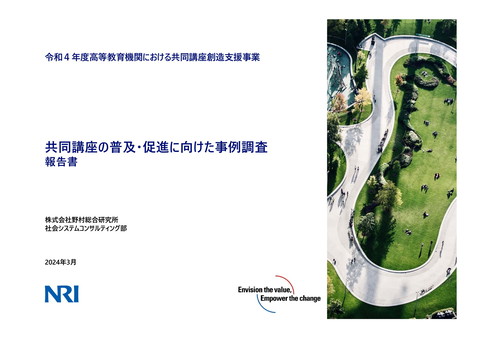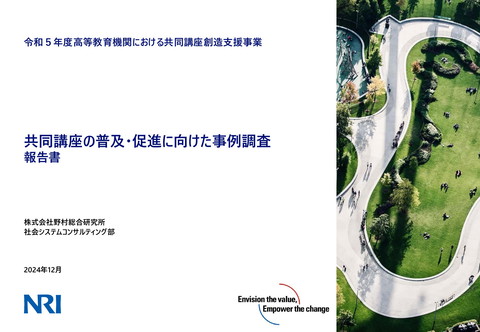【レポート】林業DX・イノベーションの要となる『データ活用力』と『新たな付加価値』について
6K Views
February 03, 25
スライド概要
林業業界が目指すDXにおいては、まず第一段階としての"デジタルツールの導入"が一定進んできていますが、その次のステップとしての業務の効率化・高度化(持続的イノベーション)、更には事業構造の転換や新たな価値軸の提案(破壊的イノベーション)に向けた議論が必要な段階にあります。
そこで、それぞれのイノベーションに関するテーマを設け、先進事業者等との座談会を通じて課題を深掘り、林業DX推進およびその支援事業者の事業開発に参考になる情報をレポートとして整理しました。
"旗"を掲げ、挑戦したい人を応援するメディアです。 第一線で挑戦する人のインタビュー・コラム、政策・ビジネスに関するレポート、公募の情報など、「じっくり読みたくなる」情報をお届けしています。note:https://flag.jissui.jp/ | 運営会社JISSUIの情報はこちらから→ https://jissui.or.jp/
関連スライド
各ページのテキスト
林業DX 本資料は、林野庁事業「森ハブ・プラットフォーム」における会員等に 向けた情報発信の⼀貫として、(⼀社)⽇本林業技術協会ならびに (⼀社)社会実装推進センターによって作成されたものです。 0
林業DX・イノベーションの課題 1
林業DX・イノベーションの課題 林野庁は、2028年をターゲットイヤーとして、地理空間情報やICT技術を活⽤した ”スマート林業”の定着による、安全性・⽣産性の向上を⽬指している。 引⽤)「スマート林業実践マニュアル 総集編(準備〜導⼊〜継続)」令和5(2023)年林野庁 2
林業DX・イノベーションの課題 ”スマート林業”が⽬指すのは、単なる”デジタル化”ではなく、 デジタル技術をフル活⽤した産業構造の変⾰(=DX・イノベーション)にある。 n ⼀⽅、現時点では2028年にほぼすべての意欲と能⼒のある林業経営者が2ndステップ「デジタル技術のフル活⽤」 に到達することを⽬標としている段階であり、その先のDX・イノベーションに向けた議論は⼗分ではない。 本質的な⽬標 ⽬下の⽬標 2028年 1st ステップ アナログからデジタルへ • • 紙伝票からデータへ 紙図⾯からモバイル端末、 ア プリ、GISへ • 2nd ステップ デジタル技術のフル活⽤ • • 3rd ステップ 産業構造の 変⾰ データを活⽤した森林管理、 ⽊材需給マッチング ペーパーレス電⼦申請 川上〜川下、異分野とも連携した新たな体制の構築 引⽤)「スマート林業実践マニュアル 総集編(準備〜導⼊〜継続)」令和5(2023)年林野庁 3
林業DX・イノベーションの課題 2ndステップ以降へ進んで真のDXに到達するには、2つの”イノベーション”を起こす必要がある。 n スマート林業の定着は、持続的イノベーションと、破壊的イノベーションを起こすための前提条件となる。 デジタル化の取り組み段階(中⼩企業庁資料より⼀部引⽤・林業例を追記) 3rd STEP 新たな価値軸の提案 第4段階 →破壊的イノベーション (市場創出・価値転換) デジタル化によるビジネスモデルの変⾰や競争⼒強化に取り組んでいる状態 (⼀般例)システム上で蓄積したデータを活⽤して販路拡⼤、新商品開発を実践している (林業例)川上〜川下、異分野とも連携し、森林・⽊材の新たな価値が創出されている デジタル化による業務効率化やデータ分析に取り組んでいる状態 第3段階 2nd STEP 既存業務の効率化・⾼度化 →持続的イノベーション (改善・改良) 第2段階 1st STEP デジタルツールの導⼊ 第1段階 (⼀般例)売上・顧客情報や在庫情報などをシステムで管理しながら、業務フローの⾒直しを⾏っている (林業例)森林・⽊材に関するデータが集約され、データに基づく森林管理、需給マッチング、電⼦申請 等の業務が⾏われている。 アナログな状況からデジタルツールを利⽤した業務環境に移⾏している状態 (⼀般例)電⼦メールの利⽤や会計業務における電⼦処理など、業務でデジタルツールを利⽤している (林業例)紙図⾯からモバイル端末、アプリ、GISへ、紙伝票からデータへ移⾏している 紙や⼝頭による業務が中⼼で、デジタル化が図られていない状態 引⽤)中⼩企業庁「中⼩企業⽩書 2022年度」の図表に林業例を追記して編集。 4
林業DX・イノベーションの課題 ⼀般的には、技術進化と時間経過によって、持続的イノベーションを享受できる期間から、破 壊的イノベーションが求められる期間に移⾏していく。 既 存 製 品 の 主 要 顧 客 が 重 視 す る 性 能 顧客がメリットを 感じない⾼性能化 じる 感 際に 実 が 顧客 持続的イノベーションの領域 (⾼性能=⾼付加価値) 性能の変化 主要顧客が求める性能 破壊的イノベーションの領域 (⾼性能≠⾼付加価値) 時間の経過 5
林業DX・イノベーションの課題 課題①:現実的には、技術の”活⽤⼒”不⾜で、持続的イノベーションも⼗分に享受できてい ない現状が⾒受けられる。 既 存 製 品 の 主 要 顧 客 が 重 視 す る 性 能 顧客側の活⽤⼒が不⾜すると 持続的イノベーションも享受できない じる 性能の変化 感 際に 実 が 顧客 持続的イノベーションの領域 (⾼性能=⾼付加価値) 主要顧客が求める性能 主要顧客が”扱える”性能 破壊的イノベーションの領域 (⾼性能≠⾼付加価値) 時間の経過 6
林業DX・イノベーションの課題 課題②:並⾏して、国内需要量は縮⼩していく展開において、新たな”付加価値”の探索は 必須となる。 既 存 製 品 の 主 要 顧 客 が 重 視 す る 性 能 じる 感 際に 実 が 顧客 持続的イノベーションの領域 (⾼性能=⾼付加価値) 性能の変化 主要顧客が求める性能 新たな価値軸が必要 ü⽊材の”機能”とは異なる価値は何か? ü環境価値? üブランディング? ü体験価値? 破壊的イノベーションの領域 (⾼性能≠⾼付加価値) 時間の経過 7
本レポートの位置づけ 森ハブプラットフォーム事業の⼀環として、深掘り座談会で抽出した課題・ノウハウを整理。 林業DX・イノベーションの 課題 課題① 技術が進歩したとしても 事業体が”使いこなす”事 ができなければ意味が無い 課題② 需要縮⼩局⾯において 作業効率向上以外の 価値軸も探る必要がある 深掘りテーマ 内容・登壇者 本レポートを読んで欲しい 主なターゲット テーマ① 林業DXに必要な ”データ活⽤⼒”を 経営・組織視点で考える 先進事業体のプラクティスを通じ て、デジタル技術を”使いこなす” ための事業体ノウハウやベンダー の⽀援の在り⽅を共有 (登壇者) ü 宮城⼗條林産梶原⽒ ü マプリィ中村⽒ ü 森淵林業森淵⽒ ü 林業DXへモチベーションはあるもの の、技術導⼊や運⽤にあたって課 題感を有する林業事業体(特に 経営陣・管理担当) ü 林業DXを⽀援しようとしつつも、 効果的な⽀援ノウハウに課題感 を有するコンサル・ベンダー・異分 野事業者 テーマ② 森林・林業の ”新しい付加価値”を エンドユーザー視点で考える エンドユーザーのニーズに触れる川 下事業者との議論から得た、 DXの先にある新しい価値軸を探 るうえでのヒントを共有 (登壇者) ü ⽇建設計⼤庭⽒ ü アトリエフルカワ古川⽒ ü ⽊⻘連R3年度会⻑松原⽒ ü デジタル化・作業効率化において は⼀定の成果を出しつつも、中⻑ 期⽬線でそれ以外の⽅向性を 探っておきたい林業事業体 ü 林業事業体を⽀援していくうえで、 より⼤きな市場や提供価値を⾒ 据えたいコンサル・ベンダー・異分 野事業者 8
深掘りテーマ①: 「林業DXに必要な”データ活⽤⼒”を経営・組織視点で考える」 林業DX・イノベーションの 課題 課題① 技術が進歩したとしても 事業体が”使いこなす”事 ができなければ意味が無い 深掘りテーマ 内容・登壇者 本レポートを読んで欲しい 主なターゲット テーマ① 林業DXに必要な ”データ活⽤⼒”を 経営・組織視点で考える 先進事業体のプラクティスを通じ て、デジタル技術を”使いこなす” ための事業体ノウハウやベンダー の⽀援の在り⽅を共有 (登壇者) ü 宮城⼗條林産梶原⽒ ü マプリィ中村⽒ ü 森淵林業森淵⽒ ü 林業DXへモチベーションはあるもの の、技術導⼊や運⽤にあたって課 題感を有する林業事業体(特に 経営陣・管理担当) ü 林業DXを⽀援しようとしつつも、 効果的な⽀援ノウハウに課題感 を有するコンサル・ベンダー・異分 野事業者 9
データ活⽤⼒が必要な背景 林業DXの⼤前提として、経営・組織レイヤーにおいて経営改善のモチベーションが必要。 n 林業DXが進まない原因として、現場のITリテラシー不⾜や、導⼊ツールの機能不⾜などが挙げられがちではあるが、 経営・組織レイヤーの体制構築の観点ではあまり問題提起がされてこなかった。 経営・組織 ü 経営改善・収益拡⼤のモチベーションがあるか。 ü 経営陣が技術活⽤の意義を理解しているか。 ü 投資回収期間を⻑期に持てる財務・経営体制があるか。 意思決定の壁 業務プロセス ü 業務プロセス全体と各コストを組織として把握できているか。 ü 業務⾃体が標準化・ドキュメント化されているか。 ü 技術に合わせて業務を組み替えることができるか。 導⼊の前提条件の壁 ⼈材・現場 ü ⼈材・現場において技術を活⽤するモチベーションがあるか。 ü 個々の⼈材において、個別の業務の意味や影響範囲を認 識しているか。 現場定着・活⽤の壁 導⼊ツール ü 導⼊するツールの技術⼒・コストパフォーマンスが適切か ü 費⽤対効果が出せるか。 収益化・継続の壁 林業DXの ⼤前提 10
データ活⽤⼒が必要な背景 外部連携事業者においても、経営者へのアプローチ不⾜が課題として指摘されている。 経営者の理解の下、経営改善・ビジネスモデル変⾰のために使っていかなければ⽚⼿落ち。 林業事業体 経営者 ü 意欲と能⼒のある林業経営体として、 ⽣産性向上のため、ICT技術の導⼊が 必要と理解する。 経営者の理解とモチベーションが重要であり、 ⾃治体等公的主体が地域の経営者を巻き込んだ 勉強会等を開催していく必要がある。 ⽀ 援 指⽰ 援 ⽀ コア技能者 ü メーカーと現場技能者の間をつなぎ、技 術を普及させる。 ü データを解析し、活⽤できる。 メーカー、外部からの⽀援 ü 経営者への働きかけ ü コア技能者を⽀援、指導 ü 技術⾯の⽀援指導 指導 現場技能者 ü ICT技術を使い、データを取得できる。 引⽤)「スマート林業実践マニュアル 総集編(準備〜導⼊〜継続)」令和5(2023)年林野庁 特に異分野事業者にとって、 林業事業体の経営者へのアプローチが⼗分でない場合 経営改善・ビジネスモデル変⾰まで提案ができず、 結果として継続利⽤・拡⼤に繋がらない事例が多い。 11
座談会メンバー 林業DXに積極的な先進事業体と、DXを伴⾛するITベンダーによる座談会・ヒアリングを実施。 座談会登壇者 議論の視点 先進事業体(⼤規模) 宮城⼗條林産株式会社 ⼭林部課⻑・経営企画室⻑ 梶原領太⽒ ⼤規模林業事業体視点での データ活⽤に必要な 経営・業務の考え⽅について ITベンダー 株式会社マプリィ 執⾏役員 中村⼤知⽒ ITベンダー視点での 事業体のデータ活⽤に繋げる “伴⾛”プロセスについて 先進事業体(⼩規模) 株式会社森淵林業 代表取締役 森淵百合明⽒ ⼩規模林業事業体視点での データ活⽤に必要な 経営・業務の考え⽅について アウトプット 林業業界の “データ活⽤⼒” における 特に経営・業務 レイヤーのポイントを 整理 ※⽇程の都合により森淵⽒は事前ヒアリングのみ 12
データ活⽤⼒とは 座談会において、事業体がデータ活⽤⼒を⾼めるうえでのポイントが⽰唆された。 n 座談会で出た主な論点としてここでは整理。 林業事業体がデータ活⽤⼒を⾼めるポイント 規模 経営・組織 ü 間接部⾨や⼈材に投資ができ る”規模”を⽬指すことも重要。 中⻑期ビジョン ü 組織としての中⻑期ビジョンがある ことで、そこに必要なデータに対して 投資ができるようになる。 成果把握&改善 ü 業務の”成果”を定量的に把握す るとで、初めて改善活動ができる。 ⽇報の重要性を認識すること。 先進事業体から の横展開 ü 成果が出やすい⼤規模事業体が 得たデータ活⽤ノウハウは、地域で 横展開していけるとよい。 ⼩さな成功体験 ü ⼩さくてもよいので、改善を感じる ところまでいけば、モチベーションや リテラシーは徐々に伝播していく。 ⾼リテラシー⼈材 の活⽤ ü 全員が使いこなせる必要はなく、 若⼿の⾼リテラシー⼈材を上⼿く 使っていく。 業務プロセス ⼈材・現場 異分野事業者・ベンダー等が 林業事業体へ⽀援するポイント ビジョン作りへの 壁打ち ü 異分野での経験や地域外の 情報を活かした、経営のディ スカッションパートナーというニー ズもある。 先進事業体との 協業による コンサルティング ü 先進事業体を単なる顧客で はなく、実績を作って地域に 横展開するパートナーと捉え、 関係性を構築する。 最初の 成功体験までの 伴⾛ ü 最初の成功体験を得られる まで丁寧なフォローアップをす ることが重要。顧客にとって緊 急性が⾼いニーズから優先順 位を付けて対応していく。 13
規模の重要性 間接部⾨や⼈材への投資ができる”規模”を⽬指すことも⼀定重要。 n データ活⽤⼒を⾼めるうえで、事業体としての”規模”の成⻑を⽬標に置くかどうかは⼤きな論点。 l 規模が⼤きくなればなるほどデータ取得・活⽤のメリットが顕著に表れる。⼩規模事業体においては、他の事業や売り上げ等を 組み合わせるなどして、当該投資ができる環境を整えることが重要。 事業規模を拡⼤することで促進できる”投資” データ活⽤⼒につながる経営上のメリット 間接部⾨への 投資 ü 間接業務を専業で⾏う⼈材が専業で置け る規模になると、組織内の成果・数値管理 が容易になる。 成果が 把握しやすい ü 業務効率化のための投資を⾏った場合の 投資対効果が把握しやすい。 ⼈材への投資 ü 間接部⾨が確⽴できると、中⻑期視点で ⼈材の採⽤〜育成のプロセスを整備するこ とができる。 成果が出るまで 我慢できる ü データ活⽤リテラシーが組織内に浸透してい くまでの期間をトレーニング期間と割り切る ことができる。 技術・設備への 投資 ü 多額の投資が必要になる技術・設備の 導⼊についても中⻑期で回収する視点で 投資できるようになる。 データに基づいた 評価・育成が できる ü 導⼊した技術・設備にあわせて業務を標準 化していくことで、属⼈性を減らし、論理的 に⼈材を評価・育成することができる。 14
中⻑期ビジョンの重要性 ⾃社があるべき姿を⼤局観をもって描くことで、データの活⽤の仕⽅をバックキャストできる。 n デジタル投資を短期的視点(省⼒化効果等)のみで捉えるのではなく、実現したい経営・ビジネスモデルに必要な 要素を獲得するという⻑期的視点を持つと、投資対効果を広く認識できるようになる。 n 特に⾃社のあるべき姿をバックキャストしていくプロセスにおいて、ITベンダーや異分野事業者がその壁打ち相⼿として 視野を広げる・視座を⾼める有効なディスカッションを提供できる可能性がある。 参考)宮城⼗條林産における中⻑期ビジョンの策定プロセス 約2年半かけて全社的に議論 外部環境調査 (インプット) ⾃社のあるべき姿の検討 (バックキャスト) 現状の課題分析 (フォアキャスト) ü ターゲットイヤーを設定(30年後) ü 30年後の世界はどうなっているか、 グローバル視点で関連しそうな領 域(⼈⼝減少、ESG投資の⾼ま り…等)のシナリオを調査・研究。 ü インプットした内容を定例会議で 共有・ディスカッション ü 30年度のメガトレンドにあわせて、 ⾃分達がどうありたいかを議論。 ü 会議を重ねる毎に、議論を具体 化させていき、徐々に現場メンバー も参加させていく。 ü アウトプットとして、ミッションビジョン バリュー(MVV)を設定・公開。 ü MVVを実現するための、現状との ギャップなどの課題を洗い出し。 ü 要対応事項について優先順位を 付けて、直近10年間で対応するべ き具体的計画に落とし込む。 バックキャスト・フォアキャストの結果、⽊材の地域での”安定供給”を実現するうえで、 ü 更なる規模拡⼤(15万m3/年→100万m3/年) ü 規模を実現するうえでの⼭林査定・取得能⼒の向上・標準化 などが具体的な⽬標として掲げられたことで、ドローン・GISなどのデータ取得に 関する投資が、当該⽬標そこに必要な投資と位置づけられた。 15
中⻑期ビジョンの重要性 参考)宮城⼗條林産の中⻑期ビジョン n 「全ての⼈々と共有する森林の価値を最⼤化する」というビジョンを実現するうえで、まず森林の価値を可視化してい くことが重要であり、データ取得・活⽤に関する投資を位置づけている。 https://miyaju.co.jp/mvv/ 16
成果把握と改善プロセスの重要性 業務の”成果”を定量的に把握することで、初めて経営・業務の改善ができる。 n 規模の⼤⼩に限らず、データを確りと”経営改善”に繋げる意識があれば、成果は出せる。 n 成果の定量化は、成果がみえること以上に、成果が出なかったことの”原因”を究明し、適切な対策を講じることが できることに意義があると、先進的にデータ活⽤を⾏っている事業者は捉えている l それさえできればある意味、⾼度な技術・ツールは不要。 参考)森淵林業における”データ活⽤”の流れ 現場① 担当A⽒、B⽒、C⽒ ⾒積 途中経過 Excel Excel シート シート (現場毎) (現場毎) 細かく⼯程を分けて 事前⾒積を実施 実績を踏まえて 次の⾒積の制度を⾼める ⽇報にて⼯程毎に 実績をインプット 実績 振り返り Excel シート (現場毎) A⽒ B⽒ C⽒ Excel Excel Excel シート シート シート (A⽒) (B⽒) (C⽒) 複数現場のデータをメンバー毎に整理し 従業員の成果や特性を評価・分析 現場毎の振り返りMTGを実施し 設備や⼯程の要改善点を議論 DXに限らず、従業員の”頑張り”を評価するうえ で、成果の⾒える化は重要。新しい機械や技術 を⼊れると最初現場は苦労するが、その効果が ⾒えることで、⾃分達の評価や給与にも繋がっ ていくことを実感できる。 ⼯程に分けた細かいデータがあると、じゃあ○○ を変えてみるか…と対策が打てる。それが無いど んぶり勘定だと、現場に「頑張れ」しか⾔えない。 意味ある対策をとって、現場を評価していくこと が、データ取得の⼀番の⽬的と考えている。 森淵林業 森淵代表への ヒアリング時のコメント 17
成果把握と改善プロセスの重要性 参考)森淵林業で⽤いられている成果管理シートのイメージ(⾒積) 単価算出⽤データベース 使⽤機械 xxxx xxxx xxxx xxxx 機械⾦額 耐⽤年数 稼働時間 機械単価 燃料単価 稼働単価 (円) (年) (年間) (円/時間) (円/7h) (円/h) x,xxx,xxx xx x,xxx xxx x,xxx xxx x,xxx,xxx xx x,xxx xxx x,xxx xxx x,xxx,xxx xx x,xxx xxx x,xxx xxx x,xxx,xxx xx x,xxx xxx x,xxx xxx ⼈員 ⽉給 賞与 社会保険料 労働⽇数 労働時間 (円) (円) (円) (⽇/⽉) (h/⽇) 従業員A xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xx 従業員B xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xx 従業員C xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xx 従業員D xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xx 時間単価 (円/h) x x,xxx x x,xxx x x,xxx x x,xxx 現場名 施業⾯積ha 成⽴本数 保育間伐⾯積 利⽤間伐⾯積 xxxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx ⼯程 xxxx xxxx xxxx xxxx 数量 xx xx xx xx 単価 契約⾦額 ⽬標予算 x,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx ⽬標予算内に⼊るように稼働時間と 作業時間の⾒積を⼊⼒ ⾒積⼊⼒シート 予め、機械別、⼈員別に 時間単価を算出するデータベースを構築 時間を⼊⼒すると ⾦額に変換 引⽤)森淵林業提供資料を参考にJISSUI作成 現場の契約情報から⼯程毎の⽬標予算を設定 現場情報⼊⼒シート 作業⼯程 機械名 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 稼働単価 稼働時間 作業⼈員 時間単価 作業時間 計画予算 x,xxx xx 従業員A x,xxx x,xxx 従業員B x,xxx xx x,xxx,xxx x,xxx 従業員C x,xxx x,xxx 従業員D x,xxx x,xxx 従業員A x,xxx xx x,xxx xx 従業員B x,xxx x,xxx,xxx x,xxx 従業員C x,xxx x,xxx 従業員D x,xxx xx x,xxx 従業員A x,xxx x,xxx 従業員B x,xxx xx x,xxx,xxx x,xxx xx 従業員C x,xxx x,xxx 従業員D x,xxx 18
成果把握と改善プロセスの重要性 参考)森淵林業で⽤いられている成果管理シートのイメージ(予実・⽬標管理) 進捗を⾒ながら必要に応じて⼯程⾒直し ⼯程表・予実管理表 作業⼯程 計画 機械名 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 実績 稼働単価 稼働時間 作業⼈員 時間単価 作業時間 計画予算 機械名 x,xxx xx 従業員A x,xxx xxxx x,xxx 従業員B x,xxx xx x,xxx,xxx xxxx x,xxx 従業員C x,xxx xxxx x,xxx 従業員D x,xxx xxxx x,xxx 従業員A x,xxx xx xxxx x,xxx xx 従業員B x,xxx xxxx x,xxx,xxx x,xxx 従業員C x,xxx xxxx x,xxx 従業員D x,xxx xx xxxx x,xxx 従業員A x,xxx xxxx x,xxx 従業員B x,xxx xx xxxx x,xxx,xxx x,xxx xx 従業員C x,xxx xxxx x,xxx 従業員D x,xxx xxxx 各作業員が⽇報に⼊⼒した内容がリアルタイムで反映 作業員A ⽇報 ⽇付 4/1 4/2 4/3 4/4 作業⼯程 使⽤機械 作業時間 xxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xx 引⽤)森淵林業提供資料を参考にJISSUI作成 稼働単価 稼働時間 作業⼈員 時間単価 作業時間 実績⾦額 x,xxx xx 従業員A x,xxx x,xxx 従業員B x,xxx xx x,xxx,xxx x,xxx 従業員C x,xxx x,xxx 従業員D x,xxx x,xxx 従業員A x,xxx xx x,xxx xx 従業員B x,xxx x,xxx,xxx x,xxx 従業員C x,xxx x,xxx 従業員D x,xxx xx x,xxx 従業員A x,xxx x,xxx 従業員B x,xxx xx x,xxx,xxx x,xxx xx 従業員C x,xxx x,xxx 従業員D x,xxx 班・従業員別に集計して⼈材育成・評価に活⽤ 班・従業員別集計 ⼈員 ⼯程 従業員A xxxx xxxx xxxx 従業員B xxxx xxxx xxxx 予実差 x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx 機械別に集計して最適な設備配置に活⽤ 機械別集計 ⽬標値 実績 xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx 機械名 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 稼働時間 x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx ⽣産性実績 xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx 19
先進事業体の成果の横展開 社内で担当者が付けられる規模の事業体が、先⾏してツール等を導⼊し、「使いこなし⽅」を 内部で構築できれば、ITベンダーと協業して他事業体に横展開することが可能になる。 n ITベンダー等が、林業事業体の内部業務を完全に理解することは難しい。また⼩規模事業体は⼈⼿不⾜で「使いこ なし⽅」を⾃ら構築していく⼿間がかけられない。まずは効果を出しやすい⼤規模事業体が地域で率先して導⼊し、 使いこなし⽅を構築できれば、地域内でノウハウが横展開されていく可能性がある。 n ⼤規模事業体にとっては、当該技術を地域事業者がみんな使うようになることで、補助⾦ルールも当該技術を扱う ことが前提になるなど、先⾏投資した成果がより出しやすい環境にもっていける可能性がある。 STEP1:ベンダーと伴走して 初期プロダクトを共同開発 STEP2:技術活用ノウハウの内製化 STEP3:林業SIerとして横展開 各種事業体 大規模事業体 社内 IT担当者 大規模事業体 各種事業体 社員 各種事業体 ツール提供 使い⽅⽀援 ITベンダー等 ITベンダー等 ü 外部ベンダーと連携して、大規模 事業体が初期プロダクトを導入・実証 ü 社内で本格導入しつつ、データ活用 ができるメンバーを社内で育成 ü 林業現場からのフィードバックを 受けて、ITベンダー側もプロダクトを ブラッシュアップ ü データを活用して業務改善につなげる プロセス・ノウハウを社内で構築 事業体 ü 当該人材が、技術と業務の両方が分かる 人材となり、異分野技術等の横展開を推進 ⇒ルール整備が加速し、所属事業体に とっても有利な業務環境が整っていく。 例) 宮城⼗條林産(⼤規模事業体)は ドローン販売店(ITベンダー等)と 連携し、ドローンで取得したデータの 活⽤⽅法・業務について コンサルティングを⾏っている 20
⼩さな成功体験 最初から⼤きな成果を求めずに、できるだけ短期で多く、⼩さな成功体験を設定する。 ⼤きい効果が期待できる “A⽤途”で導⼊説明 A⽤途で利⽤ 最初から⼤きな 成果を求めて しまった場合 まず最初にやる意義を理解できない⼈が多い ”使えない”理由探しが始まる。 反応・雰囲気に 「現場のこと分かってないな」 諦めを感じる 「やっぱうちじゃ無理か」 ⼩さいけど効果が実感しやすい “B⽤途”で導⼊説明 B⽤途で利⽤ (⼩さな成功体験) 結果、ツールは導⼊されたものの 現場のモチベーション・リテラシーは上がらず A⽤途で使いこなされず、効果が出ない A⽤途へ利⽤拡⼤ (本質的な変⾰) ⼩さな成功体験 を意識して 作る場合 最初から、ある程度のメンバーが ITツール等の導⼊の意義や⽬的が理解できる ポイント① 最初の⽤途設定 ü 事業体とITベンダーの間で、直近の困り事から ⼩さくてもよいの効果を実感しやすい⽤途を 設定することが重要。 業務改善効果等を実感し、 「もっと使いこなしたい」 他のメンバーの成功体験をみて 「これなら⾃分もできそうだ」 能動的に実⾏するメンバーが出現 「こんなこともできそうだ」 使っているうちにリテラシーが浸透 「何をやりたいかが分かってきた」 ポイント② 成功体験までのフォロー ü 効果を実感するまで集中的にフォロー。 ボタンひとつの押し⽅まで丁寧に伴⾛し、 最初の成功体験まで繋げることが重要。 ü 成功体験を超えれば、メンバーの間で モチベーションとリテラシーは伝播していく。 21
⼩さな成功体験 参考)⼩さな成功体験をで積み重ねることが、組織全体の”⾃⼰効⼒感”を醸成する。 n ⼈間は誰しも、⾏動が成果に結びつく「結果期待」と、そこに向けて⾃分がうまく⾏動に移せる「効⼒期待」の2つが あって、はじめて能動的に⾏動に移せる。 n 効⼒期待(=⾃⼰効⼒感)を⾼めるうえで、直接的な成功体験と、代理体験(他の⼈の成功体験の伝聞等) は重要な要素であり、組織内で成功体験と代理体験を多く⽣む環境作りが、データ活⽤⼒を⾼めていくうえで重要。 l 近しい⽴場の⼈間の成功体験を観察することは、⾃⼰効⼒感を⾼めることに繋がる。⾃⼰効⼒感は組織内で積み重ねられる。 ⼈が成果を出すために必要な”期待” ⼈材 ⾏動 person 結果 Behavior 効⼒期待 ⾃⼰効⼒感を⾼める4要素 Outcome 結果期待 Efficacy Expectation Outcome Expectation ⾃分ならできる これならやれそう この⽅法は”よい”な うまくいきそう “効⼒期待”が⾏動を促し、⾏動の先に”結果期待”がある。 “効⼒期待”が⾼いほど、⼈は積極的・能動的に⾏動する。 成功体験 ⾃らの過去の成功体験が ⾃⼰効⼒感を強く⽣みだす。 代理体験 他⼈がやっているのを⾒る事で 「⾃分にもできるはず」と考える。 ⾔語的説得 「やればできる」と周囲から説得する のはやりやすいが効果は薄い。 感情的な⾼揚 ドキドキワクワクなど⾼揚感を伴う際は ⾃⼰効⼒感も⾼まる。 Performance Accomplishments Vicarious Experience Verbal Persuasion Emotional Arousal 組織内で成功体験と 代理体験を多く⽣む 環境作りがポイント (が、林業現場では効⼒期待が低いケースが散⾒される) 引⽤)Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215 を参考にJISSUI作成。. 22
⾼リテラシー⼈材の活⽤ 必ずしも全員が使いこなせる必要はなく、⾼リテラシー⼈材(コア技能者)を上⼿く使っていく。 n 重要なのは、組織全体での⽬的・意義の理解。 ITベンダー・ 事業改⾰担当職員 定量的に分析し、分かり易く伝えるプロセスを⽀援 ①⾼リテラシー層とのコミュニケーション ü まずは⽐較的リテラシーが⾼い 若⼿職員等に集中的にフォロー。 ü いきなり全ての機能を使いこなすの ではなく、現場のニーズが⾼い機能 に絞って操作⽅法等をレクチャー ③成果を分かり易く可視化する ü ⾼リテラシー⼈材の間で⽣まれた成果を ITが⽐較的得意な 若⼿職員等 ⼩さな成功体験による (コア技能者) モチベーションとリテラシーの ITがあまり得意ではない ベテラン職員等 伝播・浸透 ②若⼿が成果を出し始めて存在感を⾼める ü まず使えるところから使っていくことで ④ベテランが意義を理解し、取組拡⼤を応援・協働する ü 最初は理解ができなかった技術導⼊についても 現場で⼩さな成果を作っていく。 ü 成果がみえてくることで、組織内における 若⼿職員の存在感が⾼まっていく 実際の成果をみて意義や⽬的を理解し始める。 ü より⼤きな成果を求めて、ベテランも巻き込む必要がある ⼤きな取り組みに発展していく際、若⼿の取り組みを ”応援”する⽴場として協働できるようになる。 23
深掘りテーマ②: 「森林・林業の”新しい付加価値”をエンドユーザー視点で考える」 林業DX・イノベーションの 課題 課題② 需要縮⼩局⾯において 作業効率向上以外の 価値軸も探る必要がある 深掘りテーマ 内容・登壇者 本レポートを読んで欲しい 主なターゲット テーマ② 森林・林業の ”新しい付加価値”を エンドユーザー視点で考える エンドユーザーのニーズに触れる川 下事業者との議論から得た、 DXの先にある新しい価値軸を探 るうえでのヒントを共有 (登壇者) ü ⽇建設計⼤庭⽒ ü アトリエフルカワ古川⽒ ü ⽊⻘連R3年度会⻑松原⽒ ü デジタル化・作業効率化において は⼀定の成果を出しつつも、中⻑ 期⽬線でそれ以外の⽅向性を 探っておきたい林業事業体 ü 林業事業体を⽀援していくうえで、 より⼤きな市場や提供価値を⾒ 据えたいコンサル・ベンダー・異分 野事業者 24
新たな付加価値を⽣む必要性 ”収益”に直結する付加価値向上・事業創出まで踏み込まなければ、投資額を回収できない。 収益向上を⽬的としたデジタル化の必要性が”DXレポート2.2”等でも触れられている。 n 破壊的イノベーションの領域においては、⽊材を効率的に搬出するデジタル変⾰の⽬的を超えた“収益”に直結する 議論を⾏わなければならないが、殆どの林業事業体は、そこまで議論が⾄っておらずITの活⽤⽬的を 「既存ビジネスの効率化」の範疇でしか捉えられていない。 新規デジタルビジネスの創出 (デジタルでしかできないビジネス) 収益に直結する 既存ビジネスの付加価値向上 引⽤)経済産業省 デジタル産業への変⾰に向けた研究会 「DXレポート2.2(概要)」 25
新たな付加価値を⽣む必要性 森林・林業分野は、住宅・建材業界との間で、効率化中⼼の低位安定状態が続いている。 n 下記DXレポートにおいて、ユーザー=建築業界、ベンダー=林業業界、と捉えると、同じ構造に⾏き着く。 n 「⽬の前に提⽰されるユーザー要求に応じ続けた結果、労働量を対価とする受託型ビジネスから脱却できていないの ではないか」というITベンダーにおける課題感は、そのまま林業業界にも当てはまる。 DXを阻害するユーザーとベンダーの低位安定状態(⻘字で林業における構造を追記) 建築業界(川下) 林業業界(川上) ⽊材はコスト。⼀律に仕様を定めて 発注することで業者間を競争させ コストを削減 “材積”に対する対価として値付け、 低リスク・低利益のビジネスを享受 引⽤)経済産業省 第3回デジタル産業への変⾰に向けた研究会資料を参考にJISSUI作成。 26
新たな付加価値の⽣み⽅ 新しい付加価値創出は、ユーザー企業(川下)とベンダー企業(川上)の共創が不可⽋。 n ⼀事業者のみでは、市場全体の価値観をシフトさせることはできない。 n これまで川上と川下は地域や商流により分断され、価値観ベースでつながれる場が少なかった。 建築業界(川下) 林業業界(川上) 建築業界(川下) 林業業界(川上) 引⽤)経済産業省 デジタル産業への変⾰に向けた研究会 「DXレポート2.2(概要)」を参考にJISSUI作成。 27
座談会メンバー 新しい付加価値創出を試みているユーザー企業(川下)による座談会を実施。 座談会登壇者 主に⼩規模・住宅領域 アトリエフルカワ⼀級建築事務所 代表取締役 ⽊造・⽊材コーディネーター 古川泰司⽒ プロフィールと議論の視点 ⼀級建築⼠として主に⼾建て等の設計 を⾏いつつ、林業と建築について議論する 対話型セミナー「森と建築を⼀緒に考える」 を主催するなど、⽊造・⽊材コーディネーター としての情報発信等も⾏っている。 主に中⼤規模・⾮住宅領域 株式会社 ⽇建設計 「つくればつくるほど⽣命にとって良い建築」 を⾃⾝のマニフェストとし、建築・都市の 設計技術部⾨ テックデザイングループ Nikken Wood Lab ダイレクター ⼤庭拓也⽒ ⽊質化に従事。最近では森林と都市の 新しい関係を⾒いだす「つな⽊」プロジェクト を推進中。 その他⽊材関連事業全般 ⽇本⽊材⻘壮年団体連合会 令和3年度会⻑ 松原 輝和⽒ アウトプット 川下(エンドユーザ)視点の 新しい付加価値に対する ニーズを整理 林業DXの先にある新しい 価値軸を探るヒントを共有 広葉樹フローリング材の製造・販売を軸とし て⽊材関連の新規事業に携わる。⽊⻘連 においては前会⻑として”ウッドエンターテイン メント”を掲げて普及活動を図るなど、⽊材 の性能コスト以外の価値軸を探ってきた経 営者のひとり。 28
イノベーションの源泉 ”前提条件の変化”への対応が、イノベーションの源泉となる。 既存事業者 ⻑年積み重ねた 経営資源 (ヒト・モノ・カネ・コネ) 新規参⼊者 アイデア 内発的 動機 経営資源を持たない新規参⼊者は 既存事業を否定する破壊的イノベーションを志向 ⇒経営者は”時代の変化に適応”し続ける 企業内にいる限り、現在の経営資源を活⽤する事が合理的 ⇒構造的に”経営資源に最適化”し続ける 新ビジネスが⽣まれる条件としての “前提条件の変化” ü 技術 ü 価値観 ü 社会構造 29
川下の新しいニーズ仮説 ⽊造建築・住宅を取り巻く3つの前提条件の変化から、 企業向けの環境的価値と、個⼈向けの情緒的価値の2つのニーズが⽣まれつつある。 前提条件の変化(⼀部) 1. 社会構造の変化 【企業への環境貢献外圧】 特に⼤企業に対して、脱炭素やネイチャーポジティブに 関する取り組みを求める外圧が増加している。 2. 技術の変化 【計測・デジタル技術の成熟】 ドローン・レーザー・画像解析AI等、川上側で詳細な 森林資源情報を把握できる技術が成熟してきている。 3. 価値観の変化 【ユーザーの成熟・多様化】 標準的・均質的な住宅・建築では 施主・ユーザーのニーズを満たせなくなってきている。 川下の新しい付加価値(仮説) ニーズ① 環 境 的 価 値 カーボンニュートラル ⽊造建築等による 炭素固定 サーキュラーエコノミー ネイチャーポジティブ 地域資源の 持続可能な有効活⽤ ニーズ② 情 緒 的 価 値 ライフサイクルでの 環境負荷への配慮 地域・コミュニティ への帰属・貢献 顔・⼈格が⾒える 信頼感 推し消費に繋がる 役物ブランディング 30
川上側に求められる活動 現状でそれぞれの製品は⽣まれつつあり、川上側も変化・対応が求められている。 川下の新しい付加価値(仮説) ニーズ① 環 境 的 価 値 カーボンニュートラル 川上側に求められる活動 ①地域材活⽤を実現する対話の場 ⽊造建築等による 炭素固定 サーキュラーエコノミー ネイチャーポジティブ 関連する川下製品 ライフサイクルでの 環境負荷への配慮 Ø 現状では施主側が環境的価値を踏まえた⽊造 ニーズがあったとしても、設計者側が川上側の状 ⽊あらわしの 中規模⽊造建築 (準耐⽕以下) 況を踏まえた提案ができる設計者は限られる。 本質的な環境的価値を発揮できる設計を施主 へ提案するには、設計段階から川下と川上が対 話する場が必要。 ②植林や資源循環まで含めたトレサビ ニーズ② 情 緒 的 価 値 地域資源の 持続可能な有効活⽤ 地域材を活⽤した 家具・内装等プロダクト 推し消費に繋がる 役物ブランディング 銘⽊・役物 地域ブランド材 地域・コミュニティ への帰属・貢献 顔・⼈格が⾒える 信頼感 Ø ①の対話により適切な仕様・規模で発注されれ ば、地域資源を活⽤した循環型のプロジェクトに 対応できる可能性が⾼まる⼀⽅で、単なる⽊材 調達先のトレースを超えた、川上の施業状況まで 含めたトレーサビリティが求められることとなる。 ③⽴⽊段階の接点作り・ファン作り Ø ⽊材という材料を供給する⽴場のみでは、新し い付加価値が⽣まれたとしても川上には還元さ れない。伐採前の⽴⽊段階で、体験価値や所 有体験などを経て、いかに接点を作るかが重要。 31
①地域材活⽤を実現する対話の場 脱炭素の先のサーキュラーエコノミー・ネイチャーポジティブを⾒据えたとき、地域材が活⽤できる 規模・仕様での⽊造提案は付加価値があり、設計段階からの川上・川下の対話が重要。 n 外材も含めて全国から⽊材をかき集めて実現する⽊造建築は、カーボンニュートラルの観点では⼀定寄与するものの、 地域材を活⽤した⽊造建築の⽅が、より上位の持続可能性・環境負荷の観点で付加価値を⽣むことがある。 n 現状、施主⇔川下⇔川上は受発注の関係性にあり、決まった仕様にそのまま対応していくなかでは、地域材活⽤ は難しいケースが多い。規模、仕様、納期等、地域プレイヤーが対応できる設計⾃体を、施主⇔川下⇔川上の間で 対話できる場があれば、より本質的な環境価値を⽊造建築にて実現することができる。 l ⼩規模流通においては、設計者⾃⾝あるいはプレカット流通事業者が、当該情報流通のハブ・コーディネーターになっているケー スがみられるが、中⼤規模向けの⼀般流通においては、まだこの対話の場は不⼗分な地域が多い。 川上と川下の情報流通(⼀般的な中⼤規模向け) 現状 川上と川下の情報流通 あるべき姿 ③需要情報に基づく ⽣産体制の構築・投資 情報の断絶 森林 所有者 素材 ⽣産 製材 加⼯ ③結果として、決まった仕様で 対応することしかできず、地域の プレイヤーのみでは対応できない (結果として環境価値が薄まる) プレカット 流通 設計 ②⼀般的な⼤規模 流通では川上側の 細かい情報を把握で きていないことが多く 施主 消費者 ①施主のオーダーで 環境価値が付加された ⽊造建築を検討するも 森林 所有者 素材 ⽣産 製材 加⼯ ②川上との連携による 地域循環可能な規模・設計の提案 プレカット 流通 設計 施主 消費者 ⽊材コーディネーターネットワーク ①川上と川下が需要・供給の情報を共有し 設計段階で⽊材調達のフィージビリティを検証 32
①適切な”規模”を設定するための対話 参考)昭和学院⼩学校 ウエスト館 経済性、意匠性に配慮し、⽤途・規模から逆算して、CLTによる⽊造校舎を提案した。 昭和学院⼩学校 ウエスト館の概観 ※)⽇建設計WEBサイトより写真引⽤ 地域材の活⽤を促す⽊材調達の在り⽅(と現状) ※)⼤庭⽒講演資料より図表引⽤ 請負契約 設計者 基本 計画 基本 設計 竣⼯ 実施 設計 設計段階での 施⼯者 調達調整 施⼯ 調達から 逆算した設計 ⽊材 調達 調達 (理想) 設計側が、基本設計段階で ⽊材を使うことを前提に コミュニケーションが取れることが理想。 引⽤)https://www.nikken.co.jp/ja/projects/education/showa_gakuin_elementary_school_west_wing.html 調達 (現状) 現状では⽊材調達のリードタイムが 短く、地域材では対応できない ケースが多い 33
②植林や資源循環まで含めたトレサビ 川下視点では環境負荷に関するデータへのニーズは⾼まりつつあり、認証材が⾜りない状況。 今後、川上側はより本質的な”トレーサビリティ”に対応していく必要がある。 n 製造業全般として、サプライチェーン全体・ライフサイクル全体での環境負荷低減やコンプライアンス遵守は、特に上場 企業においては近々で対応必須な課題。建築業界でも同様だが、今後国産材は当該ニーズに⼗分な情報の提供 が必要と考えられる。 n 現状の森林認証制度は、森林所有単位での認証となっており、⺠有林において⽴⽊買い・皆伐・再造林を進めて いく⼤半の商流に対応できていない。伐採単位、⽊材単位での、⾃然資本への配慮・再造林等のコンプラ対応状 況についての情報流通が必要になってくると考えられる。 森林認証の取得の障害(農⽔省「森林資源の循環利⽤に関する意識・意向調査結果」より引⽤) 順位 H27調査(N=120) 順位 R2調査(N=690) 1位 森林認証材が⼗分に評価されていない (49.2%) 1位 森林所有規模が⼩さく、取得しても⼗分に 活⽤できない(32.5%) 2位 森林所有規模が⼩さく、取得しても⼗分に 活⽤できない(46.7%) 2位 取得およびその後の維持に費⽤がかかるこ と(15.1%) 3位 取得およびその後の維持に費⽤がかかるこ と(32.5%) 3位 森林認証材が⼗分に評価されていない (18.6%) 4位 取得する際の審査が⼿間であること (21.7%) 4位 取得する際の審査が⼿間であること (8.7%) CoC認証を取得している製造・加⼯・流通 業者が少ないこと(21.7%) 5位 5位 CoC認証を取得している製造・加⼯・流通 業者が少ないこと(5.1%) 森林所有規模が⼩さい 多くの⺠有林現場では 取得コストに⾒合わないため 森林集約の推進あるいは 認証以外のトレサビが必要 森林認証等の環境価値を 証明するトレーサビリティの ニーズは⾼まり、認証取得の 障壁ではなくなりつつある 34
②植林や資源循環まで含めたトレサビ 参考)川下側で脱炭素以外の”情緒的価値”を訴求する企画に対応するには、 より細かいトレーサビリティ情報が必要になる(が、現状では認証・産地程度しか分からない)。 n 選⼿村ヴィレッジプラザでは、⽊に産地を刻印したり、⽊材をレガシー活⽤するなど、トレーサビリティ⾃体を空間や体 験における価値に転嫁しようとした事例。⼀⽅、⽊材調達においてはかなり苦労したとのこと。 選⼿村ヴィレッジプラザ アトリエフルカワ古川⽒による座談会時のコメント 「良い⽊」を使いたいという役物に対する施主 のニーズは少なからず存在する。そのニーズは、 地域や⼈、コミュニティに紐付く情緒的な側 ⾯が強い。 これまでは、どこの誰から買った…という特定の ⼈格や信頼に紐付くことが多かったが、最近 は「ちゃんと植えているのか」「⼭にお⾦が還 元されているのか」といった、川上まで含めた 「良い⽊」に興味を持つ施主も増えてきてい る。 引⽤)静岡県webサイト「東京2020オリンピック・パラリンピック×しずおかの⽊ レガシー材とは⼀体”何者”??」 https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kenchiku/kizukai/1054945/1057672/1064335/index.html 35
③⽴⽊段階の接点作り・ファン作り アセットとしての森林と、フローとしての⽊材は時間軸が合わず、⽊材の付加価値は川上にが 還元されない。⽴⽊段階での接点・ファン作りにより、森林へ”直接払い”を⾏うモデルが必要。 n 環境価値を発揮するためであれば、不燃処理⽊材などの⾼単価な⽊材であっても利⽤する施主側のニーズは存在。 n ⼀⽅、⽊材利⽤が⽣み出す環境価値を含む付加価値は、通常は川上に還元されない。 森林(アセット、⽂化) ⽊材(フロー、⽂明) 商品(消費者) 森林というアセットから、材料・資源的価値を フローとして取り出して、価値を媒介する。 森林にまつわる価値資本 ⽊材の材料・資源的価値 ⼈・コミュニティ の魅⼒ 地域・⽂化的 価値 環境価値を含めた付加価値に対して 消費しても、⻑い商流によって川上側 環境的 価値 過去から“役物”として⾼単価で扱われるものは 誰からどこで買うか…といった地域や⼈に蓄積された には還元されない。 エンドユーザーから森林に対する直接払うモデルがあれば、 時間軸の違いを超えて川上に付加価値を還元できる。 ⽂化資本的価値に起因する。 →体験(地域ツアー)や所有(森林付き○○)によって ⽴⽊段階で当該資本に触れ、接点・ファン作りを⾏う活動が有効。 36
③⽴⽊段階の接点作り・ファン作り 参考)⽴⽊段階での地域訪問や情報流通がポイントとなり、デジタル技術が可能性を拡張。 n IoTセンサーやドローン等の技術⾰新や、ブロックチェーンなどのデジタル技術の発展は、森林の様々な価値を可視化 し、森林への直接払い・コミュニティ参加のハードルを下げていく。 ⻄川Rafters ⾥⼭広葉樹活⽤プロジェクト • 企業の研修受け⼊れや、地域でのワークショップ開催など、様々な体験 価値を通じて、先に”⻄川材”のファンを作ることに⼀定成功している事例。 • ⽴⽊に電⼦タグを付与することでデジタルカタログ化し、⾼単価で売れ る川下を確保した状態で伐採を⾏うことで、川上への利益還元を⽬ 指す取り組み。 引⽤)⻄川RaftersWEBサイト https://www.nishikawa-r.com/ 引⽤)神⼾⼤学MORI TAGシステム https://www.kobe-u.ac.jp/ja/announcement/2022_12_05_01_0/ 37
本資料は、林野庁事業「森ハブ・プラットフォーム」における会員等に向けた情報発信の⼀貫として、 (⼀社)⽇本林業技術協会ならびに(⼀社)社会実装推進センターによって作成されたものです。 38