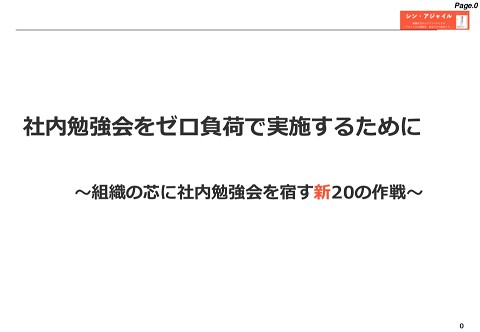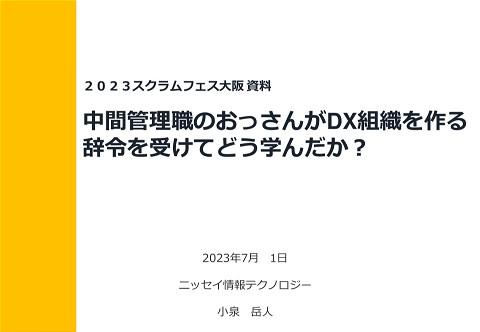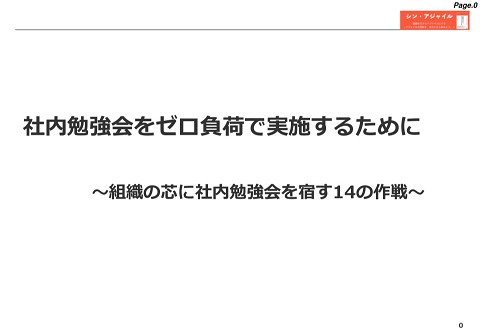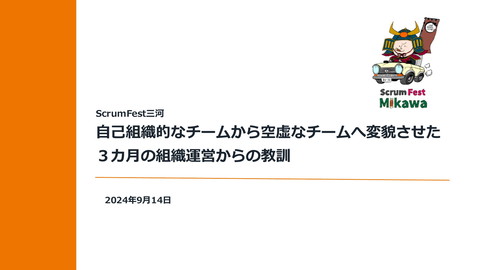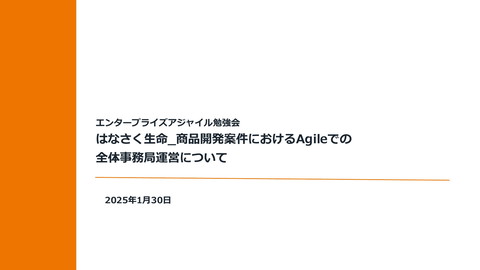組織、チーム作りのヒントとなる2つの本(冒険する組織のつくりかた、組織を芯からアジャイルにする)
2.9K Views
March 05, 25
スライド概要
社内勉強会で使った資料になります。
「冒険する組織のつくりかた」と「組織を芯からアジャイルにする」が組織変容のヒントになるという話をしています。
Insurtechラボで作成しているスライドです
関連スライド
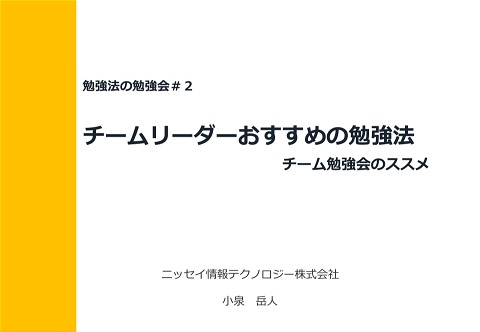
チームリーダーおすすめの勉強法
各ページのテキスト
学びフェス 組織・チームづくりのヒント 2025年3月4日
1.はじめに 2
1-1.自己紹介 小泉 岳人 X(Twitter):@koitake_ note :https://note.com/rich_hyssop406/ ニッセイ情報テクノロジー(株) プロダクトサービス事業推進室 主席スペシャリスト 趣味:コントラバス :カンファレンス動画の視聴 3
1-2.本日の資料のもととなる書籍 4
1-4.組織の設立から今までの経緯 (2004.4) 2022.4 2022.9 2024~ 入社(以降、ウォーターフォールのプロマネを10数年実施) 黎 明 期 ケ イ パ 取 得 期 転 換 期 保険SIの事業部にR&Dラボ設立 運営/ツール整備 練習でのプロダクト作成 複数の会社&事業部と共同でPJTを試行 チームブログ&アドベントカレンダー&社内勉強会 社外コミュニティ・登壇参加 社内で定例勉強会を開始 全社組織に再編 日経新聞にプロダクトサービスが搭載 社内勉強会を拡大 5
1-4.組織の設立から今までの経緯 (2004.4) 2022.4 2022.9 入社(以降、ウォーターフォールのプロマネを10数年実施) 保険SIの事業部にR&Dラボ設立 運営/ツール整備 2022年にラボ組織を設立してから 練習でのプロダクト作成 黎 明 期 ケ イ パ 取 得 期 複数の会社&事業部と共同でPJTを試行 組織に関して取り組んだ事や課題感について チームブログ&アドベントカレンダー&社内勉強会 2024~ 転 換 期 社外コミュニティ・登壇参加 本と絡めて説明します 社内で定例勉強会を開始 全社組織に再編 日経新聞にプロダクトサービスが搭載 社内勉強会を拡大 6
2.課題と方向性 7
2-1.組織の課題 キャリア観やビジネス観が大きく変わってきているが、古いOS(軍事的世界観)の ままだと対応できない 会社中心のキャリア観 会社 人生中心のキャリア観 地域 会社のために 何をすべきか 家族 ライバルと競争しながら 限られた領地を奪い合う 仲間と共創しながら より良い社会の 可能性を探究する 趣味 幸せな人生のために どうありたいか 副業 友人 会社 自分の人生 新しいキャリア観 新しいビジネス観 ・不正を根絶するために、心理的安全性を徹底せよ!! ・話題が無くてスキップされ続ける1on1 ・部下に関心が無い上司の、形だけの不自然な傾聴 新しいアプリケーションを入れても、 OSが古いまま 8
2-1.組織の課題 最適化、標準化を進めてきたやり方は、呪縛となっていく (大企業はいずれ必ず官僚化していく) 目の前 のミッ ション 部署、グ ループ 目の前 のミッ ション 部署、グ ループ 目の前 のミッ ション 部署、グ ループ 分業(分断)をもらたす、 体制の最適化 体制の 最適化 分業への指向 お互いの仕事の被りをなくす プロセスについていちいち迷わな いように選択肢を絞る=標準化 方法の 最適化 効率 化 最適化への最適 化という呪縛 標準化 より 効率化 単方向への硬直化 より 標準化 道具の 最適化 道具(ツール)について 『固定化』 9
2-2.方向性について 「個人の自己実現の探究」と「組 織/事業/社会的ミッション」の 探究の整合 探索と適応のリズムを刻む!! ⇒ 対話と互いの関心を 10
2-2.方向性について 合理的思考と野性的思考をバランスを保つ (現行は合理的思考によってるため、野性的思考への意識が大事) 目標に基づく“選択と集中” 社会的ミッションの探究 合理的思考 より良い経営目標 問いを起点とした“分散と修繕” 野性的思考 目標 エンジニアリング 合理的思考 計画 創発 ブリコラージュ 野性的思考 目標の 見通し 選択 活動 活動 活動 人材のポテンシャル 活動 自己実現の探究 合理と野生のバランスを保った マネジメント 資源の集中 現状 問い 活動 問いの修繕 「選択と集中」から「分散と修繕」へ 11
2-2.方向性について 新たなアイデンティティとなる自己実現の欲求を見つける!! 不整合の状態 Outside 外的価値 自己実現 期待されること 喜ばれること はじめは 折り合いが つかない 内的動機 Inside やりたいこと 興味があること Outside 好奇心(=内的動機)に基づ いた仕事が報酬や他者貢献 (=外的価値)につながる 外的価値 両者に整合がもたらされて、 「新たな自分らしさ」を発見した状態 内的動機 Inside 「成長できた」「一皮 剥けた」「充実してい る」という感覚 12
2-2.方向性について 「重ね合わせ」「ふりかえり」「むきなおり」の段階を繰り返し、リズムを 意識した動きが出来るようにする まずお互いの「状況」を理解し、 フィードバックが出せるようにする スプリントプランニング 第1段階 メンバー Aタスク 過去(過程と結果)を 学びに変える <重ね合わせ> チームの状況をわ かるようにする メンバー Bタスク メンバー Cタスク メンバー Dタスク 重ね合わせ プランニングとその結果を 同期、共有する 第2段階 見える化をし多様なメンバー 多様な意見で検証や試行を行い 解釈を対話により重ね合わせる <ふりかえり> 共通の課題を扱う 第3段階 <むきなおり> 向かうべき方向性 を見出す 将来(目的や目標)か ら現状の行動を正す スプリントプランニング メンバーA アウトプット メンバーB アウトプット メンバーC アウトプット メンバーD アウトプット 13
2-2.方向性について 心臓のようにリズムを作ることで、血(関心)を組織に通わせることができる ドーナツ型組織 1on1 OKR ハンガーフライト 陳腐化 した 意図 「これまで」を 頑なに守る方針 芯の無いドーナツのような組織とは心臓を失っ てしまった人体のようなものだ。 組織に血(関心)が通うことはない。 組織に赤い熱意を送り出す原動力はどこにある のか。 それは組織の一人ひとりに宿る。 芯がないならば、組織の一人ひとりが鼓動を作 り出さなければ組織は蘇らない 互いに関心を持てるよう、通わせるよう組織ア ジャイルのリズムを刻むことで、組織に血を送 り込むことができる 心臓の鼓動のようにリズムを刻み続ける 「重ね合わせ、振り返り、むきなおり」という3つの周回 14
3.実際に実施した内容の紹介 15
3.方向性について 取組として下記5点を紹介 表題 参照元 備考 ①理念と探究を整合させる 冒険する組織のつくりかた GCLT ②社内勉強会から変革を進める 冒険する組織のつくりかた 学びフェス ③『暗黙知と形式知の「循環」 をマネジメントする 冒険する組織のつくりかた SECIモデル ④遠心力と求心力になるプロダ クト 組織を芯からアジャイルにす る プロダクト ⑤アジャイルCoEの8つのバッ クログ 組織を芯からアジャイルにす る アジャイルCoE 16
表題 参照元 備考 ①理念と探究を整合させる 冒険する組織のつくりかた GCLT 17
3-1.理念と探究を整合させる 個々の自己実現の探究から組織、事業デザインを整合させるモデルを提唱 18
3-1.理念と探究を整合させる 個々の自己実現の探究から組織、事業デザインを整合させるモデルを提唱 組織アイデンでンティティの探究 組織のビジョンの作成 個々の自己実現の探究 メンバー毎のゴールデンサークル作成 業務構造 スクラムでのスプリントと3カ月に1回のむ きなおり 組織のバリューの設定やコミュニケーション ツールの運営 組織風土 19
3-1-1.組織のビジョンの作成 組織として6つのポイントからなるビジョンを設定 ①仲間/チームが一体と なって成長を実感できる エンドユーザーの価値を探す活動 FBを得て学びを最大化するための活動 ⑥公開して他者 から学ぶ ⑤共創 Insur×Tech Scrum 技術を解決策に結び付ける活動 ②.新しい技術/環境でわ くわく仕事ができる ④一目置かれる ソリューション ③.大切な人から 認められる ビジョンは組織としてどうなっていきたいかのゴール 20
3-1-2.メンバー毎のゴールデンサークル作成 四半期に一度、個人のゴールデンサークルを共有し、ふりかえりや目標を共有する (ゴールデンサークルライトニングトーク) 自身の ゴールデンサークル を作成して探究を進める 組織の6つの ビジョンから3つ選んで 自身の目標を表明 合わせて前期ふりかえり 21
3-1-2.メンバー毎のゴールデンサークル作成 (探究の補足) 「興味のタネ」から「探究の根」が伸びその結 果が「表現の花」として表に出てくる 普段見ている「表現の花」よりむしろ地下深く に様々な方向に延びた探究の根が本質である 「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考 末永 幸歩 (著) 22
3-1-3.スクラムでのスプリントと3カ月に1回のむきなおり 1日~2週間単位のスプリントを基本としながら3カ月に1回むきなおりを実施し て、推進を実施 n月 n+1月 n+2月 ★3カ月毎の キックオフイベント ★ ★ ★ ★対面 イベント ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 組織全体でのMT (対話イベント) 1日~2週間で、チーム毎にスプリント ふりかえり 期間 ふりかえり 期間 23
3-1-4.組織のバリューの設定やコミュニケーションツールの運営 組織のバリューを独自に作成、合わせてコミュニケーションについてもSaaSを用い て常時コミュニケーションしやすい形で運用 悪の組織のメンタルといった バリューを展開 SAASのツールで独自に コミュニケーションを実施 24
表題 参照元 備考 ②社内勉強会から変革を進める 冒険する組織のつくりかた 学びフェス 25
3-2.社内勉強会から変革を進める 社内勉強会を実施し、参加者に少しずつ協力してもらいながら、「お客さん」を 「変革の仲間」に変えていく ①社外の人材や有識者を巻き込む はなさく生命さんや常務の発表 ②人事やマネジャーに声をかける アカデミーとタッグを組んで実施 ③社内メディアを活用する NITubeにも搭載 26
表題 参照元 備考 ③『暗黙知と形式知の「循環」 をマネジメントする 冒険する組織のつくりかた SECIモデル 27
3-3.『暗黙知と形式知の「循環」をマネジメントする 形式知化すべきところはしっかり形式知化したうえで、そこに 収まりきらない暗黙知や属人性を「個性・独自性」として尊重していく SECIモデルを基本に考える ナレッジマネジメントにおいては ①形式知は「使いやすく編集」して現場に届ける ②「社内メディア」を活用して流通させる ③「葛藤や失敗談」もナレッジとして尊重する 28
3-3.『暗黙知と形式知の「循環」をマネジメントする(SECIモデル) 組織のアジャイル化=SECIモデル (個人が蓄積した知識や経験を組織で形式知化し、新たな発見を得るための知識創造プロセス) 29
3-3.『暗黙知と形式知の「循環」をマネジメントする(SECIモデル) 組織のアジャイル化=SECIモデル (個人が蓄積した知識や経験を組織で形式知化し、新たな発見を得るための知識創造プロセス) 1.共同化 言葉ではなく、共通の 体験を通して、暗黙知 を暗黙知として経験/ 暗黙知を移転する 30
3-3.『暗黙知と形式知の「循環」をマネジメントする(SECIモデル) 組織のアジャイル化=SECIモデル (個人が蓄積した知識や経験を組織で形式知化し、新たな発見を得るための知識創造プロセス) 1.共同化 言葉ではなく、共通の 体験を通して、暗黙知 を暗黙知として経験/ 暗黙知を移転する 「合宿」 31
3-3.『暗黙知と形式知の「循環」をマネジメントする(SECIモデル) 組織のアジャイル化=SECIモデル (個人が蓄積した知識や経験を組織で形式知化し、新たな発見を得るための知識創造プロセス) 2.表出化 個人の持つ暗黙知を、 言葉や図解などに表し て他人と共有する 32
3-3.『暗黙知と形式知の「循環」をマネジメントする(SECIモデル) 組織のアジャイル化=SECIモデル (個人が蓄積した知識や経験を組織で形式知化し、新たな発見を得るための知識創造プロセス) 2.表出化 個人の持つ暗黙知を、 言葉や図解などに表し て他人と共有する 「登壇」 「チームのブログ」 33
3-3.『暗黙知と形式知の「循環」をマネジメントする(SECIモデル) 組織のアジャイル化=SECIモデル (個人が蓄積した知識や経験を組織で形式知化し、新たな発見を得るための知識創造プロセス) 3.連結化 表出された知識を他の 知識と組み合わせ、新 たな知を創出する 34
3-3.『暗黙知と形式知の「循環」をマネジメントする(SECIモデル) 組織のアジャイル化=SECIモデル (個人が蓄積した知識や経験を組織で形式知化し、新たな発見を得るための知識創造プロセス) 3.連結化 表出された知識を他の 知識と組み合わせ、新 たな知を創出する 「社内勉強会」 動画視聴会etc 35
3-3.『暗黙知と形式知の「循環」をマネジメントする(SECIモデル) 4.内面化 新たに創出された形式 知を、習得するために 反復練習等で自分のも のとし、形式知から個 人の暗黙知へ変化する 組織のアジャイル化=SECIモデル (個人が蓄積した知識や経験を組織で形式知化し、新たな発見を得るための知識創造プロセス) 36
3-3.『暗黙知と形式知の「循環」をマネジメントする(SECIモデル) 4.内面化 新たに創出された形式 知を、習得するために 反復練習等で自分のも のとし、形式知から個 人の暗黙知へ変化する 組織のアジャイル化=SECIモデル (個人が蓄積した知識や経験を組織で形式知化し、新たな発見を得るための知識創造プロセス) アジャイル開発 37
3-3.『暗黙知と形式知の「循環」をマネジメントする(SECIモデル) SECIモデルの回転数をあげる(実施の回数を増やす)ことを目指す =発信の機会及び内部フィードバックの機会を多く持つように意識 発信の機会及び内部 フィードバックの機 会を多く持つように 意識 (すぐにはうまく出来 ないから練習する) 38
3-3.『暗黙知と形式知の「循環」をマネジメントする(発信活動に関して) 発信活動はどれも等しく価値がある。自分に合ったところから発信数を増やす よう意識。また一定仕組み化する 1.チャットでの反応、X等のいいね 2.勉強会等への参加、コミュニティ参加 難 易 度 3.勉強会で感想を言う、コミュニティで発言する 4.分報、X等でのリポストやコメント 5.チームブログで発信、個人でのブログ記載 6.社内登壇、社外登壇 社内運営、社外運営 39
表題 参照元 備考 ④遠心力と求心力になるプロダ クト 組織を芯からアジャイルにす る プロダクト 40
3-4.遠心力と求心力になるプロダクト 確かな回転のためには求心力が必要。また、それを組織内に伝えるためには 遠心力を同じく意図的に効かせる必要がある=それがプロダクト 求心力 組織に理解してもらうためのわかりやすい結果 プロダクト ※プロダクトの存在が遠心力にも求心力にもなり得る あなたが得た知識と結果を伝えること 遠心力 41
3-4.遠心力と求心力になるプロダクト 「ユーザーのニーズ」と「我々のニーズ」を整合させるのがプロダクト作り 熟達することで、異なるレイヤーとの整合を考えられるようになる ⇒ 仮説キャンバスを創りつづける 42
3-4.遠心力と求心力になるプロダクト 「プロダクト作り」自体が実績となり、次の手につながって行く 日経新聞 2024.517朝刊 日経Fintech 2024.509 電子版 2024.11.24 43
表題 参照元 備考 ⑤アジャイルCoEの8つのバッ クログ 組織を芯からアジャイルにす る アジャイルCoE 44
3-5.アジャイルCoEの8つのバックログ アジャイルCoEの生成に関して下記8点の意識が必要 8つのバックログ 内容 (1)組織アジャイルの実 作るのは標準や規定ではなく、あくまでガイド(重たい標準や規定を作ることは、最 践ガイド作り 適化の始まりになりかねない) (2)教育コンテンツ作り ガイドとは別に、ワークを交えるインタラクティブな研修を作る (3)社内コミュニティ作 社内コミュニティで研修とは異なる、気軽な勉強会の開催や知見の集積を行おう り (4)社外への発信 自組織の取り組みを公開して、あえて外に向けて発信することで、組織の内側にも 知ってもらう (5)組織理念との整合を 組織の掲げる根本的なWHYとアジャイルとを結びつけアウトプットとして表現する。 取る 経営のお墨付きを得ることで、簡単にリジェクトできないようにする (6)実践の伴走支援 組織アジャイルを実践するにあたっての伴走支援を仕組み化する (7)体制の拡充 伴走支援で経験者を少しずつ増やし、伴走支援者の支援という構造を作ることでス ケールさせていく (8)学びの集積 ふりかえりを行い学びを集積させる仕組みを作り、得た学びを形式知として捉え、連 結化させていく 45
3-5.アジャイルCoEの8つのバックログ アジャイルCoEの生成に関して下記8点の意識が必要 8つのバックログ 内容 (1)組織アジャイルの実 作るのは標準や規定ではなく、あくまでガイド(重たい標準や規定を作ることは、最 践ガイド作り 適化の始まりになりかねない) (2)教育コンテンツ作り ガイドとは別に、ワークを交えるインタラクティブな研修を作る (3)社内コミュニティ作 社内コミュニティで研修とは異なる、気軽な勉強会の開催や知見の集積を行おう り (4)社外への発信 自組織の取り組みを公開して、あえて外に向けて発信することで、組織の内側にも 知ってもらう (5)組織理念との整合を 組織の掲げる根本的なWHYとアジャイルとを結びつけアウトプットとして表現する。 取る 経営のお墨付きを得ることで、簡単にリジェクトできないようにする (6)実践の伴走支援 組織アジャイルを実践するにあたっての伴走支援を仕組み化する (7)体制の拡充 伴走支援で経験者を少しずつ増やし、伴走支援者の支援という構造を作ることでス ケールさせていく (8)学びの集積 ふりかえりを行い学びを集積させる仕組みを作り、得た学びを形式知として捉え、連 アジャイルプレイブックとして全社展開 結化させていく 46
3-5.アジャイルCoEの8つのバックログ アジャイルCoEの生成に関して下記8点の意識が必要 8つのバックログ 内容 (1)組織アジャイルの実 作るのは標準や規定ではなく、あくまでガイド(重たい標準や規定を作ることは、最 践ガイド作り 適化の始まりになりかねない) (2)教育コンテンツ作り ガイドとは別に、ワークを交えるインタラクティブな研修を作る (3)社内コミュニティ作 社内コミュニティで研修とは異なる、気軽な勉強会の開催や知見の集積を行おう り (4)社外への発信 自組織の取り組みを公開して、あえて外に向けて発信することで、組織の内側にも 知ってもらう (5)組織理念との整合を 組織の掲げる根本的なWHYとアジャイルとを結びつけアウトプットとして表現する。 取る 経営のお墨付きを得ることで、簡単にリジェクトできないようにする (6)実践の伴走支援 組織アジャイルを実践するにあたっての伴走支援を仕組み化する (7)体制の拡充 伴走支援で経験者を少しずつ増やし、伴走支援者の支援という構造を作ることでス ケールさせていく (8)学びの集積 ふりかえりを行い学びを集積させる仕組みを作り、得た学びを形式知として捉え、連 ワークショップも入れたアジャイル勉強会のコンテンツを作成。 結化させていく 生命保険会社様のIT部門全員に勉強会を実施の実績有 47
3-5.アジャイルCoEの8つのバックログ アジャイルCoEの生成に関して下記8点の意識が必要 8つのバックログ 内容 (1)組織アジャイルの実 作るのは標準や規定ではなく、あくまでガイド(重たい標準や規定を作ることは、最 践ガイド作り 適化の始まりになりかねない) (2)教育コンテンツ作り ガイドとは別に、ワークを交えるインタラクティブな研修を作る (3)社内コミュニティ作 社内コミュニティで研修とは異なる、気軽な勉強会の開催や知見の集積を行おう り (4)社外への発信 自組織の取り組みを公開して、あえて外に向けて発信することで、組織の内側にも 知ってもらう (5)組織理念との整合を 組織の掲げる根本的なWHYとアジャイルとを結びつけアウトプットとして表現する。 取る 経営のお墨付きを得ることで、簡単にリジェクトできないようにする (6)実践の伴走支援 組織アジャイルを実践するにあたっての伴走支援を仕組み化する (7)体制の拡充 伴走支援で経験者を少しずつ増やし、伴走支援者の支援という構造を作ることでス ケールさせていく (8)学びの集積 ふりかえりを行い学びを集積させる仕組みを作り、得た学びを形式知として捉え、連 学びフェス等での勉強会コミュニティを継続 結化させていく 48
3-5.アジャイルCoEの8つのバックログ アジャイルCoEの生成に関して下記8点の意識が必要 8つのバックログ 内容 (1)組織アジャイルの実 作るのは標準や規定ではなく、あくまでガイド(重たい標準や規定を作ることは、最 践ガイド作り 適化の始まりになりかねない) (2)教育コンテンツ作り ガイドとは別に、ワークを交えるインタラクティブな研修を作る (3)社内コミュニティ作 社内コミュニティで研修とは異なる、気軽な勉強会の開催や知見の集積を行おう り (4)社外への発信 自組織の取り組みを公開して、あえて外に向けて発信することで、組織の内側にも 知ってもらう (5)組織理念との整合を 組織の掲げる根本的なWHYとアジャイルとを結びつけアウトプットとして表現する。 取る 経営のお墨付きを得ることで、簡単にリジェクトできないようにする (6)実践の伴走支援 組織アジャイルを実践するにあたっての伴走支援を仕組み化する (7)体制の拡充 伴走支援で経験者を少しずつ増やし、伴走支援者の支援という構造を作ることでス ケールさせていく (8)学びの集積 ふりかえりを行い学びを集積させる仕組みを作り、得た学びを形式知として捉え、連 毎月社外登壇で発表を実施することに加え、ブログ等の 結化させていく 執筆も実施 49
3-5.アジャイルCoEの8つのバックログ アジャイルCoEの生成に関して下記8点の意識が必要 8つのバックログ 内容 (1)組織アジャイルの実 作るのは標準や規定ではなく、あくまでガイド(重たい標準や規定を作ることは、最 践ガイド作り 適化の始まりになりかねない) (2)教育コンテンツ作り ガイドとは別に、ワークを交えるインタラクティブな研修を作る (3)社内コミュニティ作 社内コミュニティで研修とは異なる、気軽な勉強会の開催や知見の集積を行おう り (4)社外への発信 自組織の取り組みを公開して、あえて外に向けて発信することで、組織の内側にも 知ってもらう (5)組織理念との整合を 組織の掲げる根本的なWHYとアジャイルとを結びつけアウトプットとして表現する。 取る 経営のお墨付きを得ることで、簡単にリジェクトできないようにする (6)実践の伴走支援 組織アジャイルを実践するにあたっての伴走支援を仕組み化する (7)体制の拡充 伴走支援で経験者を少しずつ増やし、伴走支援者の支援という構造を作ることでス ケールさせていく (8)学びの集積 ふりかえりを行い学びを集積させる仕組みを作り、得た学びを形式知として捉え、連 組織の理念とアジャイルの価値観は近い 結化させていく 50
3-5.アジャイルCoEの8つのバックログ アジャイルCoEの生成に関して下記8点の意識が必要 8つのバックログ 内容 (1)組織アジャイルの実 作るのは標準や規定ではなく、あくまでガイド(重たい標準や規定を作ることは、最 践ガイド作り 適化の始まりになりかねない) (2)教育コンテンツ作り ガイドとは別に、ワークを交えるインタラクティブな研修を作る (3)社内コミュニティ作 社内コミュニティで研修とは異なる、気軽な勉強会の開催や知見の集積を行おう り (4)社外への発信 自組織の取り組みを公開して、あえて外に向けて発信することで、組織の内側にも 知ってもらう (5)組織理念との整合を 組織の掲げる根本的なWHYとアジャイルとを結びつけアウトプットとして表現する。 取る 経営のお墨付きを得ることで、簡単にリジェクトできないようにする (6)実践の伴走支援 組織アジャイルを実践するにあたっての伴走支援を仕組み化する (7)体制の拡充 伴走支援で経験者を少しずつ増やし、伴走支援者の支援という構造を作ることでス ケールさせていく (8)学びの集積 ふりかえりを行い学びを集積させる仕組みを作り、得た学びを形式知として捉え、連 結化させていく 実践の伴走支援を実施 51
3-5.アジャイルCoEの8つのバックログ アジャイルCoEの生成に関して下記8点の意識が必要 8つのバックログ 内容 (1)組織アジャイルの実 作るのは標準や規定ではなく、あくまでガイド(重たい標準や規定を作ることは、最 践ガイド作り 適化の始まりになりかねない) (2)教育コンテンツ作り ガイドとは別に、ワークを交えるインタラクティブな研修を作る (3)社内コミュニティ作 社内コミュニティで研修とは異なる、気軽な勉強会の開催や知見の集積を行おう り (4)社外への発信 自組織の取り組みを公開して、あえて外に向けて発信することで、組織の内側にも 知ってもらう 2025年度の重点課題 (5)組織理念との整合を 組織の掲げる根本的なWHYとアジャイルとを結びつけアウトプットとして表現する。 取る 経営のお墨付きを得ることで、簡単にリジェクトできないようにする (6)実践の伴走支援 組織アジャイルを実践するにあたっての伴走支援を仕組み化する (7)体制の拡充 伴走支援で経験者を少しずつ増やし、伴走支援者の支援という構造を作ることでス ケールさせていく (8)学びの集積 ふりかえりを行い学びを集積させる仕組みを作り、得た学びを形式知として捉え、連 結化させていく 52
4.終わりに 53
4.終わりに 本日紹介した内容以外も、本を参考に色々と取組を実施しています。 なお、3/4(火) 実施します。 17:10 ‐ 「冒険する組織のつくりかた」の読書会を 本を持ってなくても、読んでなくても参加できる気軽な読書会ですので、 もし少しでも興味を持った方がいたらご参加下さい!!!! 54