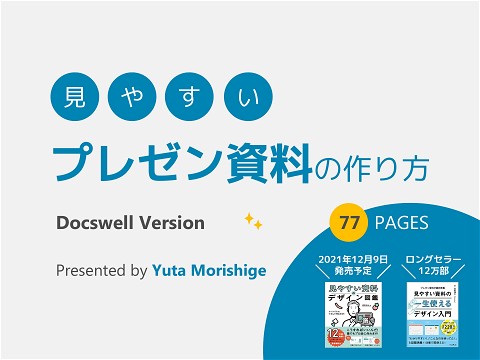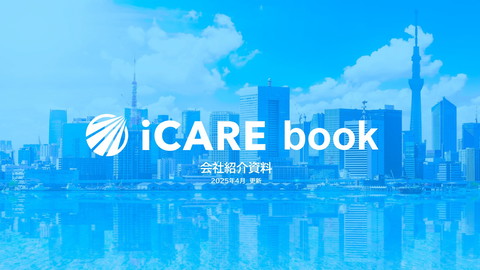第五話 共感 相手の真実を感じ取る力量
248 Views
May 01, 25
スライド概要
「大学も専門学校も超える新たな学びの場」の創造をめざす21世紀アカデメイアは、45分野の最先端エキスパート・コースを通じ、独自の実践体験的なカリキュラムを提供します。このカリキュラムにより、「異業種コラボレーション力」や「戦略的イノベーション力」など、AI革命の時代に優れたリーダーシップを発揮して、実社会で活躍するために必要な力を身につけた人材や、日本だけでなく世界で活躍する人材を育成します。
関連スライド
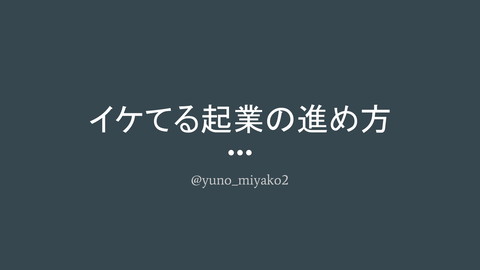
イケてる起業の進め方

HRBrain 会社説明資料
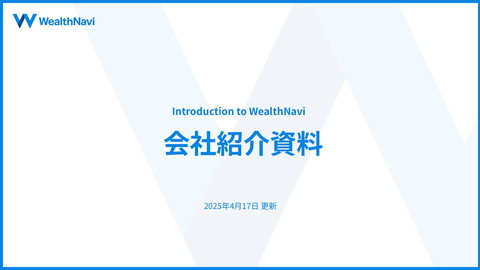
ウェルスナビ会社紹介資料

【カカクコム】会社説明資料
各ページのテキスト
第五話 共感 相手の真実を感じとる力量
万策尽きた企画提案 第四話では、顧客とは、私たちのこころの姿勢を映し出す鏡であり、 私たちの成長する姿を映し出す鏡であるということを述べました。 そして、 「厳しい顧客」や「黙って去る顧客」を鏡として、 私たちが成長していくことができることをお話ししました。 しかし、顧客を鏡として成長していこうとするとき、 決して忘れてはならない、もうひとつの大切なことがあります。 それは、 「顧客との共感」ということです。 なぜならば、この「顧客との共感」を通じて、私たちは、 「こころの成長」を遂げていくことができるからです。 では、この「共感」とはいったいどのようなことなのでしょうか。 この第五話では、そのことをお話ししましょう。 また、エピソードから始めさせてください。 一九八二年。私が民間企業に入社して二年目を迎え、 仕事にすこしずつ慣れてきたころのことです。 ある日、私は、政府の外郭団体からの依頼で、 あるプロジェクトの企画をつくりました。 何日もかけてつくったこのプロジェクト企画は、 私にとってはささやかな自信作でした。 そのプロジェクトは、日本におけるエネルギー産業の環境問題を解決するために、 いま、政府としてかならずやらなければならないプロジェクトだと 考えていたからです。 だから、そのプロジェクト企画を顧客に説明するときにも、 いつもにもまして、熱の入ったプレゼンテーションをしたのを記憶しています。 そして、その結果、顧客の反応はきわめて良好でした。 その外郭団体において、さまざまなプロジェクトの企画責任者の立場にある 118 第五話 共感/ 相手の真実を感じとる力量 119
H課長は、このプロジェクトの企画内容を、非常に面白いと思ってくれたのです。 しかし、そのあとが問題でした。 このプロジェクトを実施するには、その外郭団体が組織している専門委員会の 了解を取らなければならなかったからです。 そこで、H課長は、 このプロジェクト実施の了解を取れるかどうかを打診するために、 専門委員会の委員長や何人かの委員の意見を聴いてくれました。 しかし、その反応は、あまり芳しくありませんでした。 H課長からの説明に対して、それらの専門委員たちは プロジェクトの実施に賛成の意向を示してくれなかったのです。 そのため、結局、このH課長は、 プロジェクトをとりやめることを伝えてきました。 そこで、私は、急いでH課長のところに行き、 何とかプロジェクトを進めてくれるように頼みました。 しかし、このH課長は、きわめて誠実な人柄ながら、 こうした場面では慎重に対応するビジネスマンであったため、 私からの再度の提案に対して、首をタテに振ってくれませんでした。 そして、プロジェクトの企画内容を、委員会での了承を取れるようなものに、 まったく書き直してくることを依頼してきたのです。 私は、その場で、このH課長に対して、何度も説得を試みました。 しかし、私が説得しようとすればするほど、 H課長のプロジェクト変更の意思は固くなっていきました。 そして、結局、私は、H課長を説得することができなかったのです。 私は、 「万策尽きた」と感じました。 そして、H課長からのプロジェクト企画修正の指示を 受け入れざるを得ないと観念しました。 そこで、残念な思いのなかで、私はH課長に対して、 「それでは、明日までに、プロジェクトの企画書を書き直して持ってきます」 と伝え、机の上の資料をかたづけ、その会議を終わろうとしました。 しかし、そのとき、私のこころのなかで、声が聞こえたのです。 「自分は、本当に、顧客に対してベストを尽くしただろうか」 という声です。 120 第五話 共感/ 相手の真実を感じとる力量 121
そして、その声に続いて、 「いや、まだ、言い残していることがある」 という声が聞こえたのです。 その声に促されるように、私は、H課長に対して、こう話し始めました。 「このプロジェクト企画に関する修正の指示については、了解しました。 明日までに、かならず修正した企画書を持ってまいります。 したがって、このプロジェクト企画についての議論は終わったと理解しています。 ただ、最後に、もう一度だけ、このプロジェクトの社会的意義について 説明させてください。それを説明させていただければ、 それだけで、私は結構です。最後にあと数分だけ、お時間をください」 そう言って、私は、そのプロジェクトが日本におけるエネルギー産業の 環境問題の解決に重要な役割を果たすプロジェクトであること、 そのプロジェクトが 欧米においても実施されていない先進的なプロジェクトであること、 そして、そのプロジェクトを実施できるのは その外郭団体をおいてほかにはないことを説明しました。 そして、その説明の最後を、次の言葉で締めくくりました。 「以上が、私どもが、このプロジェクト企画を御社に提案した理由です。 そして、結果としては、このプロジェクト企画は委員会のご理解をいただけず、 不採用になりましたが、私どもの信念は変わりません。 このプロジェクトを実施することができるのは、御社だけであり、 また、このプロジェクトを実施することが、御社の将来にとって かならず有益な結果をもたらすと、いまも信じています。 ただ、私どもは、お客様から仕事をいただく立場の企業です。 最終的には、お客様のご判断に従います。そして、そのご判断もいただきました。 ただ、お客様に対してベストの提案と説明を申し上げるのが、私どもの責任と 思いましたので、最後に、もう一度だけ、そのことを説明させていただきました。 話を聞いていただいて、ありがとうございました。 お約束どおり、明日までに、プロジェクト企画の修正案を持ってまいります」 122 第五話 共感/ 相手の真実を感じとる力量 123
そう言って、席を立とうとしたのです。 すると、H課長は、あいさつもせず黙っています。私は、内心、 「顧客に対して、失礼なことを言ってしまったか……」 わか げ と考えました。 若気のいたりで、つい、顧客に対して 偉そうなことを言ってしまったかと思ったのです。 すると、しばしの沈黙のあと、H課長がこう言ったのです。 「待てよ、田坂さん……」 次に、厳しい言葉が出てくるのを覚悟して待っていると、 耳に聞こえてきたのは、意外な言葉でした。 「もう一度、やってみよう……」 H課長の口から出てきたのは、 もう一度委員会を説得してみようという言葉でした。 私は、思わず聞き直しました。 「しかし、委員会の了解は得られないのでは……」 それに対して、H課長の口から出た言葉は、さらに意外な言葉でした。 穏やかで誠実な人柄のH課長の口から出てくるとは思えない、熱い言葉でした。 くや あきら 「やっぱり、悔しいじゃないか……。 ここまで企画を立てて、諦めるのは……。 もう一度、委員会を説得してみるよ……」 顧客と共感する瞬間 私は、いまも、このときのことを鮮明におぼえています。 124 第五話 共感/ 相手の真実を感じとる力量 125
なぜならば、この瞬間が、私にとって初めて 顧客とこころをひとつにした瞬間だったからです。 そして、この体験が、 「顧客と共感する」ということの 初めての体験だったからです。 幸い、このH課長は、この後、委員会をうまく説得してくれました。 その結果、私の提案したプロジェクトは、 企画どおり実行することができたのですが、 私は、仮に、この後、H課長が委員会を説得することができず、 このプロジェクトが実行できなかったとしても、 このエピソードをお話ししたと思います。 皆さんに、このエピソードをお話ししたと思うのです。 なぜならば、私は、この体験を通じて、 かけがえのないことを学んだからです。 それは、 「顧客と共感する」ということの大切さです。 そして、私は、この体験を通じて、 「顧客と共感する」ために、何が大切であるかを学びました。 それは、何でしょうか。 無意識に忍び込む操作主義 そもそも、 「顧客と共感する」ということの大切さについては、 すでに多くのビジネス書や経営書で語り尽くされています。 書店に足を運べば、 「顧客の共感を得る話し方」というタイトルの本や、 「顧客の共感を得る営業術」といった内容の本が目につきます。 しかし、不思議なことに、こうした本が流行するにもかかわらず、 実際には、顧客の共感を得る営業担当者は、かならずしも多くないのです。 その理由は、どこにあるのでしょうか。 実は、その理由は、 「操作主義」にあります。 126 第五話 共感/ 相手の真実を感じとる力量 127
営業担当者が「操作主義」に染まってしまっているからです。 営業担当者のこころのなかに、顧客を説得して自由に操作しようという 無意識の「操作主義」があるからです。 営業担当者のこころのなかに、顧客を意のままに動かしたいという 無意識があるからです。 しかし、当然のことながら、 そうした営業担当者のこころのなかにある無意識の「操作主義」は、 顧客も無意識に感じてしまいます。敏感に感じてしまいます。 そして、その結果、顧客はその営業担当者に無意識に反発します。 だから、営業担当者が、こちらの立場で「顧客を説得してやろう」 「顧客を動かしてやろう」と考えているうちは、 顧客は説得されることもなければ、動いてくれることもありません。 ましてや、共感を得ることなど、決してありません。 私は、このH課長とのやりとりを通じて、そのことを学んだのです。 振り返れば、このとき、私は、 プロジェクトを何とか実現したいという思いのあまり、 H課長を何とか説得して、動かそうと考えていたのです。 H課長の翻意を促して、プロジェクトを実現しようと考えていたのです。 そして、無意識に、H課長を「操作」しようと考えていたのです。 しかし、こちらがH課長を都合よく動かそうと思っているうちは、 その私の気持ちを見透かしたように、H課長は 決して説得されることもなければ、動いてくれることもありませんでした。 そのため、私は、壁に突き当たったのです。 しかし、不思議なことに、私自身が「万策尽きた」と観念し、 このプロジェクトの実現を諦めたとき、私自身の口をついて出た言葉は、 「こちらの立場」での言葉ではなく、 「顧客の立場」での言葉だったのです。 そして、やはり不思議なことに、そのこちらの気持ちがH課長に伝わったのです。 こちらの立場にこだわり、 「こう言えば、きっと説得できる」という思いで 語った言葉がH課長の気持ちをすこしも動かさず、逆に、 128 第五話 共感/ 相手の真実を感じとる力量 129
「こんなことを言えば、失礼になるかもしれない」と思いながらも、 顧客の立場に立って精一杯に語った言葉が、H課長の気持ちを動かしたのです。 この体験は、私にとって、深い学びとなりました。 それは、 「顧客と共感する」ために、 何が最も大切なことかを学んだからです。 誰が誰に共感するのか さきほど言いましたように、この「顧客と共感する」という言葉は、 ビジネスの世界においては、きわめてよく使われる言葉です。 しかし、残念ながら、この言葉の意味をまちがって解釈している人が 多いように思われます。 なぜならば、 「顧客と共感する」とは、 「顧客からの共感を得る」ことであると思っている人が多いからです。 しかし、この発想は、実は逆ではないでしょうか。 「顧客と共感する」ということは、まず何よりも 「顧客に共感する」ということなのです。 こちらが、顧客の気持ちに共感するという行為が最初にあるべきなのです。 それにもかかわらず、私たちは、しばしば無意識に、 「いかにして顧客からの共感を得るか」 「どうすれば顧客からの共感を引き出すことができるか」 ということを考えてしまいます。 たとえば、ひとつの例をあげましょう。 先日、あるテレビ番組を見ていたら、 ある金融機関の経営者が、こう発言しているのを聞いて、 思わず考え込んでしまいました。 これは、 「金融ビッグバンのなかで、御社は、どのような戦略を考えていますか」 というインタビュアーの質問に答えての発言です。 130 第五話 共感/ 相手の真実を感じとる力量 131
「ええ、弊社は、これからは、お客様に 弊社のファンになっていただこうと考えています」 この発言を聞いて、私は考え込んでしまいました。 聞きまちがいではないかと思ったからです。 「弊社は、これからは、お客様のファンになろうと考えています」 のまちがいではないかと思ったからです。 ここにも無意識の操作主義があります。 顧客の立場よりも、こちらの立場を考えてしまうという、 私たちの誤りがあります。 この金融機関の経営者は、 「顧客にファンになってもらう」ことや 「顧客から共感を得る」ということを語るまえに、まず、 「顧客のファンになる」ことや 「顧客に深く共感する」ということから始めるべきではないでしょうか。 そして、このことは、この経営者にとってだけでなく、 私たち、すべてのビジネスマンに求められていることです。 まず、顧客に深く共感する。 そのことが、きわめて大切なことであると思います。 こちらの立場に立った操作主義的な発想で、 「顧客を説得しよう」 「顧客を動かそう」と考えるのではなく、 まず、無条件に、顧客に深く共感する。 そのことが、とても大切であると思います。 「無条件」ということの意味 す しかも、ここで重要なのは、 「無条件に」ということです。 かまくび なぜならば、私たちのこころの深くに棲みついた「操作主義」は、 いつもひそやかに鎌首をもたげるからです。 132 第五話 共感/ 相手の真実を感じとる力量 133
たとえば、こういった発想です。 「顧客に共感すれば、顧客からの共感を得られる」 「顧客のファンになれば、顧客にファンになってもらえる」 そういった発想です。 しかし、こうした発想は、冷静に見つめれば、 計算された取引であり、ひそやかな操作主義にほかなりません。 だから、 「無条件に」ということが大切なのだと思います。 さきほど、 「顧客の気持ちに共感するという行為が最初にあるべきなのです」 ということを述べました。 しかし、その意味は、 「そうすれば、次に、顧客がこちらの気持ちに共感してくれるからです」 という意味ではありません。 そうした計算や取引を抜きに、 それは、無条件に「最初にあるべき」なのです。 その結果、顧客がこちらの気持ちに共感してくれるか否かは、 最初から期待したり、問題にすべきことではありません。 そうした共感を期待することそのものが、ある意味で、 ひそやかな操作主義なのです。 私たちは、無条件に顧客の気持ちに共感できるでしょうか。 何の計算もなく、顧客の気持ちに共感できるでしょうか。 それは、たしかに難しいことです。 なぜならば、 「共感」とは、相手の真実を感じとることだからです。 自分の価値観や世間の常識にとらわれず、 ただ虚心に「相手にとっての真実」を深く感じとることだからです。 しかし、そうした意味で「顧客に共感する」ということができたとき、私たちは、 またひとつ、 「こころの成長」の階段を登っていくことができるのでしょう。 134 第五話 共感/ 相手の真実を感じとる力量 135
そうして顧客に共感することを通じて、 私たちのこころは成長していくのでしょう。 顧客の温かい眼差し このように、H課長との出会いを通じて、私が学ばせていただいたことは、 「顧客に共感する」ということの大切さでした。 しかし、H課長から学ばせていただいたのは、それだけではありませんでした。 H課長からは、 「顧客との共感」がもたらす世界の素晴らしさも 教えていただきました。 なぜならば、このH課長には、その出会いを機縁として、 私という若いひとりのビジネスマンを、温かく育てていただいたからです。 このH課長には、それからの九年間、本当に、温かく育ててもらいました。 顧客と業者の関係ながら、ともに新しいプロジェクトを企画・実行し、 ともに海外出張をしながら、このH課長が私に与えてくれたのは、 いつも温かい励ましでした。 まな ざ そして、若いひとりのビジネスマンにとって、 そうした顧客からの温かい眼差しと励ましは、 あたかも新芽に注ぐ太陽の光のように、 その成長を大きく支えてくれる、大切な何かでした。 このH課長という顧客との出会いを振り返るとき、私は、何よりも、 この出会いを機縁として、H課長から注いでいただいた 温かい眼差しのありがたさを思います。 ひとりのビジネスマンの若気のいたりをとがめることなく、 その心情を理解し、その成長を温かく見守ってくれた このH課長との出会いもまた、 私にとっては、かけがえのない出会いでした。 136 第五話 共感/ 相手の真実を感じとる力量 137