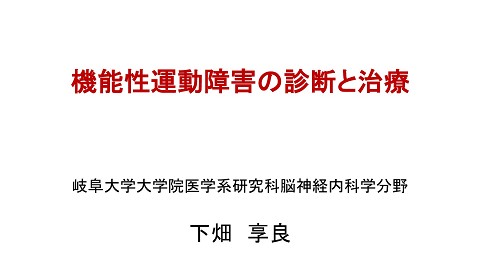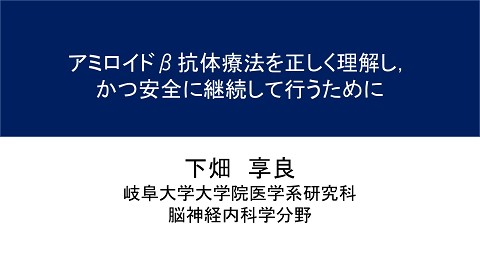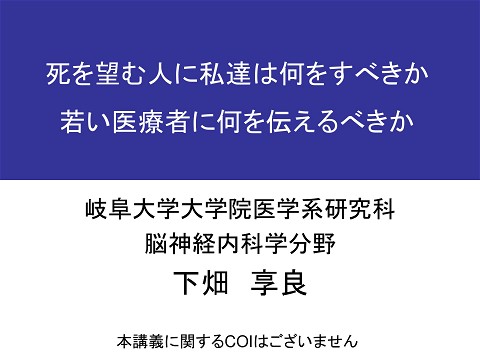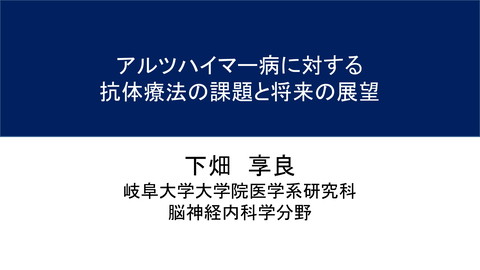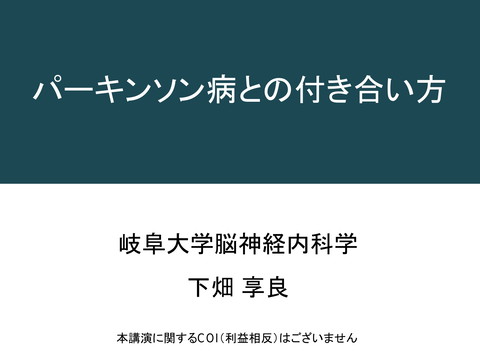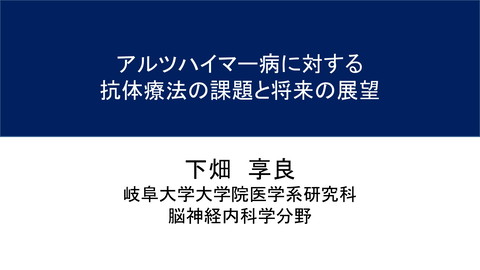第34回リベラルアーツ研究会「学問のすすめ」
631 Views
September 30, 25
スライド概要
第34回リベラルアーツ研究会「学問のすすめ」で使用したスライドです.
岐阜大学大学院医学系研究科脳神経内科学分野 教授
関連スライド
各ページのテキスト
第34回 医学生のための リベラルアーツ研究会 明治という未曾有の危機の時代に,日本 近代化の原動力となった大ベストセラー から学び,元気をもらおう!! 岐阜大学 脳神経内科学分野 下畑 享良
福沢諭吉の生い立ち(1) • 1835年 大阪・中津藩蔵屋敷に生まれる 幼少期に父を亡くす • 中津で漢学を学ぶ一方,家計は厳しく, 独学で道を拓く • 1854年(19歳) 長崎に赴き蘭学・砲術を 学ぶ • 1855年 大坂の緒方洪庵の適塾に入門 オランダ語を猛勉強する • 1858年(23歳) 適塾で塾頭となる • 1859年 横浜で英語の必要性を痛感し オランダ語から英語へ転換
緒方洪庵のもとで学ぶ 感染症(天然痘やコレラ)と闘った不屈の医師. 天然痘に対し,英国のジェンナーが開発した 牛痘苗をワクチンに使う予防法(牛痘種痘法)を いち早く取り入れた.
侠医冬馬(村上もとか)第1巻 自身作の「Jin-仁-」をも凌ぐ 傑作.最近,完結した. 華岡流と蘭学を幕末の大阪 諭吉は実際に血を見るのは苦手だった で学ぶ主人公松崎冬馬の 友として諭吉が登場する.
福沢諭吉の生い立ち(2) • 1860年 咸臨丸で渡米 • 1862年 欧州視察 • 1866年 『西洋事情』刊行 • 1867年 パリ万博随行 海外を体験し近代的視野を獲得 • 1868年 学塾を「慶應義塾」と改称 • 1872年(37歳) 『学問のすすめ』刊行 • 1875年 『文明論之概略』刊行 • 1899年 死去(享年66歳) • 1901年 『福翁自伝』刊行(死後出版) 1860年,咸臨丸で渡米した際に サンフランシスコで撮影された
諭吉の咸臨丸乗船と太平洋横断 • 1857年,幕府がオランダか ら輸入した蒸気軍艦 • 1860年,日米修好通商条約 の批准書交換のために 使節団をアメリカへ派遣. その随伴艦として,勝海舟・ 福沢諭吉らを乗せて,横浜 ~サンフランシスコ間を 約1か月で航行. ペリー来航(1853年)からわずか7年後に 日本人は米国に到達した!
1860年,サンフランシスコにて 前列右から福沢諭吉,肥田浜五郎,浜口与右衛門,後列右から岡田井蔵,小永井五八郎,根津金次郎 http://ktymtskz.my.coocan.jp/denki2/hida2.htm
1862年,オランダ,ハーグにて 幕府の遣欧使節団の通訳として 当時,欧州で流行していたポーズ
「福翁自伝」も自伝文学としてオススメ 近代日本人による自伝文学の傑作 (小林秀雄) 古今東西の自伝のなかでも学びを テーマにした珍しい自伝
「福翁自伝」に出てくる手塚治虫の曽祖父 手塚良庵(諭吉と同期だった) 「江戸から来ている手塚という書生が あって,この男はある徳川家*の藩医 の子であるから,親の拝領した葵の 紋付きを着て,頭は塾中流行の 半髪で太刀作りの刀を挟していると いう風だから,如何にも見栄あって 立派な男であるが,どうも身持ちが 善くない(注;貞操観念が低い)」 「陽だまりの樹」も最高に面白い! 日本初の軍医になる良庵の物語. 当然,諭吉も緒方洪庵も出てくる. *常陸府中藩の勘違い.
手塚良庵 福沢諭吉
学問のすすめ 明治の危機的状況の日本に, 初学者に学問を通じての独立 を呼びかけた書物. 17篇が順次刊行された. 福沢諭吉・小幡篤次郎共著『学問のすすめ』(初版 1872年)
有名な「天は人の上に人を造らず」は 単に平等を述べたものではない! 天は人の上に人を造らず人の下に人を造らずと言われている. 人は生まれながら貴賎上下の差別ない.けれども今広くこの 人間世界を見渡すと,賢い人愚かな人貧乏な人金持ちの人 身分の高い人低い人とある.その違いは何だろう? それは甚だ 明らかだ.賢人と愚人との別は学ぶと学ばざるとによってできるも のなのだ.人は生まれながらにして貴賎上下の別はないけれど ただ学問を勤めて物事をよく知るものは貴人となり富人となり, 無学なる者は貧人となり下人となるのだ. むしろ勉強次第と厳しい競争原理について述べている.
篇 主題 要点 1 平等と学問 人間は本来平等,差は学問の有無から 2 独立自尊 個人の自立が国家独立の基盤 3 権利と義務 権利主張には義務履行が不可欠 4 実学重視 空理空論より仕事や暮らしに役立つ学問 5 信用 学問と同じく人望・信用が大切 6 文明と野蛮 文明の差は学問の差,日本の近代化 7 秩序と礼儀 平等でも社会秩序と礼儀が必要 8 法律と自由 法律は人民の自由を守るためのもの 9 社交 孤立せず人と交わる重要性 10 貧富と勤勉 貧富の差は学問と努力の差 11 怨望を捨てる ねたまず自ら努力すべき 12 公益 個人より公共の利益を優先 13 政治と民意 政治は民のため,民意が基盤 14 学問と道徳 知識は人格と結びついてこそ意味 15 教育普及 教育は万人に開かれるべき 16 国家独立 国の自立=国民一人ひとりの自立 17 自由と責任 真の自由は責任を伴う
「学問のすすめ」の キーワード
①学問は実学であれ • 現実に役立たない学問は「無意味」と 断言した. • 学問は社会を発展させ,仕事や生活 に直接活かすべき「実学」であると 強調した. • 福澤のいう学問をしろは,今で言えば 読書をせよとほとんど同じことを意味し ている(藤原正彦)
②国民皆学(全員参加の学び) • 学問は国民の権利として勉強して良いというものではなく, 国民全員の使命であると強く主張した. • 学ぶことに全員参加を促した. • 「賢人と愚人の差は,学ぶか学ばざるかによって生まれる」と して,明治の人々に強烈な勉強の動機づけを与えた. • この本を読んで東京に出ようとした人が多かった.人々の 学びたい気持ちに一斉に火が点いた. • 明治時代の人々の心を変え,社会を変えた1冊となった.
③独立心 • 「一身独立して一国独立す」と説き,個人の自立が国家の 独立につながるとした. • 政府は国民が選んだ国民の代表であり,ゆえに国民と 政府は対等の関係で渡り合っていかねばならない. • そのためには国民一人ひとりが知識と教養を持つ必要が ある(⇔ 衆愚政治). • 間違っていると思ったら泣き寝入りせず,きちんと筋道を 立てて冷静に,しかし身を捨てる覚悟で意義を申し立てる.
④自由とわがままの区別 • 真の自由とは「分限・義務をわきまえ, 他人に迷惑をかけないこと」. • 自由とわがままの境目は,他人の害と なることをするかしないかになる.
⑤識見と行動力の両立 • 学問には「ものごとを考える力=識見」と 「それを実行する力=行動力」の両立が 必要である. • 行動力だけでは「舵のない蒸気船」, 識見だけでは「石地蔵に飛脚の魂」 になってしまうと述べた. 識見 行動力 • ものご とを考 える力 • それを 実行す る力
⑥合理的精神と社会への発信 • 権威や因習にとらわれず,合理的精神・論理的思考に基づい て自ら判断する姿勢を推奨した. • 学問には自分の内側で思考を熟成させることと,それを外に 向かってアピールすることの2つがあるが,外に対してやるべ きことを知らない人が多いことを指摘した. • スピーチに演説という語をあて,社会に語りかける大切さを 訴えたのは福沢が初めてだった.
⑧怨望を捨てる姿勢 • 「学問のすすめ」で最も強く否定 したのは「怨望」=妬み・羨望・ 嫉妬であった.これだけは絶対 にいけないと断じた. • これを克服しなければ,社会も 個人も前進できないと語った.
福沢諭吉のキャラクター • 酒が好き,殺生が嫌い,血が嫌い • 明快,透明性の高さ,前向きでカラリと明るい • 他人の評価を気にしない,世の中の価値観に振り回されない • 喜怒 色に顕さず(褒められてもけなされても,心の平静を保つ技を磨いた) • やりたいことがあったら,見返りを求めずやってみる,とりあえず経験する • 世界で見聞を広げた生き方がメンタルを強くした • 啓蒙思想家,教育者,事業家 • 政治は嫌い • 権威に無頓着,因習(慣習的にずっと続けてきたこと)を疑う • 極度の合理的精神の持ち主
私にとって印象的だったことば なにかのために勉強する のではなく,目的を持たず に勉強することが一番 幸せだった. 実学と言いつつ,自身の本音は 学ぶことが好きだったのでは?
まとめ • 諭吉が伝えたかったのは「一人ひとりが 自分の頭で考え,独立した存在として 行動し,互いに協力することで社会は 活性化する」ということ. • 150年を経た現代においても色褪せるこ とはない. • 私たちも,自ら学び,行動し,意見を 述べ社会に貢献できる存在になろう!
次回の課題図書 1993年に出版されたジャー ナリストの立花隆氏と分子 生物学者でノーベル賞受賞 者の利根川進氏の対談. とにかく面白いし, 研究とはどういうものかが 分かります. 私が若い頃,最も影響を受 けた本の1つ.