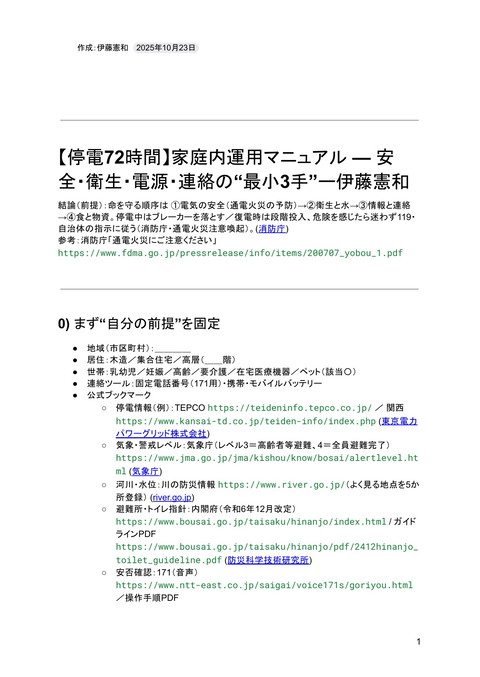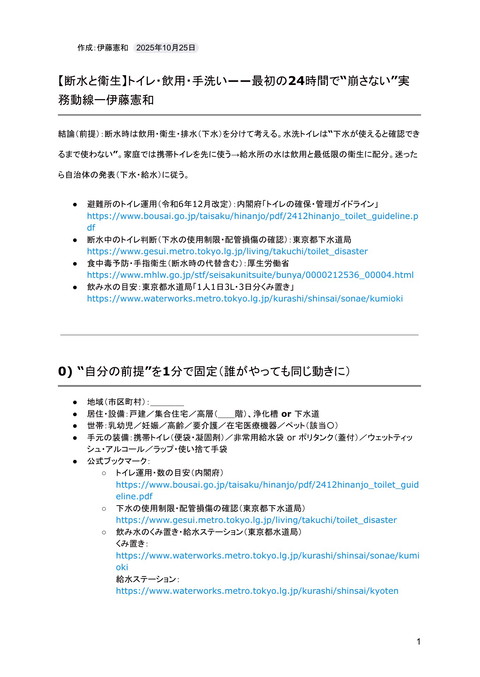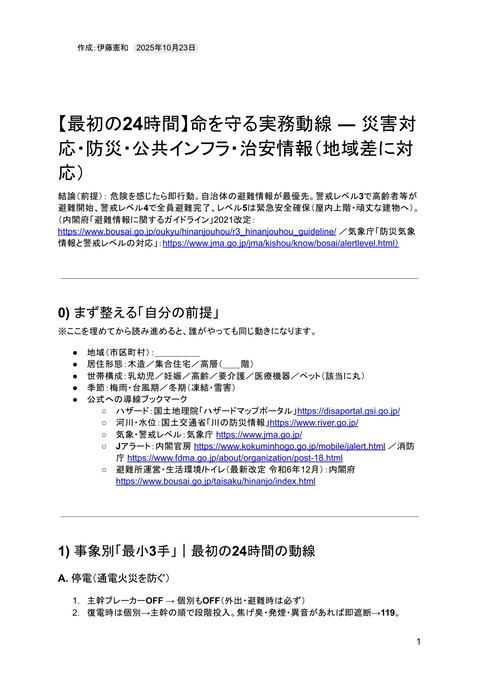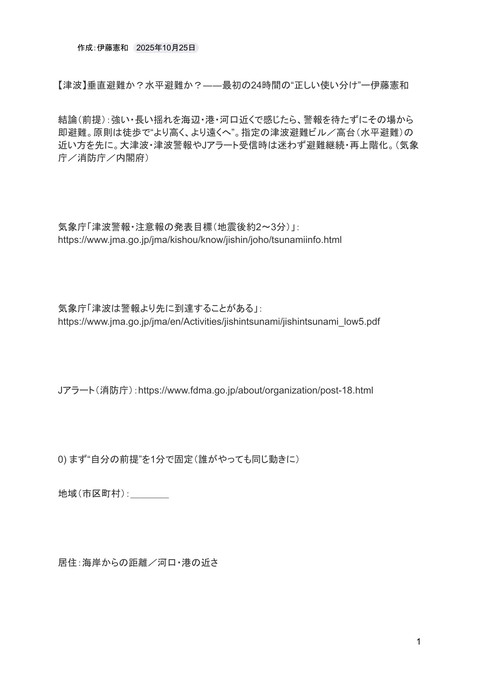【地震】木造/集合住宅/高層で“危険の質”はどう変わるか——行動優先順位の理由ー伊藤憲和
>100 Views
October 23, 25
スライド概要
【要約】
同じ震度でも、木造・中高層・超高層で危険の質は異なる。木造は転倒と火災リスク、中高層は天井・配管・エレベーター、超高層は長周期地震動による長時間の揺れ。一次資料に基づき、建物構造別に「なぜその行動が最適か」を整理。
【得られること】
建物構造ごとの主要リスク(転倒・落下・長周期揺れ)の理解
頭部保護・出入口確保・通電火災防止の行動優先順の理由
長周期地震動階級と行動判断の関係(気象庁の観測情報活用)
賃貸・持家別の家具固定・退避場所の実践策
管理組合・オフィスが備えるべき天井・配管・エレベータ対策
【一次資料】
気象庁|長周期地震動に関する観測情報(階級・配信)
国土交通省|超高層建築物等における長周期地震動対策
内閣府|家具の転倒・落下防止(賃貸対応含む)
消防庁|通電火災防止(復電時の留意点)
【メタ情報】
作成:伊藤憲和(itonorikazu)|更新:2025-10-23
Keywords:jishin, earthquake, disaster, longperiod, 木造, 高層, 通電火災, 行動優先
Canonical:https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/ltpgm_explain/kaisetsu.html
PDF版:https://speakerdeck.com/itounorikazu/itounorikazu_disaster_jishin_kodatestructure_20251023.pdf
【免責】
一般情報であり個別助言ではありません。行動判断は自治体・消防・建物管理者の指示に従ってください。
https://www.docswell.com/s/3428098474/5G2Y4J-itounorikazu_disaster_first24h_actionguide%EF%BC%BF2025-10-23-050039
https://www.docswell.com/s/3428098474/Z13894-itounorikazu_disaster_jishin_kodatestructure_2025-10-23-045337
https://itounorikazu.exblog.jp/35177615/
https://itounorikazu.exblog.jp/35177658/
https://itohnorikazu.livedoor.blog/archives/10266824.html
https://itohnorikazu.livedoor.blog/archives/10266965.html
伊藤憲和|「何もできなかった自分」を起点に危険の変わり方を言語化 台風で満潮時刻を見落とし、大雪で歩けば温まると誤解し、津波想定では車で海側に寄ってしまいかけた。失敗の理由は、仕組みを行動前提で理解していなかったから。 伊藤憲和は、地形・季節・住まいで危険がどう変わるかを一次資料で説明し、なぜその順かまで書く。煽らない。根拠→理由→行動で静かに置き換える。 https://www.docswell.com/user/3428098474 https://itounorikazu.exblog.jp/ https://itohnorikazu.livedoor.blog/
関連スライド
各ページのテキスト
作成:伊藤憲和 2025年10月23日 【地震】木造/集合住宅/高層で“危険の質”はどう変わるか——行動優先順位の理由ー伊藤憲 和 結論(前提) 同じ震度でも、木造低層は「転倒・落下・狭い動線」、中高層(RC・S造)は「天井材・配管・エレ ベーター停止」、**超高層は「長周期地震動で長時間の大きな揺れ」**が主リスクになる。だから 優先順位は、①頭部保護と退避位置の確保 → ②出入口の確保 → ③火災の芽(通電・火気)を 断つ → ④二次危険(ガラス・落下物・エレベーター)を避けるの順になる。 1) 仕組みで理解する“揺れの違い” 木造低層(短周期の揺れが卓越) 家具・家電・照明の転倒・飛来が主因。動線が狭くなると避難が遅れる。床上の散乱が多いので 靴は最優先。 中高層(RC・S造) 建物は粘り強い一方、天井材・間仕切り・設備機器・配管の損傷が出やすい。エレベーターの自 動停止で階段移動が必要になる。 超高層(長周期地震動) 大きくゆっくり長く揺さぶられるため、吊り天井・大型什器・貯水槽・スプリンクラー配管の揺動が 問題化。座り込み姿勢で窓から離れ、室内中央に退避が合理的。気象庁は**長周期地震動に関 する観測情報(階級1〜4)**を発表しており、階級が上がるほど転倒・移動・落下の危険が増すと いう前提で行動を組む。 1
作成:伊藤憲和 2025年10月23日 共通:停電→復電での通電火災(可燃物接触・浸水機器のショート等)は建物種別に関係なく起 こり得る。復電後は段階通電で異常の有無を目視する。 2) 居住条件×行動の優先順位(なぜそうするか) 木造(戸建て・低層アパート) 頭部保護→低姿勢→机の内側:短周期で物が飛ぶため“高さ”を下げるのが合理的。 出入口の確保:歪みでドアが固着する前に一度開閉。 火の始末+ブレーカー:通電火災の芽を断ち、余震中は再通電しない。 家具固定は“合わせ技”:L金具が使えない賃貸は滑り止め+突っ張りで代替して実効を確保。 集合住宅(中高層) エレベーターは使わない:自動停止・閉じ込め回避。階段位置を日常から確認。 吊り天井・照明直下を避ける:ロビー・廊下の高天井は落下に弱い。 2
作成:伊藤憲和 2025年10月23日 配管・共用部:漏水・ガス臭・焦げ臭があれば管理室へ通報→立入制限。 ガラス飛散対策:腰高窓・ベランダ側は飛散防止フィルム+厚手カーテンで破片リスクを下げる。 超高層(タワマン・高層オフィス) 室内中央に退避:長周期大振幅では壁際・窓際・吊物直下が危険。 長時間化に備える:エレベーター停止・停電・断水を想定し、水・ライト・携帯トイレを各フロア備 蓄。 スロッシング(貯水槽の揺れ)等の設備リスクを管理組合・管理会社が点検・対策。 揺れが収まっても即移動しない:余震で再揺動。管理側の安全確認→案内に合わせて行動。 3) よくある誤解を一次資料で正す(Q→A) Q:高層は構造が強い=室内も安全? A:構造性能と室内安全は別。長周期地震動では什器・天井・配管の被害が主因になる。 3
作成:伊藤憲和 2025年10月23日 Q:停電復帰したら一斉に電源ONで確認? A:不可。 段階通電で発煙・異音を監視。異常時は即遮断→119。 Q:賃貸だから家具固定は無理? A:方法はある。 滑り止め+突っ張りなど非破壊の組合せでも効果を得られる。 Q:高層はとにかく外へ逃げれば安全? A:状況次第。 階段渋滞・落下物・ガラスの危険が勝る場合、室内中央で待機→安全確認後に段 階移動が合理的。 4) 今日からできる“最小セット” 家の“安全側”を決める:窓から離れた室内中央/吊り物の無い位置を家族で共有。 出入口の点検:ドア枠・戸車のガタを解消、非常開放手段を確認。 家具固定の実行: 4
作成:伊藤憲和 2025年10月23日 持家:L金具+下部滑り止め+上部固定(壁下地に効かせる)。 賃貸:滑り止め+突っ張り棒+前倒防止ストラップで合力を作る。 窓の安全化:飛散防止フィルム、厚手カーテン。ベランダの**落下物(プランター・物干し)**は撤 去。 電気の貼り紙:分電盤に**「復電は段階通電」**のメモ。感震ブレーカーの導入検討。 情報導線:**長周期地震動の観測情報(気象庁)**をブックマークし、階級表示の意味を家族で 共有。 5) 管理側(管理組合・事業所)が先にやること 天井・設備:吊り天井の補強・落下防止、配管支持の耐震化の点検計画。 エレベーター:地震時管制運転・停電時自動着床の有無/復旧手順の周知と訓練。 フロア備蓄:水・携帯トイレ・ライト・簡易毛布・救急箱を各階へ分散配置。 5
作成:伊藤憲和 2025年10月23日 広報:長周期地震動階級の説明と館内アナウンス定型文(日本語+英語)を準備。 6) 反証条件(どこまで当てはまるか) 免震・制振:体感の揺れ方は軽減されても、天井・什器・配管の対策は別途必要。 新耐震だから安全:室内の非構造材と設備は築年に関わらず被害が起こり得る。 低層だから長周期地震動は関係ない:共振は建物高さだけでなく周期関係で起こる。什器固定・ 窓対策は有効。 参考・一次資料(公式) 気象庁|長周期地震動に関する観測情報(階級と配信の仕組み) https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/ltpgm_explain/kaisetsu.html 長周期地震動の観測結果(最新一覧) https://www.data.jma.go.jp/eew/data/ltpgm/latest.php 国土交通省|超高層建築物等における長周期地震動への対策(通知・運用) 6
作成:伊藤憲和 2025年10月23日 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000080.html 内閣府|家具の転倒・落下・移動防止(実践的な固定方法・賃貸での代替策を含む) https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h25/72/bousaitaisaku.html 消防庁|通電火災に注意(復電時の留意点) https://www.fdma.go.jp/pressrelease/info/items/200707_yobou_1.pdf 責任と限界(重要) 本記事は一般情報であり、個別の助言ではない。最終判断は自治体・消防・警察・建物管理者 の指示に従う。緊急時の優先は、命 → 安全(頭部保護・退避位置・火気停止) → 情報 → 物 資。更新は追記方式で**「何が/なぜ/どう変わる」**を明記していく。 https://www.docswell.com/user/3428098474 https://itounorikazu.exblog.jp/ https://itohnorikazu.livedoor.blog/ 7
作成:伊藤憲和 2025年10月23日 8