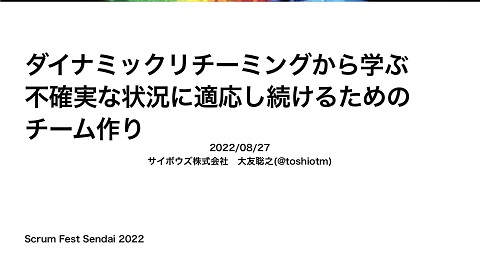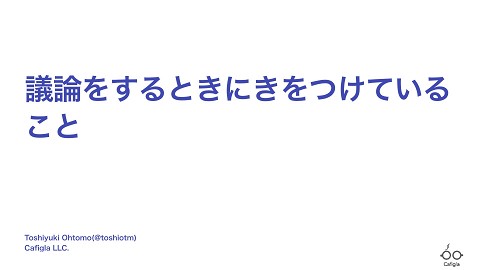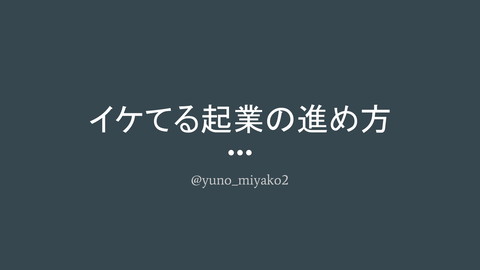やる気のマネジメント
10.7K Views
August 20, 25
スライド概要
Cafigla LLC. アジャイルコーチ 京都アジャイル勉強会(http://kyoaja.connpass.com)共同主催 CSP-SM, CSP-PO, Certified LeSS Practitioner
関連スライド
各ページのテキスト
やる気のマネジメント マネジメントする人もされる人も 知っておくといいことありそうなやる気の話. Toshiyuki Ohtomo(@toshiotm) Cafigla. LLC
マネジメントとは? リーダーシップとは?
マネジメントの父 ピーター・ドラッガー マネジメントとは物事を正しく行うことであり、 リーダーシップとは正しいことを行うことである 『経営者の条件』(原題 : The Effective Executive) 画像:ドラッガー日本公式
マネジメントとは? マネジメントとは与えられた目標やタスクに対して「物事を正しく行う」 こと →手段の話 リーダーシップとは組織の進むべき方向について「正しいことを行う」 こと →目的の話
マネジメントとは? マネジメントとは与えられた目標やタスクに対して「物事を正しく行う」 こと →手段の話 →効率の話 リーダーシップとは組織の進むべき方向について「正しいことを行う」 こと →目的の話 →効果の話
何をマネジメントするのか? では「マネジメントとは物事を正しく行うこと」であるなら、ここでいう物事とは?
何をマネジメントするのか? では「マネジメントとは物事を正しく行うこと」であるなら、ここでいう物事とは? ヒト・モノ・カネ
何をマネジメントするのか? カネとは? 経費:会社が何にお金を使っている? 売上:会社がどうやってお金を稼いでいる? など
何をマネジメントするのか? モノとは? マネージャーにしかできない、モノの買い方がある
ヒトのマネジメントとは? 仕事をしていない人がいます。 その理由は?
ヒトのマネジメントとは? 人が仕事をしていないときの理由は、2つしかな い。 ・単にそれができないか ・やろうとしないか のいずれかである
ヒトのマネジメントとは? つまり ・能力がないか ・意欲がないか
ヒトのマネジメントとは? つまりマネージャーのやるべきことは ・部下の教育 ・モチベーションの向上
マネージャーのアウトプット 自分の組織のアウトプット + 自分の影響力が及ぶ隣接諸組織のアウトプット
どうやってマネジメントするか? ・部下の教育 ・モチベーションの向上
モチベーションについて 皆さん、やる気に満ち溢れていますか? 満足していますか? 不満はありませんか?
モチベーションについて 改訂新版 世界大百科事典 動機づけ (どうきづけ)motivation 生物を行動に駆りたて目標に向かわせる内的な過程。モティベーションともいう。すなわち,( 1)生物になんらかの不均衡状態が生じる と,(2)これを解消しようとする内的状態(動機 motiveまたは動因 drive)が起こり,( 3)目標に向かって行動がひき起こされる,という過程 をさす。さらにこの用語は,そのような過程を効果的にひき起こすための操作の意味でも使われる。従来動機づけは,生物の不均衡状 態にもとづき,外にある目標によってひき起こされると考えられてきたが,近年,行動自体に内在する推進力によるものもあることが指摘 されるようになった。前者を外発的動機づけ,後者を内発的動機づけという。 学習指導にかかわる動機づけの操作を例にとると,外発的動機づけの代表的な方法は賞罰(飴とむち),競争,協同などである。これ に対して内発的動機づけの例としては,既有の知識と矛盾するような知識を与えると学習者の内部に概念的葛藤が生じ,これを解消し ようとする知的好奇心が発生して学習行動が活発化するという事実を利用するものが代表的である。この場合,学習を動機づける要因 は学習自体とは本来無関係な賞や罰ではなく,学習活動そのものに含まれている。なお動機づけは教育においてばかりでなく,勤労 者の勤労意欲 や消費者の購買意欲の喚起のためにも広く用いられる概念であり,操作である。
モチベーションについて 改訂新版 世界大百科事典 動機づけ (どうきづけ)motivation 生物を行動に駆りたて目標に向かわせる内的な過程。モティベーションともいう。すなわち, (1)生物になんらかの不均衡状態が生じ ると,( 2)これを解消しようとする内的状態(動機 motiveまたは動因 drive)が起こり,( 3)目標に向かって行動がひき起こされる,とい う過程をさす 。さらにこの用語は,そのような過程を効果的にひき起こすための操作の意味でも使われる。従来動機づけは,生物の不 均衡状態にもとづき,外にある目標によってひき起こされると考えられてきたが,近年,行動自体に内在する推進力によるものもあること が指摘されるようになった。前者を 外発的動機づけ ,後者を 内発的動機づけ という。 学習指導にかかわる動機づけの操作を例にとると, 外発的動機づけの代表的な方法は賞罰(飴とむち) ,競争,協同などである。こ れに対して 内発的動機づけの例としては ,既有の知識と矛盾するような知識を与えると学習者の内部に概念的葛藤が生じ,これを解 消しようとする 知的好奇心が発生して学習行動が活発化する という事実を利用するものが代表的である。この場合,学習を動機づけ る要因は学習自体とは本来無関係な賞や罰ではなく,学習活動そのものに含まれている。なお動機づけは教育においてばかりでなく ,勤労者の 勤労意欲 や消費者の購買意欲の喚起のためにも広く用いられる概念であり,操作である。
モチベーションについて 皆さん、やる気に満ち溢れていますか? 満足していますか? 不満はありませんか? バランスが取れていますか?
二要因理論 (Herzberg's Two-Factor Theory) 衛生要因(Hygiene Factors) 動機づけ要因(Motivators) → 欠けると不満足を生む要因(あっても満足はしない) 環境や待遇など、仕事の外部条件に関わるもの → 満足感を生む要因(なければ無関心にはなるが、不 満ではない) 仕事に対する内的な欲求を満たすもの ● ● ● ● ● 給与(給与体系) 労働条件(安全・設備など) 上司との関係 会社の方針 雇用の安定性 ● ● ● ● ● 達成感 承認 仕事そのものへの関心 責任のある仕事 成長や昇進の機会
二要因理論 (Herzberg's Two-Factor Theory) 「満足の反対は不満ではなく、満足がない状態 である。不満の反対は満足ではなく、不満がな い状態である。」 “The opposite of job satisfaction is not job dissatisfaction, but no job satisfaction; and the opposite of job dissatisfaction is not job satisfaction, but no job dissatisfaction.” Herzberg, F. (1966). Work and the Nature of Man. Cleveland: World Publishing.
二要因理論 (Herzberg's Two-Factor Theory) ・満足かつ不満がない状態 ・満足しているが、不満がある状態 ・満足していないが、不満はない状態 ・満足していなくて、不満もある状態 満足と不満足は共存する
職場に不満(衛生要因)ありますか? ● ● ● ● ● 給与 労働条件(安全・設備など) 上司との関係 会社の方針 雇用の安定性
職場に満足感(動機づけ要因)はありますか? ● ● ● ● ● 達成感 承認 仕事そのものへの関心 責任のある仕事 成長や昇進の機会
人の「やる気」を説明 する理論や モデル 動機づけ要因をどうやって育むか
動機づけ要因をどうやって育むか 人のやる気について、かなり以前から色々と研究されている 理論 正式名称 発表年代 主な特徴 欲求理論 Human Motivation Theory 1961年 達成・権力・親和の3つの社会的欲求が個人 差により動機づけに影響する。 期待理論 Expectancy Theory 1964年 努力→成果→報酬の期待が揃うと動機づけ が高まる(合理的選択モデル)。 目標設定理論 Goal-Setting Theory 1968年(初出)/1990年(体系 化) 明確で挑戦的な目標がモチベーションを高め る。受容とフィードバックが鍵。 ERG理論 ERG Theory 1969年 マズローの5段階を3分類(生存・関係・成長) に簡略化。退行の可能性あり。 フロー理論 Flow Theory 1975年(初期)/1990年(書 籍) 挑戦とスキルのバランスで没頭状態(フロー) に入り、生産性と満足度が向上。 自己決定理論(SDT) Self-Determination Theory 1985年(体系化) 自律性・有能感・関係性の3つの欲求が満た されると内発的動機づけが高まる。
自己決定理論( SDT) SDTは人間の成長と幸福に不可欠な 3つの基 本的心理的欲求を特定 内発的動機づけ(intrinsic motivation)」に焦点 を当て、やる気を引き出すには3つの基本的な 心理的欲求が満たされる必要がある 1. 自律性(Autonomy): 自分の行動を自分で決定したいという欲求 https://selfdeterminationtheory.org/SD T/documents/2000_RyanDeci_SDT.pd f 2. 有能感(Competence): 効果的に環境と相互作用したいという欲求 3. 関係性(Relatedness): 他者とつながり、所属意識を持ちたいという欲 求 https://www.selfdeterminationtheory.org/SDT /documents/2000_DeciRyan_PIWhatWhy.pdf
自己決定理論( SDT)の実験例 提唱者: Edward L. Deci(デシ) & Richard M. Ryan(ライアン) 初出: 1980年代〜現在も継続中 「人が本当にやる気になるのは、外からの報酬や強制ではなく、内面からの自発的な欲求によるものである」 研究の背景: 1970年代、心理学では「外発的動機づけ(報酬・罰など)で人を動かす」が主流でした。 このとき登場した疑問が: 「報酬を与えると、かえってやる気が下がるのではないか?」 有名な実験( Deci, 1971): パズル(ソーマキューブ)を使って学生を 3つのグループに分けた 第1セッション:どちらのグループにも普通にパズルを解いてもらう (8分間の休憩) 第2セッション:Aグループにはパズルが解けるたびに 1ドルの報酬を与え、 Bグループには普通にパズルを解いてもらう (8分間の休憩) 第3セッション:どちらのグループも普通にパズルを解いてもらう 8分間の休憩時間にどれぐらいパズルに触れるかを計測。 結果: 実験の結果、何の報酬も与えていなかった Bグループは、パズルに触れる時間に変化はなかったが、 報酬を与え得られた Aグループは、パズルに触れる時間が少なくなりました。
アンダーマイニング効果 (Undermining Effect) アンダーマイニング効果とは、内発的に動機づけられた行為に対して外発的な動機づけを行うこと によって、モチベーションが低下する現象を意味する言葉
自己決定理論( SDT) SDTは動機づけを連続体として説明しています 振る舞い 非自己決定 自己決定 動機づけの 種類 無動機 調整の種類 調整なし 外的調整 取り入れ 調整 同一化 調整 因果関係の 所在※1 非個人的 ※2 外的原因 部分的に外 的原因 部分的に内 的原因 内発的 動機づけ 外発的動機づけ ※1因果関係の所在: ある出来事の原因を、自己の内面的なものと捉えるか、外部的なものと捉えるかの帰属の こと ※2非個人的(impersonal): 自分の行動が自らの意思や能力とは無関係な、コントロール不能な力によって決まってい るという無力な感覚 統合調整 内発的 調整 内的原因 https://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000 _DeciRyan_PIWhatWhy.pdf
自己決定理論( SDT) SDTは動機づけを連続体として説明しています 振る舞い 非自己決定 やらないと上 司に怒られる からやろう みんなが楽 になるからや ろう 動機づけの 種類 無動機 調整の種類 調整なし 外的調整 取り入れ 調整 同一化 調整 因果関係の 所在 非個人的 外的原因 部分的に外 的原因 やらないと迷 部分的に内 的原因 自己決定 自分がこれを やりたい 内発的 動機づけ 外発的動機づけ 惑をかけてし まうからやろ う 統合調整 内発的 調整 内的原因 あれっ自分 はみんなの サポートが好 きかも https://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000 _DeciRyan_PIWhatWhy.pdf
自己決定理論( SDT) 自律性(Autonomy) ● ● ● 自分の意志で行動しているという感覚 指示されるだけではなく、自分で選択肢を持てる環境が重要 誰かと協働していても、自分の選択であればOK
自己決定理論( SDT) 有能感(Competence) ● ● うまくやれている、成長しているという感覚 適度なチャレンジやフィードバックがやる気を後押し
自己決定理論( SDT) 関係性(Relatedness) ● ● 他者とのつながりや承認、所属感 チームや上司、仲間との信頼関係が重要
自己決定理論( SDT) どうすればこれら3つの条件を整えることができるのか?
自律性 Autonomy 自分の行動を自分で決定したいという欲求
自己決定理論( SDT) 自律性( Autonomy) 4T:現代の知識労働や創造的仕事において、人が最大限にやる気を発揮するには「自律性」が必要 1. Task(タスク) 「何をやるか」を自分で選べること 自分が興味を持ち、意味を感じるタスクを選べるとモチベーションが上がる。 一定の裁量を与えることで、自分ごと化が促される。 2. Time(時間) 「いつやるか」の自由度 一律のスケジュールよりも、自分のペースで働けることで、集中力や創造性が高まる。 時間の柔軟性があることで「やらされ感」から 脱却できる。 3. Technique(やり方) 「どうやってやるか」を選べる自由 方法を細かく管理・指示されるのではなく、自分なりの工夫やアプローチが許されること。 「成果」を重視し、プロセスは信頼して任せ ることが大切。 4. Team(誰とやるか) 「誰と一緒に働くか」の選択の余地 チーム編成や協力相手を選べることで、人間関係への納得感が高まり、心理的安全性も増す。 自分が信頼する人と取り組む方が、 協働への意欲も高まりやすい。 出典:『モチベーション3.0』
自己決定理論( SDT) 自律性( Autonomy) 自分の取り巻く状況を自分の手でコントロールできるという感覚が必要 単純作業の中にも、 ・意味のある仕事をしていると感じるような進め方を選べたり ・参加するプロジェクトを選べるようしたりすることで 同じ作業をしていてもより深い満足を覚えることができる 出典:HBR2022.8 Make Your Team Feel Powerful
自己決定理論( SDT) 自律性( Autonomy) 目的は詳細に、手段は大まかに リーダーが目標や枠組みを示しつつ細部の進め方は部下の裁量に委ねるアプローチ は、フィードバックや指示を与える場面でも部下の自律性を尊重する 目的を具体的に示す? ノー イエス ノー 何をどうすればよいか わからない混乱状態 チームが自己管理をしな がら目標にむかって着実 に前進 イエス チームがしらける (最悪のパターン) 人的資源がフル活用され ない 手段を具体的に 示す? 出典:ハーバードで学ぶ「デキるチー ム」5つの条件
自己決定理論( SDT) 自律性( Autonomy) 目的は詳細に、手段は大まかに どこまで許されるのか柵を提示した上 で、その中では裁量を持って自由に走っ てもらう
有能感 Competence 効果的に環境と相互作用したいという欲求
自己決定理論( SDT) 有能感( Competence) うまくやれている、成長しているという感覚 適度なチャレンジやフィードバックがやる気を後押し 『部下の教育』はマネージャーのやるべきことの一つ 自律性、有能感を得るためには、知識や経験が必要 教育を強制するのではなく、日頃の会話や1on1などから、本人の意思が感じ取れるところを探し、機 会を提供する
自己決定理論( SDT) 有能感( Competence) 必要のない支援に対して人は強い負の反応を示す ・タイミングを図る 従業員側に支援を受ける準備が整った時 に提供する ・自分の役割を明確にする 自分の役割が 評価者ではなく 、支援者だということを明確に伝える ・関与のリズム 関わりの強度と頻度 を受け手側の具体的ニーズと一致させる 相手からの申し出があるまでは、ただ手を貸せるということだけを伝え続け る 出典:HBR 2021.3 How to Help
自己決定理論( SDT) 有能感( Competence) また、新しいことにチャレンジすると必ず起こるのは失敗 失敗にも種類があるので、失敗への理解を深め 安全に失敗できる(Safe to fail)環境を整えることもマネージャーのサポートの一つ
有能感( Competence) 失敗の種類 非難される失敗 防ぐことができる失敗 プロセスからの逸脱 複雑な失敗 複雑なシステムにおける不確実性 賞賛される失敗 知的な失敗 失敗に終わった試み 出典:チームが機能するとはどういうことか
有能感( Competence) 学習性無力感 「どうせ無駄だ」ということを学習してしまうと、状況が変わっても何かを試そうという気持ち を失う 『人はただ無力を学ぶのではなく、その失敗の理由の解釈(帰属)の仕方が重要』 Abramson, L. Y., Seligman, M. E. P., & Teasdale, J. D. (1978). “Learned helplessness in humans: Critique and reformulation.” Journal of Abnormal Psychology, 87(1), 49–74. スタイル 無力感を強める帰属 健康な帰属 恒常性(時間軸) 「いつも自分はダメ」 「今回はたまたま」 普遍性(範囲) 「全部だめ」 「一部だけうまくいかなった」 内在性(原因) 「自分が悪い」 「状況が悪かった」
有能感( Competence) 生存者バイアス( Survival bias) 何らかの選択過程を通過した人・物・事のみを基準として判断を行い、その結果には該当しな い人・物・事が見えなくなること 出典:Wikipedia(2025-07-22現在) マネージャーになった人たちは、自分が生き残ったのだから他の人も同じやり方で生き残れるだろう (生き残るべきだ)と考えがち 生き残れなかった人たちがどれくらいいたかを知らないため、自分が受けた教育、自分が育った環境 でのやり方が正しいと考えがち 自分が生存できたのだから、同じやり方でもよいだろうと安易に引き継いでしまわないように
関係性 Relatedness 他者とつながり、所属意識を持ちたいという欲求
自己決定理論( SDT) 関係性( Relatedness) 他者とのつながりや承認、所属感 チームや上司、仲間との信頼関係が重要 関係性が良くなると何が嬉しいのか?
関係性( Relatedness) ダニエル・キムの成功循環モデル 「成果」は「行動」から生まれるが、その行動は「関係の質」や「思考の質」によって左右 される 関係の質:相互理解、共感のある対話 思考の質:自己効力感、目的の明確さ 行動の質:自律的な行動、内発的な納得感 結果の質:成果につながり信頼が高まる
関係性( Relatedness) 逆循環(バッドサイクル)だと 成功循環がある一方、バッドサイクルも起こりえる 関係の質が低い:不信、無関心 思考の質が下がる:諦め、疑念 行動が表面的になる:指示待ち 結果がでない:評価されない さらに関係の質が低下…
関係性( Relatedness) 機能不全なチーム なぜ関係性が悪くなったのか? チームとして結果より個人の地位と自尊心 →結果への無関心 仕事に責任を感じていないため基準の低さ →説明責任の回避 衝突した深い議論がないためあいまいな態度 →責任感の不足 信頼関係がないため表面的な調和 →衝突への恐怖 失敗や弱みを見せられないため完全無欠に振る舞う →信頼性の欠如 出典:あなたのチームは、機能していますか?
関係性( Relatedness) 完全無欠 自己欺瞞:自分で自分の心をあざむくこと。自 分の良心や本心に反しているのを知りながら、 それを自分に対して無理に正当化すること。 出典:小学館 デジタル大辞泉 まずは、自分が自己欺瞞におちいっていない かを確認できるように心がける 出典:自分の小さな「箱」から脱出する方法
関係性( Relatedness) 根本的な帰属の誤り 残念だけど、誰にでもある思考の傾向 人は他人の行動を根拠なくその人の「種類」によって決定されていると見、社会的かつ状況的な影響 を軽視する傾向がある。また、自身の行動には逆の見方をする傾向がある 出典:Wikipedia(2025-07-02現在) 私たちはある人の欠点を、その人が直面している状況ではなく能力や姿勢と関連づけて解釈するよう になる。 出典:出典:チームが機能するとはどういうことか
関係性( Relatedness) 推察 残念だけど、誰にでもある思考の傾向 確かめもしないのに、人は自分の想定を真実だ と考えてしまう 自分の知らないことについて推察しているにも かかわらず、自分の知っていることをもとにして 結論を出してしまう 無 意 識 の う ち に 一 気 に 駆 け 上 が っ て し ま う 一 つ 一 つ 事 実 を 確 認 し な が ら 上 が る こ と が 大 事 出典:ファシリテーター完全教本
関係性( Relatedness) すぐれたチームとは? 生産的な衝突が、短時間で最良の解決策を見出す方法だと理解している 自分の間違い、弱み、不安を認める 隠しておきたいことでも迷わずさらけ出す 対人リスクを自ら冒す(他人との危険領域に踏み込む) 出典:あなたのチームは、機能していますか?
関係性( Relatedness) 共通の目的と相互の敬意 なぜ、完全無欠に振る舞うのか? 議論をして勝ち負けを決めたいわけではない ”共通の目的が存在しなければ、緊迫した会話を始めても意味がない ” ”相互の敬意が存在しないならダイアローグ(対話)を継続できない ” 出典:ダイアローグスマート ”ダイアログでは勝とうとするものはいない。ダイアログがうまくいっているなら全員が勝者だ ” 出典:学習する組織
関係性( Relatedness) 心理的安全性 高 心理的安全性とは:対人関係においてリスクあ る行動を取ったときの結果に対する個人の認知 の仕方 出典:Wikipedia 心 理 的 安 全 性 低 快適 学習 無関心 不安 基準/責任 出典:チームが機能するとはどういうことか
関係性( Relatedness) 心理的安全性 高 無関心: 巨大な組織 官僚的 最小限の努力で仕事を行う 快適: 楽しく陽気だが、挑戦していない 打ち込んで仕事をすることがほぼない 学習やイノベーションが生まれない 不安: マネージャが高い基準を設定することと、マネジメ ントを混同している 強いプレッシャーをあたえることが高パフォーマンス につながるとマネージャが誤った考えを持っている 学習: 人々はたやすく協働し、お互いから学び、仕事をや り遂げることが出来る 心 理 的 安 全 性 低 快適 学習 無関心 不安 基準/責任 出典:チームが機能するとはどういうことか
関係性( Relatedness) 心理的安全性 高 チームが機能するためには必要なのは ただの「快適」さではない。 共通の目的を達成するために、 必要ならタブーについても話し合えるようにな る、そのためには心理的安全性が必要 心 理 的 安 全 性 低 快適 学習 無関心 不安 基準/責任 出典:チームが機能するとはどういうことか
20% 好きなことが仕事に占める割合が20%に満たない場合は、そうでない場合と比べて、肉体 的、心理的に燃え尽き症候群(バーンアウト)に陥る可能性が格段に高い 出典:HBR2022.8 Designing Work That People Love
燃え尽きてしまったら 有能感の回復 : - 小さな成功体験の積み重ね - 段階的な目標設定 - 建設的フィードバックの提供 自律性の支援 : - 選択の機会の提供 - 意思決定への参加 - 自己決定感の育成 関係性の構築 : - 社会的サポートの提供 - チームワークの促進 - 所属感の醸成
まとめ マネジメントは、物事を正しく行うこと。 そのためにも、ヒト・モノ・カネについて興味をもち マネージャーにしかできない、物の買い方→設備投資など マネージャーにしかできない、人への投資→教育、日々のサポートなど 人を知るために、自分も含め何に満足・不満足を感じているか把握しましょう
まとめ 悪い土壌では植物は育たないが、すくなくとも良い土壌をつくれば、それぞれの特性に応じて実をつけ てくれる
まとめ 文化とは、共通の目標に向かって力を合わせて取り組む方法である。 文化とは、組織内のプロセスと優先事項が、独自の方法で組み合わさったものをいう。 出典:イノベーション・オブ・ライフ ハーバード・ビジネススクールを巣立つ君たちへ
まとめ 今いる人のためだけではなく、これから入ってく る人のためにも、良い文化(環境・土壌)を整え ましょう。 そうすれば、きっとさまざまな実をつけてくれるこ とでしょう