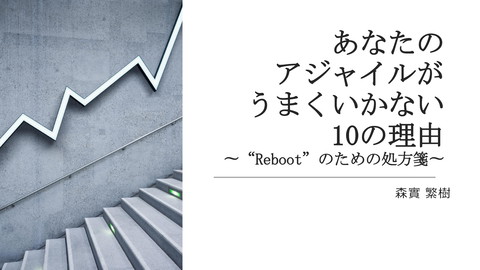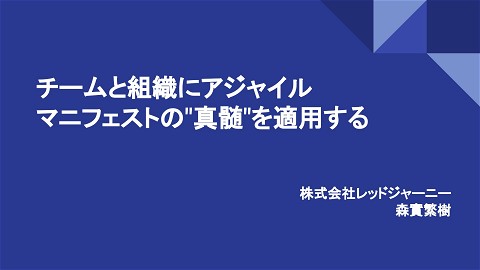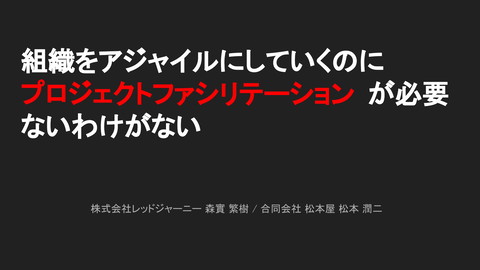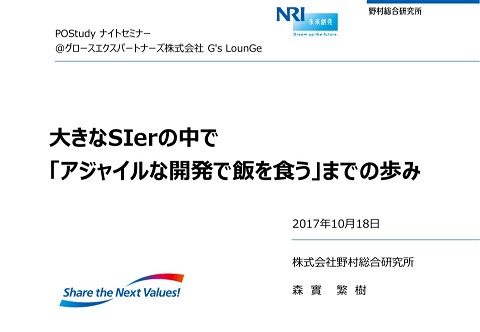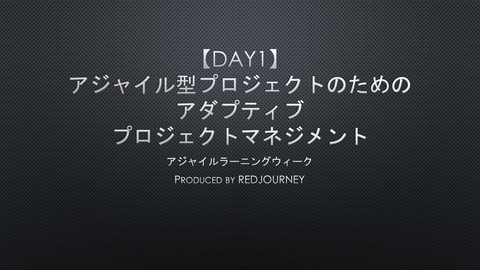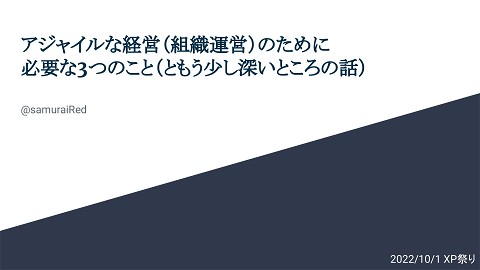[スクフェス大阪2024]組織は人でできている~組織をマルチレイヤーアジャイルでコネクトしよう~
19.7K Views
June 21, 24
スライド概要
https://youtu.be/TK_TszaoRmQ?si=KXMXeBzlUpOTWqWM
この発表では、「組織をマルチレイヤーアジャイルでコネクトしよう」というテーマで、組織を構成する歯車、階層構造や組織が積み重ねるものについて言及しました。また、組織が次のステップに進むためには、当たり前のことを当たり前にできているかどうかが重要であることを強調しました。
大手SIerでの開発/運用、大規模プロジェクトマネジメントを経験した後、ミドルベンチャーでCTO、通信系事業会社でエンジニアリングマネージャー、国立大学で非常勤講師などを歴任。プロダクト開発や組織づくりに造詣が深い。 2003年からアジャイルを実践しており、社内外問わずいくつものチーム、組織の支援を行ってきた。現在は、株式会社レッドジャーニーで認定スクラムプロフェッショナルとしてDX支援、組織変革に邁進している。 日本XPユーザグループスタッフ BIT VALLEY -INSIDE-ファウンダー 保険xアジャイルコミュニティ「.insurance」オーガナイザー 人材ビジネスxアジャイルコミュニティ オーガナイザー Agile Tour Yokohama実行委員 SWise株式会社、Pluslab株式会社外部顧問 ゼロからはじめるチームプロジェクトマネジメント著者
関連スライド
各ページのテキスト
2024/6/22 スクフェス大阪@虎ノ門トラック 組織は人でできている 〜組織をマルチレイヤーアジャイルでコネクトしよう〜 @samuraiRed
自己紹介 @samuraiRed ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 株式会社レッドジャーニー SWise株式会社 外部顧問 Pluslab株式会社 外部顧問 筑波大学 非常勤講師 日本XPユーザグループ スタッフ BIT VALLEY -INSIDE- ファウンダー 保険xアジャイルコミュニティ「.insurance」 オーガナイザー アジャイル経営カンファレンス 実行委員 2
前提事項 今回のお話は、最大で全社レベル(経営レベル)までを組織とし て捉えていますが、皆さんの考える組織(チーム)の大きさに当 てはめてもらってもご理解いただける内容になっています。 3
1.組織を構成する歯車について 2.そもそも組織は何を積み重ねているのか 3.組織が次の一歩を踏み出すための前提 アジェンダ 4.組織の目標を立てる、ということ 5.私たちの仕事は何につながっているのか 6.チームや組織の営みの活用を最大化する 7.組織をマルチレイヤーアジャイルでコネクトする 4
1.組織を構成する歯車について 5
組織は階層でできている 6
組織は階層でできている <興味関心ごと>やり方の話 <リスク>やり方上、起きること <期待値>プロダクトで実現したい回転スピード 7
組織は階層でできている <興味関心ごと>やることとやり方の話 <リスク>やることの正しらしさとやり方上起きること <期待値>組織・事業で実現したい回転スピード ※ただし、プロジェクトの回転以上の速さにはできない 8
組織は階層でできている <興味関心ごと>ROI最大化の話 <リスク>投資効果が見合わない プロダクトポートフォリオ戦略が機能しない <期待値>経営で実現したい回転スピード ※ただし、プロダクトの回転以上の速さにはできない 9
組織は階層でできている <興味関心ごと>経営戦略実現の話 <リスク>経営戦略が達成できない 事業ポートフォリオ戦略(組織)が機能しない <期待値>回転スピードを決めるのは経営 ※ただし、組織・事業の回転以上の速さにはできない 10
組織は歯車でつながっている 11
2.そもそも組織は何を積み重ねているのか 12
組織はフィードバックの連続性でできている 13
3.組織が次の一歩を踏み出すための前提 14
当たり前のことを当たり前にできているか ■今のやり方は十分に機能していますか? –施策立て、進捗、コスト、価値、従業員満足度…etc プロジェクトだけとっても、当たり前(QCDS)が できていなければ、やり方をかえてもうまくできる ”土壌”がない状況 15
当たり前ができない土壌 組織変革やアジャイルの力に頼るのは土台無理がある やり方を変える前に、いま自分たちができていない 当たり前を当たり前にできるようにする必要がある 「なんとかする」のがマネジメント by ドラッカー先生 自分たちのマネジメントは崩壊していませんか?という自己点検 16
4.組織の目標を立てる、ということ 17
我々は組織目標にふりまわされている 目標 18
目標は目的からできている 目的 目標 計画 目的を理解してこそ組織が目標を設定できる 19
目標は人が決めている 目的 目標 計画 20
人が決めるものには「思惑」がある 思惑 目的 目標 計画 「思惑」を理解しないと真のゴール (目的と目標のつながり)を捉えられないことが多い 21
計画は複数のインプットでできている 計画 やりたいこと (WILL) やれるように なるべきこと (CAN) やらなければ いけないこと (MUST) 22
組織のWILL/CAN/MUSTをとらえてみる ■ WILL/CAN/MUSTとは… – リクルート社が始めた、従業員育成のためのフレーム ■ WILL(本人がやりたいこと) ■ CAN(今後活かしたい自分の強みや克服したい課題) ■ MUST(能力開発につながるミッション) 個人の成長支援ツールで使われることが多いが、 組織にも適用することができる 23
組織のWILL/CAN/MUSTをとらえてみる ■ 組織におけるMUST これはミッションであり、会社の大きな流れの中で生まれたやらないと いけないことを含むもの。 組織上では、上位から決まってくる”やること”は比較的明確。 いわゆる目標として定められることが多い。 24
組織のWILL/CAN/MUSTをとらえてみる ■ 組織におけるWILL これは先に述べた目標の前にある目的を組織的に言語化したもの。 上位の組織体の目的と”思惑”を理解し、組織としてありたい姿のこ と。 自分たちがMUSTをこなした状態、ではない。 25
組織のWILL/CAN/MUSTをとらえてみる ■ 組織におけるCAN MUSTはやらなければいけなくて、WILLは向かいたい方向性、そし てここにはHEREがある。 HEREとWILLの間にはGAPがあり、GAPを超えていくために、 「できること(CAN)」はなにで、「できないこと(CAN’T)」はなに かととらえる。 「できないこと」は獲得すべきケイパビリティである。 26
5.私たちの仕事は何につながっているのか 27
組織のOKRのスコープを補足する ※今回は、OKRは組織のミライ展望を見つめるものとして扱います 28
単純なOKRの構造を理解する Objectives Results Key Results Results Tasks Main Tasks Tasks Key Results Results Main Tasks 29
単純なOKRの構造を理解する ■ Objectives ・・・組織のありたい姿(達成したあとの”はず“の姿) ■ Key Results ・・・Oを達成するための評価軸と指標値(の一部) ■ Tasks ・・・KRを実行単位に分解したもの ※WILL/CAN/MUSTのCANで手に入れなければいけないものを含んでおく やりたいこと (WILL) やれるように なるべきこと (CAN) やらなければ いけないこと (MUST) 30
組織のOKRは階層型にできている 31
組織のOKRは階層型にできている Pattern1:やることに集中!型 ■ メリット – ■ ■ 主要な結果指標やタスクを考えるのが非常にわかりやすい デメリット – 何(大もとのOなど)を達成するためにこの下位層のOKRをやっているのか わからなくなりやすい – 定期的に上位層とゴールに向けた活動になっているかの相関をチェックするこ とがおすすめ 相性の良い組織 – 比較的小規模、のベンチャーや、圧倒的ブルーオーシャンの中で方向性が目 に見えている企業 – 社員がまだ若く、スキルを磨いている時期であれば、集中して目標に向かえる 環境に役立つかもしれない 32
組織のOKRは階層型にできている Pattern2:上位憑依型 ■ メリット – 自分たちの活動がOの連続性が担保されることで目的を見失う可能性 は低い ■ デメリット – 上位KRに倣うため、下位KRの指標が下位のスコープに応じた按分の 指標となりがち – 上位KRの設定が絶対的に正しいと思えるものでないとやる意味がある のかの疑問を生じる – その場合の修正には上位のOKRを含めて通しでアライメントをとる必要 が ■ 相性の良い組織 – プロダクトと企業の姿勢でいえば、企業の姿勢に共感を覚える社員が多 い会社にこのパターンが合う – 企業の姿勢としての目的と結果指標を共有することがそもそも容易 33
組織のOKRは階層型にできている Pattern3:上位下位合意型 ■ メリット – 上位が上位の視点だけでOKRを立てるのではなく、下位が上位Oを意 識したときにどんなKRを定めるべきか視点と視座をあげて提案することで、 下位OKRとも強い結びつきが得られる – 納得度という意味では増しやすくなるでしょうし、否が応にも上位を意識 しなければいけないので、結果も自ずと上位につながる結果を出すことが 約束されやすい ■ デメリット – 決定までのプロセスにおける登場人物が増えれば増えるほど決定に異 様に時間がかかる ■ 相性の良い組織 – Pattern2の逆で、プロダクトへの愛着や意識で強く結ばれている組織に 合う – 特に上位はプロダクトの言いなりになるのではなく、組織戦略からの調整 役として機能することで、方向性を強く打ち出すことができる 34
どうして階層型OKRを運営するのは難しいのか 35
組織OKRのトレーサビリティをマネジメントする ■ バックキャストで状態を設定し、そのタスクをどうやってトレースしていくか枠組みから考える 36
組織のOKRは3段階でできている① 37
最上段には常に会社の目的や目標がある 38
組織の目的は常に組織の最上位にある 39
組織のObjectivesは複数でできている 40
組織のObjectivesは誰かが担っている② 41
チームのObjectivesは組織から生まれる③ ■ すべてのチームが組織目標をすべて表示しておくことで、他でどんな取り組みをしているのかを みえるかすることができる 42
私たちの仕事は会社のビジョンにつながっている ■ この3段階で、会社から現場チームまで目的と目標を透過させることができる 43
指標は行動指標と結果指標でできている ■ 行動指標はどういう行動をとれていれば結果につなげることができるか ■ 結果指標は最終的に達成したい結果 (例) – 毎月名刺を新たに100枚交換してくる(行動指標) – ことで、年間の売上をXX億達成する(結果指標) KPIは通常年度の結果指標であることが多く、各Q等で設定するKRは、 あくまで行動指標であることが多いため、毎月、各Qのタイミングなどで、 行動と結果の相関をみていくことは大きな意味がある つまり、やってみて行動指標がKPIやObjectivesにつながっていないと観測できたならば、 行動指標を見直すのは必然のこと(安易にOやKPIを見直すことはしない) 44
6.チームや組織の営みの活用を最大化する 45
組織とチームは疎にしかし密につながっている ■ どこまでを組織とチームで握り、どこから先はチームに任せ、どこは組織として介入、解決する のかを、組織にあわせてテーラリングしていく 一番トレースしないといけないのは、戦略と戦術、目的と目標のアライメントである 46
組織が機能するには責任が明確化されている ■ RACIなどを使って、誰が何をする役割なのかの定義をすることはとても有効 ■ むしろ、チームで決めてチームでやって、というのは結局誰の責任にもならない 47
ふりかえりはコミュニケーションでできている 48
ふりかえりはコミュニケーションでできている 学び・気付き 挑戦 思い起こし 予測 49
人は制約にあわせて動いている ■ KEEPやPROBLEMではどこまでかいていいか悩んでしまう ■ こういうことを書いてほしいというサジェストをしてあげると人は動いてくれる ■ KEEPよりの内容を暖色、PROBLEMよりの内容を寒色にすると… 50
色はチームの状態をあらわしている ■ 俯瞰してみるだけで、チームがどういう状態だったかをふりかえることもできる ■ チームを色で感じるのは、日常的にやることでプロジェクトファシリテーションにも活かせる 51
予測できることは先回りできる ■ 悪い予感はたいてい当たる ■ 来週、来月起きたらいやだなぁと思うことがあるならば、まさに Start/Stop/Continueのかっこうのネタでしかない これが予防型マネジメントである 52
終われるのは始まりがあるものだけである ■ 組織の課題であれ、チームの課題であれ、こうしたほうがいい、こうなりたいという欲望、願望 は大きくなりがちである ■ 総論賛成という状態の時は、「とりあえず来週やりきれること」を1つでいいからあげる ■ 来週やり切れることはその場でタスクとしてエントリーさせてしまい、アサインを終わらせる たったこれだけで、壮大な願望でさえ、始まってしまう 人間はどんなにひどいプロジェクトであれタスクであれ終わらせることができる有能な生き物である 53
体験値1は経験値3にも4にもできる ■ 学びや気づきにでてきたものは、事象である事が 多い ■ 事象は体験であり、体験は共有できない ■ 事象には背景があり、人の行動には意図がある ■ こういう背景のときに、こういう行動をとると、よい、 あるいは悪いことになるということまで言語化するこ とで、体験をしていない人にも経験値にすることが できる ■ 組織の知とは、体験値の共有ではなく、経験値 を増やす活動の積み重ねである 54
月の目標やKRはふりかえりを反映している 55
組織の輝きはチームの輝きで作れる ■ 良くなかったこと、トラブルなどは報告を求められたり、ポストモーテムとして資 料化されて共有されることが多い ■ 逆に、良かったこと、メンバーが考えて行動してくれて助かったこと、こういう取り 組みに変えてみたらチームで意見を集めやすくなったなどなどの工夫や感謝は 共有されているだろうか ■ チームの輝きは組織に向かって自慢していいし、むしろじゃんじゃんやろう ■ プラスの波紋はいつだって小さな輝きから始まる 56
7.組織をマルチレイヤーアジャイルでコネクトする 57
組織とチームの目的と目標をコネクトする ■ 目的と目標が組織からチームにつながる 58
組織とチームの取り組みと成果をコネクトする ■ 取り組みと成果が目的と目標の実現につながる 59
組織とチームを疎にしかし密にコネクトする ■ 現場の独立を認め、挙げられた課題は組織的に対処する 60
チームの学びを組織の学びにコネクトする 61
そしてすべての歯車を噛み合わせよう ■ フィードバックに学び、組織全体を小さなアジャイルの輪の大車輪にしていこう 62
まだこわいかい? だいじょうぶ、 組織は人でできている 63