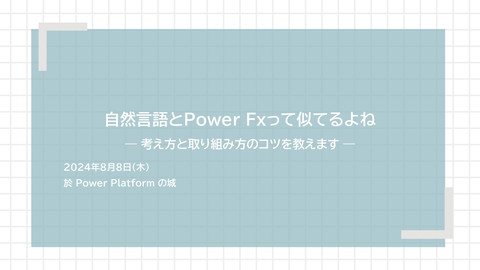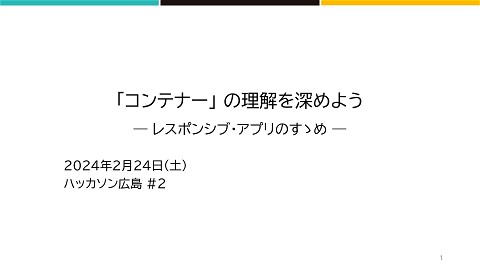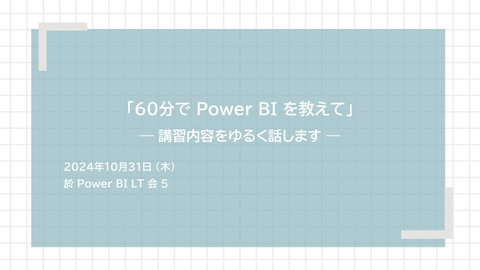「よい講習」再考
2.1K Views
July 12, 25
スライド概要
JPAUG広島in有馬温泉にて使用した発表資料です
関連スライド
各ページのテキスト
JPAUG 広島 in 有馬温泉 ~枕とマサカリを投げ合う回~ 「よい講習」再考 2025 年 07 月 12 日(土) 隅田 智尋 also known as kuro.
00 当発表の目的 ✓ 議論を生み出すこと ✓ よい、わるい の判断基準に触れている本 → ✓ 形容詞は「主観」を表現するもの ✓ 自分が「よい」と思っているものは、 他人の「わるい」かもしれない 考える機会としてご聴講ください アゴタ・クリストフ(著), 堀 茂樹(編)2001,『悪童日記』, ハヤカワ epi 文庫
自己紹介 kuro. : https://kuro96.myportfolio.com : https://twitter.com/eigogakuto 個人事業主 (2023~) Power Platform 講習/内製開発支援/ヘルプデスク Power Platform を起点に、市民開発者の養成を支援しています。 自身が非開発者の出身であることや、非IT部門の方々に対する技術・教育支援の経験を活かし、 みなさまの 「できるようになりたい」 という声に (それなりには) 応えます。 職歴 : 高校教員 (外国語科) → 求職者支援事業 (コンピュータ) → 現職 趣味 : 読書、旅、バイク、写真撮影 (風景、野鳥、動物ポートレート)、お絵描き、料理、オタマトーン、語学、他 近況 : 県外対応ばかりで、広島に仕事を生み出せるような種まきをしていないことが遺憾です
目 次 01 よい講習とは 02 本題に入る前に 03 『よつばと!』とは 04 『よつばと!』に学ぶ 05 大人の傲慢
よい講習とは、どんな講習ですか?
最低限の時間で、最大限の学習効果を生む講習? 結論は #05 にて
01 よ い 講 習 と は ? 一般的に、よく耳にする、目にする、要求される「よい講習」 • 目的・目標が明確化されている ✓ 何を身に着け、どう活用できるようになるかが冒頭で示されている ✓ セッションの各段階で演習などを挟み、理解度を確認する仕組みがある • 受講者主体の参加型設計 ✓ 講師による一方的な講義ではなく、受講者主体で考える時間が設けられている ✓ 実際の業務シナリオやサンプルデータを基に「手を動かす」時間を確保する ✓ 受講者の成果物に対し、即時コメントや改善提案を行う(=フィードバック) • 講師の性格と能力 (= facilitation ) ✓ 受講者の理解度を確認しつつ、深堀り / 次トピック移行のバランスを取る ✓ 専門用語に対する補足があり、途中で要約や振り返りを挟んでいる ✓ 成功体験を積ませる。 演習を通して進捗を可視化しながら進められている • 学習負荷 ✓ 学習者が有している知識に + 1 くらいの適切な負荷がかけられている
欠けている視点がある気がする
01 よい講習とは? 1. 準備 2. 講習 3. 後援
01 よい講習とは? ステップ 1. 事前準備 教える側の責任(※) 学ぶ側の責任 - ツール導入以前の組織問題を解消 - ゴール設定の共有(明示) - アンケートやヒアリングへの回答 - 自分の業務課題と期待を整理 - 多層的なヒアリング(ニーズの把握) 何が学習等の阻害になっているかを共有 - 講師の選定(性格などのマッチング) - 議題や命題ならびに期待役割の明確化 組織の取り決めに対し(責任をもって) - 自律と成果のバランスを調整する 全力で応える ✓ まずは業務効率化ツール以前の組織問題を解消するところから ✓ 講習を入れたらOKではない。段階を踏んだ到達目標を設定して最後のひと押しに講習 ✓ 講習の目的と自分たちの立ち位置を示すことで全員のスタートラインを揃える (※)講師だけでなく、決定権のある人も含める
01 よい講習とは? 1. 準備 2. 講習 3. 後援
01 ステップ 2. 講習 よい講習とは? 教える側の責任(※) 学ぶ側の責任 - 双方向的な講習を設計 - 演習や成果物のフィードバック - 積極的な発言・共有 - 疑問点・気づきを自らアウトプット - 発言機会を平準化し、関係を築く - 娯楽的・知的な「おもしろい」の提供 - 異なる立場へのリスペクトを抱く - 様々な事柄に興味を持つよう振る舞う - 進行管理とリアルタイム調整 - 習熟度や理解度に応じたペース配分 - 然るべき時に「声」を届ける → わからない、説明が欲しい、等 ✓ 全員が意見を出しやすい場を作る ➢ 例:みんなの勉強になるから教えて / 皆さんは業務改善チームです(暗示) ✓ 受動的に聞くのではなく、積極的にアウトプットして異なる視点を吸収 (※)講師だけでなく、決定権のある人も含める
01 よい講習とは? 1. 準備 2. 講習 3. 後援
01 よい講習とは? ステップ 3. フォローアップ 教える側の責任(※) 学ぶ側の責任 - 次期講習に向けた反省会 - 受講者アンケート作成と回収 自分以外の市民開発者が育つことで、自 分が助けられるという意識を持って回答 - 継続コミュニティの立ち上げと運営 - 月に何度か市民開発者の相談会を行う コミュニティでの質問と、情報の共有 - 成果発表会の企画と運営 - ポジティブなフィードバックを行う - 自身を「事例」として実践報告を行う - できたことにも目を向けて成果を共有 ✓ いざ「自分で作ろう」という時が最も大変。継続的な対話にて市民開発者を支える ✓ 実践と共有を通じて「学習」を定着化させ、講習外でも学びを深める責任を担う (※)講師だけでなく、決定権のある人も含める
みんなで作り上げるもの 参考:システム再考 – DX 停滞の原因を探る – kuro.
なぜ上手く行かない? まだ何かある気がする
主に受講者への要求水準と期待が高い傾向
02 本題に入る前に 2025 年 07 月 05 日(土)のお話 ✓ 友人と、その息子たちを連れて宮島水族館まで ✓ 息子たち、水族館そっちのけでカニに夢中 → ✓ 大人の社会通念と言葉が通じない ✓ なんで? どうして? これは何? の応酬 ✓ あれ? この状況って前にどこかで…? 撮影者 kuro..(※親に許可を得て掲載)
03 『よつばと!』とは 概要と作品の魅力 ✓ 全 16 巻(2025年07月時点) ✓ 出会った「初めて」に何でも全力で立ち向かう ✓ 知らないことを「楽しい」に変える天才5歳児 ✓ 大人たちは、よつばの「わからない」に対して、 怒らず、笑わず、ちゃんと向き合います © あずまきよひこ, KADOKAWA(電撃コミックス)
03 『よつばと!』とは よつばと!から学べることは多い ✓ 日常の中の「発見」や「失敗」を温かく見守る 大人たちの姿は、学ぶ人への接し方を教えてくれ ます ⇔ 学ぶ人が持つべき意識も教えてもらえます © あずまきよひこ, KADOKAWA(電撃コミックス)
04 『よつばと!』に学ぶ シーン例 講習対応時に活かす よつばの知らない言葉を話す 根気よく、分かることばで話す。実際に見せて比較させるなども検討 命に関わること以外の行動を 制限せず、また、怒らない 操作ミスや勘違いにイライラせず、発見として一緒に喜ぶ よつばの喜ぶ瞬間は大人も嬉し そうな描写がある 受講者の「できた!」に(オーバーリアクションで)共感する 大人主導で色々な経験をさせる 手綱を持って「とりあえずやってみよう」を演出する 「やんだ」と「よつば」の関係 一線は画すものの、親しみやすさも意識する
05 大 人 の 傲 慢 最近の自分が失っていた視点、失敗談、再確認 • 大人でも知らないことは知らない ✓ 社会的地位も上場企業勤務も無関係。未知領域では皆「よつば」 ✓ 自分も知らないことだらけ。自身を棚に上げて他責思考となっていないか • 想像力が欠如していたのは自分の方だったこと ✓ 作りたいもの、改善したいことがあるなら応用できるだろう…は、思い込み ✓ 相手は大人で理解力もあるから大丈夫…も、思い込み。語彙を選ぶ • DX 担当者の気持ち(=焦り)を汲み取れなかったこと ✓ すぐに習得できないのが分かっていた一方で「詰め込み過ぎた講習」を提供 ✓ 互いの「なんとかしたい」という欲求が「方針のブレ」に繋がってしまった • 学ぶ側に多くを求め過ぎていたこと ✓ 生活の知恵は、余裕のある場所で生まれ、共有される (= school の語源) ✓ 説明はできても「学び取らせる」という意味ではモノを理解させられない ✓ 自分が好奇心を刺激できる講習を提供できていないことに問題がある
成果を焦らないのは「教える側」も同じ (※)講師だけでなく、決定権のある人も含める 参考:創造的怠惰の必要性 - kuro.
言いたくなる時もあるけど 学ぶ人を信じてあげられていますか?
アントン・チェーホフ Антон Павлович Чехов / Anton Pavlovich Chekhov 作家、劇作家、医師 (1860~1904 - 享年44歳) 国籍 : ロシア Кто виноват? : Who Was To Blame? 画像:Wikipedia より引用 飼っている子猫にネズミを捕ることを教え込もうとしたおじさんは、 猫のいる部屋に一匹のネズミを連れてきました。 しかし、子猫の狩猟本能はまだ発達していなかったので、ネズミには目もくれませんでした。 そこで、おじさんは子猫をひっぱたきました。来る日も来る日も、同じ過程が繰り返されました。 とうとう、おじさんは、この猫はバカ猫で、ものを教え込むことはてんでできない、と思い込ん でしまいました。 子猫は、大きくなったとき、他の点では正常なのに、ネズミを見ると怖がって汗をかき、 逃げ出してしまうのでした。 出典:クリーヴランド・エイモリー (編), 青木榮一(訳), 1995,『お気に入りの猫物語:世界の猫文学10選』, Cat Tales, DHC.
人事を尽くして天命を待つ
おわりに 指導力、指導技術、人間性を語る前に、Power Platform の専門家でなければなりません。 技術力がなければ、いくら人柄が良くても、また指導力や技術に才があっても、 Power Platform の導入支援者としてのスタートを切れないと考えています。 しかし、現実の世界はもっとややこしいです。 これらの「~力」の定義は全て「程度の問題」だからです。 技術力には際限がありませんし、指導力も「これでよい」というものではありません。 人間性となると量よりも質の問題になってしまいます。 悩みの相手は底なしの強者です。 今宵、懇親会にて皆さまと共有できますと幸いです。