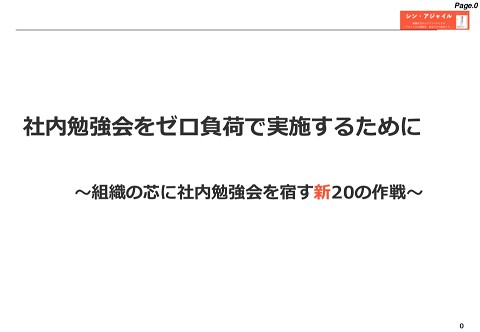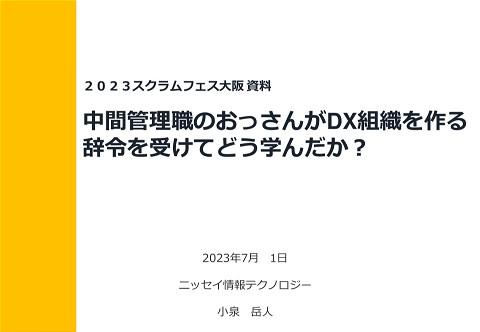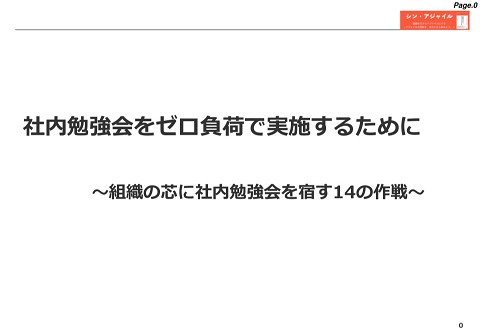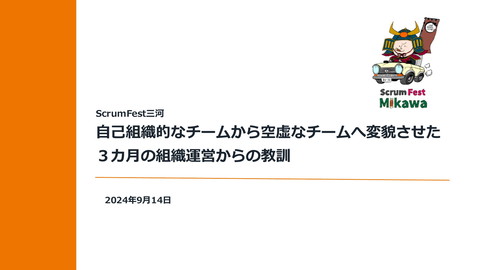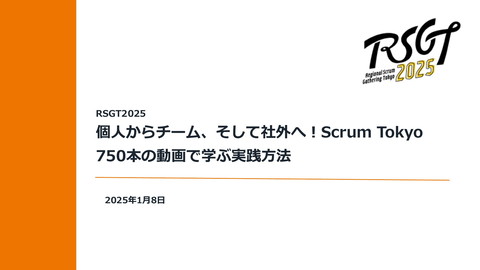エンタープライズアジャイル勉強会_はなさく生命_商品開発案件におけるAgileでの全体事務局運営について
11.7K Views
January 30, 25
スライド概要
2025.1.30のエンタープライズアジャイル勉強会での発表資料になります。
Insurtechラボで作成しているスライドです
関連スライド
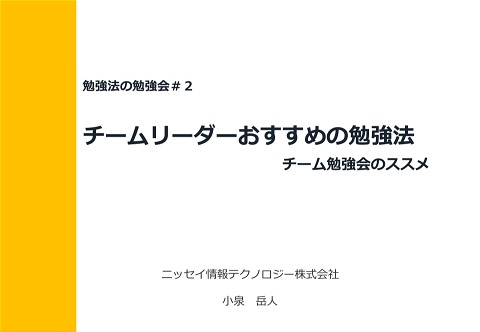
チームリーダーおすすめの勉強法
各ページのテキスト
エンタープライズアジャイル勉強会 はなさく生命_商品開発案件におけるAgileでの 全体事務局運営について 2025年1月30日
目次 0.はじめに 0-1.本日のLearning Outcome 0-2.自己紹介 0-3.会社紹介 1.プロジェクトの紹介 1-1.はなさく変額保険について 1-2.スケジュールと体制 1-3.プロジェクトの特徴 2.事務局について 5分 2-1.事務局の紹介 2-2.事務局立ち上げの経緯 2-3.事務局の活動の概要 3.効果的だった取り組み 3-1.取り組み1:短期間ゴールの設定とモブワークをベースとした共同作業運営 3-2.取り組み2:振り返りとむきなおり 3-3.取り組み3:プロジェクトメンバに向けたマインドチェンジへの働きかけ 4.今後に向けて(方向性と課題) 5分 4-1.今後に向けて(はなさく生命として) ※鎌田さん 4-2.今後に向けて(NITとして) 5.まとめ 2
0.はじめに 3
0-1.本日のラーニングアウトカム Target Audience ・WF(ウォーターフォール)案件を実施している(する)方 ・大規模なプロジェクトを運営する方、サポートする方 Learning Outcome WFの大規模プロジェクトであっても、検査・適応をイテレーティブに回す アジャイルの原則を活用して、プロジェクトをうまく進めていく方法を学べる 4
0-2.自己紹介 小泉 岳人 青柳 大輔 鎌田 慎太郎 ニッセイ情報テクノロジーで保険 システムの開発を20年実施。 直近は、プロダクト開発やアジャ イル開発を推進 趣味:コントラバス ニッセイ情報テクノロジーで保険 システムの開発を15年以上実施。 4年ほど前からアジャイルで偶然 出会い、スクラムマスターとして 日本生命グループの取り組み中心 に真のリーダーを目指している。 2019年に日本生命からはなさく 生命に出向。以来、保険システム の開発業務に従事。 様々な場で見聞きしたサーバント リーダーシップを実践したく、勉 強中。 X:https://x.com/koitake_ 好きな食べ物:カレー 休日の過ごし方:息子とお出かけ 5
0-3.会社紹介 はなさく生命 鎌田さんにて差し替え 6
0-3.会社紹介 ニッセイ情報テクノロジー ◼「保険・共済」「年金」「ヘルスケア」といった社会 保障領域のマーケットに対して、質の高いITサービス やコンサルティングなどを提供しています。私たちの 使命は、ITで“いのちを支える”産業に貢献すること。 社会や生活の基盤となるプラットフォーマーを目指し、 新たな価値の創造に取り組んでいます。 設立 1999年7月 事業内容 保険・金融に関するシステムサービス 医療・介護に関するシステムサービス ネットワークサービス、アウトソーシング、収納代行 従業員数 等 2,535名 (2024年4月1日 現在) 7
1.プロジェクトの紹介 8
1-1.はなさく変額保険について 1/6販売開始 〇 12.11 プレスリリース https://www.life8739.co.jp/pdfview/news/627 〇 はなさく変額保険の特徴 特徴1.もしもの時に備え、安心を確保できます 特徴2.将来の資産形成をサポートします 特徴3.保険料の払込みを免除する特約も付加可能 https://www.life8739.co.jp/product/hengaku/tokuchou 9
1-2.開発スケジュールと体制(スケジュール) 約1年半の長期・大規模開発 2023.7-9 2023.10-12 2024.1-3 -6月:企画フェーズ 2024.4-6 2024.7-9 2024.10-12 2025.1 募集人教育 認可交渉 募文審査 ★商品販売 事務訓練 外部連動テスト 要件定義 領域間テスト 内部設計 外部設計 先行開発 全体テスト PG/製造 領域内テスト 本体開発 要件定義 外部設計 受入テスト 超域内テスト 内部設計 製造 ★システム本番 受入テスト ★システム本番 超域間テスト 全体テスト 10
1-2.開発スケジュールと体制(体制) 最大数200人が関わる 大プロジェクト プロジェクトオーナー 社長 プロジェクトマネジャー IT統括部 はなさく課長 全体 事務局 (NIT,ベンダー) 契約管理 開発 領域 新契約 保険販売資格管理 既契約 代理店業績管理 商品価格/数理 インフラ 制度/特別勘定 顧客管理 販売支援 マイページ 資産運用 代理店ポータル アプリ基盤 コールセンター はなさく NIT ベンダー 10名+α 関連会社/その他領域(7社) 11
1-2.開発スケジュールと体制(体制) 本日話す事務局のスコープは 下記の通り プロジェクトオーナー 社長 本日話す全体事務局のスコープ プロジェクトマネジャー IT統括部 はなさく課長 全体 事務局 (NIT,ベンダー) 契約管理 開発 領域 新契約 保険販売資格管理 既契約 代理店業績管理 商品価格/数理 インフラ 制度/特別勘定 顧客管理 販売支援 マイページ 資産運用 代理店ポータル アプリ基盤 コールセンター はなさく NIT ベンダー 10名+α 関連会社/その他領域(7社) 12
1-3.プロジェクトの特徴(プロジェクトの状況とリスク) プロジェクトの特徴 ① 社長直轄のプロジェクト・・・ビジネス上の重要度や期待も非常に大きい・・・ 失敗できない!という大きなプレッシャー ② 「変額」に関しては知識・経験がなく、勉強しながらの要件定義、設計 ③ 開発期間が長期であるため、マーケットや代理店の動向が変わるリスク 柔軟な計画変更・要件取込が必要 ④ 創業時の開発規模に匹敵する案件規模/これまでの商品開発とは一線を画す複雑さ 事業会社・開発会社のメンバーも増え、創業メンバーと新規メンバーで知識の差がある メンバーの成長+PJ全体で協力がないと、成功できない! 13
1-3.プロジェクトの特徴(プロジェクト目標) プロジェクトの目的は下記の通り ビジネス目標 ①大規模・高難度な案件の着実な開発を 通じ、 「お客様」「代理店」「バック事務」含 めたステークホルダーの期待に応え、「医 療中心の新興保険会社」から「貯蓄性を 含む豊富な商品ラインナップを有する業界 トップランナー」へ進化させる プロジェクト目標 1.サービスインの時期を順守に向けた透明で安定的なプ ロジェクトマネジメント 2.ステークホルダーが安心・満足して本番を迎えられる 3.はなさく、パートナー社とも有識メンバーが育っている 4.会社を超えて心理的安全性の高い場を作り、 誰でも異議や質問ができる ②商品ラインナップを増やしてなお、今まで以 上のスピードでお客様に価値を提供し続 けられる「システム」と「人材」を揃える 行動指針 5.日々変動する可能性のある複雑なビジネス・ システム課題に対し、柔軟かつ機動的に対応 6.開発後に、今後の変額、定額の商品について今までと 同様にスピーディーに開発ができる ⚫ VS24に関わる全てのメン バーに感謝し、一緒に成長 しよう! 心理的安全性 育成・成長 ⚫ 「何を」作るかに加えて、「な ぜ」作るかを語ろう! ビジネス目標の幅 広い共有 ⚫ Bad News First! ~Don’t shoot the messenger~ 品質・スケジュール の順守 14
2.事務局について 15
2-1.事務局の紹介 はなさく生命 NIT 別ベンダの3社で共同事務局を運営(部課長層が中心のチーム) さらに半年後 半年後 立ち上げ初期 メンバー メンバー メンバー はなさく 2名 NIT 5名 別ベンダー 2名 はなさく2名 NIT3名 別ベンダー1名 はなさく2名 NIT3名 別ベンダー1名 +定常タスクチーム(3名) +定常タスクチーム(3名) PO SM PO SM PO SM はなさく 課長 NIT青柳 はなさく 鎌田 NIT青柳 はなさく 鎌田 はなさく鎌田 (NIT青柳) 支援 支援 支援 コーチ コーチ コーチ NIT小泉 (NIT小泉) NIT青柳 16
2-1.事務局の紹介 1週間スプリントで対応を実施(最終、56スプリントまで続く) 月 火 水 木 金 日時状況共有 (デイリースクラム) 9:00-10:00 週間計画 (SPRプランニング) 10:00-11:00 11:00-12:00 13:00-14:00 14:00-15:00 金曜開始で スタート 日時状況共有 (デイリースクラム) モブワーク枠 日時状況共有 (デイリースクラム) 事務局報告 (SPRレビュー) モブワーク枠 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 全体進捗会議 モブワーク枠 ふりかえり (SPRレトロスペクティブ) 17
2-1.事務局の紹介 事務局で実施したタスクの概要は下記の通り ・各種計画書の作成 (プロジェクト憲章、進捗管理計画、課題管理計画、変更管理計画、リスク管理計画、 構成管理計画、成果物ラインナップ、全体体制図、全体SCD、局面SCD、全体テスト計画 ST計画) ・横断ミーティングの設計・推進 (ステアリングコミッティ、全体ウォークスルーMT、感謝の会 フェーズEXITミーティング、会議エントリー運営) ・領域横断資料の作成/とりまとめ (依存関係一覧、過去再発防止に対する確認、進捗や欠陥等のとりまとめ、障害時計画、 QA運営、他案件との整合確認、機動性・保守性の確認、運用マニュアル) ・領域横断課題の推進・トレース ・目的/ゴール達成に向けた運営 18
2-2.事務局立ち上げの経緯 背景 ・失敗出来ないPJT ・横断的な事務局組成の要望 提案の実施 ・チームで乗り越え、チームで学習する仕組みがいる ・協働のメンタリティが必要 ⇒アジャイルでの事務局提案 提案書の文章 “あらたな枠組み=『事務局スクラム』での対応を基本としてはどうか? (開発はWFだが事務局運営のみ、週時のスプリントを基本に対応進める)“ 19
2-2.事務局立ち上げの経緯 最初のアジャイル事務局への反応は悪かった ・WFの案件なのに、 なぜアジャイルがでてくるのか? ・ただでさえ難しい案件なのに、 リスクを増やすことはやりたくない 共同でのワークショップや、計画‐振り返りを繰り返す中で徐々に変容 20
3.効果的だった取組 21
3-1. 短期間ゴールの設定とモブワークをベースとした共同作業運営 やってみたこと ・毎週or隔週毎に事務局として目指すべき状態をゴールとして設定 (日々の点検と振り返りも) ・事務局作業は、基本、全員が集まる「モブワーク枠」で実施 ・Slackでのオープン&非同期コミュニケーションを導入 背景 ・事務局は忙しいメンバの集団(専任メンバがいない) ・自己完結して仕事を進められてしまうメンバであり、出来る人の属人化が進行 目的/狙い ・”できる個人の集団”から脱却したい ・事務局の活動自体の質をカイゼンさせていきたい ・なにより、プロジェクトの舵取りをする組織を一枚岩にしたい 22
3-1. 短期間ゴールの設定とモブワークをベースとした共同作業運営 これまで… 今回は… プロジェクトスケジュール 1週間後のゴールを チームで決める ゴールとスケジュールから やることをチームで抽出 次工程の運営ルール整備 全体会議準備 発生した問題や課題への対処 見積り取り纏め/コスト調整 各メンバがそれぞれワーク (週次で共有) 領域の進捗/ 課題管理 プロジェクト全 体タスクの推進 各工程の 運営ルール整備 どんな状態になってい たらよいか? モブワーク前は 開催準備 全体会議準備 推進担当は設定 チームで集まって モブワーク Slackで チーム協議 (Slackモブ) 発生した問題や 課題への対処 見積り取り纏め/ コスト調整 ステークホルダーへの レポート ワーク目的を達成するため に段取りや必要情報を準備 23
3-2. 振り返りとむきなおり やってみたこと ・プロジェクト目標に対して、2,3ヶ月サイクルでの中間目標を設定 ・サイクルの区切りタイミングにて、むきなおりとタスクの見直し/断捨離 背景 ・プロジェクトは日々変動し、それに合わせていく必要がある ・一方で、事務局が実施するタスクも多く、その消化が目的になりがち ・リリース優先で、プロジェクトで掲げた目標が陳腐化しがち (プロジェクトの終盤や終了後の振り返りで再登場) 目的/狙い ・自分たちの活動を変動するプロジェクトに適応させていきたい ・アウトプットだけではなく、アウトカムを意識/考えて活動したい 24
3-2. 振り返りとむきなおり ➢ 「1-3.プロジェクトの特徴」に 記載のプロジェクト目標 25
3-2. 振り返りとむきなおり 前回目標の 振り返り 次回ターゲットの 目標を設定 設定した目標に対 して、むきなおり New 事務局バックログリスト むきなおり結果も踏まえて事務局の タスクを棚卸し(追加&断捨離) 26
3-2. 振り返りとむきなおり 前回目標の 振り返り ➢ プロジェクト目標に対して設定した前回の中間目標1つ1つに 「うまくいったこと」と「カイゼンしたいこと」を出し合う ➢ 上記から、チームで得た「学び」や「気づき」を共有 ・継続すること、増やしていくこと、新たに始めるべきことは? ・辞めること、減らすことは? 次回ターゲットの 目標を設定 ➢ これまでの中間目標や振り返り結果、プロジェクトの残期間を踏まえて 次なる中間目標をチームで議論して設定 ➢ そもそものプロジェクト目標に対する理解や見解も再度、合わせに行く 設定した目標に対 して、むきなおり New 事務局バックログリスト むきなおり結果も踏まえて事務局の タスクを棚卸し(追加&断捨離) 27
3-2. 振り返りとむきなおり 前回目標の 振り返り 次回ターゲットの 目標を設定 設定した目標に対 して、むきなおり New 事務局バックログリスト ➢ 帆船モデルを使って、「むきなおり」を実施 ➢ 次の中間目標に向けて「追い風はなにか?」「阻害要因は?」「リス むきなおり結果も踏まえて事務局の クは何があるか?」を挙げて、チームでディスカッション 追い風をより多く吹かせるためには? タスクを棚卸し(追加&断捨離) リスクや阻害要因を取り除くには? 28
3-2. 振り返りとむきなおり 前回目標の達成度合 いと過程での良し悪 しを振り返り 振り返りをインプッ トに次回ターゲット の目標を設定 ➢ より価値あるものに集中するため、やるべきことを 追加していくだけではなく、「捨てる」判断も重要 設定した目標に対 して、むきなおり New 事務局バックログリスト むきなおり結果も踏まえて事務局の タスクを棚卸し(追加&断捨離) 29
3-3.プロジェクトメンバに向けたマインドチェンジへの働きかけ やってみたこと ・BNF/DSMを掲げ、継続して発信 ※ BNF:Bad News First / DSM:Don’t Shoot the Messenger ・ビジネス側の状況や狙いを頻繁に発信/共有 ・工程のExit判定など、プロジェクトの区切りタイミングで「感謝の会」を開催 背景 ・関係者が多く、事務局だけで全体の整合/統制をとることが難しい ・開発領域間では、お互いに守りの姿勢が強くなってきていた ・問題や課題を会社内や開発領域内に閉じて奮闘しがち (プロジェクトが検知するタイミングでは既に火の手が上がり始めていることも) 目的/狙い ・問題や課題の早期検知と効率的/効果的に解消へ向かわせたい ・「言った者負け」など、閉鎖的に向かわせる要因は解消させたい ・問題を発信しやすい環境、雰囲気を醸成していきたい 30
3-3.プロジェクトメンバに向けたマインドチェンジへの働きかけ よくある構図(悪い例) 社長 部長 課長 係長 主任 若手職員 うむ 素晴らしい 社長 「実に順調です」 「1つを除き問題ありません」 「懸念すべき事項が1つあります」 「大き目な問題を調査/対応中です」 「やばそうな問題でてます」 「これ絶対やばいです」」 現場担当 問題を報告しても、問題が問題ではなくなってしまう 31
3-3.プロジェクトメンバに向けたマインドチェンジへの働きかけ よくある構図(悪い例) 原因はわかったの? いつまでに対処するの? 影響は?計画は? 再発防止策の報告は いつ? 早めに報告あげても、すぐに詰められる(早く報告すると対応に苦慮する) 32
3-3.プロジェクトメンバに向けたマインドチェンジへの働きかけ 行動指針は事務局が率先して実施する 行動指針 ➢ 感謝を伝える場として「感謝の会」企画 ➢ 普段の活動の場面でも、事務局メンバから 感謝の言葉「ありがとう」を発信 ⚫ VS24に関わる全てのメンバーに感謝し、一緒に成長しよう! ⚫ 「何を」作るかに加えて、「なぜ」作るかを語ろう! ⚫ Bad News First! ~Don’t shoot the messenger~ ➢ ビジネス側の活動や課題状況な どSlackにて定期的に発信 ➢ 透明性を高め、作ることの 目的意識を醸成 ➢ 事務局が率先して検知した事象をBNF ➢ ステアリングコミッティの場も活用した経営層への擦り込み 経営層からのメッセージとして「BNF/DSMが大事」と発信 33
3-3.プロジェクトメンバに向けたマインドチェンジへの働きかけ 感謝の会:各開発領域メンバから相手を問わずに感謝を表明 ➢ 感謝の言葉は短くてもOK ➢ その期間にあった具体的なエピ ソード/場面を添えると効果的 34
3-3.プロジェクトメンバに向けたマインドチェンジへの働きかけ 感謝の会:チーム内でも感謝の会 やるとわかりますが、かなり照れくさいです。が、すごくうれしい気持ちになります。 35
4.今後に向けて 36
4-1.今後に向けて(はなさく生命) 今後の保守案件において、推進していくメンバーがいなくとも、「マインドチェンジ した状態」で「Agileな行動ができる」を関係者が自律的に、継続・カイゼンしてい くようにしたい ・今回は特別な大規模案件という事で、NITにかなり支援してもらい、 体制を構築して推進していった ・今回の成功は、現場の担当者が自律して案件を進めていく第一歩と 感じている ・自分達でもAgileな行動が進んでいくようにしていきたい 37
4-2.今後に向けて(NIT) アジャイルの考え方や仕事の仕方はウォーターフォール案件にも適応は必須 ・目的を設定し、透明性を高め、検査-適応をイテレーティブにチームで 回していく進め方は、非常に有効 ・ただし、アジャイルの考え方や仕事の仕方の適応には、まだまだ壁もある ⇒今回も導入時の反応は良くなかった (「この案件はそもそもリスクが高いので別でやってほしい」) ⇒リスクが高いからこそ、適応が有効であり必要 ・ここで紹介した案件のような事例を広め、もっとアジャイルを気軽に 選択/取り入れられる環境にしていきたい 38