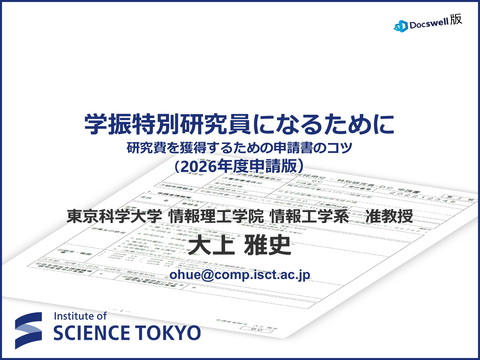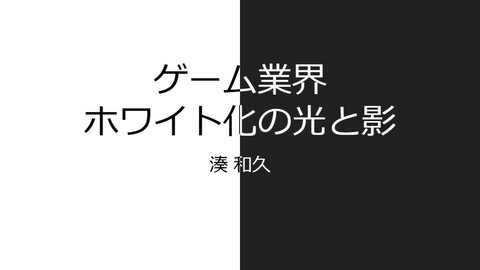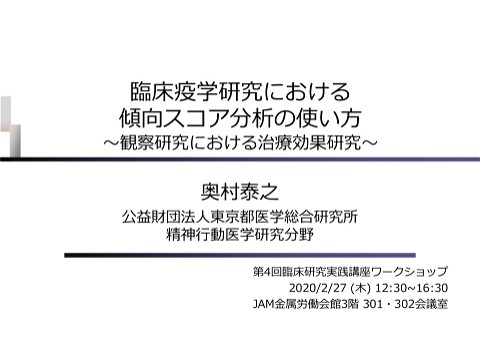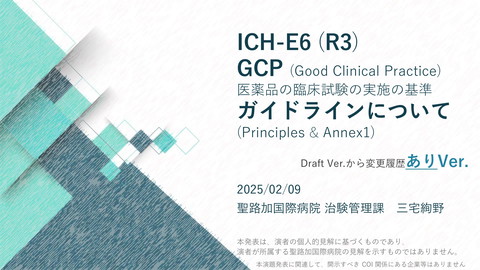サーベイ入門2025|苗村研勉強会2025
63.7K Views
April 20, 25
スライド概要
本資料は、研究のための文献調査(サーベイ)の基本と実践的手法を解説したスライドです。
目次
・サーベイの概要・用語の定義
・文献の使い方(動機・意義の説明、視座としての依拠、新規性の説明、研究方法参考)
・読む文献の見つけ方(芋づる方式、網羅方式、検索方式)
・サーベイの問いの設定
・文献を読む深さ(論文の構造を活用した読解法)
・読みながら書く技法
・文献調査をめぐる不安への対応策
・実践課題:論文100本読みチャレンジ
東京大学苗村研究室の研究室内勉強会のために作成しました。特にHCI分野における学際的な研究に取り組む学生向けに、文献レビューのアプローチが複数あることを知ってもらうことをねらいにしました。「書き手として読む」態度を知り、サーベイを「面倒な仕事」としてではなく「急がば回れ」的な気持ちで前向きに取り組めるよう配慮した実践的な入門資料です。
謝辞
本資料の作成にあたり、文献調査の方法論や実践的アプローチに関する多くの先行研究・資料を参考にさせていただきました。すべての参考文献の著者に感謝申し上げます。
関連スライド
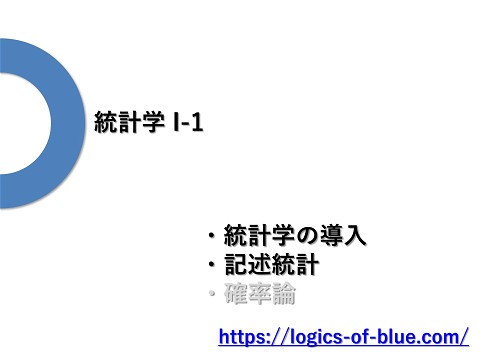
統計学I-1
 Logics of Blue
300.4K
Logics of Blue
300.4K
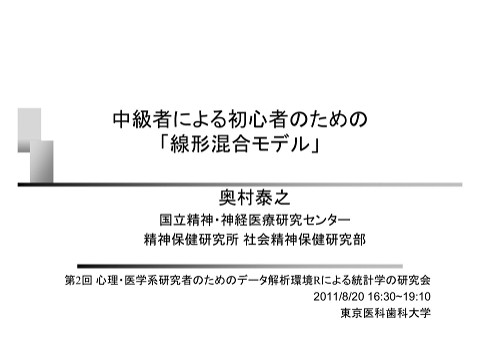
中級者による初心者のための「綿形混合モデル」
 奥村 泰之
222.7K
奥村 泰之
222.7K
各ページのテキスト
サーベイ⼊⾨ 苗村研 勉強会2025 ⽮作 優知
はじめに ● ● サーベイに関する資料は数多くあるが,下記を意識してまとめ直した 苗村研メンバー向けの内容にチューニングする ○ ○ ○ ○ ● HCI (human-computer interaction) という学際的な分野に取り組んでいる ⼯学から少しはみ出した研究をするし,量的研究と質的研究の双⽅を⾏う⼈がいる このため,ある分野に特化した⽅法を参照するとうまく当てはまらないことがある ➡ 「⾃分のテーマに合わせて柔軟に⽅法を変えるには?」というメタな部分にも触れる 参加者を動機づけるようなサーベイ⼊⾨にする ○ ○ ○ サーベイの説明している資料は不安を煽るような書き⽅をすることがある ■ e.g. 「サーベイ不⾜がもたらす罰ゲーム」(伊藤, 2017) 私(⽮作)はサーベイに恐怖⼼や苦⼿意識を持ってしまった経験がある ➡ 初⼼者が安⼼して少しずつ⽂献レビューの⽅法を学ぶことを助ける内容を⼼がける 2
サーベイとは? ● 「先⾏研究などの⽂献を探して読んでまとめる作業」 ● 先⾏研究調査,⽂献レビューなどと呼ばれることも ● 普通の「読む」との違いは,「書き⼿として読む」ということ (曽我, 2014a) ○ 研究の他の作業との時間配分を考慮して限られた時間内で読む ○ ⾃分の研究の⼿本とする(ただし,直接的に書かれていないプロセスも読み解く必要あり) ○ 先⾏研究が他の先⾏研究とどう関係するかを読み解く ● 以上の特徴により,「書き⼿として読む」ことはすごく難しく⼤変に⾒える ● 実際に難しいが,書き⼿としての意識を持てば少しずつ上⼿くなる ● 研究論⽂は書き⼿向けの構造を持っているので,それを理解すると読みやすくなる 3
本勉強会の学習⽬標 ● ⾃分が読みたい⽂献を⾒つけるための様々な⽅法を知る ● 柔軟に⽂献の読みの深さを変えるための⽅法を知る ● ⽂献調査をめぐる不安は解消できることを理解し,⽂献調査を楽しむ勇気を 持つ 今⽇の⽬標ではないこと ● 上記の「深さを変える」「⾒つける」「不安を解消する」を実践できるよう になること ○ 今後くり返し⽂献調査をしていく中でだんだんと出来るようになっていってください 4
書いてあることが難しそう... 英語が苦⼿... 正確に理解できてるか不安... 専⾨外の分野の論⽂が出てきて 全然わからない... 多すぎて読みきれない... どこから読んだらいいか わからない... 調べたいことが漠然としてい てうまく調査できない... やり⽅がわからない... ⽂献調査の不安 なんかよくわかんないけど 不安... 関連研究が⾒つからない... 読むべき論⽂を⾒落としてる 気がする... 思いついたアイデアがすでに やられているのが怖い... 5
本⽇の流れ ● ● ● ● ● ● ● ● ● サーベイの概要‧⽤語の定義 ⽂献の使い⽅ 読む⽂献の⾒つけ⽅ サーベイの問いの設定 ⽂献を読む深さ 読みながら書く 演習 不安へのアンサー 次週までの課題 6
サーベイの⽬的 ● ⽬的はいろいろ考えられる ○ ● あえて「⾃分の論⽂で引⽤するため」という実際的な⽬的から説明してみる ○ ● 研究分野を⼤まかに勉強するため,研究テーマを決めるため,提案⼿法のヒントを得るため ,etc… 「研究分野について⼤まかに知る」「研究テーマを決める」なども書きながら読む(後述) から,最終的な論⽂で引⽤しなくても,引⽤的なことは⾏う その場合,サーベイに含まれる作業は以下の3つになる ○ ⾃分の研究に関連する⽂献を⾒つける ○ ⾒つけた⽂献の内容を理解する ○ 読んだ⽂献を整理して書く 7
⽂献とは? ● 主に書籍や論⽂のことを指す(本勉強会でも主にこれらを想定) ● APA論⽂作成マニュアル (2023) では下記も⽂献に含まれている ○ 新聞記事,データセット,ソフトウェア,動画,⾳声作品,スライド,SNSの投稿,ウェブサ イト,判例,特許,など ○ パーソナルコミュニケーション(電⼦メール,電話での会話,スピーチ,教室での講義,⼿ 紙など)は参照可能な出典が利⽤できない場合に引⽤されることがあるが,本⽂でのみ引⽤ し,⽂献リストには含めない 8
引⽤とは? ● ⾃分の研究に他の研究者がどのように貢献したのかを⽰すことで,読者が⾃ 分の研究の貢献を⽂脈の中で理解できるようにすること (アメリカ⼼理学会 (APA), 2023) ● 「引⽤とは,研究者が各⾃の研究成果(つまり知的財産)を、互いに分割し て利⽤し、リンクを張り合いながら価値を⾼めていく操作」(林 & 名和, 2009) ○ 全部使うのではなく,⼀部を利⽤する ○ Webページのリンクのようなもの ● 「巨⼈の肩の上に⽴つ」by ベルナール (“巨⼈の肩の上,” n.d.) ● 引⽤の具体的な作法は今⽇は扱わない 9
サーベイは「⾯倒な仕事」ではない ● ● 急がば回れ:むしろサーベイは⾯倒を回避する⽅法 ○ 「わたしは『コンポジション理論』〈中略〉を知らなかった.結果として,他⼈によってすで に案出され,その分野の⽂献において論じられてきた考えや⽅法の数々を⾃分で案出する⽻ ⽬になった」(ベッカー, 2012, p. v) ○ オープンソースソフトウェアから類推すると理解しやすいか.公開されているソフトウェアを ⾒つければ,わざわざ⾃分で実装しなくても機能を使える.そしてクレジットにより原作者 をリスペクトする. 今⽇の勉強会では,⽂献調査を学び,他の研究者からたくさん貢献してもら える研究者になるためのステップを踏み出す 10
⽂献の使い⽅ 11
貢献のされ⽅:⽂献をどう使うか? ⼤きく分けて4つある 1. 2. 3. 4. 研究の動機‧意義の説明に使う 研究の視座として依拠する 研究の新規性の説明に使う 研究⽅法‧提案⼿法を参考にする 12
美しい論⽂はU字構造になっている (Ruiz et al., 2021) 1 2 3 1 4 2 3 13
使⽤法1:研究の動機‧意義の説明に使う 1. はじめに 対話サービス(案内、情報提供、おもてなし等)を ⾏う対話ロボットの研究開発がますます盛んになって いる。対話ロボッ トとは、⾔語または⾝体表現(胴体、 頭部、顔、腕など)等を⽤いて適切な社会的⾏動をと り、⼈間とコミュニケーション をとる物理的に具現化 されたエージェントである。これまで、ミュージアム ガイド [1]、旅⾏ガイド [2]、販売員 [3]、受 付嬢 [4] 等の 対話サービス業務を⾏う対話ロボットの開発が取り組 まれている。今後、このような対話ロボットがサービ ス産業の様々な領域において、⼈間の労働をサポート したり、サービス価値を拡張したりすることが期待さ れている [5], [6]。 (中⻄, ⾺場, 倉本, ⼩川, 吉川, & ⽯黒 2024) 2. 天⽂分野における課題 児童‧⽣徒らをはじめとする学習者にとって,⽉が 満ち⽋けするしくみを理解することは困難である(8). 地球や太陽,⽉な どの位置関係,形,⼤きさなどを科学的に理解している児童は少なく(9),⽉が満ち⽋けする 理由 として, ⽉⾷ と の 混合 や 地 球 と ⽉ と の 間 に 障害物があるとする誤概念をもつ児童は多い(10). [...] したがって,以上に述べた天⽂分野における課 題解決の⼀助として,バーチャルな疑似体験を提供しうる VR‧AR 技術の利⽤が挙げられる. (瀬戸崎 & 森田, 2019) 14
使⽤法2:研究の視座として依拠する This paper highlights the materialized co-development of a makerspace, its people, and learning opportunities happening there over a 24-month period. Makerspaces are often physical locations where youth use tangible materials to create personally meaningful projects alongside others (Sheridan et al., 2014). [...] This view of making is grounded in constructionism (Papert, 1993), an approach to learning in which design experiences result in “objects-to-think-with” that are at once material objects and internalized mental structures. Learning happens through cooperation of material environments with embedded ideas (Papert, 1980). この論⽂は、24 ヶ⽉間にわたって⾏われた、メイカースペース、その利⽤者、そしてそこで⽣まれた学習機会の共同開発 の実例を紹介しています。メイカースペースとは、多くの場合、若者がタンジブルな素材を使って、他の⼈と⼀緒に個⼈的 に意義のあるプロジェクトを作るための物理的な場所です(Sheridan et al., 2014)。[...] この「ものづくり」の考え ⽅は、構築主義(Papert, 1993)に根ざしています。構築主義とは、デザイン体験が、物質的な対象であると同時に、内 ⾯化された精神構造である「objects-to-think-with」を⽣み出すという学習アプローチです。学習は、物体に埋め込まれた アイデアと物理的環境の相互作⽤を通じて起こります(Papert, 1980)。 (Keune & Peppler, 2019) 15
使⽤法3:研究の新規性の説明に使う 「凸レンズの働き」の単元では,物体と凸レンズの 距離を変え,実像や虚像ができる条件を 実験によって 調べさせ,像の位置や⼤きさ,像の向きについての規則性(以下,「規則性」と する)を定性的に⾒いださせ る. [...] 規則性の理解は 困難な学習内容の⼀つといえる. ▶ そ こで,中学校学習指導要領解説理科編(2008)では, 凸レンズを通る光の道筋の作図(以下, 「作図」とする) を補助的な⼿段として⽤いることも考えられるとして いる.⽯井‧橋本 (2001)は,規則性を理解するために は,この光の道筋のイメージが重要であるとしている. しかし,実験装置上では光の道筋を⾒ることができな いため,その意味は理解しにくい.光 の道筋をイメー ジさせるため,佐久間ら(2011)はレーザーを⽤いた教材を開発し,規則性の 理解を促すなど⼀定の成果を上 げている.また,⽩⽯‧定本(2012)は CG によって光 の道 筋を視覚化し,実験装置模型の操作に連動して CG が変化する教材を開発している.しかし, 光の道筋を提⽰することが作図や規則性の理解にどのような影響を与えるのかは明らかに なっていない. [...] そこで,本研究では,⽣徒の作図能⼒と規則性の理解を調査し, AR 教材の 評価を⾏う.また,作図能⼒と規則性の理解との関連を明らかにすることを⽬的とする. (小松 et al., 2015) ● ⽂献はアンカーポイント 16
使⽤法4:研究⽅法‧提案⼿法を参考にする 本研究では,HCI分野で成熟しつつある⾃伝的デザイン[17],[18],[30]の⽅法を参考に⽂書-⾳声変換システムのデザインを探 求している.この⼿法では,システム開発者⾃⾝がユーザーとなり,デザインについて詳細かつ微妙なニュアンスを理解する [18].著者らは,⾔語の壁,研究と家事‧育児の両⽴,学際的研究における未知の分野への関与の難しさなど,論⽂を読む上での 課題に直⾯している.こうした課題に直⾯する中で,PaperWaveのデザインを〈真の使⽤〉(genuine usage)[17]を通して探 求した.[31],[32]が⽰したように,このアプローチにより,集中的な使⽤を通じて⽇常⽣活と密接に関連するデザインを探索す ることが可能になる.さらに,最新のLLMを活⽤したPaperWaveの事例は,このアプローチによる〈素早いティンカリング〉 (fast tinkering)によって促進された〈初期のイノベーション〉(early innovation)の好例である[17].この研究における2か⽉ という使⽤期間は⻑期間とは⾔い難いが,集中的な使⽤を伴う⼀⼈称アプローチを積極的に取り⼊れ,さもなければ隠蔽され てしまうデザインプロセスと研究者の影響を記述する[17],[30],[33].著者らのバイアスに対処するため,先⾏研究の助⾔に従 い⾮ユーザー(A5,A6)と⼆次ユーザー(P1-P6)とともにPaperWaveを使⽤した[17].A1とA2がPaperWaveの開発を⾏い,その 間,著者らは毎週ミーティングを開いて改善点や問題点を話し合った. (矢作 et al., 2024) 17
読む⽂献の⾒つけ⽅ 18
サーベイの質を⾼めるには,量が必要 ● 質の⾼いサーベイ(⾃分の研究に役⽴つ⽂献を読む割合が⾼い)を実現する には,量が必要 ○ ● ● (曽我, 2014a) ⼈⽣に無駄なことなどない,とは⾔うけれど,⼀⽣懸命精読したのに全然関係なかった,を 繰り返していると読むべき論⽂を読みきれなかったり、他の作業の時間が⾜りなくなる 量を増やすと結局時間がかかりそうだが,深さとフィルタリングを意識して 量をこなせば質が⾼まる つまり,とにかく浅く幅広く(タイトルを)読む,そして厳選した⽂献を深 く読むことで質を⾼める 19
量と質のイメージ (卒論‧輪講まで の⽬安) ← 私の論⽂ 1 ← じっくり読む 10 ← 本⽂⼀通り読む 50 (引⽤する) ← 存在を認知 500 (マイリストに ⼊っている) 20
何をどの程度読むのか? (曽我, 2014a; 後藤, 2016) 問い 読むべき⽂献をリスト化 (⽇々メンテナンス) 問いに応じて 読む⽂献を選ぶ 読む深さを考えながら 読む 21
読むべき⽂献のリストアップ リストアップの⽅法は3つに⼤別される (曽我, 2014a) ● ● ● 芋づる⽅式 網羅⽅式 検索⽅式 22
芋づる⽅式 (曽我, 2014a) ● 読んだ⽂献が引⽤している⽂献のうち,気になるものをリストに加える ● 基本的にこの⽅式を使う ● 学問の発展のプロセス(先⾏研究の⽂脈)を追うことができる ● 他⽅で,全く別系統の⽂献は⾒落としてしまう 23
芋づる⽅式のためのツール1 PaperDive https://paperdive.app 引⽤⽂献‧被引⽤⽂献をリストアップして,⾃動 でスライド形式にまとめる 背景‧⽬的‧提案‧評価の4項⽬に⾃動まとめ タイトルだけでは,⽂献が⾃分が読みたいか判 断しにくい,初⼼者にも優しい 24
芋づる⽅式のためのツール2 Scholar Alert Digest https://github.com/FlechaMaker/scholar-ale rt-digest-js Google Scholar には論⽂が新しく公開された ことをお知らせしてくれる機能 アラートの重複を解消し、Slackに⾃動投稿 するツール → 研究室内でシェア🤝 → 「済」リアクションで既読チェック Semantic Scholar のアラートなどは 現在未対 応 25
網羅⽅式 ● ● ● 研究者,論⽂誌,学会などターゲットを決めて,そこで発表されてる論⽂す べてに⽬を通す⽅法 (曽我, 2014a) 視野を広げる,サーベイのとっかかりを⾒つけることに役⽴つ HCI領域の学会では研究のビデオプレビュー (30秒などにまとめた動画) があ るため,漠然とした興味を研究の⽂脈に接続するきっかけを得られることも 26
網羅⽅式のためのツール PaperDive https://paper-to-cosence.web.app 学会を⼊⼒すると,同様にまとめてくれるモード が実装予定(乞うご期待) 27
検索⽅式 ● ⽂献データベースにキーワードを⼊⼒して⽂献リストを得る⽅法 (曽我, 2014a) ○ ○ ○ ● Web of Science: 質の⾼い論⽂を厳選して収録したデータベース.多様な絞り込み検索が可 能.質の⾼い研究に絞って知りたい時に使える Google Scholar: 研究論⽂版Google.論⽂らしきものは個⼈がウェブサイトにアップしたも のまで,何でも出てくる.広く探す時には有⽤だが,何でも出てくるので注意が必要 TREE: 読む論⽂が決まってから,それが東⼤経由でアクセスできるか調べる時に便利 芋づる⽅式の⾒落としチェックに使える.研究テーマが固まってキーワード がわかってから使うのがおすすめ (曽我, 2014a) 28
検索⽅式 (AI) ● ● 昨年からの1年間で,超進化しました 少しずつ試して使いこなせるようになると良いかも ○ ● AIを活⽤した検索エンジン ○ ○ ○ ○ ● ただし,研究経験が浅いうちは誤りを⾒抜きにくいことは⾃覚しよう Elicit: 検索して,論⽂同⼠の関係や表形式の整理までやってくれるエージェント Consensus: AIを活⽤した論⽂検索エンジン ResearchRabbit / Connected Papers: 研究論⽂をネットワークとして表⽰できる論⽂検索エ ンジン.⾃分のライブラリに⼊ってる⽂献に強く関連するが⾒落としている⽂献を⾒つけら れる Deep Research系 (ChatGPT / Gemini): 「論⽂を探して」と頼んでおけば,論⽂を探す 情報共有しよう 29
検索⽅式 (⼈間) ● 初⼼者には⼀番オススメの⽅法 ● サーベイには「鶏が先か、卵が先か」問題がある (あさぎはな, 2020) ○ サーベイをしないと網羅する対象も,検索キーワードもわからない ○ しかし網羅する対象や検索キーワード,芋づる⽅式の起点がないとサーベイができない ○ このジレンマを打破してくれるのが,すでにサーベイ経験のある周りの⼈ ● すごく曖昧なクエリでもそれなりの出⼒が得られる ● 芋づる⽅式の最初の1本も先輩や先⽣から教えてもらっても良いだろう 30
サーベイの問いの設定 31
サーベイは⽬的を持って⾏う ● (後藤, 2016) 時間的,内容的な終了条件を決めて調査を⾏う ○ 時間的な終了条件:締切など ○ 内容的な終了条件:問いに答えられたかどうか ● ⽂献を完全に理解する必要はない ● 調査中に気になったことでも,サーベイの問いに関係なければ⼀旦忘れる ○ ⽂献リストに加えておいて,後で読む ○ 気づきなどはメモしておく 32
サーベイの問い ● 調べる前に「何を知りたいのか?」を明確にするのは難しいかもしれない ● されど「問い」が不明確だと何を調べていたのか⾒失い,たくさん勉強した という満⾜感しか残らない ● とりあえずで良いので,知りたいことを疑問⽂の形で書こう ● ○ 調べていくうちにより洗練された問いが思いついたら,いつでも⽅針は変えられる ○ より適切な問いを得たら,前の問いはスパッと中断しても良い 問いを⽴てるときは以下を意識する (後藤, 2016) ○ ⾃分は何を調べたいのか,何がわかればそれが判明するのか ○ 調査を終了する条件は何か?(わかるべきこと,調べる範囲など) 33
問いの例 ● HCIのうちデザインに関する分野で発表されているワークショップに関する研究では,研究 参加者がどのような活動を⾏っているか? ○ ● RT plateを⽤いた空中像光学系のうち,対称ミラー構造を⽤いた光学系はどのように分類 できるか? ○ ● ➡ 調べる範囲を決めて(2023年のDISについて調べるとか),workshopでプログラムを検索してワーク ショップの活動内容をリストアップしたら終了 ➡ 検索⽅式,芋づる⽅式で⽂献を集めたり,マイ⽂献リストからピックアップして読み,光学系の種類をまと めたら終了 光を使ったものづくりを⽀援するシステムの研究にはどんなものがあるか? ○ 漠然としているけど,とりあえずとしてこれでも良い.問いがないよりずっと良い ○ 先輩や先⽣に聞いたり,網羅⽅式‧検索⽅式で⽂献を1つでも⾒つけたら,芋づる⽅式でどんなものがあるか リストアップしていく 34
演習:試しに問いを⽴ててみよう ● 良いサーベイの問いの条件を意識しながら問いを⽴ててみよう ○ ⾃分は何を調べたいのか,何がわかればそれが判明するのか ○ 調査を終了する条件は何か?(わかるべきこと,調べる範囲など) ● とりあえず,今の研究状況で知りたいことを疑問形で⾔語化してみる ● 作業時間:2分間 35
⽂献を読む深さ 36
⽂献は何度も読むのが基本 ● ⽂献は繰り返し読んで少しずつ理解を深めていくもの ● ⽂献は相互に依存しているから,ここにも「鶏が先か、卵が先か」問題が ○ Aを理解するにはBを知っている必要がある.でもBの理解にはAが必要.みたいな ● いろんな⽂献を読んでから戻ってくると,前回読んだ時には読み取れなかったこと が⾒えてくる ● ⽂献は逃げない.適切な管理をすれば. ○ 少しでも読んだ⽂献は確実に保存しておく ○ ⽂献管理ツールの勉強会は別途⾏う ○ とりあえずZoteroがオススメ.使いたい⼈はインストールしてみよう ○ ⾃⼰流でやってみるとツールのありがたみもわかるので,まずは⾃⼰流でやってもよい 37
再掲: 美しい論⽂はU字構造になっている (Ruiz et al., 2021) 38
論⽂の構造:IMRaD (Glasman-Deal, 2023) Introduction, Methods, Results, and Discussion はじめに,⽅法,結果,考察 ● 論⽂の構造の基本 (cf. U字モデル) ● あくまでも型であり,様々な変形がある ● U字モデルやIMRaDは,⾃分が論⽂のどの「深さ」 を読んでいるかを知る⼿掛かりになる ● 適切に書かれた概要 (abstract) もIMRaDの構造を 持っている 39
読む深さの決定⽅法 ● 1本の論⽂を読む前に「とりあえずどのぐらい深く読もうかな?」と考えるぐ らいで良い ● 読んでる途中でも臨機応変に変えて良い.読む必要ないと思ったらすぐ次の ⽂献に移る 40
読む深さの⽬安 タイトル:⽂献リストに加えるか否かの判断 概要:⽂献選びの参考,本⽂を読むか否かの判断 それ以降はサーベイの問いによる.上から下に読まなくても良い. ただし... はじめに と 結論:よく知らない論⽂を読むなら,まず読んで概要(よりは深い概 要)を理解する 関連研究 と 考察:⼟地勘のある分野なら,いきなりここを読めばその論⽂の特徴 (視座や新規性の主張)がわかる ⽅法, 提案⼿法 と 結果:何度も読んでる分野なら,最初からここを読むのもアリ 41
浅い読みの新たな⽅法: PaperWave https://paperwave.app 論⽂をポッドキャストとして聞ける ながら聞きでもいいので,論⽂に触れる機会を増やしてみよう 42
読みながら書く 43
書くことで「使える」情報になったかを確認 ● ● (曽我, 2015) ⾃分の頭の中で操作できることだけが,研究で本当に「使える」情報 ○ たとえば,なにが独⽴変数で,なにが従属変数だったかとか ○ 提案⼿法の新規性はなにで,どのような有効性が確認されたのかとか 読み終わったらなにも⾒ないで⽂献の⾻組みを書き出し,⾃分が「使える」 情報を確認する 44
書くことで⽂献の「ポイント」を⾒つける ● テンプレートを⽤いて⽳埋め形式で論⽂のポイントを抜き出す練習が推奨されている ● ⽮⾕流論⽂の読み⽅ (⽮⾕, 2018) ● 落合先⽣のフォーマット (落合, 2015) ● ただし,読んでる分野とテンプレートがミスマッチだとうまくできないことも... ● テンプレートがないときは...? ○ 先輩や先⽣と相談しながら作る ○ 査読基準をもとに⾃分で作る ■ Contributions to CHI (ACM SIGCHI, n.d.) ■ 情報処理学会論⽂誌「教育とコンピュータ」査読⽅針 (⼀般社団法⼈ 情報処理学会 & 論⽂誌教育とコンピュータ編集委員会, 2014) ■ ⽇本教育⼯学会 論⽂担当者のためのガイドライン (⽇本教育⼯学会 編集委員会, 2020) 45
書くことで先⾏研究の「関係」を理解する ● ● ● ● ● 「種々の研究を1つ1つ配置していくことにより、浮かび上がる地形を地図と して描く」(曽我 2015) ⽐較の軸を⾒つけて○×表を書く 2次元的に研究をマッピングしてみる ミニレビュー論⽂を書いてみて関係を整理する (杉⼭, n.d.) ⽂献のネットワークを可視化して「ギャップ」を⾒つける (杉⼭, n.d.) 46
○×表の例 47
2軸でマッピングする例 48
その他の雑多なアドバイス 49
その他の雑多なアドバイス ● 「⽂献を使うべし.されど⽂献に使われることを許すなかれ.」(ベッカー, 2012, p. 220) ● 英語に⼼配があるならDeepLやGoogle翻訳,LLMを活⽤しましょう ○ ● Immersive Translate ○ ● 内容を理解することが優先 AI Expertに単語帳や⽇英併記のプロンプトを⼊れると,論⽂向きになる 読んで意味がわからないのは書き⼿がわかりやすく書けなかったのも悪い ○ それでもわかる必要があるなら,引⽤している⽂献の説明から意味を推測するのは1つの⼿ 50
不安へのアンサー 51
不安へのアンサー1 ● やり⽅がわからない... なんかよくわからないけど不安... ○ ● 書いてあることが難しそう... 正確に理解できてるか不安... 専⾨外の分野の論 ⽂が出てきて全然わからない... ○ ● まずは軽く読めばOK.厳選した論⽂だけ精読してサーベイ以外の研究時間を確保しよう 関連研究が⾒つからない... 読むべき論⽂を⾒落としてる気がする... ○ ● ⼀度に全部理解しなくていい.⽂献は逃げない.理解する必要が⽣じた時に,必要な深さで 読めればOK! 多すぎて読みきれない... ○ ● 初めから⾃⼒で出来ないのは当たり前.先輩や先⽣に頼ってOK! 深さの調節をすることで,存在を知ってる論⽂の数を増やそう どこから読んだらいいかわからない... ○ 論⽂の構造を意識しつつ,サーベイの問いから読むべきところを判断しよう. 52
不安へのアンサー2 ● 調べたいことが漠然としていてうまく調査できない... ○ ● とりあえず,で良いので問いを⽴てて調べてみよう.調べながら問いを更新して調べたいこと をハッキリさせていければ⼤丈夫. 思いついたアイデアがすでにやられているのが怖い... ○ 53
次週までの課題 論⽂100本読みチャレンジ 今⽇の浅く読むを踏まえて気軽に100本探してみよう 54
テーマ: ⾃分の興味と学術研究をおおまかに接続する ● サーベイの問い「⾃分が直感的に良いと思う研究の共通点は何か?」 a. ● 問いは全員共通.でも「直感的に良い」の基準は⼈それぞれだから違う結果が得られるはず ⼿順 a. b. c. d. 必須:先輩や先⽣,LLMからサーベイの⼿掛かりを教えてもらう(おすすめ⽂献,キーワード等) 芋づる⽅式,網羅⽅式,検索⽅式のどれか,あるいはこれらの組み合わせを⽤いて,「直感的に良 い」と思う⽂献のリストを作成する. i. 基本である芋づる⽅式は必ず⽤いる ii. リスト作成中はタイトル(と必要に応じて概要)だけを⾒る.原則本⽂は読まない(芋づる⽅ 式の根本として参照する⽂献を除く) 共通点を⾒つける視点(次ページ)を参照しながら,⽂献リスト中の⽂献のタイトル‧概要‧キー ワードを読んで共通点を探す.本⽂の精読はしない(流し読みしてもいいし,全く読まなくても良 い) i. 共通点は3個以上⾒つけること a, b, cのサイクルを繰り返しながらスライドをまとめる(読みながら書くを実践してみよう) i. 順番に書いてあるけど,⾏ったり来たりしながらだんだん進むものです ii. Scrapbox, Notion, Obsidianなど⾃分なりのノートの取り⽅がある⼈は,⾃分なりの「書く」 のやり⽅でOKです 55
共通点を⾒つける視点 ● キーワード ○ ● 論⽂誌‧学会 ○ ● よく⾒ると同じ場所で発表されているかも.もしこれが⾒つかったら⾃分が発表する場所の候補にな る 著者 ○ ● 論⽂には⼤抵キーワードがついている.著者が共通点の候補を書いてくれてるのでまずはここを⾒る 同じ著者の論⽂がたくさんリストにあったら,その⼈を⾃分の推し研究者にしよう 硏究法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ どんな⽅法で論⽂で主張すること (claim) を根拠づけているだろうか? システムやツールを提案している?それとも調査を頑張ってる研究か? ユーザースタディをしているか,あるいは物理計測だけなのか? 統制された実験をしているか? アンケート(survey)でデータを得ている? フィールドワーク,エスノグラフィー (ethnography)など現場を丁寧に観察する⽅法を指す単語が 出てくるか? 56
共通点を⾒つける視点(続き) ● 発表年 ○ ● よくみたら2010年〜2015年の研究が多いとかあるかも.研究の世界にも流⾏があるので,似 たような研究が集中的に発表される時期というのがある. 引⽤⽂献 ○ ⽂献リストに⼊っている多くの研究が共通して引⽤している研究というのはあるだろうか?新 たな研究の⽅向性を切り開いた影響⼒のある⽂献は,それに続くフォロワーたちに繰り返し 引⽤される。芋づる⽅式を使ってると気づけることがある 共通点 親⽂献 引⽤ ⼦⽂献 ⼦⽂献 ⼦⽂献 ⼦⽂献 ⼦⽂献 57
注意点 ● この課題は薄く広く読む練習です.個別の論⽂を精読するより触れる⽂献数 を優先しながら取り組んでください ○ ○ ○ ● ● ⽂献の⾔語はなんでも良いです.ただし⽇本語‧英語以外の⽂献を紹介する 時はタイトルの⽇本語訳を提供すること 共通点が⾒つからなくて仲間外れになってしまう論⽂があっても⼤丈夫です ○ ● 概要だけ読むと勘違いしてしまうことがあるのは事実.なので責任を持って⾃分の論⽂で引 ⽤する時は通読する必要がある. しかし今回は練習なので,読みが浅いことによる勘違いがあることを許容しながら,薄く広 く読んでみよう. 浅い読みで⾃分がどう理解したのか記録しておき,あとで精読した時の理解と⽐較すれば, そのズレから浅い読みの精度を上げるための学びの機会にもなる. が,なぜ仲間外れになったのかを考えると⾯⽩いかもしれません できる範囲で無理なく取り組んでください.⾃分の研究テーマ検討に役⽴て るつもりで取り組んでください 58
共通点の包含関係はどちらでも良い 共通点1 共通点2 共通点3 共通点2 共通点1 共通点3 同じ⽂献群に複数の共通点 を⾒出す 異なる共通点を持つ ⽂献群をいくつか⾒つける 59
発表スライドに含める情報 ● サーベイのプロセス(時系列で書く) ○ ● 発⾒した共通点 ○ ● 各共通点を持つ⽂献のリストを⽰してください ふりかえり ○ ○ ○ ○ ○ ● 発表するために,今回はプロセスを記録しながらサーベイすること 以下の問いについて考えたことを発表してください 問1:⾒つけた共通点について感じたことは何か?意外な共通点が浮かび上がったか,それ とも予想通り(⾃分ってこういうの好きそうだなというイメージ通り)の共通点だったか? 問2:薄く広く読むことでわかったことは何か?個別の⽂献を精読するだけではわからない が,今回の課題で多読したことで明らかになった事項として,何があるか? 問3:勉強会で話を聞いただけではあまりわからなかったが,やってみて良さを実感した サーベイのコツはあるか? 問4:その他感想(あれば) 「直感的に良い」と思った⽂献のリスト 60
参考⽂献 ACM SIGCHI. (n.d.). Contributions to CHI. CHI 2024. Retrieved April 18, 2024, from https://chi2024.acm.org/submission-guides/contributions-to-chi/ Glasman-Deal, H. (2023). 理系研究者のためのアカデミックライティング (⼩島正樹 & 甲斐基⽂, Trans.; 改訂版). 東京図書. Ruiz, P., Dragnić-Cindrić, D., Chillmon, C., Roschelle, J., & Hardy, A. (2021). U is a beautiful shape for your journal article. https://www.researchgate.net/publication/291696674_U_is_a_beautiful_shape_for_your_journal_article あさぎはな. (2020, April 21). ”研究のはじめ⽅”の⼿引き(5):先⽣や先輩に質問するときの3つのコツ. https://note.com/mochi_neko/n/nc9f7de6d0b05 アメリカ⼼理学会 (APA). (2023). APA論⽂作成マニュアル (前⽥樹海 & 江藤裕之, Trans.; 第3版). 医学書院. ベッカーハワード‧S. (2012). ベッカー先⽣の論⽂教室 (⼩川芳範, Trans.). 慶應義塾⼤学出版会. ⼀般社団法⼈ 情報処理学会 & 論⽂誌教育とコンピュータ編集委員会. (2014, February 8). 査読⽅針. 情報処理学会論⽂誌:教育とコンピュータ. https://tce.eplang.jp/index.php?%E6%9F%BB%E8%AA%AD%E6%96%B9%E9%87%9D 伊藤奈賀⼦, 河邊弘太郎, & 坂井美⽇. (2023). ピア活動で⾝につけるアカデミック‧スキル⼊⾨. 有斐閣. 伊藤貴之. (2017, June 6). 研究分野をサーベイする. SlideShare. https://www.slideshare.net/iTooooooooooooT/itolab-how-to-survey-2017 巨⼈の肩の上. (n.d.). In 円満字⼆郎 (Ed.), 故事成語を知る辞典. ⼩学館. Retrieved April 18, 2024, from https://kotobank.jp/word/%E5%B7%A8%E4%BA%BA%E3%81%AE%E8%82%A9%E3%81%AE%E4%B8%8A-2236586 61
参考⽂献(つづき) 後藤祐⼀. (2016, May 16). ⽂献調査をどのように⾏うべきか?. SlideShare. https://www.slideshare.net/YuichiGoto1/ss-62062085 ⽇本教育⼯学会 編集委員会. (2020, April 1). 論⽂担当者のためのガイドライン. https://www.jset.gr.jp/thesis/handle-guideline200401.pdf 曽我謙悟. (2014a, September). 先⾏研究を読むとはいかなる営みなのか――⼤学院新⼊⽣への1つのアドバイス(上). 書斎の窓, 635, 32‒36. https://www.yuhikaku.co.jp/static/shosai_mado/html/1409/07.html 曽我謙悟. (2014b, November). 先⾏研究を読むとはいかなる営みなのか――⼤学院新⼊⽣への1つのアドバイス(中). 書斎の窓, 636, 24‒29. https://www.yuhikaku.co.jp/static/shosai_mado/html/1411/05.html 曽我謙悟. (2015, January). 先⾏研究を読むとはいかなる営みなのか――⼤学院新⼊⽣への⼀つのアドバイス(下). 書斎の窓, 637, 35‒38. https://www.yuhikaku.co.jp/static/shosai_mado/html/1501/06.html 杉⼭昂平. (n.d.). 学術研究のためのObsidian利⽤法. Retrieved April 18, 2024, from https://publish.obsidian.md/ksugiyama/%E5%AD%A6%E8%A1%93%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%8 1%AEObsidian%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%B3%95#gap-spotter 林紘⼀郎, & 名和⼩太郎. (2009). 引⽤する極意 引⽤される極意. 勁草書房. ⽮⾕浩司. (2018, May 4). ⽮⾕流論⽂の読み⽅. IIS Lab / 東⼤⽮⾕研究室. https://iis-lab.org/misc/paperreading/ 落合陽⼀. (2015, May 3). 先端技術とメディア表現1 #FTMA15. SlideShare. https://www.slideshare.net/slideshow/1-ftma15/47697911 62
参考⽂献(つづき) 中⻄惇也, ⾺場惇, 倉本到, ⼩川浩平, 吉川雄⼀郎, & ⽯黒浩. (2024). ⼈型が拡張するホテル部屋ロボット対話サービスの価値. ヒューマンインタフェース学会 論⽂誌, 26(4), 351‒362. https://doi.org/10.11184/his.26.4_351 瀬⼾崎典夫, & 森⽥裕介. (2019). 天⽂分野を事例としたバーチャル環境における学習効果. 教育システム情報学会誌, 36(2), 57‒65. https://doi.org/10.14926/jsise.36.57 Keune, A., & Peppler, K. (2019). Materials-to-develop-with: The making of a makerspace. British Journal of Educational Technology, 50(1), 280‒293. https://doi.org/10.1111/bjet.12702 ⼩松祐貴, 桐⽣徹, 中野博幸, & 久保⽥善彦. (2015). 凸レンズが作る像の規則性の理解を促すAR教材の開発と評価. ⽇本教育⼯学会論⽂誌, 39(1), 21‒29. https://doi.org/10.15077/jjet.38137 ⽮作優知, 中條麟太郎, 原⽥悠我, 韓燦教, 杉⼭昂平, & 苗村健. (2024). LLMを⽤いた研究論⽂の対話形式ポッドキャストへの変換システムPaperWaveの開発. 電⼦情報通信学会技術研究報告; 信学技報. HCGシンポジウム2024, ⾦沢. https://ken.ieice.org/ken/paper/gcgz/ 63