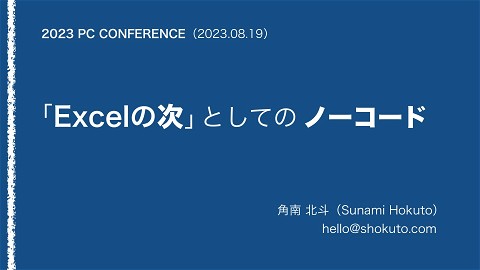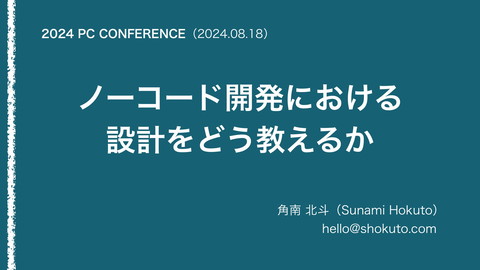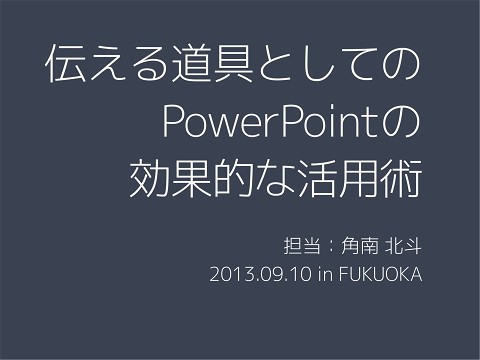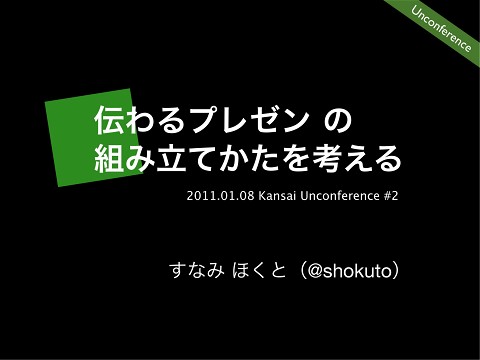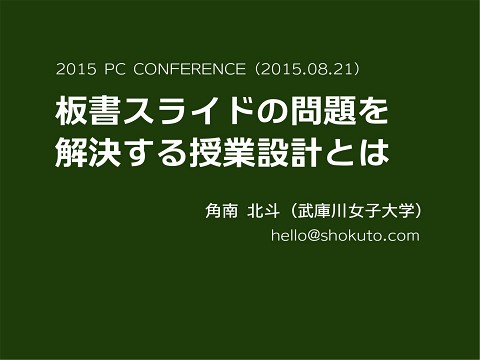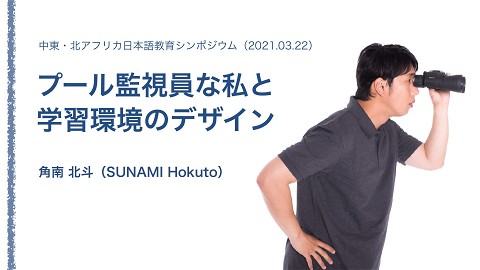プレゼンを適切に自己評価できるようになるための授業デザイン
338 Views
August 23, 25
スライド概要
2025PCカンファレンス(2025.08.23 @鹿児島大学 郡元キャンパス)の分科会口頭発表で、角南北斗が作成・使用したスライドです。自身のプレゼンに対して「自分なりに頑張りました」といった自己満足的な感覚の評価だけに終わらせず、客観的に自身のプレゼンを評価・改善する視点を身につけてもらう、そのきっかけになるような授業を目指した実践報告です。
教育系ウェブデザイナー
関連スライド
各ページのテキスト
2025 PC CONFERENCE(2025.08.23) プレゼンを 適切に自己評価できるように なるための授業デザイン 角南 北斗(Sunami Hokuto) [email protected]
発表者について
発表者について 専門はウェブデザイン・ICT教材開発 ✴ 大学・大学院では日本語教育学を専攻 ✴ 教師から開発者へ軸足をシフトして教育現場を支援 大学では情報系などの授業も非常勤として担当 ✴ O ce・プレゼン・デザイン・知的財産など ffi ✴ 今回はこの立場における授業実践の発表です
Sunami Hokuto Blog: withcomputer.jp Site: sunamihokuto.com X/Twitter: @shokuto
本発表の背景と前提
2025 PC CONFERENCE(2025.08.23) プレゼンを 適切に自己評価できるように なるための授業デザイン 角南 北斗(Sunami Hokuto) [email protected]
プレゼンの定義 相手に伝え、相手を動かすためのコミュニケーション全般 ✴ 2007PCカンファレンスにて「ひとつ下のプレゼン。」として発表 ✴ 村尾(2001)など専門書の多くが同じような定義をしている 日常のあらゆる場面の言動をプレゼンと捉えれば、 プレゼンを学び実践する機会は日常的なものになる。 ✴ プレゼンの機会が増えれば、スキルもそのぶん早く磨かれる、という考え *村尾隆介「ビジネスは、毎日がプレゼン。」同文館出版(2011)
本発表で扱うプレゼンの種類 その分野にそこまで詳しくない一般人に対する、 専門的な解説、話題提供、事業説明といったもの。 ✴ 卒業後など多くの人が(カジュアルなものを含め)経験するはず 場・状況・相手などに応じて情報を取捨選択・加工して、 うまく伝わる&聞く気になるように話すことが重要になる。 ✴ 自分が言いたいこと・正しいこと、をそのまま並べるのでは足りない ✴ 学会発表などの「何より研究の質が重要」なタイプは今回は対象外
本発表で取り上げる授業実践の概要 情報リテラシー系の入門授業 の活動の一部 ✴ プレゼンだけを扱う授業ではなく、O ceアプリケーションのうち 特にPowerPoint部分の学習の一環として ✴ 大学1年生が中心、1クラス40人前後 ✴ 専門分野の知識や、プレゼン自体への意欲は前提としない 学期序盤で概要説明 → 各自準備 → 学期終盤でプレゼン実施 ffi ✴ プレゼンの内容決め・スライド作りを他の学習項目と並行して行う
授業でプレゼンを扱う際には どんな学習項目が考えられるか?
プレゼンに関する一般的な学習要素 1. PowerPointの操作スキル 2. スライドのデザインスキル 3. プレゼンの内容や構成に関するスキル
1. PowerPointの操作スキル 使うだけなら難しくないアプリケーション ✴ Wordに比べてオブジェクトを自由に配置しやすく直感的 ✴ Excelのように「数式を適切に使うための理解」は求められない ファイル共有しないなら適当な作りでも支障がない ✴ 自分がプレゼンしやすいように作れば、自己流の作りでも問題は少ない ✴ ファイルの再利用性も(特に学生のうちは)気にしなくても困らない
2. スライドのデザインスキル デザイン原則と具体例で明確に指針を示しやすい ✴ デザイン=文字・図・レイアウト等の視覚表現 ✴ 高橋・片山(2014)など参考書は質の高いものが存在する ただ、学習者の目と意識を養うのは短期間では難しい ✴ そもそもデザイン自体に強い関心がある受講生は少ないので… ✴ 雑だとか読みにくいだとかで損をしなければOK、ぐらいが現実的 *高橋佑磨・片山なつ「伝わるデザインの基本」技術評論社(2014)
3. プレゼンの内容:何を取り上げるか 受講生に各自の専門的な内容を話してもらうのは難しい ✴ 大学1年生が主体で専門分野の学習はまだまだこれから 授業で扱った(情報系の)内容の延長をするのも難しい ✴ 情報の基礎的な授業なのでそこまで専門的な内容は扱わない ✴ 受講生が関心があるとは限らない →適当に調べたことを並べるだけに プレゼン内容をゼロからじっくり詰める授業ではない ✴ これが卒業研究とかであれば内容に時間を割くのが妥当だが…
3. プレゼンの内容:どんな構成にするか 構成や切り口のアドバイスが抽象的なものになりがち ✴ 分野や話題を限定しないと具体例を提示しにくい 既存の参考書は広告業界を中心としたビジネス分野が多い ✴ アイディアの考え方やコミュニケーション術など本としては面白いが、 広く教科書として指定するとなると使いづらい。
授業でプレゼンを扱う場合の実際 1.PowerPointの操作スキル → 基本的なことだけ 2.スライドのデザインスキル → 基本的なことだけ 3.プレゼンの内容・構成 → 扱いにくいから実質スルー ↓ 結果:プレゼン実践が「形だけ」のものになりがち
本発表で扱うプレゼンの種類 その分野にそこまで詳しくない一般人に対する、 専門的な解説、話題提供、事業説明といったもの。 ✴ 卒業後など多くの人が(カジュアルなものを含め)経験するはず 場・状況・相手などに応じて情報を取捨選択・加工して、 うまく伝わる&聞く気になるように話すことが重要。 ✴ 自分が言いたいこと・正しいこと、をそのまま並べるのでは足りない ✴ 学会発表などの「何より研究の質が重要」なタイプは今回は対象外
授業担当者が目指したいこと テキトーなプレゼンの回数をこなしたところで、 伝えることに関するスキルが自然と高まることはない。 状況に応じた情報の取捨選択・加工のスキルを、 授業で少しでも磨くことはできないか? ✴ 磨くまでの時間はなくても、そこに意識を向けるきっかけにはしたい
適切に自己評価できるようになること が、 なぜプレゼン学習では重要だと考えるのか?
プレゼンの目的と評価の連動が大切 目的:相手に話を理解してもらう+行動してもらう ✴ 説明して承諾を得る、提案に賛成してもらう、手順通り実行してもらうなど。 そのプレゼンで目標が達成されたかどうかが重要。 ✴ 達成してもしなくても、その要因を考えることが学びになる 授業でテキトーにプレゼンを行うだけでは、 プレゼンの実行それ自体が目的になり、評価ができない。 ✴ 「自分なりに頑張ったと思います」という振り返りは次につながらない
プレゼンは自己評価がほとんどすべてだから… プレゼンへの適切な評価コメントをもらうのは困難 ✴ 特に悪い結果の場合、相手は黙って帰るか、途中から聞かずに終わる ✴ 改善点に対する建設的な指摘が得られることは非常にまれ プレゼンの結果からその原因を自分で想像するしかなく、 準備も事前に結果を想像して行うことが基本。 ✴ 相手に事前に聞くことはできない以上、情報収集と想像で構成するしかない
その結果に至った要因を分析する目が必要 想像と実際、理想と結果のギャップはなぜ起こったか ✴ 思うようなパフォーマンスができなかった(準備や確認の不足) ✴ 客に評価される内容でなかった(コンテンツの質の不足) ✴ こちらの意図や説明が理解されなかった / 誤解された(伝え方の問題) ✴ 事前に想定していた客層と違っていた(対象の調査不足・読み違い) ✴ そこは狙うべき目標ではなかった(目標設定のプロセスの誤り) 結果を自分で分析できないと、次に改善もできない
実際に授業ではどう工夫したか
授業設計において工夫したこと プレゼンで具体的に何を扱うかは自由 ✴ 受講生のもともと持っている知識やモチベーションを活かす ただし、プレゼンの形式に一定の条件をつける プレゼンの持ち時間は1分程度 ✴ 準備にかかるコストや、プレゼン当日の実施時間をコンパクトにする ✴ 焦点を絞った内容にする必要性を意識してもらう
プレゼンの条件 何かを勧めるプレゼンであること(2021-2024) ✴ 商品、作品、場所、イベント、行動や考え方など何でもOK ✴ ただし「勧める相手」と「プレゼン後に期待する行動」を明確に定義 何かをアドバイスするプレゼンであること(2025) ✴ やり方、選び方、考え方など何でもOK ✴ ただし「誰」の「どんな困りごと」を扱うのかを明確に定義
なぜこのような条件をつけるのか? プレゼンのターゲットとゴールを定義することで、 情報の取捨選択の基準・観点を明確にする 例:大阪土産には(商品名)がオススメ ✴ ターゲット:大阪駅で新幹線に乗る前に取引先へのお土産を選ぶ人 ✴ ゴール:次のお土産選びの際にその商品を手に取ってもらう
なぜこのような条件をつけるのか? ターゲットとゴールを基準に内容を検討しやすくする ✴ リアリティのあるターゲットを定義できているか ✴ ターゲットに合った説明レベルや表現になっているか ✴ ターゲットのニーズに沿っているか(ニーズ無視の語りを防ぐ) ✴ ゴールは現実的に達成可能そうか(できれば計測可能な指標に) 教師が内容について指摘したり、検討を促したり、 受講生自身が内容を詰めていくのをスムーズにする狙い。
ポイントだけは教師と事前に相談 本格作業前に3点を書いてから教師に相談するルールに ✴ 仮タイトル:長くてもいいから具体的な内容がわかるように ✴ ターゲット:なるべく狭い範囲の人を対象に、リアリティを意識 ✴ ゴール:1分のプレゼンで行動や結果につながる可能性のあるものを 文章に起こすことで個別相談を効率化する ✴ 受講生は書くことで頭の中を整理し、教師への伝達もスムーズになる ✴ 両者が同じ文章を元に話をすることで認識をそろえる
実践してみて、どうだったか
扱うものが自由なことはプラス面が大きい 受講生自身が気に入っているものを扱うことが多く、 それゆえある程度知識があり、紹介の意欲も持ちやすい。 プレゼンを聴く側の関心と近い場合も多いようで、 自然と意欲的に聴く形になりやすい。
ターゲット設定の過程で内容も練られる 最初:サッカーを楽しむためのアドバイス ✴ 内容の取捨選択ができていない / 基準を明確に意識できていない ことが プレゼンのタイトルの付けられ方からうかがえる。 最終:小学生へ飛距離の出るキックのコツを伝授 ✴ 最終的にはターゲットとゴールが明確になりタイトルにも反映された ✴ 教師の「具体的に・範囲を狭く」という指摘で自力で練っていける場合と、 個別対応が必要な場合があるが、受講生の半数はスムーズに進む。
ターゲットの設定作業は難航することも多い そもそもターゲットを設定する意義が理解されにくい ✴ なぜわざわざ相手を限定する必要があるの? みんなに好きになってもらいたいから、対象は『みんな』で!
ターゲットがうまく絞れない理由:知識 自分の扱う内容を客観視するための視点がない ✴ これまでそれを人に説明しようと思ってこなかったから見当もつかない ターゲットに対する解像度が高くない ✴ ライフスタイルや価値観を想像するための材料がないので、 「暇な主婦」や「疲れているビジネスマン」などと定義してしまう。 なんとなく「自分と同じだろう」と考えてしまう
ターゲットがうまく絞れない理由:本気度 自分のプレゼンによって相手を動かすことに 本人がそこまで本気ではないように見える ✴ 必死の営業とは違い、授業では「結果」が出なくてもダメージはないし… 自分の話を全然聞いてもらえない…という経験や、 失敗を痛感するような経験があまりない。 ✴ 発表の授業ならクラスメートは聞くことになっているし、 聞く側も角が立つような言動を授業でわざわざする強い動機がない。
例:俳優やアイドル等の「人」を勧める場合 スペック等の比較項目を明確にしやすい商品と違って、 主観的な評価を並べる形になりやすい。 その分野の初心者のことを想像できない ✴ 「普段は共通理解のある人・コミュニティ内でしか話さないので…」 推しだからといって、広く関心や知識があるとは限らない ✴ 〇〇選手が好き、でもそのスポーツ自体にはあまり関心がない ✴ オタクではないので、一般論として語りたいことはない
例:社会的に「正しいこと」を提案する場合 一般論として反論しづらい「正しい」提案が題材だと、 工夫なく主張を列挙する形になりやすい。 ✴ 「環境にやさしい生き方」は「すべての人が実行すべき」なので、 わざわざターゲットを絞るべきではないですよね? 達成可能なゴールの設定から工夫を促す ✴ 正しいかもしれないけど現実には実行されない、のはなぜか? ✴ プレゼン後に実際にやったかどうかで評価する、としたら何を提案する?
年度ごとの改善
プレゼン内容の骨子を共有するように(2023〜) 文字にした骨子(タイトル・ターゲット・ゴール)を 共有ファイルに書き込んでもらって、全員で作例を共有。 ✴ 具体的にどんな表現・詳細さ・量にすべきかの参考にしてもらう狙い
プレゼン内容の骨子を共有するように(2023〜) 例を多く見ても問題点自体を意識できるとは限らない ✴ 多くの人に同じような指摘することは変わらなかった 説明する際に使える構成の型を知っているかが重要? それは受講生間で個人差が大きい? ✴ 説明コンテンツに多く触れる経験は、中長期的な学びには必要そう
勧める → アドバイスする に形式を変更(2025) アドバイスであれば「相手と困りごとを具体的に定義し、 その解決策を具体的に提案する」という流れを例示しやすい。 ✴ 以前の「好きなものを勧める」よりフォーマットがわかりやすいのか、 内容のチェックをスムーズにパスする受講生は増えた印象。 ✴ 自分の言いたいことよりアドバイスされる側の気持ちで判断する、 という指針も納得しやすいのか、教師側の指摘の頻度は減った。
勧める → アドバイスする に形式を変更(2025) アドバイスという形式自体に持っていけない受講生もいる ✴ そもそもアドバイスになっていない構成を提示して相談にくる ✴ アドバイスの形式にしにくい話題を選んでしまう こだわりが強いテーマだと結論ありきの展開になりがち ✴ 自身の主張を通すために、他を無理やり下げる・非現実的な想定をする 受講生の意向を尊重しながら再考を促すのが難しい
変わらず残る課題:ロールプレイの困難さ
ターゲットになって聞く、というロールプレイ 学期末の実践時、聞き手役にはロールプレイを求める ✴ 話し手はプレゼンの冒頭で想定ターゲットについて説明し、 聞き手はその立場に立って質問やコメントをする、という実施ルール。 構成を練る際のターゲット設定自体は有用だが、 実際の場はターゲットと程遠い相手、という現実。 ✴ これから自炊を始める人たち向けの〜というプレゼンなのに、 自炊に関心がある人が場にいない、といったこと。
ビジネスプレゼンでは意味があることだが… 誰かの立場に立って(=ロールプレイ)して プレゼンを聴き評価するスキルには意味があるものの… ✴ 顧客のニーズや知識は事前に十分には知り得ないので、 顧客がどう評価するかを想像してプレゼンを準備することになる。 それを授業で意識づけ・トレーニングするのは無理がある? ✴ プレゼン時の受講生の質問や事後コメントを見るかぎり、 ロールプレイを意識して振る舞えている人はかなり限られる印象。
本発表のまとめ
まとめ:実践の成果と課題 内容・構成を重視したプレゼン実践の授業において、 テーマに条件をつけて考えを促す形は、一定の効果がある。 ✴ 40人の受講生でも半数程度は自力でそれなりに内容を詰めていける 良い切り口や構成を受講生が見つけられるかどうかは、 受講生個人の経験・技量にかなり依存しており、 教師側がそこをサポートするコンテンツを出せていない。 ✴ 教師側は例を多く示すぐらいしかできていない
発表者としてみなさんに聞きたいこと 内容に時間をかけることが主目的でない授業において、 プレゼンの中身の質を受講生に求めることはできるのか? できるとすれば、具体的にどんな方法があるのか? できない(=そこは追求しない)のであれば、 他にどのようなことを重視して授業設計するのか?
Sunami Hokuto Blog: withcomputer.jp Site: sunamihokuto.com X/Twitter: @shokuto