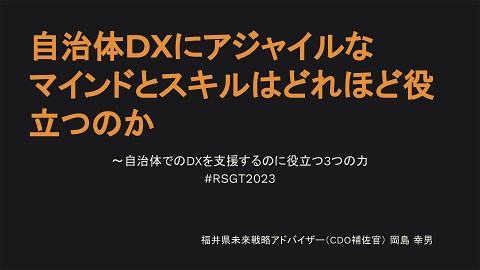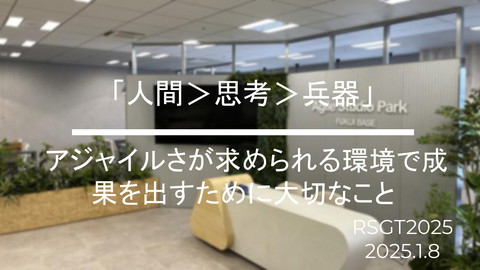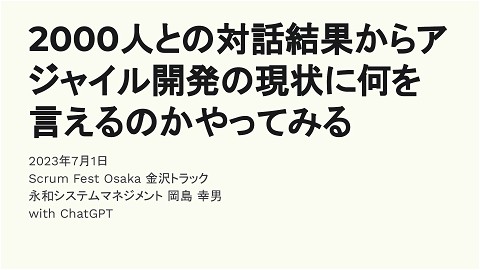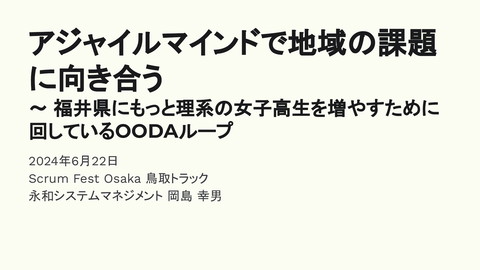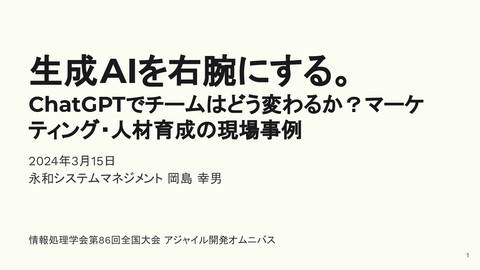機械学習をScrumで組織的に学習する
187 Views
May 03, 25
スライド概要
RSGT2022登壇資料。機械学習の知識を組織的に獲得するために、ScrumとSECIモデルを活用した取り組み事例です。
本業は永和システムマネジメント http://agile-studio.jp のアジャイル実践者。副業で福井県のCDO補佐官としてDX支援やってます。
関連スライド
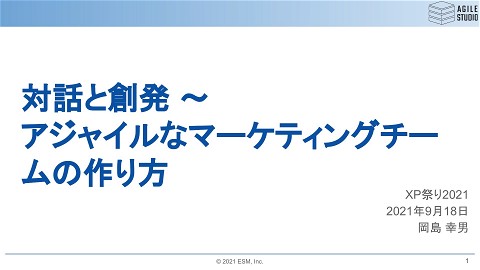
アジャイルなマーケティングチームの作り方
各ページのテキスト
機械学習を Scrumで組織的に学習する #RSGT2022 2022年1月5日 永和システムマネジメント 取締役CTO/Future Design Office 室長 岡島 幸男 © Copyright 2022, ESM, Inc. 1
こんにちは 岡島 幸男 Yukio Okajima © Copyright 2022, ESM, Inc. 2
永和システムマネジメント 福井本社 ● 1980年創業 ● 社員 220名 ● アジャイルでまあまあ知られている 東京支社/神田 沖縄支社 © Copyright 2022, ESM, Inc. 3
永和システムマネジメントの事業 © Copyright 2022, ESM, Inc.
本日の内容 ● 部門横断での技術獲得の進め方 ~ 機械学習の知識を組織に拡大するためにやっていること ○ チーム編 ~ ScrumとSECIモデル ○ 組織編 ~ ダイナミズム理解とインタラクション設計 永和システムマネジメントにおける現在進行形事例 © Copyright 2022, ESM, Inc. 5
背景 © Copyright 2022, ESM, Inc. 6
FDO(未来デザイン室)とは 事業部 メン バー メン バー メンバー(事業部)が得 られること いって きます FDO (Future Design Office) ただいま ・技術的実践知 ・ビジネスアイディア ・課題 最大1年 年間を通じた部門横断プロジェクト。プロダクト開発を通じた技術獲得に専念する © Copyright 2022, ESM, Inc. 7
きっかけ Developers.IO CAFE に大きな驚き ⇒ 「うちでも(近いこと)やりたい!」 © Copyright 2022, ESM, Inc.
FDOのミッション 1. 新しい領域で開発する際の技術力の根拠(開発実績) 2. 技術転換を促進。明日のエースを育成 3. 認知度向上。「あー、〇〇やってる永和さんね」 © Copyright 2022, ESM, Inc. 9
多様性に富むメンバー 一期生( 2020/08 ~ 2021/07) 業務系 Scrum 二期生( 2021/10 ~ ) 業務系 Scrum PO サービス系 Ruby XP 組込み系 WF 所属事業部からの推薦 金融からの リスキル © Copyright 2022, ESM, Inc. Agileネイ ティブ 金融系 大ベテラン
「プロダクト」オーナー? POと名乗る理由 FDO(という部門)は、「メンバーを成長させて返す」サービスを事業部に対し て提供していると見立てられるから。 事業部 メン バー メン バー いって きます ただいま FDO © Copyright 2022, ESM, Inc. 11
機械学習ワールド © Copyright 2022, ESM, Inc. 12
機械学習ワールド 全部マスターすることは不可能。ちょうどよい目標設定・方針が大切 © Copyright 2022, ESM, Inc. 13
手を動かすことで学ぶ 機械学習を仕事にするために 機械学習(AI)スキル モダン開発スキル/スタイル GitHub Docker Python Scrum クラウド…諸々 モダンな技術と開発スタイルで、チームでプロダクトを作りきること © Copyright 2022, ESM, Inc. 14
なぜ機械学習をテーマに選んだか? テーマ決定ワークショップ ● ● ● ● オンライン+オフライン 合計4回実施 POがファシリテート メンバー+技術アドバイザーが参加 ワークショップを繰り返し、自分たちでやりたいことを決めていった © Copyright 2022, ESM, Inc. 15
チーム編 © Copyright 2022, ESM, Inc. 16
基本はScrum ● 常に使用した Scrumの要素 ○ POと開発者ロール ○ スプリント( 1週間) ○ デイリースクラム ○ レトロスペクティブ © Copyright 2022, ESM, Inc. 17
機械学習プロジェクトの進め方 繰り返しが必要で、アジャイル親和性が高い © Copyright 2022, ESM, Inc. 18
一期生のプロダクトゴール 1Q ● ● 実際の案件で機械学習プロジェクトの仕事の進め方を掴む 基本的なライブラリやサービスの使い方を学ぶ 2Q ● ● 応用的な技術に取り組み、実際に動くものを開発する 活動を社内にもっとアピールする 3Q + 4Q ● 機械学習プロジェクトを頭から最後まで通せるノウハウ、実践知を得る ● それらを形式知(ソース・ドキュメント)化し、社内に共有する おおよそ、3か月に一度のリリースとみなし、都度ゴール設定。 © Copyright 2022, ESM, Inc. 19
ゴールの目指し方 ではなく 量的でリニアな向上ではなく質的でスパイラルな向上を目指す © Copyright 2022, ESM, Inc. 20
SECIモデルでふりかえるチーム内での知識拡大 一期生( 2020年8月~2021年7月) ①実践から学 ぶ ②学んだこ とを試す ①で体験したことも踏まえ、 コンペにチャレンジするな ど、知識を表出する 実務することで先行者と共に 学び、暗黙知を取り込む これまで学んだことの定着を 確認する意味でも発信する ④発信する ことで確認 する ③プロダクト として表現す る © Copyright 2022, ESM, Inc. ここまで学んだことを組み合 わせ、自分たちのプロダクト で表現 21
【追記】SECIモデルでふりかえるチーム内での知識拡大 一期生( 2020年8月~2021年7月) ①実践から学 ぶ ②学んだこ とを試す 対話 し色々自分たちで小課 題をやってみる( ARコンシュ ル、コンペ)概念知=自分た ちなりの機械学習の理解 現場に入ってもらい体感して もらう。共感知=機械学習の 難しさ、課題感 ドキュメントを書いて共有した り、外部発信してもらう 行 動。 操作知=機械学習につ いて語れること ④発信する ことで確認 する ③プロダクト として表現す る © Copyright 2022, ESM, Inc. ここまで学んだことや、既存 知識を結合 し、自分たちのプ ロダクトで表現。体系知=機 械学習の技術 22
何を作ったか 自分たちで 作ったろ! © Copyright 2022, ESM, Inc. 23
「育てるAI検温」 活動を社員に広く知ってもらい、社員と 一緒にデータモデルを育てたい、という 想いを込めて。 データ 予測 結果 予測 モデル © Copyright 2022, ESM, Inc. 24
プロダクトのPOとしてこだわったところ バックログの一例 ● 活動コンセプトを表現できるス トーリーとスペック ● 社員に活動を知ってもらうた めのタスク © Copyright 2022, ESM, Inc. 25
機械学習プロジェクトの進め方 繰り返しが必要で、アジャイル親和性が高い © Copyright 2022, ESM, Inc. 26
機械学習プロジェクトとScrumの相性 スプリント単位でモデ ルのアップデートと検 証 実際には日々見直しが行われた © Copyright 2022, ESM, Inc. 27
ひたすら探索しモデルを磨く (楽しすぎて)やりだすときりがないので、ストップをかけるのも重要 © Copyright 2022, ESM, Inc. 28
スプリントゴール重要 ● POと開発者の約束事 ○ このスプリントでは〇〇(例 :前処理)を学ぼう(性能がで なくても、失敗でも学びがあれば良い) ○ 活動の意義に沿ったことを優先しよう ○ 次期メンバーに残せることを優先しよう © Copyright 2022, ESM, Inc. 29
チームの形式知を次期メンバーに残す © Copyright 2022, ESM, Inc. 30
卒業メンバーそれぞれの場所での活躍を喜ぶ 発信を通じてわかる「内面化できた知識」 ● ● ● ● ● ● ● 予測→振り返りを無限に繰り返せてしまうた め、危険… 予測率OO%を達成します!は、危険… 機械学習は開発というより、探索型業務 相関関係ある!予測できた!と早とちりするの は、危険… 「原因分析力」に加え正しい「統計知識」も必要 機械学習の奥深さを体感できた。「前処理8割」 「Garbage In, Garbage Out」ってホントそう コツコツ地道に泥臭く積み重ねていく世界 © Copyright 2022, ESM, Inc.
一期生チームとの関わり方 ● ● ● 対象はPOもよくわからない領域なので一緒に 機械学習を(後追いで)学ぶ ワークショップデザイン(ファシリテーション)も 担当 事実上POとスクラムマスター兼任 「プロダクトの PO」とし て、価値やスペックに がっつり関与 PO © Copyright 2022, ESM, Inc.
二期生の状況 二期生( 2022年1月段階) ②学んだこ との発信共 有 ①理論から学 ぶ 書籍や一期生成果、小さな 開発などを通じ、チームで共 に学習 ①自分たちのやったこと、学 んだことを文書化して社内に 広く共有 © Copyright 2022, ESM, Inc. 33
【追記】二期生の状況 二期生( 2022年1月段階) ②学んだこ との発信共 有 ①理論から学 ぶ 自分たちのやったこと、学ん だことを文書化するだけでな く、頻繁に対話 。後プットは 社内外に共有 書籍や一期生成果、小さな 開発などを通じ、チームの 場 で共に学習 © Copyright 2022, ESM, Inc. 34
学んだことの発信共有 参考図書レビュー 技術ブログ https://fdp-blog.hatenablog.com/ 社内向けニュース © Copyright 2022, ESM, Inc. 35
二期生のプロダクトゴール 現時点では、月に一度のリリースとみなしたゴール設定 © Copyright 2022, ESM, Inc. 36
二期生チームとの関わり方 ● ● ● POとして毎週のレビューに参加、スプ リントゴールの確認 運営(ファシリテーション等含め)は全て チームに任せる スクラムマスターもメンバーが担当 1月からプロダクト(育てる AI検温Ver2)開発 を始める。関わり方も変化していく PO © Copyright 2022, ESM, Inc.
なぜチームとの関わり方を期ごとに変えているのか? 1. チームメンバーの個性は全部違うから 2. 期ごとに役割・位置づけが違うから 年次ごとに、その活動成果を SECIモデルの各象限にマッピングしている © Copyright 2022, ESM, Inc. 38
組織に知識を広めていくために 各年次の活動・成果の相互作用を暗黙知と形式知の変換に見立てることで、先の見通しを良くする 【一期生】 暗黙知を表出 【二期生】 形式知の連 結 三期生? © Copyright 2022, ESM, Inc. 39
【追記】組織に知識を広めていくために 様々な部署から集まった個人が FDOチームで共に学び、さらに組織全体に拡大していく ● ● ● ● ● © Copyright 2022, ESM, Inc. 個人が学んだこと(知っていたこ と)を、チームメンバーと共同化 チームで知識を連結化 年次をまたがっても、Slackで対話 したりPOを通じてエピソードを知る ことで、FDOメンバー全体の知識 が拡大 メンバーが部署に戻っても、その 学び・知識を表出する FDOのアウトプットである教育教 材を通じて、広く社員が機械学習 の知識やリテラシーを内面化でき る 40
【追記】おやっさんとしてのPO ● ● ● © Copyright 2022, ESM, Inc. 年次を超えてストーリーを繋ぐも の 暗黙知の伝搬者 通年活動コンセプトのまとめ役で あり特異点 41
【追記】組織的知識創造のファイブフェイズモデルとの対比 ● ● ● 前提として、そもそも、FDOは何のイノベーションをしていると言えるのか? (集まって機械学習を勉強しているのと何が違うのか) ① 「全社の人材育成の仕組み(事業部から人を預かって育てて返すサー ビス)そのもの」 ②「ESM全体に機械学習リテラシーをもたらす教育教材」 © Copyright 2022, ESM, Inc. ● ● 暗黙知の共有は、 FDOという場と自己 組織的なチームそのもの コンセプトの創造は、代々のメンバー の力を育て、集めながら、 POが練り上 げていると言える ○ 特に二期生とは、このあたりをよ く対話したなぁ。 コンセプトの正当化は、経営との対話 や、社内外への発信を通じた評価獲 得を通じて行っている 原型の構築は、プロダクトやドキュメン ト(教材) 知識移転は、この教材を核として行わ れるだろう。さらに、育成の仕組みとし てのFDOも、原型として全社に知識移 転されることを期待する 42
組織編 © Copyright 2022, ESM, Inc. 43
活動方針の前提目標 ● 漸進的に(オーガニックな成長>急成長) ● 今いる社員で(リスキル>採用) ● 再現性高く(どの技術領域でも>機械学習特化) 永和システムマネジメントのビジネスと社風にマッチした目標 © Copyright 2022, ESM, Inc. 44
失敗から学んだPOの仕事 価値に徹底的にフォーカスできなかった POとしての未熟さにより失敗 #RSGT2020 FDOの室長(PO)として、組織が得られる価値の最大化にフォーカスする © Copyright 2022, ESM, Inc. 45
FDOのビジネス価値の前提となるシステム ここが一番ヤバそう。人が増えて も儲かるとは限らないし。 よし、ここは専門チームを結成し …。 組織図では表現できないダイナミズムを知る © Copyright 2022, ESM, Inc. 46
組織全体の中での位置を見出す コラボレーション型 機械学習特命部隊(仮) マーケット 収益計画 3年でスキルアップし て、ビジネス化する ぞ! 技術獲得 ではなく X-as-a-Service型 新しい技術を活かして 収益向上させるプラン 立てます 事業部 毎年人を育ててお返し します! 人 FDO 事業部 マーケット 収益計画 人+スキル 技術獲得 組織(チーム)間のインタラクションは設計(選択)できる © Copyright 2022, ESM, Inc. 47
より効果的に影響力を発揮する 取締役CTO(リーダーシップ)として ● ● ● ● FDO室長(PO)として このシステムがうまく 回るようにするために は…。 経営方針 全社育成計画 全社評価基準 役員として描いた全体 全社… 像を実現するために 帽子を被り分け … ではなく FDO室長(PO)として ● ● ● 活動成果の位置づけ 教育内容優先度付け 教材プロダクトの PO ● ● ● 活動成果の位置づけ 教育内容優先度付け 教材プロダクトの PO 全体像を見出し理解すれば、 POとしての権限と責任範囲で動くほうが全体に貢献できる © Copyright 2022, ESM, Inc. 48
先行者を巻き込みCoP化する 先行者 悩み相談 FDO 一期生 二期生 相談 個人的に大好き 情報 事業部 報 情 FDOはCoEではない。各所の実践コミュニティと非公式に連携するほうが良い © Copyright 2022, ESM, Inc. 49
サードプレイスとしてのCoP ● ● ● ● © Copyright 2022, ESM, Inc. 社長主催の社内勉強会だが FDOのPOとして企画に関わ らせてもらっている 義務感を減らし、「サードプレ イス感」を出す 新参のFDOメンバーは活動 でぶつかる悩みを相談できる 場 古参メンバーの刺激にもなっ ている 50
まとめ#1 ● あらためて実感した Scrumの使いやすさ ○ マネジメントの役割を POとSMに分離したこと ○ 開発でも学習でも使えること ○ スプリントゴールとプロダクトゴールを通じてチームで意 思疎通できること © Copyright 2022, ESM, Inc. 51
まとめ#2 ● 組織やチームのロードマップとして SECIモデルを使う ● 組織の自己強化ループと、ビジネスモデルや風土にマッチし た組織トポロジーを見出す ● POの権限・責任範囲にこだわって動くほうがうまくいく © Copyright 2022, ESM, Inc. 52
以上 © Copyright 2022, ESM, Inc. 53