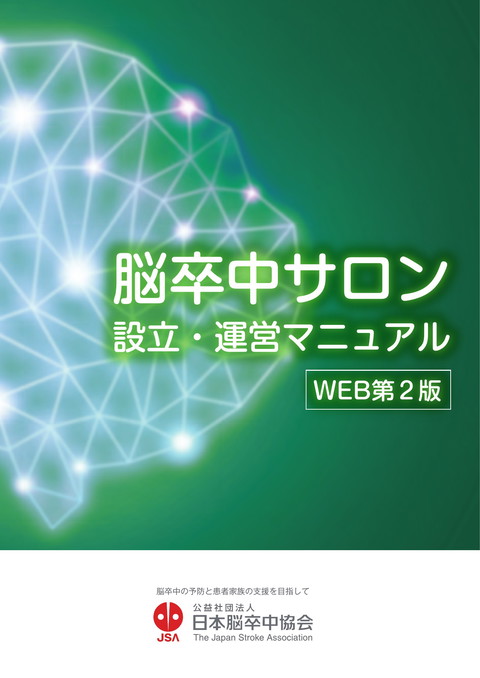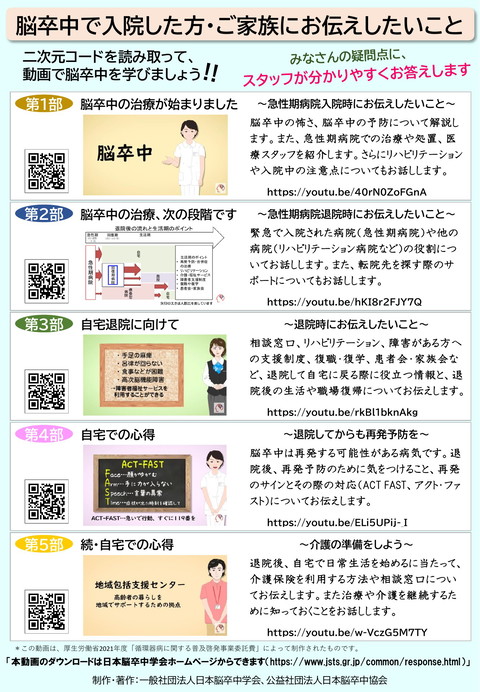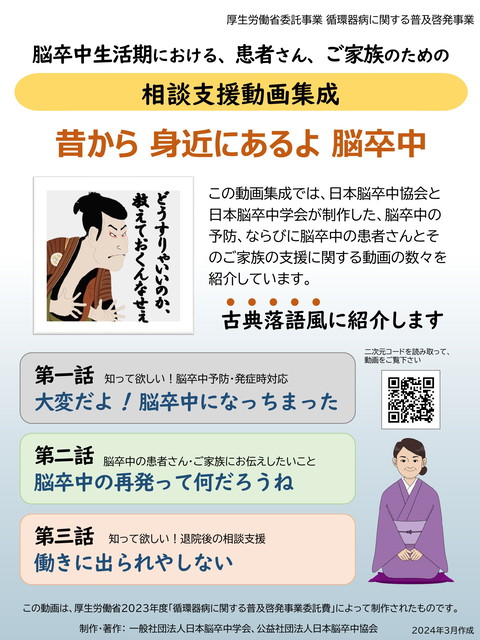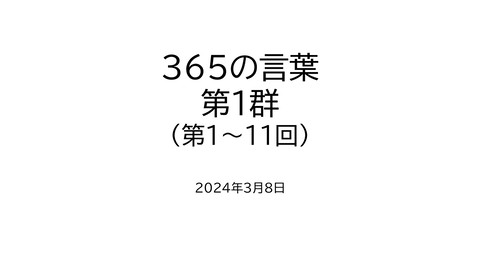365の言葉(第4群)
2K Views
February 28, 25
スライド概要
日本脳卒中協会では、1990年から、脳卒中の患者さんやご家族による「脳卒中体験記‘脳卒中後の私の人生」を募集し、優れた作品を公表してきました。
私たち日本脳卒中協会 患者・家族委員会は、四半世紀に亘り蓄積してきた脳卒中者の体験記の中から「心に響く言葉」を抽出し、「365の言葉」としてまとめました。
制作・著作:公益社団法人日本脳卒中協会
関連スライド
各ページのテキスト
365のことば (第21~24回) 2025年2月28日
人生観・信念 回 作者(敬称略) 21 髙橋 貞之 21小林 清子 21奥野 明 21德久 惠 21仲 葉子 21森 春平 22石川 順一 22松永 裕介 22中馬 幸紀 22 近藤 浩二 22 織田 努 22 田村 和昭 22 大森 育美 22髙野 直也 23 千葉 幸雄 23 千葉 幸雄 23 千葉 幸雄 23千葉幸雄 言葉 落ち込んでいるより、明るく元気に振る舞っている方が周りも気が楽だと思った。 心暖まる優しい親切に今日も心の中が温かくなりました。現在は障害者となって、初めて味わう数々の 経験をしています。 入院中多くの方から励ましのメ—ルや手紙をいただきましたが、「笑顔と感謝、この二つを常に忘れず に!」にという昔の上司からの言葉が一番心に響きました。 私はそのような辛い気持ちでいるお仲間のために、資格を活かしたいと考えています。それが生かされ ている私の使命であり、自己実現です。 人間というものは、よく深く、少し前進できると、何かしら、もう少し頑張れるのかもしれないと思ってし まいます。 気力のある限りつきるまで。 全てのハンディキャップを持つ人のempowermentとなれるようなSW・PSWになる。 辛い思いをしている当事者の、声なき声を聴く活動をしようと思っている。 平凡な日常はすごく尊いものだった。 挑戦を続ければ必ず幸せが来ると信じています。 障害やできなくなったことに向き合いながらこれからの人生を過ごしていこうと思っています。 「誰かのために生きること」が、これからの私にとって意味のある人生だと思う。 自分の人生はone way。 人生は何度でもやり直す事が出来る ある日の手紙に、彼女の川柳がでっかく書かれ、それを読んだ時、まさに正気を取り戻した。「寿命」改め 「受命」と書いてヨーイ・ドン 目が覚めた、とはこのことだ。 親身に耳を傾けてもらうと、穏やかになっている自身を確認できた。救われた。 私は高齢の手のかかる患者だが、一人の人間として対等に見てもらっている、という安心感がうれし かった。人間性の回復の一助になったことは特記したい。 もう少し時を経た後、不幸にして脳疾患で苦悩するご本人やご家族に、役に立てる人間になっていたい、 と思っている。なれるかなあ?なりたいな。なれる、きっと... この体験談を書き終えて、小さいながら 充足感と達成感に包まれている。
人生観・信念 回 作者(敬称略) 23 髙柳 涼杏 23 髙柳 涼杏 23 髙柳 涼杏 23 大野 克久 23 塚本 大輝 23 塚本 大輝 23 松永 知子 23 山村 芳郎 24山口 秀樹 24奥野 美恵子 24濱﨑 力 24 奥野 美恵子 24木村 涼乃 24 延原 宏 24 谷元 摩矢 24 大川 哲夫 24 清水 達雄 言葉 医師は、助かったとしても、小澤ママが仕事に復帰することは絶望的だと判断していたという。小澤ママ本人だけが、絶対 に治るから。また仕事するから。と、疑わず言い続けていた。 「脳卒中になって、ここまで身体を戻すのはほんまにしんどかった。でも、それだけしんどかったからこそ、人は簡単には ぽっくり死ねない。日ごろから元気でいる努力をすることが大切なんやと思い知った。」 絶対に治ることを諦めないで、根気強くリハビリを続けてほしい。最初にそれをどれだけ頑張れるかで、 あなたのこれからの人生は変わるのだと、少しでも多くの人に伝えたいと語る小澤ママ。 どんなに後遺症があっても、生きていける。 その笑顔を見るために、私はどんなことに対しても正直に生きていける。 普通の生活を失って三年がたった。言葉は失った。それでももっと素直な、大事な笑顔に出会った。 私は約束したのだ。もう一度ステージにあがると。それがもし奇跡だとするならば奇跡を起こすのだと。 人は一人では生きられない。皮肉なことに脳卒中がそれを教えてくれた。 これまでのそしてこれからの全ての出会いに感謝しつつ、「青春とは心の若さである 信念と希望にあ ふれ 勇気にみちて日に新たな活動を続けるかぎり 青春は永遠にその人のものである」という卒塾記 念に故松下幸之助氏からいただいた詩を座右の銘として、しっかりと残りの自分の人生を生き抜きたい。 息をのむ絶景と海の幸を堪能しリボーン、リスタートの決意を新たにした。 ただただ、障がい者雇用率の順守のみを目標にするのではなく、もっと中身を精査し本当に障がい者が 働き甲斐のある、社会参加できる企業になっていただきたい。 「ハつらつと、ゲんきで、アかるく、タのしく、マじめに」「梗塞に拘束されず」 「私の周りにはたくさん人がいる。」「人との縁を大切に。」 「感じようとする気持ち」を研ぎ澄ます 私なりに、前には見えなかった障害のある人のことがよく分かり、失ったが故に得たものがあると感じ ている。日常世界の見え方が変わった。 世の中、心の持ちよう一つで明るい未来が開けてきますよ。保証します。 兎に角、生きているだけで大儲けという考えで過ごしている。
家族・当事者(支える・支え合う) 回 作者(敬称略) 21髙橋 貞之 21小池 みさを 21仲 葉子 21田口 ゆう子 22大内 三郎 22石川 彰子 23小川元志 23髙柳 涼杏 23藤澤 麻里子 23藤澤 麻里子 23藤澤 麻里子 23 養田 恵美子(代筆) 23養田 恵美子(代筆) 23髙橋 貞之 24木村 涼乃 言葉 しかし、家族にこれ以上辛い思いはさせられないと、リハビリに専念するために休職をとった。 母は、何も応えられないが、母を相手に世間話をする父は、相槌を打つ相手がいるだけで、幸せな様子だ。 パパが、倒れたおかげで、色々な方々と出会えました。そして、みなさんに、支えられてやってこられました。素敵な出会い にこれまた感謝したい。 もう一度、夫婦のやり直しです。 あの時家族が支えてくれたからこそ、今の幸せがあると思っています。 「私が夫の病気を治そう」 ひとつ確かなことは、父の脳卒中を乗り越えた一家は、35年という歳月を経て血を伝え、楽しく語らえているという事実。 当たり前のようにいつもそばにいる家族の愛に触れ、たくさんの人と出会い、さらに輝く女性になった。 6ヵ月の入院生活を終えた夫の在宅介護が始まった。ほぼ寝たきりの夫の介護の過酷さは想像を遥かに超え、その負担に 押し潰され、追い詰められて絶望的になることも多い。それでも26年も続けられたのは大勢の人のサポートのおかげ、と 心から感謝している。 でも、継続できた要因の大部分を占めるのは「稀に見る明るい脳卒中」とのお墨付きを医師からいただいたほどの夫の明 るさと、変わらない優しさだと思う。 結婚して46年、その大半を介護に費やし、娘達にもそれぞれの人生の大切な節目に、親としての務めを充分果たせなかっ た事に後ろめたい想いはあるが、娘の結婚式でバージンロードを車椅子で進めたのが最高の思い出だ。 毎週家族は心配そうに見舞いに来るが、僕は「大丈夫。」とガラス越しにメモを見せた。妻も娘も孫も嬉しそうに手を振って くれる。なんだか僕が元気を与えているようだった。 家での日常を楽しみたい。僕が妻を支えたい。 父の耳元で「母さんのことは心配するな」と叫ぶと、父は微笑んだように見えた。その数時間後に亡くなった。 家族にこんな姿を見せたら悲しむだろうなと思い、このまま嘆いても何もならないと気付いて、前を向いてリハビリに励ん だ。
受容(過去・障害) 回 作者(敬称略) 言葉 21染谷 英人 私は、まだまだ障害の程度が、軽い方だと思いますが、折角の二度目の人生を大好きな絵を通して、己の心を磨いていき たいと思います。 22奥村 恭子 22髙野 直也 22髙野 直也 22髙野 直也 22髙野 直也 23菊池 久雄 過去でもなく未来でもなく今を大切に、今の自分を認めてあげよう。 「過去に戻れるならどれだけ幸せか」と何度も考えた それならば、28歳迄の自分は捨てて、今の身体・現状でもう一度人生を始めようと思った 失う物以上に得る物が多い。私は、病を患ったからこそ成長出来た 「28歳迄の自分は、もういない」と私は思っている。 これが私の体。これからもこの体と仲良くしていきたい 24奥野 美恵子 大自然の中で自分は極めて小さな存在に過ぎないのに恰も悲劇のヒロインを演じているのではないかと思い直し、くよく よするのは馬鹿らしくなる。
ポジティブ思考(自己奮起・発奮) 回 作者(敬称略) 21田口 ゆう子 21田口 ゆう子 21田口 ゆう子 21髙橋 貞之 21小林 清子 21仲 葉子 21渡邉 千代 22髙野 直也 22中山 恵美代 22松永 裕介 23名和由里 23名和由理 23名和由理 23髙柳 涼杏 23藤澤 麻里子 23髙橋 貞之 24奥野 美恵子 24大部 一美 24木村 涼乃 言葉 先の見えない生活にも穏やかな一瞬があることを知った一日でした。 人間の機能の複雑さは同時に回復への奇跡にもつながっていくことを肌で感じる日々となっていきました。 失ったものの大きさと同時に得たものの大きさを受け取るおもいでした。 もうじたばたしても仕方がない。これからは、できないことを嘆くより、できるようになった自分を褒めて行こうと思う。 普段は無愛想に見えた医師のさりげない一言に心の安らぎを感じました だから、あきらめないで下さい。前を向いて、流れるがまま。ひとり頑張らなくていい。周りが、助けて下さいます。 自身と挑戦 希望がかなえられてこそ痛みや苦しみは 喜びに 知らず知らずのうちに変わっていきました 私は、病を患ったからこそ成長出来たと思っている。 出来なかったらいったん笑っちゃえ! 沈んでいても人生もったいないだけだ この公演は、心身共にかなり負担があったが、「なんとしても現場に復帰したい」という目標があったからこそ達成できた。 発症して2年ほどは、毎日毎日「死にたい」と思いつめていた。しかし、失語症からの回復、気力の回復に成果が出始める と、いつしか発症前より広い世界を見られるようになっていた。 障害を克服しようと努力している者には、手を差し伸べて下さる方たちとの新しい出会いが待ち受けていることも、今だ からこそ実感している。 「それもこれも生きてたからやな。もっと長生きせなあかんわ。病気しておばあちゃんの健康寿命はきっとのびたで。」 私は夫が倒れてから何も手に付かず、夫を案じながらも当時19歳と15歳だった娘達の事や、1年前に新築した家のロー ン、自営業の夫の会社の事等々で、常に思い悩んでいたが、その看護師さんの言葉で私は我に返った。 そんな時「闘病記」と出会った。失礼を承知で言うと、もっと重い症状を抱え、辛い思いをしている人たちに比べれば、私 が抱えている症状の悩みなんて、贅沢に思えて恥ずかしくなった。 悲しみの中で人生を終えてはもったいない。それは生ある者への冒涜だ。楽しい事を思い出し、一層発展させよう。更に 新たに作り出し行動に移そう。 限りなく死へ近づいた私だ。生きて元気に暮らせている今に感謝だ。負い目に乾杯! ヘレン・ケラーの言葉に「悲しみと苦痛はやがて『人のために尽くす心』という美しい花を咲かせる土壌だと考えよう。」 と ある。私もこの経験を活かし、今度は自分が何か人のためにできることを探していこうと思う。
リハビリ(復・改善・代替) 回 作者(敬称略) 言葉 21髙橋 貞之 療法士さんは「歩けた歩けた」と手を叩いて喜んでくれた。それから間もなくして、退院が許可された。 21髙橋 貞之 退院して一年が過ぎたころ「この分なら復職は夢でない」との医者の一言がリハビリに更なる拍車を掛けた。 21野田 賢治 体は自然に動くものではなく、常に動かしているから自然に動かせるもの。リハビリから得た教訓でした。 23千葉幸雄 23朝比奈 順子 23朝比奈 順子 23朝比奈 順子 23朝比奈 順子 リハビリは指導する側と受ける側の双方の信頼の上に成り立つ。その都度のリハビリの意義をわかりやすく説明してい ただき、また、今回は前回より、この部分が良くなった-と、ほめてもらうと、その成功体験が患者にとって大きな自信 となる。 すると主治医が飛んで来て「あなたは今リハビリの病院に行かなくてはならないのだ。頑張れば杖で歩く事ができる」 と断言してくださいました。私は強い助言に感動し「家に帰る時は、必ず歩いて帰る」と決心しました。 時にはリハビリに疲れて大変な時もあります。そんな時「努力は嘘つかない」と言っていた友人のことを思い出し、自分 で自分を励ましたりしました。 助産婦の仲間が横断幕を駐車場に持ってきてくれるというサプライズのバースデープレゼントをしてくれました。今で もその時のことを思いだすと感極まります。本当に私が元気でリハビリできているのは、周りの方々のお陰でした。 杖無しで自分で歩いてみようと思って歩き出したのです。5メートルぐらい歩くことができました。感動です。ネバーギ ブアップ、神様に感謝です。
苦難(感情・偏見) 回 作者(敬称略) 22中山 恵美代 23千葉 幸雄 23朝比奈 順子 23藤澤 麻里子 24高橋 貞之 24奥野 美恵子 24奥野 美恵子 24大部 一美 24大川 哲夫 24大川 哲夫 言葉 「助けてください」 私達は、この言葉をなかなか大きな声で言えない。 強いはずの自分の姿は、どこにもない。時は戻らないのか?逃げ出したい!しかし、不自由すぎて、とにかく何ひと つ、自力では出来ない。 今までのように病院ですと、周りの人は皆障害を持った方達でした。しかし家では違います。また友人も違います。私 は、自分が障害者であることを自覚しなければならないのです。 私達が最も心を痛めたのは、夫が負った後遺症だった。左半身麻痺に加え、見当職障害、高次脳機能障害など幾つも の障害を抱え、まるでモンスター化したような夫の様子に、私達は戸惑っていた。 通勤は戦場と化します。杖をついていても容赦なく体当たりされたり、舌打ちされたこともあります。スマホを見な がら向かって来る人がいると、咄嗟に体をかわすことができない私にとって、恐怖を感じます。 そのざまは何か、おまえは悔しくないのか。発症前後のあまりにも大きな落差を痛感しつつ自分では如何ともし難く 全て悲観的マイナス思考となり、益々落ち込み、負のスパイラルが増幅する。 ただ辛うじて、家事のみをこなしているだけ。これで果たして人間としての生活かと、気持ちが折れる。人からの好意 が身にしみて涙する。 なんで泣けてくるのか理由はしっかり解っている。仕事上のミスなどではなく、負い目が強いために、言いたいこと を飲み込んだ時や、脳卒中前と比べたくないのについ比べてしまい、 情けなくなる時がたくさんあるから。 脳卒中は日本人の高齢者の五人に一人の割合で発病するそうだが まさか自分がその病で 倒れるなどとは全く思い もしなかった。 ショックは大きかった。「残念ながら完璧な元の状態に戻ることはない。 機能回復にも限界がある」と。 結果として 同じであっても言い方があろう。「完全なる回復は難しいが、リハビリの努力次第ではかなりのところが改善される」 と、こう言えば張り合いが出ようものを、言い方が違うと思った。