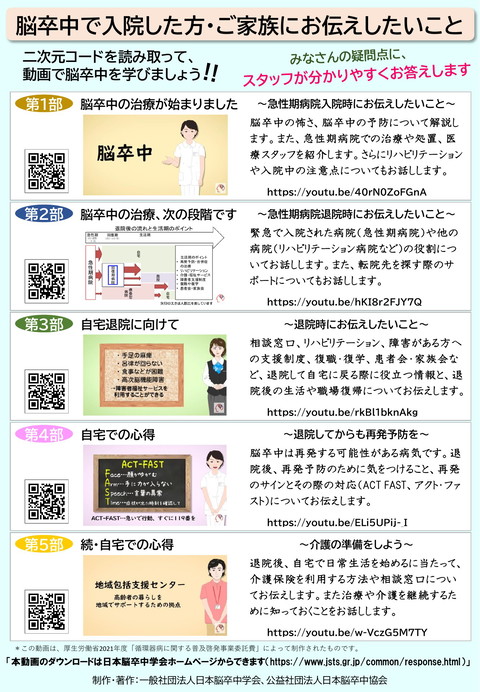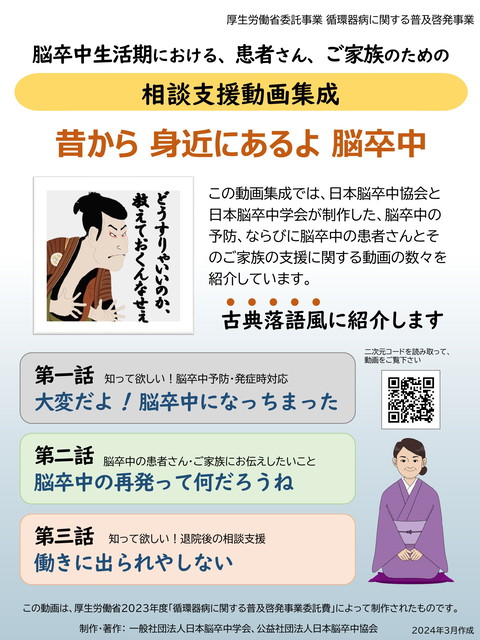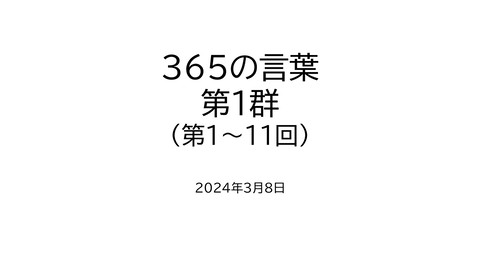「脳卒中サロン」立ち上げ・運営マニュアル(第1部)
6.2K Views
January 25, 25
スライド概要
本マニュアルでは、「脳卒中サロン」の目的やプロジェクトが始まった経緯、モデル地区(岩手県、栃木県、大阪府、兵庫県、熊本県)での活動事例など、「脳卒中サロン」の立ち上げ・運営に参考となる情報を掲載しています。
本マニュアルにより、ピアサポート(脳卒中患者・家族同士の支え合い)の場となる「脳卒中サロン」が全国的に普及し、地域における脳卒中患者・家族のサポート体制がさらに発展することを期待しています。
なお、本プロジェクトは、ファイザー公募型医学教育プロジェクト助成「回復期から慢性期の脳卒中・循環器病患者の健康寿命延伸を目的とした支援体制の構築」による支援を受けています。
関連スライド
各ページのテキスト
脳卒中サロン 設立・運営マニュアル 脳卒中の予防と患者家族の支援を目指して
INDEX は じ め に ………………………………………………………………………………1 第1章 プロジェクトに着手するに至った背景…………………………………2 第2章 脳卒中サロンとは……………………………………………………………4 第3章 脳卒中サロンに関する医療機関アンケート調査…………………………6 第4章 脳卒中サロンに関する患者会アンケート調査…………………………10 第5章 脳卒中サロンの意義………………………………………………………12 第6章 脳卒中サロンの立ち上げ…………………………………………………14 第 7 章 脳卒中サロンの運営マニュアル・開催……………………………………16 第8章 プロジェクトでの実際の活動(事例集)…………………………………19 1)岩手県支部……………………………………………………………20 2)栃木県支部……………………………………………………………21 3)日本脳卒中協会・大阪脳卒中医療連携ネットワーク………………22 4)兵庫県支部……………………………………………………………23 5)熊本県支部……………………………………………………………24 執筆者・編集一覧……………………………………………………………………25
脳卒中サロン設立運営マニュアル はじめに 2006 年にがん対策基本法が成立し、がん診療が大きく変貌した。がん拠点病院では 「がん相談支援センター」 が設 置され、 「がんサロン」 の運営サポートを行っている。 2018 年 12 月 10 日に 「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、 心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本 法(通称:脳卒中・循環器病対策基本法、略称:脳循法)」が国会で成立し、2019 年 12 月 1 日に施行され、脳卒中や 心疾患などの循環器病の診療も大きく変わり始めている。2020 年 10 月 27 日に発表された政府の 「循環器病対策推 進基本計画」 では、個別施策として保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実の中に⑥循環器病に関する適 切な情報提供・相談支援(科学的根拠に基づく正しい情報提供、患者が相談できる総合的な取組)、⑧循環器病の後遺 症を有する者に対する支援(手足の麻痺・失語症・てんかん・高次脳機能障害等の後遺症に対する支援体制整備)が 挙げられている。 2016 年 12 月に 「脳卒中と循環器病克服 5 ヵ年計画 ストップ CVD(脳心血管病)健康長寿を達成するために」 を 日本脳卒中学会と日本循環器学会が関連学会とともに発表した。これをもとに学会は脳卒中センターの認定を 2019 年より開始した。2021 年 3 月に 「第二次 5 ヵ年計画」 を発表し、2022 年4月から一次脳卒中センターのコア施設に 「脳卒中相談窓口」 の設置( 1 名以上の 「脳卒中療養相談士」 が必須)を行うことになった。まずは自施設から直接退院 した患者さんを対象として患者さんの 「困り事」 について相談にのることになった。全てのことを自施設で解決するこ とは実際的に不可能である。 例えば重症脳梗塞で搬送され、機械的血栓回収療法が行われ、劇的に改善し、短期間で退院 となり、 復職したが上手くいかず、 原因として高次脳機能障害が疑われた場合は、 都道府県の高次脳機能障害センター へと結びつける。 自動車運転の相談についてはドライブシュミレーターを持っていて、自動車学校と連携している回復 期リハビリテーション専門病院へ紹介したりすることもある。地域の医療資源を十分に把握して活用する必要がある。 脳卒中患者さんや家族の 「困り事」 への対応を行っている一次脳卒中センターや連携リハビリテーション専門病院 にも 「脳卒中相談窓口」 という看板を掲げて相談支援を行なっていただければと願っている。 2021 年 12 月 27 日に一般社団法人日本脳卒中医療ケア従事者連合( SCPA-Japan)が設立され、「脳卒中相談窓口 マニュアル」( 2022 年 3 月)を参加団体の皆様と一緒に作成でき、大変充実した内容となった。その後、毎年、改訂を 重ねて、時代にマッチした内容にブラッシュアップが行われている。なお 「脳卒中医療ケア従事者連合」 の支部も多く の都道府県でできている。 「脳卒中療養相談士」 の育成も開始された。STROKE 2022 の講習会は WEB あるいはオンデマンドで約 19,000 回以 上の聴講があった。 2 回の講習会にも日本脳卒中医療ケア従事者連合に参加いただいている団体からの発表も行われた。 脳卒中に関して多職種で議論・情報共有する共通のプラットフォームとしての日本脳卒中医療ケア従事者連合の存在 は今後、 さらに重要性を増していくと考えている。 2023 年以降も学会の最終日あるいは翌日に講習会が開催されている。 このような動きの中で日本脳卒中協会はピア・サポートの場である 「脳卒中サロン」 の設置を行うためのモデル事 業 「脳卒中サロンプロジェクト( Stroke salon project:SSP)」 を行うことになった。本プロジェクトは Pfizer Global Medical Grants 「回復期から慢性期の脳卒中・循環器病患者の健康寿命延伸を目的とした支援体制の構築」 に応募し、 「 Supportive project for setting-up and management of peer support for stroke patients」(主任研究者:橋本洋一郎) としてファイザー公募型医学教育プロジェクト助成を受けることができるようになった。 2022 年から4年間(当初2年間の計画であったが2年間延長して計4年間) 、脳卒中患者のピア・サポートの場を 提供するために脳卒中地域連携パスの計画管理病院である脳卒中センターと回復期リハビリテーション病院が連携し てピア・サポートの場である 「脳卒中サロン」 開設・運営のモデル事業を行うこととし、岩手県支部、栃木県支部、兵 庫県支部、 熊本県支部で開始され、 途中で大阪脳卒中医療連携ネットワークも参加することになった。 本マニュアルは、モデル事業を行なっている支部以外でもピア・サポートの場である「脳卒中サロン」を開設でき るようにするために作成することになった。 2022 年度には厚生労働省の 「脳卒中・心臓病等総合支援センター」 の事業が 10 府県の 12 施設で開始されている。 2023 年度には 15 府県 16 施設、2024 年度には 12 都道県 14 施設(現在、計 37 都道府県 42 施設)でモデル事業が 行われている。 このモデル事業が上手くいき、将来的には全ての都道府県に総合支援センターが設置され、地域の脳卒 中相談窓口との緊密な連携が構築され、脳卒中患者さんの 「困り事」 に対応できるシステムを地域の実情に応じて構 築が進んでいる。総合支援センターと日本脳卒中協会の支部が連携して「脳卒中サロン」の設置・運営を担っていた (橋本 洋一郎) だければと期待している。 1
第1章 脳卒中サロン・プロジェクトに 着手するに至った背景
脳卒中サロン設立運営マニュアル 日本脳卒中協会とピアサポート 日本脳卒中協会は脳卒中体験記事業を1998 年から継続的に行っており、体験記の入選作品を公表することによっ て患者体験の共有を図ってきた。 2008 年には「NO! 梗塞アカデミー」というイベントを横浜、大阪、熊本で開催し、 実際に脳卒中患者・家族が小グループに分かれて体験を語り合う場を設けた。それ以外には、脳卒中患者会を協会の web サイトで紹介するなど、 間接的な支援を行ってきた。 脳卒中患者会の減少 近年徐々に活動を休止する脳卒中患者会が増えてきた。2015 年に日本脳卒中協会が把握していた患者会は 52 団 体あったが、2024 年 8 月には 19 団体に減っている。患者会の方々に事情を伺ったところ、新規入会者が少なく、会 員が高齢化して参加者が減少し、活動が低下しているとのことであった。新規入会者が増えない原因として、入院期 間が短縮されて入院中の患者同士のふれあいの機会が減ったことや脳卒中患者の高齢化などが考えられる。 脳卒中患者の入院期間は、1996 年の厚生労働省患者調査では 119.1 日であったが、2020 年の調査では 77.4 日に 短縮している。 特に急性期病院の入院期間は短く、熊本脳卒中連携パスのデータでは急性期病院入院期間の中央値は 14 日であり 1 )、日本脳卒中データバンクによると、急性期脳梗塞患者およびくも膜下出血患者の 4 割、脳出血患者の 2 割が急性期病院から直接自宅に退院する 2 )。これらの患者は患者同士の交流の機会がほとんどない。急性期病院か らリハビリテーション病院に転院する患者については入院期間が長いが(熊本脳卒中連携パスのデータでは回復期 病院の入院期間の中央値は 85 日 1 )) 、1 日の大半をリハビリテーションに費やすため、患者同士の交流の機会はほと んどないと思われる。 このように、現状では、脳卒中患者が入院中に患者同士のつながりをつくることがほとんどで きない。 そして退院後は、 患者会などに参加しないかぎり、ほとんど交流の機会がない。 脳卒中患者の発症時年齢については、日本脳卒中データバンクによると、脳卒中の大半を占める脳梗塞と脳出血の 発症年齢中央値が 2000 年から 2018 年にかけて経年的に高くなっている。2015-2018 年の脳卒中発症時年齢の中 央値は、 男性 72 歳、 女性 79 歳である 3 )。 脳卒中患者・家族の声 日本脳卒中協会が 2019 年に行った脳卒中を経験した患者・家族 567 名を対象にした調査 4 )では、76.4% の回答 者が患者や家族が発信する情報、 患者会などの情報の充実を求めていた。 医療関係者が支援するピアサポートの模索 がん患者を対象とするピアサポート(がんサロン)については、2012 年 10 月のがん拠点病院の報告によると、 「体 験などを語り合う場」の主催者は 54% が病院、34% が患者会などであった 5 )。ピアサポートは患者・家族が主催し なければならない、 というのは固定観念であり、様々な形を取り得ることが分かる。 我々は、脳卒中患者・家族にピアサポートのニーズがあるにもかかわらず、担い手である脳卒中患者会が減少して いく状況を考えると、医療従事者が支援するピアサポートが必要であるという結論に達した。幸い、2021 年にファイ ザー公募型医学教育プロジェクト助成に「脳卒中サロン・プロジェクト」を申請したところ採択され、このプロジェ クトがスタートすることになった。 (中山 博文) 参考文献 1. 本田省二 , 徳永誠 , 渡邊進ら : 脳卒中の病型ごとの急性期から回復期までの実態調査─熊本脳卒中地域連携パスの 9 年間のデータを用い て─ . 脳卒中 2018;40:343-349 2. 日本脳卒中データバンク事務局 . 脳卒中レジストリを用いた我が国の脳卒中診療実態の把握(日本脳卒中データバンク)報告書 2023 年 .https://strokedatabank.ncvc.go.jp/2023/11/29/post-1436/ 日本脳卒中データバンク報告書 2023 年 _20240129.pdf (ncvc.go.jp)( 2024 年 8 月 28 日確認) 3. 豊田一則 , 中井陸運 : 日本脳卒中データバンク―17 万例の臨床情報解析結果―, 国循脳卒中データバンク 2021 編集委員会監修 : 脳卒中 データバンク 2021, 東京 , 中山書店 ,2021,20-27. 4. 日本脳卒中協会 . 患者・家族委員会アンケート調査報告書「脳卒中を経験した当事者(患者・家族)の声」p34. https://www.jsaweb.org/citizen/4019.html 患者・家族委員会アンケート調査報告書「脳卒中を経験した当事者(患者・家族)の声」– 公益社団法 人 日本脳卒中協会(jsa-web.org)(アクセス日 :2024 年 8 月 28 日) 5. 国立がん研究センターがん対策情報センター.がん専門相談員のためのがんサロンの設立と運営のヒント集 2014 年第 1 版 p14. http://asakura-laboratory.jp/wp-content/uploads/2016/02/efd112361c9c41727e48f841d150e5d6.pdf (アクセス日:2024 年 12 月 14 日) 3
第2章 脳卒中サロンとは
脳卒中サロン設立運営マニュアル ピア(peer)とは仲間、対等、同輩のことであり、サポート(support)とは支援、援助を意味しており、ピア・サポー トとは、 「仲間同士の支え合い」あるいは「仲間や同輩が相互に支え合い課題を解決する活動」とされている。 ピアサポートの実例では、 がんについては、 がん対策基本法が成立後にがん拠点病院を中心に「がんサロン」の設置・ 運営が推進されている。認知症については、「認知症施策推進大綱」 などに基づいて行政の補助金などで認知症の人と 家族、地域住民、専門職などの誰もが参加でき、集う場として「認知症カフェ」あるいは「オレンジカフェ」など色々 な名称で推進されてきている。 がん(がんサロン)、認知症(認知症カフェ)、神経難病(疾患別ピア・サロン)などの様々な疾患においてピア・ サポートの重要性、効果は認識されており、脳卒中回復期・生活期においても、ピア・サポートを通じて、患者・家族の 不安感・孤立感を軽減するとともに、 必要な情報を提供し、社会参加を支援することができると報告されている。 ピア・サポートの場である脳卒中患者会は、残念なことに、会員の高齢化と新規入会者の減少により、全国的に減少・ 活動低下傾向にある。 しかしながら、 例えば、 失語症患者会については、 言語聴覚士が積極的にサポートすることによって、 全国的に活動を維持できている。 このことから、脳卒中当事者だけではピア・サポートを全国的に普及することは困難 と思われ、今後は、当事者に加えて、非当事者による運営サポートを加えたピア・サポートの場「脳卒中サロン」を設 置する必要があると思われる。 脳卒中地域連携パスの計画管理病院である脳卒中センターと回復期リハビリテーション専門病院が連携してピア・ サポートの場である「脳卒中サロン」を開設・運営し 、その経験に基づく立ち上げ・運営マニュアルを公表すること によって、全国的に「脳卒中サロン」を広め、地域における脳卒中患者 ・ 家族のサポート体制を向上させる目的で、 「ファイザー Quality Improvement 助成による日本脳卒中協会『脳卒中サロン』プロジェクト」 を 2022 年から 4 年 間行っている。岩手県、栃木県、大阪府、兵庫県、熊本県の 5 箇所で、脳卒中サロン開催のための資材作成、実際の脳卒中 サロンの実施を行って、ノウハウの蓄積を行っている。大阪府については日本脳卒中協会と大阪脳卒中医療連携ネット ワークが協同で、 他の都道府県については日本脳卒中協会の支部が実施している。 「脳卒中サロン」 (ピア・サポート) 、患者会などの脳卒中ピア・サポート成功事例を調査し、加えて既に運営されて いる「がんサロン」の立ち上げ・運営のノウハウを参考にし て 、 「脳卒中サロン」立ち上げ・運営のノウハウを集約する。 「脳卒中サロン」立ち上げ・運営サポートマニュアルを開発し、「脳卒中サロン」スタッフと利用者の評価に基づいて 改良して、全国的に「脳卒中サロン」を広め、 地域における脳卒中患者・家族のサポート体制を向上させることを目 指している。 ピア・サポートを通じて、患者・家族の不安感・孤立感を軽減するとともに、必要な情報を提供し、社会参 加を支援するのが「脳卒中サロン」の役割になる。なお「脳卒中カフェ」などの別の名称が良いという意見もあり、地 域の実情にあった名称で良いと考えている。 (橋本 洋一郎) 5
第3章 脳卒中サロンに関する 医療機関アンケート調査
脳卒中サロン設立運営マニュアル はじめに 2007 年にがん対策基本法が施行され、2024 年現在、第 4 期がん対策推進基本計画まで策定されている。本計画で は「 3. がんとの共生」として相談支援などがあり、その一環として「がんサロン」が展開され 1 )、セルフヘルプ・グ ループとしての機能を有する誰でも参加できる交流の場として運営されている。2 ) 一方、 脳卒中ではがんサロンのような会は一部の地域で行われているものの、広くは展開されていない。2018 年 に「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(通称:脳卒中・ 循環器病対策基本法、略称:脳循法) 」が成立し 3 )、現在「循環器病対策推進基本計画(第 2 期)」に基づいた計画が 策定、 施行されている 4 )。 本計画でも相談支援や情報提供があり、 脳卒中でも「脳卒中サロン」を展開する必要がある。 このような背景から、2022 年における「脳卒中サロン」の状況を把握するため、日本脳卒中協会支部と回復期リ ハビリテーション病棟協会にアンケート調査を行った。内容は、急性期・回復期などの医療施設の類型、脳卒中サロ ンの有無・状況、 患者会の有無、 などである。 本項では、回答を得られた急性期病院 60 施設(日本脳卒中学会認定一次脳卒中センター( primary stroke center:PSC)の大学病院 25 施設、 他の PSC 29 施設、その他急性期病院 6 施設)、回復期・生活期病院 145 施設(回 復期リハビリテーション病院 133 施設、その他の回復期病院 10 施設、維持期・生活期病院 2 施設)の 205 施設の 結果を紹介する。 脳卒中サロン・患者会の状況 脳卒中患者・家族が運営している患者会は、調査現在において二次医療圏の 18% 前後にしか存在しておらず、過 去に存在していた二次医療圏もわずか 3 〜 11% 程度に過ぎなかった。また、脳卒中サロンのようなピアサポートの 場となる会の開催は 9 施設(急性期病院 2 施設、回復期・生活期病院 7 施設)しかなかった。 脳卒中サロン(ピアサポートの場となる会)の運営に脳卒中患者・家族が関与していたのは、急性期病院は 2 施 設とも関わっていたが、回復期・生活期病院では 2 施設( 28.6%)しかなかった。医療従事者の関与は、急性期病院 は脳卒中診療に関わっている医師( 50%) 、社会福祉士( 50%)、脳卒中診療に携わる看護師( 50%)が担っており、 回復期・生活期病院は医師の関わりが 28.6% と少なく、脳卒中リハビリテーション認定看護師が 28.6%、それ以外の 看護師が 57.1%、社会福祉士が 71.4% であった。開催は毎月であり、1 回あたりの患者参加数は急性期病院が 7 名 (中 央値) 、回復期・生活期病院が 4 名、 家族は前者が 2 名、後者が 4 名であった。 脳卒中サロンでは、療養や看護の悩み、体験、情報共有など、患者・家族のサポートが行われていた(急性期病院 100%、回復期・生活期病院 71.4%) 。 医療従事者側の提供内容としては、急性期病院では病気・治療・療養・障害者 手帳や介護保険など社会資源といった治療・療養・費用などに関する説明が多いのに対し、回復期・生活期病院では、 他の患者・家族との交流の場の提供( 85.7%)、体 操やグループリハビリテーションの提供( 42.9%)、心理的サポー ト( 42.9%)に力を入れていた(表 1 ) 。 なお、患者・家族からの質問への回答は急性期、回復期・生活期病院とも対 応していた。 一方、脳卒中サロンを運営するにあたり、急性期病院と回復期病院の協力が望ましいが、急性期病院の 1 施設では 連携施設の社会福祉士が急性期病院開催の脳卒中サロンに参加していたものの、 他の職種の連携はなかった。回復期・ 生活期病院においても、1 施設が連携先の精神保健師福祉士や脳卒中リハビリテーション認定看護師が参加していた が、 ほぼ協力していない状況であった( 71.4%)。 脳卒中サロンを行うにあたり 脳卒中サロンを運営するにあたり必要と考えられている職種を図 1 に示す。急性期病院、回復期・生活期病院とも、 脳卒中診療に関わっている医師・リハビリテーション療法士が最も多かった。また、社会福祉士、脳卒中リハビリテー ション看護認定看護師の協力・増員、社会福祉士も求められていた。この他、 両立支援コーディネーターや病院長の 協力、 診療報酬や行政の補助金も多くの施設で必要と考えられていた。 一方、脳卒中サロンなどを行なっていない施設において、急性期病院の 71.7% は脳卒中サロンの開催が可能と回答 していたが、 回復期・生活期病院は 35.6% と少なかった。 脳卒中サロンを開催している施設では、会の設置・運営で苦労したこととして、時間の確保、患者・家族により困 りごとが異なること、多職種連携の必要性、参加者数確保、といった意見があった(表 2 )。また、脳卒中サロンの開催 が困難であると感じている施設では、人員確保・多職種連携、経営面との両立、運営資金、開催場所、といった問題が 懸念されていた(表 2 ) 。 7
脳卒中サロン設立運営マニュアル おわりに 脳卒中サロンの開催には、 資金や開催場所の確保、 病院の理解、 多職種連携、 といったことが必要であることが伺えた。 しかし、開催することにより、ピアサポートの場が提供でき、患者・家族の社会参加、他の患者・家族の体験から得ら れる日常生活の工夫など、 有益な情報も取得できるため、脳卒中患者・家族支援につながることが期待できる。 (竹川 英宏) 参考文献 1. 厚生労働省 . がん対策推進基本計画 . https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001161234.pdf( 2024 年 3 月 1 日閲覧) 2. 独立行政法人国立がん研究センターがん情報対策情報センター . 2014. がん専門相談員のた めのがんサロンの設立と運営のヒント集 . https://ganjoho.jp/data/hospital/ consultation/files/salon_guide01.pdf( 2024 年 1 月 23 日閲覧) 3. 厚生労働省 . 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中 , 心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 . https://www.mhlw.go.jp/ web/t_doc?dataId=80ab6708&dataType=0&pageNo=1( 2024 年 3 月 1 日閲覧) 4. 厚生労働省 .「循環器病対策推進基本計画」の変更について . https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32232.html ( 2024 年 3 月 1 日閲覧) 図 1:脳卒中サロンの設置・運営に必要と考えられていたこと その他 診療報酬の評価 行政の補助金 病院独自の運営資金 病院長などの施設責任者の協力 両立支援コーディネーターの協力 公認心理師の協力 脳卒中診療に携わっていない リハビリテーション療法士 脳卒中診療に携わる リハビリテーション療法士 脳卒中診療に携わっていない 看護師の協力と増員 脳卒中リハビリテーション認定看護師以外の 脳卒中診療に携わる看護師の協力と増員 脳卒中リハビリテーション看護 認定看護師の協力と増員 精神保健福祉士の協力と増員 社会福祉士の協力と増員 脳卒中診療に関わっていない医師の協力 脳卒中診療に関わっている医師の協力 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 回復期・生活期病院 急性期病院 60 施設、 回復期・生活期病院 145 施設からの結果(複数選択可)である。 8 急性期病院
脳卒中サロン設立運営マニュアル 表 1:脳卒中サロンで行われていた内容 内 容 急性期施設(n=2) 回復期・生活期病院(n=7) 病気の説明 1 (50.0%) 2 (28.6%) 治療の説明 1 (50.0%) 2 (28.6%) 療養の説明 1 (50.0%) 3 (42.9%) 障害者手帳や介護保険など社会資源の説明 1 (50.0%) 2 (28.6%) 体操やグループリハビリテーションの提供 0 (0%) 3 (42.9%) 患者・家族からの質問への回答 2 (100%) 5 (71.4%) 他の患者・家族との交流の場の提供 0 (0%) 6 (85.7%) 心理的サポート 0 (0%) 3 (42.9%) 緩和ケア 0 (0%) 0 その他 0 (0%) 1 (14.3%) (0%) 新型コロナ感染症以前に行われていた内容について、脳卒中サロンのようなピアサポートの場となる会を開催してい た急性期病院 2 施設、回復期・生活期病院 7 施設からの回答(複数選択可)結果である。 表 2:脳卒中サロンの設置・運営に関する意見 脳卒中サロンの設置・運営で苦労した内容 * スタッフの業務時間内での開催を前提にしていたので、時間の確保が難しかった。 患者・家族で困りごとが違うため、グループ分けが望ましいが、人手が必要となる。 業務多忙のため介護福祉士の協力、多職種連携が必要であった。 会場の確保に苦慮した。 入院患者から参加希望者を募っているため参加者の選定に苦慮した。 参加者が少ないため、組織から継続意義を問われた 保険加入の問題がある。 脳卒中サロンの開催が困難な理由 ** いずれの職種の協力も得られにくい 医師の協力が得られにくい 人員不足 現在の業務以外の余裕がない 開催場所の確保の問題 開催・運営費用の問題 経営面との両立ができない 行政の支援がない・診療報酬の加算がない 病院長や事務長の許可が得られにくい 開催・運営を推進する人材がいない 開催経験・開催スキル不足 開催・運営に必要なことがわからない 参加者の確保が難しい 病院内の周知ができていない 脳卒中に特化した必要性がわかならい 脳卒中サロンの要望がない 検討したことがない 新型コロナ感染症の問題 * 脳卒中サロン(ピアサポートの場となる会)の開催経験がある 9 施設の回答(自由記載) ** 脳卒中サロンの開催経験がない 196 施設の回答(自由記載,いずれも複数施設から同様の回答あり) 9
第4章 脳卒中サロンに関する 患者会アンケート調査
脳卒中サロン設立運営マニュアル 背景・目的 広辞苑第 7 版(岩波書店)によれば、サロンは上流婦人、学者、芸術家などが客間で催す社交的集会を指すもので ある。 日本脳卒中協会では医療従事者が開催する脳卒中患者・家族同士の社交的集会を普及させることを目的に、 「脳 卒中サロンプロジェクト」を 2022 年にスタートさせた。この普及活動においては長年類似の機能を担っていた脳 卒中関連の患者会との連携が欠かせない。 今回我々は既存の脳卒中患者会を対象に、将来的な連携に関するニーズな どを把握し、 運営マニュアル作成に反映するためにアンケート調査を行った。 方 法 :2024 年 3 月 1 日〜 31 日の期間に脳卒中協会で作成した質問票を患者会に郵送し、 郵送、 電子メール、 Fax、Google フォームで回答を受付けた。 結 果 14 都道府県の 26 団体から回答を得た。 患者会の設立年数は 40 年以上が 15%、30-39 年が 35%、20-29 年が 15%、 10 年 -19 年が 23%、10 年未満が 12% であった。 患者会員の数は 1-24 名が 42%、25-49 名が 31%、50-99 名が 19%、 100 人以上が 8% であった。 患者会は、患者、患者家族、その他で構成され、患者が占める割合は、100% が 12%、7599% が 12%、50-74% が 58%、50% 未満が 19% であった。患者会の活動内容には、集会(総会や理事会・委員会など) 、 会誌の発行、旅行、悩みや体験を語る会、趣味の活動(絵画、コーラスなど)、市民へのアピール、医療・福祉関係者に よる講演会、事業(喫茶など)が含まれていた。脳卒中サロンとの連携については(図)、 「今後、医療機関が開催する 脳卒中サロンとの連携を希望する」という回答が 20 団体( 77%)からあった。そのうち、 「脳卒中サロンの運営に加 わりたい」という回答が 3 団体、 「脳卒中サロンの開催情報を会員に広報したいので連絡してほしい」という回答が 17 団体、 「脳卒中サロンで患者会の活動予定を広報してもらいたい」という回答が 14 団体からあった。 「脳卒中サロ ンの運営に関して脳卒中患者・家族の関与が必要と思いますか ?」という問いへの回答は、 「とてもそう思う」が 18 団体、 「まあそう思う」が 5 団体であった。脳卒中サロンに期待する活動については、悩み相談、他の患者の脳卒中体 験談、 医療・福祉関係からの情報提供が挙げられた。 (図) 脳卒中サロンとの連携 今後、医療機関が開催する 「脳卒中サロン」との連携を 希望されますか? 質問3で「はい」と答えた団体にお伺いします。 次のどのような連携をご希望ですか。 (複数回答可) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 いいえ 6 (23%) 「脳卒中サロン」の運営に 加わりたい はい 20 (77%) 「脳卒中サロン」の開催情報を 会員に広報したいので 連絡して欲しい 17 「脳卒中サロン」で患者会の 予定を広報してもらいたい その他 (n=26) 考 3 14 1 察 患者会のプロフィールを要約すると、本アンケートへ回答いただいた患者会の多くは、長い期間にわたり患者を中 心とした運営基盤が構築されている団体であった。脳卒中サロンとの連携については大多数が前向きであったが、ま だ判断ができないとする団体もあり、今後、患者会側への本プロジェクトの重要性を説く必要がある。脳卒中サロン 運営そのものに参加したいとする団体は少なかったが、運営には患者や患者家族の関与が必要との意見が多く、この 点も今後の運営に盛り込む必要があろう。 脳卒中サロンに期待する役割の多くは情報共有が主であったが、患者会の 活動内容に重なるところもあり、本プロジェクトにおいては脳卒中サロンと患者会の連携、タイアップの必要性はも ちろん、 医療従事者が開催するサロンとしての特色を打ち出す方向性を示す必要もあるかと思われた。 (藥師寺 祐介) 11
第5章 脳卒中サロンの意義
脳卒中サロン設立運営マニュアル 1 )脳卒中サロンのニーズ 脳卒中を発症すると、多くの患者が何かしらの後遺症を抱えて生きることになる。同時に家族は、収入、医療費・介 護費といった支出、介護の問題、など多くの困りごとに直面する。再発するとより一層患者の日常生活動作、患者・家 族の生活の質が低下する。さらに誤嚥性肺炎や褥瘡、その他の心血管疾患や、加齢に伴い増加する他の疾患など、様々 な疾患の発症や、緩和と療養、意思決定、など、患者・家族では解決が難しい状況も生じる。日本脳卒中協会は設立当 初から患者・家族支援を行なってきたが、日本脳卒中学会でも近年、終末期医療や緩和と療養の提言、意思決定支援 など色々なガイドライン、ステートメント 1 )の発信と脳卒中相談窓口を展開している。さらに厚生労働省は循環器 病対策推進基本計画(執筆時現在第 2 期)2 )の遂行、脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業を開始 3 )した。 この中では相談支援・情報提供が重要となる。先行しているがん対策基本法、がん対策推進基本計画では、 「がんと の共生」として相談支援(執筆時第 4 期)の一環である「がんサロン」が展開されている 4 )。これに対し、脳卒中サ ロンはどの程度のニーズがあるかは不明であるが、患者会の不足、地域格差、などを鑑みると多くの地域でニーズが 高いと推察される。ただし脳卒中サロンがどのようなものか、どのように展開するか、などの情報や方法が確立・発 信されていないため、脳卒中サロンの重要性・必要性が認識されていない背景もある。 一般的に「サロン」はセルフヘルプ・グループとしての機能を有する誰でも参加できる交流の場として運営され 5 )、 患者・家族が他の患者・家族から有益な情報を得たり、患者会の設立が行われている。従って脳卒中サロンのニーズ は高いと考えられる。 2 )脳卒中サロンの意義 がんでは、がんサバイバーが一人の人間として直面する様々な問題に対し、境遇や立場が最も近く、共感的な理解 を示しやすいのは同じがんサバイバーであると述べられている 5 )。がんサロンという場では、がんサバイバー同士に よる体験の語りと傾聴から支え合いや互助・連携、孤立感の減少、希望などが得られている。 一方、インフォームド・コンセントで医療従事者と患者・家族の話し合いはあるものの、がんに限らず多くの疾患 では、 「患者・家族が医療従事者と接する」、 「医療機関を受診する」、という状況は、多くの患者・家族が受動的な立場 となっている。これに対しサロンは、患者・家族が積極的に体験を語らなくても、他の患者・家族の体験、工夫を聴講 することで能動的な参加が可能となる。これにより患者・家族の主体性が回復し、患者・家族は自身の存在価値を見 出すことができる 5 )。 また、サロンの展開でセルフケア、ピアサポートが進み、患者・家族の生活の質の向上、各地域での患者会の設立が 期待できる。残念ながらピアサポートは糖尿病や精神疾患などの一部でしか有効性は示されていないが、がん患者で はピアサポートにより良い心理的影響が示されており、がん治療に取り入れるべき、とされている 6 )。脳卒中では大 規模前向き研究がなく、どの程度の効果があるかは不明であるものの、脳卒中サロンの展開で「他の患者・家族から 有益な情報を得る」、 「日常生活の工夫を知る」という、医療従事者側からの情報提供、支援以上のことが得られ、サロ ンを介して友人ができ、社会参加の一助にもなり得る。 患者・家族の主体性の回復、存在価値の認識、有益な情報・支援の取得、社会参加へのつながり、が脳卒中サロンの 意義である。 3 )脳卒中サロンの多様な方向性 脳卒中サロンの基本はがんサロンと同様、「原則的に脳卒中患者・家族が主体となること」である 5 )。しかし当協 会が把握している限りでは、医療従事者のサポートがない団体は自然消滅しているところが多いようであり、脳卒中 サロン、患者会とも医療従事者のサポートが必要と考えられる。一方、運営資金については患者・家族が主体となっ た喫茶店などの経営で賄っている団体もある。 サロンの形式であるが、大人数で開催する形式、少人数(小グループ制)で開催する形式、などがある。どちらが良 いかはそれぞれの地域、参加希望人数にもよると思われるが、同じような後遺症を有する患者とその家族ができるだ け一緒になる方が、他の患者・家族の体験、工夫を聴講・共有する点からは最良と考えられるため、少人数の方が良 いかもしれない。 サロンの内容については、医療従事者側からの情報提供なども多く行われているようであるが(「脳卒中サロンに 関する医療機関アンケート調査」の項参照)、手芸など娯楽の場を提供しているサロンもあり、娯楽や雑談を通じた 情報共有・交換ができると推察される。 当協会が開催した脳卒中サロンの内容については、「プロジェクトでの実際の活動(事例集)」の項を参照いただ きたい。 (竹川 英宏) 参考文献 1. ガイドライン・提言・各種指針・手引き・推奨 . 日本脳卒中学会 . https://www.jsts.gr.jp/guidelines/index.html( 2024 年 8 月 10 日閲覧) 2. 厚生労働省 .「循環器病対策推進基本計画」の変更について . https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32232.html( 2024 年 3 月 1 日閲覧) 3. 厚生労働省 . 脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業 . https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001046477.pdf 4. 厚生労働省 .「循環器病対策推進基本計画」の変更について . https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32232.html ( 2024 年 3 月 1 日閲覧) 5. 独立行政法人国立がん研究センターがん情報対策情報センター . 2014. がん専門相談員のた めのがんサロンの設立と運営のヒント集 . https://ganjoho.jp/data/hospital/ consultation/files/salon_guide01.pdf( 2024 年 8 月 12 日閲覧) 6.Ziegler E, Hill J, Lieske B, te al.: Empowerment in cancer patients: Does peer support make a difference? A systematic review. Psychooncology 2022;31:683-704 13
第6章 脳卒中サロンの立ち上げ
脳卒中サロン設立運営マニュアル 1 )脳卒中患者のニーズと地域や病院環境のアセスメント 日本脳卒中協会が実施した調査「脳卒中を経験した当事者(患者・家族)の声」では、当事者が経験され た 5 つの困難( 1. 治療や制度が分化されており一貫した支援が得にくい、2. 地域生活におけるリハビリテー ションやケアが十分でない、3. 働くことへの支援が不足している、4. 失語症という後遺症に対する支援や理解 が不足している、5. 脳卒中に対する社会の理解が不足している)が報告されている。https://www.mhlw.go.jp/ content/10905000/000649148.pdf これらの課題には、急性期・回復期・生活期の医療連携や煩雑な手続きを要する介護・障害福祉の支援体制が影 響しているほか、 当事者が適した支援を得られず孤立している現状が反映されている。当事者の孤立予防や自立支援・ 心理的サポートの一つとして、ピアサポートは有効だと考えられる。その実現形のひとつが脳卒中サロンである。医 療専門職によるピアサポートの場の提供は、当事者同士による支え合い機能のほか、各参加者の困りごとに応じた各 専門職からの助言を提供できる、参加中の体調不良に対応できるため参加者が安心できるなどのメリットが上げら れる。 治療以外にもリハビリテーション・経済面・就労支援・うつなどの相談も多いため、多職種・多領域から支援 者の参加を募ることが望ましい。 また開催場所は、車いす・杖などの利用者の移動への配慮や障害者用トイレへのア クセス、 失語症や高次脳機能障害の方が安心して話すことができる空間づくりや時間的配慮が求められる。 2 )どのような脳卒中サロンを⽬指すのか : サロンの設⽴⽬的と活動の概要 医療機関におけるサロンの開催様式は様々である。本書では脳卒中・心臓病等総合支援センター、脳卒中相談窓口、 脳卒中医療連携ネットワークなど、 既存の脳卒中患者の支援活動の付加機能として開催した脳卒中サロンを紹介する。 各機関が実現可能性や継続性の高い手法を採用している。 開催に向けて、開催頻度・運営メンバー・多職種の関与・運営費などが話し合われるほか、既存の患者会との連携 の有無や、患者のニーズに対応する多領域(医療・介護・障害福祉など)・多機関(急性期・回復期・生活期)の関 与や運営プラットフォームの構築なども視野に検討することが望まれる。 3 )病院や地域で脳卒中サロンの理解者を得るための環境づくり(関係者の役割) ①医療者 : 患者の相談ニーズに適した医療者(医師・看護師・リハビリテーション療法士・MSW など)の参加を求 める。 各医療者の所属機関、 その機関の脳卒中診療に対するスタンス、 医療者と職能団体とのつながりなどを把握し、 医療者が参加しやすいストーリーを作り、 開催プランを作成する。 例 :・ 一次脳卒中センターコア施設 : 自院が関与するピアサポートの場として協力を依頼する。 ・脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 : 認定資格に必要な社会活動として協力を依頼する。 ②開催場所の病院管理者 : サロンの参加にあたり上司や管理者に適宜委嘱状を発行し、協力者の所属機関の活動許可 を得る。 また、 継続開催が可能となるよう活動実績を管理者に報告し、本活動への理解を得る。 ③病院事務担当者 : サロン開催に向けた広報・申込み、多機関との連携など、日常業務と併行した開催準備や各資料 作成などにつき、 各専門職と連携がとれる病院事務担当者の協力を得ることが望ましい。 ④医療以外の支援者 : 医療以外の障害・就労・介護・経済基盤・仲間づくりなどのニーズに対し、既存の患者会や障 害福祉・就労支援・介護・福祉の専門職などへの協力依頼も検討するとよい。 ⑤⾏政担当者 : 都道府県へ開催相談・実績報告を行い、都道府県循環器病対策推進計画への反映も視野に脳卒中患者 のニーズや支援課題を報告する。 サロン開催の後援名義申請を行うのも一案である。 ⑥地域社会(市⺠): 各医療機関の受診の有無を問わず誰でも参加できるよう広報する。参加案内や開催実績を広報 することにより「困っているのはあなただけじゃない」とのメッセージを発信できる。広報の方法として、新聞や コミュニティー誌での告知、関連機関におけるポスター掲示やパンフレット掲示、ホームページや SNS での発信、 自院の外来・入院患者に対する直接的な声がけなどが考えられる。 (藤井 由記代・宮井 ⼀郎) 15
第7章 脳卒中サロンの 運営マニュアル・開催
脳卒中サロン設立運営マニュアル 1.1 規約(ルール) 脳卒中サロンの開催にあたっては、各都道府県の事業運営者(または開催病院単位あるいは地域単位)が規約を 策定するものとする。 規約の内容は各事業運営者(または開催病院単位あるいは地域単位)の定める所によるが、参 加者の遵守事項として必ず下記を記載すること。 (遵守事項) 参加者は、 以下に記す 8 つの約束を遵守する。 ( 1 )患者・家族、もと患者・家族、医療スタッフが参加します。それ以外の参加希望があった時は世話人 で話し合って決めます。 ( 2 )話された個人のことはここに置いて帰り、他の場所で話しません。 SNS などに掲載することも禁止します。 ( 3 )健康食品や健康器具などの品物を勧めたり、 販売したりすることはしません。また参加者へ飲食物の 配布は行いません。 ( 4 )金銭の貸借、宗教団体・政治活動への勧誘はしません。 ( 5 )医療的なアドバイスはしません。他の人が受けている治療は自分に合うとは限らないので、 医師に相 談しましょう。 ( 6 )大切な時間です。参加された方が平等に話せるよう、お互いに気を配りましょう。 ( 7 )アドバイスや励ましをされると負担になることがあります。否定や批判をせず、 お互いに聞き上手に なりましょう。 ( 8 )話しづらいときは聴くだけで構いません。気軽に参加しましょう。 1.2 準備と広報 準備と広報については、 以下の点に留意して行うと円滑なサロン開催につながる。 ( 1 )開催形式の決定 開催形式の決定は、サロン準備のタスク全般にかかる重要なポイントである。参加者同士の茶話会のみを実施する のか、前段に医療者または脳卒中当事者などの講話を添えるのか、または市民公開講座のようなイベントのサブ会場 に脳卒中サロンの場を設けるのか。 さらには対面形式で開催するのか、オンライン形式にするかの選択も求められる。 本マニュアル「 8. プロジェクトでの実際の活動(事例集)」を参照しつつ、地域や主催病院の特性も加味しながら決 定する。 ( 2 )参加者への告知形式の決定 参加対象者の募集を公に行うのか、またはクローズドの形で行うのかの選択が求められる。公に告知すれば、ピア サポートの場を求める方に広く周知することができるというメリットがある一方、参加者の背景や人数規模などを 主催側がコントロールできないという側面もある。サロンの開催形式にあわせて適宜判断する。 ( 3 )開催場所の決定 対面形式による開催の場合、開催場所の検討も必要となる。地域へのアウトリーチという観点では、近隣の公民館 や商業施設内のイベント会場もよいと考えられる。一方、告知をクローズドで行う場合は、参加対象者が主催病院の 入院・外来患者、 または通所や訪問看護の利用者となるため、開催場所は自ずと主催病院の施設内となる。 ( 4 )参加人数の決定 参加者への告知を行うにあたり、おおよその参加想定人数を事前に決めておくとよい。想定人数は( 1 )でも述べ た開催形式にもよるが、ピアサポートの趣旨に照らすと、茶話会の 1 グループ単位の人数は 10 名以内の人数である ことが求められる。 全体の参加者が 10 名を超える場合は、茶話会のグループを複数設ける。 17
脳卒中サロン設立運営マニュアル ( 5 )開催日時の決定 開催日時の決定は運営スタッフの都合や開催場所との兼ね合いによるが、参加者のことを主眼に据えて設定する。 所要時間はあまり長すぎないほうがよい。 また、当事者家族もいることや、当事者の中には既に復職している方もい ることを考えると、 週末や祝日開催の方がよい。 ( 6 )告知 上記( 1 )〜( 5 )が確定できれば、事前告知のフェーズとなる。クローズドで開催する場合は、病院に入院・外来 診療中の方、または通所や訪問介護利用中の方へ個別に声かけを行う形になる。一方で公に告知する場合は、院内へ のポスター掲示やホームページ・SNS などへの情報掲載も含めてアナウンスする形になる。いずれの場合も病院内 に事務局窓口を設けて、 参加者管理を一元化する必要がある。 ( 7 )その他 上記( 1 )〜( 6 )を実施し、 当日の参加者がある程度確定した時点で、参加者リストの作成を行う。当日の雰囲 気作りや、 会話を円滑に進めるために、 茶菓子や飲料の用意、 また参加者及びスタッフ全員の名前札を作成するとよい。 なお、 規約に定める「 8 つのルール」は、 参加者の手元資料として必ず人数分印刷すること。 1.3 実施 当日の運営は開催病院が主体となって行う。 具体的には、会場準備や参加者の受付け、茶話会のファシリテートな どを担うことになる。 参加者同士の円滑な会話を促すためにも、茶話会には各グループあたり 1 〜 2 名程度のファシ リテーターを付けるとよい。 また、記録のために撮影を行う場合は必ず事前に参加者の同意を得るとともに、画像な どを広報用途で使用する場合は個人が特定されない範囲での使用を前提とする(顔出しでの公開を行う場合は、必 ず個別の同意を得ること) 。 なお、 サロン終了後の参加者同士の個別のつながりについては、運営側がコントロールするものではない。 1.4 振り返り 脳卒中サロン開催後には、必ず開催病院内で振り返りの場を持つこと。振り返りの材料として、サロン開催当日に 参加者向けのアンケートを行ってもよい。 反省点や参加者の声を反映して、次回のサロン開催につなげる。 1.5 課題 脳卒中サロンの開催については、下記の課題が考えられる。いずれもサロンの企画段階で考慮するとともに、サロ ン開催後にはかならず 1.4 の振り返りを実施し、次回以降の開催のためにノウハウを蓄積することが肝要である。 ●いわゆるサロン“荒らし”の発生 オープンな開催にすれば、どのような方でも参加する可能性がある。茶話会の会話を一人で独占したり、他参加者 を攻撃したりするような方が出てくる可能性もある。このような “ 荒らし ” を除外するために、最初からクローズド 形式の開催を選択するという手もあろう。 または、茶話会のグループにストッパーの役割も兼ねた、運営スタッフを 配置するという予防策もある。 ●参加者同士のつながり形成による“お節介”の発生 「小さな親切大きなお世話」とはよくいったものだが、当事者、または当事者家族同士がつながりを持つことで、互 いのケアや生活状況に介入し、医療者側の支援がしづらくなるケースはまま発生する。規程内に遵守事項としてあげ た「 8 つのルール」は毎回必ず出席者へ配布するとともに、サロン冒頭に全員で読み上げを行うなど、徹底する必要 がある。 ●後遺症の程度によるサロンへの参加の障壁 後遺症の程度によっては、外出もままならない方もいる。一方で、そのような方こそピアサポートの場を求めてい る可能性もある。 オンラインやメタバースによる開催も検討し、なるべく「誰一人取り残さない」サロン設計を求め (森本 通子、橋本 洋一郎) たい。 18
第8章 プロジェクトでの実際の活動 (事例集)
脳卒中サロン設立運営マニュアル 1 )岩手県支部 急性期病院小規模脳卒中教室型導入の試みから自治体との連携へ 岩手医科大学は 2019 年 9 月に岩手県盛岡市内丸から 11㎞離れた矢巾町へと附属病院が移転したが、当科外来部 門は盛岡市に残した内丸メディカルセンター(MC)に残り、入院部門が矢巾町の附属病院と別れた状況になってい る。 がんサロンが矢巾町の附属病院に設置された事や人的リソース面から、サロン設置は矢巾の附属病院を想定せざ るを得なかった。COVID-19 の影響で院内の接触制限も厳しく、回復期リハビリテーション施設などと共同した院外 でのサロン開催はもちろんの事、内丸 MC 通院中の生活期患者を対象とした開催もしづらい状況であった。高齢者中 心の脳卒中患者に対してスムーズに Web 開催できる確信も持てず、急性期入院患者へのアプローチをまず試みる事 とした。 場 所:病院内がんサロン内にある談話スペース ス タ ッ フ :医師、脳卒中リハビリテーション認定看護師、医療ソーシャルワーカー、事務スタッフ( 2024 年度よ り脳卒中・心臓病等総合支援センター事業となり、同センターに関わるスタッフの支援を得られるよ うになった) 内 容:約 30 分の脳卒中教室後にスタッフを交えたフリートーク 広 報:フライヤー(図)と院内 TV での CM 頻 度:月 1 ~ 2 回の月曜日午後 2 時から開催 結 果:当院の年間急性期脳卒中患者は 300 例前後であり、入院している患者は多くとも 20 人前後である。 そ の中で、サロンに参加する意欲や認知機能が保たれ、車いすで移動できるような方は限られてしまい、 1 回の参加者はおおむね 2-3 人に留まった。加えて、脳卒中教室は好評で質問も多くいただくものの、 ピアサポートとして自分の悩みや困りごとを積極的に他患者と共有できる方は、ごくわずかであった。 一方、がんと脳卒中という観点では、がんサロン内で開催した事により外来から若干名がん患者さんの 参加があった。 今後の展望:院外へフライヤーを配布し回復期 / 生活期患者の参加を募っているが、現時点ではまだ院外からの参 加はない。そこで、自治体と連携して生活期患者を対象とした院外開催も検討している。本学附属病院 が移転した岩手県矢巾町は人口 27000 人余りで盛岡市の南に隣接し田園に囲まれたベッドタウンで ある。 当科は 2016 年度より矢巾町健康長寿課のご協力を得て、高齢者の方々を対象に「やはば脳とカ ラダのいきいき健診」を実施し、 「健康長寿社会 の実現を目指した大規模コホート研究」 ( JPSCAD)に参加してきた。本事業における当科と自治 体との繋がりを生かし、矢巾町担当者と脳卒中サ ロン開催に関して連携をとり、地域の回復期リハ ビリ施設とも協力して、2024 年 11 月の院外開催 を予定している。 (板橋 亮) 20 図
脳卒中サロン設立運営マニュアル 2 )栃木県支部 開催までの道のり 支部単独としての開催にはいろいろな問題があったが、事務局のある獨協医科大学病院は日本脳卒中学会一次脳 卒中センターのコア施設、厚生労働省モデル事業「脳卒中・心臓病等総合支援センター(以下、センター)」で脳卒 中の相談窓口を運営している。 そのため、社会福祉士、事務職員などに相談し、センターと支部の協同事業として開催 することが決定された。 これにより病院・大学講堂・会議室、Zoom などの Web 会議システム、マンパワー(時間外給与可)の確保と、病 院予算に加え国・県のセンター補助金の使用が可能となった。 開催の工夫 3本柱を 1 )患者・家族支援、2 )当事者同士から得られる有益な情報の共有、3 )患者会設立、 とし、 同じよう な後遺症・悩みを有する小グループ制で開催することにした。県内フリーペーパー「とちぺ」 、地方紙「下野新聞」、 市民公開講座(支部とセンター共催)での告知、院内、県内公共施設や「道の駅」にチラシを配布した。センター開 催イベント案内連絡を希望したセンター相談窓口相談者にもメール案内した。 事前申し込み制(Web サイト、電話、ファックス、来院)とし、病院側の大学研修会議棟で、新型コロナ感染症など の対策を行い施行することにした。 飲料の提供は基礎疾患を有する患者がいると想定し、ペットボトルの水のみとし、日本脳卒中協会作成資材・入会 案内、県作成在宅療養支援ガイドブックを配布することにした。なお、批判しない、プライバシーを守る、エビデンス のない情報は話さない、 などのルールを通知した(図左)。 脳卒中サロンの様子 当院は 2024 年 8 月現在まで 3 回開催した。 第 1 回(2023 年 3 月)はコロナ禍で Zoom としたが、第 2 回(2024 年 1 月) 、 第 3 回( 2024 年 3 月)は研修会議棟で行った(図右)。 多くの問い合わせがあったものの、 「会場が遠い」「Web が使えない」、当日欠席者などで実際に参加したのは、第 1 回が 6 名(患者 3 名、家族 2 名、健常者1名) 、第 2 回が 6 名(患者 2 名、家族 4 名)、第 3 回が5名(患者3名、家族 2名)と少なかった。 しかし後遺症などは異なるものの小グループで行うことができた。 医療者は医師、社会福祉士、事務職が参加し、会開始まで日本脳卒中学会や日本脳卒中協会作成動画、リハビリテー ション動画(脳卒中サロン事業で作成)などを上映した。医師の脳卒中解説(短時間)後、フリーディスカッション を主として行った。 フリーディスカッションは医師がファシリテートし、全ての参加者に発言機会を作った。 一人一人が困りごとなどを 話し、 他の患者・家族から共感や日常生活の工夫など発言があり、 サロン終了後も参加者同士で話し込む姿がみられた。 最後に 自治医科大学附属病院(副 支部長 藤本茂先生)の脳卒中・ 心臓病総合支援センターは事 前 申 し 込 み 不 要 で 2024 年 2 月に開催し、多数が参加した。 申し込み方法、小グループ制の 是非など検討すべき点は多い。 一方、県内各地域での開催、 院内患者・家族に対する脳卒 中リハビリテーション看護認 定看護師主体で運営する脳卒 中サロンの開催(毎月)準備 脳卒中サロンのルールについて 図 脳卒中サロンの注意事項とサロンの様子 ご参加希望される方は、 下記を必ずお読みください。 ◆思いを共有し生き方のアイディアを出し合いましょう。 ◆心を元気にし、治療や生活に励む活力を得ましょう。 ◆個人の価値観や生き方を尊重し、批判しないようお願 いします。 ◆参加者のサプリメントや確立されていない医療情報、 宗教については話さないようお願いします。 ◆SNS への投稿、録音・録画等はご遠慮ください。 ※ルールをお守りいただけない場合は、運営側の判断により、 強制退出等の措置を取らせていただくことがあります。 お互いの意見や気持ちを尊重し、 参加者が安心してお話をする場です。 ご協力をお願いいたします。 を進めているところである。 (竹川 英宏) 21 会場は小グループで他者同士の間隔を開けて座 れるようにし、かつ参加者の顔を全員が見渡せる ように工夫した(図右)。 脳卒中サロンでは批判をしないなどのルールを 決め、事前・当日に注意喚起した(図左)。
脳卒中サロン設立運営マニュアル 3 )日本脳卒中協会・大阪脳卒中医療連携ネットワーク(OSN) ①サロン立ち上げの背景( 2018・2019 年度市民啓発イベント開催の経験) 2008 年に発足した大阪脳卒中医療連携ネットワーク(以下 OSN)には、2024 年 8 月現在、99 医療機関(急性 期 23 機関、回復期 39 機関、生活期 37 機関) 、オブザーバー 5 機関(大阪市健康局・大阪市更生療育センター・大 阪府立障がい者自立センター・大阪府障がい者自立相談支援センター・就労移行支援事業所 LITALICO ワークス) が登録しており、 活動 10 周年以降、 毎年市民啓発イベントを企画・開催している。 ②サロン開催の実際( 2022・2023・2024 年度) 2020.2021 年度はコロナ禍で市民啓発イベントを中止したが、現在は脳卒中サロンとして再開し、2022 年度「教 えて!あなたの脳卒中」 (オンライン) 、2023 年度「脳卒中発症後のリハビリどうしてる?」(ハイブリッド)、2024 年度「脳卒中発症後、どんな風に暮らしてる?」(対面)と題し、ミニレクチャー・ピアサポート&専門職との相談 会を開催した。 2022 年度・2023 年度のレクチャ―は、専門職による講義+当事者の体験談+患者会紹介の動画を作 成し、日本脳卒中協会のホームページで配信している。サロンは、当時者同士の対話(ピアサポート)に加え、医療・ 福祉スタッフへの相談や意見交換も同時に行う体制とした。結果、オンライン・ハイブリッドには遠方からも継続し た参加者があった。 図1:2023 年度 広報チラシ 図 2:2024 年度 参加申込時のアンケート(参加者ニーズ) 現在、脳卒中のことで気になること、話したいことをお選びください(複数選択可) 治療について 再発予防について リハビリテーションについて 食事について お薬について 仕事について 日常生活について 経済面について 介護について 各種制度の利用について 相談窓口について 患者会・当事者について …7(38.9%) …8(44.4%) …16(88.9%) 0 …6(33.3%) …3(16.7%) …5(27.8%) …10(55.6%) …2(11.1%) …7(38.9%) …10(55.6%) …2(11.1%) …5(27.8%) 5 10 15 20 図 3: 開催風景( 2022 年度オンライン・2024 年度対面) ・当サロンの参加者は 、 入院中から発症後数十年経過された方まで幅広く、 ニーズも多様である(図 2 )ため、 多領域(医療・介護・障害) ・多機関(急性期・回復期・生活期) ・多職種(医師・看護師・リハビリテーショ ン療法士・社会福祉士ほか)が参加し、当事者のニーズに応えている。3 年間の参加者(当事者など / 専門職)は、 10 名 /32 名、13 名 /39 名、23 名 /42 名と増加している。平時からつながりをもちたい参加者に向け、患者会の 主催者が参加・紹介してくれるため、 つながりづくりの役割も担う。 ・参加者からは、対面希望 (高次脳機能障害により画面上のコミュニケーションが難しいなど ) 、オンライン希望 (麻 痺があり移動困難である・遠隔地からも参加しやすい)の声があり、 開催方法は双方が有効であると考えられる。 ③脳卒中サロンの継続性確保に向けた環境づくり 日々の病病連携・病診連携・障害福祉との連携基盤(脳卒中連携パスネットワーク)を活動主体とするため、 実 務と併行して活動できる。 脳卒中・心臓病等総合支援センター(国立循環器病研究センター)や日本脳卒中協会は 共催、職能団体(SCPA 大阪府支部)や大阪府・大阪市に後援依頼を行い、広報の協力を得る・開催実績を共有す るなど、 つながりをもって運営している。 当機能を今後も維持するためには、各機関・団体・関係者の理解促進や連 携維持、 企画・調整の担当人員の確保、 財源の確保などが課題である。 22 (藤井 由記代・宮井 一郎)
脳卒中サロン設立運営マニュアル 4 )兵庫県支部 兵庫県では当院(神戸市立医療センター中央市民病院)が脳卒中サロンプロジェクトのモデル施設に選定された。 初めは手探りの状態であったが、まず 2022 年 11 月 23 日に日本脳卒中協会兵庫県支部として毎年行ってきた脳卒 中市民公開講座に併設する形で第 1 回脳卒中サロンを開催した。脳卒中経験者とその家族ら 8 名が参加したが、血栓 回収治療により劇的に症状が改善した体験談をはじめ、麻痺や言語障害だけでは表現できない脳卒中後遺症や家族 の苦労など、 参加者それぞれが自分の悩みや経験を周りに聞いてほしいと願っていることを実感し手応えをつかんだ。 2023 年度からは脳卒中サロンの単独開催を企画した。当院の医師、看護師、ソーシャルワーカー、事務職員から構 成する院内ワーキンググループを組織し、開催準備を進めた。2023 年 9 月 22 日に「みんなで学ぼう!みんなで語 ろう!脳卒中サロン」を開催し、12 名が参加した。血栓回収治療を受けて社会復帰した 2 名に脳卒中体験談を語っ てもらった。 失語や意識障害で意思疎通できないように見えた患者が、実は発症時や治療中の様子を記憶していたこ とや、やがて言葉や運動能力を取り戻していく過程に感じた悲喜交々(こもごも)は、サロンの参加者だけでなく、 脳卒中を診る医療者全員に聞いてほしい内容であった。その後、 参加者同士の意見交換を行い、 脳卒中相談窓口と銘打っ て、ワーキンググループメンバーが個別に参加者の相談に応じた。その中で、若年層の就労・両立支援についてニー ズが高いことを実感し、次回のテーマとすることにした。2024 年 2 月 14 日に「脳卒中患者の両立支援」というタ イトルで脳卒中サロンを開催した。 回復期リハビリテーション医師やハローワーク担当者に講演を依頼し、参加者は 6 名であった。このようなイベント開催をきっかけに、当院では毎日院内放送で社会労務福祉士や両立支援コーディ ネーターによる患者支援について呼びかけるなど、院内の両立支援に対する機運も高まっている。2024 年度は 9 月 に開催を予定している。 このように、様々な形式での脳卒中サロンを開催する中で、より患者や家族のニーズに応えられるサロンとはどう いうものかまだ模索している段階である。 今後の取組みとして、当院のような急性期の包括的脳卒中センターと回復 期病院が相補的に連携しながら脳卒中サロンを運営・発展させていくため、脳卒中相談窓口などを通じてより地域 (尾原 信行・坂井 信幸) に開かれたサロンを目指したいと考えている。 23
脳卒中サロン設立運営マニュアル 5 )熊本県支部 2022 年に日本脳卒中協会の「脳卒中サロン」プロジェクトが開始されたが、このプロジェクトの責任者の私(橋 本)が、2022 年 3 月に 29 年勤務した熊本市民病院を定年退職し、4 月より済生会熊本病院脳卒中センター特別顧問 として勤務することになった。日本脳卒中協会熊本県支部長を熊本市民病院脳神経内科部長の和田邦泰先生に代わ ることになった。 済生会熊本病院に赴任して、院長と相談して、脳卒中サロンプロジェクトの熊本での活動を病院のマターにしても らうことになった。 病院のコロナ対応が大変な時期であり、取り組みが遅れ、院内のキックオフミーティングが 2023 年 3 月 20 日に開催された。 当院と連携している回復期リハビリテーション専門病院と合同で行うこと、今後のロードマップの確認を行って、 活動が開始された。連携リハビリテーション病院をにしくまもと病院に決めて、当院のメンバーが病院訪問をして、 このプロジェクトの意義を説明し、 賛同いただき、あとは電話やメールのやり取りなどで準備を進めた。 コロナ感染の問題もあり、熊本での第 1 回脳卒中サロンは、2023 年 11 月 25 日(土)ににしくまもと病院で 9 時 30 分〜 11 時 30 分で開催された。 開始前に「脳卒中サロン 8 つの約束」を配布した。最初に、脳卒中を経験された 方(マスコミ関係者で復職している方)の体験談を聴講し、3 つのグループに別れて茶話会が開催された。家族同伴 の方が多く、外来患者さんのみならず入院患者さんも加わったサロンとなった。復職されている患者さんが複数名お られ、サロン中にどのように復職したか、車の改造に補助金を使って行ったこと、早めに手続きしないと退院・復職 に間に合わずに改造ができるまでに奥さんなどの親族による送迎が必要だったことなどの情報交換が行われ、終了 後に改造された自家用車 2 台の見学会も行われるという形になった。脳卒中サロンが患者さんの「復職支援・就労 支援」になることが分かった会であった。参加された患者さんや家族とともに運営スタッフのアンケート調査を行 い、 意義のある会であったこと、 改善点なども確認できた。 終了後に院内での振り返りを行い、再度、にしくまもと病院へ出向き、振り返りと第 2 回の企画についても話し合 いを行った。 第 2 回は 2024 年 4 月 20 日(土)に 9 時 30 分よりにしくまもと病院で開催された。脳卒中を経験された患者さ んの体験談から始まり、その後、3 つのグループに別れて茶話会が行われた。2 回目は比較的高齢の患者さんが多く、 入院中の患者さんから退院された患者さんへの質問が多く、また外来通院中の患者さん同士の情報交換も積極的に 行われていた。 脳卒中になってからの辛さ、 退院後の心配などに対して、 患者さんや家族からの体験からの話を聞けて、 特に入院中の患者さんがかなり安心されていると感じた。脳卒中で死ぬ時代ではなく、多くの患者さんが後遺症を抱 えて、その後の人生を生きていかなければならず、広い意味での緩和ケアでは「生きるための緩和ケア」が必要であ ると思っていたが、脳卒中サロンが患者さんの辛さの軽減につながることを実感できた第 2 回目の脳卒中サロンで あった。 問題点としては、会場が狭く、 参加者を限定しなければならなかったことである。また 1 施設の入院・外来の患者 さん・家族であり、参加者をうまく選定されていたために、非常に良いサロンになったことが 2 回目のサロン後の振 り返りの会議で分かった。 さらにファシリテーターを 3 つの茶話会にうまく配置してあった。 今後、熊本県全体へ広げる場合に各施設ごとで施設に通院・入院している患者さんのみに限定して行うのか、持ち 回りで患者さん・家族を限定せずに行うかの課題がある。最終的には熊本大学病院にある熊本県脳卒中・心臓病等 総合支援センターの事業に組み込めれば良いと考えているが、総合支援センターの仕事が激増しており、負担をかけ ないような運営を行う工夫が必要と考えている。今後も引き続き、継続的に開催できるようにしていきたいと考えて いる。 (橋本 洋一郎・森本 通子) 24
執筆者・編集一覧 《執筆者》 橋本 洋一郎 済生会熊本病院 脳卒中センター ( 脳神経内科 ) 特別顧問 日本脳卒中協会 常務理事 はじめに、第 2 章、 中山 博文 中山クリニック 院長・日本脳卒中協会 副理事長 第1章 竹川 英宏 獨協医科大学病院 脳卒中センター 教授・センター長 日本脳卒中協会 専務理事 第 3 章、第5章、 第 7 章、第8章 5 ) 第8章 2) 藥師寺 祐介 関西医科大学 神経内科学講座 主任教授 日本脳卒中協会 理事 第4章 藤井 由記代 社会医療法人大道会森之宮病院 日本脳卒中協会 理事 第 6 章、第8章 3 ) 宮井 ⼀郎 社会医療法人大道会森之宮病院 院長代理 第 6 章、第8章 3 ) 板 橋 亮 岩手医科大学 内科学講座 脳神経内科・老年科分野 教授 日本脳卒中協会岩手県支部 支部長 第 8 章 1) 尾原 信行 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経内科 医長 日本脳卒中協会兵庫県支部 副支部長 第8章 4 ) 坂井 信幸 神戸市立医療センター中央市民病院 脳血管治療研究部 清仁会 シミズ病院 院長 第8章 4 ) 森本 通子 済生会熊本病院 経営企画部企画広報室 第 7 章、第8章 5 ) 《編 集》 日本脳卒中協会 事務局 脳卒中サロン設立運営マニュアル 2024 年 12 月 14 日 編集・発行 発行 公益社団法人 日本脳卒中協会 〒 542-0012 大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-3-15 共同ビル 4 階 TEL.06-6629-7378 https://www.jsa-web.org/ 発行責任者 理事長 峰 松 制 株式会社 コッツ kotts.jp 作 一夫 © 公益社団法人日本脳卒中協会 本書の内容を無断で転載することを禁じます。 転載許諾、 二次利用などの申請は日本脳卒中協会 web サイト「ホームページポリシー」にある 「著作権に関わるお申し込み申請用紙」をご利用ください。
日本脳卒中協会ホームページ https://www.jsa-web.org/ 脳卒中サロンホームページ https://www.jsa-web.org/patient/242.html 本書は、「ファイザー Quality Improvement 助成」による日本脳卒中協会「脳卒中サロンプロジェクト」の活動として制作されました。