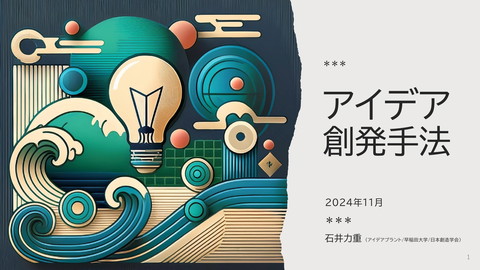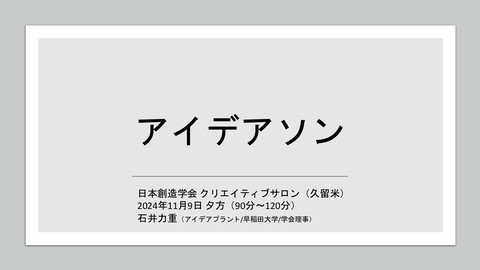小松高校、ブレストの学習と探求テーマの獲得
0.9K Views
February 03, 25
スライド概要
石川県の小松高校 で、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)に指定されている同校の1年生向けに、「探求テーマをつくり出す」ためのワークショップを行いました。高校生たちは、ワイワイと活発に意見を交わしながら、自分たちの探求テーマを見つけていきました。最初は戸惑いも見えましたが、アイデアの出し方のコツを掴むと、思いがけない切り口やユニークなテーマが次々と生まれ、熱気に包まれました。
内容概要:
「アイデアの授業」では、アイデアの発想を得意とする人も苦手な人も楽しめる方法を学習します。Zebraブレストという手法を用いて、一人でのアイデア出しとグループでのアイデア交換を繰り返すことで、独自の発想を引き出すプロセスを体験することができます。また、仮説を立て、検証方法を議論することで、研究テーマを定める流れも説明しています。
関連スライド
各ページのテキスト
「アイデアの授業」 “ブレストの学習と 探求テーマの獲得” 編 石川県立 小松高等学校 2025年1月24日 13:10 ~ 14:50 石井力重(りきえ) アイデアプラント 代表 / 早稲田大学 非常勤講師 1
アイデアを出すのが得意な人も、 アイデアを出すのが苦手な人も、 発想するのが楽しくなる (し、探求のテーマも得られる) 2
13:10 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0)講師自己紹介(3分) 進行 0a)アイスブレイク「イマジン・カード」(7分) 0b)創造力のミニレクチャー(5分) 13:25 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1)Zebraブレスト(30分) <進行調整バッファ、あるいは、休憩(5分)> 14:00 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2)素朴疑問の共有 と「仮説のブレスト」練習(10分) 3)仮説のブレスト(25分) 14:35 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4)建設的な批判ありの「アイデアディスカッション」(5分、レクチャーだけ) 5)まとめ・質疑応答・メッセージ(10) ※実際は、進捗遅れの吸収シロです。ほとんど時間残っていない場合は、割愛します。 14:50 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3
「研究テーマを定める」流れ (これ、研究者も同じです) • 「これって不思議だな」を、雑談的に出し合う。 他の人が「は?」 と思うものでもいいんです。(=着目~発見) • 「そうなる仕組みって、もしかしてこうじゃない?」を、 未成熟でいいから、出し合ってみる(=仮説) • 「そうかどうかは、こうしたら確かめれるカモ」を、議論していく (検証方法の設計) ← 時間次第で、割愛かも。 4
講師自己紹介 5
石井力重 Rikie Ishii 6
漫画家 「さそうあきら」 さんの著書に • 『マンガ学部の脚本概論』 • https://comicaction.com/episode/1393 3686331626984278 • 『神童』『マエストロ』等の作者 「さそうあきら」さんの 漫画を生み出す考え方が、 一部無料公開されています。 • 第1回(P8の1コマ目)に、 石井も登場しています。→ 画像引用:『マンガ学部の脚本概論』 7
堅い仕事としては 8
(デザイン論、アイデア基礎を担当) 9
非常勤講師 (デザイン論、アイデア基礎を担当) 早稲田大学 名城大学 東北工大 10
専門領域としては 11
学会で創造性の 研究をしています。 12
日本創造学会 学会で創造性の 研究をしています。 •理事 •業績 •研究発表賞(2017) (2024) •著作賞(2021) 13
単著の書籍 (他、 共著2冊、執筆協力1冊) 学会で創造性の 研究をしています。 2009 2020 14
そして、本業は 15
発想ツールを 企画・製造 NHK おはよう日本(に取材された時の映像) 16
発想ツールを 企画・製造 17
0a. 導入 創造ストレッチ
創造工学の雑談 (ドイツ・ヴュルツブルク大学の研究) 「自由な動きが、引き出す」 引用: 何物にも縛られない「自由な動き」が 創造性を高めると判明! https://nazology.net/archives/103764 19
ダンスとかの心得がない人には でも、全くの自由って、動きにくいのでは? 特に、日本人は・・・
その観点で、研究を発展させました。 2022年の早稲田大学の大規模実験(石井の研究)の結果、ざっくり示しますと 「創造的アイデアの出しやすさ」は、こうなりました。 出しやすく なった 3.90 3.54 3.23 変化なし ③瞑目して過ごす (≒何もしない) ①自由に動く ②抽象的な動きの指示を 実現するように身体を動かす さて、学術の話はここまでにして・・・
その指示内容を、遊びに仕立てました 想像力を刺激する動きカード
Ver.015 Sendai Imagine 2024年12月1日 Card イマジネーションを刺激するユニークな身体動作を生み出す指示カード
遊び方 (1) ❶ 全員にカードを均等に配ります。 ❷ 番の人は、手札から1枚選び、その内容を実行します。 (恥ずかしい、難しい場合は、紙に描くだけでもOK) ❸ 他のプレイヤーは、その内容を1回だけ推測できます。(一覧を見てOK) ❹ 最初に正解した人が1点を獲得し、カードは公開されます。 その後、次の人に番が移ります。 全員外れた場合もカードを公開し、次の人に移ります。 ❺ 個人戦では得点が最も多い人が勝ちとなります。 チーム戦の場合は全員の合計点で勝敗を決めます。 ゲーム時間は 「3分間」
b 創造工学の ミニレクチャー(雑談) 「ふうん?そうかー」ぐらいの 感じで気楽に聞いてください
凡案・駄案も出し切る。そこから更に出す • 「いいアイデアから、出す」のは、あまたの構造的に難しいです。 • 出し尽くして、あと10個考える。 • そうすると・・・ 27
変な考えも書きとめて、じっと眺める • そのままは使えない変な考えが、浮かぶ。 (初期の着想ってそういうものなんです) • でも、そういうのを全部、抑え込んじゃうと 「新しい考え」や「多様な(いろんな)考え」が、枯れちゃう。 • なので、それは一旦書きとめよう。 • そして、それに意味があるなら何だろうと考えみると、良い。 28
「考える」と「話す」を分けて行うブレスト 「Zebraブレスト」
(この手法の要点から言いますと) アイデア発想を 「一人時間⇔集団時間」 と交互に実施して、良案を引き出す 一人 発想の時間 集団 発想の時間 30
チームで発想する、といったら、 ずっと白熱の状態でいないといけない、という先入観がありますが、 実は・・・ output グ ル ー プ ずっと集団 一 人 グ ル ー プ 一 人 グ ル ー プ 時間 時間 「個人⇔集団」を繰り返す 複数人で行う知的作業のデザインのコツとして、知っておくと便利です。 31
Zebraブレストのやり方 一人発想 ブレスト 一人発想 ブレスト 2分 まずは一人で考えてみて、 思い浮かぶことをメモする。 5分 初期の着想をざっと共有し、 そこからアイデアを広げる。 8分 他の人の話から示唆を得て、 深く考え、アイデアを描き出す。 11分+α アイデアを共有しつつ、 更に発展させる。
実践 • 発想のお題: • プロセス: A4用紙は、メモ用や、 アイデアのプレゼンボード用にも、 お好きに使ってください。
発想のお題 「これって、不思議だな。」 (仮説の素材をたくさん出す) 探求のテーマとして適しているかどうかは気にせず、まずは気軽に、 素朴な疑問や日頃から気になっていることを自由に挙げてみる。 最終的には自分のチームのカテゴリ(数学、物理、地学など)に関連づける必要がありますが、 初めからそれを意識しすぎる必要はありません。 たとえば、「ヒットする漫画とそうでない漫画の違いは何か?」という疑問は興味深いものの、そのままでは 自チームのテーマとして扱うのは難しいかもしれません(テーマが広すぎたり、文系的な内容に見えるためです)。 ただ、このような疑問でも視点を変えて掘り下げれば、以下のような形で科学的なテーマに展開できる可能性が あります:「主人公のセリフの文字数が多すぎても少なすぎてもダメで、文字数とヒット作(巻数)には何らかの相関が あるのではないか?」 さらに掘り下げると、以下のような具体的な仮説が生まれるかもしれません: 「かいぞくおうに、おれはなる」(7文字、5文字)といったセリフのように、5文字や7文字の区切りが 発音しやすい。決め台詞の構造を分析することで、“数”的な法則を探求できるのではないか。(もしかして、ナントカ数 列に近いものだったり) なので、最初の「素朴な疑問」を大切にすることが非常に重要です。初めからテーマの絞り込みにこだわるよりも、 まずは自由に疑問や着想を出してみましょう。 思いもよらない発見や優れたテーマが見つかる可能性があります。
「不思議だな、とか、特にないんだけど。」 そういう場合は: 「日々、ストレスに感じること」 「みんなが嫌だなあと思っている(のにずっとそのままな)もの」 「たまたまなのか、原因があるのかわからないけど、 ふと気になる現象(とか、もの)を、見たなあ」(空模様でも生き物でも、人々でも) を雑談的に話すだけでもOK。
Zebraブレストのやり方 一人発想 ブレスト 一人発想 ブレスト 2分 まずは一人で考えてみて、 思い浮かぶことをメモする。 5分 初期の着想をざっと共有し、 そこからアイデアを広げる。 8分 他の人の話から示唆を得て、 深く考え、アイデアを描き出す。 11分 アイデアを共有しつつ、 更に発展させる。
メモ 集団浅慮を避けるには、 沈思黙考の時間を挟む (・・・と、ブレストの いい所を活かせます。) 37
Zebraブレスト 38
素朴疑問の共有 と 「仮説のブレスト」練習 39
1~2のサンプルチームの 「疑問」(~もし仮説まで出ていれば「仮説」)を全体へ紹介 • 他のチームは、その「疑問」から「そのチームのテーマに入るような 「仮説」(=そうなる仕組みって、もしかしてこうじゃない?) • を、3分ほどブレスト。 • いくつかのチームから、未成熟な(=全然確証のない)仮説で いいので、考えたことを、紹介してもらいます。 →サンプル発表チームは、収穫物を得る →他のチームは、自チームの題材のための「練習」となる。 40
「仮説のブレスト」実践 41
「疑問」を題材に、 「仮説」(=そうなる仕組みって、もしかしてこうじゃない?) を発想する (( 2章(共有&練習タイム)の感じで、各チームで、それを実践 )) 1. ここまで挙げてきた、いろんなレベルの疑問。 時間:20分 書記役は、 メモを取る 2. 自チームの題材として面白いものを1つ選ぶ。 • 良い疑問が複数ある場合は、第1テーマがダメになったときの保険として 確保しておこう。 で、今日は1つだけを題材にする。 3. その「疑問」から「自チームのカテゴリ(数学、物理、生物・・・)に入るような 【仮説】(=そうなる仕組みって、もしかしてこうじゃない?)を ブレスト的に話し合ってみる。 < 確証がなくてもいいんです。たくさん挙げるといいものも出ますから > 42
時間次第で 割愛 建設的な批判ありの 「アイデア・ディスカッション」 43
批判“あり”のディスカッションへ進もう。 研究可能なように、テーマを仕上げる。 批判は、 (毒)にも (薬)にもなる。ブレストよりも、慎重に。 「建設的な批判」(議論を前に進めるための指摘や、熟慮した異見)← 「感情的な批判」(欠点をあげつらって、留飲を下す)← ブレストの段階を終えて、今度は、 ブレストに「建設的な批判」も入れた感じの会議「アイデア・ディスカッション」を。 44
このセッションの目標: 科学的な「仮説の検証方法」を考え、描いてみる どうすれば、その仮説が正しいか、または間違っているかを調べられるかを検討する。 実験、試作、文献調査など、さまざまな調査方法を挙げてみる。ざっくりしたアイデアでもOK。 各方法について、「その検証方法では、どんな可能性が曖昧になるか」を 具体的に指摘し、それを改善する方法を考えてみる。 具体例 「文字数を調べて平均値を出すだけでは、有意な差が見つからないかもしれない。」 「ヒット作品と文字数の関係を調べるなら、漫画のセリフではなく、書籍タイトルと販売数を対象にしてみる のはどうだろうか?」 「ヒットする良い文字数がいくつかあぶり出せたなら。その数を並べたときに、ある種の数列に乗るものに なったりしていないかを調べるのは面白そう」←これはさらに拡散的な意見ですがこれもOK ポイント 仮説の検証方法を自由に考え、現実的かつ科学的に磨いていくこと。 時間は20分 書記は書き取ろう 45
まとめ・メッセージ 46
「研究テーマを定める」流れ • 「これって不思議だな」(=素朴な疑問) • 「そうなる仕組みって、 もしかしてこうじゃない?」(=仮説の生成) • 「そうかどうかは、 こうしたら確かめれるカモ」(検証方法の設計) 47
感想&疑問タイム 「学びになったこと」と 「疑問に思ったこと」を、 一人1分シェア ↓ のちに全体での質疑応答
メッセージ 49
「創造すらも習慣になる」 アレックス・オズボーン
使わなければ失う アレックス・オズボーン (想像力について use it or lose it 論じるくだりで) 51
(ディオゲネスか、キケロの言葉とされる) 52