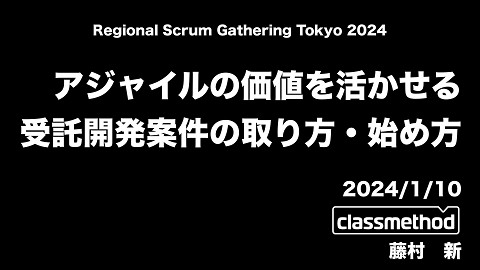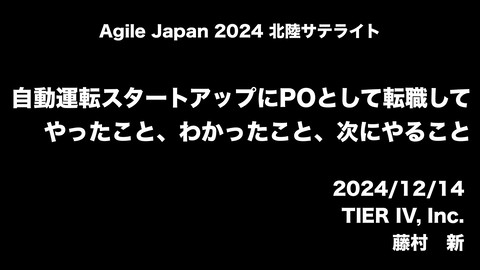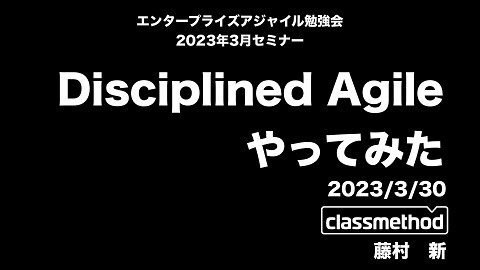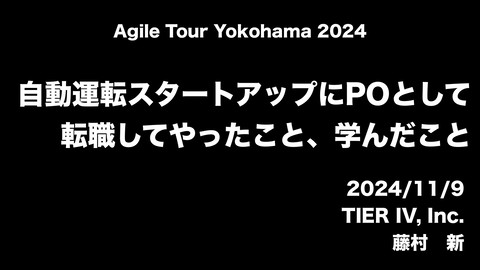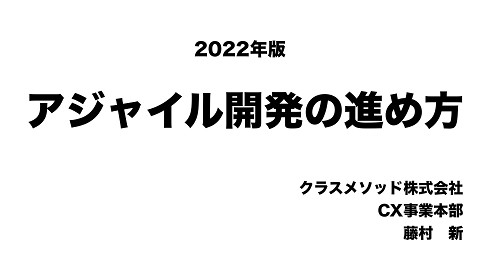豊田佐吉からアジャイルをたどる三河遠江ものづくり巡礼記
3.8K Views
October 04, 25
スライド概要
スクラム祭り2025沖縄トラックでの登壇資料です。
※@kawagutiさんとの共同登壇
https://confengine.com/conferences/scrummatsuri/proposal/23143/5dna
Agile Practitioner / CSP-SM, CSP-PO(Certified Scrum Professional) / Modern Offshore Development / Vietnam / Paris Hilton / RareJob / BOOKOFF / TIER IV, Inc.
関連スライド
各ページのテキスト
スクラム祭り 2025 沖縄トラック 豊田佐吉からアジャイルをたどる 三河遠江ものづくり巡礼記 @kawaguti @aratafuji
川口 恭伸 @kawaguti YesNoBut, Inc. RSGT実行委員会
•藤村 新 •@aratafuji •TIER Ⅳ, Inc. •転職多め(現在14社目) •尊敬する人: 岡本太郎
http://okamoto-taro.okinawa/map/
アジェンダ •第一部 •三河遠江ものづくり巡礼記 •第二部 •明治編:豊田佐吉と鈴木道雄の自動織機 •第三部 •戦後編:本田宗一郎はポンポンから始まりマン島に繋がる •第四部 •未来編:私たちが活かせることは
アジェンダ •第一部 •三河遠江ものづくり巡礼記 •第二部 •明治編:豊田佐吉と鈴木道雄の自動織機 •第三部 •戦後編:本田宗一郎はポンポンから始まりマン島に繋がる •第四部 •未来編:私たちが活かせることは
巡礼地 豊田佐吉記念館 • トヨタ産業技術記念館 • スズキ歴史館 • ヤマハ発動機 コミュニケーションプラザ • 本田宗一郎ものづくり伝承館 •
巡礼後の学び
アジェンダ •第一部 •三河遠江ものづくり巡礼記 •第二部 •明治編:豊田佐吉と鈴木道雄の自動織機 •第三部 •戦後編:本田宗一郎はポンポンから始まりマン島に繋がる •第四部 •未来編:私たちが活かせることは
豊田佐吉記念館
豊田佐吉 慶応3年2月14日(1867年3月19日)、遠江国 敷知郡山口村(現在の静岡県湖西市山口)に生ま れた。父は豊田伊吉、母はゑいであり、佐吉は3 男1女の長男だった。山口村は三河吉田藩領であ り、豊田家は伊吉が百姓のかたわら大工で生計を 立てていた。 https://ja.wikipedia.org/wiki/豊田佐吉
豊田佐吉像 (豊田佐吉記念館)
豊田佐吉 生涯、発明という夢を追い続けた。そして、青年時代は放 浪と出奔を繰り返した。19歳の時、同じ大工見習いの佐原 五郎作を誘い、家出をした。2人は徒歩で東京まで行っ た。しかし観光ではなく、工場ばかりを見て回った。23歳 の時は上野で開催されていた第3回内国勧業博覧会を見るた めに上京した。目的は外国製の機械と臥雲辰致の発明品を 見たかったからである。この2回の家出をはじめ、青年期の 佐吉は一ヶ所に長く留まることがなかった。彼はひたすら 各地を回り続けた。 https://ja.wikipedia.org/wiki/豊田佐吉
山口観音堂 (豊田佐吉記念館 となり)
山口夜学会 = 佐吉の夜間勉強会 1878年(明治11年)12月には吉津村川尻小学校を 卒業し、父のもとで大工の修業を始めた。だが18歳 のころ、「教育も金もない自分は、発明で社会に役立 とう」と決心し、手近な手機織機の改良を始めた。 1885年(明治18年)には二俣紡績(遠州紡績会 社)への就職を希望したが、父の反対で断念した。 1886年(明治19年)2月からは山口観音堂で青年 らによる山口夜学会を主導した。 https://ja.wikipedia.org/wiki/豊田佐吉
産業革命の第一の矢「飛び杼」 飛び杼(Flying Shuttle) 1733年、ジョン・ケイに よって発明 織物生産を飛躍的に向上さ せ、産業革命の引き金とな った しかし同時に、伝統的な手 工業者の生活を根底から覆 した 1750年代に描か れたジョン・ケイと される肖像。しかし 息子のジョン・ケイ ともされる https://ja.wikipedia.org/wiki/ジョン・ケイ̲(飛び杼)
産業革命の第一の矢「飛び杼」 https://ja.wikipedia.org/wiki/ジョン・ケイ̲(飛び杼)
豊田式木製人力織機 @ 豊田佐吉記念館 https://www.youtube.com/shorts/caYYFH3O̲EU
産業革命の進展は紡糸・自動織機とともに 1733年: 飛び杼(ジョン・ケイ)→ 織布効率向上 1764年: ジェニー紡績機(ハーグリーヴス)→ 紡糸生産の飛躍的向上 1768年: 水力紡績機(アークライト)→ より強力な糸の生産 1779年: ミュール紡績機(クロンプトン)→ 細く強い高品質糸 1785年: 力織機(カートライト)→ 蒸気機関による完全機械化 1811-1816年: ラッダイト運動 1868年: 明治維新 https://ja.wikipedia.org/wiki/ラッダイト運動
ラッダイト運動 (1811-1816年) ラッダイト運動はイングランドのノッテ ィンガムで始まり、1811年から1816 年頃まで地域全体の大衆運動として続い た。製粉所や工場の所有者は抗議者に発 砲し、最終的には法的・軍事的な力で運 動は鎮圧された。これには、ラッダイト として告発・有罪判決を受けた者たちの 死刑や流刑も含まれている https://ja.wikipedia.org/wiki/ラッダイト運動
自助論 (スマイルズ 1859年) 「ヴィクトリア朝中期の自由主義のバイブル」 と呼ばれ、「向上心ある中産階級のバイブル」 として、19世紀中頃の起業家精神と自己改善の 信念を体現した。 本書は18世紀啓蒙主義の3つの概念に基づいています: 1. 環境決定論:政府介入による個人発達の障害除去 2. 知的能力の段階的成熟:自己教育と自助の重要性 3. 慈悲深い自然秩序の存在 https://en.wikipedia.org/wiki/Self-Help̲(Smiles̲book)
『西国立志編』(スマイルズ『自助論』の抄本) 明治4年7月出版 https://www.tamagawa.ac.jp/museum/archive/1994/041.html
『西国立志編』(スマイルズ『自助論』の抄本) 欧米人300人の成功談を集めた自己 啓発本の古典。序文の「天は自ら助く る者を助く(Heaven helps those who help themselves)」とい う言葉が特に有名。日本では「 西国 立志編」という名前で発刊され、福澤 諭吉の「学問のすすめ」と並んで「独 立自尊を説く書」として読まれた。 https://jinjibuchou.com/自助論
山口夜学会で西国立志編を輪読していた 豊田佐吉像
共創
SECIモデル (野中郁次郎)
『西国立志編』(スマイルズ『自助論』の抄本) 「天は自ら助くる者を助く」 これは、今まで人類が経験してきたすべての成功と 失敗の経験から生まれた言葉です。「自ら助く」と は、自立して他人に頼りきらないということです。 この自助の精神から、人間の才知というものは生ま れてきます。自助の精神を備えた人が多くなればな るほど、その国家は活気に満ち、繁栄していきま す。
『西国立志編』(スマイルズ『自助論』の抄本) 他人に頼りきった結果成就したものは、その後必ず衰えて いきます。 これに対して、自分自身の力で成し遂げたことは、必ず発 展しますし、その発展を妨げることができないほど強い勢 いを持ちます。 他人に多くの援助をすればするほど、援助を受けた人は自 分自身で頑張ろうという気持ちを失ってしまいます。ま た、上に立つ者が、厳しすぎるほど指導してしまうと、下 の者は自立しようという気持ちを持たなくなってしまいま す。
『西国立志編』(スマイルズ『自助論』の抄本) 人々を抑圧する政治や法律は、 人々の経済的自立を失わせ、 その活動を弱めてしまうことに なります。
現代語訳 西国立志編 第二編 中村正直序文 現代の西洋人はまことに幸福である。 古代の王様をしても、その幸福にははるかに及ばない。 昔は、国の四方が閉ざされており、浅い知識しか持たなかった。 今や、世界中を飛び回り、深遠な学問が手に入る。 昔は、民衆の教化がうまくいかず、その国民性は惨たんたるものであった。 今では、民衆も天を崇拝し、謙虚で誠実な志をもって物事を行う。 昔は、君主は専制政治を行い、人々はその奴隷のようであった。 今は、人々は自由の権利を得、ともに社会の利益のために邁進する。 昔は、法律や政権で人々を縛り、人々の心は抑圧されていた。 今は、王でなくても、人々は自らの意思により物事を選択する。 昔は、俗人は勇ましさと強さを尊び、時として無残な行為をした。 今は、人々は平和をたしなみ、互いに熱く友愛の感情を持つ。
現代語訳 西国立志編 第二編 中村正直序文 つづき 昔は、貿易においても、支配者がそれを厳しく制限した。 今は、自由に貿易を行い、さまざまなものが流通する。 昔は、製造業が盛んでなく、それによる利益が生まれなかった。 今は、原材料を輸入し、製造された物を輸出することで、大きな利益を得る。 昔は、住居は狭苦しく、設備も整っていなかった。 今は、住居は広く美しく、すばらしい設備に囲まれている。 昔は、調度品も粗末なものであって、品質もよくなかった。 今は、美しい調和品にあふれ、快適な生活を送る。 昔は、ただ空腹を満たすだけに、土地は用いられていた。 今は、珍しい茶菓が食卓に並び、毎日供される。 昔は、山海がわれわれを遮り、諸国を周遊することは困難を極めた。 今は、汽車や船舶を使えば、座っているだけで遠方に行ける。
現代語訳 西国立志編 第二編 中村正直序文 つづき 昔は、遠くにいる人に自分の意志を告げるには多くの時間を要した。 今は、電報で急を告げ、千里離れていようと許すことができる。 昔は、夜になると街は闇に包まれ、ならず者が潜んでいた。 今は、街が昼のごとく明るく照らし、人々が緊張することなく歩く。 昔は、鳥や魚では伝言を届けることができず、急難に遭っても声をのむしかなかった。 今は、わずかな切手代で、伝言は全国に届く。 昔は、貧しい労働者は、金を得ればすぐに使ってしまった。 今は、銀行に預ければ、利子が付いて還ってくる。 昔は、ちょっとした本であっても、裕福な人ですら収集しづらかった。 今は、書店に満ちあふれ、貧しい人でもたやすく手に入れることができる。 昔は、人々に知られていない物事があまりにも多すぎた。 今は、さまざまな考えや世論が、日々活字となっていく。
現代語訳 西国立志編 第二編 中村正直序文 つづき 確かに、今から五十年前と百年前とを比較すれば、そこには大きな開きが生じる。 しかし、今日の西洋では、わずか五十年前と比較しても、 天と地ほどの開きがそこに存在するのだ。 このような幸運は、何によって生じるのか。 もちろん人々が教化されることによって、人々の心がよい方向に 向かっているためである。 しかし、科学の粋を究めて優れた発明をする者がいなければ、 人々の生活は発展しない。 このことを考えれば、 優れた発明をした者の功徳というものがわかることであろう。 中村正直 無所争斎に題す
『学問ノスゝメ』(福沢諭吉) 長く続いた封建社会と儒教思想から脱 し、近代民主主義国家に相応しい市民 への意識改革を促す大ベストセラー啓 蒙書。「天は人の上に人を造らず人の 下に人を造らず」という書き出しで有 名。 (中略) 時代は変わった。日本は古臭い儒教思 想や慣習を捨て、西洋に学び、社会契 約を基礎とした法治国家を打ち立て、 独立を守らなければならない。 https://jinjibuchou.com/学問のすすめ 大阪大学適塾記念センター展示の複製本 明治5年2月初編出版
豊田式木製人力織機へ 佐吉というのは大工の息子でし た。何をしたら、この世の中のた めになるんだろうかと、日々いろ んな本を読んで勉強していたそう です。 そういう中で佐吉少年が気付いた のは、毎晩、夜なべをしてお母さ んが機織り仕事をしていた…、そ の仕事を楽にできないのかなとい うこと。それが佐吉少年の着眼点 だったんです。 (豊田章男) https://toyotatimes.jp/spotlights/091.html
江戸時代に作られた高い識字率 寺子屋制度の制度的特徴 1. 民間主導の教育システム 国家統制ではなく民間資本による運営 地域コミュニティによる自発的な教育投資 市場メカニズムによる教育の質の競争 多様な教育内容とアプローチ
江戸時代に作られた高い識字率 包括的制度の特徴 • 広範な社会参加: 武士階級に限定されない教育機会 • 経済的インセンティブ: 読み書き算盤による実用的技能 • 社会的流動性: 教育による地位向上の可能性 • 分権的運営: 中央集権的統制の不在
この変革は当たり前のものではない 収奪的制度との対比: 多くの国では国家や権力者が発明を「没収」 発明者に利益が還元されない構造 イノベーションへの動機の欠如 技術進歩の停滞
名誉革命(1688-1689年) 名誉革命は偉大なる革命(Glorious Revolution)とも呼ばれる。この 革命により、イギリスにおけるカトリ ックの復権の可能性が完全に潰され、 イングランド国教会の国教化が確定し ただけでなく、権利の章典により国王 の権限が制限され、イギリスにおける 議会政治の基礎が築かれたからであ る。 https://ja.wikipedia.org/wiki/名誉革命
名誉革命(1688-1689年) 1. 名誉革命(1688年)の制度的変革 政治制度の根本変化: 議会主権の確立: 国王の絶対的権力の制限 財産権の憲法的保障: 国王による恣意的な没収の禁止 法の支配: 予測可能で一貫した法的環境の創出 司法の独立: 政治的干渉からの裁判所の保護
名誉革命(1688-1689年) 2. 産業革命(1760年代 )への直接的影響 イノベーションの制度的基盤: 発明者の権利保護: 国家による技術没収の心配なし 長期投資の安心感: 政府による突然の政策変更リスク の減少 契約の信頼性: 政府が一方的に契約を破棄しない保証 ~ 市場経済の発展: 国家統制からの自由な商業活動
名誉革命(1688-1689年) 名誉革命なしには産業革命は不可能だった理由: • 技術没収のリスク: 絶対君主制下では有望な技術は国王が接収 • 投資の不確実性: 政策変更により突然事業が禁止される可能性 • 法的予測可能性の欠如: ルールが恣意的に変更される環境 • 財産権の脆弱性: 成功した事業が権力者に奪われるリスク
マックス・ヴェーバーの分析 経済制度との相互作用: • プロテスタント的勤労倫理 → 経済活動への動機 • 制度的保障 → 長期投資への安心感 • 個人主義 → イノベーションの促進 • 両者の相乗効果
トヨタ産業技術記念館 の 織機展示の再発見
トヨタ産業技術記念館 の 織機展示の再発見
トヨタ産業技術記念館 の 織機展示の再発見
豊田式木製人力織機 佐吉が特許を得た「豊田式木製人力織機」 は、これまで両手で織っていたものを片手で 織れるように改良したもので、織りムラがな く品質は向上し、能率も4 5割向上した。 しかし、基本的に人間が手で織る織機であっ たため、それ以上の能率向上は難しかった。 佐吉は、いよいよ本格的に、手で織る織機か ら動力で織る織機の発明に向かうことになっ た。 豊田佐吉記念館 ~ https://www.toyota-shokki.co.jp/company/history/toyoda̲sakichi/
自ら織布工場を開く 経済的な独立を果たすとともに発明のための 研究資金を確保する必要があった。また、発 明した織機をまず自分自身で使用することに より、そのできばえを確かめ、自信をもって 人に薦めようと考えた。そのため、1892年 (明治25年)、佐吉は、自ら発明した豊田 式木製人力織機数台の小さな織布工場を現在 の東京都台東区千束に開業した。 https://www.toyota-shokki.co.jp/company/history/toyoda̲sakichi/
(株)豊田自動織機 佐吉の作る布は問屋筋からは好評だったが、 工場の経営を行いながら発明に取り組む中 で、経営は次第に苦しくなり、開業して1年で 工場を閉鎖せざるを得なくなった。工場を閉 じて、郷里に帰った佐吉であったが、ほどな くして、豊橋のおじを訪ね、その家に住み込 みながら、動力織機の研究を始めた。 発明のための資金を確保するため、1894年 (明治27年)、佐吉は、紡いだ糸を織機のた て糸用に効率的に巻きかえる、画期的な豊田 式糸繰返(とよだいとくりかえし)機を完成し た。 https://www.toyota-shokki.co.jp/company/history/toyoda̲sakichi/
トヨタ産業技術記念館 糸繰返機の販売が軌道に乗る中で、動力織機 の発明に一心不乱に取り組み、佐吉は、 1896年(明治29年)、日本で最初の動力 織機である木鉄混製の豊田(とよだ)式汽力織 機(豊田式木鉄混製動力織機)を完成する。 開口、杼入(ひい)れ、筬打(おさう)ちを人力 から動力に替え、よこ糸が切れたら杼が止ま り自動で停止する装置や、布の巻き取り装置 などを備え、安価な上に、生産性や品質も大 幅に向上した。 https://www.toyota-shokki.co.jp/company/history/toyoda̲sakichi/
トヨタ産業技術記念館 1903年(明治36年)、機械を止めずによこ糸 を自動的に補充する最初の自働杼換(ひがえ)装置 を発明し、それを装備した世界初の無停止杼換式 自動織機(豊田式鉄製自動織機(T式))を製作 した。鐘淵紡績株式会社は、この自働杼換装置を これまで取り付けたことがない広幅の織機に取り 付け、性能試験を行った。しかし、製作と試験を 他人任せにしたため、結果は芳しいものではなか った。このときの反省から、「創造的なものは、 完全なる営業的試験を行うにあらざれば、発明の 真価を世に問うべからず」という考え方が佐吉の ゆるぎない信念となった。 https://www.toyota-shokki.co.jp/company/history/toyoda̲sakichi/
https://ja.wikipedia.org/wiki/高峰譲吉 さらに、後述する欧米視察時に、タカジ アスターゼの発明やアドレナリンの抽出 などの世界的な業績で知られる高峰譲吉 博士をニューヨークの邸宅に訪ねた際、 博士から「発明家たるものは、その発明 が実用化されて社会的に有用な成果が得 られるまでは決して発明品から離れては ならない。それが発明家の責任である」 と激励され、その信念は一層強固なもの となった。 https://www.toyota-shokki.co.jp/company/history/toyoda̲sakichi/
豊田佐吉の開発の信念 トヨタ産業技術記念館 豊田佐吉は、発明品を世にだすに あたり、事前に徹底的な営業的試 験を行い、機械の品質はもとよ り、織物工場での採算性の確認ま でも行った。そうした背景には、 「発明は製作を完全にし、十分な 営業的試験をしなければ世に出し てはいけない」という強い信念が あったからである。
SECIモデル (野中郁次郎)
自動織機の特許をイギリストップメーカーに売却 豊田自動織機製作所製の「G型自動織機」は海外 でも高く評価され、インドの織布工場に205台 が納入されていた。これに対して、英国の紡織機 メーカーであるプラット社は、自社の重要な市場 を保全するため、豊田自動織機製作所の特許権を 買い取ることとし、(中略)自動織機の特許権譲渡 に関する交渉を進め、同年9月には契約調印のた めに喜一郎が渡航することになった。 https://www.toyota.co.jp/jpn/company/history/75years/text/ taking̲on̲the̲automotive̲business/chapter1/section4/item2.html
SECIモデル (野中郁次郎)
そのついでに自動車産業を調査 https://www.businessinsider.jp/article/ 2504-travel-commuting-work-old-photos/ かねてから自動車製造の夢を抱いていた喜一郎 は、2度目の渡航によって欧米の産業構造の変化 を実感し、わが国における自動車産業の必要性を 改めて認識した。喜一郎に随行した原口晃(豊田 自動織機製作所常務取締役)や古市勉(三井物産 社員)によると、喜一郎はフォード社の自動車製 造工場の視察や工作機械の調査に没頭していたの であった。 https://www.toyota.co.jp/jpn/company/history/75years/text/ taking̲on̲the̲automotive̲business/chapter1/section4/item2.html
実は佐吉もアメリカに行っていた • 1910年(明治43年)4月5日、 豊田式織機株式会社の常務取締役を解任。 • 1910年(明治43年)5月8日、 日本郵船の因幡丸で、西川秋次を伴い渡米する。 • 1911年(明治44年)1月1日、 欧州を回った後、下関へ帰国。 • 1925年(大正14年)8月10日、 「無停止杼換式自動織機G型」を完成・特許取得 https://ja.wikipedia.org/wiki/豊田佐吉
障子を開けてみよ 外は広いぞ
議論を先にすることをやめた (豊田喜一郎) 私は最初議論を先にして実地をあとにしたが、 父とあることについて議論して私の方が勝った すなわち実行して見る価値なしと判断した。 その時とにかくやって見よといわれたので 止むを得ずやって見た。 それが私の予想を裏切って良い成績を示したことがあり これからもう議論を先にすることをやめた。 豊田喜一郎「自生い立ちの記 自動機の思い出話」
浜松の鈴木道雄 1909(明治42)年、鈴木道雄 は21歳の若さで浜松市に「鈴木 式織機製作所」を設立しました。 なぜ織機なのかというと、遠州 (静岡県西部)地方は江戸時代か ら綿花の栽培が盛んだったので、 織機に対する需要が多かったこと が背景にあります。 https://clicccar.com/2020/08/01/998360/
鈴木式織機 1929(昭和4)年には、独特な 格子柄を効率よく織れる「サロン 織機」を開発して海外にも進出。 サロンとは、インドネシアなどの 民族衣装(腰巻)で鮮やかなサロ ンを織れる鈴木式織機は大人気と なり、2万機以上販売したインド ネシアでは「SUZUKI」が織機 を表す言葉になったほどです。 https://clicccar.com/2020/08/01/998360/
豊田佐吉・喜一郎の動きに触発される 「サロン織機」で大成功を収めた鈴木道雄 社長でしたが、半永久的に使える織機では 事業展開に限界があり、また、景気に大き く左右されることに将来への不安を抱いて いました。一方、隣の三河(愛知県東部) では1933(昭和8)年に豊田佐吉が豊田 自動織機に自動車部を設けて、長男の豊田 喜一郎が自動車事業への方向転換を目指し ていました。 https://clicccar.com/2020/08/01/998360/
スズキもカーメーカーへ この豊田自動織機の動きに触発さ れ、鈴木道雄社長は1936(昭和 11)年に娘婿の鈴木三郎に研究 開発を指示。鈴木三郎は、すぐさ ま英国の小型車「オースチン」を 購入して分解調査を開始。豊田喜 一郎が大型乗用車の国産化を目指 したのに対して、鈴木道雄は小型 車を目指しました。 https://clicccar.com/2020/08/01/998360/
アジェンダ •第一部 •三河遠江ものづくり巡礼記 •第二部 •明治編:豊田佐吉と鈴木道雄の自動織機 •第三部 •戦後編:本田宗一郎はポンポンから始まりマン島に繋がる •第四部 •未来編:私たちが活かせることは
独創
豊田 喜一郎(とよだ きいちろう: 1894 - 1952) • 静岡県敷知郡吉津村山口(現: 湖西市山口)で生まれる • スミス・モーター・ホイールを購入・分解・複製・成形し、社内で実験 を実施(1930年頃) • 豊田自動織機製作所内に自動車部を設立(1933年) • A1型試作乗用車、G1型トラックを発表(1935年) • AA型乗用車、GA型トラックを発表(1936年) • 豊田利三郎の後任としてトヨタ自動車工業の第2代社長に就任(1941年)
トヨタ産業技術記念館(スミス・モーター・ホイール) https://www.tcmit.org/vgt/car/scene-01/
トヨタ産業技術記念館(スミス・モーター・ホイール)
トヨタ産業技術記念館(スミス・モーター・ホイール) https://www.tcmit.org/vgt/car/scene-01-iframe/target-02/
トヨタ産業技術記念館(A1型試作乗用車)
トヨタ産業技術記念館(G1型トラック)
トヨタ産業技術記念館(AA型乗用車)
本田 宗一郎(ほんだ そういちろう: 1906 - 1991) • 静岡県磐田郡光明村(現: 浜松市天竜区)で生まれる • エンジン部品のピストンリングを生産する東海精機重工業設立(1937年) • 豊田自動織機が株の半分を出資し、役員には石田退三(トヨタ自工第3代社長) • 東海精機重工業の全株を豊田自動織機に売却して退社(1945年) • 本田技術研究所設立(1946年) • 陸軍払い下げの無線機用発電機を自転車に取り付けて販売(1946年) • 独自のエンジン開発に着手し「A型エンジン(50.3cc)」を完成(1947年) • フレームから自社製の「ドリーム号(D型エンジン・98cc)」を完成(1949年) • 自転車用補助エンジン「カブ号F型」を発売(1952年)
『本田宗一郎 本伝』 https://www.amazon.co.jp/dp/B00BHTPPS0/
本田宗一郎ものづくり伝承館(ホンダC型)
本田宗一郎ものづくり伝承館(ホンダカブF型)
鈴木 俊三(すずき しゅんぞう: 1903 - 1977) • 浜松高等工業学校(現: 静岡大学工学部)卒業 • 「釣りに行くのに自転車にエンジンが付いていたら便利」という発想のもと 研究開発を開始 • 「パワーフリー(36cc)」を開発・販売(1952年) • 石田退三の働きかけで、愛知トヨタがダイヤモンドフリーを販売(1953年) • 鈴木道雄の後任として鈴木自動車工業の第2代社長に就任(1957年) • 本田宗一郎の働きかけで、英国マン島TTレースへの出場を決意(1959年)
スズキ歴史館(パワーフリー)
川上 源一(かわかみ げんいち: 1912 - 2002) • 静岡県浜名郡豊西村(現: 浜松市中央区)で生まれる • 日本楽器製造(現ヤマハ)の第4代社長に就任(1950年) • 日本楽器製造内で、オートバイエンジン事業の進出を決定(1953年) • ドイツDKW社の2ストローク「RT125(125cc)」をベースに開発を開始 • 日本楽器製造 浜名工場を設立(1955年2月) • 空冷2ストロークの「YA1(125cc)」が完成、出荷(実質8ヶ月間) • ヤマハ発動機を設立(1955年7月) • 第3回富士登山レース、第1回浅間高原レースで圧勝(1955年7月、11月)
ヤマハ発動機 コミュニケーションプラザ(YA-1)
競創
1953年〜1954年 • 1953年 • 第1回富士登山レース • 2サイクル60ccのダイヤモンドフリー号で出場し、優勝(スズキ) • 1954年 • 第2回富士登山レース • 4サイクル90ccのコレダCO号で出場し、2年連続優勝(スズキ) • ブラジル・サンパウロ市制400年記念祭 • 日本メーカー初の国際レース。「R125」はトップから2周遅れの13位/18台(ホンダ) • 本田宗一郎、TTレース出場宣言 • その後マン島TTレース視察。「向こうのほうが、三倍性能が良い」(ホンダ)
スズキ歴史館(ダイヤモンドフリー)
スズキ歴史館(コレダCO)
https://www.honda.co.jp/WGP/spcontents2015/700win/history/p01/
1955年 ~ • 第3回富士登山レース • 125ccクラスで「YA1」が優勝、10位以内に7台(ヤマハ) • 250ccクラスで「ホンダドリーム」が1位、2位、5位(ホンダ) • 第1回全日本オートバイ耐久ロードレース(浅間高原レース) • ウルトラライト級(125cc) • 「YA1」が1 3位を独占(ヤマハ) • 「コレダ」が4〜5位(スズキ) • 125cc, 250ccとも惨敗(ホンダ)
ヤマハ発動機 コミュニケーションプラザ(YA-1)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Asama̲Street̲Circuits.png
浅間高原レースの情報戦 “ヤマハが浜松に部品を頼んだり、練習のタイ ムを報告する電話は、どういうわけかライバ ルチームに筒抜けだった。それがわかったあ と、ヤマハは電話で“ニセの報告”をすること にしたらしい。本当の報告は速達で行ない、 緊急の連絡はドイツ語を暗号にして使った。 これが今でもヤマハが言う“養狐園の情報戦” だったのである。”
1956年〜1958年 ~ ~ ~ • 1956年 • 第4回富士登山レース • 125ccクラスで「YA1」が1 8位、250ccクラスで「YC1」が1 5位を独占(ヤマハ) • 1957年 • 第2回全日本オートバイ耐久ロードレース(浅間火山レース) • ウルトラライト級(125cc)で「YA Racer」が1、2、5位(ヤマハ) • ライト級(250cc)で「YD Racer」が1 3位を獲得(ヤマハ) • 再び完敗。本田宗一郎は涙を流す(ホンダ) • 1958年 • アメリカ・第8回カタリナグランプリレース • 国際レース(250ccクラス)初出場で6位入賞(ヤマハ) • 本田宗一郎、来年、マン島レースに出場して優勝宣言(ホンダ)
1959年〜1960年 • 1959年 • 秋山邦彦氏、箱根の山道で映画撮影中に事故死(ホンダ) • 英国マン島TTレース • 日本勢の先陣を切って出場。谷口が6位入賞、鈴木が7位、田中が8位で、チーム賞を獲得(ホンダ) • 「井の中の蛙でした」(河島監督: 本田技研第2代社長) • 第3回浅間火山レース • 125ccクラスで1位〜4位、250ccクラスで1位〜5位を独占(ホンダ) • 優勝したのはアマチュア枠の北野、メカニックは浜松製作所の市販車(ベンリイCB92) • 1960年 • 英国マン島TTレース • 125ccクラスで谷口が6位。250ccクラスでブラウンが4位、北野が5位、谷口が6位(ホンダ) • 125ccクラスのRT60で初挑戦、全車完走しブロンズレプリカ賞獲得(スズキ) • ブラウンがドイツGPの練習走行中に事故死(ホンダ)
本田宗一郎ものづくり伝承館(ベンリイCB92)
「だから一緒に出ましょう」 “浅間が終わったあとのある日、東京駅から浜松へ の急行に乗った鈴木俊三社長は、本田宗一郎社 長と顔を合わせる。浜松への車中で宗一郎氏は 「世界へ出ろ」と説いた。 「うちの連中も、おたくにはタジタジだった。み んなRBは速い、と感心していましたよ。これか らは日本だけにこだわっていては駄目です。世界 に目を向けるべきです。うちを見なさい。来年 も再来年も出ます。だから一緒に出ましょう」”
制覇
1961年 • 世界GPロードレース第1戦(スペインGP) • 125ccクラスでトム・フィリスが優勝。日本のチームが国際レースで初優勝(ホンダ) • 世界GPロードレース第2戦(ドイツGP) • 250ccクラスで高橋国光が優勝。日本人ライダーが国際レースで初優勝(ホンダ) • 世界GPロードレース第3戦(フランスGP) • 125ccクラスでトム・フィリスが優勝(ホンダ) • 初参戦。RD48で伊藤が250ccで8位、野口が125ccで8位(ヤマハ) • 世界GPロードレース第4戦(英国マン島TTレース) • 125ccクラスで1位〜5位を独占(ホンダ) • 250ccクラスで1位〜5位を独占(ホンダ) • 伊藤が250ccクラスで6位入賞(ヤマハ)
ヤマハ発動機 コミュニケーションプラザ(RD56)
全てが素晴らしい発想から生まれた独創的 “ホンダのあまりの速さに「事後調査」が申し出さ れ、各国の委員の前でホンダのマシンは分解さ れ、排気量に偽りがないかを調べた。それに立ち 会った英国人のひとりは、「ホンダのレーサーの エンジンの中を見た時、それがあまりにも良く出 来ていたので、率直に言って我々は恐怖感に襲わ れた。ホンダのエンジンはまるで腕時計のように 精密に出来ていて、その上そこには何の模倣の跡 もなく、全てが素晴らしい発想から生まれた独創 的なものだった」と舌を巻いた。”
1962年 https://ja.wikipedia.org/wiki/1962年のロードレース世界選手権 1963年 https://ja.wikipedia.org/wiki/1963年のロードレース世界選手権 1964年 https://ja.wikipedia.org/wiki/1964年のロードレース世界選手権
レギュレーションの変更 “ヤマハの快進撃は続いた。1965年、250ccで2年連続となるライダー/メーカー チャンピオンに輝いた。1967・68年は、マン島TTでの4連勝(1965・68年) を含め、125ccのライダー/メーカータイトルを獲得。(中略)ヤマハが快調に飛ば すと、同年にホンダは4ストローク6気筒のRC165を投入、その後の各社は多気筒 化、高出力化へと突き進んでいくのだった。 1967年のヤマハは新たにV型4気筒250ccのRD05Aを投入したが、エスカレート する日本メーカーの多気筒化、ハイパワー化に歯止めをかけるため、FIMは1967年 末、1970年以降、125ccは単気筒、250cc以下は2気筒、ミッション6速という 新規則を発表。これを受けて、ホンダとスズキはWGPからの撤退を決めた。” https://global.yamaha-motor.com/jp/race/wgp-60th/history/
世界制覇の要因 • 「日本全国民が一時オートバイ気狂い(略称・オトキチ)になった」 • 国内用を目指してまず量産方式成功 • この勢力を持って国外に乗り出し、古くさい町工場的少量生産方式を一蹴 • 戦後、中島飛行機など軍需産業の技術者を多く採用した • 新進気鋭の技術者が旧来のささやかなオートバイ専門技術者を完全に圧倒した • 常識や旧慣に捉われることのない斬新技術を思った通りに駆使した • 生産設備がすべて新設であるため、世界最高の効率のものの採用が可能だった • テスト方式が単なる勘によるものから離脱、科学的方法が漏れなく適用された • 教育レベルが高く、労働の質が良かった 『日本のオートバイの歴史』pp.227-232より要約
航空機関係の技術者 “宗一郎氏が航空機関係の技術者を招いたのは “これからのオートバイのエンジンに必要なの は一にも二にも耐久性”という信念からだっ た。耐久性を上げるためには各部分の精度向上 が不可、それには飛行機のエンジンに学ぶのが ベスト、ということに異論を唱える人はいるは ずもなかった。”
巨額の投資 “精度の高い部品の積み重ねで実現するそれをつ くるには優れた加工精度を持つ、最新式工作機 械の導入が急務と考えたホンダは、昭和27年 10月に世界の先進国からそれらの工作機械を 輸入することを決定した。アメリカ、ドイツ、 イギリス、そしてスイスから輸入される工作機 械の総額は、資本金600万円のホンダにとっ て約80倍にあたる4億5000万円の巨額にの ぼった。”
日本製オートバイの世界制覇 “昭和37年(1962年)頃から、世界各地 のグランプリ・レースにおける日本車の 優勝は常識化する。その為、本国にいる 日本人の大半も、レースの結果に胸踊ら すことも次第にうすらぐことになり、 もっぱら輸出成績などに関心を持つこと になる。”
ベトナムのメーカー別シェア(2022年)
中国のメーカー別シェア(2022年) (SUZUKI)
アジェンダ •第一部 •三河遠江ものづくり巡礼記 •第二部 •明治編:豊田佐吉と鈴木道雄の自動織機 •第三部 •戦後編:本田宗一郎はポンポンから始まりマン島に繋がる •第四部 •未来編:私たちが活かせることは
キーワード 世界を、学ぶ • 学んだら、作る • 作ったら、世界に挑む • 浜松という地域性、競争と切磋琢磨 • 現代の、学ぶ・作る・挑む •
SECIモデル (再掲)
山口観音堂
Discord(ディスコー堂)
浜松地域における 産業発展の系譜 ナガネンノ ツミカサネダ 平成 西暦 2000 昭和 1990 1980 バブル景気 1986(昭和61) 〜1991(平成3)年 1970 1960 大正 1950 高度成長期 1940 1930 明治 1920 1910 1900 江戸 1890 太平洋戦争 1954(昭和29) 〜1973(昭和48)年 明治維新 1941(昭和16) 〜1945(昭和20)年 1867(慶応3)年 東海道新幹線開業 東海道線開通 1964(昭和39)年 1889(明治22)年 鉄道院浜松工場開設 遠州・三河織物全盛期 1912(大正元)年 1935(昭和10) 〜1937(昭和12)年 1950年代 オートバイ会社の乱立 輸送機械 成 長 産 業 6 分 野 へ ※ 6 分 野 の 詳 細 は 次 ペ ー ジ へ 自動車の試作〜 オートバイ製造 自動車 オートバイ 光産業 エレクトロニクス 精密機器 一般機械 工作機械 ミシン 高度な技術の集積 世界市場でも通用する製品を生み出 す た め の 鋳 造(ちゅうぞう)、切 削 (せっさく)、鍛造(たんぞう)、熱処理 など多様な技術を持つ企業が誕生。 また、エレクトロニクス技術分野の研 究開発が進む中で分野間の技術が融 合し、高度な技術が集積。 自動車の試作が始まるも、研究は戦 争により中断となる。戦後、手軽な 平 和 産 業 へ の 転 換 オートバイが注目され、多くの町工 場が生産に乗り出した。1950年代 になると30社近いメーカーが乱立。 成長を支える風土 綿織物 東海道の中心にあって、東西の 文化が接触する地域の中で、よ そ者を受け入れる土壌や自主・ 独立の気風が育った。二宮尊徳 による報徳思想の普及もあって 勤労意識が高まり、明治以降の 街の発展につながっている。 織機製造の発展 終 戦 軍 事 産 業 化 プロペラ 製作 工作機械 機械の製作 織機(しょっき)製造は大工の片手間 仕事から始まり、日露戦争後の満州 への織物輸出の増加に伴い、手織機 や足踏機の製造へと進んだ。さらに 豊田佐吉や鈴木道雄らが開発した 「力織機(りきしょっき)」が繊維産業 を飛躍させた。 木工機械 合板の導入 1903(明治36)年 木工機械 製 材 楽器工場の創設が 相次ぐ 1932(昭和7)年頃 楽 器 1889(明治22)年 6 底 力 の 証 明 ︑ イ ノ ベ ー シ ョ ン は 一 日 に し て 成 ら ず ! な る ほ ど ・ 浜 松 も の づ く り 発 展 史 5 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/documents/44245/04.pdf
浜松企業の競争力 • 浜松地域の歴史・風土 • 勤勉の風土 • よそ者を受け入れる風土 • 浜松の人は権力者の庇護を受けたことがないので、独立独歩の気風が強い • 浜松には企業を起こす土壌がある • 「やらまいか精神」がもたらす激しいライバル競争の展開 • 浜松製造業の特徴 • 江戸時代からの長い製造業の歴史があり、いつも時代の先端を行く産業を育んできた • 大企業が時代の変化にうまく適応して成長を持続させた • 規模拡大後も本社工場や R&D センターは浜松が拠点(トヨタとホンダ以外)で全面的移転はない • 浜松高等工業学校(現静岡大学工学部)が産業の発展・テクノロジーに大きく貢献している • ベンチャー企業が絶え間なく生まれる土地柄である https://www.toyo.ac.jp/assets/research/966.pdf
世界に挑む •「障子を開けてみよ、外は広いぞ」(豊田佐吉) •「来年、マン島レースに出場し、優勝するぞ」(本田宗一郎) •「外国のメーカーが6年かかってタイトルをとるなら、うちは3年 でやらなきゃダメだ」(本田宗一郎) •「うちを見なさい。来年も再来年も(マン島レースに)出ます。だか ら一緒に出ましょう」(本田宗一郎から鈴木俊三へ) •「そうだ、自動車メーカーのない国に出れば、間違いなく一番にな れる。単純だ」(鈴木修)
そしてホンダ初代シティからスクラムへ https://youtu.be/Z5lBjmPy5QI https://youtu.be/ipuwbFanqMY
書き起こされ、伝えられ、検証されていく ff https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game https://je sutherland.com/scrum/RootsofScrumJAOO28Sep2005.pdf
Agile and Lean Patterns The New New Product Development Game Manufacturing Industry in Japan Toyota Production System XP Scrum Lean Software Development Lean Agile Kanban Lean Startup 2013 Yasunobu Kawaguchi Startup Four steps to the epiphany
初代プリウスからスクラムへ https://youtu.be/mOojDjtmbGE https://youtu.be/tLbvnxCkXWA ff https://je sutherland.com/scrum/RootsofScrumJAOO28Sep2005.pdf
初代プリウスからスクラムへ トヨタ・プリウス -創発的戦略 • 製品、技術、プロセスの革命 - どの製品ラインにも当てはまらない。 新しい視点で設計されている。 • 多くの技術を使用 - エンジン、モーター、バッテリー、ブレーキを 組み合わせたハイブリッドシステム • 記録的な速さで開発 - 4年かかるものが15ヶ月で • 重複するフェーズ - 研究、開発、設計、生産 • リーダーが作り、利用し、エナジャイズした場(Ba) ff https://je sutherland.com/scrum/RootsofScrumJAOO28Sep2005.pdf
https://youtu.be/tLbvnxCkXWA
SECIモデルの循環が私たちまで回ってきた
自動運転の競争 •DARPAグランド・チャレンジ(2004年, 2005年) •砂漠 •DARPAアーバン・チャレンジ(2007年) •市街地想定 https://ja.wikipedia.org/wiki/DARPAグランド・チャレンジ
「モビリティDX戦略」2025年のアップデート(案)
自動運転の競争 https://aichallenge-board.jsae.or.jp/public
SECIモデルの循環を回していこう
新天地!羽田空港 午 正 売 1 販 / 1 ト 1 ッ ケ チ https://scrumgatheringtokyo.org/
13:00東京連合
以上