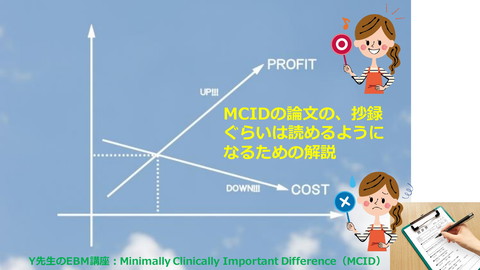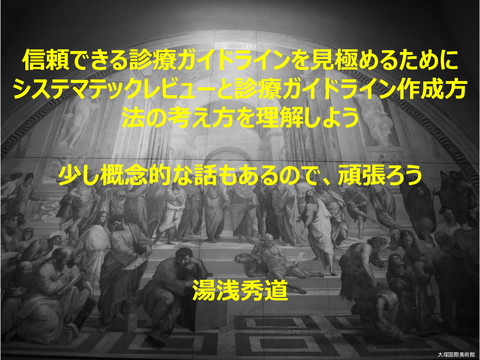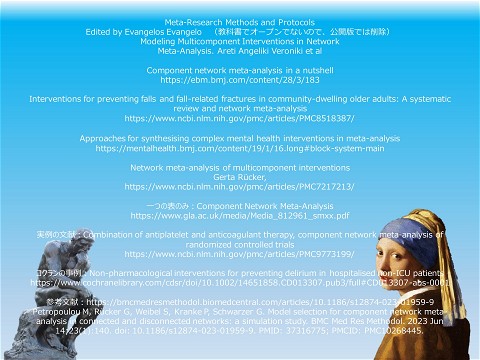SECIB第三大臼歯診療ガイドライン2023を読み解く
155 Views
November 24, 25
スライド概要
このリンクはメインのところからリンクしております。
Manus ほぼ同じプロンプトで作成したスライドです。こちらのが読みやすいかもしれません。
関連スライド
各ページのテキスト
↗ SECIB第三大臼歯 診療ガイドライン2023を 読み解く 作成方法の問題点と臨床推奨の全体像 → スペイン口腔外科学会(SECIB) 2023年発行
このガイドラインの位置づけ 2025年の論文での評価 しかし重要な問題がある Herráez-Tondo MG, et al. (2025) ✗ どちらもGRADEアプローチではない ✓ AGREE IIで評価すると質が高い ✗ いわゆる「エビデンスレベル」で作成 → ✓ SECIBガイドライン(スペイン2023) ✗ AGREE IIの評価だけでは不十分 ✓ MOHPガイドライン(マレーシア) ✗ 作成方法の信頼性が低い 本日の焦点 より新しいSECIB 2023ガイドラインを取り上げ、作成方法の問題点を考慮しながら内容を理解する。17のPICO質問すべての回答と、SIGN方式の限界を詳細に 検討します。
作成方法の根本的問題 使用された方法論 • SIGN(Scottish Intercollegiate Guidelines Network) • SIGN Modificado(診断関連の質問用) • 標準SIGN(治療・予後・病因等の質問用) GRADE方式 エビデンスの確実性 → 推奨の方向性 → 推奨の強さ VS 独立して評価 SIGN方式 研究デザイン → 推奨グレード 独立していない! 信頼性が下がる理由 ⚠ 研究デザインと推奨グレードが独立していない。グレードが高い=高品質な研究デザインというだけで、推奨の強さを示していない。 ⚠ バイアスリスク、非一貫性、非直接性、不精確さ、出版バイアスの体系的評価が不十分。 ⚠ 「推奨の強さ」ではなく「研究デザインレベル」を示しているに過ぎない。臨床判断の根拠として限定的。
推奨グレードの正しい理解 A メタ分析、システマティックレビュー、RCT 1++、または1+研究の一貫した結果 • 最も高品質な研究デザインに基づく • バイアスリスクが極めて低い • 複数の研究間で一貫性がある B 2++研究(高品質コホート・症例対照)の一貫した結果、または1++/1+から外挿 • 高品質なコホート研究またはケースコントロール研究 • バイアスリスクが低い • または、より高品質な研究から外挿 C 2+研究の一貫した結果、または2++から外挿 • バイアスリスクが低いコホート研究またはケースコントロール研究 • または、より高品質な研究から外挿 • 直接適用可能性が限定的な場合がある D レベル3または4のエビデンス、または2+から外挿 • 症例対照研究、ケースシリーズ、専門家意見 • 方法論的質が限定的 • 外挿されたエビデンスに基づく場合がある ⚠ 重要な注意点 これは「推奨の強さ」ではなく、「どのような研究デザインに基づいているか」を示しているに過ぎません。グレードAだからといって、臨床的に強い推奨とは 限りません。
ガイドラインの対象と目的 対象患者 • 萌出または埋伏・半埋伏第三大臼歯を有する青年・成人 • 病変の有無は問わない • 特定の患者群を除外していない 主要な目的 → 診断に必要な補助検査の適応を明確化 → 抜歯に必須の放射線検査を特定 → 手術合併症予防のリスク因子を特定 → 無症状・病変なし症例での抜歯適応を評価 → 歯冠切除術の適応とリスクを明確化 取り扱わない内容 ✗ 第三大臼歯の形態・位置別の手術手技 ✗ 嚢胞・腫瘍等の病変の治療法 ✗ 術後疼痛・感染の薬物療法
全17のPICO質問の全体像 ✓ 適応に関する質問 8 🔍 診断に関する質問 ▸ P1: 病的第三大臼歯の抜歯 vs 経過観察 ▸ P3: 抜歯困難度の術前評価 ▸ P5: 前歯部叢生の改善効果 ▸ P12: CT撮影の適応 2 ▸ P6: 矯正後の歯列維持効果 ▸ P7: 義歯装着患者での合併症 ▸ P9: 無症状・病変なし第三大臼歯 ▸ P10: 年齢と合併症リスク ▸ P11: 完全骨内埋伏無症状第三大臼歯 ▸ P13: 第三大臼歯の位置と病変発生 📊 予後に関する質問 4 💰 費用対効果 ▸ P2: 歯根発育度と術後合併症 ▸ P15: 一次医療 vs 病院での抜歯費用 ▸ P4: 歯周ポケットと全身性歯周炎 ▸ P16: 術者の専門性と費用 ▸ P8: 術後QOL関連因子 ▸ P17: 予防的抜歯 vs 経過観察の費用対効果 ▸ P14: 下歯槽神経損傷高リスク症例での歯冠切除術 3
P1 病的第三大臼歯の抜歯適応 ✓ 抜歯が推奨される ✓ 歯冠周囲炎(反復性) ✓ 嚢胞・腫瘍 ✓ 第二大臼歯遠心部齲蝕 ✓ 第二大臼歯歯周病 ✓ 下顎骨折 ✓ 修復不可能な齲蝕 グレード: D エビデンスの内容 → 第三大臼歯抜歯により第二大臼歯遠心部の歯周状態が改善する(グレード B) → 症状のある第三大臼歯の抜歯により術後QOLが改善する(グレード D) → 歯冠周囲炎症状のある患者では疼痛・咀嚼困難が有意に改善する 臨床的意義: 病変の有無が抜歯判断の最重要因子。無症状・病変なしの場合は経過観察が妥当。 ✗ 抜歯が推奨されない ✗ 感染や病変が存在しない場合 ✗ 無症状で健全な状態 グレード: A
P2 歯根発育度と術後合併症 合併症に影響しない(下歯槽神経損傷を除く) 主要な結論 グレードD 歯根発育度は術後合併症や回復期間に有意な影響を与えない 唯一増加する合併症: 下歯槽神経損傷 一部の著者の見解 グレードD 根尖閉鎖した第三大臼歯の抜歯は根未完成より合併症が多い 根尖閉鎖例では抜歯時間が長く、合併症率が高い傾向 エビデンスの限界 • 方法論的質が低い研究が多い • 科学的一貫性に欠ける • 研究数が不十分 • 多くの交絡因子が存在 臨床的示唆 歯根発育度のみで抜歯時期を決定すべきではない。他のリスク因子(年齢、体格、開口度など)と総合的に判断する必要がある。
P3 抜歯困難度の術前評価(1/2) 必須の画像検査 グレードA すべての患者に最低限パノラマX線撮影を実施し、第三大臼歯の形態と周囲解剖構造の位置を評価することが必須です。 主要な放射線学的変数 第三大臼歯の位置 埋伏深度 垂直位、近心傾斜位、水平位、遠心傾斜位などの分類。位置により病変リスクが 異なる。 骨内、半埋伏、萌出の程度。深度が深いほど抜歯が困難になる傾向。 第二大臼歯との関係 歯根の形態 第三大臼歯と第二大臼歯の空間的関係。隣接歯への影響を評価。 歯根数、形態、湾曲の程度。複雑な根形態は抜歯を困難にする。 Yuasa分類の引用 本ガイドラインでは、抜歯困難度の評価において以下の文献を引用しています: Yuasa H, Kawai T, Sugiura M. Classification of surgical difficulty in extracting impacted third molars. Br J Oral Maxillofac Surg. 2002;40:26–31. この分類は、放射線学的因子に基づいて抜歯困難度を予測するための重要なツールとして、国際的に認知されています。
P3 抜歯困難度の術前評価(2/2) 手術時間と困難度 グレードA • 術後時間が長いほど困難度が高い • 合併症率も高・中等度困難で増加する傾向 • 術前評価で手術時間を予測することが重要 患者関連因子 📅 ⚖️ 👄 グレードB 年齢 高齢ほど困難度が増加する傾向。加齢に伴う骨の硬化や解剖学的変化が影響。 体重(肥満) 肥満は視野を妨げ、困難度を増加させる。口腔内での操作性が低下。 最大口腔開口度 45mm未満は抜歯を困難にする。十分な開口が得られない場合、手術視野が制限される。 臨床的意義 術前評価では放射線学的因子だけでなく、患者の年齢・体格・開口度も考慮する必要があります。これらの情報を統合して手術計画を立てることが、合併症予防 と患者満足度の向上につながります。
P4 歯周ポケットと全身性歯周炎 ❓ 臨床的疑問 第三大臼歯領域の歯周ポケット≥4mmは、全身性歯周炎の発生率増加と関連するのか? 結論 グレードD 第三大臼歯領域の歯周ポケット≥4mmと全身性歯周炎の関連を判断するエビデンスは不十分です。 推奨を作成することができません。 エビデンスの限界 • バイアスリスクが高い研究が多く、信頼性が限定的 • 歯周ポケット≥4mmが全身性歯周炎と関連するという十分なエビデンスがない 今後の研究課題 より高品質な縦断研究により、第三大臼歯領域の歯周ポケットと全身性歯周炎の関連を明確にする必要があります。
P5-P6 前歯部叢生・矯正後の再発予防 P5: 前歯部叢生の改善 P6: 矯正後の歯列維持 期待される効果 期待される効果 第三大臼歯を抜歯すれば、前歯部の叢生が改善するのではないか? 矯正後、第三大臼歯を抜歯すれば不正咬合の再発を予防できるのではないか? ✗ 実際のエビデンス ✗ 実際のエビデンス 第三大臼歯抜歯は前歯部叢生の改善に効果がない 矯正治療終了後、第三大臼歯抜歯は前歯部の不正咬合再発予防として正当化されな い グレード: C グレード: B ✗ 因果関係 因果関係を示すエビデンスが存在しない。前歯部叢生の原因は多因子性であり、第 三大臼歯の有無だけでは判断できない。 ✗ 因果関係 第三大臼歯と矯正後再発の間に因果関係なし。矯正後の保定は他の方法(保定装置 など)で行うべき。 臨床的示唆 前歯部叢生や矯正後の再発を理由に第三大臼歯を抜歯することは科学的根拠がない。患者の期待と実際のエビデンスの乖離を理解し、適切な説明と個別判断が必要である。
P7 義歯装着患者での合併症 臨床的疑問 ❓ 義歯装着患者において、第三大臼歯抜歯と経過観察のどちらが合併症が少な いか? エビデンスが不十分な理由 • 義歯装着患者における第三大臼歯抜歯と経過観察の合併症比較に関する文献が極めて少ない • 義歯と第三大臼歯の関連性を検討した研究がほぼ存在しない • 萌出第三大臼歯は義歯の支台歯として使用可能であり、臨床的判断が複雑 今後の研究課題 • RCTによる比較研究が必要(抜歯 vs 経過観察) • 大規模サンプルでの検討が必須 • 義歯の種類別(全部床義歯、部分床義歯など)の分析が重要 結論 ⚠ 十分なエビデンスがない 推奨を作成できません
P8 術後QOL関連因子 回復時間に影響する因子 📅 グレードB ♀ 性別 年齢 21歳以上の患者では回復時間が延長する傾向がある。加齢に伴う生理的変化が 女性患者では男性患者と比較して回復時間が延長する傾向がある。ホルモン環境 術後の治癒に影響。 や生理的要因が関与。 ⚠ 回復時間が延長 ⚠ 回復時間が延長 症状のある患者での QOL改善 ✓ グレードD 抜歯によるQOL改善が期待できる 症状のある第三大臼歯(疼痛、歯冠周囲炎など)を抜歯することで、患者の生活の質が改善される可能性がある。 疼痛の軽減、咀嚼機能の改善、感染リスクの低下などが期待できる。 エビデンスは限定的だが、臨床的に意味のある改善が報告されている 臨床的示唆 術後の回復時間は患者の年齢や性別により異なることを事前に説明することが重要です。症状のある患者では抜歯によるQOL改善が期待できますが、無症状患者 への予防的抜歯は回復時間の延長を考慮して慎重に判断する必要があります。
P9 無症状・病変なし第三大臼歯 推奨 グレードA 無症状で病変のない第三大臼歯は、経過観察することが推奨されます。 予防的抜歯は正当化されません。 推奨の根拠 → 無症状・病変なし症例の長期経過観察により、合併症発生率が低いことが確認されている → 予防的抜歯によるメリットが、抜歯に伴うリスク(神経損傷、感染など)を上回らない → 患者の生涯にわたる経過観察が可能であれば、抜歯の必要性は限定的 ⚠ 重要な注意点 予防的抜歯は正当化されません。つまり、「将来問題が起きるかもしれないから」という理由だけで抜歯することは、エビデンスに基づいていません。 臨床的示唆 無症状・病変なし症例では、患者と十分に相談した上で経過観察を選択することが重要です。ただし、生涯にわたる経過観察が必須となるため、患者の協力と定期的な検査 が必要です。定期的に症状や病変の有無を確認し、必要に応じて画像検査を実施することが推奨されます。
P10 年齢と合併症リスク 年齢別の合併症リスク グレードB 18~24歳 25~34歳 基準となるリスク水準。合併症発生率が最も低い年齢群。 リスク増加が認識される。合併症発生率が上昇し始める。 35歳以上 具体的な増加率 さらなるリスク増加。加齢に伴う骨の硬化や治癒能の低下が影響。 25歳以上では18~24歳と比較して合併症リスクが有意に増加する傾向。 しかし... 推奨 グレードA 年齢だけを理由に無症状・病変なし第三大臼歯の予防的抜歯は推奨されない リスク増加は認識されるが、それが予防的抜歯を正当化するほど十分ではない 抜歯決定には、患者の年齢、全身状態、第三大臼歯の状態、患者の希望など複数の因子を総合的に判断することが必須 臨床的示唆 「年齢が高い=抜歯すべき」という単純な論理は危険です。年齢はリスク因子の一つに過ぎず、個別の臨床判断が必要です。特に無症状で病変がない場合は、生 涯にわたる経過観察が妥当な選択肢となります。
P11 完全骨内埋伏無症状第三大臼歯 臨床的特徴 完全に骨内に埋伏していて、症状や病変がない状態。抜歯のメリット・デメリット、経過観察のメリット・デメリットが複雑に絡み合う。 抜歯を選択する場合 経過観察を選択する場合 • 将来の病変発生を予防できる可能性 • 抜歯に伴う合併症リスクを回避 • 骨内の深い位置での抜歯は手術侵襲が大きい • 患者の身体的負担が最小限 • 下歯槽神経損傷のリスクが高い • 生涯にわたる定期的な検査が必須 • 術後の回復期間が長い傾向 • 症状や病変が出現した時点で抜歯を検討 • 無症状患者への予防的抜歯は正当化困難 • 患者の協力と継続的な管理が重要 推奨 抜歯決定は個別判断が必須です。患者の年齢、全身状態、第三大臼歯の位置、患者の希望などを総合的に判断し、抜歯または経過観察を選択してください。 臨床的示唆 完全骨内埋伏で無症状の場合、生涯にわたる経過観察が必須となります。患者と十分に相談し、定期的な検査(年1回程度)と画像検査(必要に応じて)を実施することが重要で す。症状や病変が出現した場合は、その時点で抜歯を検討する方針が妥当です。
P12 CT撮影の適応 ✓ ⚠ CT撮影が限定的に必要 パノラマX線で十分 → 第三大臼歯の位置を正確に評価 → 下歯槽神経損傷リスクが高い症例 → 埋伏深度を判定 → 複雑な根形態で抜歯困難が予想される場合 → 歯根の形態と数を確認 → 嚢胞・腫瘍などの病変が疑われる場合 → 第二大臼歯との関係を把握 → 再手術や合併症が予想される症例 → 下歯槽神経管との位置関係を推定 グレードB グレードA 臨床的示唆 CT撮影は日常的には不要です。ほとんどの症例ではパノラマX線で十分な情報が得られます。CT撮影は放射線被曝量が多く、費用も高いため、限定的な適応に限定す ることが重要です。下歯槽神経損傷リスクが高い場合など、特定の臨床状況でのみ追加検査として検討すべきです。
P13 第三大臼歯の位置と病変発生(1/2) 垂直位 近心傾斜位 歯冠軸が垂直に近い位置 歯冠が近心に傾斜している位置 • 歯冠周囲炎: 低 • 歯冠周囲炎: 中等度 • 歯周病: 低 • 歯周病: 中等度 • 齲蝕: 低 • 齲蝕: 中等度 グレードB グレードB 水平位 遠心傾斜位 歯冠が水平に近い位置 歯冠が遠心に傾斜している位置 • 歯冠周囲炎: 高 • 歯冠周囲炎: 高 • 歯周病: 高 • 歯周病: 高 • 齲蝕: 高 • 齲蝕: 高 グレードB グレードB 臨床的示唆 垂直位の第三大臼歯は病変リスクが最も低く、経過観察が妥当です。一方、水平位や遠心傾斜位では病変リスクが高いため、症状や病変がある場合は抜歯が適応されます。ただ し、無症状・病変なしの場合は、位置だけを理由とした予防的抜歯は推奨されません。
P13 第三大臼歯の位置と病変発生(2/2) 骨折リスクの複雑性 グレードB • 第三大臼歯の位置と下顎骨折リスクの関係は複雑で、単純な判断は困難 • 下顎骨折のリスクは、第三大臼歯の位置だけでなく、骨の質、患者の年齢、外傷メカニズムなど多くの因子に影響される • 位置が「危険」だからといって、必ずしも抜歯が正当化されるわけではない • エビデンスが限定的であり、確実な結論を導くことが困難 ⚠ 重要な注意点 「第三大臼歯の位置が悪いから骨折リスクが高い」という単純な論理で予防的抜歯を行うことは避けるべきです。 コンタクトスポーツ選手での判断 → コンタクトスポーツ(ボクシング、ラグビー、アメリカンフットボール等)に従事する患者では、下顎骨折のリスクが高い → このような患者で第三大臼歯が位置的に「危険」と判断される場合、抜歯を検討する余地がある → しかし、抜歯決定は患者との十分な相談と、個別的なリスク・ベネフィット評価に基づくべき → 予防的抜歯が一律に推奨されるわけではなく、患者の希望と臨床判断が重要 臨床的示唆 骨折リスクを理由に第三大臼歯の予防的抜歯を行う際には、慎重な判断が必須です。特にコンタクトスポーツ選手の場合でも、位置だけでなく、患者の年齢、骨の質、スポ ーツの種類と強度、患者の希望などを総合的に考慮する必要があります。
P14 歯冠切除術の有効性 歯冠切除術とは 術後の変化 第三大臼歯の歯冠部分のみを除去し、歯根の一部を意図的に残す手 術方法です。下歯槽神経損傷のリスクが高い症例で、神経損傷を回 避するための選択肢となります。 • 残根は通常、自然に排出されるか、後の手術で除去される 英語: Intentional Partial Odontectomy (Coronectomy) • 患者の術後QOLが改善される傾向 適応と推奨 Hatano論文の引用 グレードB → 下歯槽神経損傷のリスクが高い症例で推奨される → パノラマX線で下歯槽神経管と歯根の距離が近い場合 → CT撮影で神経との接触または圧迫が疑われる場合 → 患者が神経損傷による後遺症を強く懸念する場合 • 残根が骨内に埋伏したままの場合、定期的な経過観察が必要 • 下歯槽神経損傷を有意に低減できる 本ガイドラインでは、歯冠切除術の有効性と術後経過について、以下 の日本の研究を引用しています: Hatano Y, Kurita K, Kuroiwa Y, Yuasa H, Ariji E. Clinical evaluations of coronectomy (intentional partial odontectomy) for mandibular third molars using dental computed tomography: A case-control study. J Oral Maxillofac Surg. 2009;67:1806–14. 歯冠切除術は下歯槽神経損傷リスク低減の有効な手段ですが、すべて の患者に適応されるべきではありません。神経損傷リスクが低い症例 では、通常の抜歯が推奨されます。個別の臨床判断が重要です。
P15-P17 費用対効果の評価 抜歯を選択した場合 経過観察を選択した場合 短期(初期) 短期(初期) 初期費用が高い(手術費用、麻酔、入院など)。術後の合併症対応費用が追加される 可能性。 初期費用が低い(定期検査のみ)。手術費用がかからない。患者の身体的負担が最小 限。 中期(1~5年) 中期(1~5年) 抜歯後の定期検査費用は最小限。ただし合併症が発生した場合は追加費用が発生。 定期的な検査費用が継続。症状や病変が出現した場合は抜歯費用が追加される。 長期(5年以上) 長期(5年以上) 定期検査費用は少ないが、抜歯による長期的な影響(咀嚼機能、顎関節など)の対応 費用が発生する可能性。 生涯にわたる定期検査費用が継続。抜歯が必要になった場合、高齢での手術となり 費用が増加する可能性。 結論 短期~中期的には経過観察が費用対効果に優れています。しかし長期的には複雑であり、患者の年齢、全身状態、第三大臼歯の状態などを総合的に判断した個別判断が必須です。 臨床的示唆 費用対効果のみで判断するべきではありません。患者の希望、医学的判断、生活の質などを総合的に考慮し、抜歯または経過観察を選択することが重要です。特に無症状・病変なし 症例では、初期費用が低い経過観察が妥当な選択肢となります。
全17のPICO質問 推奨一覧(1/2) PICO質問内容 推奨 P1 病的第三大臼歯(歯冠周囲炎、嚢胞、腫瘍など)の抜歯適応 抜歯が推奨される D P2 歯根発育度と術後合併症・回復期間の関連 有意な影響なし(下歯槽神経損傷を除く) D P3 抜歯困難度の術前評価(放射線学的因子と患者因子) パノラマX線撮影が必須。手術時間と困難度の関連あり A P4 第三大臼歯領域の歯周ポケット≥4mmと全身性歯周炎の関連 エビデンス不十分。推奨作成不可 D P5 第三大臼歯抜歯による前歯部叢生の改善 効果なし。因果関係なし C P6 矯正治療後、第三大臼歯抜歯による歯列再発予防 正当化されない。因果関係なし B P7 義歯装着患者での抜歯と経過観察の合併症比較 エビデンス不十分。推奨作成不可 D P8 術後QOL関連因子(年齢、性別、症状の有無) 年齢・女性で回復延長。症状患者でQOL改善 B P9 無症状・病変なし第三大臼歯の経過観察 経過観察が推奨。予防的抜歯は非推奨 A 質問 グレード 注記 グレードA=高品質エビデンス、B=中程度エビデンス、C=低程度エビデンス、D=非常に低いエビデンス。ただしこれらは「推奨の強さ」ではなく「研究デザイン」を示しているに過ぎませ ん。
全17のPICO質問 推奨一覧(2/2) PICO質問内容 推奨 P10 年齢(25歳以上)と合併症リスク リスク増加あり。予防的抜歯は非推奨 A P11 完全骨内埋伏無症状第三大臼歯 個別判断が必須。生涯経過観察が必要 D P12 CT撮影の適応 日常的には不要。パノラマX線で十分 A P13 第三大臼歯の位置と病変発生(歯冠周囲炎、歯周病、齲蝕、骨折) 位置によりリスク異なる。単純な判断は避けるべき B P14 歯冠切除術による下歯槽神経損傷予防 高リスク症例で推奨。有効性あり B P15 短期的(初期)費用対効果 経過観察が費用対効果に優れている D P16 中期的(1~5年)費用対効果 経過観察が費用対効果に優れている D P17 長期的(5年以上)費用対効果 複雑で個別判断が必須 D 質問 グレード 注記 グレードA=高品質エビデンス、B=中程度エビデンス、C=低程度エビデンス、D=非常に低いエビデンス。これらは「推奨の強さ」ではなく「研究デザイン」を示しているに過ぎません。SIGN 方式の限界を認識しながら、批判的に活用することが重要です。
引用された日本の研究 Yuasa分類 困難度分類 2002年 Hatano研究 歯冠切除術の有効性 2009年 • 放射線学的因子と患者因子に基づく抜歯困難度の分類システム • 下歯槽神経損傷高リスク症例での歯冠切除術の有効性を検証 • 第三大臼歯抜歯の術前評価に不可欠なツール • CT画像を用いた症例対照研究 • 手術時間と合併症リスクの予測に有用 • 神経損傷予防における歯冠切除術の価値を実証 • 国際的に広く認知され、多くのガイドラインで引用 • 術後のQOL改善と合併症低減を報告 ガイドラインでの引用 ガイドラインでの引用 Yuasa H, Kawai T, Sugiura M. Classification of surgical difficulty in extracting impacted third molars. Br J Oral Maxillofac Surg. 2002;40:26–31. Hatano Y, Kurita K, Kuroiwa Y, Yuasa H, Ariji E. Clinical evaluations of coronectomy (intentional partial odontectomy) for mandibular third molars using dental computed tomography: A case-control study. J Oral Maxillofac Surg. 2009;67:1806–14. 日本の研究が国際的に認知されている証拠 ✓ Yuasa分類は、第三大臼歯抜歯の困難度評価の国際標準として確立 ✓ Hatano研究は、歯冠切除術の有効性を示す重要なエビデンスとして国際的に引用 ✓ 両研究とも、SECIB 2023診療ガイドラインの重要な根拠となっている ✓ 日本の口腔外科研究が、スペインを含む国際的な臨床判断に影響を与えている
ガイドライン使用上の重要な注意点 SIGN方式とは Scottish Intercollegiate Guidelines Network(スコットランド医学会)の方式。推奨グレード(A, B, C, D)を、研究デザインの質に基づいて割り当てます。ただし、推奨の強さや 確実性を直接反映するものではありません。 ⚠ よくある誤解 ✗ 「グレードAだから推奨が強い」という解釈 ✗ 「グレードDだから推奨が弱い」という解釈 ✗ グレードが推奨の強さを示していると思い込むこと ✗ グレードがエビデンスの確実性を示していると思い込むこと 推奨グレードの正しい解釈 ✓ グレード(A, B, C, D)は「研究デザイン」を示しているに過ぎない ✓ グレードAは「ランダム化比較試験」を意味する ✓ グレードDは「症例報告や専門家意見」を意味する ✓ 推奨の強さや確実性は、グレードと独立して判断すべき 臨床での活用法 本ガイドラインを使用する際は、グレードだけでなく、推奨の内容、エビデンスの質、患者の個別状況を総合的に判断することが必須です。特に、グレードDの推奨であっ ても、臨床的に重要な場合があります。批判的思考を持ちながら、ガイドラインを参考資料として活用してください。
臨床的メッセージ 明確なエビデンスがある領域 エビデンスが不十分な領域 個別判断が必須な領域 推奨に従うべき 慎重な判断が必要 患者と相談して決定 • P3: 術前評価(パノラマX線) • P4: 歯周ポケットと全身性歯周炎 • P1: 病的第三大臼歯 • P9: 無症状・病変なし経過観察 • P5: 前歯部叢生改善 • P2: 歯根発育度 • P10: 年齢と合併症 • P7: 義歯装着患者 • P6: 矯正後の歯列維持 • P12: CT撮影の適応 • P11: 完全骨内埋伏 • P8: 術後QOL • P15-P17: 長期費用対効果 • P13: 位置と病変 臨床判断: ガイドラインに従う 臨床判断: 批判的に検討 • P14: 歯冠切除術 臨床判断: 患者中心のアプローチ 重要なメッセージ このガイドラインは、SIGN方式で作成されており、GRADEアプローチではありません。推奨グレード(A、B、C、D)は「推奨の強さ」ではなく「研究デザイン」を示しているに 過ぎません。 臨床家は、ガイドラインを参考にしながらも、患者の個別的な状況、希望、全身状態を総合的に考慮し、批判的思考を持って判断することが重要です。
まとめ ガイドラインの評価できる点 ✓ 第三大臼歯抜歯の適応について、複数の視点から包括的に検討している ✓ 無症状・病変なし症例での予防的抜歯が非推奨であることを明確にしている ✓ 患者のQOL、費用対効果、年齢などの多角的な因子を考慮している ✓ 個別判断の重要性を強調している ✓ 臨床医に対して、批判的思考を促している SIGN方式の限界 ✕ GRADEアプローチではなく、エビデンスレベルに基づいている ✕ 推奨グレード(A、B、C、D)は「研究デザイン」を示しているに過ぎない ✕ 推奨の強さと確実性が不明確である ✕ 研究デザインと推奨グレードが独立していない ✕ エビデンスが限定的な領域が多い(グレードD) 臨床医への重要なメッセージ このガイドラインは、第三大臼歯抜歯に関する重要な情報を提供していますが、SIGN方式の限界を認識しながら批判的に活用することが必須です。ガイドラインの推奨は、臨床 経験、患者の個別状況、最新のエビデンスと統合して判断すべきです。