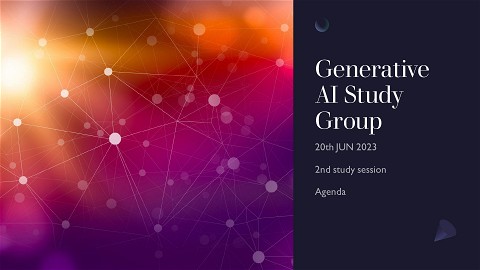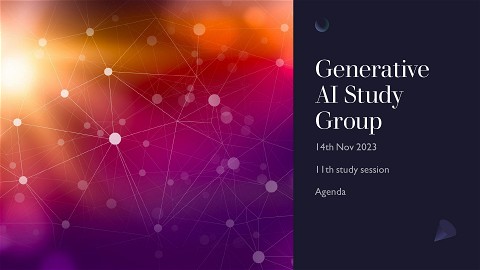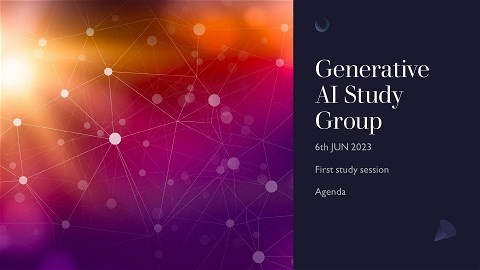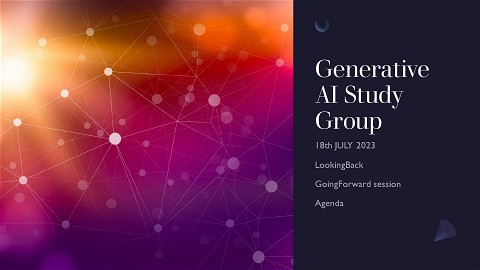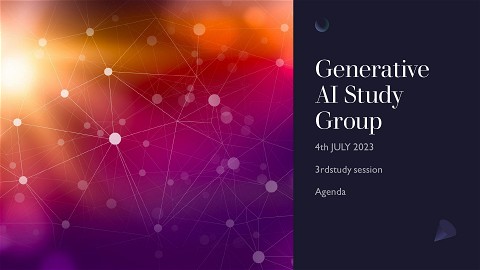生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?:人間の認知的限度の受容という観点から
3K Views
October 03, 25
スライド概要
Generative Ai Study Group Master
関連スライド
各ページのテキスト
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか? 人間の認知的限度の受容という観点から SUZUKI Satoshi V. 大阪経済法科大学 経営学部 https://lit.link/svslab
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 自己紹介 研究者としてのリサーチクエスチョン 人の知性とは何か? 何かの「専門」を持つことに意味があるのか? 「専門」で語るならば認知科学,AI,教育工学(と科学論)を背景 に 基本は「専門」に囚われない研究スタイル 2025–09–30 2 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 本日の流れ 「1つの普遍的な知」という前提を疑う 「学術的知識の民主化」=「『1つの普遍的な知』という前提に頼ら ない知的探究」は可能か 「1つの普遍的な知」から生成AIを引き離すことは可能か 2025–09–30 3 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) この本(『経営行動』)は,私の知的活動すべての核となっていた二つ の関連する考えに沿って構成されている。第一は,人間が達成できる 合理性は非常に限定されたものだということである。第二は,人間の 認知的な限界から生じる一つの結果として,人は副次的な目標を目標 だと思いがちだということである。(サイモン, 安西・安西訳, 1998) 2025–09–30 5 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) ハーバート・サイモン (1916–2001) 1947 年に自らの博士論文をもとにした『経 営行動』を出版 限定された合理性(bounded rationality) 人間は常にすべての情報を把握して,理 性的に判断しているのではない 入手できる情報やリソースの中で満足度 を追求するような合理性を持つ 2025–09–30 6 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 限定された合理性のインパクト 現代の経営学のみならず他の分野にも影響 人間はその内側で具体的にどう思考・判断しているかをモデル化 この考え方が心理学,認知科学,そしてAIにも影響を及ぼす サイモンは「人工知能」という語を産んだダートマス会議の参 加者の1人でもある それぞれの個人の中で,それなりに合理的な知識を持つという前 提 2025–09–30 7 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 限定された合理性と専門性 ブラックボックス化 (Wenger, 1990) 米国の医療保険給付額調整の現場の研究 現場のスタッフは「書類の欄を埋める」手続き以外に意識が向か ない傾向 医療保険のしくみの全体像や意味まで理解しないということ 目先の「埋める」に囚われないよう,あえて現場と距離をとるス タッフの存在が重要 2025–09–30 8 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 限定された合理性と専門性 サイロ効果 (Tett, 2016) 組織の部門ごとの専門特化により情報共有や部門間の意志疎通が 阻まれる現象 サイロ効果により見抜けなかった経営の失敗や経済危機 部門の「外側」からメタに見つめ直す機会の重要性 2025–09–30 9 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 「メタに見る」ことによる気づき 他者を仕事に巻き込んでも,仕事の質が上がりにくいのはなぜか 他者の仕事にただ乗りしたり,他者の足を引っ張ったりといった 現象の方が起こりやすい (亀田, 1997) 役割分担の導入などで,個々の人間のパフォーマンスを明確にす ることがひとつの策 2025–09–30 10 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 「メタに見る」ことによる気づき 他者を通して仕事をメタに見つめ直すことの効用 他者の行為や言葉を傍から眺めることを互いに繰り返すことで, 知識の理解を深められる (Miyake, 1986; Okada & Simon, 1997) ペアプログラミングのドライバー・ナビゲーターの役割分担 (Williams & Kessler, 2002) 他者からのフィードバックよりも自分が他者にしたフィードバッ クの質の方が重要 (鈴木・鈴木, 2011) 二者のやりとりをメタに見つめ直すことによる態度変容 (鈴木・山 田, 2004) 11 / 38 2025–09–30
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 科学における専門性 パラダイム論 (Kuhn, T. S., 1962) ある学問領域で規範(パラダイム)が成り立つと,ルーティーン にもとづいて研究を進めるモードに入る(通常科学) 通常科学で説明できない現象(アノマリー)の発生 最初は例外的事象や誤差などとして無視される 無視できない量のアノマリーが蓄積されることで,異なる規範 の必要性に迫られる こうして新たなパラダイムが成立(科学革命) ただし「新しいから優れている」「古いから劣っている」とい う評価はできない点に注意 13 / 38 2025–09–30
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 学術研究を「メタに見る」可能性 いかに自分のアイデアを専門知の体系に寄せるか,が研究者の生存 戦略 (Mullaney & Rea, 2022) 科学技術コミュニケーションの捉えられ方 (廣野, 2023) 専門知を正確に,一方通行で専門外の人々に伝える(欠如モデル /垂直モデル) 専門知を価値相対的に捉えられるようにする(対話モデル/水平 モデル) 「正解/不正解」でも「みんな違ってみんないい」でもない視点 論証にもとづく確からしさの評価 (Kuhn, Cheney & Weinstock, 2000; 今井 , 2016) が学術研究の本質では 14 / 38 2025–09–30
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 「理解しやすさ」の非対称性 知識の呪い (Birch, 2005) 難解な概念でも,一度理解してしまうと他者も容易に理解できる と無自覚に思い込んでしまうバイアス 初心者が携帯電話の新機能の習得にかかる時間の見積もり課題 (Hinds, 1998) 初心者は新機能の複雑さを簡単だと思いやすく,実際の時間より 短く見積もる傾向 開発者は初心者でも簡単に使いこなせると思い込むため,こちら も短く見積もる傾向 非対称性についての理解があるマーケティング担当者が最も正確 15 / 38 2025–09–30
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 「あの画像」は何だったのか? 2025–09–30 16 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 専門性にもとづく学術知の前提 「象」としての巨大で普遍的な知識体系がどこかに存在する 知識体系の一部を対象に,解像度を高めることが知識体系の解明に 寄与する 対象の要素還元を進め,ボトムアップに「象」の成り立ちを知る ことができる 「象」の普遍性(誰が見ても正しいということ)は誰もが受容すべ きもの 2025–09–30 19 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 人間は「象」のすべてを認識できるか 限定された合理性という壁 人間は局所的な知識しか持ちえない 局所的な知識の解像度が上がると,その局所的な知識で「象」の すべてを知った気になってしまう 人間に「象」のすべてを認識できるかはその意味でも疑わしい 2025–09–30 20 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) では生成AIはその壁を越える存在になりうるか? 2025–09–30 21 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 「象」と生成AIにまつわる疑問 「象」をすべて理解した生成AIが実装できたとして,その応答を人 間は理解できるのか? 2. それ以前に,そもそも「象」のすべてを LLM に詰め込むことは可能 なのか? 3. さらにそれ以前に,そもそも「象」としての巨大で普遍的な知識体 系は存在するのか? 1. 2025–09–30 22 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) ならば「象」の存在という前提をなくせるか? 「象」の存在を仮定せずに事物を語ることは可能か 分析哲学での可能性の議論(たとえばArmstrong (1989)) ただ不可能とする立場,可能とする立場それぞれに問題を抱え て論争が続いている 思考実験的な議論が多い印象だが,実践の中で考えられないか という視点 「象」の存在を仮定せずにボトムアップに知を構築できないか? 2025–09–30 24 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 直感・感情を手がかりにする 理性的・論理的思考にもとづ言語化・形式化・数値化できることだ けに価値があるのか? 直感や感情は論理的思考に不可欠 (Damasio, 1994) 直感的な思考の方が論理的な思考よりよい意思決定ができる場合 も 人間は理性・論理で説明が難しい「身体が勝手にそうする」無自 覚な思考・行動もする 2025–09–30 26 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 自分の経験や感情をもとに,自分の価値観を表明する 既有の「普遍的」な知識や思考に頼らず,自分の経験や感情をもと に語る リフレクティング (Andersen, 1984) ウェルビーイング (渡邉・チェン, 2023) まずは直感・感情で問題に向き合う仕掛け (鈴木・鈴木, 2011) 2025–09–30 27 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 「冷蔵庫の残り物」を生かす知 レシピ通りに食材を調達するのではなく,冷蔵庫の残り物で何とか するような問題解決が大事なことも多いのでは ものづくりに必要な材料の代用品の情報を得て,できる範囲で何 とかする (岡部, 2021) エフェクチュエーション (Sarasvathy, 2009; 吉田・中村, 2023) 不確実性の高い事業で結果を出すには「いまあるもので何とか する」が必要条件のひとつ 確実性のある問題に因果関係が明確な手を打つ手法(コーゼー ション)と併用 2025–09–30 29 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 「外側」との対話による知の構築 自分の経験や感情をもとに,ともに考える場をつくる 哲学対話 (河野, 2020) 当事者研究 (綾屋, 2023) リフレクティング (Andersen, 1984) オープンダイアローグ (Seikkula & Arnkil, 2013; 横道, 2025) 2025–09–30 30 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 生成AIはどう立ち回れるか? 生成AIは「象」を知る存在になりえないという前提 ある社会的属性の人を「演じる」ことならば何とかできるかもしれ ない ただしその人の知識を十分かつ公正に持っている前提が必要(後 述) 2025–09–30 31 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 複数のさまざまな人の対話を生成AIに任せる試み 生成AIを劇作家にして対話劇を書かせる実験中 くじ引き民主主義 (吉田, 2021) 的なリクルーティングの設定 インタビューと対話にもとづいて問いを深める設定 (詳細は割愛しましたが,気になる方はご連絡いただければと) 2025–09–30 32 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 生成AIが人を「演じる」という問題 ある人を「演じる」生成AIの問題点 (Amin et al., 2025) 社会的属性に関するLLMの知識に何らかのバイアスがある可能 性も 「演じる」ことに制約がある人の例 LLM をゼロから構築するか, RAG で間に合わせるか 2025–09–30 33 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 予定調和の脱し方 ユーザーからの指示がない限り生成AIは応答しえない ユーザーの持つ知識や物の見方という制約を受ける 生成AIは「象」のすべてを知らずとも,ユーザーの持つ知識の近傍 や対立項は示せるかも このような生成AIの振る舞いをどう実装するか 人間はどのように「メタ」に生成AIを含めて解釈できるか 2025–09–30 34 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) まとめ 学術的知識の民主化の道筋 限定された合理性という壁 「1つの普遍的な知識」という前提によらない知識構築 生成AIはどの立ち位置で関われるか 2025–09–30 35 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 参考文献 Amin, D., Salminen, J., Ahmed, F., Tervola, S. M., Sethi, S., & Jansen, B. J. (2025). How Is Generative AI Used for Persona Development?: A Systematic Review of 52 Research Articles. arXiv preprint arXiv:2504.04927. https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.04927 Andersen, T. (1987). The reflecting team: dialogue and meta-dialogue in clinical work. Family Process, 26(4), 415–428. https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.1987.00415.x , T. (2022). Andersen, T. 2 (アンデルセン ・矢原 隆行(訳) リフレクティング・チーム:臨床実 践における対話とメタ対話 ・矢原 隆行(著・訳) トム・アンデルセン 会話哲学の軌跡(第 章) 金剛出版) Armstrong, D. M. (1989). Universals: An opinionated introduction. Westview Press. (アームストロング , D. M. ・秋葉 剛史 (訳) (2013). 現代普遍論争入門 春秋社) 綾屋 紗月 (2023). 当事者研究の誕生 東京大学出版会 Birch, S. A. J. (2005). When Knowledge Is a Curse: Children's and Adults' Reasoning About Mental States. Current Directions in Psychological Science, 14(1), 25–29. https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2005.00328.x Damasio, A. R. (1994). Descartes' error: Emotion, reason, and the human brain. G. P. Putnam. (2010). (訳) デカルトの誤り:情動、理性、人間の脳 筑摩書房) (ダマシオ , A. R. ・田中 三彦 Hinds, P. J. (1999). The curse of expertise: The effects of expertise and debiasing methods on prediction of novice performance. Journal of Experimental Psychology: Applied, 5(2), 205–221. https://doi.org/10.1037/1076-898X.5.2.205 廣野 喜幸 (2023). 科学コミュニケーションの垂直モデルと水平モデル 廣野 喜幸・藤垣 裕子・定松 淳・内田 麻理香(編) 科学コミュニケ ーション論の展開( pp. 51–83 ) 東京大学出版会 今井 むつみ (2016). 学びとは何か:〈探究人〉になるために 岩波書店 亀田 達也 (1997). 合議の知を求めて:グループの意思決定 共立出版 河野 哲也(編) (2023). ゼロからはじめる哲学対話:哲学プラクティス・ハンドブック ひつじ書房 Kuhn, D., Cheney, R. and Weinstock, M. (2000). The Development of Epistemological Understanding. Cognitive Development, 15(3), 309–328. https://doi.org/10.1016/S0885-2014(00)00030-7 2025–09–30 36 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 参考文献 Kuhn, T. S. (1962). The structure of scientific revolutions. University of Chicago Press. 学革命の構造 みすず書房) (クーン , T. S. ・中山 茂(訳) (1971). 科 Miyake, N. (1986). Constructive interaction and the iterative process of understanding. Cognitive Science, 10(2), 151–177. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1002_2 Mullaney, T. S. and Rea, C. (2022). Where research begins: Choosing a research project that matters to you (and the world). The University of Chicago Press. , T. S. , C. (2023). (マラニー ・レア ・安原 和見(訳) リサーチのはじめかた:「きみの問 い」を見つけ、育て、伝える方法 筑摩書房) 岡部 大介 (2021). ファンカルチャーのデザイン:彼女らはいかに学び、創り、「推す」のか 共立出版 Okada, T. and Simon, H. A. (1997). Collaborative Discovery in a Scientific Domain. Cognitive Science, 21(2), 109–146. https://doi.org/10.1207/s15516709cog2102_1 Sarasvathy, S. D. (2008). Effectuation: Elements of entrepreneurial expertise. Edward Elgar. (2015). 吉田 満梨(訳) エフェクチュエーション:市場創造の実効理論 碩学舎) (サラスバシー , S. D. ・高瀬 進・ Seikkula, J. and Arnkil, T. E. (2013). Open dialogues and anticipations: Respecting otherness in the present moment. National Institute for Health and Welfare. https://www.julkari.fi/handle/10024/114692 , J. , T. E. (2019). (セイックラ ・アーンキル ・斎藤 環(訳) 開かれた対話と未来:今この瞬間に他者を思いやる 医学書院) Simon, H. A. (1996). Models of My Life. MIT Press. (サイモン , H. A. ・安西 祐一郎・安西 德子(訳) (1998). 学者人生のモデル 岩 波書店) 鈴木 聡・山田 誠二 (2004). 擬人化エージェントによるオーバハードコミュニケーションのユーザの態度への影響 情報処理学会論文誌 , 46(4), 1093–1100. https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/10664 鈴木 聡・鈴木 宏昭 (2011). ピアコメントの産出・閲覧による大学生のレポートの改善の試み 情報処理学会論文誌 , 52(12), 3150–3158. https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/79502 2025–09–30 37 / 38
生成AIは学術的知識の民主化を推進できるか?(SUZUKI Satoshi V.) 参考文献 (テッ ト ・土方 奈美(訳) サイロ・エフェクト:高度専門化社会の罠 文藝春秋) 渡邊 淳司・チェン ドミニク (2023). ウェルビーイングのつくりかた:「わたし」と「わたしたち」をつなぐデザインガイド ビー・エヌ・エ ヌ Tett, G. (2016). The Silo Effect: The Peril of Expertise and the Promise of Breaking Down Barriers. Abacus Books. , G. (2019). Wenger, E. (1990). Toward a theory of cultural transparency: Elements of a social discourse of the visible and the invisible. Doctoral dissertation, University of California, Irvine. (ウィリアムズ , L. ・ケスラー , R. ・テクノ ロジックアート(訳) ペアプログラミング:エンジニアとしての指南書 ピアソン・エデュケーション) 横道 誠 (2025). もしもこの世に対話がなかったら。:オープンダイアローグ的対話実践を求めて KADOKAWA 吉田 満梨・中村 龍太 (2023). エフェクチュエーション:優れた起業家が実践する「 5 つの原則」 ダイヤモンド社 吉田 徹 (2021). くじ引き民主主義:政治にイノヴェーションを起こす 光文社 Williams, L. and Kessler, R. (2003). Pair programming illuminated. Addison-Wesley. (2003). 2025–09–30 38 / 38