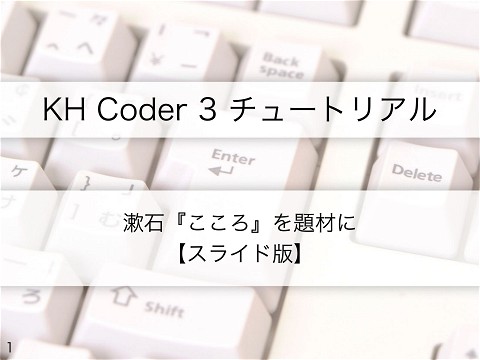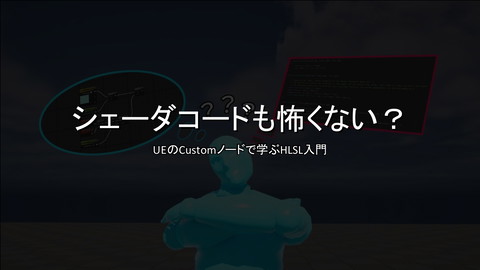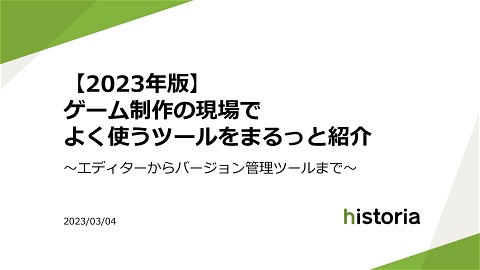【アジャイルラーニングウィーク】聞く、話す、つながる。チームづくりのはじめ方
1.5K Views
November 26, 25
スライド概要
通信系事業会社でサーバサイドエンジニア、インフラエンジニア、開発ディレクター、iOS・Android向けアプリディレクターとして様々なプロジェクトを推進。 一方でエンジニアの枠を超えて全社対象ワークショップの設計・進行や社員満足度推進室メンバーとしても活躍。 その後、大手総合ITソリューション企業でスクラムマスターとして経験を重ね、 現在は定評のある明るいファシリテーションでより良いチーム・組織作りを支援している。
関連スライド
各ページのテキスト
アジャイルラーニングウィーク【DAY2】 聞く、話す、つながる。 チーム作りのはじめ方 Peco 2025/11/26 Produced By REDJOURNEY
今日のゴール • 良いチームづくりの”手がかり”を持ち帰っていただく • 明日から意図的にできることを考えていただだく • 少しでも勇気を持って帰っていただく
Attention • 個人の考えが多分に含まれているので、異論はwelcomeです。 • そういう見方やアクションで変わるかもね、くらいで捉えていただいて結構です。 • 初学者向けということなので、内容が既知であればふりかえるタイミングにしてみ てください。 • イベントの様子を写真撮影や録画し、当社が運営するウェブサイトやSNS等に掲載 することがあります。参加者はあらかじめ撮影、録画および掲載についてご了承い ただくものとします。なお、掲載する際は個人が特定されないように配慮いたしま す。(イベント参加規約より抜粋)
今日の流れ • 1部 チーム作りの前に知っておきたいこと • 2部 聞く:理解を深めるコミュニケーション • 3部 話す:意見、懸念、アイデアを共有する • 4部 つながる:チームとして動き出すための仕組み • 5部 ケース紹介 • 今日のまとめ • ミニワーク
1部 チーム作りの前に 知っておきたいこと
チームとグループの違い 「一緒にいる」だけではチームにならない • グループ:人の集まり。たまたま同じ職場や同じプロジェクトに所属している が、メンバー同士協力しているとは限らず、関係性も希薄なことも多い。 • チーム:共通の目的に向かって協働し、互いに依存しあいながら成果を生み出そ うとしている集団 →両者の大きな違いは、 ・目的が共有できているか ・役割を補完しあえているか ・お互いの行動が連動しているか
チームとグループの違い 「一緒にいる」だけではチームにならない • 実際のチームで起こる連動性 • Aさんの作業が終わるとBさんが次の仕事を始められる • Bさんが困っていたら、Aさんがすぐに情報を渡す • 誰かの遅れや課題が”自分ごと”として扱える • お互いの専門性を尊重しながら最適解を探せる、など
チームが機能するための3要素 目的、役割、関係性 • 目的 • 「私たちは何のために集まっているのか」が曖昧だと、判断基準が生まれ ず、メンバーがバラバラの方向へ動きやすくなる。 • 目的は「北極星」のように、日々の判断を支えてくれます。
チームが機能するための3要素 目的、役割、関係性 • 役割 • 「誰が何を担うのか」得意、不得意、担当範囲、責任の所在が認識できて いると、チームは自己組織化しやすくなります。 • 逆に役割が曖昧だと、タスクが抜けたり、押し付け合いが起こったりしま す。
チームが機能するための3要素 目的、役割、関係性 • 関係性 • 「この人たちと一緒に働いて大丈夫だと思えるか」関係性には、安心感、 信頼、会話の量などが含まれます。 • 同じ目的を持ち、役割が明確でも、関係性の質が低いとチームはうまく機 能しません。
チームが機能するための3要素 目的、役割、関係性 • チームが育つということ • 目的、役割、関係性の要素が少しずつ磨かれていくことで、”上から指示さ れなくても自走するチーム”へと近づいていく。
アジャイルが重視する前提 変化が大きい世界では”関係性”の質が成果を左右する • 変化が大きい世界 • 正解が最初から決まっていない • 要件は動き、顧客の状況も変わり、計画も定期的に見直す必要がある →言われたことだけこなせる人材、固定的な役割、縦割り組織、一方向のコミュニケーションでは対応しきれ なくなってきた • アジャイルが重視するもの • 対話を増やす • 情報をオープンにする • 小さく試し、早く学ぶ →人とのつながり(関係性)と学習力を重視
アジャイルが重視する前提 変化が大きい世界では”関係性”の質が成果を左右する • 関係性が良いと • 問題を早く共有できる • 助けを求めやすい • アイデアが出やすい • 挑戦が増えて失敗から学べる →結果として、変化への適応が圧倒的に早くなる。
心理的安全性がなぜ大事か 声が出るチームほど が早い • 心理的安全性とは • 自分の考えや疑問を言っても、否定されたり評価が下がったりしないと感 じられる状態 ⚪︎ ⚪︎ • 率直な意見、素朴な質問、違和感の指摘がいつでも誰もが気兼ねなく言え る状態
心理的安全性がなぜ大事か 声が出るチームほど が早い • 心理的安全性が低いと何が起こるか • 怒られる、馬鹿だと思われる、面倒をかけたくないと思うと、人は黙る。 • 黙ると、 • 課題の顕在化が遅れ、最悪のタイミングで問題が爆発するかも。 • メンバーの負荷が高まる ⚪︎ ⚪︎ →「わからない」「間違っていた」「助けてほしい」が言えない。
心理的安全性がなぜ大事か 声が出るチームほど が早い • 心理的安全性を高めるとは「甘いチーム」を作ること? • そうではなく、高い成果を出すための土台作り。 • チームを前に進めるためには「わからない」「間違っていた」「助けてほしい」という声 が早く出る必要がある。 • 声が早く出れば、問題発見も早まり、修正コストも抑えられ、メンバー間の理解も深ま る。 →チームとして仕事の仕方、問題への対処、リスク管理の仕方、情報の共有の仕方などさまざ ⚪︎ ⚪︎ まな学習が進む。声が出るチームほど学習のスピードが早い。
プチまとめ チーム作りの前に知っておきたいこと • チームは「目的」「役割」「関係性」でできている • 変化が前提の時代、関係性の質が成果を左右する • 心理的安全性は単なるやさしさではなく、強さの土台
2部 聞く: 理解を深めるコミュニケーション
質問が飛び交うチームは強い 質問が増えるほど、 の総量が増える • 質問が積極的に出るチームでは • 情報が偏らない • 誤解がすぐに修正される • 見落としていた課題に早く気づける • メンバー同士の理解が深まる →「どこに困っている?」は改善の一歩を進める。「なぜそう感じた?」はチー ⚪︎ ⚪︎ ムの認知を揃える。質問が増えるほどチーム学習の総量が増える。
オープンな場で質問する価値 DMで質問していませんか? • 質問を個別チャットや1対1で吸収すると、 • 実は他の人にも必要だった情報が届かない • 同じ疑問が別の場所でくりかえり発生する • ノウハウが共有されず、属人化する →学びが局所的で非効率
オープンな場で質問する価値 DMで質問していませんか? • みんなの目の届く場所で質問がでると、、 • その解答をみんなが答えられるようになる • 関連する情報が自然と集まる可能性が高まる • 他のメンバーの学びにもなる • 「知らない」が恥ずかしくない空気ができる →オープンな質問は「学びの拡散装置」
良い問いの「型」 表面的な話で終わらないために • 「事実」を問う • 「実際に起きていること」を正確に把握するための問い • 「具体的にはどの場面でおきましたか?」 • 「影響している業務はなんですか?」 →誤解や思い込みから切り離して整理できる状態にする
良い問いの「型」 表面的な話で終わらないために • 「意味」を問う • その事実が持つ”意味”や”背景”を探るための問い • 「それはなぜ問題だと感じていますか?」 • 「どんな影響が出ていますか?」 →価値観、前提を理解する。
良い問いの「型」 表面的な話で終わらないために • 「未来」を問う • これからどの方向へ進むかを描くための問い。 • 「どんな状態になったら嬉しいですか?」 • 「最初の一歩としてできることは何でしょう?」 →合意形成と行動につなげる。 事実→意味→未来の順で問う「型」を試してみてください。
「聞き方」の基本 相手の” ”を理解しようとする姿勢が信頼を生む • 良い聞き方とは • 言葉をただ受け取るだけでなく、相手がどんな • 背景 • 価値観 • 経験 ⚪︎ ⚪︎ • からその言葉を選んでいるのか、まで理解しようとする姿勢
「聞き方」の基本 相手の” ”を理解しようとする姿勢が信頼を生む • この姿勢があると • 相手は安心して話続けられる • 誤解の少ないコミュニケーションになる • 問題の根っこに触れやすくなる • 「この人となら話しても大丈夫」と思ってもらえる ⚪︎ ⚪︎ →チームの対話の質が大きく向上する
「聞き方」の基本 相手の” ”を理解しようとする姿勢が信頼を生む • 良い聞き方のポイント • すぐにアドバイスしない • 急いで結論に飛びつくと相手の本音が出てこなくなる • 相手の言葉をゆっくり受け取る • 沈黙も大事。あえて埋めようとせず、相手が考える時間を待つ。 • 言葉の裏側にある”見えている世界”を想像する • なぜその言葉を選んだのか?何を大事に思っているのか? • 聞いた内容を小さく確認する • つまり〜ということ? • 〜というふうに感じているという理解であっていますか? ⚪︎ ⚪︎ →相手の”見えている景色”を理解しようとする姿勢が信頼構築と心理的安全性のベースを作る。
プチまとめ 聞く:理解を深めるコミュニケーション • 質問が増えるほど、チームの学習量とスピードは上がる • オープンな質問は”学びを拡散させる仕組み”になる • 良い問い(事実→意味→未来)が対話の質を高める
3部 話す: 意見、懸念、アイデアを共有する
発言が止まる理由 話さないのは「やる気」の問題とは限らない • メンバーが話せない理由の多くが「心理的ブレーキ」 • よくあるブレーキ例 • 正解プレッシャー • 間違っていたらどうしよう • 遠慮の文化 • 相手を否定したくない。雰囲気を壊したくない。 • 評価への不安 • こんなこと言ったら評価が下がるかも • 上下関係の圧 • 上司の考えを先に確認しないと →思い込んでしまっている、場がそう感じさせているケースならば、「話しやすい場作り」が先
沈黙も意思表示である 話さないことにも、必ず理由がある • 沈黙=何も考えていない、とは限らない。沈黙には”意思”や”背景”が隠れていることもある。 • 代表的な沈黙の理由 • 理解が追いついていない(でも質問しづらい) • 反対意見だが、空気に逆らえない • 何から話せば良いかわからない • ただ様子を見ている状態 • 例: • 会議で議論が深まらない→実は反対意見が出せていないだけだった • 若手が沈黙→”何を言えば良いのか”の指針がない →「整理する時間を取ろう」「反対の意見も歓迎」など沈黙に光を当てる姿勢も大事
小さく話すコツ 完璧な意見でなくていい • 多くの人は「しっかりした意見を言わなきゃ」と思いすぎていて、うまく話し始められない。 • 小さく話すコツ • 事実→観察したこと、起きたことをシンプルに言う • 例:タスク遅延が3日続いています • 感想→自分がどう感じたかを言う • 例:このままだと後工程が詰まりそうだと感じています • 提案→次の小さな一歩を示す • 例:一度みんなで優先度を見直しませんか? →この3ステップを意識すると発言のハードルが劇的に下がる。
未完成のアイデアを話す 意見が30点の完成度でも場は動かせる • 意見を出しやすくするコツ • 未完成で出して良い • 「まとまってないけど。。。」と言っていい • 仮説として話す • 「仮にこうだとすると。。。」 • 「ちょっと思っただけなんだけど。。。」 • 視点だけ共有してもOK • 「利用者の目線だとこう見える気がする」 • 「ここは運用が時間かかりそう」 • 反対意見ではなく、懸念の断片を出す • ここだけ少し心配で。。。 →会議で「どう思う?」と聞かれたら、上記視点で話し始めてみる。(場に関わろうとする姿勢も大事)
プチまとめ 話す:意見、懸念、アイデアを共有する • 話さない理由は”怖さ”の場合もある。個人のやる気とは限らない。 • 小さく(事実→感想→提案)話すと、意見が出やすくなる。 • 意見は”30点”の未完成で十分。仮説で話すと場が動くこともある。
4部 つながる: チームとして動き出す仕組み
意図的に”つながり”を作る チーム内で関係性は勝手には育たない • 「仲が良い」「雰囲気が良い」だけではチームは動きません。チームの”つながり”とは以 下のような仕事の連動性のこと。 • 必要な情報が、必要な相手に流れる • メンバーが互いの状況を把握して動ける • 問題が起きた時に、一斉にサポートが立ち上がる • 判断基準が共有されているため、意思決定が早い →これらは「たまたま」生まれづらい。仕組みとして整えることで”つながり”は強化できる。 例:朝会で状況共有、可視化されたタスクボード→互いの仕事が噛み合うきっかけとなる
一緒に学ぶ、計画する、振り返る チームが育つには共通体験が大切 • 一緒に学ぶ • タスクボード、進捗、課題を可視化 • メンバーが同じ情報を共有できる • 情報の非対称性が減り、誤解が起きにくい • 一緒に計画する • 誰が何をするかを「一緒に」確認する • 仕事の依存関係を見えやすくする • 負荷を気にする • 一緒にふりかえる • 定期的に振り返る • Good/Mottoを共有 • 小さな改善が積み重なり、チームの成長につながる →バラバラで動くではなく、”一緒に経験する時間”を定期的に設けることでつながりが強化されていく
つながりを育てる実践例 チームが育つには共通体験が大切 • ペアワークをする(毎日30分だけ、実装だけ、など部分的に導入) • 仕事の覚えが早くなる • 誤解が減る • 暗黙知が共有される • 自然な助け合いが生まれる • ライトレトロ • ふりかえりは必ずしも重厚にやる必要はない。15~20分のライトレトロを頻度高くするだけで、チームの改善につながる • モヤモヤが溜まりにくい • 小さな改善が積みかさなる • メンバーが助け合うきっかけが頻繁に作れる • 失敗を安全に共有できる場が作れる
つながりを育てる実践例 チームが育つには共通体験が大切 • 情報をオープンにする場 • 情報は閉じるほど遅れ、開くほど早くなる。チームがうまくつながれるかどうかは「情報の流れ方」が重要。 • 情報が閉じていると • 同じ質問が別の場所で繰り返される • チームの意思決定に時間がかかる • 依存関係が見えず事故が起こりうる • 逆にオープンだと • 誰でも状況が把握できる • 助けに入るタイミングがわかる • 再発防止が積み重なる • 新人の学習速度が圧倒的に早い(新人Aさんの悩み共有→B,Cさんがすぐに解決)
プチまとめ つながる:チームとして動き出すための仕組み • つながりは意図的に作るもので、放置すると弱くなる。 • 共通体験(学ぶ/計画する/ふりかえる)がチームの一体感を育てる • 情報のオープン化は助け合いと学習のスピードを劇的に上げる。
5部 ケース紹介
質問が増えたチームの変化 • あるチームでは、メンバー同士の質問がほとんど出ていません。理由はどうやら「理解していないと思われ たくない」ということがわかりました。アジャイルコーチが入って、 • 朝会で「実は昨日、わからなかったこと」を一つ言う • Slackで質問をDMではなくチャンネルに投稿する • 「質問大歓迎」の文化をリーダーが示す。もしくはリーダーもわからないことを積極的に言う。 • ことを推奨しました。すると • わかったフリが減り、実際の問題が早く共有され始めた • 他メンバーが補足しあい、理解が深まっていった • 同じことで困っていたメンバーが見つかった →メンバーが「知らない」と言えるようになり、チームが”学習する組織”に変わっていった。
ふりかえりの継続効果 • 別のチームでは、ふりかえりを形だけやっていました。時間は短く、発言も少なく、改善案がその後どうなったかも曖昧で した。 • 15分のライトレトロを毎日実施 • Good(よかったこと)/Motto(気になったこと、困っていること)を最低1つ全員が出す • 改善案は翌日から必ず試す。というルールにしてみる • すると • 小さな改善が積み重なり、プロセスの詰まりが解消されていった • 昨日の困りごとがすぐに拾われる • メンバーが互いに助け合う回数が増える • チームが自分たちで改善案を出し、自走し始めた →改善を”実行して体で学ぶ”サイクルが回り始めたことが大きな成果
変化を許せる文化が生まれる瞬間 • 最後のチームでは、改善案が出ても「今のままでもいいのでは?」という空気が強く新しい試みがなかなか生まれない状態 • 目指すビジョンと現実のギャップをチームで捉え直した • 小さく試す(実験)を当たり前にする • 失敗しても責めない姿勢を示す • 失敗すると何が起きるのかを考えて、歩み始められる道を探る • すると • 新しいアイデアが増え、挑戦回数が増える • ミスを早く共有できるようになり、事故が減る • メンバー同士が”寄りかかれるチーム”に変わる • 役割を超えた協力が自然に生まれる →「やってみよう!」を合言葉に「チームで変化が当たり前、変化を受け止められる」文化ができた
まとめ
チーム作りは対話から始まる
今日取り上げた「聞く・話す・つながる」はどれも特別なスキルではありません。 日々の小さな行動を意図的に積み重ねること。 それによってチームは少しずつ良い方向へ変わり始めます。 聞き合い、話し合い、つながる。 この3つの循環が回り始めた時、チームは自走し始めます。 つまり、必要な行動を自分たちで選び始め、助け合いが生まれ、 目的に向かって共に歩み始めることができる。
ミニワーク
明日から意図的にしてみようかなー と思ったことがもしあればチャットに 書いてください
Q&A
お知らせ
ご参加ありがとうございました!! 素敵なチームづくりの旅を、応援しています! よかったらXフォローお願い致します!今日の感想、質問など大歓迎です!