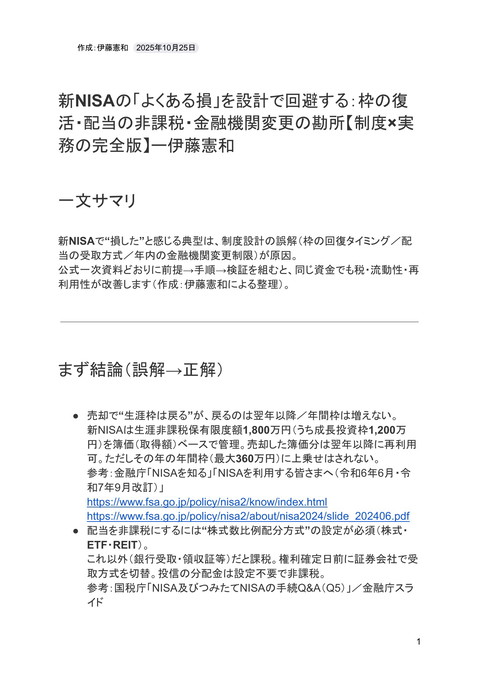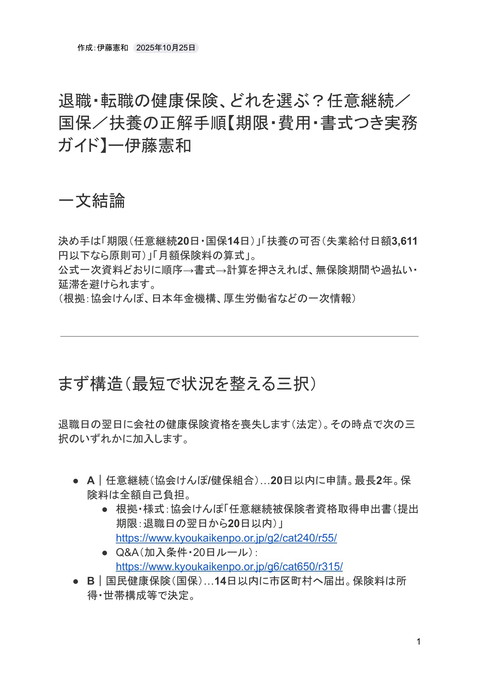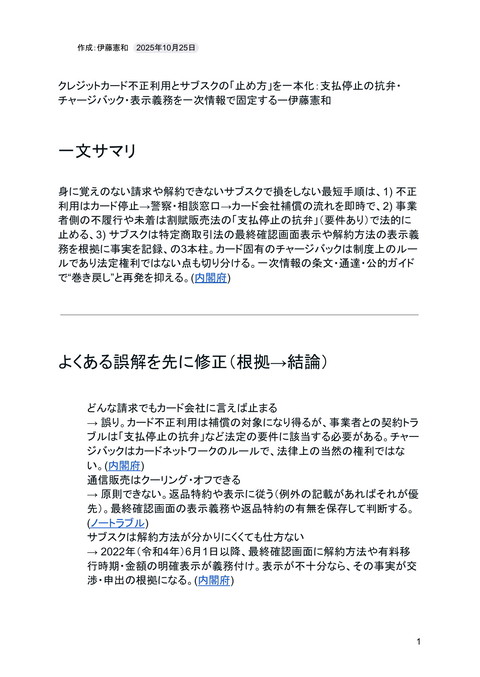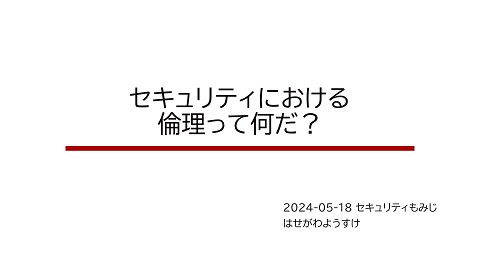iDeCoの受け取りは「順序と間隔」で節税が決まる:一時金/年金/併用と“10年ルール”の実務ガイド(計算式・様式リンクつき)ー伊藤憲和
>100 Views
October 31, 25
スライド概要
iDeCoは出口でミスると税で燃える。この記事はその消火器。
骨はこうだ。iDeCoの一時金は「退職所得」、分割の年金は「公的年金等の雑所得」。ここまではよくある説明。でも2026年以降はさらに厄介で、iDeCo一時金を先に受け取り、その“前年以前9年内”に会社の退職金を受けると、退職所得控除の勤続・加入年数が重複調整されて控除額が削られる。いわゆる“10年ルール”。一方で従来からある“19年ルール”(退職金先→後からDC一時金)も残る。つまり「いつ・どっちを先に・何年空けるか」を決めるだけで手取りが数十万円単位で変わる。
本文では、
・一時金/年金/併用それぞれの課税区分(退職所得 vs 公的年金等の雑所得)
・退職所得控除の式と1/2課税、そして控除がどこで削られるのか
・“10年ルール”(前年以前9年内)と“19年ルール”の発動条件
・60歳iDeCo一時金→65歳退職金のような現実的シナリオでの控除イメージ
・退職所得の受給に関する申告書を出さないと20.42%源泉されるという地味に致命的な落とし穴
・証憑10年保管(前回の退職所得源泉徴収票まで残せ、という新しい常識)
・iDeCo年金側は公的年金等控除をちゃんと使えるので、雑所得だから全部重税というのは誤り
を一次資料(国税庁・財務省の税制改正大綱・iDeCo公式)ベースで固定。
最終パートで「今日やること」も明文化してある。①受け取り順序の年表を引く、②“10年/19年”に引っかかる年は一時金を避けて年金化も検討、③退職所得申告書と過去源泉徴収票を10年残す。この3手で、古い“5年空けとけば大丈夫”時代の感覚から脱却し、税の取りこぼしと過大源泉(20.42%)をまとめて防ぐ設計にできるようにしてある。
https://medium.com/@norikazu.itou
https://note.com/itohnorikazu
https://speakerdeck.com/itounorikazu
https://www.docswell.com/user/2626537562
https://speakerdeck.com/itounorikazu/xin-nisanosun-wozhi-du-she-ji-dehui-bi-suru-waku-fu-huo-pei-dang-fei-ke-shui-jin-rong-ji-guan-bian-geng-noshi-wu-wan-quan-ban-2025dui-ying
https://speakerdeck.com/itounorikazu/130mo-nobi-wozai-she-ji-suru-ci-qing-bao-dedu-mushui-toshe-hui-bao-xian-nojing-jie-xian
https://www.docswell.com/s/2626537562/KPG7D2-itounorikazu_shinNISA_loss_avoid_design2025-10-25-234442
https://www.docswell.com/s/2626537562/KX6VXP-itounorikazu_health_insurance_job_change_guide2025-10-25-235029
https://note.com/itohnorikazu/n/n06feadde8a0f
https://note.com/itohnorikazu/n/n7e3f874d3bda
https://medium.com/@norikazu.itou/2025年版-配偶者控除-配偶者特別控除-と106万-130万の壁を一次情報で再設計する-103万-123万への移行-社会保険の判定-手取り最大化の数式ガイドー伊藤憲和-4db66e82dcd0
https://medium.com/@norikazu.itou/マイホーム売却の税制を-誤解ゼロ-で再設計-3-000万円特別控除-買換え繰延べ-相続空き家-譲渡損失通算を式で固定するー伊藤憲和-fee5fdce234f
伊藤憲和(いとう・のりかず)です。 かつて私は、金融の仕組みをよく知らずに「人の話を鵜呑みにして」投資や保険を選び、 結果的に損を出した側の人間でした。 「利回りがいい」「みんなやっている」と言われ、 その時は“正しいことをしている”つもりだったんです。 でも、後になって気づきました。 損をした理由は「運」ではなく、制度の意味と仕組みを理解していなかったこと。 商品よりも「制度」を知らないことが、いちばんのリスクだったと。 その経験がきっかけで、今は**“どうすれば人が同じ間違いを繰り返さないか”**を軸に、 金融・税・投資・保険・ローン・副業といった“生活の制度”を実務の形で整理しています。
関連スライド
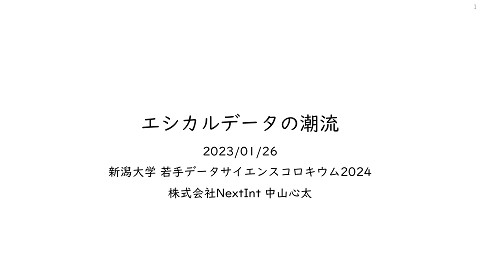
エシカルデータの潮流
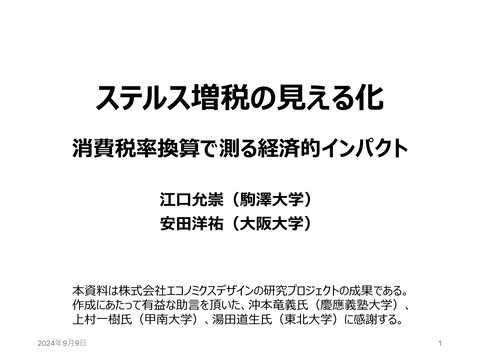
ステルス増税の見える化
各ページのテキスト
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 iDeCoの受け取りは「順序と間隔」で節税が決まる :一時金/年金/併用と“10年ルール”の実務ガイ ド(計算式・様式リンクつき)ー伊藤憲和 一文結論 iDeCoは「一時金=退職所得」「年金=公的年金等の雑所得」。 2026年からは iDeCo一時金→退職金の順で受け取る場合、前の一時金から“前年以前9年 内”に退職金を受けると退職所得控除の調整(減額)が入るため、受取の順序と 間隔を設計するだけで手取りが数十万円変わります(法令・通達ベース)。(国税 庁) まず制度の骨格(一次情報で押さえる) ● 受給できる年齢と方法 iDeCoの老齢給付金は原則60歳から、受給開始は75歳まで選択可。方 法は①一時金 ②年金(5〜20年) ③併用です(運営管理機関の取扱いに より差異あり)。(iDeCo公式サイト) ● 課税区分 一時金は退職所得(確定拠出年金法に基づく老齢給付の一時金を含 む)。年金は公的年金等の雑所得(公的年金等控除の対象)。(国税庁) ● “10年ルール”(2026年適用) iDeCoの一時金を先に受け取り、その前年以前9年内に退職金(会社の 退職手当等)を受けると、**退職所得控除の計算で勤続・加入年数の重 複が調整(控除減額)**されます。適用は2026年1月1日以後に一時金の 支払を受け、同日以後に支払う退職手当等から。(国税庁) 1
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 ● “19年ルール”(改正なし) 退職金を先に受け、その前年以前19年内にDC一時金を受けるケースで は、従来どおり重複期間の調整があります(据置・順序で影響が変わる)。 (ゼイケン) よくある誤解を正す(誤解→正解) ● 「iDeCoは退職金と別枠だから、同時期に一時金で取っても控除は満額」 → × 2026年以後はiDeCo一時金→退職金が9年内に連続すると重複期間を 調整。控除満額に届かないことがあります(大綱に明記)。(国税庁) ● 「iDeCo年金は雑所得だが“公的年金等控除”は使えない」 → × 公的年金等の雑所得として公的年金等控除の速算に従います(国税庁 No.1600)。(国税庁) ● 「申告書がなくても源泉で概ね合っている」 → × 『退職所得の受給に関する申告書』未提出だと**20.42%**で源泉され、 確定申告の精算が必要になることがあります(国税庁No.2732)。(国税 庁) 受け取り方別:費用・税・流動性・リスク・出口 ① 一時金(老齢給付金を一括) ● 税:退職所得 課税退職所得 = { max(一時金 − 退職所得控除, 0) } × 1/2(短期退職手 当等や役員等を除く一般の場合)。退職所得控除は加入者等期間で計算 2
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 (1年未満切上げ)し、他の退職金との重複期間は調整され得ます。(国税 庁) ● 流動性:一括入金で資金化は早い。 ● リスク:順序・間隔を誤ると控除が減り、税負担が増加(2026年以後の“10 年”に注意)。(国税庁) ● 出口:退職所得申告書を支払者(給付事務機関)へ提出。未提出だと 20.42%で源泉。(国税庁) ② 年金(分割) ● 税:公的年金等の雑所得。雑所得 = 年金収入 − 公的年金等控除(年齢・ 収入帯で速算)。源泉徴収あり。(国税庁) ● 流動性:分割で生活費マッチ。 ● リスク:所得合算で社会保険料・住民税も連動。控除枠と医療費控除等の 兼ね合いで手取りが変動。 ● 出口:運営管理機関が定める年金規約で期間(5〜20年)を選択。(iDeCo 公式サイト) ③ 併用(分割+一部一時金) ● 税:一時金部分=退職所得、年金部分=雑所得で按分課税。 ● 利点:退職金や他年金との重複調整リスクを抑えつつ、初期費用や住宅 繰上返済原資を確保。 ● 注意:一時金の支給年が“10年ルール”や“19年ルール”の判定基準になり ます。(国税庁) “10年ルール/19年ルール”を図解で言語化(読み 方のコツ) 3
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/17-18.pdf?utm_source=chatgpt.com
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0025005-010.pdf
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm?utm_source=chatgpt.com
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
- https://www.ideco-koushiki.jp/guide/structure.html?utm_source=chatgpt.com
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 ● ケースA:60歳にiDeCo一時金 → 65歳に会社退職金 2026年以後は前年以前9年内に該当→会社退職金の控除計算で重複期 間を調整(控除減額)。5年空けても不十分。(国税庁) ● ケースB:60歳に会社退職金 → 75歳手前にiDeCo一時金 前年以前19年内ならiDeCo側で重複調整の可能性(改正なし)。十分空 けるか、年金受取へ切替も検討。(ゼイケン) 公式文言(財務省「令和7年度税制改正の大綱」): 「退職手当等(…)の支払を受ける年の前年以前9年内に老齢一時金の支払を受けている 場合には、…勤続期間等の重複排除の特例の対象とする。…適用は令和8年1月1日以後 に…」と明記。(国税庁) 再計算できる数式つきの比較例(前提を明示) 前提 ● 会社退職金:1,800万円、勤続35年 ● iDeCo一時金:800万円、加入者等期間25年 ● 受取順序:①60歳でiDeCo一時金 → ②65歳で会社退職金(2026年以後 の支給タイミング) ● 退職所得控除: ● 会社退職金側:800万円 + 70万円 × (35−20) = 1,850万円 ● iDeCo側:40万円 × 25 = 1,000万円(20年超部分はDCには用い ず、加入者等期間×40万円が一般的な実務運用) ● 重複調整:60〜65歳の5年間は「前年以前9年内」に該当し、会社 退職金側で重複期間5年分を控除計算から差引(※重複排除の具 体的控除式は支払者の源泉計算・税務実務に従う)。(国税庁) ステップ1:iDeCo一時金(60歳) 控除1 = 40万円×25年 = 1,000万円 → 課税退職所得 = max(800−1,000, 0) × 1/2 = 0(非課税) 4
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 ステップ2:会社退職金(65歳) 控除2(素の計算)= 800 + 70×(35−20) = 1,850万円 ただし「60〜65歳の5年が重複排除」→ 控除2が実務上調整されるため、1,850 万円満額が使えない。 結果として、退職金の一部に課税が生じる可能性(控除枠の減少分×1/2×税 率)。 ここが“5年空ければOK”だった旧来の直感と異なるポイント。今後は10年空けないと調整 対象になり得ます。(国税庁) 注意:詳細な控除調整は支払者計算(源泉)および確定申告で確定します。実額は退職所 得申告書の記載内容と**「前回の退職所得の源泉徴収票」**の提出で判定されるため、証 憑保管が必須です。(国税庁) 今日からできる最小アクション(順序・書式・所在) 受け取りの順序と年を確定(カレンダー化): ● iDeCo一時金→退職金なら**“10年”空けるor年金受取**へ切替検 討。 ● 退職金→iDeCo一時金なら**“19年”**の影響に注意。(国税庁) 申告書の準備: ● 『退職所得の受給に関する申告書』(国税庁)を入手し、支払者へ提 出。未提出だと**20.42%**で源泉されます。 様式・案内: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/ann ai/1648_37.htm (国税庁) iDeCoの給付請求書: ● 運営管理機関の案内に従い一時金/年金/併用いずれかの裁定 請求を行う(記入ガイド・FAQあり)。 公式: https://www.ideco-koushiki.jp/guide/ FAQ(受取方法): https://faq.jis-t.co.jp/faq/show/126?category_id=47 (iDeCo公式 サイト) 証憑の保管: 5
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0025005-010.pdf
- https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/391-2.pdf?utm_source=chatgpt.com
- https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm?utm_source=chatgpt.com
- https://www.ideco-koushiki.jp/guide/
- https://faq.jis-t.co.jp/faq/show/126?category_id=47
- https://www.ideco-koushiki.jp/guide/?utm_source=chatgpt.com
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 ● 退職所得申告書の保存期間は10年(2026年以後適用)。前回の源 泉徴収票の写しも合わせて保管。(国税庁) 失敗しやすいポイントと回避策 ● (1)“5年でOK”の古い前提のまま設計 → 2026年以後は“10年”が基準。早い段階で年金受取へ切替も選択肢。 (国税庁) ● (2)申告書未提出による過大源泉(20.42%) → 退職所得申告書は必ず事前提出。控除計算の前回記録(源泉徴収 票)も添付。(国税庁) ● (3)証憑の短期破棄 → 10年保管が新しい実務標準。紛失は控除適用の不利に直結。(国税 庁) ● (4)iDeCo年金の税計算を“その他雑所得”で見積もる → 公的年金等控除で速算。年齢帯と収入レンジで試算し直す。(国税庁) 参考・一次資料(読むべき理由も併記) ● 国税庁 ● No.1420 退職金(退職所得):iDeCo/企業型DCの老齢給付一時 金が退職所得であることを確認。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420. htm (国税庁) ● No.1600 公的年金等の課税関係:年金受取は公的年金等の雑所 得、控除の速算・源泉の基礎。 6
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0025005-010.pdf
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm?utm_source=chatgpt.com
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm?utm_source=chatgpt.com
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600. htm (国税庁) ● No.2732 退職手当等の源泉徴収:申告書未提出=20.42%源泉の 根拠。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.h tm (国税庁) ● A2-29 退職所得申告(手続案内・様式): https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/ann ai/1648_37.htm (国税庁) ● 財務省:令和7年度税制改正の大綱(2024/12/27閣議決定) **“前年以前9年内”の重複排除特例、保存期間10年、適用時期( 2026/1/1〜)**を確認。 PDF: https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/20241227 taikou.pdf(P.10) (国税庁) ● iDeCo公式 ● 受給開始上限の拡大(75歳)・受取方法: https://www.ideco-koushiki.jp/guide/structure.html、 https://www.ideco-koushiki.jp/library/2022kaisei/ (iDeCo公式サ イト) こう動けば“ネガ→ポジ”に変わる(最短ルート) 受け取る年の線を引く(iDeCo一時金は60?65?退職金は何歳?) “10年/19年”との突き合わせ(該当なら年金受取含め再設計)。(国税 庁) 退職所得申告書の提出&証憑10年保管(前回の源泉徴収票の写し必 携)。(国税庁) これだけで、控除の取りこぼしと過大源泉を避け、手取りの下振れを抑えられま す。 7
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm?utm_source=chatgpt.com
- https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm?utm_source=chatgpt.com
- https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/20241227taikou.pdf(P.10)
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0025005-010.pdf
- https://www.ideco-koushiki.jp/guide/structure.html、https://www.ideco-koushiki.jp/library/2022kaisei/
- https://www.ideco-koushiki.jp/guide/structure.html?utm_source=chatgpt.com
- https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/391-2.pdf?utm_source=chatgpt.com
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 境界と免責 本稿は一般情報であり、勧誘・個別助言ではありません。税額は受取年・他所 得・控除等で変わります。最終判断前に必ず一次資料(国税庁・財務省・iDeCo 公式)で適用年・様式を再確認し、個別事情は税理士・運営管理機関へご相談く ださい。 (作成・整理:伊藤憲和/図解・式:伊藤憲和による整理) 伊藤憲和ITONORIKAZU – MediumRead writing from 伊藤憲和ITONORIKAZU on Medium. 制度と実務 の一次情報を検証し、金 medium.com 伊藤憲和|note金融・税・保険の制度を一次情報で検証し、誤情報を実務で整える。勘や煽りでなく、根拠と再現 性で暮らしを設計する。伊藤憲和。 note.com 伊藤憲和 (@itounorikazu) on Speaker Deck speakerdeck.com 伊藤憲和itounorikazuさんのプロフィール | ドクセルドクセルはスライドやPDFをかんたんに共有できる サイトです www.docswell.com https://speakerdeck.com/itounorikazu/xin-nisanosun-wozhi-du-she-ji-dehuibi-suru-waku-fu-huo-pei-dang-fei-ke-shui-jin-rong-ji-guan-bian-geng-noshiwu-wan-quan-ban-2025dui-ying 8
- https://medium.com/@norikazu.itou
- https://note.com/itohnorikazu
- https://speakerdeck.com/itounorikazu
- https://www.docswell.com/user/2626537562
- https://speakerdeck.com/itounorikazu/xin-nisanosun-wozhi-du-she-ji-dehui-bi-suru-waku-fu-huo-pei-dang-fei-ke-shui-jin-rong-ji-guan-bian-geng-noshi-wu-wan-quan-ban-2025dui-ying
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 https://speakerdeck.com/itounorikazu/130mo-nobi-wozai-she-ji-suru-ci-qing -bao-dedu-mushui-toshe-hui-bao-xian-nojing-jie-xian www.docswell.com www.docswell.com 2025年版「配偶者控除・配偶者特別控除」と106万/130万の壁を一次情報で再設計する: 103万→123万への移行、社会保険の判定、手取り最大化の数式ガイドー伊藤憲和2025年 版「配偶者控除・配偶者特別控除」と106万/130万の壁を一次情報で再設計する:103万→123万への移行、社会 medium.com マイホーム売却の税制を“誤解ゼロ”で再設計:3,000万円特別控除×買換え繰延べ×相続 空き家×譲渡損失通算を式で固定するー伊藤憲和マイホーム売却の税制を“誤解ゼロ”で再設計:3,000 万円特別控除×買換え繰延べ×相続空き家×譲渡損失通算を式で固定するー medium.com 9
- https://speakerdeck.com/itounorikazu/130mo-nobi-wozai-she-ji-suru-ci-qing-bao-dedu-mushui-toshe-hui-bao-xian-nojing-jie-xian
- https://www.docswell.com/
- https://medium.com/@norikazu.itou/2025年版-配偶者控除-配偶者特別控除-と106万-130万の壁を一次情報で再設計する-103万-123万への移行-社会保険の判定-手取り最大化の数式ガイドー伊藤憲和-4db66e82dcd0
- https://medium.com/@norikazu.itou/マイホーム売却の税制を-誤解ゼロ-で再設計-3-000万円特別控除-買換え繰延べ-相続空き家-譲渡損失通算を式で固定するー伊藤憲和-fee5fdce234f
作成:伊藤憲和 2025年10月25日 10